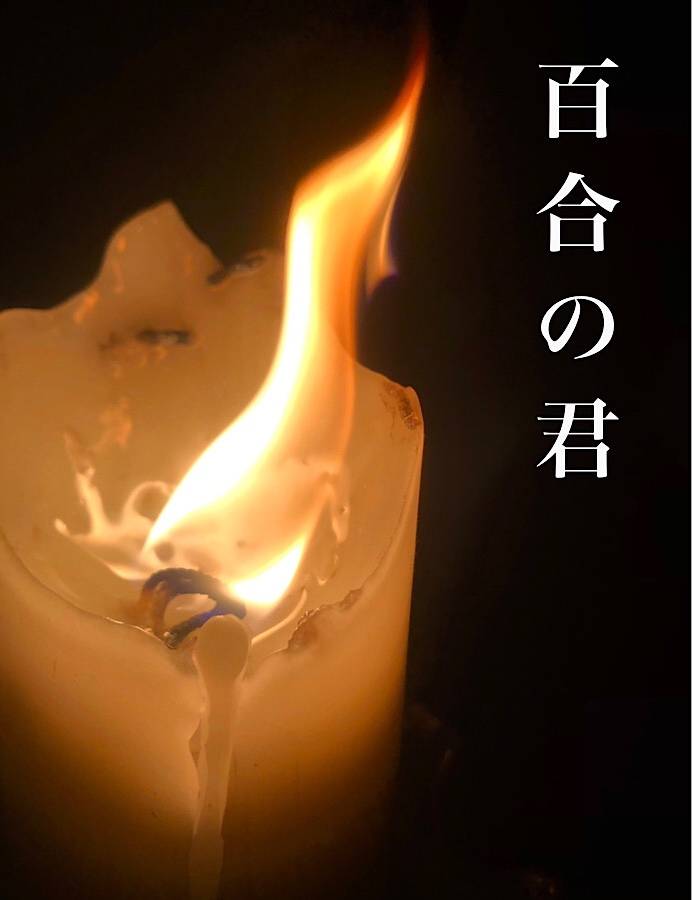
百合の君(45)
刈奈羅からの侵攻は、出海浪親率いる八津代の勝利に終わった。勝利と言っても、得たものは何もない。ただ失わなかったというだけだ。そして失わなかったと言っても、国土が残ったというだけで、多くの男、女、子供、老人の家族や友、過去の思い出や今の生活、その将来が奪われた。
例えば剃胡地村の甚太という少年は、三つ歳下の妹を失った。村が襲われ手をつないで逃げていたはずの妹は、いつの間にかいなくなっていた。予感も伏線もない。現に甚太が妹の不在に気づいたのは、小便をしようとした時だ。死という結論さえもなく、いつまでも決着のつかない心を抱いて、彼は父と荒れた畑を耕している。八津代の人々はそういった喪失と引き換えに、土地と城を守ったのだ。
しかし大国である刈奈羅が、そのまま八津代を放っておくはずがない。二年後の正退三年九月、浪親は再び侵略の気配ありとの報を受け、使者を古実鳴の煤又原城に遣わした。
浪親は城の庭に立って、東の国境の山々を眺めていた。まだ紅葉には早いが森の緑はすっかり深く、日はまだ強いが冷たい風が吹いた。浪親の胸中には、期待と嫌悪の入り混じった感覚があった。
期待というのは古実鳴の喜林臥人が逝去し、代替わりしたので以前のように無下にはされないのではないかというものだった。新たに君主となったのは臥人の娘婿にあたる喜林義郎という男だが、先の戦で八津代との同盟に唯一賛成した重臣だと聞く。同盟成立の可能性は高いように思われた。
が、嫌悪もまた同じ所にあった。
義郎はその座を奪うために義父を殺害した、というのがもっぱらの噂だ。これだけ手を血に染めても正義感を捨てきれない浪親にとって、そのような男と組むのは気の進まないことだった。
使者の帰りを待つ間、浪親は馬を出して城下を見物していた。きれいに掃き清められ塵一つ落ちていない道の両端には、空を少しだけ区切るように建物が並んでいて、障子紙が秋の日を吸い込んでいる。軒先では売り子が千代紙や手毬などを商っている。自分が守り切った町を眺めるのは心地よかった。城で家臣たちの揣摩臆測に付き合っているより余程良い。
視界の端に色が走ってーー店先の風車が目に留まった。止まった状態ではただ赤や青の色が飛び散っているだけだが、風が吹くと揺れる花のように見えたり、巡る月と星になったりする。職人は面白いことを考えるものだ。
浪親は黒い馬に跨った武士が走っているように見える物を買った。自分の馬が黒毛でなく白いのを少々残念がり、浪親はそれが風の強さによって速く駆けたりゆっくり歩いたりするのを見ながら漫歩していた。
しかし、町も外れまで来ると手足のない者や顔面に包帯を巻いた者が多く見受けられるようになった。きっと故郷の村が焼き払われ、ここに逃げて来たのだろう。
浪親はあの長美千尋村で会った母親を思い出した。赤子を殺され、刈奈羅への呪詛の言葉を吐いていた女だ。あの時と同じ怨念が、体臭とともに漂っている。たかっている蝿を気にもせず、底なしの泥沼のような目で、馬上の浪親を見上げる。
浪親は戦慄した。一度追い返したくらいでは、彼らの恨みはなくならない。どうすればこれを消せるだろう? この戦いに勝ち別所を滅ぼし、私が将軍になって太平の世を築いたら、本当にこれはなくなるのだろうか?
敵の子供を殺せと言った、あの母親の怨讐が。
風車はすっかり止まってしまった。路上には五、六歳の女の子が座っている。伸びっぱなしの髪を無理やり後ろで結び、破れた着物から汚れた肌が覗いている。ただ一か所真っ白な左目の眼帯が、いやでも目についた。
「その目はどうした」
少女は馬を下りる浪親を片目でじっと見た。なかなかきれいな瞳をしているが、近づくとやはり臭った。浪親はまた風車が回ることを願った。
「分からないのです」
先の戦から二年。この少女が覚えていないのも無理はない。
「戦か?」
「みんなそう言います」
少女は、片目を失ったことを悲しんでさえいないようだった。両親はどうしたのだろう。隣にいる爺は、ちょっと親には見えない。
浪親は、思いついたことがあって少女を馬に乗せた。爺が歯のない口で訴えるような媚びるような笑いを浮かべて近づいて来たので、少額の金銭を馬上から投げてやった。爺はそれを空中で取ろうとして焦って落とし、それらは地面に着くことなく他の者によって持ち去られた。
少女は嫌がる様子もなく、浪親の背中に掴まっている。
百合の君(45)


