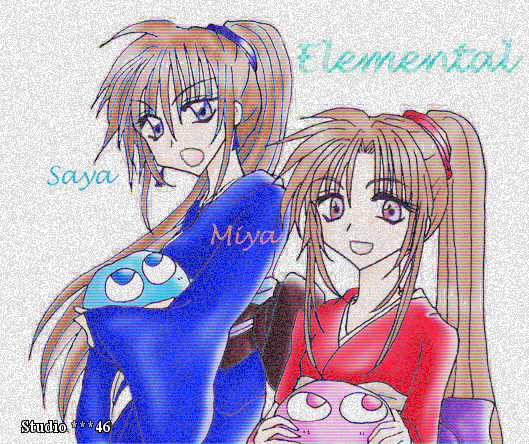
Elemental 起
沙夜。貴女は最初に愛した人と生きることはできない。
明らかに普通ではない育ちの中で生きてきた沙夜が、普通でないものにばかり出会いながらも、めげずに人間生活を頑張っていく物語。
update:2025.1.1
関連作:D3→https://slib.net/119597
序章
それは果たして、親愛からの忠告なのか。
それともただ、死にゆく彼女の歎きだったのか。
――サヤ、と。
もう何番目の親かも忘れた、亜麻色の髪と、灰青の目をした女性が自分の名を呼ぶ。
――貴女は、最初に愛した人とは生きることができない。
何故なら。彼女は哀しそうな目をして囁く。
――貴女はその人と、出会うことすらできない。
正直、意味はよくわからなかった。
けれどその声が、あまりに優しかったから。今でも沙夜は、信じているのだ。
――でも忘れないで。貴女は沢山の愛に出逢う。
たとえそれは、真っ赤な血が飛び散って、沙夜を抱き締めた誰かが崩れ落ちた瞬間であっても。
唯一守りたかった少女が冷たく固くなって、沙夜を見ても笑わなくなったその日にも。
1
――あんた、親に捨てられたんだろ?
けろりと簡単に、そんなことを口にする性格の悪い男。沙夜は負けじと、平然と睨み返した。
――だったら、何なの?
今まで何度も、同じ類の無頼漢の声に、沙夜はそう返してきた。
――私は悪くないし、間違った事もしてない。真っ当に生きる限り、幸せになる権利はあるはずだもの。
男はそんな沙夜を、眩しくも痛ましくもあるような、蒼い眼で見つめていた。
普通を求める彼女に今後訪れる、普通でない日々を知るかのように。
そうして何度、沙夜は心に決めたことだろう。
――今度こそ、新しい家族と仲良く頑張る!
狭間沙夜。新たな後見人で養子先の姓。なのに居候初日から、既に道は険しかった。
「ちょっと沙夜! 何ぼーっとしてんのよ!」
いきなり、角ばった制鞄を投げつけられた。
教科書、筆記用具が入っているソレはなかなか、当たり所が悪ければ凶器になりそうな重みだ。
「あ、陽美さん――ごめん、なさい」
投げつけた当人はそんなことを、全く考えていないのは確かだった。考えてない相手に文句を言っても始まらないので、沙夜はぐっと、顔色を変えずに憤りを飲み込む。無造作に腰元まで下ろされた、薄い茶色で真っ直ぐな、長い髪だけは軽く揺らして。
対する相手は、短くて濃い、今時の茶髪を思いっきり揺らして強い怒りを表していた。
そう。この養子先の家の娘の陽美が、突然現れた沙夜に怒りを覚えることも当然だろう。
「今日から一緒に暮らすことになった沙夜君だ。陽美、仲良くするんだよ」
新後見人たる狭間さんの、経緯を全て省いた簡潔な紹介はどうなのか、と沙夜も思う。いきなり家族とか、どうなってんの!? と怒る陽美は事情を何も話されておらず、沙夜も何故自分がここに引き取られたのか、検討がつかない。
――そもそも……狭間さんって何者?
沙夜にわかるのは、多分三、四人目くらいの、何度も入れ替った最新の後見人というだけだ。
それでいいのか、私?
否応なく順応力の育った自分に、たまには自分でつっこみを入れる。
「本っ当、気味悪い奴! 何処の馬の骨かもわからないんだから!」
「……」
ここで笑えば、何ヘラヘラしてんの、と怒られ、今のように無表情を通せば更に不機嫌になる。どう対応していいか、早くも全くわからない相手に、沙夜は黙り込むしかできない。
まぁ、わけがわからないのは、今までのどの家も似たようなものではあった。拙い回想を巡らせて沙夜は何とか、気持ちを落ち着けていく。
これでもう自分は何度、住む家を変わってきただろうか。最早数えることすらやめてしまった。
――今までの所とは、一応うまくやってきたけど。
ただしそれは、ある程度家人と距離を置いていたからでもあった。
だからある意味、感情をここまでストレートにぶつけられるのは、この狭間家が初めてだった。
「アタシ、あんたなんか絶対認めないし!」
初めてだからといって、有り難いわけでは全くない。陽美の部屋で溜め息を抑えて、沙夜は改めて尋ねる。
「あの、陽美さん」
「何よ!?」
「明日から学校、何処に行けばいいでしょうか?」
既に高校では、沙夜は最上の学年だ。しかも年度が変わって一ヶ月強という妙な時期の転校生で、目の前の陽美以外、行く先の手掛かりがない。
「知るか、そんなの! 勝手に行きなさいよ!」
沙夜用の制鞄や制服を投げつけてきたのは、まだしも助かる展開だった。これで学校の準備だけでもできる。
――でも……学校まで連れてってくれそうにはないな、このヒト。
おそらく、狭間さんがいる前で尋ねれば、無愛想でも陽美は何とか答えてくれただろう。しかし狭間さんは普段からあまり家に帰ってこないらしく、陽美の母に至っては、沙夜をほぼ完全に無視している状態だ。辛うじて食事が別に用意されているだけで僥倖だろう。
うーん。ひとまずどうやって、学校に行こう。
真剣に悩む沙夜を視界の端にして、陽美は面白くなさそうにパソコンに向かっていた。
十畳の洋室内で、ドア側四分の一の片隅に置かれたロフトベッドが、沙夜に与えられた全スペースだ。元々空いていた場所だと言うが、だとしても何の相談もなく養女を同室にされ、一人部屋でなくなった陽美の不快感も理解はできた。
――それとこれとは、話が別だけど……。
今や誰もが、一人一つは持っていて当然のスマートフォンも、沙夜は持っていない。パソコンなどこれまで何一つも、情報通信機器に触れていない。小学生すら当たり前に持っているこの時代に。
――そういうの持ってたら、学校とかある場所、すぐにわかるっていうけど。
今の沙夜にできるのは、陽美についていくか、人に尋ねるしかない。手続きの時に車で一度行っただけで、高校の名前も記憶にない転校慣れぶりには笑うしかなかった。
*
そして案の定。かなり朝の強い沙夜以上に、根性で早起きしたらしい陽美は、翌朝早く消え去っていた。
「……逆に、尊敬するかも」
ここまで露骨に嫌われると、めげるなあ、と肩を落とす。少しでも陽美を信じてみたかったのだ。
沙夜の胸元で、青い天然石のペンダントが揺れる。養母のその形見を握りしめて、溜め息をつく。
――今度こそ、仲良くなりたかったのにな。
これまで暮らしてきた里親の家は、子供のいない老夫婦や、忙しい若夫婦の家庭で、同年代の娘がいるという今回は、少しは期待していた。
しかし夢は儚く打ち砕かれ、今や行くべき道一つすらも、現実問題さっぱりわからない始末だ。
「……えっと。本気で、高校、どっちよ」
余裕をもって道を尋けるよう、早く出たことが却って裏目に出た。朝早い閑静な住宅街に出歩く人影はほとんどなく、それもそのはず、小高い丘上のこの辺りでは、大体の通勤人は車を使っていた。
「まさか手当たり次第に、インターホン押してきくわけにもいかないし……」
仕方ないので、沙夜はとりあえず、最寄の地下鉄の駅までとにかく下りることにしたのだった。
「ああもう……! 地下鉄、小さ過ぎ!」
走る。とにかく必死に沙夜はひたすら走る。
「駅すらすぐに見つからないなんて!」
教えてもらった最寄の高校は、その駅と反対方向だった。しかもかなり遠く、道もわかりにくい。
地下鉄に乗れば、たった二駅の距離。しかし沙夜には、自由になるお金はほとんどない。
「これじゃ本気で、遅刻じゃない……!」
転校早々! 恥ずかし! と、百メートルを最高十秒台後半で走れる足に全力を込める。
といきたいところだが、実際は道々分岐を気にしながらの疾走なので、そうもいかない。
でも、だから、自分と同じように必死に走っている少女が目に入った。
そして制服が自分と同じことにも、気が付く余裕もあったのかもしれない。
「うわーん……! 遅刻遅刻ー……!」
寝過ごしたぁぁー! などと、動揺のあまりに周囲も構わず叫ぶ誰かがいた。
「――! 同じ制服――ってことは!」
あの子さえ捕まえれば、まっすぐ目的地まで連れてってもらえるはず!
道を気にしながらの疾走に疲れていた沙夜は、うわぁぁんと慌てている少女の方へ華麗にUターンした。
……が、次の瞬間に現実を知る。
「うわぁぁん、転校初日なのにぃぃぃぃー」
聞かなければ良かった。少女の直前まで来たところで、頼りない真実にすぐ曝された沙夜だった。
それでも一応、ダメ元で声をかけてみる。
「ねえ、おはよ。ちょっといい?」
「って――あれ……?」
沙夜に気付いて、あわあわとした少女が大きな目を丸くする。沙夜は淡々と話しかける。
「ねぇ、あなた、私と同じ高校? 悪いけど私、転校したてで道がわからなくって」
「え? あなたも転校されてきたんですか?」
少女は立ち止まり、改めて沙夜の方をじっくりと見た。
「え? ってことは……迷子、ですか?」
「――そう。あなた、道わかる?」
落ち着いて尋ねる沙夜に、泣きそうな目で、少女が真っ直ぐなポニーテールを揺らした。
「ごめんなさいっ……自信ないですっ……!」
ふぇぇーん……! と聞こえてきそうな顔で、両手を握り、沙夜をまっすぐ見返していた。
「あー……」
この状態の相手を、先程のように疾走して見捨てていくわけにもいかない。
要するに、事態は一層悪くなった。どうしたものか、と立ち止まっていた時だった。
「――東高校の生徒さんですか?」
二人がいた大通りの交差点で。角にある開店前とおぼしき花屋から、鉢植えを抱えて出てきた、エプロン姿の華奢な青年がいた。
「「――?」」
「その制服。この先の市立東高校ですよね?」
にこにこと微笑みながら、青年がくいくい、と交差点の先を指差す。沙夜は、何故か軽く、理由のない衝撃を受けた自分にふっと気付いた。
とても整った顔立ちの青年。色の薄めな鋭い短髪が、青緑のフードパーカーとよく合っている。
「えっ……えっとっ……!」
「――道、わかるなら教えて」
突然声をかけられ動揺する少女と、淡々と冷静な沙夜に、青年は再び柔らかく微笑んでいた。
「この先は地下鉄の真上の道なので、地上はずっと商店街になります。商店街の南沿いを、ひたすら走れば十分程でつきますよ」
え。沙夜が教えられた大通りとは、随分違うわかりやすい近道で首を傾げる。
青年は沙夜の戸惑いを知るように、いたずらっぽく笑った。
「ただし最後は、裏門になります。頑張って塀、越えてくださいね」
現代風の制服で短いスカートの二人の女子に向かって、いとも簡単にそんな事を言う。その後はもう、青年はさっさと店に引っ込んでしまった。
「「………」」
沙夜と少女は、しばし黙って顔を見合わせていた。
「――いこ。最後、難しかったら手伝うよ」
ひょいっと、少女の鞄を沙夜は取り上げる。
「えっ?」
「急ごう。あなた、足早くなさそうだし」
ともすれば失礼な言い方だが、だから荷物は持ってあげようと思った。少女が全力で走り易いように、沙夜なりに気を遣ってのことだった。
少女は咄嗟に事態が理解できず、ポカンとしていた。それでも慌てて首を縦に振って、青年に言われた通りの道を急いで走り始めた。
そしてきっかり十分後。そう高くない塀に囲まれた、一般的な公立学校の裏門に二人は到達していた。
「よし、誰もいない! ほら、早く!」
「え、あ――ハイ!」
沙夜に軽く背中を支えてもらい、少女が何とか先に塀を越えた。丁度予鈴が鳴り始めて、少女が焦り顔で沙夜の方に振り向いた。
「私は大丈夫だから、早く!」
「ご、ごめんなさいっ……!」
やっと塀の内に降り立った少女の姿を、沙夜は見届ける。その後に実に、少女の三分の一にも満たない時間で、あっさり塀を登って中に入った沙夜だった。
軽々とした身のこなしに、少女は予鈴も忘れた顔で、またしてもポカンとしているようだった。何しろ、二人分の鞄を持った上での早業で、沙夜の運動能力の高さは傍目に明らかだった。
「あ、あのっ!」
「――?」
「ごめんなさいっ、ありがとうございます!」
「へ?」
少女の目は、何故かじんわりと潤んでいる。
沙夜はよくわからず首を傾げたまま、一年の教室の方へ駆けていく少女を見送っていた。
「…………」
三年生の教室は二階にあり、一年生よりは近い。焦らずに階段を上がりながら、沙夜は少女のゆらゆらと揺れていたポニーテール、自分とよく似た髪の色を思い出していた。
「――ほんと。まさに、馬の尻尾の色よね」
薄めの茶色で、昨今では珍しくない色だが、あの薄さだと色を抜いていないかと言われているだろう。沙夜にもよくあることなのだ。
自分の出自も全然知らない沙夜は、本当に日本人なのかも正直怪しい、とたまに思う。
自分と同じ髪の色で、同じように時期外れの転校生の少女。灰色の目は沙夜の方が鋭い雰囲気。
「……名前、きいておけば良かったな」
別にその時、何かを予感していたわけではなかった。それでも沙夜は、何故か出現したふんわりとした気分を、何となく大事に、ゆっくり噛みしめていた。
*
一度だけ事前の手続きで見学にきた時に、三年E組ということだけはきいていた。迷わず教室に入った沙夜が、まず困ったことは一つ。
――空いてる机……ない……。
大体の生徒は既に席についていて、何個か生徒がいない机はあるが、どれにも横や中に荷物があった。
これまで転校した時は大体、教室の後ろに空いた机がある事が多かった。しかしそれが、全く用意されていないとなると―――
――E組っていうのすら、嘘情報だったのかな。
そこからまず疑った沙夜の前に、つかつかと、同じクラスの陽美が突然寄ってきていた。
「――!」
「……うざっ」
わざわざそれだけ、耳元で呟いて立ち去る。
「――あなた、転校生?」
入れ替わり様に、日直らしく黒板消しを持つ無愛想な黒髪の女生徒が、沙夜に気が付いていた。
「あ、うん。どこ座ればいい?」
「……」
女生徒は怪訝な顔をして、教室を見回す。
沙夜の存在に驚かないのは、転校生が来るというのは既に周知のことなのだろう。それならクラスは合っているはずなのに、沙夜の机が無いことを彼女も不審に思ったらしい。
「……とりあえず、沖咲さんの所に座って。海外留学中で、当分帰ってこないはずだから」
彼女はそれ以上、沙夜に関わるのはご免だと思ったのか、それだけ言って自席に帰った。
「わかった。ありがと――橘さん」
黒板の隅に書かれた日直者の名前を見ながら、沙夜は淡々と女生徒に礼を言った。
それからすぐに、定番の転校生紹介のSHRが終わった。何の変哲もなく、昼休みまであっという間に時間は過ぎていった。
お金も身寄りも何もない居候は、あまり簡単に嘆くことはできない。養家の方針にいくらか不満があろうと、路頭に迷うよりはましだ。
「あー……お腹、減ったな……」
嫌がらせもあまり露骨になると、こうも何も言えないものか、と沙夜は実感しつつあった。
朝、狭間家で用意されていた沙夜用らしきお弁当袋には、某十円の駄菓子が二つだけ入っていた。これはもしやウケ狙いか、と勘繰ってしまうほどだった。
「現物支給って、きっついなぁ……」
そこまで沙夜のことが嫌いなら、その程度でも何か用意している分、むしろ相手も律儀かもしれない。
そうして超速度で、お昼ご飯の終わってしまった沙夜は、机に突っ伏すしかなかった。
――でも忘れないで。貴女は沢山の愛に出逢う。
唐突にそんな、優しいだけの声を思い出した。
「……」
今のこの状況で、そんな言葉を信じろと言われても困る。知らず、ペンダントを軽く睨む。
養母の曖昧さの少ない英語を思い出しつつ、沙夜はふてくされて、両目を強く閉じた。
――陽美さん、いったい私のこと、どんな前情報を流してくれたものやら?
転校生の沙夜に対して、周囲はいくらか興味を持っている様子だ。それでもヒソヒソと、遠目に話すだけで近寄ってこようとしない。
高校三年目の初めともなれば、既に仲良しグループはでき上がり切っている。
そこに後から割り込むのは元々難しいが、悪意をもった妨害者がいるとなると、余計に沙夜の対人ハードルは上がる一方だ。
――あー……。やりにくいなぁ、本当……。
いくつも色んな学校を経験してきた沙夜は、今時にしては平和な方のこうした高校、大きな特色もない公立学校には逆にそぐわない。一見ワケアリに見えそうな転校生に、近付きにくい相手も多いのだろう。
「……」
ふっと、沙夜の脳裏をよぎったこと。
自分と同じように、時期外れの転校生で。しかし派閥はでき上がり切っていないだろう、一年の教室に向かった少女のことを思い出した。
――……ダメだよね、邪魔しちゃ。
少女を探してみようか、と顔を上げたのも束の間。再び沙夜は諦めの境地に立って、ぽてん、と机に突っ伏そうとして――
「狭間さん。先畑さんって子が呼んでるけど」
「――へ?」
狭間陽美と紛らわしくないよう、しっかりと自分の横に立って、今日の日直の彼女が言った。沙夜はがばっと顔を上げた。
「あ、先輩~! 良かった、見つけたー!」
日直の彼女の視線の先で、心底嬉しそうに顔を崩した少女がいた。ドアの所から手を振って沙夜を見ている一年生に、一瞬、教室全体の時間が止まっていた。
にこにこにこにこ。初めての学校にも関わらず物おじせずに、上級生の教室までやってきて笑っている少女。朝に二人で乗り越えた裏門に来て、沙夜は完全に毒気を抜かれるように、少しひきつりながらも、つられて微笑んでいた。
どうして来たの? と、教室を離れてから真っ先に尋ねた沙夜に、少女はポカンと答えていた。
「だって、先輩も転校生だったから……まだあんまり、知り合いとかいないかな、って」
足場にした低い石垣に並んで腰かけていた。自分と同じ茶色い髪の少女が笑う。
「それにわたし、まずは朝のお礼がしたくて。先輩のおかげで遅刻せずに済んだんですから」
「先輩はやめて。沙夜でいいから」
「沙夜……さん?」
「あなたは? とりあえずまず、名前教えて」
あ。完全に忘れていたらしい少女は、照れたように目をそらしながら、早口に呟いた。
「先畑美夜です。ごめんなさい、本当に今頃」
「別に私はいいけど……同級生にはちゃんと名乗ってるわよね?」
当たり前ですー! と不満げに慌てる。
先畑美夜。髪の色だけでなく、名前も少し、沙夜と系統が似ている。
しかしそのくるくると、笑ったり慌てたり目まぐるしい表情は、沙夜とは正反対の雰囲気だった。
「ほんっとに久しぶりに寝坊しちゃったから、朝は慌ててただけなんですー!」
「……」
焦る美夜がどうにも愛らしく、沙夜は不覚にも、これまでの無愛想からまたも顔が緩んでしまった。
「えーー。何で笑うんですか、沙夜さんー」
「別に……でも、いいの? せっかくの昼休み、ちゃんとクラスで友達作った方が良くない?」
「――……」
唐突に美夜が黙り込んで、生き生きしていたはずの笑顔に影がさした。
理由はわからないが、空気を察した沙夜はマズイ、と思ったものの。
「あ、ゴメンなさい……! わたし、多分、あんまり長くここにいられないから」
沙夜のその気持ちを更に察したのか、美夜はあっさりと、黙り込みの理由を白状していた。
「ずっと色んな所、転々としていて。だから今までも、友達、作れてないんです」
空気が重くならないように、明るく言おうとしているらしい。代わりに沙夜が黙り込んで、ますます美夜が慌て始めた。
「ごめんなさい、沙夜さん何か、話しやすくて――こんな話ダメですよね、暗いですよね!」
あわあわあわ、と一人で慌てる美夜を、今度は沙夜がポカンと見つめる。
何か明るい話題を、と焦ったのか、美夜は思い出したように顔つきを変えて笑った。
「それより知ってますか? 朝、道を教えてくれたお花屋のお兄さん、実はこの辺りでは評判のお花屋さんらしいんです。朝のお礼に今日の帰り、一緒によりませんか?」
「へー……評判、って?」
「お任せセットの花束がとても安くて、でも凄く素敵らしいんです。何というか、口ではうまく言えない素敵さらしいんですけど」
「……は?」
何その、胡散臭さ……。きらきらとした目で言う美夜には悪いが、歳の割にリアリストな沙夜は、つい真っ先にそう思った。
しかし、お任せセットがどれだけ安くて、有り得ないくらいに素敵だったとしても。
「ごめん、美夜ちゃん。私全然お金ないから、一緒に行けない」
「えっ?」
「お礼したいのは山々だけど……正直、今日のお昼ご飯にも事欠く状態なんだ」
ええーっ! と美夜は、某十円菓子の包装紙を取り出した沙夜に、しばし絶句してしまった。
「――ちょっと待ってて下さい!」
そうして何やら、突然足早に駆けていってしまった。
「??」
お昼休みも、残りわずか。なのにいったい、何処に行ってしまったのだろう。ぽけっと沙夜は美夜の帰りを待っていたが。
やがて数分もしない内に、美夜が、朝より早いかもしれない程の足取りで息を切らして駆け戻ってきた。
「沙夜さん! 朝のお礼です、これ!」
「――へ?」
ずいっと、どう見ても学食のものと疑わしき菓子パンを美夜が差し出す。
「今日、沢山お弁当持ってき過ぎちゃって! 食べ切れなかったのでもらって下さい!」
――あー……それはー……。
今まで沙夜は、こうした貰い物は、決して受け取らないと決めていたところがあった。それは多分、何処かに施しのような要素があったり、同情や憐れみは重いからだ。沙夜は昔からずっと、あまり自分の境遇を重く考えないようにしてきた。
しかしきっと、大真面目に全力疾走し、肩で息をしている美夜を見ると、迷いも何処かに飛んでいった。
「……ありがと。別に、お礼されるようなこと、何もしてないけど」
何故か美夜は、これはお礼のチャンス! と本気で頑張ったらしい。運動は苦手そうな全身からその空気が伝わってきて、とてもいらないとは言えなかった。
「それと、あの、お花屋さん……わたし、凄く行きたいので、ついてきてくれませんか?」
お花はわたしが買いたいんです、と。それも本当に、心細そうな美夜の本心だった。
「それじゃ……放課後、またここで」
淡々と言ったが、美夜は心から、やった! という顔でまたニコニコーと喜んでいる。沙夜も何故か、自然に顔が綻ぶのだった。
らしくないな、と少しだけ、自分のことでも首を傾げつつ。
*
2
「ちょっと沙夜。はい、これ」
「――?」
クラス全体から遠巻きにされたこと以外、平穏に終わった転校初日。
放課後に唐突に、沙夜は陽美から、箒とチリトリを当然のように手渡されていた。
「あんたは居候なんだから、何かアタシに恩を返すのが当たり前でしょ」
周囲に聞こえないよう、小声で囁く。反論できない沙夜を横目に、振り返ることもなく陽美は帰ってしまった。
「……」
どうやら陽美と同じ掃除当番の生徒も、今日はいい、と彼女に言われて帰ったらしい。
――陽美さん達の担当って、隣の空き教室?
あの机と椅子を全て一人で移動させて、丸々一つの教室を自分一人で掃除するのか。沙夜は大きな溜め息をついて、恨めしげに箒とチリトリを眺めていた。
しかして数十分後。
「――ごめんね、美夜ちゃん。待たせた上に手伝わせちゃって」
「そんなことないです! これでやーっと、今朝のお礼の二つ目ができました!」
他の生徒が帰っているのに、なかなかやって来ない沙夜の様子を美夜は見に来た。一人で空き教室を掃除している沙夜を見つけて、憤然と雑巾を持って押し入ってきたのだった。
「二つ目が、って……私そんなに、何かしたっけ?」
「沙夜さんは優しい人です! なのにこんな、それを利用した意地悪は許せないです!」
先程から美夜はずっと、怒り任せに床を拭き殴っている。沙夜に対しての怒りではなく。
――本当に、ころころ表情が変わる子だなぁ……。
無愛想な沙夜には感心してしまうくらいだ。そして意外にも、美夜はてきぱきとしている。美夜が参戦してからの掃除の進行具合は、沙夜の基準からすれば働き慣れした人の動きだった。
――手抜き……と、言えなくもないけど。
重要ポイントを押えて美夜は掃除を済ませる。空き教室なので確かに大きく拘る必要もない。
「大雑把なことは得意なんです、わたし」
やっと少しずつ憤慨を治めて、ささっと机の位置を素早く戻して笑う。
「そうよね。ここに必死に手をかける必要、別にないよね」
真面目に一人で、きっちり掃除をやり遂げようとしていた沙夜は、苦笑するしかないのだった。
「美夜ちゃん……バイトか何かしてる?」
空き教室を後にしてから、近道のために裏門に向かう途中で、何となく沙夜は淡々と尋ねた。美夜はぎく、っと体を固めた。
「えーっと……」
沙夜の方を見ずに、固まったまま俯いている。
「……わかっちゃいます?」
「――ううん。ただ、何となく?」
どうやら図星だったらしい。悪いこときいたかな、と少し声をひそめる。
――確かここ、アルバイト禁止だったよね。
だから沙夜も、学校を出てからきけば良かった、と思った。美夜も今までより声が小さい。
「と言っても、もう夕方だし、誰もいないか」
帰宅部の下校生徒のピークは過ぎた。部活動をする生徒は運動場か体育館に集まっている。
「それにしても美夜ちゃんって、正直よね」
沙夜はただ純粋に、感心してそう口にした。美夜はそれを、え? と困ったような顔をして沙夜を見る。
「それ……いいことですか?」
「――と思うけど? わかりやすいし」
「ええー……」
しかし本人としては、良いと思えないらしい。わかりやすく困惑を浮かべていた。
「正直ついでにきいちゃうけど、美夜ちゃん、何でバイトしてるの?」
どちらかというと美夜は、あまり規則を破る方に見えない。小遣い稼ぎという理由ではないのではないか、と沙夜は気になり始めていた。
「えーっと、うち、お母さんが病気なので、わたししか働けないんですよ~」
何でもない事のようにあっさり答える。沙夜もうっかり聞き逃しそうになった。
その一。先畑さんちは多分母子家庭らしい。
その二。先畑さんちの家計は何と美夜頼み。
かなり重要な情報を危うく拾い上げて、沙夜はがばっと振り返った。
「それって凄くない……!?」
美夜はきょとん、と首を傾げる。
「え? そうですか?」
今日の雑巾がけのせいで、更に目立つひび割れだらけの手。何枚も貼った絆創膏を軽くさする。
「でも医療費は保険から出てますし、家賃は知り合いの所を転々としてて安いみたいですし」
大したことないですよ、と笑うが、つまりは他の家計費は美夜が担っているということだろう。
「……今日、大丈夫なの? 遊んでて」
しかも花買ったりなんかして……と、本気で沙夜は心配顔になっていたが、
「転校初日なので、夜しか仕事入れてません!」
だから大丈夫! と胸を張る美夜。
とりあえず感心し過ぎて、絶句しかできない沙夜なのだった。
――……そりゃ、なかなか友達も作れないわ。
昼休みの美夜の暗い影を思い出した。沙夜も気持ちが少し暗くなった時に、丁度、朝の花屋のすぐ近くまで辿り着いていた。
そこで彼女達二人は運命と出会うことを、この時はまだ、知るはずもなく。
――あれれ、と。最初に首を傾げたのは、小さな財布を取り出そうとした美夜だった。
「先客でしょうか?」
鞄をあさって止まっていた時、大通りから二つの人影が、花屋に足早に入っていった。賑やかな笑い声や慌てるような青年の声が中から聞こえてきていた。
「何か、身内みたいな感じね」
夕暮れ時で、閉店より少し前の時間。客足の少ない頃合いを見計らってきた者達だろうか。
アハハハ! ともれてきた大きな声に、沙夜と美夜は期せずして顔を見合わせていた。
「「……」」
何となく、今お邪魔していいものだろうか、と。そんな躊躇いを感じさせる程に、店内は和やかでリラックスした雰囲気になりつつあった。
――と、そこへ。
「あ、やっぱり! お客さんだー!」
ひょこっと、店の中から、沙夜達に向かって顔を出した人影があった。
「ほら、おれの言った通りだった! 今日は絶対ぎりぎりまで開けてる方がいいって!」
「何騒いでる。いちいちそんなこと、大っぴらに口にするんじゃない、蛍」
新たな誰かが、人影をゴツンとこづいた。いてぇ! と不満そうな、子供っぽさの残る声が上がる。
そしてようやく、花屋の主が人影の間から外に出てきて、沙夜と美夜の姿に気付いていた。
「ごめんなさい。驚かせちゃいましたね」
青年は、二人の姿を見て、まるで当たり前に待っていたようなそぶりを見せた。
「朝はあれから、大丈夫でしたか?」
一見、社交辞令のようにそう尋ねるが、二人の返事を待つこともない。良かったらどうぞ、と、当然のように二人を招き入れたのだった。
そして初めて、沙夜が「彼」の無愛想な顔を見た時。
自分の中に生まれた心を、何と名付ければ良かったのか。ずっと後々も、何度考えても、結局沙夜にはわかることはなかった。
「……あんたら……」
店内にいたのは三人。今朝の大人しげな花屋の青年と、野球帽を被った短い茶髪の子供っぽい者。
あと一人、黒く尖った、それでも丸みのある鳥頭で、高い背に黒い革のジャケットを羽織る男。
「あんたら――普通じゃ、ないな」
男が不躾に、おそるおそる店に入ってきた沙夜と美夜を、無遠慮にその黒い眼で見貫いた。
え? と驚いた二人が振り返ると、男の眼には心なしか、蒼暗い光が宿っていた。
「……どういう意味?」
圧倒されてしまった美夜をかばう形で、沙夜はずいっと男の真正面に立った。真っ直ぐに男の眼を見返してそう口にした。
「…………」
男はその沙夜の眼光に、逆に不可解そうに表情を固めてしまう。
――何、コイツ……何で何も言わないのよ?
相手から突然、つっかかってきたのだ。沙夜が自分でも珍しい程、苛立ちを感じそうになったその時。
「なーに変なこと言ってんだよ、馨兄!」
ばんばんばん! と。爽やか過ぎる笑い顔で野球帽の青年が男の背中を激しく叩き、沙夜の前にぱっと滑り込んだ。
「ごめんなーお嬢さん、気にしないで忘れて! 馨兄は時々ナンパの仕方を間違えるんだよ!」
オイ、と強く不服そうな男をものともしない。
「おれ、葉月蛍! お嬢さん達、ここらじゃ見ない顔だけど、新入生? それとも転校生?」
葉月蛍。そう名乗った野球帽の彼は、にっぱりと裏表のない顔で笑う。
何故話しかけられたか、状況が全く飲み込めない沙夜は呆気にとられる。
「ここ、おれの弟分の、番夜織って奴がやってる花屋なんだけどさ。手前みそで悪いけど結構いけてるぜ! 良かったら買ってってな!」
ひたすらぐいぐい押してくる彼。え……と、黒髪の男のことはすっかり忘れて、危うく頷きかねない状態になってしまった。
さすがに見かねる状態だったのか、花屋の青年が割り込んできた。
「ちょっと、蛍さん。勝手にヒトの本名をばらさないのと、お客さん達を脅かさないで下さい」
「――あ、あのっ!」
沙夜の後ろで縮こまっていた美夜が、やっと生色を取り戻した。取り成しに出てきた花屋の青年の方へ、震え混じりの声をあげた。
「朝は本当、有難うございました! ここのお花、お任せセットが凄くキレイってきいて、良かったら一つお願いします!」
「……――」
花屋の青年は、あれ……という感じで、何故か美夜を珍しげに見つめた。
知らない相手に怯みつつ、必死に要点だけを叫んでいる美夜。確かにその姿は可愛い、と沙夜も思ってしまう。
「だってー、夜織! お任せセット、一つ!」
野球帽の彼は、今度はそんな花屋の背中を、遠慮なくばんばんと叩いた。うわっ、という顔で背中の痛みを堪えるように身をかがめる。
「――わかりました。ちょっとお待ち下さい」
それから再び、今朝のような柔らかい笑顔を浮かべる。切花を並べたエリアに向かい、ひょいひょいと無造作に花を選び始めた青年だった。
美夜は花屋の青年のそんな背中を、何故か必死に見つめ続ける。美夜は思いもしなさそうだが、沙夜から見ると、何とフリーダムなチョイス、と驚く小さな花束ができあがっていく。
色合いや花の大きさ、種類や形など、統一感やテーマがまるで感じられない。花屋なのにアレンジは習っていないのだろうか、とまで感じられる。
が、それを青年から受け取った美夜は、思わぬ反応をすぐに見せていた。
「うわあ……! 凄い、これ本当、凄いです!」
沙夜には全然理解できなかった。美夜は心の底からその花束に感動し、それは決して、お世辞や社交辞令のレベルではなかった。
「――良かった。気に入ってもらえて」
花屋の青年はふわりと、その美夜の様子に安堵したような顔。今までのような笑顔ではなく、僅かな微笑みが目端に浮かんでいる。しかしそれも束の間だった。
「お連れの方にも用意しますね」
え。沙夜が断る暇もなく、再び切花エリアに行ってしまった。
――そして。再びやってきた青年が沙夜に渡してくれた花束は。
「……ウソ」
先程と同じだ。それは決して、フラワーアレンジメントとしてみれば全く上質ではない。
値段相応の切花が特に芸もなく、無造作に束ねられただけの花束。なのに驚くことに、美夜の感動がある程度は理解できてしまった。
「どうして……私の好みの花ばっかり……」
えっ。と美夜が、ばっと沙夜の方を向いた。
「わたしもです! このお花、名前とか全然知らないけど、どれも大好きな感じなんです!」
驚いて顔を見合わせる二人に、花屋の青年は柔らかくニコニコとする。
「それは良かったです。貴女達のイメージで選ばせてもらったので」
「くぅー、ニクイ事言うねぇ、このイロ男!」
む。と、野球帽の彼からの茶々には少し不満そうにする。
「他のお客さんの悪ふざけでご迷惑をおかけしたので。お代はいりませんよ」
笑ってそう言うと、ほらほらと青年達を追い立てながら、旧式なレジスターの電源をチン、と落としてしまった。
「えっ……! でも、そんな……!」
慌てて美夜が、ずっと手に持っていた小さなお財布を開けようとする。
「気にしない気にしない! それでも悪いと思ったらまた来てくれよな!」
「貴方が言える立場ですか、それ……」
美夜は野球帽の彼に強引に手を握られ、財布の口を閉められてしまった。一連の流れを見ながら、沙夜は言うべき言葉が見つからない。
「……イメージと言うなら……根無し草だろ、どっちかというと」
ぼそっと、ずっと黙って潜んでいた黒髪の男が、そこで呟いた一言。沙夜はいつも、そういうことを聞き逃がしはできない注意力を常備していた。
「……アナタねぇ? さっきから、いったいどういう――」
根無し草。天涯孤独の沙夜には確かに一番、ふさわしいかもしれない植物。
――何かコイツ、信じられないくらい的確な、ムカつく一言多いんだけど!?
「すみません、もう閉店時間なので」
しかしまたしても、男を窘めるように人が割って入った。花屋の青年がやんわりと扉を指して促してくれたので、沙夜は何とか心を治めて、場から離れることができたのだった。
「……何なの……あの人」
「――? 沙夜さん?」
シャッターの下ろされた花屋を後に、お任せセットの花束を持って美夜は嬉しげにしている。沙夜と黒髪の男とのやりとりは気付いておらず、ただ不思議そうにしている。黙って歩く沙夜について、朝と同じ道を逆向きに辿っていくのだった。
そして、そんな二人の後ろ姿を、ガラス戸から見守っていた三人。
彼らが沙夜達のことについて話していた内容など、当然知るべくもない。
「――ちょっと、馨兄。何、さっきの」
「……」
野球帽の青年が物凄く不満そうに、彼女らが店に入る前にこづかれた頭をさわさわと撫でる。
「おれには余計なこと言うなって言って、自分は何なんだよ? 何か一番、きわどくなかった?」
彼は痛く不満そうだが、何分全身の雰囲気が幼いため、詰問口調にはどうしてもならない。だからか却ってバツが悪そうに、黒髪の男はやれやれ、と片手で自分の頭を抱えていた。
「正直……俺にもよくわからない」
どうしてわざわざ、男は殊更、彼女の神経を逆撫でするような言葉を口にしたのか。
しかしその不可解感は、彼だけではななかった。
「そうですね。僕も少し、やりすぎました」
あー、やっぱり、と。野球帽を被り直した、一見は一番幼く見える青年が冷静に頷く。
「彼女達……普通過ぎて、おかしいですね」
そうして、夕暮れに消えていった少女達を見つめながら、彼らは同時に静かに頷いていた。
*
3
……ああ。今日は何て、長い一日なんだか。
部屋の主の陽美がお風呂に入っているので、一人でゴロン、とロフトベッドの上段に転がり、やっと一息がつけた沙夜だった。
狭間家に帰り着いた途端、陽美は「遅い!」と偉い剣幕だった。
確かに夕方花屋を出た後、道をよく覚えていなかった美夜の家までいく形になり、思ったよりも帰宅時間が遅くなった。
「うちの門限は六時だし! ていうかあんた、ちょっとこっち来なさいよ!」
――門限? そんなの初耳なんですけど!?
しかし、台所で待っていた狭間さんの困り顔に、沙夜は弁明できなくなってしまった。
台所ではゴミ箱の蓋が開けられて、中には沙夜に用意されていたと思われるお弁当が、容器ごと打ち捨てられていた。
「朝、せっかくお母さんが作ってくれたのに。これどういうこと?」
――どういうことなんて……私がききたい。
どう考えても、沙夜のお弁当を勝手に捨てて、十円菓子とすりかえたのは目前の娘としか思えなかった。
「……」
いつもは穏やかな笑顔の狭間さん――黒髪で七三分けの四十台男性が、硬い顔つきで腕を組んで黙り込んでいる。
――陽美さんが悪いなんて……言えない。
迷惑をかけたくないなら、それが一番だろう。
それでも沙夜は、やってもいないことを白々と、ごめんなさい、と言える程不誠実ではない。
「…………」
狭間さん以上に硬い顔色で黙り込んだ沙夜に、狭間さんはやがて、大きな溜め息をついた。
「……沙夜君。とても残念なのだが……」
ゆっくりと、低い声で話し始める父親に、陽美はこころなしか期待するような目つきをしたが、
「こういうことは、なるべく我慢して振舞ってもらうように、大人としてお願いするよ」
狭間さんからの叱責らしき言葉は、たったそれだけだった。
「……――」
拍子抜けした沙夜が顔を上げると、そこには、納得がいかない様子の陽実と、難しい顔で考え込んだ狭間さんという、よくわからない光景が広がっていた。
その後は結局、それ以上のお咎めはなかった。多忙らしい狭間さんが、珍しく一緒の夕飯が終わり、さっさと部屋に帰してもらった沙夜だった。
「さっきのって結局……どーいう意味?」
ベッド上で、一人ごちる沙夜の「さっき」は、狭間さんのよくわからない苦言だけではなかった。
――あんたら――普通じゃ、ないな。
むかむかむかグサ……。
夕方の出来事を思い出すと、何故か先程のお弁当事件以上の怒りが沙夜を襲った。
「ていうか……」
アイツ、陽美さんよりムカつくのは何で?
美夜と別れるまでは何とか抑えていたが、ここまで自分が腹を立てていたとは、ここで一息つけるまでは沙夜は気付いてすらいなかった。
あからさまな嫌がらせをする狭間陽美に、沙夜が抱く思いは色々と複雑だ。
腹も立つし、現実問題生活上も困るので、できればもう少しうまくやっていきたい。
――でも……陽美さんの気持ちも、わかる気もするし……。
他人である沙夜には、狭間さんは穏やかな良い人だ。しかしもしも彼が自分の父親で、突然見も知らない相手と同居を強要し、何かあった時にもあの歯切れの悪さでは苛々もするだろう。闖入者に八つ当たりだってしたくなる。
それでもこう何回も嫌がらせをされると、怒りというより、気疲れが強まる一方だった。
――根無し草だろ、どっちかというと。
ぐさぐさぐさムカ。
青年のその言いぶりは、それ自体は正しかった。
「そりゃ、誰とも……今も連絡取るような人、いないけど」
胸元に揺れる青い石だけが、辛うじて一つ、確かに与えられた愛を示す。けれど贈り主は死んでしまったし、何より沙夜は、最後まで彼女に打ち解けることができなかった。
「だって……」
その青い目で若い、義理のお母さんは、
「普通じゃ……なかったんだもの……」
そう言って周囲の人――夫にすら怖がられた。遠巻きにされていた儚い面影が瞼に浮かんだ。
――サヤ、と。
日本的な名前を発音し難そうに、それでも常に、穏やかに微笑みながら呼んでくれた。
多分初めて、沙夜を我が子のように可愛がってくれた。異国の女性の青い目が、ペンダントの向こうに見えた気がした。
これまでひたすら、たらい回しにされてきた沙夜は、一時はアメリカで暮らしていたこともあった。だから実は、英語もペラペラに話せる。
その時の養母が、沙夜がずっとつけている天然石の、青いペンダントをくれた人だ。
若くして病気で亡くなったその養母は、元々異常な世界に近い感じの人だった。様々な予言めいた言動をしては、よく周囲の人達を驚かせていた。
「普通じゃないっていうような人は……多分、ああいう人のことだよね」
沙夜もあまり、養母の言うことは理解できなかった。それでも養母が「悪いことが起きる」というと、必ず何か嫌なことがあった。
――別に、お義母さんのせいじゃないけど。
いつしか自然と、その養母とはあまり、話をしたくないと思ってしまった。沙夜をとても、可愛がってくれたにも関わらずに。
その養母との生活は、養母が亡くなるまで二年続いた。多分一つの家で暮らせた最長記録だ。
養父の方とは、当たり障りなくやっていたが、養母が亡くなるとすぐに縁を切られ、現在も音沙汰は全くもってない。
だから、沙夜を求めたのは完全に彼女で。
――私はずっと、可愛い娘がほしかったの。
そんな彼女が、最後に沙夜に遺した言葉は。
痩せこけた青白い顔で、死の間際に彼女は、沙夜に伝えた。かなり迷った様子を見せて、沙夜の手を握って、形見のペンダントを持たせながら言った。
――サヤ。貴女は最初に愛した人とは生きることができない。
何故なら。彼女は哀しそうな目をして囁く。
――貴女はその人と、出会うことすらできない。
そんな不吉な予言を伝えられて。沙夜は、死にゆく彼女に歎いたらいいか、それとも怖がるところか、自分の心を見失った。
ただ、不思議と涙だけは、ひたすらとめどなく流れ落ちた。手を握る養母の両手をぽたぽたと濡らし続けていた。
最初に愛した人と、私は生きられない――
正直、今でもその意味は、よくわからないままだ。
――でも忘れないで。貴女は沢山の愛に出逢う。
曖昧さのない英語には多分、覚え違いはない。
優しく頬を撫でてくれた記憶も、儚い愛も。
――だから決して諦めないで……大切にして。
きっと、その声があまりに優しかったから。最後まで養母に心は開けなかったとはいえ、今でも沙夜は、信じているのだ。
例えその予言を、理解していなかろうと。
今度こそ。私は絶対、幸せになれると。
「だってあれだけ、悪いことは当たったんだし」
それなら良いことだって、当たってもいいだろう。その石を見つめていると、そんな風に思えた。
寝ている間に絡まないよう、そっと、青いペンダントを外す。いつまでもお風呂から上がらない陽美を、待つのを諦めた沙夜だった。
――もうさっさと寝て、明日は朝一番でお風呂借りよう……。
養母のことを久々に思い出したせいなのか、いつの間にか治まっていた怒りも忘れた。
「明日の朝……美夜ちゃん、会えるかな……」
一緒に登校しよう、と一応待ち合わせをした、少女の朗らかな笑顔を思い出した。少しだけ安らいだ気持ちで、まだ少々早い時間だが、沙夜は眠りに落ちていけたのだった。
*
今度こそ本当に。というよりついに。
陽美は洒落にならないことをしてくれた、と、沙夜は叫びたいような思いに揺さぶられて、高校のゴミ収集場で手当たり次第にゴミ袋をひっくり返していた。
――助けて、美夜ちゃん。
どうしてここまで自分が混乱しているかも、正直よくわからなかった。それでも、今の自分を落ち着かせることができそうなのは、唯一その名前だけが度々浮かんだ。
あれから、可能な範囲で登下校を一緒に、と美夜と約束した。しかし美夜は、翌日から早々、二日連続で学校を休んでいた。
普通の現代の若者達なら、スマホやネットで理由がきけて、元気かも簡単に確かめられる。けれど沙夜は何一つ、そういうツールを持っていない。露骨に無視されている狭間家では、電話一つ気軽に借りることもできない。
――そもそも、連絡先もまだ知らないし。
仕方ないので、今日は放課後に直接家まで行ってみよう、と思っていたのだが……。
「え――ない?」
着替えを置いた机の上で、制服の間に挟んでおいたはずの、ペンダントに起きていた異変。異様なことに、天然石のペンダントトップだけが、鎖紐を残して忽然と姿を消していた。
鎖紐の装着部の金具を見ると、不自然な歪みがあった。どう見ても引き千切られた痕だった。
「何、変な顔してんのよ。落し物でもしたの?」
にやにやと、意地悪な顔をして楽しげに言う陽美に、誰が犯人かは明らかな状態だろう。
今日は転校してから初めての体育の授業で、英語と体育を得意とする沙夜は、久しぶりに張り切って授業に参加できた。同級生達も、沙夜の鮮やかな身のこなしを見て感嘆の声をあげ、やっと一人二人、話しかけてくれる人が現れていた。
陽美は見学していたが、度々姿の見えない時間があり、多分その間に仕掛けたことだ。
「あ、あの……ペンダントがなくなったんです……!」
あまりに焦って、無駄と知りつつ、沙夜は言わずにおれなかった。
「寿命で壊れて、勝手に千切れたんでしょ」
それだけ言うと、陽美は満足そうな顔をして、自分の席へと戻ってしまった。
「……――」
何故か沙夜は、いてもたってもいられなかった。
六時限目の授業がまだあることにも関わらず、教室から飛び出し、まっすぐゴミ収集場へ向かったのだった。
「ない……ない、どこにもない……!」
もうこれで、いくつめのゴミ袋をぶちまけただろう。汚れの目立ち難い濃灰のブレザーまですっかり黒ずみ、そもそもここに探す物があるとは限らない不安が、ますます沙夜の頭を混乱させていく。
「ない……見つからないよ、お義母さん――」
何故なのだろう。彼女を失った時のような、わけのわからない涙が両目に溢れていく。
沙夜は彼女に、心を開いていなかったのに。
――だから決して諦めないで……大切にして。
彼女の優しい声が、頭の奥にがんがんと響く。周囲をゴミに囲まれながら、沙夜は途方に暮れて座り込んでしまった。
こんな、泣いてる場合なんかじゃないのに。
早く次を探さなきゃ、と、手は必死に新しいゴミ袋に伸びる。それでもこれまで、ぶちまけては詰め直したゴミ袋の中身だって、決して完璧に探せたわけではなかった。
「こんなの……探せっこ、ない……」
透明度の低い薄い青で、球形の小さな天然石の欠片。養母の青い目を思い出させるその石は、一度失えば、取り戻すにはあまりに儚過ぎた。
そんな、一人ぼっちの彼女の姿を、彼はつい、見るに見かねてしまったのか。
「……オイ。何やってるんだ、あんた」
ぼそっと、背後からかけられた気怠げな低い声。沙夜は涙目のまま、ゆっくり後ろを振り返った。
「って……え?」
そこにいたのは、暗い紺のブルゾンの制服を着て、同じ色の帽子を被った男。どう見ても生粋の、郵便配達人で。
「仕事中だよ。あんたも本当は、授業あるだろ」
その郵便配達人は、ゴミ収集所の近くにあるポストを指差し、集配物が入る鞄も見せて、深めに被る帽子をとった。
「って、アナタ、この間の!」
沙夜は思わず立ち上がった。帽子の下から現れた黒髪の、丸みある鳥頭を持った男。先日花屋で喧嘩を売ってきた彼に、警戒心満天の涙目を向ける。
「……アナタとか言われると、くすぐったいな。俺は鷹野馨だ。あんたは?」
「えっ……さ、沙夜。――狭間、沙夜」
そうか。と落ち着いた無表情でマイペースに頷く彼、鷹野馨に、沙夜は何だか気勢をそがれる。
「……何の用?」
涙を拭いながら、そうきくだけで精一杯だった。
「……」
馨は無表情に、沙夜の汚れた制服を一瞥する。
「……失くし物でもしたのか、あんた」
この状況を見れば、誰でもわかるだろう。何故か重々しく、静かに口にする。
「……」
またしても溢れてきた涙を抑えんと、黙って一度だけ沙夜は頷く。
「失くし物の一部か写真――持ってるか?」
「……え?」
馨は淡々と、沙夜の目をまっすぐに見て言った。
沙夜はわけがわからないまま、そう言えば、と、千切られて残っていた方の鎖紐を取り出した。
「――上々」
馨はその鎖紐を沙夜から受け取ると、静かに柔らかく握り締めて、両眼を閉じた。
「――」
まるで、息の詰まるのような緊張した空気が、眼を閉じた馨の全身を包み込んだ。
けれどそれは本当に一瞬で、その後一分もたたない内に馨は眼を開けた。
「――ゴミはゴミだけど。どうやらまだ、ゴミ箱の中にあるっぽいぜ」
そう口にすると、くるっと振り返って、足早に歩き始めた。
「えっ――」
鎖紐を持ったまま、さも当たり前かのように構内へ向かっていく。この高校のOBなのか、勝手知ったる我が家という感じで、迷わず体育館の方に足を進める彼を、戸惑いながら沙夜は小走りでついていった。
うそ……と、沙夜は思わず、立ちすくんだ。体育館裏の倉庫のゴミ箱から、青くて白い小さな天然石が出てきた。
ほらよ、と石を手渡す馨に、お礼も言えずに黙り込んでしまう。
「大事にしとけよ。それ、あんたを守りたい想いが込められてるぜ」
「え……なん……で――」
――何で、わかるの?
やっと何とか、それだけ口にした沙夜に、馨は少しだけ迷った様子で、やがては諦めたように息をついた。
「何でも何も。わかるものは、仕方ないだろう」
そして、あんただって、と意地悪そうな顔で言う。
「何で自分が、天涯孤独かなんて、きかれてもどう答えようもないだろう?」
「――」
きょとん、と、沙夜は目をまん丸くした。馨はにやりとする。
ムカ……と、純粋なむかつきがお腹の底から湧き上がってきた。それでも手の中にある青い石の感触で、何とか冷静に心を鎮めた。
「それ……何の関係があるの?」
純度の高い怒りの効果か、先程までの混乱も忘れ、元の調子に戻りつつある沙夜に馨は不敵に笑う。
「どっちも天命ってことだ。どうしようもない」
だから、何でなんてきいても仕方ないだろう。
ペンダントの在り処だけではなく、沙夜の身の上まで当ててしまった馨は、そんな風に何処か、儚くも見える顔で笑った。
「……おかしな人」
沙夜はペンダントを、当座の保管場所として小銭入れにしまい、溜め息をついた。
「そうか? 俺は至って真っ当な、一介の郵便配達人だけどな?」
不機嫌そうな沙夜に、何故か馨は楽しげに、そんな軽口を始める。
「何よ。私だってごく普通の女子高校生だし」
「……本当、そうだな。普通過ぎるのが変というか、逆に普通であることが異常というか」
「――どういう意味?」
もう何度、この男に尋ねたかもわからない問いを、改まって沙夜ははっきりと口にした。
馨はそんな沙夜に、更なる燃料を注いでくる。
「あんた、親に捨てられたんだろ?」
けろりと簡単に、そんなことを口にする性格の悪い男。沙夜は平然と睨み返した。
「なら、少しは歪む方が普通じゃないか?」
「だったら何なの?」
本当に冷静に、沙夜は普段のままの顔でいた。今までだって何度も、同じ類の無頼漢の声に、沙夜はそう返してきたのだ。
「親には親の事情とかあったんだろうけど。それって私の責任じゃないわけだし」
「ふーん……なるほど?」
「親がどうあれ、私自身のことは――私がどんな人間になるかは、私の自由だもの」
それが、様々な暮らしを経験する内に沙夜が掴んだ、沙夜なりの生きる筋道だった。
今この環境に生み落とされて。どんな風に生まれるかまでは、誰も選べないのだから。
「私は悪くないし、間違ったこともしてない。だから真っ当に生きる限り、普通に幸せになる権利、あるはずだもの」
どうしても上手く説明できないので、いつもそう言うしかない沙夜だ。
「――親のことは、普通じゃない言い訳にはならない、ってことか」
馨はそんな沙夜を、眩しくも痛ましくもあるような、蒼い眼で見つめていた。
「……」
元々、沙夜は口下手な方だ。
――何かかなり、違って伝わってるような?
しかし勤務中だった馨がくるっと踵を返してしまったので、それ以上無理に話そうとは思わなかった。
「――」
じゃあな、と遠ざかっていく郵便配達人に、有り難うと言い忘れたことだけが気になっていた。
*
4
六時限目の授業どころか、HRもとっくに始まってしまった。
体育館裏から裏門に出て、こっそり学校を後にした沙夜は、一路、美夜の家へと向かった。
途中にどうしても、店の前を通ることになる例の花屋。ここ数日の登下校時、何故か必ずタイミング良く花屋の青年に出くわし、早くも二人は「沙夜さん」、「夜織さん」と名前で呼び合う間柄になっていた。
――別にそこまで、仲いいわけじゃないけど。
何度も名字の変わった沙夜は、自分を名前で呼んでもらうように習慣化している。それでも確かに、夜織が話しやすい相手であることもあった。
「へえ……。全然見ないとは思ってましたが、学校休まれてたんですね、もうお一方は」
番夜織は、元々沙夜達の通う高校のOBで、現在十九歳らしい。卒業してすぐこの花屋を営み、大学には行っていないということだった。
「良かったらこれ、どうぞ」
お見舞いです、と夜織が差し出した花束を見て、軽く息をついてしまう。
「……ありがと。美夜ちゃんに届けるわ」
本当はタダで受け取りたくないのだが、転校初日に美夜の家に行った時、「病気の母」がお任せセットの花束に大喜びしていた。狭間家に持ち帰るのが微妙な沙夜の花束も飾ってもらったので、ま、いっか、と憮然と受け取った沙夜だった。
「多分美夜ちゃんは、元気だと思うんだけど」
「わかるんですか?」
「何となくだけど……お母さんの方に、何かあったんじゃないかな」
どうしてか、沙夜の中にはその確信があった。夜織が不思議そうにしているが、説明できる理由もないので誤魔化すことにする。
「あのさ、前にここにいた――鷹野馨さん?」
話題を変えるためとはいえ、こちらも大事な用件だった。沙夜の口からその名が出たことに、更に不思議そうな顔で夜織が沙夜を見る。
「今日、ちょっと助けてもらったことがあって。でもお礼言い忘れちゃって、もしまたここに来たら伝えてもらえない?」
「馨さんが人助け? 珍しいこともあるものですね」
夜織は沙夜より二つも年上なのに、物腰が柔らかい。それでいて率直で、夜織の方が丁寧語なので、どちらが年上かわからない状態だ。
「ふーん……珍しいの?」
「ええ。彼はあの力は、隠して生きてますから」
――……と。しれっと口にした夜織に、沙夜は思わず、花束を握り潰しそうになった。
「待って――夜織さん。馨さんがどうやって私を助けてくれたか、わかるの?」
「……」
……あ、しまった。自分で自分を不思議がるように、夜織が目を丸くしている。
「沙夜さんには何か、嘘がつけないばかりか、隠し事も難しいみたいですね……」
だからなのかな、と。一人で勝手に納得したように、夜織はうんうん頷いている。
そして改めて、夜織は苦笑いをして言った。
「別に、沙夜さんと馨さんに、どういうことがあったのかはわかりません。ただですね……沙夜さんが、アイツ何者!? と強く思ってるのはとても伝わってくるんです」
「って――えっ?」
「そして、そうですね。沙夜さんが感じてる通り、僕達は異常者です。……でも――」
内緒にしてくださいね、と。にこにこ笑って簡単にそんなことを言う。
「はい――?」
沙夜は確実に一歩、後ずさりながら、そう返すしかできなかった。何故なら、図星だったからだ。
しかしこれは、夜織流の、タチの良くない冗談。咄嗟にそう必死に飲み込む。
夜織はそれ以上は何も言わず、にこにこと黙って、美夜の家に向かう沙夜に手を振った。
そんな彼の挙動を、家に辿り着いてから、美夜に話してみたところ……。
「――それはもしかすると、あれですね!? 最近流行りの超常現象とか怪異みたいな!」
「いや……別に、流行ってないと思うけど……」
美夜はちょうど、夜からバイトに出る所だったという。在宅中に来れたのは良かった。
全く元気でぴんぴんしている美夜と、家の奥で、やはり調子が悪いらしい美夜の母がいた。
「昨日と今日と、病院で点滴してもらって。後三日は少なくとも行かなきゃダメみたいで、ちょっと当分、学校休みますね」
かなり考えていた通りの状況に、沙夜自身、もやもやとした思いを抱える羽目になった。
「しかし美夜ちゃん……超常現象とか、そういう話、好き?」
「えぇー。沙夜さんは嫌いですか?」
正直、あんまり……と口にすると、美夜は少しだけ残念そうにしていた。
実際にそちらの世界に住む人――たとえば沙夜の養母。そういう人と暮らしたことがあれば、沙夜の気持ちもわかってもらえそうだ。
「でも確かにあのお花屋さん、何だか不思議空間ですし! 沙夜さんの体験が本当ならきっと、透視とか共感とかそういう何か、不思議事が実際にあるに違いありません!」
現状、自らそちらに飛び込みたがっているこの様子は、一応止めねば、と沙夜は苦笑う。
「でも、内緒にしてって言ってたし。確かに表沙汰になれば、あの人達も困ると思うよ」
……。馨や夜織から、直接話されたわけではない美夜は、ぐぐ……と頷くしかない。
話題を変える必要を感じた沙夜は、すっと家の中を見回して言った。
「ところで美夜ちゃん、何時頃、家出るの?」
「えっと、後一時間後です」
そっか。一時間あれば何とかなるな、と沙夜は立ち上がった。
「台所と食材、使っていい? 夕飯作るよ」
……? 美夜は、沙夜が何を言っているのか、全く飲み込めないように首を傾げた。
「バイトまで、美夜ちゃんは休んでなよ。朝もバイトで疲れてるでしょ?」
早朝バイト、母の通院、いくつかの家事、そして夜バイト。美夜の今日一日の流れをきいて、沙夜はそれを心に決めていた。
「って――そんな、ダメです! 沙夜さんはお客さんなんですし、沙夜さんこそゆっくりしてください!」
「時間が勿体無いから、借りるよ。使ったらまずいものあったら教えて」
有無を言わせず台所に入り、冷蔵庫の中身や調理用具を確かめ、沙夜は腕まくりをした。
これまで長い居候生活の賜物で、沙夜は一通りの家事はできる。主婦のように手早くできるかと言われれば怪しいが、自分のペースで良いなら、普通にきちんとした仕事ができる。
「沙夜さん……あの――」
調理用具はどれも、豊富に揃っているわりに、しばらく使われた形跡がない。おそらく、美夜の母は料理をしていたが、美夜はあまり得意ではないのだろう。
棚にはいくつか缶詰やインスタント食品があるが、新鮮な食材はあまりなかったので、沙夜は手早く献立を決める。
「パスタ作るね。後、お母さんにはお粥と」
「…………」
この状態で作れるとしたら、そんな感じか。今度は美夜ちゃんと買い物に行ってみるのもいいな、と、寂しい冷蔵庫を見ていて思った。
ぱっぱっと準備をし始める沙夜に、美夜は台所の入り口に立ったままで。
やがて、じんわりと、両目に涙を溜め始めた。
「――って、美夜ちゃん?」
焦り顔で振り返った沙夜に、美夜はぶんぶんと首を振って涙を拭う。
「ごめんなさい! 何かもう……沙夜さん、優し過ぎるから……」
沙夜がどうしてそんなことをしてくれるのか、全くわからないらしい美夜は、俯きながら呟いている。
「沙夜さんの方が大変なのに……いっぱい、しんどいことあるのに……」
陽美からの迫害っぷりなど、別に特に話したわけではない。自分が養子であること、それでいくつも住む家を変わってきたことは、初日の帰り道で美夜には打ち明けていた。
「そうかなぁ……私には、美夜ちゃんの方が大変に見えるんだけど」
私は、生活できなかったことも、生活のために外で働いたこともなかった。沙夜はそう思う。
環境は次々と変わったものの、後見人という存在は確固としてあり、お金も自由に使える分はないが、衣食住は確保されていた。
対して美夜は、生きていくための糧を、この歳にして自分で得なければいけない。それも病気の母親を抱えて。その不安はどれ程だろう、とどうしても心配になる。
「ほら、泣かないで。何か私、悪いことしてるみたいじゃないの」
ぐすっ。パスタのソースに使えそうな缶詰を棚から取り出しながら、沙夜はぽんぽん、と俯く美夜の頭を撫で叩いた。
「美夜ちゃんが笑ってくれると、何だか私、元気が出るんだから。たまにこうして、おうちに来てもいい?」
ばっと美夜は顔を上げると、何を言うべきかわからなかったらしく、とにかく必死で首をうんうんと振る。
――うん。何か本当、美夜ちゃんって癒しだ。
この出会いがあったことが、今回の引越しでは一番の収穫だった。沙夜は素直にそう思えていた。
そうしてコンロへ向き戻り、夕飯作りを続ける沙夜の姿に、美夜は今度はマジメに、何かを真剣に考えているようだった。
そして美夜の出発直前。彼女が何を考えていたのかが、あっさり明かされることになる。
「へっ……ぴーえっち、えす?」
突然美夜から手渡されたソレは、白くて縦長の手の平サイズで、一昔前の携帯電話を彷彿とさせる有名な通信端末、プラス充電器だった。
「沙夜さん、携帯とか何もないんですよね? 昨日今日みたく、待ち合わせに行けない時とか、どうやって連絡しようか悩んでて……これ、余ってるので、使って下さい」
――携帯が……余る??
沙夜には全くもって、理解不能なことを美夜は言う。しかし本気らしい。
「元は母さんが使ってた物なんです。でも最近はもう、外には出れないので……費用も家族契約だから、私とは通話料もタダですし」
そもそも……! と、美夜がイキイキとし始めた。
「元々メールもタダの上、ネットは見れない単純端末だから通信費はかからないし、更に家族割キャンペーンで基本料金タダなんです! だから全然使ってないけど解約してなくって、もったいないって常々思ってたんです!」
最早沙夜には、何が何だかさっぱりわからない話。美夜の熱い勢いに頷くしかできない。
「本当は家族以外が使うのはダメですけど、これなら全然お金がかからずに、沙夜さんと連絡がとれるんです。わたし、沙夜さんと電話やメール……したいです」
最後の方は、しゅん……と。それが一番の本心であるように、子犬のような目で沙夜を見る美夜だった。
「でも……大本の契約料金は、美夜ちゃんが払ってるんでしょ?」
常識的に考えれば、こうした物を借りるのは有り得ないことだろう。美夜もそれがわかっているから、先程あんなに考えていたのだ。
「わたしがわたしの料金を払うのは当然です。でも沙夜さんに渡す方は、元々タダです」
それは決して、嘘ではないらしい。どうやら美夜は相当、この手のキカイ系に強いように見えた。
「……ありがと。じゃあ、美夜ちゃんにだけ、使わせてもらうね」
「メールだけなら、他の人とも大丈夫です。わたしがこの町にいる間は、良ければ好きに使って下さい」
何とかPHSを受け取った沙夜に、美夜は本当に嬉しそうに、そう笑ったのだった。
「……」
でもなぁ……と。先畑家を出てから、沙夜は項垂れた。既に門限らしい六時を過ぎていることもある。
「陽美さんとかにばれたら、何て言われるか」
しかも正直、全く使い方がわからないこと。今日はそこまで聞ける時間はなかった。
「明日また、美夜ちゃんち行って、きこ……」
それでもこの数日間だけでも、これまでにない新しい世界。いつまで続いてくれるかはわからなくても、気分はとても良い方だった。
「嫌なこともあるけど……良いこともあるよね」
美夜から渡された白いPHSを眺めて。心からの気持ちで、穏やかに沙夜は笑った。
……ところが。
――ちょっと待って……!
新しい世界、新しい出来事。それは時に、立て続けのタイミングで訪れることもある。
「――沙夜君。来週の土曜日に、私と一緒に携帯屋さんへ行こうか」
「……へ?」
狭間さんから突然、そんな話が出た時には。沙夜は自分の耳を疑った。そしてちらりと、陽美の顔色も伺わずにはいられなかった。
今夜も帰った狭間さんのおかげで、本当にあるかが疑わしい門限や、六限以降サボりの件で陽美に怒られることはなかった。穏やかな食卓で、狭間さんから色々話しかけられた。
「ところで沙夜君。身の回りで何か特に……変わったことが起きた、ということはないかね?」
「――はい?」
そんなの、ないですけど……。狭間さんの意図が全くわからず、沙夜は無難にそう答える。
「そうか。しかしだね……もしも今後、何かあった時には、遠慮なく私に連絡をとってほしい」
そうして、だから携帯が必要だろう。という流れになったわけだった。
「……」
陽美は始終黙り込んでいて、沙夜に向かってそんな事を和やかに話す父を、横目でこっそりずっと睨んでいた。
色々話したいこともあるから、と。狭間さんにしては強引に、沙夜を連れての携帯屋行きがその後、決まってしまった。
「まさか……もう持ってるなんて、言えないし」
――そもそも、陽美さんの沈黙が怖過ぎだし。
できれば何とか遠慮したい珍事態。沙夜はひたすら、頭を抱えるのだった。
*
美夜がようやく学校に復帰したのは、週が明けてからのことだった。
「沙夜さーん! お昼ご飯、食べましょう!」
病気の母は、一旦何とか落ち着いたようだった。もう少し悪ければ入院ということらしいが、不思議なほどに彼女の容態は、本当にまずい状態の一歩前でずっと維持されているらしい。
「ごめん、美夜ちゃん……私、お弁当なくて」
転校初日のお弁当事件以来、沙夜にお弁当は必要ないのよ! という流れになってしまった。昼はひたすら、毎日水を飲んでしのいでいる沙夜だった。
「残り物、いっぱいあるんです! 私得意の炊飯器クッキング、伊達じゃないですよ!」
美夜はまたそんな謎なワードを口にしつつ、確かにやたらに量は一杯の、よく味の染みた煮物を持参していた。
水しか飲んでいない沙夜を昼に誘うのは気まずいのか、少しずつ話せつつある同級生とも、まだお昼の壁は越えられていない。
「美夜ちゃんも……ちゃんとクラスで友達、作らないとダメだよ……」
沙夜は少しだけそう憂いつつ、うきうきお弁当を必ず多めに持参する美夜と、裏門でお昼を一緒にするのが日課になっていた。
「ごめんね、ご馳走になって」
お詫びにまた夕飯作るね、と言うと、美夜は笑う。
「えへへへ、実はそれが目当てなんですよ! だから遠慮なく食べて下さいね!」
美夜が学校に復帰する前から、何度となく美夜の家にいって家事を手伝った沙夜は、もうすっかり美夜の母とも顔見知りになった。
「直美さんはどう? 体調大丈夫?」
「何だか最近、沙夜さんが来てくれるようになってから、母さんも調子が良くて。沙夜さんのご飯は美味しいって、少しでも食べてくれるんですよ」
そう……と沙夜は、直美の青白く痩せた体を思い出しながら、言葉を濁していた。
――沙夜さん。あなたにはわかりますよね?
「本当に、わたしも料理、上手ければなぁ。母さんももう少し、食が進むだろうに」
「……」
その美夜の空元気が、沙夜には辛かった。
美夜の母である直美は、美夜がいない時にやって来た沙夜も、歓迎して家にあげてくれた。
一見大人しげには見えるが、元々気丈な女性なのだろう。動くことすら辛そうな体なのに、寝床から出て沙夜を出迎える。
――私はもう長くありません。だから……。
……沙夜が気付かずにいられなかったのは。直美が、若くして亡くなった沙夜の養母と同じ顔色で、同じような薬を飲んでいたこと。
――お義母さんも……死んじゃう少しだけ前、不思議なくらい持ち直した時、あったし……。
わたしには、母さんがいるから。沙夜と自分の境遇をあえて比較する時、美夜は自分の方が余裕があるから、と強調する。
何かできることがあったら言ってほしい、と。親身にそう言ってくれた少女が、もうすぐ大切な身内を失ってしまう。
「ねぇ、沙夜さん。今日またあのお花屋さん、寄ってもいいですか?」
母さんに花を買っていきたいんです、とそう笑う美夜に、沙夜はノーとは言えなかった。
あれから沙夜は、夜織との遭遇率は減っていたが、花屋に近い郵便局に勤める馨や、その従弟らしい蛍とよく顔を合せた。沙夜の帰る五時過ぎに彼らは出入りしており、顔見知りの間柄になった。
――でも美夜ちゃんは学校休んでたから、全然行けてないわけだしなぁ。
「……あんまり、長居はしないでいこうね。直美さんも待ってるだろうし」
はい! と素直に笑う美夜は、沙夜の真意をわかるはずもない。
――あんまりあの人達……関わりたくないし。
特にあの、馨と夜織とは、と。沙夜はこっそり気を引き締める。
――あんたら、やっぱり普通じゃないぜ。
――沙夜さんは、普通じゃないと思いますよ。
何故か二人は、まるで示し合わせたように、同じことを沙夜に言うのだ。
「……ほんっと、失礼な……」
「――沙夜さん?」
不思議そうにする美夜に、慌てて何でもない、と言う。
そう言えば「あんたら」と複数形で言った馨は、あの初日以外に何処で美夜を見たのか、少しだけ気になった沙夜だった。
普通であることが普通じゃない。
馨も夜織も、言葉は違うが同じように言う。
――何つーか……沙夜さん、健気過ぎねぇ?
最近よく話すようになった、後一人の青年、野球帽と白いTシャツの似合う蛍はそんなふうに言った。
葉月蛍は、あの三人の中では普通に見える。
――ちょっと見た目とか、口調とか幼いけど。
蛍の二つ年下の夜織より子供っぽいのは難だが、すぐに人がぐさりとくるようなことを言う馨や、沙夜が自分でも気付いていないようなことを言い当てる夜織に比べると、蛍の話題はマトモだった。
PHSの使い方とか、連絡先の交換の仕方。そうしてちゃっかりと、美夜以外では初めての、沙夜のメル友になっているのも蛍だ。
――ついに大型二種免許とったぜ! これでおれも夢に一歩近づきんぐ☆
そんな、用件も何もないメールが入った時は、沙夜は何とも感動したものだった。
――美夜ちゃんのお母さんの状態が悪くて、私に何か、できることってあるかな?
そうメールで何となく相談した時、返ってきたのがさっきの言葉――「健気過ぎ」だ。
――何で、健気?
そう返すと蛍はその後、少し謎のメールを返して来ていた。
――沙夜さん、お母さんに頼りにされるよ。
それだけ返してきて、やり取りは終わってしまった。それ以外は普通に、何でもないメールを続けていた。
HRが終わると、今週は陽美も沙夜も掃除当番でないため、すぐに学校を出ることができた。
しかし美夜からは、メールが入っていた。
――ちょっと用事ができたので、先にお花屋行ってて下さい。
う。一人だとあんまり行きたくない、それが沙夜の正直な所だ。
「……」
とりあえず店が見える所まで来て、遠目から店の様子を窺ってみた。
ちょうど夜織が、数人の女子高校生客の相手をしていて、板についた愛想の良い笑顔を見せる。沙夜はアレ、と違和感を持った。
「何あれ……すっごい、営業スマイル……」
最初に美夜と話した時や、沙夜が店の前を通って話す時は、あんなにあからさまな作り笑顔ではない。その辺り、無愛想なことを隠していない馨や、常時天然スマイルな蛍とは、目先の夜織はかなり異質に思えた。
「あ、沙夜さーん! 遅くなりましたー!」
女子高校生が去るのを待っていたら、美夜が追いついてきた。すっかり裏門の塀を一人で越えられるようになった美夜に、沙夜は少し苦笑いする。
「今夜織さん、忙しいみたいよ。ほら」
「あー……本当、ですね……」
美夜は、その様子を見て、しばらくその場で立ち止まってしまった。
「……」
どうした偶然なのか、美夜も何かその光景に思うところがあるらしい。ともすれば、切なそうな、そんな顔をしている。営業スマイルの夜織を見る美夜に、沙夜はがん、と衝撃を受けていた。
――あれ……これ、ちょっとまずくない?―
美夜は多分、夜織のあの作り笑顔に、沙夜と同じように気が付いている。しかしその方向性は、沙夜とは違った。
「何でかな……何か、辛そうに見えます……」
そう呟いて、今まさに、美夜は涙しそうな勢いだった。
それはおそらく、初めて会った時の夜織が、美夜の前では本当に自然な笑顔をしたからで。あの愛想笑いを辛く感じるとしたら、多分、自然な彼に好意があるのではないか。
「美夜ちゃん……まさか……」
一目惚れ……? みなまで言えなかった沙夜は、ただ呆然と、息を飲んだのだった。
*
何故か毎日、放課後に花屋に通うことまで、沙夜と美夜の日課となってしまった。
「沙夜さん、遅くなってすみません!」
「う……うん……」
週末の夕方、五時ジャストに花屋に入る。
客足の少なくなる時間帯から、閉店までにフラワーギフトを作るのを手伝ってほしい、と夜織からの直々のバイト依頼だった。
「以前は馨さんが手伝ってくれてたんですが……就職されてからは忙しくなっちゃって」
夜織は花屋などやっているわりに、そうした華やかな飾り物の演出というのは苦手らしい。ボックスフラワーやフラワーバスケットなど、どうしても需要はあるため、こうした対策で何とかニーズに応えている。
「育てる方が得意なんです、僕」
この花屋にある花の半分以上は、屋上で自家栽培されたものらしい。美夜が目をきらきらさせる。
「凄いですね! 季節外のお花もあるのに!」
喜んでいるが、店では何を手伝うでもなく、依頼をされたのは沙夜だった。美夜もそうしたアート系は苦手らしく、単に沙夜についてきて、他のバイトまでの時間、入り浸っているのだった。
しかし夜織も、沙夜の付き添いとしてくる美夜に、何の文句もありそうにない。
「美夜さん。これどうぞ、お母さんに」
「すみません……いつも頂いてばかりで……」
「いえ、どうせ閉店後は処分するものなので」
むしろこれ、ひょっとして私、ダシの状態?
こつこつと沙夜は、生花を完全な我流で飾りつけながら、釈然としない思いで初めてのバイトに精を出すのだった。
以前に馨が作ったという、数々の見本の写真を見るにつけて、やるせなさが沙夜を襲う。
――何でこんな隙のない物作れるの、アイツ。
馨も我流で作っていたらしいが、女性の沙夜より優れた美的感覚を窺わせる作品。細かい所にも気配りの行き届いたアレンジに、ただ悔しい、としか言いようがなかった。
馨も夜織も、そして蛍も。この三人には、ある共通していることがあった。
「ええっ!? 月一回の店内大掃除はいつも、蛍さんとされてるんですか!?」
「はい。業者さん顔負けのレベルでキレイにしてもらえますよ」
この三人は、一般女性以上の家事能力を全員が持っている。馨に至っては料理も非常に得意なようで、専業主婦の手早さと匠の技巧、両方を有するという反則ぶりらしい。
「凄いですねー……」
家事が苦手でバイト中心という美夜は、ただきらきらした目で、三人と楽しそうに話すのだった。
「それでいて皆さん、お仕事も毎日されてるなんて……わたしなんてまだまだですね」
馨は郵便局の集配営業部にて、非常勤勤務。蛍は私設マイクロバスの専任運転手に就職。そして夜織はこの花屋と、若いわりに生活感あふれる彼らだ。
「あの二人は確かにそうですけど……僕は、兄の援助で自営業をしてるだけですから」
「でもこんなに素敵な花屋じゃないですか。本当に皆さん、ちゃんと社会人ですね!」
「…………」
……そうなのよね、と沙夜は複雑になる。
この花屋で彼らと会う時間が増えるにつれて、段々と、彼らがそんなに違和感のある存在に見えなくなってきたこと。そもそもどうして、違和感があるのかも悩む。
失くし物探しだけでなく、気付けば馨の周囲にある物がふわふわ浮かぶ異常な光景を目撃したり。
蛍がこうなると言ったことは大概当たり、養母と似た空気を感じることがあったり。
沙夜がちょうど喉が渇いた時に限って、はい、と、飲みたい物を出してくる夜織の、キレイな笑顔に空恐ろしくなったり。
そんなことが立て続けに起こるにも関わらず、沙夜は、慣れてきた自分を感じつつあった。ところが何故か、美夜が彼らの近くにいる時には、そういうことはほとんど起こらなかった。
――異常なんて……勘違いだったのかも。
やっぱり自分達は、馨や蛍、夜織も含め、本当は全員、マトモ。そう思っていたい沙夜でもあった。
しかし夜織は、そんな沙夜の思いを錯覚と断定するかのように言う。
「その辺りはあの二人も、そして沙夜さんと美夜さんも、不思議なくらい真っ当ですよ」
えっ? ぽかんと首を傾げる美夜に、夜織は何処か影のある顔つきで先を続ける。
「あの二人……自分が特別だっていうことを、全然気にしてませんからね」
「特別……?」
だから殊更、社会でも家族でも、何処に壁を作るようなこともない。儚げにも見える顔で、夜織はそう呟いていた。
「夜織さんは……違うんですか?」
隣の美夜も、不思議そうにしている。憂いげに潤む目で夜織を見る美夜に、いくらか夜織の心は和んだようだった。
「……警戒心はみんな、持っていますけどね。意識するからこそ歪む者と、意識していても普通でいられる人達は、多分異質ですよ」
その夜織の台詞は沙夜にとって。
過ぎた日を思い出させる痛い言葉だった。
――おかあさんは……普通じゃないから。
最初にそんなことを言ったのは、いったい誰だったのか。
普通じゃないから。あんなに優しいのに、周りの人から怖がられ、一人にされた。
そんな恐怖を抱いた誰か。本当はどちらが、歪んでいたというのだろう?
「……っ」
ぽき……と。手にしていた生花の茎を折ってしまい、沙夜ははっと我に返った。
「――沙夜さん? 大丈夫ですか?」
「あ――……ごめん」
花、ダメにしちゃった……と。俯く沙夜に、夜織は困ったような顔をして笑った。
「今週はここまでにしましょうか。週末は、ゆっくり休んでくださいね」
「そっか、作業は平日の夕方だけなんですね。沙夜さん、土日は休めそうですね」
良かった、と笑う美夜は、沙夜が疲れていると思ったらしい。
しかし沙夜はこの土曜には、狭間さんと携帯屋行きの予定があるのだ。
――しまったなぁ……アレ、どうしよう。
結局、上手く断る口実は見つけられていない。陽美の機嫌は日増しに悪くなっている。
段々、狭間さんがいる前でも、沙夜を罵ることが増えた状態になってきていた。
誰にも話せずに、陽美の嫌がらせに耐えてきた沙夜には、限界が近づきつつあった。
しかし沙夜には自覚はなく、ただ心身には、新生活の疲れが早くも出始めていた。
ああ、もう……と。
夜にバイトに行く美夜と別れた後、思い切り両手を広げて背伸びをした。沙夜はしっかり、夜の空気を胸深くまで送り込んだ。
「らしくないぞ、私……こんなの、むしろ、今までより幸せなくらいじゃないの」
自分に言い聞かせるように、昔のことを思い出してみた。
幼少の頃――多分幼稚園くらいの頃までは、あまり覚えていないが、可愛がってもらった気がする。我が侭も少しは言った気がする。
物心がつき、自分を面倒くさそうに迎える新しい家族の顔を見るたび、なるべく迷惑をかけてはいけない、そう思うようになっていった。
「そう言えば、何で、いつも……」
――どうして、別に望まれていないのに、沙夜は彼らに引き取られたのだろう。引き取り先の人選、基準はいったい何だったのだろう。
その答はやがて、狭間さんの正体が判るその時に訪れること。この夜から動き出す運命と共に、沙夜は全てを知ることになる。
*
5
「遅いし! 何であんたいつも、六時までに帰ってこないの!?」
帰り着くと、玄関先で陽美が怒りの形相で、まさに仁王立ちで待ち受けていた。
「……すみません」
狭間さんから直接、門限を言われたわけではない。美夜の家によってから帰ると、どうしても六時には間に合わず、あえて意識しないようにしていたところがあった。
それでも陽美が、それをルールだと言うなら、謝るしかない。沙夜にも非はあることだ。
「ちょっとこっち来なさい。今日こそ自分の立場っての、思い知らせてあげる」
強引に腕を掴まれ、居間の方へ引っ張っていかれる。
狭間さんや奥さんの寛ぎ場であるそこには、沙夜はなるべく邪魔しないようにしていた。夕方の今は奥さんは台所にいて、二日ぶりに帰った狭間さんがゆっくりTVを見ている。
「お父さん。これ、見てよ」
「陽美……どうした?」
陽美の剣幕に驚き顔の狭間さんの前、陽美は沙夜の鞄を強引に取り上げると。
「――……!」
美夜から借りたPHSを迷いなく取り出し、テーブルに叩きつけるように放り出した。
どうやら常日頃から、沙夜の持ち物検査も無断でしていたらしい。隠そうと思っていた沙夜が甘かったのだろう。
「沙夜君……これは……」
「――……」
あの……と、事情を口に出そうとしかけて、遮られた。
「盗んだに決まってるじゃないの! 沙夜にこんな物、契約できるお金なんてないし!」
「――違います!」
信じてもらえるとは思えなかったが、そんな言いがかりはさすがに、黙って受け流せない。PHSを貸してくれた美夜の、嬉しそうな顔が脳裏をよぎる。
「それは友達から借りた大事な物なんです! 黙ってたことは本当ごめんなさい、でも……!」
「何言ってんの、そんな物貸す人間なんているわけないでしょ!? どうせならもっとマシな言い訳考えなさいよ!」
PHSを取り戻そうとしたが陽美に阻まれる。動揺して声が出せずに、沙夜は硬直してしまった。
「……」
狭間さんはそんな二人を、とても硬い表情で見つめた。ゆっくり、ソファから立ち上がった。
――パシン、と。
何が起こったのか、沙夜にも陽美にも一瞬わからなかった。
強い勢いで打たれた頬を押え、茫然とする陽美の姿に、沙夜はやっと我に返った。
「狭間……さん?」
二人の前で彼は厳しい顔つきをして、陽美をまっすぐに見つめていた。
「お前がずっと、沙夜君に何をしてきたか。気付いていないと思っているのか、陽美」
「……!?」
その声は、今までの狭間さんとは一線を画す、厳しさと重さに満ちた声。父親というより、何か事情を秘める男の声だった。
「沙夜君は被害者だ――そしてお前も、私の仕事に巻き込んだ被害者だった。あくまでこれまでは」
彼は初めから、沙夜を同居させたことへの娘の反感を覚悟していた。そんな口ぶり。
「今のお前は、ただの加害者だ。そんなこともわからないのか、高校三年生にもなって」
「……何よ……何よ、偉そうに……!」
頬を押さえて歯を食い縛り、涙もなく陽美はぎっと父親を睨み上げた。
「全然帰ってこないくせに、父親面しないで! アンタなんか何がわかるっていうの――!」
沙夜の鞄を叩きつけて、居間から飛び出した陽美を、沙夜は反射的に追いかけていた。
居間には、憮然とした顔つきで立ち尽くす狭間さんと、残されたままの白いPHS。新しいメールの着信を告げて、ぶるぶる寂しげに震えていたのだった。
自分の部屋に飛び込むと、陽美はすぐに、鍵をかけてしまった。廊下側に取り残された沙夜は、一度だけダンと扉を叩いた。
「陽美さん――! ごめんなさい、私――」
何を言えばいいかはわからなかった。少なくとも、先程の父と娘の亀裂の一端は、自分にあることを謝らずにいられなかった。
「何が気に入らないか言ってください! 私、努力しますから――陽美さんに迷惑かけないように頑張りますから!」
門限を守らないとか、そんな表面的なことではないはずなのだ。沙夜がここに現れた時から、陽美はずっと沙夜を拒絶している。
「陽美さん……!」
それは決して、沙夜の非ではない。
それでも沙夜は、こんな形で誰かを傷付けるのなら、自分が頑張らなければいけない――そう思ってもう一度、ダン、と扉を叩こうとした時だった。
「うるさい……」
扉の内側から聞こえてきた声。呪うような言葉に、沙夜は必死に耳をすませて続きを待った。
「沙夜。アタシ、あんたのそういう所が嫌い」
「……え?」
「何でいっつもそんなふうに、しれっとしてられんの? ……悪いのはあんたなのに」
咄嗟に、何も言えなくなった。沙夜は白く閉ざされた、厚い扉の向こうで立ち尽くす。
目端に薄く溜められた涙と、歪んだ笑みをたたえる陽美を、まるで直接目に映したかのように全身を凍らせる。
「あんた、自分がどれだけ迷惑か――考えたことないの?」
だからそんな、平静にしてられるんでしょ、と。忌々しそうに、目障りそのものという声で、陽美はその結論を告げた。
――そうした沙夜そのものが、彼女はとにかく、不快で仕方ないのだと。
「……………」
そんな答を、はっきりと伝えられて。全く動揺しないでいられるものだろうか。
沙夜は、ふら……と、扉の反対側の廊下の壁に倒れるようにもたれかかった。
――助けて、美夜ちゃん……――さん……。
いつかと同じ、救いを求める悲鳴を胸に。
ついに受け入れられることはなかった家を、拙い足どりで飛び出していたのだった。
鞄も何も持たずに、沙夜は狭間家を飛び出していた。制服のまま、せっかく借りたPHSもなく、狭間家の居間に置いたままであることにもしばらく気付けなかった。
「……どう、しよう」
逃げるようにあの家を出て、真っ先に思い出したのは美夜のことだ。
――美夜ちゃんなら……泊めてくれるだろうけど。
しかし苦労している彼女に、これ以上負担をかけても良いものだろうか。その思いがずっと、沙夜の足を止めてしまった。
「今行っても……直美さんにも、迷惑かけるし」
美夜は多分、まだ夜のバイト中だ。沙夜を家にあげようとすれば、病身の直美に起き出してもらわなければいけない。
PHSもない以上は、先に相談することもできない。
――あんた、自分がどれだけ迷惑か……。
やっぱり、できない……そう項垂れて、美夜のことを頭から消そうとしたその時だった。
――……え?
その声は確かに、沙夜の何処か深い所へ、直接届いてきていた。
――美夜……泣いてる……?
夜のしじまも、立ち並ぶ建物も全て飛び越え、沙夜の魂へ訴えかけるかのようだった。
美夜が一人ぼっちで、肩を落としていた。暗い街の何処かで闘っている姿が、何故かありありと唐突に、沙夜の暗い視界を占拠していた。
「……」
沙夜はその光景を、全く疑うことはなかった。
「……行かなきゃ」
つい先刻まで、自分の中で吹き荒れていた嵐も、まるで忘れたのかのような強い足どり。
夜の街に向かって、一度も行ったことのない場所を正確に思い描きながら、ゆっくりと歩き出していた。
*
「えっ……沙夜、さん!?」
終電の時刻も過ぎてしまった頃だった。
ようやく想定外の時間外労働から解放され、バイト先の建物から出てきた美夜を、沙夜は建物の裏路地で待っていた。美夜が慌てて涙を拭いながら、驚きの声をあげていた。
「どうしてここが……しかも、こんな時間に!」
「――ごめん。家出してきちゃって、私」
ナハハ、と、その一言だけで沙夜の切迫状況を察したらしい美夜に、あえて沙夜は軽く言った。
「それなら、わたしの家に行って下さってたら!」
家で帰りを待っててもらえば良かった。沙夜を受け入れる選択肢を前提として、美夜はそう焦っている。沙夜は胸が痛みつつ、ううん、と小さく首を振った。
「何か、美夜ちゃんに何かがあった気がして。気がついたらここに来てたんだ」
「えっ……?」
美夜はどきっとしたように、体を硬直させた。
「こんな遅くまで仕事って、何かあったの?」
「…………」
俯いて黙り込んでしまった。かなりの間、ためらった後……美夜は、意を決したように顔を上げた。
「……一緒に帰りましょう、沙夜さん」
そうしたら話します、と。
沙夜の不自然に気丈な様子に、美夜なりに危機感を持ったのか、そう強い目で口にしていた。
「――まいったなぁ」
美夜の家に行くことへの躊躇いは、お見通しに見えた、わかった、と言うしかない沙夜なのだった。
早い話、と。美夜は淡々と、話し始めた。
「バイト……クビになっちゃいました」
「――え?」
繁華街を抜けて、歩く程に暗さの増していく夜道。二人の影が街灯に照らされて長くのびる。
「もう随分古いパソコンだったんですけど……わたしが使った直後に、動かなくなって」
美夜曰く、その店では必需品のパソコンが、美夜が使うまでは何の不調もなく動いていたのに、美夜の次に店長が使った時、全ての記録を道連れに壊れてしまったらしい。
「お客さんの情報とか、全部入ってたので……何とか今日中に復旧させろ、って言われて」
技術者は最短で明日にしか来られないらしく、責任をとって直せ、直せないならクビだ、とはっきり言われたということだった。
そして結局、今まで粘っても何ともならず、店長から追い出されたということだった。
沙夜は正直、パソコンとかそういうものは、授業でさわったことくらいしかない。なので、美夜がじわりと涙する程に、どれだけ責められたのか……それを思って顔をしかめた。
「それ、店長が壊したんじゃないの?」
「違うと思います」
あっさり断言する美夜は。何故か確信を持ってそう言っているようだった。
「だって美夜ちゃん、キカイ系強いのに?」
「……はい、苦手ではないです。だからこの時間まで、頑張りましたし」
でも。沙夜の方を見ずに、美夜は俯く。
「よくあるんです……同じようなことが」
「え?」
「わたしが使ってる時には調子がいいのに。その後に、もうどうにもならないレベルまで急に物が壊れちゃうこと……一回や二回じゃなかったんです」
だから何度も、バイトも変わってきた事実を美夜が明かす。
「それが本当、酷い時は何度でも、何処でも起こるような時があって……その度母さんは、わたしを連れて引越しを重ねてきたんです。……一番酷かったのは、わたしが部屋を出て扉を閉めた直後、家が傾いたなんてこともありました」
だからもう、人を巻き込みかねない集合住宅は借りなくなった。それで一戸建ての賃貸に入っている。
「……何、それ」
沙夜はふつふつと。自分の中を湧き上がってくる、怒りに近い感情を自覚し始めた。
「それって……本当に、美夜ちゃんが悪いの?」
「……」
ただの偶然じゃないの? 厳しい顔色で言う沙夜に、美夜はますます俯いてしまう。
「偶然でこんなこと……何回も重なりますか?」
「それはわからないけど……でも……」
沙夜はぎゅっと両手を握りしめて、俯く美夜を見ずに先を続けた。ともすれば――叱咤激励ともとれるような、突き放した声色で。
「美夜ちゃんは普通だと思う。そんな異常なことの責任……とる必要、ないのに」
その沙夜の声に、美夜は少しだけ哀しそうにする。
「…………」
沙夜さん……と。それも、沙夜の方を見ずに、小さく呟いていた。
「わたし……普通でも、そうじゃなくても。沙夜さんは、優しい素敵なヒトだと思います」
「……――?」
その言葉にどんな思いが込められていたのか。この時の沙夜にはわからなかった。
意味を尋ねる前に二人は先畑家に辿り着き、そこで容赦なく訪れていた運命の足音に、安らぎの夜の喪失を知る。
「そんな……母さん!?」
「直美さん! 大丈夫ですか!?」
家の中では、ベッドから倒れ落ちて苦しげに胸を押さえ、止まらない咳き込みを続けて血を吐いてもがく直美の姿があった。
*
黄ばんだ白い天井と、三つ穴の珍しいコンセント差し込み口。そんなものが床近くに連なる壁の前で、点滴の台や上下に動く電動ベッドの上で、ようやく直美は少し落ち着いていた。沙夜と美夜は、大きく息をついた。
「急変ですね……詳しくは明朝に、医師からお話があると思います」
珍しい金髪の、外人らしい看護師が説明する。この町に来てから直美のかかりつけである病院に、時間外だが何とか救急搬送してもらえた。
直美のたっての希望で、人工呼吸器などの使用はせず、点滴と酸素の吸入のみで様子をみることになった。その晩はそのまま個室内で、美夜と沙夜も泊っていい、ということだった。
「あの……こんな遅い時間に本当に、有難うございます」
「先週から状態は良くなかったのですから。入院時期の判断を誤ったのはこちらですよ」
「たかの」と平仮名の名札をつける看護師は、そうして苦く笑って、一礼して退出していったのだった。
沙夜はそのやりとりを眺めながら、思わずにはいられなかった。
――私がすぐ家に行ってたら……もう少し早く、直美さんが大変なことに気付けたのに……。
結局、どうすれば良かったのか。そればかりが頭をまわり、ずっと顔をしかめ続けていた。
「良かった……母さん、大分楽みたい」
美夜はそんな沙夜の心を、知ってか知らずか。
「沙夜さんが近くにいると、いつもそう……空気がキレイなのかな……」
そう、わけのわからないことを言いながら直美の手を握る美夜に、沙夜は困惑するしかない。
「沙夜さん。先に眠ってください」
「美夜こそ。今の内に寝ておかないと」
朝には先生、すぐ話しに来るんでしょ? 苛立ち混じりでそう言う沙夜に、美夜は、一瞬何故かポカンとしていた。
「……有難うございます」
沙夜とは対極の、穏やかな笑顔でそう笑う。そして遠慮なく、寝袋に入っていった。
「……」
美夜の言う通り、というわけではないのだが……直美はさっきまでの苦しみが嘘のように、穏やかな顔で眠っている。そう言えば養母も、最後まで家にいるほど症状は穏やかに済んだことを、沙夜は思い出していた。
――直美さん……すぐ横にあった家の電話すら、かけられないくらいひどかったのに……。
沙夜と美夜が駆け寄った後だ。美夜が薬と水を取りに違う部屋に行っている間、彼女はそんな体をおしてまで、ある物をベッドの下から取り出して沙夜に託していた。
――お願いです……私が死んだら……。
さすがに詳しく事情はきけなかった。美夜には隠していたらしい物を、沙夜はどのタイミングで美夜に打ち明ければいいか、直美の寝顔と美夜の寝息を横に、ううん……と悩み続けていた。
「頼りにされるって……こういうこと?」
蛍からの謎メールの意味を、今頃噛みしめていた。やっぱり普通じゃないな、あの人達、と。
ぼんやりとした頭で、沙夜は直美の横に座り、静かに様子を見続けていた。
翌朝。
美夜が医師の話を聞きに別室に行く間、沙夜は直美のそばにいるように頼まれていた。しかし清拭をするということで部屋から出され、お金は全くないものの、何となく売店の方へ来てみていた。
「美夜に何か、食べさせなきゃ……」
きょろきょろと、何故かATMを探してみる。ブレザーのポケットには、直美から預かった物がまとめてつめられている。
「――って」
「――あ?」
そんな挙動不審の沙夜を、朝も早くから、似合わぬ場所にいる黒髪の男が見咎めていた。
「何やってる、あんた」
「馨さん……どうしてここに?」
売店で何やら、朝食らしき品々を買っていた馨の姿。沙夜は心底、首を傾げたのだった。
なるほどね、と。馨は直美の病室で、先程仕入れた朝食をつまみながら言う。
「もう一人の姿をここでよく見かけたのは、このせいか」
直美が眠っているのを良いことに、軽い言い草をする。沙夜は一気に不機嫌顔になりながら、馨の眼は全然軽くないことにも気が付き、黙り込むしかなかった。
「ここ、うちのお袋も入院してるんだよ」
「えっ……そうなの?」
「本当に、勝手な奴でさ。父なし子でおれを生んでおいて、おれが高校の頃に男とどっか行きやがった。それが病気となるやいなや、もう一度会いたい、許してくれとかいって、帰ってきやがるんだから」
「…………」
突然そんな、ヘビーな過去を話されても……。唖然とする沙夜に、馨がふっと振り返る。
「夜織の言う通りだな。あんたには何でか、いらないことまで話したくなるみたいだ」
そう穏やかに笑い、沙夜の肩をぽんぽん、と優しく叩いていた。
「今日はおれも一日病院にいる。何かあれば呼べよ」
そう言って、自分の母の病室番号と、メールアドレスをその場でメモに書いて沙夜に手渡した。面食らった沙夜がお礼を言う余裕もない内に、病室から出て行ったのだった。
「……って……」
それ、どういう意味。沙夜はまた懊悩する。
「呼んでいいって……何で?」
ただ単に、顔見知りに過ぎない自分達だ。どういう流れでこうなったのだろう。
――そりゃ、二人だけだと、心細いけど……。
それでも美夜は、医者の話は一人で聞ける、と気丈に言って出た。沙夜にも短い間だが、仮眠をとれる時間まできちんと配分してくれていた。
「何か……みんな、しっかりしてるなぁ」
純粋に沙夜は、それで感心してしまう。そう思うと、陽美一人に拒絶された程度で、家を飛び出す程に動揺した自分が情けなく思えた。
自分と彼らで、いったい何が違うのか……今の沙夜には何がベストなことなのだろうか。
やっと少し調子が戻って、沙夜がベッドの横に戻って座ろうとした――その時だった。
―― … … … ! !
「――え――?」
美夜……? と。
昨日の夜と同じことが起きた。突然頭に響いてきた、今度は泣き声ではない、美夜の叫び声。
直美の容態に関する医師からの話が終わり、色々な動揺を一人で堪えるべく、美夜は病院の中庭で呼吸を整えようとしていた。
「何――……誰……!?」
突然、人影の少ない朝の中庭に、暗い色の背広を着た数人の男達が現れていた。
彼らは美夜を強引に取り押さえると、すぐ近くに停めてあった白いバンに連れ込み、そのまま病院を出て何処かへ消えてしまった。
「えっ……うそ……!?」
その、あまりに唐突で、わけのわからない異常な光景。沙夜はとにかく急いで部屋を出て、行ったことのない中庭へ全速力で駆け込んでいった。
「合ってる――景色は同じ、合ってる……!」
頭にずっと響き続けていた美夜の声は、いつしかプツン、と途絶えてしまった。
――少なくとも、絶対……美夜、今、この病院の何処にもいない……!
怖い程に、確信があった。沙夜は急いで中庭から出て、白いバンが去っていった方へ駆け出そうとして――
「沙夜さん!? 何してんだ!?」
「うわっ、危ない!」
ききーっと。信号も考えずに道路を渡ろうとした沙夜に、慌ててブレーキをかけた車から、見知った二人が降りてきた時には。
……運命って本当にあるのかな、と。沙夜は、思わずにはいられなかった。
「蛍さん、夜織さん……!」
沙夜の尋常でない様子に、うんうん、と蛍が沙夜の両肩を掴んで落ち着かせるように頷く。
「美夜が攫われた……! たった今、何処か連れていかれちゃった――!」
「――ぁんだってぇ!?」
沙夜以上に、一気に驚愕の顔色となった蛍と、
「美夜さんが――攫われた?」
無表情のまま、時間が止まったように顔色を硬めた夜織。沙夜はただ、助けて、とだけ、無我夢中で二人にしがみついていた。
*
6
とにかく、落ち着いて話を聞かせてほしい。
馨に会うため病院まで来たらしい蛍と夜織が、沙夜を連れて直美の病室まで来た。その場で馨にも電話を始めた。
「馨兄の方は相部屋だからな。こっちの方がゆっくり相談できるだろ」
冷静な顔で言う蛍に、沙夜は混乱した心のまま頷く。病人がいる所にすみません、と頭を下げる夜織に、ぶるぶると首を横に振った。
「――うん。馨兄、すぐ来るって」
そう言うと蛍は、どいてどいてー、と、何故か扉の前の空間を広くあけるように促した。
「って……――えええっっっ!?」
次の瞬間、沙夜は本気で、我が目を疑っていた。
扉が突然、不自然にぐにゃりと歪んだ――沙夜にはそう見えた。
「何があった!?」
一瞬の錯覚の後に、何故かその場所には馨が立っていた。
「今、沙夜さんの意識をそのまま伝えます」
何の断りもなく、座り込む沙夜の額に夜織が右手を当てた。もう片方の手は馨の額に当てて、突然現れた馨はなるほど、とすぐに頷いていた。
目前で展開されるあまりの事に、最早動揺など通り越して、逆に頭が冷えた沙夜は呟くしかなかった。
「アナタ達……超能力、者?」
それもおそらく、いわゆる空間跳躍や読心能力。前にみた馨のあの能力は、美夜が言っていた通り透視ではないだろうか。
漫画や小説はあまり読んでいない沙夜だが、そうした超常現象については色々知っていた。養母がいったい、どういった人間だと思えばいいのか、知りたいと思った時があったからだ。
「何だ、今頃納得したか――悪いが、そうだよ」
「無理もないですよ。一応これでも、普段はずっと力を抑えてますからね、僕達」
しれっとそんなことを言う、馨や夜織と、
「いいなー、馨兄と夜織はそんな制御できて。おれなんて視えたら視えっ放し、視えない時はとことん視えないしさー」
直美の意識がないのを幸いとばかり、蛍までそんなふうに、彼らと同調するのだった。
しかし今は。彼らは異常な者であると――そんなわかりきっていたことに、驚く場合ではない。沙夜は不甲斐ない自分に喝を入れる。
「じゃあ、アナタ達ならわかる? どうして美夜が――」
攫われるような目に合うのか、と。自分は普通ではない、と語った美夜を思い出しながら、そう口に出しかけた沙夜だったが。
――それは、と。思わぬ言葉が後に続いていた。
「美夜は、ずっと監視されていました――あの子の父親に」
沙夜と、そして場にいた三人の普通でない彼らは、揃って驚いて振り返った。
酸素のマスクを外し、電動ベッドをリモコンで起こした直美が、毅然と表情を固めていた。
沙夜は、驚きと心配の両方で焦って縋りつく。
「直美さん――大丈夫なんですか!?」
ベッドに駆け寄って直美の横に両膝をつく。そんな沙夜に、長い髪を肩の上で束ねながら、直美は優しそうに微笑む。そっと沙夜の頭に、まるで撫でるような形で手を置いていた。
「……貴女は、事情を知っているようですね」
すっと、表情が硬いままの夜織が、冷淡にも見える目で直美を見る。直美はその目の理由を知ってか、困ったように笑う。
「驚きました。美夜にいつの間に、こんなに沢山、お友達ができてたなんて」
広くはない個室を占める、初対面の相手を直美は見回す。
何故かにかっと笑う蛍や、無愛想な馨など、ともすれば悪いお友達とも見えそうな面々だが、有難う、と青白い顔で笑っていた。
そして改めて、沙夜の方を真剣な顔で見る。
「沙夜さん。昨日お願いしたこと……引き受けていただけますか?」
「えっ……」
「私に何かあった時は、美夜を連れていってほしい――……あの子を守ってほしい、と」
昨晩のあの時。そう言って直美は沙夜に、美夜名義で貯めていたという預金通帳と印鑑、そしてキャッシュカードを託していた。
「受けていただけるなら、全て、お話しします……あなた達について、私が知る現実を」
「私達の……現実……?」
直美の声は、力は失われていないものの、小さく細い。三人の青年達は静かに見守り、沙夜と直美の邪魔をしないようにしている。
沙夜さん、と。まっすぐに沙夜の目を、差し迫った顔色で直美は改めて見る。
「そんなの、引き受ける気がなければ、私はここにいません」
沙夜ははっきりと、強い気持ちでそう答えた。
安心したように頷いた直美は、まるで美夜を見る時のような優しい目で、沙夜の頭をもう一度撫でて柔らかく笑った。
「やっぱり……運命というものは、確かにあるのでしょうね」
そして。続く一言で、直美は驚くべき真実を告げる。
「沙夜さん。あなたと美夜は、全く同じ血を分けた、実の双子なんです」
「……え……――?」
沙夜は初め、何を言われたかがさっぱりわからなかった。頭を真っ白にして直美を見返していた。
後ろで見守る三人の青年は、やっと納得がいった、というように、互いに顔を見合わせ頷き合っていたのだった。
事の始まりは、彼女達が生まれた時のこと。
先畑直美の実の妹、藤桜由穂が「異常な」双子の娘を授かった時から起きたこと、と、直美は静かに話し始めた。
「由穂は、笑い者になることが常の、超常現象の研究家でした。同じく超常現象研究家である基囲学と結婚し、結婚後も研究を続けました。そして、よりによってそんな彼女の下に、生まれた直後から超常現象を起こし、特殊な脳波を持つ子供達が生まれてきたんです」
夫である学は狂喜した。由穂も研究者としてのそれまでの不遇から、内なる悪魔の囁き――自らの好奇心に負けてしまった。
「沙夜さん一人では、特に何も起こらなかった。けれど美夜はそこにいるだけで、周囲の古い機器が壊れるか、購入時のような好調さに戻る。そして二人が揃った時には、同じ場所にいる者全て、若返ったように調子が良くなりました」
だから自分も、こうして話せている。沙夜を見て直美は儚げに笑った。
「美夜は特に、研究用の機器にも影響を与えてしまうので、問題視されていたようです。そして由穂と基囲は、美夜を研究するため、眠らせ続けることを決意しました」
沙夜の近くにいると、美夜の謎の能力は強まったという。しかし沙夜から遠く引き離し、成長も止まるような低体温を維持すれば、影響が弱まることを彼らは見つけたというのだ。
「そして二年――……二人は、美夜の研究を続けました。けれど――」
そこまで話して直美は初めて、沙夜のことを、とても痛ましい目で申し訳なさげに見つめた。
「その間、沙夜さんのことは由穂が育てました。何か超常現象が起こらないか、観察するはずだった由穂は……」
その逆に、と。実の妹の過ちを嘆くように、直美は両手を握りしめていた。
「沙夜さんを育てる内に、由穂は後悔し始めたのです。大切な娘を、研究材料としてしまったことを」
「……――」
「あの子がずっと誤魔化していた、人として――母親としての良心の呵責。二年の時間が流れる内に、それはついに限界を超えたんです」
そうして藤桜由穂は、学に黙って、沙夜を信頼できる後見人に託した。
美夜の低体温状態も内密に解除して、母子でまんまと研究所から逃げおおせることになった。
「私に全ての事情を話し、由穂は美夜を私に託しました。基囲と話をつけるために、研究所に戻って――彼に、殺されたのです」
まるで、映画か何かみたい。沙夜は直美の声を、半分夢のような気分できいていた。
同時に、胸の底からつき上がるような、痛みとも知れない耐え難い熱があった。
――沙夜、と。
自分と同じ亜麻色の髪と、灰色の目をした女性が自分を呼んでいる声。
どうしてなのだろう。唐突に、記憶の底からそれを手繰り上げていた。
幻想を振り切るように、沙夜は残酷な現実の黄ばんだ白い部屋に戻る。
「直美さん……それじゃ、あなたは……」
「ええ。私は美夜の本当の母親ではなく、美夜と沙夜さん、二人の伯母です」
ああ、と。沙夜はどれだけ、血の繋がった人に会いたいと思ったかしれない。
それなのに、実際そうした状況になった今は、どうしても現実感が持てなかった。
多分その原因である、非日常過ぎる様々な出来事、異常な青年達の存在。そして――
「父は――母を、殺したんですか」
「ええ。研究組織の力を借りて、秘密裏に。そして、私と美夜を監視し続けていました」
もう、真剣に受け止めれば壊れてしまいそうな現実。馨達がいて良かった、と思ってしまった。
ここに誰もいなければ、あまりの動揺で直美を責めてしまったかもしれない。今は意地でも、これ以上動じない、そんな意地でこの場に立っている気分だった。
結局、美夜は直美がずっと庇い続けた。沙夜の方は、託された後見人が行方を晦まし、学の魔の手から守ってくれたという。
「基囲が再び美夜を低温状態にしなかったのは、解凍された美夜は、力を失っていたからです。彼はずっと、美夜がまた超常現象を起こすことを、待ち続けていました」
だから直美は、美夜に少しでもその兆しがある度に、引越しを重ねていたらしい。
「土地を変えると、何故か美夜の不安定さはいつも治まりました。けれどどの場所でも、その土地に慣れた頃に、また同じようなことが起き始めてしまう」
それでも今回は、早過ぎた美夜の力の兆し。それは多分、沙夜と再会した影響だ、と、直美は目を伏せて口にしていた。
「基囲もそれに気が付いたのでしょう。だからこうして、美夜を回収しにかかった」
それもおそらくは、直美が限界にきたタイミングを見計らって。
「じゃあ父は……私がこの町に来て、美夜と出会ったことを、知ってるってことですか?」
それでも沙夜は、父の興味を惹かなかったということだろうか。今まで存在すらも知らされたことがなかった。
「そうでしょうね。あなたが無事だったのは、本当に幸いでした」
「…………」
黙り込んだ沙夜に呼応するかのように、直美が突然咳き込んだ。苦しげに顔を歪めて、再び酸素マスクを口元に当てた。
「私があなたに今お話しすべきことは……もうこれくらいです」
沙夜の後ろで、黙って話を聞いていた彼らは、それぞれの表情で直美を見つめた。
美夜が何処に連れていかれたのか、研究所の所在まではわからない、と。項垂れる直美に、沙夜は決意を込めた目で、顔を上げた。
*
「おれ達側の発端はさ。久々に、おれが予知夢を見たことだったんだ」
ガタガタガタ、と。舗装なき林道を走らされる、コンパクトカーの悲鳴をものともせずに蛍が笑う。
沙夜と馨、夜織を車に乗せて、出会い初日の真相を語り始めた。
「予知夢……?」
助手席の沙夜は、焦る目を少しだけ丸くしながら、運転席の方を見る。
「夜織の花屋に、光り輝く女の子達が、迷い込んでくる夢。珍しく日時も覚えてる程、はっきりした夢で……勝手なイメージで言えば、ゲームとかの精霊みたく光でできたような、本当きゃわいい子達と出会いがあるってさ。そんな夢を見たんだよなー」
こんな状況でも軽口を叩く彼だが、目は全く笑っていない。真剣な顔でハンドルを握る。
隣の市との境になる山林を、近道と称して脇道に逸れた。信号がないのを良いことに飛ばす蛍の運転テクニックは、バスの運転手を志すくらいなので、相当自信があるのだろう。
「本当にこの道で合ってるのか、蛍」
「えー、だってこの方角なんだろ、沙夜さん?」
「……」
こくり、と、沙夜は力強く頷く。
――私……美夜のいる所なら、多分わかる。
今まで誰にも言わなかった、自分のその「異常」。
美夜を助け出すことに協力してくれるという彼らに、沙夜は迷わず口にしていた。
――警察への連絡は、おそらく無駄でしょう。
――身代金とか、要求があればまだしも……もうあちらは、目的は果たしてるからな。
彼らは全員、口を揃えてそんな風に言った。
美夜を誘拐した者の目的が、彼女の異常な力であると言うなら。攫われた証拠もなく、そんなことを通報したところで、警察は本気で動いてはくれない。それは沙夜にも一応わかった。
――邪魔が入らない方が、俺達も動きやすい。能力者を甘く見たこと、後悔させてやるよ。
そう言って馨は、手も触れずにぐにゃりと、鉄製のパイプ椅子を有り得ない形に畳んでしてしまった。
しかもその後、そのパイプ椅子だった物を受け取った夜織が、軽くそれを解いてしまった。
沙夜はもう、驚くことすらなかった。
――……何で?
ただそれだけを、何とか尋ねたのだった。
――馨兄と夜織は、能力の制御だけじゃなくて、身体の強度までいじっちまえるんだよ。
蛍曰く、夜織はリミッターを外す程度だが、馨に至ってはまるで獣の如く変われるらしい。だから空間跳躍なんて荒業に耐えられるとのことだった。
――そうじゃなくて、と。沙夜は改めて、彼らをまっすぐに見て尋ねる。
――聞きたいのは……何で、助けてくれるの?
今ここに、当たり前のように共にいてくれる彼ら。それだけは尋かずにいられなかった。
そりゃー……と。沙夜がそれを尋ねることを不思議がるように、彼らは顔を見合わせる。
――他人事じゃないですしね、僕達にとって。
夜織はちらりと直美を見て、硬い顔で言う。
――だって、沙夜さん、もうダチじゃん?
――大体、助けて、と言ったのはあんただろう。
ふう、と呆れるように言う馨。沙夜はまた少しだけ、カチンときていた。
――だって、殺されるかもしれないことなのに。
自分の実の父が、実の母に手をかけた。残酷な事実を噛みしめながら、睨むように彼らを見ていた。
……そんな空気を、あっさり覆す天性の小悪魔が、後部座席で隣に乗る相手を今もからかっている。
――まあ気にするな。夜織なんて完全、惚れた女のための私利私欲だからな。
――って、馨さんっっ!!!
ずっと冷たい目だった夜織に、突然人間味が戻った。
唖然、とする沙夜に、バツが悪そうに言っていた。
――美夜さんが大切なのは、沙夜さんだけではないのは、本当です。
気まずそうに視線を逸らしながらも。夜織ははっきり、強い口調で言い切っていた。
話を続ける運転席の蛍に、沙夜は意識を戻して話を聴いた。
「とりあえずそれでおれ達、光る女の子っていったい何者だって、大分ドキドキしながらあの日を待ってたんだけどさ」
そして出会ってみれば、何のことはない。少女達からは確かに、能力のある者に特有の強い気配が漂ってくるのに、全身の雰囲気は普通過ぎた。しかも二人は他人らしいのに、受ける印象が似通っていて、青年達は戸惑ったということだった。
「しばらく近くで眺めてれば、何の能力者かわかるかなー、と思ってたけど」
「今でも結局、正直よくわからないな」
双子というのは納得だがな、と馨が口を挟む。神妙な顔で運転しながら、蛍も頷く。
「馨兄の眼でもわからないなんて、よっぽどだな、うん」
馨には空間の跳躍や、パイプ椅子を歪めたような念動能力だけでなく、相手の本質まで時に視通す能力がある。そんな彼らの力の説明を道々受けていたら、やがて沙夜の言った通り、一見はただのログコテージに見える森の中の一軒家が、林道の先へと見えてきていた。
「……」
ついに本気で、こんな所に来てしまった。
沙夜の顔色はずっと厳しい。それは後部座席の夜織も同じだった。
夜織はずっと、緊迫したというより、ただ冷たい色の目をして窓の外を眺めていた。そんな彼が気になるのか、馨にからかわれていた時を除いて。
「美夜……絶対に、助け出すから」
沙夜はそう、覚悟を決めるためにも、同じ言葉を繰り返し呟いていた。
「……ねぇ、夜織さん」
「――?」
少し遠い所に車を停めて、木々の陰に隠れてログコテージに近付く。
沙夜はふと、目の前をずっと先導していた夜織の背中に、他愛ないことをつい尋ねていた。
「美夜の何処が好き?」
ブフっ! と。気配を潜めつつの行動なのに、思わず吹き出しかけた夜織が、一応マジメにきいている沙夜に困ったように振り返った。
「……今、するような話でしょうかねぇ」
しかし沙夜がそれを考えていること自体は、読心で伝わっていたのだろう。そのキッカケを話し始めてくれた――彼なりの、あるがままに。
「美夜さんは……久しぶりに、心を読んだ人だったんです」
「――え?」
「僕は普段、この力は意識して封印してます。そうでなければ始終周囲で、誰かの声が常に響いて――気が狂ってしまうような状態なので」
沙夜は黙る。笑ってくれているのに、目は冷たいままの夜織に改めて眉をひそめる。
「封印と言っても、完全なのは無理で、相手の望む物を感じ取る程度はできます。でも、声の方は二度と、聞こうとは思わなかった」
本当は、誰かが望む物を感じてしまうことすら苦痛。そう示すように彼は目を伏せる。
「けれど美夜さんからは、声が聞こえて……それも、全然、気持ち悪い声ではなくって」
それは今まで、人の醜い本性ばかりを覗いてきた彼にとって、信じ難い奇跡だったという。
最後の部分だけは、少しだけ幸せそうに、優しく夜織は微笑んでいた。
「でも。沙夜さんにバイトをお願いしたのは、美夜さんに会うためじゃないですよ」
「……」
そんなどうでもいいことまでわざわざ言うのは、やはり今、彼は沙夜の心を感じ取っている。沙夜が彼ら三人のことを――正直怖くもあるが、人生で初めて、信頼できる友人と感じているのを。
「――お喋りはここまでだ」
一番先頭を行っていた馨から、作戦開始の号令が告げられる。
「俺は後で、内部の様子を視てから跳ぶ。沙夜を頼むぞ――夜織」
え。唐突な呼び捨てに沙夜が驚く暇もない。
「一度も行ったことのない場所に跳ぶのは、危険ですよ、馨さん」
「だからじっくり、透視して行く。心配するな、似たようなことは、何回かやってる」
そうして馨を一人、林の中に残して、沙夜は夜織と正面玄関の前に出ることになっていた。
沙夜と夜織は、今まで隠れていた木陰から堂々と出て行った。程無くして、拳銃まで持っている暗い色の背広の男達に囲まれていたのだった。
*
7
父とは直接、話をつける。
そう口にして一歩もひかなかった沙夜に、彼らはその勇気に半ば呆れていた。
――むしろその方が、確実かもな。
馨がそう言い、その後すぐさま、この算段は練られていた。沙夜を囮とする美夜救出作戦を。
父と対峙する沙夜のお供には夜織。内部の様子を窺って、警備装置や銃火器をこっそり念動で無効化した後、潜入するのが馨。
「だからってよー……おれはこんな所で、一人待機だなんてさー……」
ブツクサブツブツ、と車の番人を命じられた蛍が、林の中で一人でふてくされる。
「そりゃーうちの親父の愛車だし? 俺が一番弱いわけだし。仕方ないんだけどさー」
沙夜さんについて行きたかったよー……と。
恨めしそうに、沙夜とメールをする携帯を見つめていた時のことだった。
「って……おおおお!?」
ぴるるる~、と、沙夜のメールを告げる着信音。
今の彼女に、メールをする余裕があるわけもなく、一人で驚きのけぞった蛍は――
その新たな力となる存在の到来を、運命の糸を手繰り寄せるように鷲掴みにする。
一見、一つの豪華な別荘にも見える程に広く大きく作られたログコテージ。それ以外に変哲はない研究所の、土台よりも更に下の方で。
木製コテージの地下に、そんな空間が広がるとは信じ難い場所。いかにも化学研究所といった雰囲気で、高校の実験室に近い空気を持つ工房がそこにあった。沙夜と夜織は、いくつもの拳銃を向けられながらも、コテージの主との対面を果たしたのだった。
「何だね――何でわざわざ、こんな所にまで来たのかね、君達は」
大きな白い机を前に、何故か椅子には座らずに、携帯に似た物をいじりながら立っている男性。
科学者らしく、色褪せた白衣を纏い、厚い眼鏡をかける若白髪のその男。ただただ不可解そうに、アポイントメントなき訪問者達を一瞥する。
「まさかこのような僻地を見つけられるとは、それに関しては、検討すべき価値があるがね。やはり大したものだね、双子というのは」
「――あなたが」
厳しく目を細める沙夜を、見ようともしない。基囲学――藤桜由穂と結婚後も、研究所では夫婦別姓でいた彼は、手前の机に目を落としていた。
「そうだよ、生物学上は君と美夜の父親だ。最もそんな事実には、一円の価値もないがね」
一応夜織のことは、美夜の彼氏だとして、同伴の理由は作っておいた。しかし部外者への不審感や興味そのものが、学にはないようだった。
――この人……何か全然、私達とは違う人だ。
沙夜はもう既に、この目の前にいる男と、まともな会話はできないことを感じていた。
「美夜は何処――お父さん」
それでも父、と口にするのは、彼女の覚悟だ。
自分は殺人者の娘であり、その現実からは、この先決して逃げられない、と。
「やっと連れ戻したのに、教えると思うかね」
ほとんど初対面の娘に、父と呼ばれることに、彼は違和感すらも持てていない。
「……どうして……お母さんを、殺したの」
沙夜の内面がそこで、どれだけ煮えくりかえっていても。呪うような心でそれを口にしていると、考えることもできないようだった。
隣の夜織はそれをまともに感じているのか、ずっと俯いたまま動かず声一つ上げない。
「君のその疑問こそ、不可解だね。どうして私が、あの裏切り者を生かさなければいけないのだ」
そこで初めて、彼は少しは人間らしい怒りの感情を見せる。
「あれからどれだけ私が苦労したか、君らにわかることはあるまい。力を失っていた美夜に研究予算は打ち切られ、辛うじてこの僻地に私財を投じて全ての設備は移したものの、再び予算を取りたいなら異常能力の確証をよこせなどと、愚かな無学者共に頭を下げ続けた」
だから美夜のことも、組織の力を使って連れてくることは、簡単にはできなかった。この十四年の見せかけの平穏の種明かしをする。
「十四年だよ。十年以上だよ、君。そんなにも長い私の年月が、無駄に費やされてしまった。君も私の時間をこれ以上無駄遣いさせるなら、あの裏切り者と同じ末路を辿るべきだね」
そうして、チャキ……と。警備員達だけでなく、学自ら銃を取り出し、沙夜の方へ向けた。
「……」
沙夜はその状況に、何の感情も持つことはなかった。
「私のことは……美夜と違って、必要ないの?」
あくまでただ、確認のために。
気付いてしまった自らの間違いを知るため、その荒涼とした問いを最後に投げかけた。
「いや、君は役に立ってくれた。君のお蔭で、美夜はまた力を取り戻したのだから」
学はにこり、と、子供のような顔で笑った。
「実に平凡で、君自体には、価値など全くないがね」
だから別に、いらないけどね――
その彼の純粋な笑顔と本心に。沙夜は静かに、幼き日の過ちを受け入れていた。
どうして自分が、親から捨てられたのか。
――それって私の責任じゃないわけだし。
考える必要は無い。その答はとっくに掴んでいたのに。
それでも、考えずにはいられなかった。
――私が悪い子だから……捨てられたの?
何か異常なところがあったから。だから捨てられた。そうだったらどうしよう、と、沙夜は誰かの孤独を見つめる度に怯えた。
普通とは少し違ったが故に、愛し合ったはずの夫からも拒絶された、養母のように。
養父は別に、これといって変な人ではなかった。周囲の人から信頼されて愛されていた。
だから悪いのは、異常者の方。自分にはそんな真実が存在しないように――きっと誰かに、愛してもらえるように。
異常を拒否しろ、と。沙夜は自身に呪いをかけた。
――普通じゃなかったら……捨てられたのは、私が悪かったってことになっちゃう。
だから精一杯、真っ当に生きなければ。自分は何も異常でないと、証明できなくなる、と。
不治の病に犯され、差し迫った命の期限を知った養母は、夫に懇願していた。自分が死ぬまでという条件で、やっと一番の望み――たった一人、子供を養子という形で辛うじて手に入れていた。
そこまでの状態にならなければ、彼女には願いを叶えてもらえる権利はなかったのだ。
「……バカみたい……」
世界のそうした、理不尽の数々。幼い沙夜がどうして、わかることができただろうか。
「異常じゃないから、普通だから……だから捨てられたなんて、アリ……?」
――こんな奴のいる所でだけは、泣くもんか。
沙夜はその自分への強い怒りだけで、何とか崩れ落ちそうになる体を必死に支えた。
結局は。誰かに愛してもらえたり、逆に受け入れてもらえないことに、明快な理由はない。それは多分、巡り合いという時の運が大きい。
――自分がどれだけ迷惑か、考えたことないの?
その真実こそ、沙夜はずっと怯えていたのだ。だから胸を張れるように、真っ当に生きる、と。強くなるための答を、ちゃんと掴んだのに。
――でも。それで大切な所、間違えちゃった。
異常だから、と養母の愛を受け入れなかった、自分は何て、バカだったのだろうか。
――本当は……大好き、だったのに……。
もう謝ることすらできない、青い目の誰か。
それでも……。
「――それはきっと。その人はわかってます」
ずっと無言で、沙夜の斜め後ろに立っていた夜織が、背後から沙夜の肩にそっと手をかけた。
沙夜が自らその心を思い出すように。ほんの僅かだけ、背中を押したのだった。
――さや、と。
自分と同じ亜麻色の髪と、灰青の目をした女性達が自分の名を呼んでいるその声。
――おかあさんは……おかあさんにそっくり。
全然国籍も人種も違う、二人の女性。
しかし二人はよく似た髪の色で、目の色も二人共薄い方で……そして何より、沙夜を我が子のように愛してくれたこと。
そうね、似ているわ、と――養母は沙夜に、嬉しそうに笑っていたことを思い出した。
――だって、私もその人も、サヤのことが大好き。
そう言って自分を抱きしめる彼女。けれど、沙夜は、腕の中で震えていた。
――でも……どっちも、いなくなるんでしょ?
幼い沙夜は悲痛を浮かべる。
沙夜、許して、と……ただひたすら泣きながら自分を抱き締め、いなくなってしまった灰色の目の人。
どうしてこのタイミングで、思い出しても痛いだけの心を自覚したのか。
人の心を覗いたことを、悪びれもせずに隣の彼は言う。
「沙夜さんがその人に、心を開けなかったのは――その人とは、長くはいられないからですよ」
沙夜は、ある一つの予言。
歎きのようなあの言葉を思い出していた。
――サヤ。貴女は、最初に愛した人とは生きることができない。
人が最初に愛するはずの人。それはきっと、どんな人でも、たった一人ではないのか。
――貴女はその人と、出会うことすらできない。
もう、この世界にいないその母には、愛してもらうことができない。どれだけ望んでも出会いはできない。
「……そう、よね」
たとえほとんど、その記憶が残っていなくても。
「お母さんを殺したお父さん……私は絶対に、あなたを許さない」
目の前の人間が肉親であっても、そんなことは、根無し草として生きる沙夜には関係ない。
そう。根無し草というのは、それでも強く生きてきた沙夜には、最大の褒め言葉なのだ。
「美夜は私が連れて帰る。あなたの好きにはさせない」
沙夜は顔をあげて、鋭く強い眼光で学を直視する。
その答を待っていたというように、夜織も大きく頷いて、次の瞬間――
何故か。沙夜と夜織を囲んでいた警備員の男達の銃口は、全て学に向けられていた。
「うむ……?」
学は不可解そうに、その異常な光景を見つめる。
「もう誰も、貴男を貴男とは思っていません」
銃火器は全て馨が無効化している。学がそんな作戦を知るわけもないので、それは脅迫材料として十分なはずだ。
最早、洗脳の域にすら達する伝心能力――相手に触れなければ複雑なことはできないが、学の方こそ侵入者である、と警備員の認識をすり替えるくらい、夜織には簡単だという。読心能力だけでなく、馨に沙夜の思念を伝えもできたのだから。
「よくやったぜ。沙夜、夜織」
場に突然馨が現れ、この作戦で囮となる沙夜、実際に能力を使う夜織を労う。
警備員達を逆にこちらの手駒として、学を脅迫して美夜を解放させる。彼ら全員の脳に夜織が介入する時間は沙夜が稼ぐ。
しかし、何か不測の事態があった時は馨が助ける――その約束だったので、馨が来たということはその何かがあったはずだ、と、沙夜が表情を強張らせた時だった。
「そうかね。君達も能力者だったとは――」
学のその声は、逆に歓喜に染まっていた。
「それは何と――」
何と嬉しく、都合の良い偶然なのだろう、と。
そう呟き、ずっと持っていた携帯のような機械のスイッチを、馨の出現に沙夜達が気をとられた隙にONとしていた。
場に跳び込んできた馨は、学の前にあった白い机をきつい目で睨んだ。
「美夜はここだ」
馨の怒りに、夜織もわかっている、というように頷く。
「復温してもらわなければ、連れ出せませんね」
ビリっと、机を覆っていた白い粘着シートを力任せに引き千切ると、そこには無残な姿があった。
「うそ……美夜……!?」
机のような形で、天板だけはガラス張りの箱があった。その中に、屈葬されたような形で横向きに体を丸め、青褪めた姿で横たわる美夜が入っていた。
「不細工だとは思ったんだが……早速ここの機器に影響が出始めたから、急いで昔の形に戻したんだよ」
だから着のままなんだ、と、それだけ残念がるように、制服のまま低温状態にされた少女を見る。
沙夜は背筋が凍ったように、顔色を青ざめさせていた。
「――」
馨も夜織も、あまりに怒りが溢れ過ぎた眼光で学を睨んだ――その次の瞬間だった。
「……!!?」
ごぼっと。突然夜織が胸元を掴んだ直後に、大量の赤い物を口から吹き出し、胸と口を押さえながら膝をついていた。
「夜織さん!?」
「夜織――!?」
沙夜と馨が駆け寄った先では、呼吸もろくにできない程に夜織が喉に血を絡ませている。
「――何だって!?」
馨の手を必死で掴み、その最後の意思だけは必死の形相で伝える。
「!!!」
更に大量の血――心臓から吹き出したとまで思いそうな程、多くの血を吐き出していく。
そして力なく倒れ込み、夜織は意識を失っていた。
「能力を――使うな、だと!!?」
「夜織さん……! どうして……!」
馨のように、夜織から事情を伝えられていない沙夜は、わけがわからず必死に夜織を助け起こした。どんどん顔から血の気がひき、様々な所で同じように出血が起きていることを否応なく悟る。
くくくくく、と、その様子を見て学は自らの研究の成果をはっきり実感する。
「伊達に私も、能力者の研究を続けていないよ」
馨は沙夜と夜織の前に立ち、学から庇うよう対峙した。夜織が意識を失ったせいだろう、警備員達が我に返って慌て出し、再び銃口が彼らに向けられていた。
圧倒的優位に戻った学は、一研究者として楽しげに語り始める。
「うちの娘もそうだが、能力者が力を使う時、ある特有の脳波が高確率で認められる。私はずっとそれを研究し、外部から意図的に、脳波を増幅できる装置を開発したんだよ」
その意味は、君達ならわかるだろう、と言う。
沙夜は全くわけがわからないが……馨はぎりっと歯を食い縛って、血が滲む程に両手を握り締めていた。
「君達能力者は、必ず何処か、心身に負担をかけて能力を使っている」
「……」
「程ほどの力なら、逆に一時的な身体強化が可能な者も多い。しかしこの装置は、君達の脳波と共振を起こし、それにより君達の力は制御不能の暴徒と化す」
「てめえ……」
それでも、と学は、歪んだ微笑みと共に夜織を見ていた。
「ここまでの状態になるとは、私も想定していなかったよ。どうやら彼は余程、強い能力の持ち主だったようだ」
「そ……んな……」
夜織でその状態なら、念動など更に物理的に作用する能力者の馨は、能力を使えばどんな暴風が体内を吹き荒れるのか。
沙夜は知らず、すっと馨のジャケットを、彼の行動を遮るように掴んでいた。
「…………」
馨はその沙夜の手の感触から、心なんて読めずとも、彼女が何を恐怖したかをわかったようだった。
沙夜はとにかく、前に出ていた。
「やめてお父さん、みんなを傷つけないで! いらないのは私だけで十分でしょう!」
その破綻した叫びが、馨にとって逆効果なこと。それにはついぞ、気が付く余裕がなかった。
自分の前に飛び出した沙夜の肩に、そっと後ろから馨が手を置いていた。
「無駄だ。どうせアイツは、もうおれ達に一目惚れしちまってる」
「馨さん……!」
振り返る沙夜に、何故か馨は穏やかに笑う。
「そうだね。平凡な娘はともかく、君達には充分研究価値がある。美夜と同様、保存処置を施せば、しばらくは相当楽しめそうだね」
だから彼らは大丈夫だよ、と。
「今すぐ死ぬのは君だけだ、沙夜。安心してあの裏切り者の所に行くといい――」
そしてカチリ、と。沙夜に向けた自らの銃の引き金を、学が躊躇いなくひいた時だった。
「何だ――不発か?」
その隙に馨は、沙夜を突然強引に抱き寄せていた。
「あんただけでも逃げろ」
驚いて声も出ない沙夜に、それだけを囁く。
「力を増幅してくれると言ったな――」
それなら、と彼は、不敵に微笑む。
「派手に、やらせてもらうぜ」
次の瞬間。
ゴゴゴゴと唐突な地鳴りが、激しい音量で響いていた。地下の狭い空間を耳を壊しそうな重低音が埋め尽くし、直後から地下空間を激し過ぎる振動が襲った。
その有り得ない事態に、そこにいた誰もが、床に這いつくばった。ひたすら必死に、天井や壁など、あちこちから崩れくる瓦礫から頭を庇う。
「――って、何だぁぁぁ!?」
「――!?」
地上のログコテージの前で、今まさに、中に突入すべく相談していた者達が驚愕する。
「蛍君、離れるんだ!」
「わかってるけど――おっさんも、こっち!」
何処に離れたら安全なのか、咄嗟に予知した光景を頼りに、蛍はコテージから大急ぎで距離をとった。つくづく、こういう時には視えて良かった、後でそう思う通りに蛍のいた地盤が崩れていった。
今や、コテージは大きく傾くだけでなく、まるで地下から押し上げられるようにせり上がっていた。周囲の地面には亀裂が走り、ここだけ大地震があったかの如くに。
「馨兄……!?」
そんなことが可能だとしたら――その従兄以外には有り得ない、と蛍は目を見開く。
――あんただけでも逃げろ。
そう言って強く抱き締め、崩壊する地下室の瓦礫から、身をもって沙夜のことを彼はかばった。
「馨さん……!! 馨さん――!!」
叫んでもがく沙夜を、更に強く馨は抱き締めてかばう。魂の奥底から突き上げるように、不自然に増幅された力の元で、ある約束された衝動……誰かが彼を呼ぶ声を聴いた。
その声に従い、たとえ自らの身がここで崩壊しても、仲間が助かるなら後悔はないと――ありったけの心でその身を委ねていた。
沙夜にはただ、呪いのような声だけが響いていた。
――……思い出して……。
――沙夜、美夜……お前達は……。
やがて地上に、ログコテージの台座だった冷たい石造りの、半ば崩れ落ちた地下空間が城壁のように顕現していた。その状況に多数の人間が、驚愕に目を見張った。
「何ということだ、これは……!?」
「――気持ちはわかるけど、おっさん!」
茫然と呆ける男の背中を叩き、自らにも喝を入れるように両頬をバシンと両手で打つ。
「沙夜さん馨兄夜織、大丈夫か――!?」
現れた地下空間に、崩れた壁の隙間を見つけた。後先考えずに蛍は中に飛び込んでいた。
そこで目にした凄惨な事態に、膝をつかなかったのが不思議なくらいだった。
――カハ、と。
吐き出す血は少量で済んだものの、体中に、臓器の裂けたような痛みが迸った。
革のジャケットをも引き裂く程に、行使したのは強い力だった。馨の全身から、赤い血が無遠慮に滲んでいった。
ずっと抱き締めていた沙夜まで、容赦なく真っ赤に染める。そして力無く、馨も崩れ落ちた。
「馨兄――何――」
目を逸らすようにぐるっと周囲を見回すと、瓦礫に挟まれて倒れている敵側の男達と、全く生気を感じさせずに倒れている二人にも否応なく気が付いていた。
「って夜織!? 美夜さん!? 何でみんな、何があったんだよ――!?」
おそらく二人は、馨の采配で瓦礫からは守られたが、弟分の夜織は上半身を血で染めて倒れている。美夜は先程まで彼女を閉じ込めていた箱が壊れ、冷たく固いままの状態で横たわっている。
沙夜は、馨が倒れ込むのを無言で見届けた。俯いたまま両膝をついて、力なく両方の手をだらりと下げていた。
「えっ……沙夜さん!?」
駆け寄った蛍は、沙夜の両肩を掴もうとする。
「――あちっ!」
その内から湧き上がる、高濃度の力――普通の人間には感じ得ない光を目の当たりにする。
今度こそ茫然と、蛍は理性を手放していた。
さや……と。自分を呼ぶ懐かしい声が、全てが崩れ去っていく挟間で聞こえた。
誰かが優しく、強く沙夜の手を引っ張ってくれた。
沙夜は今、この世界に住む存在としての、人間の自分に。惜しむ間もなく、別れを告げた。
――あなたはきっと……ヒトの……。
小さな沙夜が、沙夜に手を振る。その子は誰か、哀しそうな顔をした女の人と一緒にいる。女の人に手を引かれながら、沙夜に笑いかけている。
――さや。あなたはヒトの、あるがままを助ける精霊。
ヒトの根源。全てをつくる元素の申し子。そう口にしてから、女の人は小さな沙夜を愛しげに抱き締めていた。
――でも、そんなことは、関係はないのね。
女の人は、喜んで彼女を抱き締め返す少女に、精一杯の思いを込めて伝える。
――愛なんて……道具だと、思っていたのに。
ただ、自らの研究を続けるため、都合の良い相手を生涯の伴侶に選んだ。そして都合の良い子供を得たはずだった彼女は。
自分を純粋に求める幼い命を前に、己の罪深さと、これまでの過ちの源を知る。
私は、多くの人間を傷付けてしまった。
夫と共に、幾人もの能力者を実験してきた女は、あまりに今更の後悔だとわかっていた。それでもこれ以上の犠牲を増やさないため、我が子の救出だけでなく、夫の社会的失墜も目論んで行動に出る。
門外不出の研究資料は、全て実の姉に預けた。姉はそれを盾に女の娘を守るが、夫の方も長い時間をかけて姉を蝕んでいく。
――沙夜。きっといつか、迎えに行くからね。
あなたが生きてる内に、私が罪を償えるとは思えないけれど――離れることを不安がる娘を安心させるために、女は優しい嘘をついた。
――だから、いい子にしているのよ……誰も、あなたの利用価値に気が付かないように。
本当にそれだけが、女の最後の心配だった。
それ程に異常な何かを秘めた少女に、愛しているわ。女は最後に、その子達に伝えた。
そして、明るい色の髪をした女性が、沙夜達のすぐ前に立っていた。
――思い出して。
女性は沙夜に、キレイな笑みを向けて伝える。
「思い……出す?」
今、沙夜の心を占めているのは、ただ二つのこと。
鮮血に染まった誰か達の姿と、冷たく固くなった大切な誰か。
――あなた達の力なら、彼らを助けられる。
ただし、と。女性は困ったように、愛しげに笑う。
――それをすれば、あなたは人間でなくなる。
それはきっと、あなたを滅びの道へ導く。女性は悲しげな声で、それを伝える。
……だったら、何。誰かの最後の願いを振り切るように、沙夜は首を振って顔を上げる。
――迎えに来た、と。
自分の名前を呼んでいる声と、自分の心からの強い望みに。
沙夜は強く頷いて、その黒い手を迷いなく取った。
「沙夜さん――……!!」
必死に沙夜の名を口にし、迫り来る自壊を知るような誰かが、手を伸ばしていた。
ふっと顔を上げた沙夜の周囲から、目映い光が立ち昇った。
「――!」
それこそ蛍が初まりに視た、あの明晰夢の光。
心を開いた少女を真っ白に照らし上げて、秩序を持って展開される光の円陣は、次々とその直径を広げる。万物を補う根源の「素」で現世を織り上げていく。
そして光は、もう一人の少女をも取り込んでいく。かの性質を知る「元」において、現世の綻びを原形へ推し戻していく。少女一人の力であれば、一時の幻であったとしても。
補い戻すことで、ようやく幻想は現実となる。
何より遠く、誰より近い二つの奇跡。元素という同じ名を持つ二人が織り成す、夢に似た白い光が場に満ちていった―――
*
8
青い目の誰かが、彼女を現世に贈り還した。
目が覚めた時、沙夜は自分を覗き込んで、ぽたぽた涙を落とす少女の下にいた。
しばらく視界がぼやけていた。何がどうなって、自分がいったい誰なのかすら、その声を聞くまで思い出せなかった。
「沙夜さん……! 沙夜お姉ちゃん……!」
慣れない様子ながら、事情を知ったのか自分を姉と呼んで、双子の妹が泣きじゃくっていた。
「美……夜?」
まずその名前から、最初に思い出した。
沙夜はばっと、朝に仮眠をとった家族用ベッドから起き上がった。危うく、目前の美夜と頭をぶつける所だった。
「お姉ちゃん――!」
良かった……! と、すかさず美夜が抱きついてきた。
「あれ――ここ、病室?」
それも多分、先畑直美が緊急入院をした個室。
昨日から容態が急変して、入院したはずの直美だけでなく、他にも沢山の見知った人がいる。広くない個室を暑苦しく埋めて、全員が沙夜を心配そうに見守っていた。
「夢じゃ――ないの……?」
朝の仮眠の中でもなく、まして、死んだ後の世界でもない。そちら側に行ってほしくない人達の姿と、行っているはずのない、そしてこの場にいるはずのない人の姿があった。
沙夜はまず、その一番の不思議が気になってしまった。
「狭間さん……どうして、ここに?」
「沙夜君。本当にすまなかった」
狭間陽平。沙夜の後見人を引き受け、そして自ら養父の立場をも引き受けた、正体不明の現在の保護者。直美のベッドと平行な家族用ベッドの足元に立ち、扉に近い場所に立った青年達を背に、沙夜を見ている狭間さんがいた。
生きている。
美夜も自分も、そして馨や夜織、蛍も。
それを一目で確認できた沙夜は、彼らのことが一番気にはなるものの――
「私は君を、囮にしていたんだ。それなのに、君を守ることができなかった」
本当にすまなさそうに、狭間さんがいきなり口にするので、そちらを先に聞かざるを得なくなった。
「……はい……?」
「狭間のおっさんは刑事なんだよ。一時期は生活安全課にいて、おれも世話になったんだよな」
狭間さんの後ろに、ひょこっと蛍が顔を出した。何の気なしにそんなことを言って笑う。
「沙夜君のPHSも、無断で使わせてもらった。君達を探すためとはいえ、すまない」
突然、沙夜のアドレスから蛍に「狭間だが」と謎のメールが入った。蛍はそれはそれはびっくりした、と大真面目に語った。
沙夜の行方を追うために、手がかりを求めて狭間さんはメールの履歴を見た。そこに見知った名前の「葉月蛍」が表示されており。それで彼はそのまま返信をしたという。
「私が囮って……どういうことですか?」
沙夜を探すだけなら、後見人として、そこまで不思議な出来事ではない。
しかしその不穏な単語は、刑事という彼の正体を知って、聞き逃すことはできなかった。
「基囲学は、妻である藤桜由穂を殺害し、更に他にも人体実験を行っていた疑いがある。そうした密告と、この資料が送られてきてね」
狭間さんが取り出したのは、藤桜由穂と署名の入った、何かの記録のようだった。
「基囲学には双子の娘がいて、彼はその娘も実験材料にしようとしているが、先の殺人や実験を含め、この資料以外に物的な証拠はないと。だから彼の娘をマークし、守ってほしい、とこの方から直接相談をいただいたんだ」
そうして狭間さんは、ベッドの上で座り、成り行きを黙って見守っている直美を見て言った。
「直美……さん?」
「沙夜さん……危ない目に合わせて、本当にごめんなさい」
直美は俯き、沙夜の目を見ずに項垂れた。
「私はずっと、基囲学を、この資料の存在で脅迫することで美夜を守ってきました。彼から美夜を育てる援助金を得るためでもあり、実際にこれを警察に委ねた場合、彼の属する組織からの報復を恐れてのことでもあった」
その危うい均衡の上で、美夜の平穏は成り立っていた。もしも学の背後にある何者かが、本気で美夜を狙い始めれば、容易に崩れていただろう薄氷の生活。
「でも個人的に、長年この事を相談していた狭間さんから、沙夜さんを見つけたと聞いて――この体では、私が美夜を守るのも限界でした。だから私は、やっと、戦うことを決意したんです」
そして狭間さんは、見つけた沙夜を自ら引き取っていた。
同時にそれまでの後見人から、この子は実の父に命を狙われている、だから養子先の人選には注意するよう、状況証拠の裏付けと申し送りを受けたのだった。
「まいったな……本当に迷惑な養子ですね、私」
沙夜はそう、穏やかに笑うしかない。助けてくれて有難う、とまず口にする。狭間さんと直美は目を丸くして、扉近くの夜織が溜め息をついた。
「沙夜さんは人が良過ぎますよ。直美さんに利用されたも同然なんですから」
けれどもそれは、あくまで学の現行犯逮捕のためだ。それもわかっていた夜織は、直美の話さない部分を読み取りつつも、何も言わなかったと後に語る。
「父はもう、捕まったんですか?」
「ああ、警備員も含めて現行犯逮捕だ。何故か全員、重傷の状態から無傷に戻った後で」
あの、倒壊しつつ地上に現れた地下空間を思い出した。狭間さんも硬い表情をしながら、今後も君達のことはフォローするから安心してくれ、と、沙夜をまっすぐに見て言ってくれた。
重傷の状態から、無傷に戻った。死にかけていた大切な人達を、取り戻すことができた。
不思議ですね、とだけ、沙夜は他人事のように嘯いていた。
「全く――異常な出来事もあったもんだな」
自分のことは完全に棚に上げた、口の悪い馨を沙夜は笑って睨み返す。
「お姉ちゃん……みんな。助けに来てくれて、本当にありがとうございます」
涙混じりでありながらも、心から嬉しそうに笑ってくれた美夜。沙夜もつられて微笑み、やっとそこで、彼女は新たな自分を受け入れていた。自分をここに連れ戻してくれた、青い石を胸に。
――忘れないで。貴女は沢山の愛に出逢う。
――きっといつか、迎えに行くからね。
その声があまりに、優しかったから。今も、そして明日も、沙夜は信じていける気がした。
今度こそ。私は絶対、幸せになれると。
*
――何であんた、あそこまでしたんだ?
あの後彼は、珍しく神妙な顔付きをしてきいていた。
彼女は、彼の命を引き換えにする覚悟で傷付けた、沢山の人間をも救う奇跡の光となった。だから彼女が、平凡な人間に戻れた後に、そう尋ねていた。
それは自分の台詞だ、と、彼女は微笑み返す。
――ただ、そうしたかったから……何でなんて、きいても仕方ないじゃない?
大切なものが大切であることに、理由はきっと、沢山あるだろうけど。
その境界は、特に考えない。そんな心を彼女は大事にしている。
理由という鎖で、互いのあるがままを縛って、歪めてしまわないように。
いつからそうで、どうしてそうだったのか。
それは多分、彼もきかれても困ることだろう。
――つまり、天命でしょ。どうしようもないわ。
そう、いたずらっぽく笑って答える沙夜に。
おかしな奴、と、馨は儚い顔付きで笑っていた。
終章
そして、一ヶ月は後のことだった。
長年、美夜を守り育ててくれた、先畑直美のささやかで静かな葬儀が終わった。
何とか喪主を務め切った美夜は、その後もしばらく、悲嘆から逃げるようにバタバタと忙しくしていた。
「これで今日からわたし達――『藤桜』です!」
そう言って嬉しそうに、沙夜と自分の新たな住民表を、今度から住み込みで雇ってもらうバイト先の店主に確認してもらっていた。
「色々手続き、お疲れ様です、美夜さん」
「先畑のままでいるか、藤桜にするか、凄く悩んだんですけど……やっぱりお姉ちゃんと、一緒がいいな、って思って」
その少女の、嘘のない自然な葛藤と結論。安心したように店主――番夜織は微笑む。
「美夜さんは本当に、正直な人ですよね」
そうして沙夜の方に、改めて振り返った。
「それでは、藤桜沙夜さん、それに美夜さん。しばらくよろしくお願いしますね?」
「夜織さん……本当に、それで良いの?」
沙夜は黙々と、ボックスフラワーを作りながら、顔を上げて物好きな雇い主に尋ねる。
藤桜の姓になるために、狭間さんの養子でなくなった沙夜は、美夜と二人で暮らすことを決意していた。しかしそのために、美夜に残されたお金をいきなり大きく使うのも不安だった。
「うち、二階は全然使ってませんでしたし。バイト代が家賃で良いなら、助かるくらいですよ」
美夜には主に、配達要員でいてもらうとのことだった。今まで通り他のバイトも続けるという美夜に、沙夜は少しだけ、心配で頭を抱えるのだった。
そして、沙夜と美夜の少ない荷物を、二階の大部屋に運び終わったある日のことだった。
「ちわーっす、夜織! 住みに来たぜー!」
そんな謎の言葉を口にしつつ、二段ベッドを手土産にやって来た無法者の姿があった。
「……は?」
さすがの夜織も、呆然、という顔でその訪問者を迎えた。
沙夜と美夜が間借りすることになった大部屋の隣に、物置だった部屋があった。蛍はそれを得意の家事で勝手に整理し、二段ベッドを組み上げて設置してしまった。
さすがに夜織は、厳しくその一言だけはハッキリ伝えた。
「今月から大掃除は月二回にして、バイト代から家賃にしますからね」
「えーっ、冷てー! 馨兄と二人で泊まりに来るのに、おれだけそんなのアリぃ!?」
「馨さんも……来るの?」
蛍のその言葉に反応した沙夜に、どうしてか蛍は、少し面白くなさそうな顔を見せた。
「もう既に来てるぜ。全く、おれにだけ片付けさせてくれちゃってさ」
二段ベッドの上に、いつからそこで寝転がっていたのか、よっ、と手だけを振る無頼漢がいる。
貴方達ですねぇ……と、呆れる夜織の後ろで。沙夜と美夜はポカンとした目で顔を見合わせ……同時に大きく笑い出したのだった。
Elemental. 了
Elemental 起
ここまで読んで下さりありがとうございました。
2025年、明けましておめでとうございますに代わり、10年以上前の発掘作品でした。
一生眠らせておいていいくらい、今見るとあちこち設定がひどい作品なのですが、別作D3が完結し、D3の隠れ重要キャラである馨のルーツがこちらにあるので、完結記念に不定期で載せさせていただくことにしました。
Eシリーズといえなくもない『エレメンタル』は、少なくとも4話くらいまで書かないと、物語としては終わらない作品です。しかしこの後、馨などの重い先行きは、D3や探偵シリーズをご覧下さった方にはわかるかと思われ、あえて今更続きを書くかも悩ましい話です。
ちなみに馨の従弟の蛍が、探偵シリーズに出演する穂波の兄です。魔女やその近縁も後々に出るのが、この『エレメンタル』シリーズなわけでした。
キャラクター的にもあまりぱっとしない話なので、多分この初話だけで、供養は終わると思います。
辰年中にDシリーズをご覧下さった方々は、本当にありがとうございました。
今後の創作活動は相変わらず現在不定です。どこかでまたお目見えできる機会があればとても幸いです。
初稿:2014.5.4


