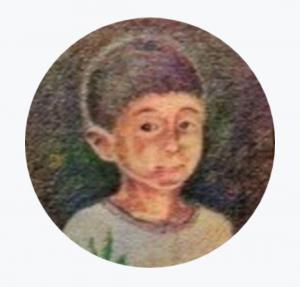はじまりのパ·ド·ドゥ
バレエ「くるみ割り人形」に発想を得て書きました。
この小説に登場する人物、人名、団体名は架空のものであり、この物語はフィクションであることをお断りしておきます。
Ⅰ・くるみ割り人形
今年のクリスマスも、例年のように天気予報は当たらなかった。雪は降らなかった。
中川季衣子にとって、クリスマスは今でこそどうでもいい年中行事のひとつになったが、何かと腹を括れなかったあの頃は一人で街を歩くのさえ、自分が何となく惨めに思えて、うつむきかげんに早足で歩かずにはいられなかった。
毎年、街の景色は十一月下旬から思い出したように、イルミネーションがあちこちで鮮やかに点滅し始め、老いも若きも大切な人が隣にいれば、それだけで皆幸せそうだった。誰もがホワイトクリスマスを期待して、雪が降るのを心待ちにしている中、予報が外れて喜ぶような、そんなひねくれ者は季衣子くらいしかいなかった。
一人暮らしだった季衣子が、大人になってからクリスマスを再び母の美那江と一緒に過ごすようになったのは、ここ数年のことである。
子供の頃は、毎日家に帰って来ているとはいえ、帰りが遅く滅多に顔を会わすことのなかった父の孝也が、クリスマスだけは季衣子を先に寝かすことを許さなかった。
母の美那江は炬燵に突っ伏して今にも眠りそうな、季衣子の眠い目を何とか開けさせようと、様々なことを言って聞かせた。
「もうそろそろサンタクロースがプレゼントを持って家に来る頃じゃない?」とか、「寝ずに待ってて今年こそはお礼を言おう」とか、「どんな顔をしているのかお母さんと一緒に見てみよう」とか、それはいろいろな「手」で、季衣子を寝かせまいとしたが、美那江がどう頑張ったところで季衣子の眠気に勝るものはなかった。
炬燵のテーブルに顔を埋めて、季衣子が夢の国のお姫様になった頃、孝也の野太い声が玄関先から夢うつつの季衣子の耳に聴こえて来た。
「ただいま」
「お帰りなさい」
「季衣子は?」
「さっきまで頑張って起きてたんですけど、炬燵で突っ伏して、今頃は夢の中ですよ」
笑いながら美那江が言うと、
「今夜はあれ程、起きて待ってろと言っておいたのに。毎年のことなのに仕方のない奴だなぁ」
孝也が呆れて少し怒ると、
「だって仕方がないじゃありませんか。いつもならもうとっくに寝てる時間なんですよ」
美那江が季衣子を庇うように応戦した。
この会話が始まると、季衣子は目を覚まさずにはいられなかった。
もう少し、夢の国で綺麗なドレスを着て、召使いをこき使うお姫様でいたかったが、現実世界に生きる季衣子はそうはいかなかった。眠い目を擦り、急いで炬燵から出て玄関へ走り、孝也の帰りを出迎える。
季衣子の気配を感じると、それまで小競り合いをしていた両親の会話はピタリとやみ、孝也は季衣子にケーキを差し出した。
「さぁ、季衣子。今日はクリスマスだからな。ケーキをたくさん買って来てやったぞ」
そう言って孝也が差し出したのは、叩き売りになった半額の日持ちのしない、大きな生クリームのホールケーキだった。
小さいながらも、スーパーの店長を任されていた孝也は、毎年売れ残ったクリスマスケーキをさばくのに四苦八苦していた。
幼いながらもそんな孝也の立場を知っていた季衣子は内心、半額のケーキに落胆しながらも喜んで孝也に礼を言い、その小さな腕に大きなケーキの箱を抱いたが、まだこの他にも車の中にはケーキがあり、朝昼晩と三時のおやつも忘れずに、三日がかりで残りのケーキを平らげなければならないことも、毎年のことだった。
孝也が残りのケーキを車に取りに外へ出ると、孝也には済まないが季衣子は小さなため息をつかずにはいられなかった。
その一方、季衣子の同級生の久我山翔の家は、季衣子の家とは何もかもが正反対のちょっとした金持ちで、クリスマスにはお馴染みのチャイコフスキーのバレエ「くるみ割り人形」を、東洋バレエカンパニーが神林ひろ美の主演で上演すると、毎年、家族でめかしこんで観に行くのが恒例行事となっていた。
特に翔は、主役であるクララ役を務めるプリマ・バレリーナ、神林ひろ美の美しさに見惚れる、ませた男の子だった。
毎年、年が明けて冬休みが終わり、三学期が始まると、季衣子は翔から「くるみ割り人形」の感想を、胸をワクワクさせて聞くのだった。
はじめのうちは、テレビのバレエ中継ですら観たことがなかったから、季衣子は興味津々で翔の話を聞いていたが、毎年同じ「くるみ割り人形」の話を聞くのも、翔には失礼な話だが、季衣子はだんだん厭になってきた。
翔にはそんな気はさらさらなかったが、季衣子には翔の家庭が自分の家とは違い、どれだけ裕福で幸せなものであるのか、毎年、変わることのないその「くるみ割り人形」の話から否が応でも連想させられた。
翔の家とは凡そかけ離れた我が身の虚しさを痛感したのもあるが、実のところ、翔の口から神林ひろ美の話をされるのが、季衣子は堪え難くなっていた。
それは、翔の瞳を輝かすことのできるたった一人の女である神林への、ませた季衣子の一丁前の女としての嫉妬だったのかもしれない。
そんな小学五年の三学期、翔は珍しく季衣子に「くるみ割り人形」を鑑賞してきた土産に、公演プログラムを買ってきてくれた。今までそんなことは一度もなかったが、季衣子がまだ見たことのない夢の世界を、せめて写真でだけでも見せてやろうと、子供心に思ったのだろう。
翔は季衣子に照れくさそうにプログラムを差し出した。季衣子の喜ぶ顔を思い浮かべていた翔だったが、その年の季衣子は毎年の季衣子とは違った。
その日の朝、家を出る前、季衣子はまた翔から「くるみ割り人形」の感想を、神林ひろ美のことを楽しげに聞かされることに、ため息を漏らしていた。すると、そんな娘の切ない胸の内も知らない美那江に、朝からため息なんかつくものではないと叱られたものだから、季衣子の怒りは爆発した。
どうして家は翔の家のようにモダンで裕福な家じゃないのか。
どうして毎年、残り物のケーキを何日も食べさせられなければならないのか。
どうしてあれ程、一度でいいから見たいと毎年言い続けている「くるみ割り人形」を見に連れて行ってくれないのか。
そんなことは幼い季衣子にも分かっていることだった。
この商いのおかげで、一家三人、慎ましくも堅実に、路頭に迷わず「中の上」の暮らしをして来られたのである。それは季衣子にも十分分かっていたが、それでも、季衣子はずっと胸に溜め込んでいた「どうして」を言わずにはいられなかった。
そんなつまらないことで美那江と一悶着あり、昂る気持ちを鎮めることが出来ないまま、季衣子は学校へ登校した。そんな最悪なタイミングで、何も知らない翔は恒例の「くるみ割り人形」の話をする前に、季衣子に公演プログラムを差し出したのだった。
「はい、季衣ちゃん。これ」
翔が照れくさそうに、公演プログラムを季衣子の前に差し出すと、それを見た季衣子は、突然、怒り出した。
「何よこんなもん!自分がお金持ちの家の子だからって。翔くんのお父さんやお母さんに買ってもらわなくたって、私のお父さんだってお母さんだって、これくらい買えるもん!」
季衣子はふんだくるように翔からプログラムを奪い取ると、一瞬のためらいの後、床に思い切り叩きつけた。僻みと言えば僻みだが、それは決して裕福ではないが、心から愛する両親と、そして自分の小さなプライドを守るための、季衣子の幼気な抗いだった。
そうとは知る由もなく呆気にとられた翔は、床に叩きつけられたプログラムに目を落とすと、何も言わずに寂しそうな顔をしてそれを拾い、季衣子の元から離れて行った。
自分から売った喧嘩の手前、季衣子は翔に詫びも言えず、そのまま一月も終わりに近づいた。そんなある日のことだった。
翔と仲直りをしようと、いつか家族で旅行に行った時、父の孝也が買ってくれた雨蛙のキーホルダーを、翔に詫びの代わりにプレゼントしようと、季衣子は翔の家を訪れた。相変わらず、一目で金持ちと分かるような、そんなに大きくはないが作りのいい洒落た家が季衣子を出迎えた。恐る恐るベルを鳴らしてみたが、誰も出て来る気配がない。
ぴょんぴょんと飛び跳ねて家の中を覗いて見たが、誰もいる気配はなかった。
昔から一人、翔が生まれた時から住み込みで働いているお手伝いのさおりが、いつもは必ず家にいる筈なのだが、そのさおりも今日は生憎留守のようだった。
仕方なく諦めた季衣子はとぼとぼと家に帰った。
明日、学校へ行ったら翔に真っ先に謝って、このキーホルダーを渡せばそれで万事解決する。そう思い直した季衣子の足取りは、翔の家へと歩いて来た時より幾分軽やかだった。
翌朝、季衣子が学校へ行くと、教室はいつものように賑やかで騒々しかった。
昨日、会うことができなかった翔の姿を探したが、翔の席にその姿はなかった。
相変わらず教室は賑やかで騒がしいままだったが、担任の大沢が来ると、生徒たちは急いで席に着いた。すると、担任の大沢から、生徒たちは思いもかけない事実を告げられた。
昨日、久我山翔は引っ越したという。
大沢はそれ以上何も言わず、何もなかったように、すぐに一時間目の国語の授業を始めた。
季衣子は上の空で大沢の朗読に耳を傾けていたが、余りに急で、詫びを言うどころか別れの挨拶すらできなかったことに、その小さな胸を痛めた季衣子は授業どころではなかった。
それから数日すると、久我山一家は夜逃げをしたという噂が、誰からともなく季衣子の耳に入ってきた。
久我山家は先代、つまり翔の祖父が一代で財を成した家だったが、何の苦労も知らない二代目である翔の父親が、新たに事業に手を出したが失敗し、昨年辺りからどうにも立ち行かなくなっていたらしい。子供である翔が、そんな一家の一大事を知っていたのか季衣子は知る由もなかったが、あの日が、目を輝かせた翔の口から「くるみ割り人形」の話を聞けるのも最後だったのである。
何も知らなかったとはいえ、あんな酷い態度を取って翔の話を聞かなかった季衣子は、人生で初めての後悔を経験することとなった。
それが、自分の人生にどれだけ根深く傷を残すことになるのか、この時の季衣子は知る由もなかった。
久我山一家が姿を消して、一月ばかりが経とうとしていたある日。
季衣子宛に一通の郵便物が届いた。
郵便受けから郵便物を取り出した美那江が裏を見たが、差出人の名前はなかった。手紙にしてはいやに大きい封筒だった。不審に思った美那江だったが、普段、季衣子が読んでいる少女雑誌か何かの懸賞でも当たったのだろうと、ちょうど学校から帰って来た季衣子に郵便物を手渡した。
受け取った当の季衣子は、身に覚えのない自分宛の郵便物を手に、首を傾げながら自分の部屋に入ると床にペタンと座り込み、ハサミを手に恐る恐る封を開けた。すると、見覚えのある、しっかりした少し薄めの本のような物が顔を出した。
それは、翔が最後に季衣子に「くるみ割り人形」の話をしようとしたあの日、照れくさそうに季衣子に差し出した「くるみ割り人形」のプログラムだった。季衣子が床に叩きつけた際、汚れがついたのだろう。表紙は少し黒くくすんで、角が潰れていた。
季衣子がプログラムをパラパラ捲ると、そこには季衣子が生まれて初めて見る、夢の世界があった。
場面場面で設えられた豪華なセット、華やかな衣装に身を纏った団員たちによる一糸乱れぬ群舞。おかしな顔をしたくるみ割り人形や、ハンサムな王子に姿を変えたプリンシパルの大城裕二や、翔が幼心に魅せられたクララを演じた、今をときめくプリマ・バレリーナ神林ひろ美の舞い踊る美しい姿が、季衣子をあっという間に夢の世界へいざなった。
最後のページを捲り、プログラムを胸に抱きしめた季衣子は、思い出したように床に突っ伏しておいおいと泣いた。それはもう、二度と会えない翔から、季衣子への最初で最後の贈り物だった。
Ⅱ・動き出した時計の針
あれから三十年。季衣子は来年、四十になろうとしていた。
子供が産めるうちにと急いで結婚した男とは相性が合わなかったのか、子宝に恵まれるどころか結婚生活も上手く行かず、すぐに別れた。
化粧品会社に就職していた季衣子は、結婚しても幸い仕事を続けていた。自活していた季衣子が、相性の悪い男とぐずぐずいつまでも結婚生活を続ける理由など、何一つなかった。
しばらく一人で暮らしていたが、五年前、父の孝也が心不全で呆気なく世を去ってから、母の美那江も季衣子同様、一人暮らしをしていた。
朝できなければその日の晩、季衣子は必ず一度は美那江に電話をかけていた。
その日、朝電話をかけられなかった季衣子はその夜、美那江に電話をかけた。
いつもは待ってましたとばかりに、すらすらとその日あった一日の出来事を話す美那江が、今日に限って歯切れが悪い。
「お母さん、どうしたのよ。調子でも悪い?」
「季衣子、ねぇ、今から家に来れないかしら。お母さん、ちょっとね、何だか朝から調子が良くないのよ」
珍しく美那江の弱気な言葉に、季衣子は妙な胸騒ぎをおぼえた。季衣子が今から行こうかと返事をしようとした次の瞬間、電話口でドスンと鈍い音がした。
美那江が倒れたのである。
幸い命に別状はなかったが、美那江は数日前に引いた風邪をこじらせ肺炎を起こしていた。大事を取って十日程入院して事なきを得たが、気が弱った美那江が季衣子に同居を持ちかけたのは、退院許可の下りたその日のことだった。
短大を卒業してから結婚離婚を経て、すっかり気ままな一人暮らしに慣れていた季衣子は、美那江の申し出にひとつ返事はできなかった。
返事を渋っていた季衣子に、美那江は季衣子が孝也の死に目に会えなかったことを持ち出した。
それは娘に対してあまりに卑怯だと季衣子は思ったが、悔いの残る親との別れを二度と経験したくないと思うのも本音だった。
それから間もなく、季衣子はわずかな荷物と共に、二十年振りに母の住む実家に帰ったのだった。
久しぶりの美那江との生活は、季衣子が思っていた以上に窮屈で、そして、忍耐のいるものだった。
二十年前、季衣子が家を出た時に、玄関先でその一人立ちを見届けてくれた、凛とした美那江の姿はもうそこにはなかった。
倒れる直前まで、あれだけ自分のことは自分で何でもしていた美那江が、季衣子と一緒に暮らし始めた途端、季衣子に頼りきりになった。
化粧品会社勤務の美容部員である季衣子は、ひとたび出勤すると座る暇もないくらい、慌ただしい一日を送る。
毎日、シフトの都合で朝早くて夜が遅いという日もあれば、その逆もあった。応援で他店への出勤もざらである。美那江はそんな季衣子の仕事の都合など省みもせず、自分の生活スタイルを一向に崩そうとはしなかった。
そんな美那江の我の強さや、生活のズレがだんだんと深い母娘の溝へと変わり始めたのは、同居を始めてから一月も経たない、クリスマスも間近に迫った頃のことだった。
前の晩、季衣子は歳末謝恩セールで片道二時間かかる大手デパートへ応援を頼まれ出勤し、帰りが遅くなった。
翌日は仕事が休みだから、静かに寝かせてくれと美那江に前日、伝えておいたにも関わらず、美那江は趣味で通っているハーモニカ教室で親しくなった仲間たちを家に招き、クリスマスに老人ホームを慰問するための「ジングル・ベル」の練習を、ラストスパートで始めたのである。当然、一人や二人ではないから、その聴くに堪えない頼りない不安定な音色は、布団の中で疲れ果てて眠る季衣子の耳に、聴こえない筈がなかった。
寝起きのまま上着を羽織り、寝室からこそ泥のように忍び足で階段を途中まで降りた季衣子が、そっとリビングを覗き込むと、美那江が仲間たちと楽しげにハーモニカを奏でている。
季衣子は腹立たしかったが、少しばかり物哀しかった。自分が家に帰れば美那江はどんなにか心強いだろうと思っていたが、いざ家に帰ってみると、弱気になって同居を願い出たあの日の気持ちなどすっかり忘れて、自分だけ元の生活を謳歌している。
季衣子は美那江を疎ましく思った。
呆れた様子でリビングに集う美那江と、その客人たちを見つめていた季衣子の冷めた視線に美那江が気づいた。
「あら、季衣子。そんなところで何しているの?お客様がいらしてるっていうのに、そんな格好でご挨拶もしないで。みっともないじゃないの」
ゆっくり寝かせてくれとあれほど頼んでおいた季衣子の願いを、美那江はすっかり忘れていたばかりか、大勢の大人たちの前で季衣子に飛んだ恥を掻かせた。
「早く見繕いをして来て、お客様にご挨拶なさい」
怒りに震える季衣子を横目に、尚も美那江は続けた。
「全くもう、いい年をして。中身は子供のままなんだから、ねぇ皆さん」
季衣子に気を遣ったのか、客人たちは季衣子から視線を外し、下を向いたまま黙っていた。
季衣子は急いで洗面所に向かうと、歯を磨き、顔を洗い、髪をセットし化粧をして部屋に戻ると、パジャマからいちばん気に入っている余所行きに着がえ、再びリビングでハーモニカの練習を続けている客人たちに満面の笑顔で挨拶をすると、美那江を睨みつけてそのまま黙って家を出た。
外に出ると、まだ眠気の残る季衣子の頬に、突き刺すような冷たい風が吹きつけた。
空きっ腹で家を出た季衣子は、思い出したように遅めの朝食を摂るべく、引っ越して来てからいつかは行ってみたいと思っていた、昭和の雰囲気が漂うレトロな喫茶店「Eternity」へ駆け込んだ。
手動の扉を静かに開けると、頭の上で賑やかにカランカランと鐘が鳴った。
空いてる席に適当に座り、パンとコーヒーとハムエッグを注文した。それらを待っている間に店内を見回すと、季衣子の目に一枚のポスターが目に留まった。
「今年の冬も、東洋バレエカンパニーが、あなたを素敵な夢の世界へといざないます」
そう書かれた大きなキャッチコピーの下に目をやると、東洋バレエカンパニー、主演・神林ひろ美「くるみ割り人形」場所・日本夢芸術劇場とあった。公演日時を見ると、ちょうど今日の午後からである。
「神林ひろ美、今も踊ってたんだ」
季衣子が思わず呟くと、注文のパンとコーヒーとハムエッグを盆に載せた、この店のマスターらしき人の良さそうな年嵩の男が、それらを盆から順番にテーブルに置きながら、季衣子に話しかけてきた。
「お客さん。失礼だけど、神林さんのファンですか?」
「あっ、いえ、ファンて程じゃないんですけど。名前だけ···」
決まりの悪そうに返事をすると、
「神林ひろ美、私は昔から大好きでしてね。デビューした当時から毎年必ず一本は観に行ってるんですよ。若い頃ですけどね、神林さんにファンレターを書いて、送ったことがあったんですよ」
客が神林ひろみに関心があると見ると、マスターはいつもこの話をするのだろう。季衣子が頷きながら聞いていると、マスターは饒舌に話し始めた。
「忘れた頃に返事が来ましてね。私は常治と書いてつねはると読むんですが、彼女が三崎ジョージ様ってシャレで書いたのか、本当にジョージと読んだのか分からないけど、私もそれが気に入りましてね。親には済まないけど、それからずっと、私はジョージって名乗るようになりましてね」
喫茶「Eternity」のマスター・三崎常治は、彼女と同世代で共に同じ時代を生きて来た。
神林の話をする三崎のその瞳は、まるで少年のように輝いていた。
その三崎の少年のような瞳に、季衣子は懐かしい人物を思い重ねていた。
次の瞬間、三崎は断言するように季衣子に言った。
「神林さんのバレエ、まだ観たことがないんだったら、大袈裟ではなく本当に一生に一度は見ておいた方がいいですよ。残念だけど、近々引退するかもしれないって話も出てますから」
「えっ、本当ですか?」
まだ踊り続けていた神林に季衣子が安堵したのも束の間、一転、その神林が引退するかもしれないという。
ゆらゆらと微かに揺れるコーヒーの黒い液体を、まるで自分の心の内を見るように季衣子はじっと見つめていた。
「もし当日券が手に入ったらご覧になってみては。絶対後悔はしないから。ねっ、それじゃ、ごゆっくり」
「ご親切にどうも」
吸い込まれるように見つめていたコーヒーから目を離し、軽く会釈をしながら三崎の背中を見送ると、季衣子の脳裏に三十年前の苦い記憶が蘇ってきた。
久我山翔のことである。
季衣子はこの三十年、神林の「くるみ割り人形」を見たいと思いながらも、一度も見ることはなかった。翔に対して自分の取った行動が、どうしても許せなかったのである。そんな自分が、翔が大好きだった神林と「くるみ割り人形」を見てはいけないのだと、ずっと言い聞かせて来たのである。
あの頃、毎年、翔から話を聞いていた「くるみ割り人形」を踊っていた神林ひろ美も、もう来年は還暦を迎える。
三十年という歳月はあっという間に過ぎ去り、来年自分も四十である。
孝也も死に、美那江の申し出で同居を始めたが、これから美那江も自分もいつどうなるかなんて分からない。
第一、神林が引退するかもしれない。
翔が見た「くるみ割り人形」を、神林が演じるクララを、自分は一生見ることができないかもしれない。翔が味わったその感動を、一生共有することができなくなるかもしれない。
そう思った季衣子は、テーブルに並んだパンとコーヒーとハムエッグを急いで平らげると、レジに急いだ。
「マスター、いえ、ジョージ、ありがとう。私、これから神林さんの『くるみ割り人形』見に行ってきます」
季衣子の弾けるような笑顔を目にした三崎は、嬉しそうな顔をして言った。
「素敵な一日になるといいね、お嬢さん」
あの日以来、季衣子の止まったままだった時計の針が、再び時を刻み始めた。
Ⅲ・かくも嬉しき偶然
喫茶「Eternity」をつんのめるように後にした季衣子は、急いで駅に向かうと電車に飛び乗った。三十分揺られて最寄駅で下車すると、人混みをかき分け日本夢芸術劇場へと、再び走り出した。
チケット売り場に並んだがすでに行列で、当日券も手に入るかどうか分からない有り様だった。
季衣子の前に並んだ客が一人減り二人減り、やがて季衣子の番が来た。
「あの、東洋バレエカンパニー、神林ひろ美主演の『くるみ割り人形』の当日券を··」
高鳴る胸の鼓動を抑え切れずに身を乗り出したが、窓口の女が季衣子に「一枚」とまでは言わせなかった。
「申し訳ございません。当日券は先程のお客様で売り切れとなりました」
「そんな···」
大きなため息をつくと、季衣子は窓口の女に頭を下げ、黄色く色づいた銀杏の木の下のベンチに腰を下ろした。
「私はやっぱり『くるみ割り人形』には縁がないんだわ。翔くんにあんな酷いことしたんだもの。神様はやっぱり見てたってわけか」
行き交う人々に踏みつけられた、黄色く紅葉した銀杏の葉を季衣子はぼんやり眺めていた。わずかな時間でも十二月の屋外は思いの外寒い。
「あぁ、何だか寒くなってきた」
我に返った季衣子が気を取り直して、その場を後にしようとしたその時だった。
季衣子の座るベンチの隣に、季衣子と同じ年くらいのスーツを着た男が、スマートフォンを片手に話しながら腰を下ろした。
「えっ、熱があるって。何度?八度五分?何だって今日に限って。残念だけど仕方がないなぁ、チケット無駄になっちゃうから、僕一人でも見て帰るよ。とりあえず今はゆっくり休んで。終わったらすぐ連絡するから。それじゃ」
話し終えると、男はスマートフォンをズボンのポケットに仕舞うと、深いため息をついた。
隣でその様子を盗み聞きしていた季衣子は、項垂れる男にためらいながらも声をかけた。
「あの、すみません」
妙な一瞬の間の後、男が返事をした。すると、季衣子はベンチから立ち上がって頭を下げると、恥を忍んで男に言った。
「盗み聞きしていたようで大変失礼ですが、ごめんなさい。聞こえてきちゃったんです。でも、やっぱり盗み聞きになっちゃうのかな。失礼ついでにお願いします。私にそのチケット、譲っていただけないでしょうか」
こんな不躾な願いを聞いてくれる筈がないと、はじめから諦めていた季衣子だったが、もうこれを逃したら神林ひろ美の「くるみ割り人形」を見ることは一生ないかもしれない。そんな切羽詰まった思いに恥も外聞もなかった。
そんな季衣子の思いとは裏腹に、すっとんきょうな顔をしていた男の顔が、次の瞬間、満面の笑顔に変わった。
「いいんですか!?それは助かるなぁ。チケット無駄になっちゃうところだったから、僕の方こそ願ったり適ったりです!」
「本当ですか?!悪い冗談じゃないですよね?ありがとうございます!良かったぁ、チケットおいくらですか?」
バックから財布を取り出すと、季衣子は男に訊ねた。
「おいくらですかって嫌だなぁ。どうせ無駄になるところだったんですから、お金なんていいんですよ」
男は笑顔を絶やさずさらりと言った。それは季衣子が今まで出会ったことがないくらい、相手に気を遣わせないスマートな物の言い方だった。
「そうはいきませんよ。見も知らぬ男の人に、ただでチケットを譲っていただくなんて···」
季衣子は恐縮した。すると、男は今度はユーモアを交えながら、季衣子に言った。
「気を悪くなさったなら謝ります。ただ、今更、払い戻しもできないんですから。クリスマスのサンタさんからの、ちょっと早いクリスマスプレゼントだと思って、このまま受け取って下さいよ」
開演の時間は刻一刻と近づいていた。遠目から見ても、会場のロビーは人でごった返し始めていた。
きっとこの先、こんな押し問答を繰り返しても、男はチケットの代金を受け取ることはないだろう。このままグズグズしていても、却って男に迷惑をかけるだけかもしれない。
「それじゃ、ちょっと早いサンタさんからのクリスマスプレゼントだと思って、ありがたく受け取ります」
季衣子は負い目を感じながらも、男の申し出を男を真似て、ユーモアを交えて受け入れた。
「良かったぁ。大の男が一度言い出したことを引っ込めるわけにはいきませんからね。もうそろそろ開演ですから早いとこ会場に入りましょう。席は連番で取ってありますから私の隣ですが、それでも構いませんね?」
「えぇ、勿論です」
思いがけない巡り合わせに、季衣子と男はもうすぐ始まる東洋バレエカンパニーと、神林ひろ美がいざなう「夢の世界」に、足を踏み入れようとしていた。
Ⅳ・いざなわれし夢の世界
会場に入り、男に席を案内された季衣子は仰天した。座席では最も値段の高い、二万円の最前列の真ん中、SS席だったからである。目の前にはオーケストラのボックスがあり、それを挟んだ二メートルくらい先に舞台があった。
季衣子が男に気づかれぬよう、横目で男の顔を見ると、男はそれに気づくこともなく平然とした顔で季衣子を席に座らせ、自らも席に座った。
一九五〇年代後半に建てられたという、日本夢芸術劇場はモダンな内装だった。海外の様々な演奏家からも「リサイタルをするなら是非この劇場で」と言われる理由も、大いに頷けた。
まだ幕が開いていないというのに、季衣子の心は昂っていた。
初めて見る「くるみ割り人形」、神林ひろ美のバレエ、生演奏で聴くチャイコフスキー、そのどれもが魅力的だったが、季衣子は今、自分のすぐ隣に座る男に大きな関心を抱いていた。
「どうかしました?」
「本当にいいんですか、こんないい席を私なんかに、ただで···」
季衣子は、ステージに登場するキャストが豆粒にしか見えないような、安い席だとばかり思い込んでいた。のこのこと男の言いなりになって、一緒について来てしまった自分に呆れた。
そんな季衣子の思いなど意に介さず男は言った。
「お嬢さん、ここまで来てもうそれは言いっこなしですよ。さぁ、もうそろそろ舞台の幕が開きますよ」
年甲斐もなくお嬢さんと一日に二度も言われて、頬を真っ赤に染めた季衣子の顔をまるで隠すように、会場の照明は徐々に暗くなり、ピンスポットがオーケストラの指揮を務める山崎太一を照らすと、会場からは大きな拍手が起こった。
それに応えて一礼し、山崎が客席に背を向けオーケストラに指揮棒を振ると、東洋バレエカンパニーの「くるみ割り人形」の幕が開いた。
チャイコフスキーの「くるみ割り人形」の調べにいざなわれるかのように、舞台には雪が降り始めた。
季衣子がわくわくして舞台を見つめていると、クララに扮した神林が、まるで少女のような愛らしい姿で舞台に現れた。会場からは「待ってました!」と言わんばかりの、盛大な拍手が起こった。
神林ひろ美は来年還暦を迎えるというのに、まるで衰えを知らない素晴らしい踊りを観客に披露した。
年齢を重ねたからこそ滲み出る、神林の何とも言えぬ人間味に溢れた演技力と、その優美な踊りに心を奪われた季衣子は、遠い昔、翔が胸をときめかせ、その瞳を輝かせて熱く季衣子に語った理由が、三十年かかって、今ようやく理解できた。
時折見せる神林の笑顔が、今、同じく年齢を重ねた季衣子の心に、遠いあの日の久我山少年の顔を、ぼんやりと思い出させた。
第二幕の「別れのパ・ド・ドゥ」で衣装を着替えた神林が、パートナーのダンサー・魚住愛斗と華やかに踊る姿を目にした時、既に季衣子の目には涙が溢れていた。
神林の姿に涙し、鼻を啜る季衣子に気づいた男は、季衣子にハンカチをそっと差し出した。
男に軽く頭を下げてハンカチを受け取ると、季衣子は頬を伝う涙を静かに拭った。男も同じ場面に胸を打たれたのか、季衣子が横目で見ると声を殺すようにして泣きながら、神林の踊りを食い入るように見つめていた。
思わず季衣子が呟いた。
「私、この曲を聴くと、もうダメなんです」
すると、男も季衣子の耳に顔を近づけ、小声で言った。
「僕は、神林さんが今日の今日まで、こうして毎年『くるみ割り人形』を踊り続けて来てくれたことに、今、物凄く感動して、感謝の思いで胸がいっぱいなんです」
わずかに言葉を交わした二人は、再び舞台で舞い踊る神林に心を鷲掴みにされた。
こうして、季衣子が初めて目にする神林ひろ美主演の「くるみ割り人形」の舞台は、盛大な拍手と共に幕を閉じた。
幕が降りても観客の熱狂的な拍手は鳴り止まず、神林と東洋バレエカンパニーのキャストが、再びカーテンコールに笑顔で応えた。
クララ役の神林が相手役を務めた魚住に促され、中央に歩み出て美しいレヴェランスをすると、会場の拍手はますます大きくなり、観客の誰もが神林を幕の向こうへ引っ込ませようとはさせなかった。
季衣子が神林に見惚れていると、隣の男は立ち上がって一際、大きな拍手を神林に送り、「ブラボー!」と叫んだ。季衣子も黙って座っていられなくなり、立ち上がると男と一緒に「ブラボー!」と張り裂けんばかりの大きな声で叫んだ。
そんな季衣子を目にした男は酷く嬉しそうだった。
それに気づいた舞台上の神林が二人に視線を送り、にっこり微笑んだ。
こうして、東洋バレエカンパニーによる神林ひろ美主演の「くるみ割り人形」と、季衣子の夢のような時間が終わりを告げた。
終演後、あたたかな気持ちに包まれた季衣子と男は、しばらく座席に腰を下ろしたまま、帰路に着く観客の姿を眺めていた。
その後ろ姿を眺めながら、男が感心頻りに言った。
「これだけの人を魅了する神林ひろ美って、やっぱりすごいなぁ」
「本当に。私たちが『ブラボー!』って叫んだ時、神林さん、私たちに微笑んでくれましたね。お気づきになりました?」
「えぇ、勿論ですよ!」
男は満面の笑みで答えた。
「あの、もしこの後、お時間あるようでしたら、今日のお礼に何かご馳走させて下さいませんか」
「えっ」
「あっ、いえ、ご迷惑でなかったらですけど···」
男は季衣子の突然の申し出に戸惑ったが、今日のこの感動を一緒に分かち合える相手が目の前にいることを喜び、条件付きで快く季衣子の申し出を受け入れた。
「軽く、お茶だけでも良ければ···」
Ⅴ・君に重ねし面影
会場の中にある喫茶店に場所を移した二人は、初めて面と向かい合った。
そういえば、季衣子と男は、まだ互いの名を知らなかったことに気づいた。
どちらからともなく自己紹介をしようと口を開きかけたが、ウェイターが水を運び注文を取りにやって来たことで、それはお預けになった。
「お先にどうぞ」
「じゃ、僕はレアチーズケーキと、アイスコーヒー」
「せっかくですから、何か軽く召し上がって下さいよ」
言われるままメニューに軽く目を泳がせ、
「それじゃ、贅沢ミックスサンドイッチを」
「それじゃ、私も。贅沢ミックスサンドイッチとホットコーヒー。それから苺のたっぷりタルトを一つ」
「かしこまりました」
ウェイターが注文を繰り返し去っていくと、気を取り直して、季衣子が口を開いた。
「今日は本当にありがとうございました。私、とても感動しました。それなのに、私ったら失礼なことに。まだあなたのお名前を伺っていませんでした」
季衣子が詫びると、男は笑って自分の顔の前で扇ぐように手を振った。
「そんな、そんな、いいんですよ。名乗る程の者じゃありませんから···」
「そうはいきませんよ」
「そうですか?それじゃ仕方ないな。僕は片桐といいます。名刺を差し上げたいところですが、今日は仕事を休んだものですから、そういうの持って来てなくて」
「そんな、いいんです。お名前さえ分かれば···」
季衣子は一人、頬を赤く染めてコップの水をゴクリと飲んだ。
「僕もあなたのお名前、伺ってもよろしいんでしょうか?」
男は遠慮気味にテーブルに手を置くと、恐る恐る季衣子に訊いた。
「私、中川っていいます」
「中川さん、か。それじゃ、中川さん、お言葉に甘えてご馳走になります」
片桐は急に居住まいを正すと、季衣子に深々と一礼した。
二人はゆっくりお茶を飲みながら、今さっき見終えたばかりの「くるみ割り人形」の感想を熱く語り始めた。最初に口を開いたのは、またしても季衣子の方だった。
「片桐さんは、昔から神林さんの『くるみ割り人形』をご覧になっているんですか?」
「えぇ。子供の頃から神林さんの『くるみ割り人形』は 見に行っています。元々は、私の両親が彼女のファンでしたから、それで一緒に」
「そうだったんですね。私の両親はこういうのには全く疎くて。おまけに父は仕事仕事で、家族のことはいつも放りっぱなしでしたから···」
季衣子は五年前に死んだ、父の孝也を思い出していた。
「そうすると、中川さんはバレエに関しては全くもって、その、ノータッチだったんですか?」
「えぇ」
と言いかけたところで季衣子は言葉を改めた。
「いえ、バレエも好きでしたし『くるみ割り人形』も大好きでした。だけど、私の家はさっきも言いましたけど、片桐さんのご両親のように文化的ではなかったものですから、実際に舞台を見たのは今日が初めてなんです」
季衣子が片桐の両親のことを文化的文化的と何度も言うものだから、片桐は決まりが悪くなって横を向くと軽く笑った。
「ただ、小学生の頃、よくバレエのことや神林さんのことを、とても熱心に話してくれた同級生の男の子がいたんです。いつもその子から話を聞いて、いいなぁ、自分もいつか見に行ってみたいなと思いつつ、あっという間に月日は過ぎ去ってしまいました」
あの日以来、会っていない久我山少年のことを思い出した季衣子は、どうしようもない寂寥感に襲われた。
「中川さんの同級生にも、僕と似たような人がいたんですね。いつの時代にも、そういう奴っているんだなぁ、どこにでも」
片桐は季衣子に気づかれないように、季衣子の顔をそっと盗み見た。
そんな片桐に気づかず、思い出したようにまた季衣子が話し始めた。
「その子ったら『くるみ割り人形』の話をするだけならいいんですけど、神林さんの話まで熱っぽくするから、何だか私、妙に腹が立ってしまって···」
「また、どうしてそんなに腹なんか立てたりしたんです?」
「さぁ、それが自分でも分からないんです。でも、今思うと、多分、その子のことが好きだったんじゃないかなぁ、なんて」
片桐は少し目を左右に泳がせながら、腕を組み黙って頷いた。
「下手したら、親子くらい歳の違う神林さんに、私、嫉妬していたのかもしれないですね。今考えるとバカみたい」
三十年も前の子供の頃の、甘酸っぱくも苦い思い出を、大人になってから見も知らぬ男に話すとは夢にも思っていなかった季衣子は、恥ずかしさにうっすらと顔を赤らめ、ケタケタと笑った。
すると、片桐が、
「中川さんは、その子に、自分の思いは伝えなかったんですか?」
鋭い問いかけだった。
「自分の思いって、その頃はただその子から『くるみ割り人形』の話を聞かせてもらうのが楽しみで。それ以上の気持ちなんてなかったんじゃないかなぁ、多分···」
季衣子の頼りない答えを聞いた片桐は、少々落胆した。
「嫌だなぁ、片桐さんてば。どうして片桐さんがそんな落ち込んだ顔をしなければならないんです」
「いえね、それだけ熱心に話を聞いてくれる女の子だったなら、彼の方も中川さんに好意を持っていたんじゃないかと思って。話を聞いてたら、『多分、好きだった』とか、『それ以上の気持ちはなかった』とか、中川さん言うことコロコロ変わるから。その男の子が急にかわいそうに思えましてね。何だか他人事とは思えなくて、彼に同情の気持ちが湧いてきたんですよ」
「どうして片桐さんが彼に同情しなければならないんですか。片桐さんて本当にどこまでもお人好しなんですね」
高価なチケットをただで譲るような、どこまでも人のいい片桐に、季衣子は感心しながらも半ば呆れたように遠慮気味に笑った。
「自分にも同じような苦い経験があったものですから。その子の気持ちが何だか手に取るように分かるんですよ」
「まぁ、片桐さんにも、そんな苦い経験がおありになったんですか?」
「いや、まぁ、そういうわけでは···」
口ごもる片桐に、季衣子は遠い昔を懐かしむように言った。
「月日が流れてみないと、自分の気持ちでさえ分からないことってあるんですね。今になって、あの頃の答え合わせをしているみたい。したところで正解かどうかなんて、ちっとも分からないですけど」
「そう言われてみればそうかもしれませんね。正解だったのか、そうじゃなかったのか」
「間違いと分かったところで、もうそれを正しに行けないところまで、遠くへ来てしまったんだもの」
片桐が深く季衣子に同調し、何かを言おうとした時だった。
「今、どうしているのかなぁ、翔くん」
季衣子が思わず翔の名を口にした。すると、片桐が、
「中川さん、今何て?」
「えっ、あぁ、翔くん?」
「翔くん?」
「えぇ、その男の子の名前が翔くん。久我山翔って言うんです」
名前を聞いた片桐は、わずかに驚いたような顔をして、
「久我山翔くんかぁ」
と呟き、一人ニヤニヤした。
「何をニヤニヤしてるんです、片桐さんたら」
片桐にからかわれているような気がした季衣子は、ちょっと怒ったように片桐を問い詰めた。
「いえね、最後に会ってから三十年も経つっていうのに、こうして中川さんを少女のようにさせている久我山翔くんは、何て罪なんだろうと思って」
いささか片桐が笑い過ぎたのか、季衣子の顔色がすっと変わった。
「そんなんじゃないんです。私、彼に、久我山翔くんに酷いことしちゃったんですよ」
「何をしたんです?」
片桐が興味深そうな顔で季衣子に訊いた。
「いえ、思い出すだけでも自分が嫌になるから。この話はもう···」
過去の自分を思い出し、落ち込む季衣子に片桐はやさしく声をかけた。
「中川さんの気持ちは分からなくもないけど、多分、その久我山翔くんって子は、中川さんのこと、はじめから怒ってないと思うけどなぁ」
「そうだといいんですけど」
「そうですよ、きっと」
冷めたコーヒーを飲み干した片桐が、
「そろそろ出ましょうか」
そう言って伝票を素早く手中に収めた。
「あっ、嫌だなぁ、片桐さん。困ります、それは私が払いますから。返して下さい」
季衣子の言うことには耳を貸さず、片桐はさっさと足早にレジに向かい、会計を済ませた。
店を出た季衣子は、呼び止めても一向に意に介さない片桐の腕を思わず掴んだ。
「片桐さん。本当に私、こんなことされちゃ困るんです」
季衣子が鼻息を荒くし、鼻の頭をピクピクさせて少し怒ったように言うと、片桐は劇場内に設けられた「くるみ割り人形」のグッズ売場へ駆け出した。
「ねぇ、中川さん。やっと人も空いてきたし、良かったら、グッズ見ていきませんか。今ならゆっくり見られますよ」
「もう、片桐さんたら。まるで子供ね」
何だか季衣子はおかしくなった。それまで一定の距離を感じていた片桐に、急に親しみを感じている自分に気づいたからである。
夢のような舞台も終わり、片桐との楽しいティータイムも終わった今、もうそろそろこの楽しい時間も終わりに近づいていると、季衣子は感じていた。
グッズ売り場には東洋バレエカンパニーのオリジナルグッズである今日の公演プログラムを筆頭に、おかしな顔をしたくるみ割り人形のキーホルダーや、パ・ド・ドゥを踊る神林ひろ美のアクリルスタンド、四年前に自身の舞踊生活五十五年を振り出版した自叙伝が、所狭しと並んでいた。
そんな中から、神林のアクリルスタンドを手に取った片桐が、感心したように言った。
「ねぇ、見て見て中川さん。神林ひろ美のアクリルスタンド!これって推し活しろってことだよね?こんなのがあるなんて、これも時代だねぇ。僕が幼い頃には勿論、こんなもんなかったよ。これから益々、神林さんの応援しなきゃ!」
アクリルスタンドを手に握りしめたまま、片桐は年甲斐もない自分に可笑しくなり、ケタケタと笑った。
「神林さんの推し活するんだったら、それ、私にプレゼントさせて下さい」
季衣子は片桐の気持ちが変わらないうちにと、アクリルスタンドを手に取った。
「いいんですか?!パ・ド・ドゥを踊っているのと、クララに扮してるのと、どっちがいいかなぁ」
二つを手に取り、何度も見比べるが、中々一つに決められない片桐は一人唸った。
「片桐さんたら、まるで子供みたいなんだから。どちらも欲しいんでしたら、私が両方プレゼントしますから、どうぞご心配なく」
「本当に、いいんですか?!」
季衣子の言葉を聞いた片桐が、まるで子供のように季衣子の隣で両手を上げて喜んでいる。少し見上げた先に見える片桐の顔を眺めながら、この片桐が、あの久我山翔だったらどんなにかいいだろうと季衣子は思った。
今だったら片桐と過ごしたように「くるみ割り人形」を見て、こうして舞台の感想を語り合ったり楽しい時間を共に過ごせたのである。
「もう一度、久我山翔に会いたい」
気がつくと、季衣子は片桐に大人になった久我山翔の姿を重ねていた。
Ⅴ・窓越しに名を呼びて
劇場を出ると、もう街は漆黒の闇に包まれ、空を見上げると三日月が綺麗に姿を現していた。
「はい、これ。どうぞ」
季衣子は片桐にアクリルスタンドを手渡すと、
「本当に今日は、何から何までありがとうございました。片桐さんのお陰で、子供の頃からの三十年越しの夢が叶いました」
礼を言うと深々と頭を下げた。
「嫌だな、改まってやめて下さいよ。今日は僕の方こそ、チケットも無駄にしなくて済んだし、楽しい時間をありがとうございました」「いえ、本当に私の方こそ···」
何度も頭を下げ合う季衣子と片桐は、数時間前、まだ見知らぬ者同士だった時のように、終わることのない押し問答を繰り返した。
「さっきもこんなんでしたね、僕たち」
「そういえばそうでしたね」
そんな自分たちを、急に俯瞰して見た季衣子と片桐は、白い息を吐きながら大きな声で笑った。
「そうそう。それはそうと片桐さん。連絡しなくていいんですか、さっき電話で話してた、その···」
左手に結婚指輪はしていなかったが、季衣子は片桐が既婚者だと思っていた。
「あぁ、そうでした!じゃ、ちょっと失礼。出てきたばかりで何だけど、寒いからロビーにでも入っていて下さい」
そう言うと、片桐は季衣子を気遣い、自分は寒空の下、冷たい風に吹かれながらズボンのポケットからスマートフォンを取り出すと、電話をかけた。
ガラスを隔てた向こうで、それまで動かなかった片桐の口が、パントマイムのように動き出した。相手が電話に出たのだろう。
「こういう時、読心術があったらなぁ」
季衣子は片桐が一体、何を話しているのか気になった。
どうやっても分かりはしないのに、ちょっと屈んだり背伸びをしたり、体を斜めに傾けたりしながら季衣子は片桐の様子を伺った。それに気づいた片桐は、時折季衣子に笑顔を向けたり、手を振ったり、頭を下げたりして話を続けた。
電話を終えた片桐が、ロビーで待つ季衣子の元へ、腕を擦りながら走って来た。
「おぉ、寒い寒い。お待たせしました」
片桐が詫びた。
「いいえ。それより、奥さんの具合は如何でした?」
奥さんと聞いて、片桐はきょとんとした顔をして季衣子を見ると、我に返ったように答えた。
「あぁ、妻ね···」
「まだ、熱は下がらないままですか?」
何かを言いたそうな顔をしたまま、片桐はズボンのポケットに両手を突っ込み、まだ体が凍えているのか頻りに体を揺すりながら答えた。
「汗を掻いたらだいぶ楽になったそうです」
「そうですか、それなら良かった」
言葉とは裏腹に、季衣子は寂しかった。
「ご心配をおかけしました。それじゃ、そろそろ帰りましょうか。中川さんは電車?」
「えぇ、JRで上り。片桐さんは?」
「JR。僕はここから新幹線」
「えっ、新幹線?」
季衣子と片桐は黙って駅まで歩いた。駅まで歩いたと言っても、日本夢芸術劇場から駅まではものの五分足らずである。
別れの時は、刻一刻と迫っていた。
相変わらず、漆黒の街は十二月の冷たい風が吹き、季衣子の頬を痛く刺した。
駅に着くと、季衣子が口を開いた。
「私、最後に片桐さんを見送らせていただいてもいいですか?」
何か考え事でもしていたのか、それまでとは打って変わって厳しい顔をしていた片桐が、季衣子に笑顔を見せて礼を言った。それから季衣子と片桐は、再び新幹線乗り場へと無言のまま歩き出した。
自動改札を通り抜けホームに入ると、今度は片桐が沈黙を破った。
「中川さん」
「はい」
しばらく歩くと、片桐はふいに立ち止まり、季衣子に手提げ袋を差し出した。
「これは?」
差し出された手提げ袋に、季衣子が恐る恐る手を伸ばすと、片桐が言った。
「今日の公演のプログラム。アクリルスタンドのお礼です」
「片桐さん···」
手提げ袋から大切そうに公演プログラムを取り出すと、季衣子の頭に三十年前のあの日の苦い記憶が蘇った。
「片桐さん。私、こんなものもらう資格なんかないんです」
季衣子は視線をプログラムに落としたまま、声を震わせた。
「えっ、どうしてです?」
片桐が季衣子の顔を覗き込んでも、季衣子が視線を片桐に向けることはなかった。
「久我山くん···」
「久我山くんが?」
片桐が問い返した。
「私、久我山くんに酷いことしたから。だから、これは、これだけはどうしても受け取れないんです」
また二人が押し問答を始めると、片桐が乗る新幹線がもうじき発車しようとしていた。
片桐が急いで新幹線に飛び乗ると、季衣子はプログラムを片桐に押し返した。
「中川さん!」
季衣子は深々と頭を下げたまま、顔を上げようとはしなかった。
車掌のアナウンスとベルがけたたましく鳴り響くと、新幹線のドアが閉まりかけた。
「季衣ちゃん!」
片桐の叫びは季衣子に届くことはなかった。
片桐を乗せて走り出した新幹線はだんだんと季衣子を置き去りにして、やがて小さくなって消えて行った。
Ⅶ・くるみ割り人形、ふたたび
それから一年後の二〇二五年十二月、東洋バレエカンパニーが神林ひろ美を主演に「くるみ割り人形」を上演する季節がやって来た。公演を半月後に控えた日曜日の午後三時、滅多にテレビ出演などしない神林が、珍しくテレビに出演した。
マルチタレント・髙栁節子が司会を務める人気トーク番組「節子とお茶を」に、神林は髙栁からの熱烈な出演依頼を受けた。
踊ることにしか情熱を注いで来なかった神林は、自分はバレエのこと以外は世間知らずだし、おまけに口下手だからと一度は出演を断ったが、司会の髙栁から、
「引退するのかしないのか、世間じゃちょっとした騒ぎになっているから、この際、私の番組の中で、はっきりご自分の思いをおっしゃったらいかが」
という提案を受け、苦手なテレビ出演の依頼を承諾したのだった。
番組が始まると、主役を務める舞台「くるみ割り人形」の話や、自身のバレエを始めたきっかけ、世界的に活躍を始めた二十代の頃の話など、ベテラン髙栁の人柄と話術で、口下手だと公言していた神林も、この日は饒舌に自身のことを語った。
番組が終わる少し前、髙栁が神林にやさしく促すように、だが核心をついて訊いた。
「あなた、引退するって噂がまことしやかに流れてますけど、今日、あなたにお話伺った様子では、私はあなたに限ってそれはないと思いました。でも、実際のところはどうなのかしら?」
高柳の言葉に目を左右に泳がせながら、神妙な面持ちで神林は少し考えてから、髙栁の目を見て語り出した。
「これだけ長く踊り続けて参りましたけど、私にはまだ、私自身が見たいと思った景色っていうものが、まだまだ見えて来そうもないんですね。ですから、それをこの目で見ることが出来るまで、先のことなんて分かりませんけど、怪我や病気に気をつけながら、一日も長く踊り続けていきたいと思っています」
神林の話が終わるか終わらないかというところで、もう司会の髙栁が喜びを抑えきれず、拍手をしながら言った。
「まぁ皆さん、お聞きになりました?神林さんがまだまだ踊り続けるっておっしゃいましたよ。『くるみ割り人形』私もぜひ、拝見したいわ」
あと三十秒で番組が終わるという時、髙栁が神林に言った。
「最後に、ファンの方々にメッセージを」
神林の顔が、カメラがだんだんとクローズアップしていく中、
「また今年も『くるみ割り人形』に出演することになりました。皆さんを夢の世界へいざなうために、私も東洋バレエカンパニーのメンバーも、一生懸命稽古を積んで参りました。ぜひ、皆様、劇場にお運び下さいませ」
神林が頭を深く下げたところで「節子とお茶を」は無事に終わった。
この日、仕事で番組を見られなかった季衣子は、録画で番組を見た。
「神林さん、今年は大丈夫。私、もうチケット取りましたからね」
季衣子は一人、テレビの中の神林に向かって話しかけた。
季衣子は既に、日本夢芸術劇場一日限りの公演チケットを手に入れていた。座席は去年のようにSS席とはいかないが、もしかしたら、片桐がまた今年も見に来るかもしれない。いや、きっと来る筈である。
あの日、駅の新幹線のホームで別れたきり、季衣子が片桐と会うことはなかった。
連絡先を交換したわけでもなかったし、インターネットであれこれ調べはしたが、タレントでもない片桐のアカウントに辿り着くものは、何一つなかった。
季衣子が大きなため息をつくと、階下が何やら騒がしい。
「季衣子。皆さんいらしたからちょっと騒々しくなるけど、親孝行だと思って我慢してちょうだいね」
階下から美那江が季衣子に詫びを言った。
去年、季衣子との一悶着で美那江は心を改めたらしい。また賑やかなハーモニカによる「ジングル・ベル」が、今年は心地よく季衣子の耳に聴こえて来た。
東洋バレエカンパニーによる「くるみ割り人形」の公演まで、あと一週間。
それまで秋と冬を行ったり来たりしていた季節は一気に歩みを進め、本格的な冬が訪れた。
迎えた「くるみ割り人形」公演当日。
今年も神林ひろ美見たさに会場のロビーは大勢の来場客でごった返していた。
こんなことなら開場時間と同時に入場するべきだったと季衣子は思った。
こんなに人がいては、片桐を見つけられるか不安になったのである。
季衣子はロビーのソファーに座り、入り口の方をじっと眺めていた。片桐の姿を探したが、間もなく開演の時間である。
今年は去年よりも若い観客が多かった。
滅多にテレビに出演しない神林が、人気タレント・髙栁の「節子とお茶を」に出演したことも影響したのだろう。
片桐は一際背が高いから、滅多なことでは気づかないことはないと思っていたが、もう既に入場しているのだろうか。季衣子が再び用心深く、キョロキョロと入口の方を見渡している、その時だった。
舞台開演五分前を告げる館内放送が流れ出した。
気持ちが落ち着かぬまま、季衣子は座席へと急いだ。
席に着くと間もなくして、場内の照明は暗く落とされ、ピンスポットが昨年同様、オーケストラの指揮を務める山崎太一を照らした。
今年も東洋バレエカンパニーによる神林ひろ美主演の「くるみ割り人形」の幕が開いた。
山崎が指揮棒を振り、オーケストラが演奏を始めると、舞台にはまた昨年と同じように、照明による雪が降り始めた。
クララに扮した神林が登場すると、会場は割れんばかりの拍手が起こった。
神林の踊りは、去年よりも更に季衣子の胸を熱く揺さぶった。特に第二幕の「別れのパ・ド・ドゥ」は、若い頃は考えるにまで及ばなかった自らの舞踊人生が、今ではいつ終わっても不思議ではない年齢に達した神林が、毎年毎回、これがラストダンスと言わんばかりに、歳を増すごとにその気迫と惜別の思いが、このシーンには強く込められるているからなのだろうか。
神林のそんな覚悟を決めたような嘘偽りのない誠実な踊りに、季衣子をはじめ、会場に詰めかけたたくさんの観客は咽び泣くと一転、コーダでは神林の躍動感と生きる喜び、尽きぬバレエへの情熱が観客たちを華やかな夢の世界へ連れていき、感動のうちに舞台の幕が下りた。
去年と同様、観客の拍手は止むことはなく、次の瞬間、舞台の幕が上がり、東洋バレエカンパニーキャスト一同が再び姿を現した。
神林は感無量といった面持ちで、二〇〇〇人を収容するその会場に詰めかけた観客たち一人一人に、まるで礼を言うように時間をかけてゆっくりと最前列の席から二階席、三階席と全ての観客に視線を送り、美しいレヴェランスで観客の拍手に応えた。
今年も神林の踊りを見ることができた。
その喜びに季衣子が胸を熱くしていた時だった。
「ブラボー!」と叫び、最前列の座席でスタンディングオベーションをしている男がいた。目を凝らしてじっとその男を見つめた季衣子は、嬉しさの余り声を上げた。
去年一緒に舞台を見た片桐だった。
「やっぱり見に来てたんだ。しかも去年と同じ一番高いSS席で」
季衣子も座席から立ち上がり、神林と片桐に届けとばかりに「ブラボー」と叫んだが、周りの観客の熱い拍手にその声は掻き消され、二人の耳には届かなかった。
Ⅷ・再会のテーブル
終演後、感動冷めやらない季衣子は急いで席を立ち、片桐の後を追った。が、季衣子の前で折り悪く幼い女児が転んで泣き出した。母親が帰り支度をしているちょっとの間に、一人で神林を真似てぴょんぴょん飛び跳ねていたらしい。
床に転んだまま泣いている女児をやさしく季衣子が起き上がらせると、慌てて母親が飛んで来て季衣子に詫びると礼を言った。
季衣子が女児に気を取られているわずかな間に、片桐の姿はもうそこにはなかった。急いで通路に出て、人をかき分け小走りにロビーへ走ったが、片桐の姿は見当たらなかった。ソファに腰をかけ、項垂れていた季衣子の耳に、誰かが自分の名を呼ぶ声がした。
「中川さん?」
喧騒の中から自分の名前を呼ぶ声が、段々と近くに聴こえてきた。声のする方を振り返ると、そこには一年前と全く変わらない、爽やかでスマートな片桐の姿があった。
片桐の姿を発見した季衣子は、感激の余り、声を上げて片桐の元へ駆け寄った。
「片桐さん!さっき、姿を見つけたのに、私見失ってしまって。良かったぁ、今年もまたお会いできて」
「きっと今年も」と、続きを言いかけて、季衣子は言葉を引っ込めた。片桐の斜め後ろに、深紅のベルベットのワンピースに身を包んだ、抜群にスタイルのいい美しい女が立っていた。
「あっ、ごめんなさい私ったら。お連れの方がいらっしゃるのに気づきもしないで。一人ではしゃいだりなんかしてしまって···」
季衣子が詫びてうつむくと、片桐は季衣子に改まって挨拶した。
「良かった、お元気そうで」
「片桐さんも。去年のお話からして、今年も絶対に見にいらっしゃると思ってました。だから···」
季衣子が言葉を詰まらせた。すると、
「中川さん、ゆっくり食事でもしながら、また去年のように一緒に舞台の感想を語り合いませんか?」
片桐は去年と全く変わらない、季衣子を魅了する佇まいと、有無を言わせぬスマートな振る舞いで季衣子を食事に誘った。
「でも今日は、お連れの方もいらっしゃることですから、私は···」
気後れした季衣子は、やっとの思いでそれだけ片桐に伝えると、黙って下を向いた。
「もし今日、中川さんと再会することができたら、会わせたいと思って連れてきたんです。去年は熱を出して来られませんでしたけど」
それまで片桐の斜め後ろにいた女は、片桐の隣に歩み出ると笑顔で口を開いた。
「片桐灯です。どうぞよろしく」
やはり片桐の妻だった。ここで無下に誘いを断るのも却ってみっともない。第一、片桐の妻に対して失礼ではないか。そう思った季衣子は笑顔で片桐の誘いを承諾した。
片桐は去年と同様、会場の中にある喫茶店へ季衣子を案内した。
ウェイターが注文を取りにテーブルへとやって来て水を置き、注文を聞いてまた去って行った。これも去年と同じ光景だった。
唯一変わったのは、今年は片桐と自分の二人きりではないということだけだった。
片桐の隣に座る美しく、品のいい片桐の妻を季衣子は目の前にしながら、このどうしようもない沈黙を早く破りたかった。
「あの···」
意外にもはじめに口を開いたのは、片桐灯だった。
「去年は私の代わりに舞台を見て下さってありがとうございました。おかげでチケットが無駄にならずに済んだと、兄も喜んでいました」
「えっ、兄?」
季衣子は思わず聞き返した。
今、目の前にいる灯は間違いなく片桐のことを兄と言った。
「兄って。あの、失礼ですけど、あなた片桐さんの奥様じゃないんですか?」
「嫌ですわ、片桐翔は私の兄です」
「片桐翔、翔···」
「あの、中川さん」
何が何だか分からず、戸惑うばかりの季衣子に片桐が言った。
「季衣ちゃん、僕、久我山翔。小学生の時に『くるみ割り人形』の話を毎年季衣ちゃんに聞かせていた、神林ひろ美の大ファンだった久我山翔だよ」
「片桐さんが久我山翔って。そうしたら、片桐さんは誰なの?第一、片桐って名字が違うじゃないですか。やっぱり隣にいるのは奥さんで、婿入りしたとでもいうつもりですか?」
季衣子は片桐にからかわれていると思った。
片桐は隣に座る灯と顔を見合わせながら、困り果てた。
「何から話せばいいのかな。えっと、家の両親は離婚してね。僕と灯は母に引き取られて、それで母の旧姓である片桐を、今もそのまま名乗ってるんだよ」
そう言っても尚、まだにわかに信じがたい顔をしている季衣子に、片桐は胸の内ポケットから小さな袋を取り出した。
その袋から大事そうに片桐が取り出したのは、一個の古びた雨蛙のキーホルダーだった。所々、色が剥げかかっているそのキーホルダーは、季衣子が三十年前、家族旅行に一家で出掛けた際、
「季衣子が毎日、無事に家に帰って来るように」
と、験を担いだ父の孝也が季衣子に買い与えた物だった。
翔と喧嘩したあの日、仲直りに渡そうと季衣子が持っていたキーホルダーである。
目の前に差し出された雨蛙のキーホルダーに、ためらう季衣子の白く細い手が伸びた。
「これ···」
季衣子の脳裏に、五年前に他界した孝也の顔が浮かんだ。
口数の多い父ではなかったが、このキーホルダーには不器用ながらも娘を愛する、孝也の愛情が目いっぱい詰まっていた。
「それじゃ、片桐さんは本当に久我山くんなの?」
問いかけたところで、季衣子にもう一つ、大きな謎が浮かんだ。
翔に謝りに行ったあの日、久我山の家は留守で、翔には会えなかった筈である。
「このキーホルダー、翔くんに渡せなかったから、そのまま家に持って帰って来た筈なんだけど」
キーホルダーを手にしたまま、季衣子が考え込んでいると、翔がヒントを与えた。
「季衣ちゃん、覚えてないかな?家にさおりさんってお手伝いさんがいたの」
季衣子はすっかり忘れていた。
さおりさんと聞いて、三十年前の遠い昔のあるシーンがピント外れのまま、季衣子の頭に蘇って来た。
あの日、季衣子はさおりと会っていたのである。
おっちょこちょいだったさおりは、あの日、十四歳の時に死別した母の形見のブローチを、部屋の机の抽斗に忘れて、どうしてもそれだけは取りに行かせてくれと、主人である翔の父に泣いて頼んだ。
翔の父はそれどころではないと怒ったが、さおりの母親代わりでもあった翔の母が翔の父を説得し、わずかな時間、さおりはこっそり翔の家に戻っていたのである。そんな時、タイミング悪く季衣子が家のベルを鳴らしたのである。
ドキッとしたさおりは居留守を使って季衣子が帰るのを見届けると、急いで家を出たが、家へ帰った筈の季衣子が何を思ったのか、もと来た道を引き返して来たという。
季衣子とばったり会ってしまったさおりは、なぜ翔は家にいないのかしつこく訊かれて困った揚げ句、咄嗟に旅行に出かけたと口から出任せを言った。
嘘を言った手前、季衣子が気の毒になり途中まで一緒に歩きながら、季衣子の話を聞いてやったのだった。その時、季衣子からこのキーホルダーを翔に渡してくれと、今にも泣きそうな顔で頼まれたというのである。
さおりが快く預かると、季衣子は安心したのか、顔を綻ばせ帰って行ったという。
一度は郷里の祖父母の家に帰ったが、ほとぼりが冷めた頃、片桐親子と再会を果たしたさおりから、翔はこのキーホルダーを渡されたのだという。
「これで、やっと信じてもらえたかな」
「それじゃ、本当に翔くん?」
「疑り深いなぁ、季衣ちゃんは」
翔は、再会から一年、やっと正体を明かせたというのに、浮かない顔をしている。
「どうして、私だって気づいた時に言ってくれなかったの」
季衣子はこの一年間、どんな思いで過ごして来たか、翔に切々と訴えた。すると、翔は目をクリッとさせておでこに三本シワを寄せると、おどけたように言った。
「親の都合とはいえ、夜逃げなんてかっこいい去り方じゃなかったから。今になって何もなかったように、昔の同級生面して季衣ちゃんに顔を合わすのが、本当のところ後ろめたかったんだ。さよならもありがとうも、何も言わずにいなくなっちゃったからさ」
抱えていたすべてのことを、季衣子に打ち明けることのできた翔のその顔に、もう一点の曇りはなかった。
「だけど、同級生の僕の顔見て、季衣ちゃん分からなかった?」
「分かるわけないでしょう。だって、あれから三十年よ。それなら私も訊くけど、翔くんは私のことどうして分かったの?」
間髪を入れずに否定された翔は、思わず吹き出したが、季衣子だと気づいた理由を、わずかな自信と期待を込めて話し出した。
「匂いだよ。季衣ちゃんの匂い。いつもいい匂いがしてただろう、スイカの。気づいてなかった?」
季衣子はドキッとした。
「授業参観に来た時、季衣ちゃんのお母さんも季衣ちゃんと同じスイカの匂いがしてたんだ」
季衣子の匂いの正体は、長年、美那江が愛用している香水だった。
ませていた季衣子は、美那江の大事にしていた香水を、美那江に隠れてつけていたのである。
「僕が去年、あの日。ベンチで季衣ちゃんの隣に座った時、フッと僕の方に風が吹いたんだ。その瞬間、何か懐かしい気持ちがしたんだ。それでその後、一緒に『くるみ割り人形』を見ただろう。そしてその帰り、喫茶店でお茶しながら話していた時、僕と同じような同級生の男子生徒の話になった。それで帰り際、僕がプレゼントしたプログラムを受け取れないって、僕に突っ返したじゃないか。まさかとは思ったけど、あの時、多分、きっと季衣ちゃんだなって」
「でも私、翔くんに酷いことした」
季衣子には三十年経っても消せない、それは苦い記憶である。
「だから去年、僕は言ったじゃないか。はじめから怒ってなんかいないって」
「本当に翔くん、怒ってないのね?」
「怒ってなんかいないさ」
「あのプログラム、私、今も大事に持ってるの。辛かったけど、私、ずっと持ってたの」
「僕も、季衣ちゃんがくれた雨蛙のキーホルダー、ずっと持ってたよ。あっ、そうだ!」
思い出したように、翔がもう一つ、季衣子の前に袋を差し出した。
「これ、去年のプログラム」
「これはもう、受け取ってくれるよね」
「ありがとう、もちろんよ」
季衣子は翔の目の前で、去年のプログラムをパラパラと捲った。
「神林さんのお陰で、また翔くんと再会できた。神林さんが今も踊ってくれていなかったら、私たち、こうして再び会うことはあったのかしら?」
プログラムから視線を翔に移すと、季衣子は人生の不思議をしみじみと感じずにはいられなかった。
「そうだ、季衣ちゃん。このキーホルダー、季衣ちゃんに返すよ」
翔は、差し出した季衣子の手のひらに、キーホルダーをそっと握らせた。
「親父さんからもらった、大事なキーホルダーだったんだろう?」
「翔くん」
「僕は、無事、季衣ちゃんの元に帰って来られたから。もう、このキーホルダーは持ってなくても大丈夫」
「翔くんたら、上手いこと言うのね」
ケラケラと楽しそうに笑う二人を横目に、窓の外を見た灯が「あっ」と小さな声を上げた。
灯の声につられて外を見ると、雪がパラパラと降り始めていた。
「このまま降り積もっちゃうと帰るの大変だから、兄さん、私先に帰るわ。それじゃ、季衣子さん、兄をお願いしますね」
帰る口実を探していた灯は、これを逃すまいと急いで席を立った。
「おい、灯」
「兄をお願いしますねって···」
戸惑う二人を置き去りにして、灯は店を後にした。
「素敵な妹さんね」
「まったく、いい大人をからかって」
それまで賑やかだったテーブルが、しんと静まり返った。
「灯さんの言う通りだわ。私たちも帰りましょうか」
季衣子が椅子から立ち上がると、翔は冷めたコーヒーをゴクリと飲み干し、次の瞬間、引き留めるように翔は咄嗟に季衣子の手を掴んだ。
「もう少し、もう少しだけこのまま···」
いつも冷静な翔の心の乱れに季衣子はドキッとしたが、何も言わず静かに頷いた。
我に返った翔が、季衣子の手を離そうとしたが、今度は季衣子がその手を離そうとはしなかった。
再び席に座ると、二人は言葉も交わさず、しんしんと降り続ける雪を、時が経つのも忘れていつまでも眺めていた。
はじまりのパ·ド·ドゥ
この小説の構想は2001年から始まっていたことに、今年になってやっと気がつきました。
人生は1分、1時間、1日、1週間、1ヶ月、1年、10年と数字で区切られてはいますが、全ては地続きなのです。
そのことに気づいた今、私は自画自賛と笑われるかもしれませんが、この小説に非常に愛着を感じています。
多くの方に読んでいただけたら、どんなに嬉しいかしれません。