
雑種化け物譚❖Cry/A. 完結篇
12月中旬から掲載しているCry/シリーズC零Aの本来の完結篇です。不定期公開です。
A初話→https://slib.net/121266
手背に「Z」を刻む化け物の国で生まれ、飛竜と人間の混血である青年がやがて英雄になるまでの伝奇ファンタジー。
それと知らず「力」を視る心眼を持った飛竜の青年は、ある事情で存在を隠す双子の弟や、「千里眼」と呼ばれる同郷の女性、そして竜の血をひく娘達に関わったことで、永遠に消えない憎悪の火――「赤の鼓動」をその身に宿していく。
update:2024.1.25-2.29 Cry/シリーズzeroA 中後篇
※エブリスタでは一作にオマケ話が集中しています
中篇・序
その日その時、沢山の誰かの運命が変わったこと。
誰が本当に、命の重さという願いの意味を知っていただろう。
「――」
争いを続ける二つの国の、中立地帯であった聖域で。
振り返った女の胸を、正面から一瞬で、凝縮された水の槍が貫いていった。
「あ――……」
どんな化け物の力も、通すはずのない女の鎧。それを貫いた流水が弾け、地に還った直後に、女はふわりと仰向けに倒れ込んだ。
女の過ちを裁くべく、場に現れた化け物の姿。
「……うん……わかってた、よ」
赤く染まった女は、己の咎だけを伝え、短い生を終えた。
「アナタに……いつか、殺されるって」
その玄い水の主――純粋な化け物の力だけは、赤い鎧に通じる。何故ならそもそも、鎧の力はその化け物のものなのだから。
だから殺意は当然のこと。そうして化け物の力を奪った、人間の女の過ち。
誰かの希みが、永遠に失われたその日。
化け物の国と人間の国の、長い暗闇が始まる。
+++++
「ピアはもう……五年は家族に会ってないはずよ」
「……?」
少し前に、第一峠という雪山に居を置く大使を待つ傍らで。ある人間の女について、同郷の女性が化け物の青年に一つの話をしていた。
青年は第五峠という、ある中立地帯の大使館を守った。そこで共に戦った人間の女について、幼い頃から姐貴分な女性は語った。
「お父様がまず亡くなって――その後に、お母様から絶縁状を叩き付けられて。ピアが家族と暮らせたのは、三年程しかない」
人間の女は三歳からこの国の旧王城で、軍人とするために鍛えられた。しかし化け物とは違い、「気配探知ができない弱小者」と、十歳で親元に帰された。その三年後に絶縁されたという。
そしてつい先刻に、短い生をあっさり終えたその人間は――もう二度と、家族との時間を取り戻せることはない。
その人間の女の、妹を知る青年は、深く項垂れる。
人間の女が絶縁された経緯は、知り合いの国王からもうっすらと聞いた。
「あの人間は……そうしなければいけない咎人なのだ」
その時それは、彼の咎でもあると言わんばかりの沈痛な声色だった。
「それを己に許せるような優しき国で、生きていないのだ」
まるで罰と言わんばかりに、その国王も、人間の女が生を終える瞬間を目の当たりにする。
そうして、ある咎が形を成した化け物から、幾人ものヒトが裁きを刻まれる――
+++++
中篇・起
――間違いありません、と。金色の髪を揺らがせる一国の王女が、悲しげに口にした。
生来の柔らかさを消し、厳しさを潤ませた赤い目が悲痛に澱む。
「その客人が連れていた子供が……我が国で発掘されたはずの、古代の鎧を貫いた力の持ち主です」
「……」
第五峠の大使館に一人でいた青年は、全ての事が起きてから、結果だけを突き付けられていた。
事の次第を把握するため、まずはこの場所に来ることになった理由――記憶を黙って辿る。
現在、青年がいる第五峠ディレステア大使館という場所は、青年の出身国のゾレン領だ。世界の秘境の一つ「地の大陸」において、化け物の国ゾレンと人間の国ディレステアは長く冷戦を続けている。第五峠は両国の国境であり、中立地帯と定められた唯一の地域となる。
話しているディレステア第二王女は、第五峠ディレステア大使館に常駐している。悲願である和平の実現に向け、ゾレンの「五色のケモノ」という不戦派組織の青年と協力してきた。青年は沢山の力を借り、第五峠での和平交渉の設定にまでこぎつけていた。
ところが和平交渉を目前に控えて、突然峠を、幾重もの大洪水と、人間による連続爆破事件が襲った。そのため否応なく、王女と青年が設定した和平の場は白紙となってしまった。
「見慣れないその客人は、先日からゾレン大使館に滞在していました。ゾレンの王族であると申し出がありましたので……和平交渉についても、この峠で行うとお話してありました」
「それならその客人の王族が……第五峠であれだけの惨劇を起こして、和平を妨害した黒幕ということですか」
「おそらくは。でも――……確証がありません」
「……洪水を起こしたのは……王族の連れの子供だとしても?」
「我々人間には、それが証言できないのです、ライザ殿」
辛そうに王女が目を伏せる。確信があっても証明できないことは同じである青年は、それ以上何も言えなかった。
数々の爆破を起こした犯人は、ゾレン在住の人間達だった。ディレステア人の人間ではなかった。
そのゾレン人達は、第五峠には敵国の悪魔が存在すると信じ込んでいた、「悪魔祓い」を名乗る人間の集団だった。
「洪水を起こした悪魔を討伐に来た、と。検挙された者は全員、そう証言していると、騎士団からは報告があります」
「……それで、悪魔を祓うために、あれだけ町を破壊したと?」
第五峠が中立地帯とされている理由は、両国の病人を抱える医療施設が集中するからだ。そんな地域で起きた惨劇は、それでなくとも物資不足に悩む町への大打撃となった。
洪水や爆破事件による負傷者が溢れながら、満足な治療も受けられない凄惨な状況が現在だった。
その混乱の中、ディレステア王女は惨事の元凶だと罪を擦り付けられた。そのため王女の拠点たる大使館は、「悪魔祓い」を名乗る人間達に占拠されたのだ。
「貴方がたのご協力でこの大使館を取り戻せたことを……本当に、感謝致します」
「…………」
和平の場として重要な第五峠で起きた洪水。原因を巡って峠に来た青年と、青年の連れ二人の助力で、大使館は大過なく奪回されていたが。
「ピア・ユークのことは……とても、残念でした」
「……――……」
その連れの一人、人間の女がつい先刻、命を落としたという。
人間でありながら、古代の鎧を使う女は化け物を上回る強さを持っていた。その死を未だに信じられない青年に、静かに現実を突き付けるように……場に立ち会った王女が、俯きながら伝える。
「ピア・ユークを殺せる力を持ち、部下殿にも重症を負わせた化け物達について……私が見たことを、全てお話し致します」
まだ成人前でありながら、気丈な声色には隠しようのない気品と勇気。柔和さと意志の強さを両立させた、赤い目が見た事実を、王女は厳然と語り始めたのだった。
その布陣は、化け物より強いと言われた人間の女にとっては不本意だった。
王女の守りについた人間の女は、元は占拠された大使館に乗り込む気だった。しかしどうしようもない誤算がそこにはあった。
「本当……すっかり忘れてたなー……」
「――?」
人間の女の溜息に、ディレステア第二王女は目を丸くする。
自国の大使館奪回に力を貸すと言った敵国者を信じ、指示通り、王女は山中の大使館から少し離れた岩陰で息をひそめていた。
「人間の敵は、人間ってことかなー……この鎧、化け物の力は何一つ効かないのに、銃は当たるってどういうことだろ?」
女が纏う赤い鎧は、胸に漆黒の珠玉を填める古代の秘宝だという。その鎧を纏う限り、化け物並みの身体能力と、どんな化け物の力も弾く見えない壁を得ることができていた。
「占拠してる奴らが、ほとんど人間だなんて。それじゃあたし、あんまり役に立てないじゃないの」
「なるほど。それで、大使館に乗り込むメンバーが貴女からライザ殿に変更になったのですね」
「うん。あたしはリミットと一緒に、王女様を守ってくれって言われちゃった」
傍らに、ひたすら黙って部下の男が控える。大火傷を負った顔をほぼ包帯で隠し、一見は十代後半とみられる者の肩を叩きながら、人間の女はただ苦笑した。
自身が戦うつもりだった人間の女は、好戦的というよりは、ただ戦闘が得意な身の上らしい。
「本当、大丈夫かな。リーザはともかく、ライザは化け物とはいえ頑丈じゃなさそうだから」
「しかし……お二人は双子であるとお聞きしましたが?」
「そうなんだけど。さっきライザが説明した通り、リーザはライザの操る『飛竜』……ライザの一部って言って育てられたくらい、生粋の化け物なんだけど」
青年は最強の獣と言われる「飛竜」の名を継ぐ。しかし双子と力を分けて生まれてしまったようで、どちらも不完全な化け物と言えた。
「お母様が人間だから、なのかな? リーザは飛竜なのに炎を吐けないし、ライザはまず飛竜になれないんだって」
双子の弟は、ヒトの姿から羽を持つ四足の獣に変化できる。兄である青年はいくらか炎が使えるだけで、ヒトの時でも頑強な弟とは違い、身体の強さも一般的な化け物と変わらない。
「その分、妙な特技はあるみたいだけどねぇ……こう、銃弾とか飛び交う中で、役に立つかは微妙だし」
心配の理由がある程度わかった王女は、そこで深く頷いていた。
「それは……とても心配な事柄ですね」
何故なら、と、王女自身の懸念も先に続ける。
「その上、双子という身上は隠さなければならない、と仰っておられませんでしたか?」
これまで王女は、青年に双子の弟が存在するとは全く知らなかった。隠し立ての理由と存在を明かされたばかりだ。それなら青年は、瓜二つな双子――適度に尖った銀髪で灰色の目の弟と、人前で共に戦ってはいけないはずだった。
「そう。だからリーザは、魔法で自分の顔を隠してるみたい」
「あらまぁ……それは、便利な特技をお持ちですね」
飛竜に変化できる弟は、頑強さと共に「魔道」の心得まで持つ。まさに、最強の獣の名に恥じない実力者だった。
「でもその魔法を使うせいで、他の大きな魔法は同時に使えないから。武器でしか戦えないんだよね、リーザも」
兄と同じ場にいる時は、弟にもそうした枷が課される。それを人間の女は教えられていた。
そのような弱味を背負い、大使館へ乗り込んだ双子の兄弟が、人間の女はひたすら心配のようだった。
「相手はたかが人間で、数も知れてはいるみたいだけど……」
あたしも手伝いたかったなー、と。そればかり女が緊張感のない軟らかい声で口にするので、王女はついつい、
「それで貴女は……どちらの方と良い仲なのでしょうか?」
そんな女子会話を出してしまうくらい、待機組はしばらく平穏そのものだった。
「…………」
青年は、その時女が答えたという台詞に、ただ灰色の両眼を歪める。
人間の女の見立て通り、その頃青年達は、いくらか苦闘していた。
「なかなかいい銃、持ってやがるな。魔法なしだとちょっときついぜ」
双子の弟は、両端に短い刀身がついた棍を武器とする。銃弾程度で致命傷には至らない頑強さを持っているが、あまり多くを受けると動きは鈍ること、何より大事な上着が破れる、と嫌がる。
「ああ。思ってたより、時間がかかるな」
短刀と炎を主な武器とする青年にも、飛び道具での遠隔攻撃は厄介だった。
「まるっと焼き払っていいなら、早いと思うけど」
「あのな。それならオレも、とっくに飛竜やってるっての」
大使館を崩壊させかねない化け物の力を、双子の兄弟は抑えて戦う。地道に敵の人間を、少しずつたたむ方針をとっていた。
時間の問題の館内の敵より、謎の気配を、気配の探知に長ける双子の弟が不意に感じ取った。
その大使館がある低い山を登り、近付きつつあった強大な気配――
「――あァ? 何だ……コイツら」
「リーザ?」
青年は気配探知があまり得意でなく、情報収集は視覚に依存する部分が大きい。なのでその脅威の意味にはさっぱり気付けなかった。
「何か強い化け物が、少なくとも二人、近くに来てるぜ」
事も無げに言った双子に、そうか、と頷くことしかできない。
「化け物相手なら、万一王女が見つかっても、ピア一人で十分たたんじまえるだろーが……」
最強の獣と言われる弟と、対等に渡り合える人間の女の強さ。それを知っていた弟は、冷静にそう見立てていたものの。
しかし何かそこで、言い知れぬ悪い予感を持ったのか――それまで共に戦っていた青年の方へ、気まずげに振り返った。
「多分知り合いの気配だけど、まだ他にも強いの一つがいるし。こっち――任せていいか? アニキ」
「ああ。元々ここは、俺一人のつもりだったし……リミットを護衛に専念させたら、最悪ピアは、三対一だろ」
それはさすがに大変だ、と、青年も即決で双子をそちらへ送ることにしていた。
そしてその後――単身で大使館を奪回した後で、双子の負傷という信じ難い事態と、女の部下の重傷。そして女の死という有り得ない結果を、青年は伝えられることになる。
「謎の二人の化け物は……麓から大使館に帰って来たゾレン王族の客人と、客人の男が連れていた幼い子供でした」
男は王族にしては庶民的な恰好で、癖の強い短い茶髪の、整った顔立ちらしい。その連れは幼いながら祭祀のような儀礼服を着て、黒く短い髪で青い目の、十歳未満らしき男の子供だという。
それらがゆっくり、二人で山を登ってきたのだ。
「彼らの姿もまだ見えない内から、ピア・ユークは突然、全身を強張らせました。厳しい目をして、わたくし達に、岩陰から決して動かないように言い付けて、山道に出て行きました」
人間の女は、化け物のような気配探知の力は持たなかった。ただ直感という、曖昧だが的確な虫の知らせが存在していた。
「今思えば……化け物の正体に、その時点で気が付いておられたのでしょう」
そもそも人間の女は、峠を襲った洪水の正体を求めて峠へ来ていた。
大使館にいた王族の男が、第五峠に用があると言い、共に連れていった子供。その子供こそが、水脈を司る化け物の力を振るい、峠に大いなる天災を呼んだことを、既に気が付いていたのかもしれない。
「二人の化け物とピア・ユークが、山道で巡り会う直前に……大使館の方からリーザ殿が、麓からは最後の一人の化け物が、全員場に現れたのです」
一人出て行った人間の女が気になった王女は、女の部下を連れてこっそり後を追った。そこで明らかになる、最後の来訪者の姿に驚愕することになる。
「最後の一人……その姿は間違いなく、現ゾレン国王、トラスティ・レオンでした」
そうして山道に、青年の双子と人間の女と、ゾレン国王が直線的に揃った時だった。
「その直後に、ピア・ユークは……リーザ殿とゾレン国王の目の前で、幼い子供が放った力に胸を貫かれたのです」
それはまさに、王女が場についた瞬間でもあった。
――来ないで、と。
双子の姿を目にした時に、それだけ女は、小さく叫んだと言う。
「これは……あたしの――……」
そして女が、二人の化け物へと振り返った瞬間。
「……は――?」
双子の目前で、どんな化け物の力も通さないはずの鎧を、杙のように凝縮された水の槍が突き通していった。
「ピア……!?」
衝撃で体が軽く飛ばされ、引きずり痕を残して倒れた女の姿。
頭が真っ白になったような双子は、王女にも気付かず、ただ必死に駆け寄っていた。
「おい、ちょっと……! 待てよ、こんな――……!」
双子の腕の中で、人間の女は既に目を閉じていた。
抱える両手がぐしゃぐしゃに赤く染まっていく。取り返しのつかない速さで命が零れ落ちている。それだけはわかった様子だった。
声も無く人間の女を凝視し抱き締めていた。それはまるで、止血にすらもならなかった。
言葉もほとんど残さず事切れた女の姿に、部下の方も、命じられた護衛を一瞬で忘れていた。
「リー……ダー……!!!」
頭に血が上ったように場に飛び込む。人間の女を貫いた力を放った子供に対して、幼い懐に錐型の短剣を突き立てようとした。
「……そんなの効かないよ。……脱落者」
子供は幼子らしからぬ凛とした青い目で、自分を狙う相手を、女を貫いたものより細かく数多な水の刃で弾き飛ばしていた。
「――!! リミット!!」
その姿に気が付いた双子は、ようやくそこで己を取り戻したようだった。
「て……めぇ――……!!」
飛竜の縦型の瞳孔が開く。兇獣の双眸が双刃の棍と共に血走る。
幼い子供相手に全く容赦なしに、上段から斬りかかる形で飛び込んでいったが。
「来るな――……野蛮人」
刃が子供に届く直前、子供の周囲の地面から、何本もの熱された水の槍が立ち昇った。それが子供の最も得意な「力」のようで、魔道に長ける双子をもそこで弾き返していた。
「……――!!」
本気の攻撃を防がれた上に、頑強な身体に双子は負傷を受けた。ようやくそこで、その子供の脅威に真に思い至る。
「まさか……――ウソ、だろ」
双子と違い、女の部下は起き上がることもできない重傷を負った。ちょうど足元にいた紅い目の部下を、跪いた状態で抱えながら双子は絶句する。
その双子と対極の位置で、茫然としていたゾレン国王も、思わず呟いていた。
「……本物の『竜人』が……現れたか――」
幼い子供と、それに付き添う王族の男を国王は見やる。
旧知である人間の女が貫き飛ばされた時から、国王はずっと立ち尽くしていた。
「……何と……いう、ことを――……」
王たる理性で、彼は全ての衝撃を噛み殺さんとする。
険しさだけをのせた顔で、幼い子供の傍に立っている、並々ならぬ因縁のある王族の男を凝視していた。
「ダウテッド。貴様――……何を考えている」
どちらも王家であるが故に、目前の王族の名前をしかと口にする。そしてその因縁は、あっさりと明らかになった。
「兄者こそ。国王たるアナタが、何故このような地へ?」
王族の男はニヤニヤと、整った顔立ちでなければ下衆にしか見えない微笑みで、国王へと向き直った。
「ボクはただ、可愛い臣下の仇敵がいたので、討伐しただけですよ?」
そうして王族の男は、息を引き取って倒れている女の横に立った。
「――てめぇっっ!!?」
王族の男が、女の亡骸をよっと抱えた。双子は女の部下を離し、瞬時に斬りかかろうとしたが、隣の子供が再び地中から熱水の槍を呼び起こして阻む。
「よしよし、それでいいよ。君はよくできた子だね、デュラ」
肩に担ぐ形で女を抱え、空いた手で王族の男が子供の頭を撫でる。きらりと一瞬、男の手元が光ったように王女には見えた。
「君を売った悪魔のような姉上は、これで成敗することができた。後はもう、君のものになるはずだった力を、取り返すだけだ」
「……」
そのために、女の亡骸は彼らに必要なのだと、王族の男は子供に言い含めるかのように笑う。子供は人形のように冷淡な顔で、頷きもせずに従う。
そして更に、女に纏わるある真実を、王族の男が言及する。
「ところで兄者。この女とは知り合いですか?」
「…………」
沈黙を守る――口を開くことができない国王に、王族の男はにやりと微笑む。
「ゾレン西部を預かるボクの見たところ、この女……この赤い鎧は、西部の国賊『子供攫い』首謀者が身に着けている物と、何やらそっくりですよ?」
王族の男が管轄する西部の軍。「子供攫い」とは、その軍と敵対する国賊集団だった。
「第五峠に悲劇をもたらしたのも、もしやこの女では?」
臣下を通じて人間の女を殺めたことを、笑顔で話したその王族。法の秩序の元、大義がない限りヒト殺しを禁ずる国の王が、厳と反論する。
「――貴様はただの、前王の『王属』に過ぎない」
国王は瞬時に、剣山の厳しさを両目に湛えた。
「中立地帯たるこの第五峠においては、何一つの権限もなく――その女が何者であれ、裁く権利もない。身の程を弁えるがいい、うつけ者」
「ひどいなぁ。腹違いとは言え、実の弟に向かって」
「西部とて、軍が独断で貴様に従事するに過ぎない。どちらが国賊であるか、ここで明らかにしても良いのだぞ」
第五峠を中心に、東西に分かれた国土において、旧王都のある西に王族の男は拘っている。東を重視した若き国王が即位したのは一年前であり、東に遷都して日も浅い。
そのためこうして、まだ派閥をまとめ切れておらず、西に東に走り回る日々だった。
前王の嫡子。王族にして、前王の腹心である「王属部隊」である男。それはとても、前王を嫌う双子の弟には聞き逃せない内容だっただろう。
子供に牽制され、片膝をついたまま動かなかった双子が、二重の憎悪を燃やして王族の男を見た。
「その女を――離しやがれ……!!」
「――ん?」
王族の男はその双子の姿に、女を抱えたまま何やら首を傾げる。
「君は……ボクと何処かで、会ったことがないかい?」
「――」
ふっと、虚を突かれたように双子は、蒼白に声を呑んだ。
「前王の王属」に対して激した感情は、そのままそっくり、ある警鐘へと変わったのだ。
双子は「存在しない者」だ。これまでずっとそう生きてきた。それはひとえに「前王の王属」――「子供狩り」から青年を守るために。
「何処だったかな。確かに君には、覚えがあるんだが」
何処で見られたのかはわからない。しかしそれを王族の男が思い出してしまった場合、双子が守り続けてきた切実な嘘が、白日に晒される可能性に思い至る。
正体を明かすわけにはいかない。そのあまりの重さに、黙り込んでしまった双子を目にして、事情を知る国王が再び王族の男を睨みつけた。
「何処へなりと行け。その目障りな姿を我が前から消すがいい、ダウテッド」
「おや? いいんですか、兄者?」
相変わらず王族の男はにやにやと、肩に担いだ女の身体を横目で見る。
「この女の亡骸は――ボクがいただきますよ?」
「……――!!」
黙る国王より、すぐさま双子が、意識の無い部下を置いて場に飛び出そうとしたが、
「構わん。その抜け殻は、貴様らの役には立たん」
鉄の理性で国王は口にし、そのまま双子をも睨みつけた。
まず双子が、これ以上目立ってはいけない。それはあえて口にせずに、視線だけで国王は伝える。
「その者を放置すれば命に関わる。貴様にはわからないのか」
「――」
「一刻も早く手当してやれ。あの人間もそれを望むだろう」
厳し過ぎた国王の眼光には――おそらく唯一。
その時の双子を止められるだろう、同じ種類の痛みが満ち満ちていた。
「……――……」
放り出しかけた女の部下を、双子は崩れ落ちるように、膝をついたまま力無く抱えた。
人間の女を抱え、去りゆく化け物達の後ろで、そのまま黙って俯く。
そこにはどれだけ大きな敗北感があっただろう。あの不敵な双子が、周囲にそんな無様な姿を晒すこと自体、青年には信じられなかった。
たった一つの嘘を守るために。深追いを抑え、全ての言葉を失った双子に、国王も痛ましい視線を後に向けた。
「……おそらく、時間はかかるが。あの人間は必ず、私が探し――……貴様らの元へ帰す努力をすると、ここで約束する」
国王がとても信頼する青年の、双子である者。同じ痛みを持った者へ、最大限の憐れみと誠意。
そうして、その長い暗闇の始まりを、国王はそこで告げていたのだった。
「それで……リーザはリミットを連れて、峠の病院へ?」
青年は途中から顔を上げられなくなった。俯いたまま、王女が語る事の顛末を聞き続けていたが、王女も力無く頷いていた。
「トラスティは……そのまま、王都へ帰ったのか?」
「……はい。とてもではありませんが、わたくしも名乗り出て、声をかけられる状態ではありませんでした」
「それは当然だ……あんたに何もなかったのが僥倖なくらいだ」
普段の青年は、無骨な無表情ながらも声色は優しく、もう少し丁寧な口調で話す。全てが終わった後に、沈痛な面持ちで大使館に現れた王女には、衝撃を隠せなかった。
――早いところ終わらせて。みんなで、里に帰ろう。
つい先程口にした、当たり前のような自身の言葉。それが最早叶わないことを、押し付けられるままに、黙って呑み込むしかなかったのだ。
+++++
川という川の大洪水に続き、爆破事件が相次いだ第五峠では、どの医療施設にも負傷者が溢れ返っていた。
「――物資が足りねぇ。ろくに手当もしてやれねーよ」
知り合いのいる施設に双子の弟はいた。重傷の部下を連れていき、応急処置だけ受けさせたという。
「オレなんて全然軽傷だしな。ちょっくら里に帰って、救援物資のことでも『五色』に相談してくるぜ」
重々しい面持ちで現れた青年とは対照的に、王女から聞いた話が嘘のように、双子はけろりと青年を出迎えていた。
「……リーザ?」
青年が属する「五色のケモノ」には、双子とはいえ本来弟は関係が無い。そのためにも青年は怪訝な顔をする。
青年の重い顔の理由を、忘れたわけではないと、双子は簡単に話題を変える。
「サライの奴にも言わないと駄目だろ。アイツらのリーダーは、もういませんってな」
先刻死んだ人間の女。それが首領だった「子供攫い」というお尋ね者が、彼らの里には秘密裏に潜伏している。重い役目を事も無げに、双子は自分が請け負うと宣言していた。
そうした双子のあまりの屈託のなさに、逆に青年は、いっそう気分が重くなった。
「……本当に……ピアは死んだのか、リーザ」
彼らの知り合い――姐貴分である同郷の女性がいる病室の外で、俯きながらそれを尋ねた。
「ああ、死んだよ。キレイさっぱり、ここからいなくなった」
自らの腕の中で女を看取った双子は、それは間違いないと断言する。病室にいる女の血縁に聞こえないよう、声だけは潜めて言った。
「あの妹にそれを伝えるのは――ライザに任せたぜ」
「……」
淡々と、それは青年の役目であると現実を突き付ける。青年が顔を暗くする最も大きな理由は、それだと言いたいかのように。
「わかってる……元はと言えば、ピアを巻き込んだ俺のせいだ」
青年は和平を目指す「五色のケモノ」の真リーダーとして、ディレステアの王女を助けると決めた。人間の女は本来、その事件に関わりはなかった。
「何言ってやがる。『五色』を手伝うと言ったのはピアの方だ。それはサライの目的にも沿うし――大体、ピアを殺したのは大使館の奴らじゃねぇよ」
「…………」
青年とは対照的に、顔を上げ続けている双子には、青年もこれまで見たことのない強い眼光が宿っているように見えた。
「デュラ・ユーク……ピアやその妹より『竜人』の血の濃いクソガキを、『子供狩り』のクソ野郎が手なずけたのさ」
「子供狩り」。前王の統括していた西部の軍を指し、青年と双子を縛る長い嘘のきっかけとなった集団の俗称。「子供攫い」とは対極に位置する制度を今もこなす王属部隊について、双子はただ忌々しげに、吐き捨てていた。
長い憎悪の相手に、更なる怨恨が加わった。それだけだというように。
死んだ女の妹と、女の仲間で青年達の同郷者の女性がいる病室。双子が場を後にしてからも、青年はすぐには立ち入る覚悟ができなかった。
「……ひどい怪我だな……」
搬送者のあまりの多さに、施設の隅で寝かされるしかなかった部下の方へと先に向かった。袋小路の廊下で、硬く閉じられた紅い目の包帯男の横に、青年は坐し続けていた。
「…………」
ずしん、と。先程から何度も地震のように――第五峠広域に、何処からか伝わる衝撃の波が、横たわる部下の包帯を揺らす。
その紅い目の部下は、青年が最初に会った時から、大火傷後の顔を包帯で覆い、紅く光る片目だけを見せた姿だった。
あまりに痛々しく、そして醜い異形の姿。それを一時的な護衛と傍におかれた人間の王女は、全く恐れる様子を見せなかった。
――第五峠にいらっしゃい。そんなに大きな火傷の痕を、ずっと放っておくのは良くありません。
峠に常駐し、多くの医療施設を日々訪問する慈悲深き王女。むしろ愛しげに、主たる者の気遣いも拒み続けた部下に、躊躇なく微笑みかけていた。
――リミットは自分にも他人にも厳しいしねぇ。
紅い目の部下は元々、「子供攫い」たる女の正体を偶然知った青年を監視していた。青年が口を滑らせた時には殺すために、姿と気配を透明にする能力で青年に付き纏い続けていた。
「でもやっぱり……十歳には、とても見えない」
一見は十代後半の、化け物としては十分成熟した姿。その内実はまだ年端もいかない少年であると、人間の女から青年は聞かされていた。
「脱落者……か――」
ゾレンとディレステアが冷戦を続けるために、二人以上の子供がいる家からは、第一子を強制的に徴兵する制度がある。それが俗称「子供狩り」で、女も部下も元々徴兵され、ゾレン西部の旧王城で軍人として鍛えられた経緯があった。
しかし、一定の基準に満たなかった人間の女や、訓練の中で全身に火傷を負い、使い物にならなくなった化け物は「脱落者」として、軍に送られることはなかったのだ。
「リミットの親は……引き取りを拒否したんだっけな」
そうした脱落者は、家に帰されるか、旧王城で働くことになる。働くこともできない重態だった少年は、周囲の者から、役立たずやゴク潰し――そして醜態と蔑まれていた。
その旧王城から数十人もの子供を攫い、子供の望む道を可能な範囲で歩ませる集団――「子供攫い」の女を除き。
――使えない者というのは、この国では罪でしかない。
それを誰より、人間の女は自らの身をもって知っていた。だから咎人と同等の扱いを受けていたボロボロの化け物を、わざわざ攫い出したのだ。
――あの子にはもう……自分自身の心は欠片しか残ってない。
そして攫われた化け物は、紅い魔性の片目――「魔縁」となってまで、女の部下となる道を自ら選んでいた。
「それでやっと……動けるようになったというけど」
魔縁という、ヒトを食って生きる存在へ自らを堕として、その化け物は成熟した体を得た。元々持っていた、姿や気配を透明とする能力を強化したというが、それと引き換えに人間の女の血を貰って生きる身にもなっていた。
「……それでも……まだ……」
そうしてずっと、苛烈としか言えない一途さで、その部下は「子供攫い」の女の力となることだけを生きる目的としたのだ。
そんな、外見は大人の化け物の傍らへ、青年は坐し続けていた。
「まだここにいたのか――ライザ」
青年が本来あるべき病室の患者を担当する、医者の男が青年を探しに来てしまった。物静かながら、内には激しさを宿す赤い髪と目の医者。
同郷の女性を入院させる時に顔見知りになった医者が、静かに話しかけてきた。
「エアとあの娘が、オマエを待ってるぞ」
「……」
その病室で青年を待つという患者達。白銀の髪に白い肌、薄赤い眼という儚い色合いの同郷の女性と、死んだ人間の女の妹。
一人は幼い頃から姐貴分の、「千里眼」と呼ばれる特殊能力を持つ人間の女性。光に嫌われたと自らの弱い体質を自嘲している。
もう一人は水脈を司る化け物、自然の脅威をヒトの姿とした、「竜人」の血をひく混血の少女だ。
人間の母を持ち、ほぼ人間だった姉とは違い、少女は「魔道」を勉強している。この第五峠を守る「騎士団」の見習いだった。
「その『魔』が、そんなに気になるのか」
「……」
青年の前で横たわる者の正体を、医者は一目で看破していた。
「俺の実家も大概『魔』よりだから、俺は気にならないが……騎士団や悪魔祓いの連中に気付かれたら、事だぞ」
医者はゾレン西部の北の、ザインという秘境で、高名な化け物の家の出自だ。しかし家系にそぐわない適性の持ち主で、ヒトを食わなければ生きていけない魔縁を咎め立てしないのは、おそらくこの赤い髪の医者ならではだった。
生家と折り合いが悪く、この峠に流されて様々な生き物と関わっている医者に、青年は俯いたままで答える。
「……ああ。それは、わかってる」
何の感情もあえて込めない。今はそうしないと、叫び出してしまいそうだった。
「だからこうして――見張ってるわけだし」
「……」
「多分、この子は……放っておいたらこの身体でも、勝手に何処かへ消えて暴れてしまいそうだ」
物資の不足のため、応急処置だけの包帯は変えられず、ところどころ血が滲んでいる。痛々しく横たわる姿に青年は顔をしかめる。
「俺以外に誰も、今。この子を見張れる奴は……もういない」
その場所に坐し続ける理由を、無機質な声で口にする。医者はただ、大きな溜め息を一つついた。
「……今は、どの施設にも、非常事態宣言が出されている」
だから、と医者が、横たわった者をおもむろに抱えた。
「可能な限り、多くの個室患者に、相部屋に協力させている。さすがに性別を分けないのは問題だが……患者が了解して、付添いが確約されるなら、それも特別措置の内だ」
「……――クラン」
医者の意図を悟った青年は、ようやくそこでゆっくりと立ち上がった。
「オマエが見張ってろ。それならエアと、同室に置いておける」
危険極まりない存在である魔縁を、そうして、医者の姓まで貸し与えた女性のいる部屋へ、黙々と移す医者だった。
「……すまない……」
その病室には、一刻も早く行かなければいけなかった。
医者のその厚意に青年は心から頭を下げ、後に続いたのだった。
びっくりしたわよ、と。同郷の女性は、青年と魔縁がその部屋に移ってくるなり、無表情に口にした。
「ミリアが突然、静かに泣きながら目を覚ましたと思ったら。『ピアが死んだ夢を見た』なんて……それも静かに、淡々と言うんだもの」
「……――」
その部屋に、つい半日前に少女は運び込まれた。洪水騒ぎに巻き込まれ、体力を大きく消耗していた少女を、少女の姉が預けていたのだ。
「ミリア……それは――……」
青年が振り返った先では、少女が硬い顔で黙りこくっている。姉の仲間だと紹介された女性が座るベッドの横の椅子で、俯いて両手で膝をふるふると掴んでいる。
口を開かない少女に代り、同郷の女性がベッドから、少女の長い黒髪を優しく撫でる。肩までの銀色の髪の女性は、人間には珍しい色無き赤の眼を、困ったように潤ませて微笑んでいた。
「あんまり真に迫ってるから。私も真に受けて、信じちゃった」
「――……」
「ピアはいなくなった。そうよね? ……ライザ」
その「千里眼」は本来、人間という弱小な気を観ることは難しい。だから人間の女の死については、感じ取れたはずはなかったのだが……。
「ライザの顔を見たら……嫌でも、何かあったとわかったしね」
口を閉じていた少女が、くしゃくしゃな顔の青い目で青年を見上げた。
「……ねぇ。ピアは……デュラに、殺された?」
震えながら、決して途切れない強い声色。
少女の実の弟が、実の姉を手にかけた。その冷たい現実を、自ら顔見知りの青年に問いかける。
ずしん、と。
この部屋に来る前に、何度も青年の足場を揺らした震動。今はもう途切れているにも関わらず、青年の内へと再び響く。
「……俺も直接、それを見たわけじゃないけど」
「……」
運び込んだ魔縁が眠る傍ら、少女からは斜め後ろで、俯きながら青年は先を口にした。
「黒い髪で青い目の、強い水の力を持った子供が……この国の王の弟に連れられて、俺達の近くまで来て……」
少女はただ、悲しげに見つめてくる。
「俺達と一緒に戦ってくれたピアを、その子供が殺したと……俺は聞いている」
「……――……」
はっきりと、俯きながら言い切った青年に息を飲む。
ゆっくり椅子から立ち上がった少女は、青年の正面に立つと、ちょうど身長の差で見上げて顔を覗き込んできた。
目線を合わせて、少女は包帯だらけの青年の腕を強く掴んだ。
「……ごめんなさい」
何故かそんな――青年には理解できない言葉を、強く口にする。
「わたし……デュラを、止められ、なかった――」
そのまま少女は、茫然とする青年の胸元にしがみつき、嗚咽を抑えながら全身を震わせ始めた。
この施設に預けられた少女が、半日前に、そこまで体力を消耗した原因。ある子供が起こした禍に対して、無力だった己をひたすら嘆く。
姉の所へ出向く前に、その子供は先に少女と会ったのだ。己を止める少女を巻き込まないよう、少女を囲んで封じる「力」と共に、峠中の川の氾濫をその後に巻き起こしたという。
「せっかく会えたのに……二人共、いなくなっちゃった――」
少女達と同じ、自然の脅威を司る父の血をひく実の弟。
少女には、共に往かないかという誘いを。もう一人には裁きを与えた。その非情な現実を、小さな体で全て受け止め、少女はただ泣いた。
「ミリアは……何も悪くない」
青年は無表情に、涙する少女を両手で支える。人間の女が少女に伝えた言葉を、ほぼ同じに繰り返していた。
「それはミリアのせいじゃなくて――俺達のせいだ」
迷い惑いながら、それだけは伝えられた答。
少女は、そんな青年を見ることはできなかった。
そして青年には、ずしん、と。
胸元で泣く少女の重さと、足場を揺らす誰かの衝撃が、ただ繰り返し伝えられてくる。
「すまない……ミリアの姉さんを、俺達は守れなかった」
その誰かを間近に見ていた青年は、青年を揺らし続ける誰かの代りに、それだけ何とか口にしていた。
その峠を大きな洪水が襲った時に。
峠に向かうことを真っ先に望んだ人間の女は、青年に大切な話をしていた。
――あたし達の父さんは、竜と言われる化け物だった。
自然の脅威という、世界でも有数の有り得ない化け物。
河川の爆流をヒトにした父を持つ女には、人間の母と、人間である自分、混血の妹と……そして。
――……本物の『竜人』が……現れたか。
父に最も近い同胞、「竜人」と呼ばれる弟が存在していた。
――ピアはもう……五年は家族に会ってないはずよ。
三歳からこの国の旧王城で、軍人とするため鍛えられた人間の女は、十歳で弱小と親元に帰され、その後三年家族と暮らした。
――お父様がまず亡くなって。その後に、お母様から絶縁状を叩き付けられて。
たった三年。その絶縁の理由が、女が家に帰された年に生まれた弟の存在だった。
――君はよくできた子だね、デュラ。
普通の化け物であれば、「力」は第一子が継ぐことが多い。しかしその竜の子達は、第二子以降の方が「力」が大きかった。
最も化け物の血の濃い第三子が生まれ、三歳となった頃のことだ。使えなかった第一子の代りに、第三子を国に差出すようにと、彼らの生家へ再び「子供狩り」が姿を現したのだ。
――あんたはやっぱり……ただのいい奴なのに。
青年達の助けになってくれた女に、そう言った青年に対して、
――……いい奴なんかじゃないわ。あたしは。
自らの罪を知っていた女は、苦しげな微笑みを浮かべる。
――大事な所では、自分を守るために、ヒトを見捨てる。
既に父が死に、人間の女は母と妹と幼い弟、四人で暮らしていた。そんな所に再び「子供狩り」はやってきた。
女達の父は、自然の脅威である弟の、大き過ぎる力が悪用されないよう、決して手放してはいけないと言い残した。だから女の母と妹は、それを守り、決死の抵抗で弟を隠そうとした。
しかしそこで人間の女は、自然の脅威より、自らの家族の脅威に屈する。
――君を売った悪魔のような姉上は、成敗することができた。
泣き叫ぶ幼い弟を、非情にその場へ引きずり出した。そうしてその「竜人」を、人間の女は「子供狩り」に差出していた。
――でもそれを、許されたくて……サライを、始めたのかもね。
その後、実の母から絶縁された女は、竜である父から託された形見、漆黒の珠玉を手に、十三歳という幼さで家を飛び出したという。
やがてその珠の「力」を生かすある古代の鎧を、隣国で手に入れることとなる。
――父さんの力はあたしが奪ってしまった。
本来は弟に伝えるよう、漆黒の珠玉は女に預けられていた。父の一部だった「竜珠」と呼ばれる珠玉には、大いなる「力」が秘められていることを、その直感のためか女は気が付いていた。だからこそ、弟を引き渡しながらも、「子供狩り」からそれだけは隠し通したのだ。
自然の脅威がヒトの姿をとった竜人という化け物には、純粋な自然の化身に限り、三つの宝が先天的に宿されているという。
自らを見据え、まずヒトの形を得るための「竜の眼」。
ヒトであり竜である己の心――力を制御する「逆鱗」。
自然そのものである「力」と命の、核である「竜珠」。
竜人としてみなされるには「竜の眼」一つで充分だったが、これを三つ共揃えた竜は類稀な、強い自然の化身と言われる。
女の父はその条件を揃えた、まさに有り得ない化け物だった。
――あんな鎧は、まじで反則だ。
弱小な人間の体であっても、化け物と戦える「力」を女は求めた。そのため、弱小な人間が世界に君臨していた古代の秘宝――人間の国である隣国で発掘された、「竜珠」を生かせる鎧を見つけて手に入れた。
その鎧を使いこなせるようになった後、旧王城の内部を知る自らの経歴を生かした、「子供攫い」を始めたのだ。
「……でもね。その時にはもう、秀逸だったピアの弟は、既に何処かに送られていて。城にはいないと、ピアは知っていたわ」
第一峠という雪山で、そこの大使を待つ傍らで、同郷の女性は青年にその女の過去を話した。現在、同郷の女性と同じ部屋で坐し続ける青年は、今更のようにそれを思い出した。
「だからピアの償いには……出口も期限も、ありはしないのよ」
人間の女は、その弟から許される日は来ないと知っていた。弟を助けられないと知っていても、「子供攫い」をやめることはできなかった。
――あたし達には、先行きも退路もない。
己の「子供攫い」をそう語った女に、青年は項垂れるしかない。
――あんたはいつまで……『子供攫い』を続けるんだ?
女の答は、何故か今の青年には、もう思い出せなかった。
+++++
王都に帰ったものとばかり思っていた若き国王が、翌日の夜には、身分を隠すように身を窶し、青年達の前に現れていた。
第五峠の医療施設の一個室に、わざわざ国王が現れた時には、青年は呆けずにいられなかった。
「……本当に忙しいな、アンタ」
こんな一国民の元に足を運ぶ王に、溜め息と共に呟くしかできない。
「夜分に失礼するぞ……エア・フィシェル」
まだ眠り続ける魔縁を気にして、青年は病室から出られない。国王は仕方なくその部屋を密会の場として、同郷の女性に真面目にそう声をかけていた。
「来ると思ってたわ――トラスティ」
「相変わらずの『千里眼』だな。さぞ体も傷んでいることだろう」
第五峠から中々離れられない女性の理由を、当たり前のように口にする国王に、青年は憮然と息をつく。
「レインさんは……トラスティとも知り合いなのか」
本名はエア・レインという「千里眼」の女性は、第五峠では主にエア・フィシェルと名乗っている。「千里眼」として力を駆使する時は魔道の大家で有名な医者の姓を、箔付けと言って借り受けているのだ。
「トラスティの極秘部隊と言ってもいいサライに関われば、嫌でもね。リーザにもトラスティは、こっそり会ったことがあるしね」
「子供攫い」に「千里眼」の力を貸し、同郷の女性は死んだ女と協力関係にあった。体を壊すばかりの女性の無理を、青年は良く思っていない。
「……俺の知らない間に、本当に『子供攫い』は、俺の周りを色々と変えてたんだな」
兄弟のいる家が対象の「子供狩り」制度から青年を守るため、双子の弟は生まれた時から存在を隠されている。そんな双子のことを、まさか国王にも知られているとは思いもよらず、大きな溜め息をつくしかなかった。
考えてみればそれを知らないと、人間の女が死んだ時、国王は双子を抑制することはなかっただろう。双子の魔道で、顔が青年と同じことに気付いていないのだと青年は思っていた。
「お前の双子を初めて見た時は、何と不遜で似ていない弟かと我が目を疑ったが」
日頃から剣山の厳しさを持ち、柔らかさを生まれつき持たないような国王。真面目が軍服を着て歩く相手は、今夜は何処か覇気のない声色だった。
まるでそれは、初めて会った時のような、生来の物憂げな表情に見えた。
「大丈夫か、アンタ……さすがに疲れが来ているんじゃないか?」
「……」
無表情ながら、青年の声色もいくらか落ちる。
「……お茶を、いれます」
青年の隣で、紅い片目の魔縁を見てくれていた黒髪の少女が、ぺこりと国王に対してお辞儀する。
その姿を見て国王は、更に物憂げに口を引き結んでいた。
国王が青年の元へ現れた理由を説明する。
「子供攫い」の首謀者の女が死んだことで、ある波紋が広がっている。その危機を迅速に青年に伝える。
「あれから私は、西部へ馬を飛ばしたが――……」
西部の旧王都も東部の現王都も、王の駆る俊足の化け物であれば、第五峠から半日で往復できる。地下道を行く時以外にはそれを主な足とする国王は、まだ王都へ帰らずにいたという。
「我が腹違いの愚弟、ダウテッド・レオンは『西派』総帥と考えてくれ。前王――父上が最も目をかけていた側室、人間の女の息子で、前王の『王属部隊』だ」
「……それじゃ、『子供狩り』の……」
「ああ。現在の首謀者と考えて差し支えない」
前国王が制度化した「子供狩り」は、ゾレン西部中心の徴兵制だ。西部に王都を戻そうと拘る「西派」で、旧王城を守る西部の軍が、今も子供を集める形だった。
「『東派』のピア・ユークは、元々睨まれていた。しかし今回、『子供攫い』の首謀者であるとわかり……彼女が滞在していた隠れ里の全ての者が、『子供攫い』の者でないかと、『西派』は疑い始めている」
「――何だって?」
その隠れ里は青年の故郷だ。「五色のケモノ」の本部でこそあれ、「子供攫い」とも「東派」とも本来全く無関係だ。
「無理もないわね……サライは元々、幹部は少人数とはいえ、西部中に協力者の潜む一大集団よ」
「千里眼」の女性が難しい顔で両腕を組む。女性の故郷でもある里への嫌疑に顔色を曇らせた。
「その上、西部の他の組織より実態の掴めない地下組織だったから……『西派』としては、少しの疑いであれ、この機会に徹底的に弾圧したいはず」
しかも、と、むしろそれが一番の問題と言うように、青年の方を哀しげに見る。
「和平を進めようとする『五色』も、そもそも徹底抗戦主義の『西派』は潰したいはず。『五色』の本拠に、サライの疑いをかけられるなら、願ってもない展開のはずよ」
「……残念ながら、エア・フィシェルの指摘の通りだ」
元は西部出身である国王も頷く。西部までは足さえ運べば、情報収集の手段には事欠かないようだった。
「ということは……今、俺達が少しでも隙を見せれば、いつでも『西派』が俺達を討伐に来るわけか?」
「彼らとて、軍として動くには上申書のための大義を必要とする。それ無しに彼らをのさばらせる程、私は甘くない」
しかし、と逆に、国王は一層難しげな顔色を呈する。
「大義を申し立てられれば、私とてお前達を庇うことはできぬ。お前達が私の『王属部隊』とでもならない限りは」
それはこの若き国王が、青年と「千里眼」と、そして「子供攫い」の女に、以前から持ちかけていた話だった。
「王属部隊」とは基本的に、国王直属の腹心を指す。
中枢は絶対王政、末端は地方自治制であるゾレンにおいて、国全体にまたがる公職の軍部と政務部に匹敵する権限を「王属部隊」は持たされている。王の意志を受けて国内を監視する、少数精鋭機関だった。
「しかし一度、『王属』となれば、王の意志に反した時には死をもって償ってもらわねばならない」
「そうだったわね。そんな話も確かあったわね」
あっけらかんと言う同郷の女性など、弱小な人間の女でありながら、密かにそこまで国王の信頼を得ていたらしい。今更ながらに青年は眼を見張る。
「唯一の例外は、血縁者の『王属』くらいだが。それくらいの覚悟を要す『王属』は、こうした状況で勧めたくはないのだが」
真面目な国王はおそらく、窮地のためでなく、青年達自身の意思でそれを引き受けてほしいのだ。ひたすら難しい顔をする姿に、青年も何となく悟っていた。
「でもね、トラスティ。それって、『西派』にびくびくするか、貴方にびくびくするか――今この状況の私達には、それだけの違いよ?」
辛辣な女性に、だからこそ国王は信頼しているように返す。
「違いない。それは私にも本意ではない」
強く納得したように頷く、真面目過ぎる国王。
あくまで青年達がおかれた危機を示す例え話として――それ以上は特に、「王属部隊」への勧誘を続けることはなかった。だからこそ未だに配下が少ない、若き国王だった。
ひとまず、と国王は話をまとめ、要点を切り出す。
「しばらく、『五色』の活動であっても派手な動きはするな。『子供攫い』との関連を否定するのは当然だが、『東派』への所感を尋ねられても、否定的な返答をしろ」
「……トラスティ。それは――」
そこで国王は、今までで一番厳しい顔で青年達を睨む。
「ピア・ユークのことを何かきかれても、仲間などとは決して答えるなということだ」
「……――」
がたん、と。話には加わらずに、魔縁の傍に座っていた妹の少女が、動揺して椅子を揺らしてしまった音だけが静かな場に響いた。
「……ごめんなさい……」
涙声で俯く少女は、心から申し訳なさそうに、口元を押さえる。
「…………」
その少女の悲しげな姿が、たとえ今ここに無くても――
愚かしくまっすぐな青年は、そうした小細工を元々好まなかった。
「……それは断る、トラスティ」
銀色の髪には怒気の震えを。彩なき灰色の眼には獣の赤い鼓動を宿す。
「共に戦った仲間を否定するくらいなら――……俺はとっくに、この『五色』にもゾレンにも縛られずに、自由に生きてる」
そうしてある炎の獣に耳を傾けるように、怒りのままでそう口にした。
国王は青年の怒気に、全く表情は変えずに、溜め息だけをついていた。
「お前なら、そう言うだろうと思っていた」
だからこそ、わざわざ釘を刺しに来たのだと、改めてこの場に来た目的を口にする。
「しかし事は、お前だけの感情で済むレベルではない」
「…………」
国王は相変わらず、柔らかさを持たない顔付きながら、やはり何処か覇気のない様子で淡々と続ける。
「お前が一人、身勝手な行動や言動をとれば、お前の里ごと滅びの危機に瀕していると私は言っている」
「……それなら、何かする前に、俺は里を出るだけだ」
これまでの双子のように、放浪に生きる、と青年は吐き捨てる。
おそらくそれは、この青年の性には合わず――何かの形で青年の身に、破滅を呼ぶ選択だと自覚しながらも。
「――わからないのか。ピア・ユークの率いた『子供攫い』……その悲願はまだお前達にかかり――ここに残っていることを」
あくまで覇気がなかった国王は、ここに来て、僅かにその声色に熱を持たせ始めた。
「『子供狩り』にはお前とて、私怨があるはずだ。そして、『五色』が目指す和平が叶えば、私も『子供狩り』を廃止する大義ができる」
死んだ人間のことを、本気で考えるのなら。自らのプライドや感情など何の意味があるのか、それを国王は青年に突き付ける。
「そのため表面上、あの人間を斬ることに何の罪がある。必要とあらば、私は無限に彼女を断罪する。その願いのためであれば」
「……――」
青年はそこで、国王の言う内容にでなく――
――あの人間は……そうしなければいけない咎人なのだ。
確実に女の過去を知っており、「王属」に迎えたいとまで信頼を寄せていた国王の覚悟。そこまでして堪える想い、誰かと同じその目の光に、不意に胸を衝かれていた。
「俺は……」
私情を殺し、「子供攫い」を続けた人間の女を思い出した。青年の全身からは急速に赤い怒気が抜けていった。
「俺は……アンタやピアみたいに、自分に嘘をついてまで……何かの目的を成し遂げようとは、思っていない」
「……」
けど、と。ずっと黙っている「千里眼」や、黒髪の少女を傍に力無く俯き、青年は珍しく苦い微笑みを浮かべた。
「……アンタやリーザが我慢してることを……俺だけが嫌だって言うのは、確かに、我が侭だな」
そこでぎゅっと、青年の服を横から黒髪の少女が心配げに掴む。困ったように笑いかけた青年に、しがみついた少女の肩をそっと片手で抱く。
少し続いた沈黙の後、青年が心から信じる者達は、安堵したように苦く笑っていた。
その後、国王がようやく王都に帰っていった後で。
長く青年の姐貴分である女性は、溜息をつくように笑って言った。
「本当に……ライザは大義とか、悲願のためじゃなくって、守るために戦う時だけ頑張るのよね」
「――?」
同郷の女性は、青年が「五色のケモノ」を創始者の父から引き継ぎ、最近は急いで進めていた理由を知っている。
青年の横でちょこんと座り、大人しく眠る魔縁を見守りつつ不思議そうな黒髪の少女に、ふふ、と穏やかに笑いかける。
「他にしたいことがないって点では、私と似たりよったりだけど。仲間とか家族、大切なヒトを、自分なりに守りたい時にだけやる気が出る――モノグサな子なのよ、ライザって本当に」
「レインさん……それ、少なくとも褒めてはないですよね」
肩越しに振り返る青年に、くすくすと同郷の女性が笑う。
「いいじゃないの。こんな風にみんなでお泊りできるなんて、とっても珍しいことなんだから」
ぽかんとする青年と少女に、リミット君さまさまねー、などと、一見は至って気楽な女性だった。
様々な惨事の後で、相部屋初日の昨夜は誰もが疲れ切り、全く話などできなかった。
「ミリアも明日には、お母様の所と騎士団に帰るって言うし」
それならチャンスは今日だけよ! とばかりに、同郷の女性がまた笑う。
すっかり体力の回復した黒髪の少女――家族を亡くしたばかりでも、気丈に立ち上がっている姿を愛おしむように、女性は少女と話をしたがっているようだった。
「冷戦も『五色』も実際、そこまで興味はないのに。大切な周りが身を削って頑張ってると、心配だから手伝おう、そんなんでしょ? ライザって実のところ」
「……そうなの?」
きょとんとして青年を見る少女に、バツが悪いだけの青年は、
「……俺、何か悪いことしましたか、レインさん」
何故、そのような話に、と、女性の言葉を暗に認めるのだった。
女性はそこで、これまでで一番少女をしっかりと見る。
「当分は、トラスティやリーザが心配で我慢するでしょうけど。そういうのが無くなったら、ちょっとプッツン来るとすぐにヤケになっちゃう子だから。気を付けるのよ、ミリア」
「そうなんだ……」
ふぅむ……とばかりに少女が頷く。
「何の話ですか、レインさん……」
勘弁して下さい。という顔を最早隠さない青年に、
「まぁまぁ。明日はきっと、いいことあるわよ」
ゴメンね。と笑うように、赤い眼を細めた「千里眼」だった。
+++++
洪水と連続爆破事件の惨劇から、二夜が明けた。
ようやく静穏に慣れ始めた第五峠に、にわかに騒ぎが起こりつつあった。
「――やって来たで! 『五色のケモノ』のご到着や!」
使役できる限り全ての怪鳥を飛ばして、化け物の仲間とも共に、大量の箱を抱えて第五峠に降り立った一団があった。
「今日はこれだけで精一杯やけど、後何回かは往復したるわ! 特に急ぎの物入りがあったら、先言うといてくれ!」
「地の大陸」では東よりの訛りで、「五色のケモノ」と名乗る碧毛の代表が前に出る。
第五峠の災難を聞き、仲間を総動員して物流がある第一峠へ行き、救援物資を買い込んで第五峠に現れたのだ。
「本当に有難うございます、『五色のケモノ』バルフィンチ殿。このご恩は一生、忘れはしません」
「いやいや、ヴァルトでええって! 困った時はお互い様やろ!」
第五峠に常駐し、深く頭を下げるディレステアの王女。鳥の化け物である代表はでれっと下がる糸目を隠しもせず、王女とがっしり手を取り合うのだった。
そんな代表とは対照的に、同じく「五色のケモノ」の幹部で、代表とはまたいとこにあたる幼馴染が、青年達の所へ、何やら世界が滅びたかのような暗い面持ちで現れていた。
「……ライザ……ピアは本当に、死んじゃったの?」
青年が驚いたことには、幼馴染はこれまで、その人間達を彼らの里への侵入者と毛嫌いしていたはずだった。
「どうしよう。私もっと、ピアに優しくしてれば良かった――」
「ハーピア……?」
そこまで幼馴染が沈痛にするのは、どちらかというと、死んだ人間のためというより――
「リーザ、私達の前ではいつも通りにしてるけど……一人の時は別人みたいに、ずーっと無表情なの」
青年の双子の存在を知らされている、数少ない同郷者の幼馴染。沢山の小鳥を魂を介して使役する幼馴染は、昔から双子を、たまに仲間の小さな鳥に頼んで監視までする程、良く言えば気にかけていた。
「リーザと仲良くするななんて、ピアに言わなければ良かった。私が心配しても、今はリーザ……聞いてくれそうにない……」
「……」
死んだ人間の女は、表向きは「東派」として彼らの里に滞在していた。
――それで貴女は……どちらの方と、良い仲なのでしょうか?
ディレステア王女をしてそんな問いを出させる程、女は青年達――特に双子の弟と気安かった。
「五色のケモノ」も手伝わず、放浪を続けていた双子が、
――あいつら放っとくと何するかわかんねぇ。
そんな風に言って、「子供攫い」の協力までしていた根本。青年は最初から、それが一番の理由と、兄として悟っていた。
――オマエ……あの女に負けたのか。
最強の獣と呼ばれた彼らの父が、母には負けた、と何度も豪快に笑っていた。その口癖を思い出しながら、弟にそう尋ねた青年だった。
暗い表情で黙り込む幼馴染に、病室の主の女性は、何故かけろりと尋ね返した。
「リーザ、そんなに落ち込んでる? ハーピア」
同じ「五色のケモノ」の幹部に、不思議そうにきく。
「どちらかと言うと、あの子、ひたすら怒ってそうじゃない? 『西派』ぶち殺す。って」
「……うん。どうしたら『竜人』に勝てるかって、悩んでたわ」
「千里眼」の言う通り、戦うことばかりを考えている最強の獣。そう呼ばれる「飛竜」すら、そうして悩む相手――
獣を凌駕する自然という「力」に、部屋にいる同じ血の少女も黙って座り、表情を硬くしていた。
「……落ち込めるなら、まだいいんだけど」
ぽつりと呟いた「千里眼」の女性の方に、一度だけ振り返りながら。
双子の兄弟のどちらと、仲が良いのか。
そう尋ねられた人間の女は、至って無責任に、軽い調子で答えたらしい。
「えー、難しいなあ。だってどっちも、あたしはもう勝手に、家族くらい大事って思ってるもの」
のほほんと、幸せそうに笑っていたと、王女は語った。
「でもあえて言うなら……一人はあたしの大切なヒトで、もう一人は、あたしの妹の大切なヒト……ってとこかな?」
あくまで願望だけどねぇ、などと後に付け足した。素敵ですね、と王女も、心から共感して返したというのだった。
王女がその病室へ、普段は護衛をしてくれる騎士団長を伴い、「五色のケモノ」の代表も連れてくることになった。
「すまない、ミリア。リミットをなるべく隠すようにしてくれ」
「うん。ちょっとくらいなら、多分できると思う」
王女はともかく、騎士団長はまずい。「魔道」を勉強中の少女に頼み、その魔縁をなるべく目立たなくせんと、青年は悪あがきをする。
「……」
「マイス殿? どうされたのですか?」
扉を開けた直後に、不思議がる王女の横で、寡黙で若い黒衣の騎士が、とてつもなく不機嫌そうな赤い目で青年をじっと見つめた。
「……気に入らないのは、重々わかる」
「…………」
青年は仕方なく、少女が薄めてくれた魔縁の気配を利用する。
「でもあの子はまだ弱い。アンタと同じで、かえってこれる」
今まではっきりとは、口にしなかったこと。その騎士団長に対しても、青年が見ていた真情……「魔」に堕ちる手前で留まる天上の鳥の、赤い光と不可視の翼を暗に伝える。
「何や何や? どうしたんや、騎士団長サン?」
「五色のケモノ」の代表、地上の鳥が不思議そうにするように、騎士団長は普通の化け物とは違う。天上の鳥が地に降り立った、珍しい「神」寄りの化け物である正体は、王女と知り合った時から青年は気が付いていた。
だからこそ「魔」を拒み続ける寡黙な騎士団長は、ただ敵意を向ける。
青年が第五峠に援助の手を差し伸べた「五色のケモノ」でなければ、その魔縁は見つかったそばから処断されていただろう。
「あ……目が、覚めたの?」
ひとまず追及は後で、ということで、王女と青年達が話す傍ら、ようやく魔縁が紅い片目を開けた。傍に座り、見守る黒髪の少女を見上げ――すぐさま、体を起こそうとした。
「……!!」
「駄目。せっかく包帯、変えたばかりなのに」
しかし少女にあっさり取り押さえられ、まだ塞がらない重傷からも、それ以上無理は効かないようだった。
「お、マエ………」
呪うような声で少女を見上げる紅目に、少女は淡々と応える。
「ずっとライザが心配してるし……ピアも、きっとそうする」
澄んだ青い目で魔縁を見つめ返し、躊躇いもなくその名を出した。
「……――」
そこで魔縁の周囲の紅い空気が、不意に、少女の纏う悲しげな青い大気へ溶けかけた。それを確かに、青年は眼にする。
「それで、ライザ殿。『五色』としての意見はどうでしょうか?」
王女の声で我に返った青年は、大の大人達が会合をするには確実に狭い部屋で、立ち話の続きを口にした。
「王女達の覚悟はよくわかりました……けど、本気でその話を実行するなら、危険なことがあまりに多過ぎます」
難しい顔をする青年に、他の「五色のケモノ」も頷く。
「まさか、最前線の第六峠で、和平交渉の場を設定するなんて。本当にアヴィス第一王女は承知されているの?」
「そうやで、王女サン。さすがにそれは無謀やろ」
口を揃える化け物の鳥達に、弱い人間は逆に笑顔で胸を張る。
「でも王女の言う通り、それこそ一番必要なことじゃない?」
一応同じ人間の「千里眼」は淡々と、王女からの申し出に同意を示す。
「国王だけが平和な場所の談合で、和平と頷いたところで、戦っている者達が納得しなければ、結局すぐに破綻するんじゃないかしら」
それに――と、彼らのある事情をも踏まえ、先を続ける。
「今後は第六峠を管轄する『西派』を巻き込んで交渉を考えないと、下手をすれば私達、国賊扱いをされてしまうわ」
昨夜に国王からの、直々の警告があった話。内密とはいえ王女は特例として、その危機を真っ先に説明した同郷の女性だった。
「『五色』内にも、ピアを慕ってた子は沢山いた。そのピアを討伐した『西派』には、『五色』の側も……それでなくても、互いに反感を持っておかしくない状態よ」
少し前から彼らの里は、様々な事情で軍が中心の「西派」と折り合いが悪くなっていた。それもあり、穏健な自称「東派」の女達と打ち解けつつあった。
「その上、『東派』を騙る『子供攫い』を滞在させていたことは、『西派』からは必ず――いつか糾弾の材料にされる」
その「東派」の正体も、躊躇いなく「千里眼」は同郷者に伝えていた。
「そうやな。『東派』の奴はあのねーちゃんが死んだときいて、ザインに身を隠す言うて早々に引き上げとったわ」
それを止めなかった「五色のケモノ」は、それ程に「東派」を名乗る者達を認めた、対等な関係性を持っていた。
里の長老の孫である代表は、顔色を暗くして先を続ける。
「あのねーちゃんを殺した『西派』と話してまで、和平の場を取り持つやなんて……ハラワタ、煮えくりかえるけどなぁ」
「バカね。アンタがそう思うってことは、下の子達もそうでしょ。だからこそ、エアは正しいわ」
幼馴染は実に複雑そうに、両腕を組んだ。
「『子供攫い』は正直、嫌いじゃなかったけど……」
一方からは非情な国賊、他方からは反戦派の義士と、評価が分かれるのがその実態不明な集団の特徴だった。
考え込んでいる「五色のケモノ」に、王女が憂い気に尋ねる。
「皆様は――『子供攫い』とは、関係がなかったのでしょう?」
部外者であるため、口にするのを躊躇いながらも、ずっと寡黙な騎士団長の横で現実的に話を進める。
「それなら可能な限りに……皆様と周囲の方々も争わないで済む形で、両国の平穏のため、力を貸していただけませんか?」
「…………」
表向きの代表でなく、真リーダーとされる青年は硬い顔で黙る。
「和平を求めるというのは、そういうことではないでしょうか? そのためならわたくしも、姉のアヴィスも――この身をかけて、皆様のご厚意に応えたいと思っております」
あくまで危険は厭わない、と凛とした赤い目で王女が言う。
その王女が先日の惨劇の際、自らの護衛をしてくれる騎士団を全て峠の守りに向かわせ、一人の状態で危うく殺されかけたことを青年は知っている。だからその覚悟が真であると、誰よりもわかっていた。
「……俺達は力の限り、俺達の目的のため、貴方達を守ります」
青年の静かな返事に、王女は心から嬉しそうに微笑む。
「ありがとうございます。わたくしも、貴方がたを信じられるからこそ、勇気を持って臨みたいと思っております」
なるべく流血を避けたいと願う王女の望み通り、青年は大使館でも敵の人間を可能な限り殺さずに捕縛した。そうした青年に、大きな信頼の眼差しを王女は向けるのだった。
「日時は全て、ゾレン国王のご都合を優先下さい。わたくしかアヴィスが必ず、信頼する護衛を連れてお伺いします」
そこで王女は、騎士団長の方をにこにこと振り返る。
ね? などと、あまりの気安さで、その同伴を全く疑わない信頼。黙り続ける騎士団長に親友のように笑いかけていた。
「……」
本来、騎士団長は第五峠の守護のみが管轄になる。
王女の護衛はあくまで峠内でのみ、峠を守る一環のはずだ。それでも他の峠に出向こうという王女に、同伴する気はあるらしい。
そもそも青年が王女と初めて、話をしたきっかけは……今から考えればあれは逢引だったのだと、その裏に思い当たっていた。
あらあら、まぁまぁ、と。
青年が王女と、よく話をした秘密の謁見の場――王女のお気に入りという山中の展望台へ、見えない翼を持つ謎の鳥が降り立ったことに気が付いたのが、王女や騎士団長との出会いだった。
謎の鳥を追いかけて行くと、先客だった王女が目を丸くしていた。
「……アンタ、まさか――」
流行の病にかかり命を落とした青年の親を、王女は自らも感染の恐れがありながら、手厚く看取ってくれた。その姿を青年は覚えていた。
「……こんな所で、何をしているんだ?」
しかし王女の正体を口にするのは思い留まり、言葉を呑んで質問を変えた。王女は安堵したように微笑んでいた。
「はい。家に帰る前に、いつもここで休んでいるのです」
「こんな遅い時間に?」
「仕事がとても忙しくて。でもここから夜の空と海を見ると、気持ちが落ち着くのです」
にこにこと、大真面目にそう話す王女の後ろには、青年が視た、謎の透明な翼を持つ若い男が黙って佇んでいた。
「それは……危なくないのか?」
「はい。でもそのおかげで、守っていただけるのです」
山中の展望台で、休む余裕を持つために騎士団長を連れ回すという。最早どちらが目的かわからない王女だった。
見えない翼――光を失っていたその一つ一つの羽。しかし翼という「意味」を失わずに留める特殊さを持った、天上の鳥の力。
生まれつき、「力」を視ることができる、と後に人間の女から言われた眼を持つ青年は、その鳥を連れている王女に忠告する。
「……天使は地上でも厳しいから、注意した方がいい」
天上の鳥はあまねく存在、特に「魔」には容赦がない。だから思わずそんなことを呟いてしまったのだが……。
「いいえ。マイス殿は、ヒトの親のある、ヒトの子さんですよ」
全く動じることなく、王女が騎士団長の腕を掴んで笑う。騎士団長も一言、天上の聖火をたたえる赤い光を残す目で呟いていた。
「これは――……生前の、名残だ」
羽が光を失った理由はそれか、と、青年もそこで納得する。
「魔」でもなく「堕天使」でもなく、ヒトとなった天使。「神」寄りの珍しい化け物を、しばらく無遠慮に眺めたのだった。
その化け物も、ともすれば――化け物である以上は、暴徒と堕ち、「魔」に染まる可能性がある。
「騎士団をされる前は、マイス殿もとてもやんちゃでしたね」
それを引き戻し、中立地帯という聖域を守る鳥たらしめたのが、幼馴染とも言える存在の王女。だから騎士団長も信頼を寄せ、自らの役目の次に大切なものと認識しているようだった。
「五色のケモノ」と王女の、狭苦しい会合が終わった後で。
「……本当にこの方を、もう連れて帰られるのですか?」
意識の戻った包帯だらけの魔縁を背負い、病室を出た青年を、見送る王女は少し不服そうに見つめた。
「すみません。しっかり手当を受けさせたいのは山々ですが……今は負傷者の数が多過ぎて、それどころじゃないでしょう」
冷静に言う青年に、王女も黙り込む。
青年も、「魔」を騎士団長が見逃してくれている内に、聖域から遠ざけるのが一番だと判断していた。
「……」
騎士団見習いの黒髪の少女は、自身も帰ると病室を出て、青年を黙って悲しげな顔で見つめる。
「ミリアは……今まで通りに。それをピアも、願ってるだろ」
「…………」
俯く少女は両手を握り締め、黙って青年を見送ったのだった。
他の「五色のケモノ」は、再び物資の買い込みに出発した。青年は一人、魔縁を連れて、徒歩で里に帰ることになった。
「すまんなぁ。今はライザにまわしてやれる鳥がおらんわ」
「当たり前だ。そんな余裕があれば峠にまわしてくれ」
「リーザに手伝ってくれんか聞いたんやけどな……アイツ、ライザの迎えすら断りよった。あのカラダやったら大分沢山、物が運べんねんけどなぁ」
「……」
双子の弟は、「東派」をまず逃すべく飛竜となり、ザインに飛び立ったということらしい。
しかしその、帰りのことであるのか――
上空にあっても見えない壁が外敵を阻む、砦の国ディレステアに起こったある異変を、目撃した地上の鳥は憂い気に語った。
「ほんまにアイツやったかどうかは、わからんのやけど。何や、おれの鳥の一匹が見たっちゅーことには……」
国の周縁を外壁に囲まれる、ディレステア上空で。まるで、壁を壊し、内部に侵入せんとするが如く体当たりを続ける、飛行型の化け物がいたということだった。
ずしん、と。
遠い空の震動が、たった今伝わってきたかのように。
青年もありありとその衝動を感じることができていた。
「もしもそれが飛竜やったら、アイツ、何考えてんやろな?」
「……」
心配げに顔を伏せる代表――青年と双子の悪友に、青年は無表情に言葉を呑み込む。
「リーザとあのねーちゃん、もしやデキとったんかねぇー……」
ここ最近、放浪に出ずに里にいた不審な双子。心配ながら羨ましげにそう呟いた、気の多い悪友だった。
+++++
中篇・承
――なぁ、と。
負傷した魔縁を背負い、青年が帰った時に待ち受けていた、双子の第一声は。
「ソイツ……小さくなってねぇ?」
「――え?」
傷口がなるべく開かないよう、穏やかに、と気を使って運んできたせいか、道中は思ったよりかなり時間がかかった。
「そう言えば何か……途中から、歩きやすくなったような」
「まじかよ。っつか本気でコレ、十五歳くらいだろ」
自宅の寝床に横たえた魔縁は、まさに、少年化していた。
「ライザが小さくできるの、オレだけじゃなかったのか」
「いや……アレをやった覚えはないけど」
共に出歩く時には、青年は双子を手の平サイズの飛竜にできる。そうした妙な特技を持つ青年は、確かに縮んでしまった魔縁に、はて? と首を傾げる。
双子は一見、これまでと全く変わらない様子だった。
「なるほどなー。コイツ多分、そもそも姿を変えられる系統の化け物なわけだな」
ふむふむ、と魔縁の様子を確認しながら、包帯を替える。
「大人になったり、透明になったり、そもそもコイツの能力の一環だったわけだ。だとすると、コイツの意志で、この姿になったんじゃね?」
「……そうかな? 『力』だとしても、無意識じゃないか?」
帰路がやはり辛かったのか、意識を失った魔縁が、少しでも運ばれやすい姿になったのは有り得る話だった。
「もしくはライザが洗脳したか……だな」
「は?」
「ま、いーか。ところでコイツ――」
そこでくるっと、双子は紅目から青年に振り返った。
「エサ、どーする? これでも『魔』なんだろ?」
「……」
それは青年も帰り道すがら、頭を悩ませたことの一つだった。
「人間の血なら質もいいし、少量で長く食い繋げたろーけど。供給源のあのバカ女は、もういねーんだしさ?」
あっけらかんと言う双子に、青年は少し不服気に黙り込む。
「回復したら、サライの連中の後を追うのか、それとも好きな所に行くのか。それだけオレは確かめたいんだ」
既にザインまで、双子は「子供攫い」の他幹部を送っている。そこまでは自分の仕事と捉えているようだった。
「何かこの里も、軍に睨まれてるっぽいし。オレが長居すると、下手したらばれるだろ、オレらのこと」
魔縁のことさえカタがつけば、また放浪に出る気らしい。淡々とそうして眠る魔縁を見下ろしていた。
しかしそんな、時間の猶予は無いとばかりに。彼らの小さな丸木の家に、飛び込んできた人影があった。
「大変よ――! リーザ、ライザ!」
「?」
「あぁ? ハーピア?」
短くもふわふわと揺れる茶髪が逆立つ勢いで、幼馴染が小さな鳥を肩に血相を変えていた。
「軍が里に向かってる! ピアの通行証を探してるみたい!」
「――!」
「――まじかよ」
青年と双子はばっと顔を合わせる。今まですっかり失念していた、数日前の出来事を思い出した。
「まさかとは思うけど、リーザが持ってたりしないわよね!?」
「何でわかんだ、ハーピア……」
「持ってるの!? なら急いで隠して! 見つかったら確実に死罪よ、それ!」
早く! と焦る幼馴染は、里を取り巻く仲間の小鳥から、軍がまさに接近している情報を得たようだった。
「というかリーザ自体、早く隠れて!!」
存在を隠された双子という、彼らの事情も知る幼馴染の剣幕。青年と双子は心底困って顔を見合わせる。
「通行証――……どうやって隠す?」
「……マズイな、まじで」
頷き合う双子の兄弟の、弟が持っている他人の「通行証」は、言わばこの国の身分証だ。名前を刻まれ、戸籍を持つ者全てに一人一つずつ与えられ、軍の助力なしに国境を越えられる魔法具になる。
しかし名前の主以外には、譲渡も貸与も、いずれも死罪――そう定められた、命の次に大切とまで言われる小さな結界石なのだ。
死んだ国民の通行証は通常、遺体周囲で探知道具で探されて没収される。先日に討伐された「子供攫い」首謀者の通行証は、亡骸からは見つからなかったのだ。
「完全に借りっぱだったじゃねーか、あいつの通行証」
「ああ。俺もすっかり忘れてた」
大使館という、まさに国境上で青年達は戦闘を行っていた。戸籍が一つであるため、二人で一つしかない通行証では、どちらかが国境にひっかかる恐れがある。そう言って死んだ女は直前に、自身の通行証を貸してくれていた。
「これそもそも、隠せんのかよ?」
国境として軍が定め、常時展開している魔法の結界を、通り抜けしても感知されなくなる魔法具が「通行証」だ。荷物に紛れ込ませてもそれは軍の魔力探知機に反応し、隠し立ては不可能と言われる道具に、彼らは途方に暮れた。
「それ持って今からリーザが、大急ぎで逃げるしかなくないか」
「もう遅いわよ! 里の他の家まで軍は来てるわ!」
その状況で、逃げ去る飛竜が見落とされるほど、軍は甘くない。幼馴染はひたすら、焦燥の目で双子を見つめていた。
そして数分後。
彼らが何とか、イチかバチかの対策を打ったところで、軍の気配が丁度すぐ外まで来た状態となった。
「ちょっとライザ! このコ誰なの!? どうするの!?」
焦り続ける幼馴染は、今度は包帯だらけで横たわった少年を見つけ、混乱したまま顔を引きつらせる。
「そうか、しまった。下手したらリミットは連れていかれる」
肩に蒼い飛び蜥蜴を乗せた青年は、少年の元にかがみ、少年の意識はある事を確認する。
「透明になれるか。君には話がある、ここにいてほしい」
率直にそう伝える。少年はわけがわからなかったようながら、軍に見つかるのは嫌だと感じたのか、指示通りにすぐその姿と気配を透明化していた。
その直後に、乱暴に彼らの家の扉は押し開かれた。
先日もこの里にある理由で強引に押し入ってきた、国境を担当する軍の一団が、ぞろぞろと入ってきたのだった。
「――何だ。ここは貴様の家だったのか、飛びトカゲ」
「……」
居丈高な声を隠しもしない、豪強な准将の男を筆頭に、数人の軍人が入り込んできた。黙り込む青年と幼馴染の前にぞろぞろと立つ。
「この里に潜伏していた『東派』――正確には『子供攫い』、首謀者ピア・ユークの通行証を探している。協力しなければ、貴様らも国賊とみなすぞ」
「……」
青年が黙って睨む准将の手には、魔力探知機とおぼしき、小さな傘のような道具が握られている。
准将と常にコンビである将軍は他の家を回っているらしく、最悪には国賊となっても戦う選択肢も一つと、青年は覚悟を決めた。
そのためかつい、准将に向かって悪態が口に出る。
「……アンタ達も、暇なことをしてるな」
「ほほう? 国境を死守する我らの役目を、侮辱するのか?」
「死守って、実際戦うのは大体自治団じゃないの」
青年につられてか、幼馴染までがんをつける。ぴりぴりとした空気が否応なく場に満ちていった。
「文句ならあの軟弱な東の王に言うがいい。我ら西部の軍備を削減し、あからさまな軽視などするから、『子供攫い』の如き国賊がのさばるのだ」
探知機をあちこちに向けながら、准将も苛々とした顔付きで、ひたすら捜索を続ける。
「……――」
探知機はまだ、青年の方には向けられていない。それが青年の――肩の蒼い獣に向けられた時が、彼らにとっては勝負だった。
基本的には通行証は、表面に名前は刻まれるが、個別に違う反応をすることはない。存在の有無と数を問われるだけで、その部屋にある通行証を確認し、名前を照合する作業が主だった。
「ライザ・ドールド。ハーピア・スピリーズ。……ふむ」
戸棚にあった青年の通行証と、幼馴染の持つ通行証が確認され、特に異状はないと准将は納得したようだったが。
「……む?」
ある一つのおかしな反応に、否応なく准将は気付いていた。
「――貴様ら。この、後一つの通行証は、いったい何だ」
この部屋にある通行証の数と、ここにいる者の数が合わない。そう厳しい顔で、立ち並ぶ青年達の方を見る。
ずかずかと、その反応の元へと、軍人数人には狭い室内を遠慮なく汚して横断していく。
「……――」
彼らが向かう場所に、まさに立ちはだかっている青年は、強くその顔を歪め……――
「……その子に、触るんじゃない」
青年の肩の蒼い獣には目もくれずに、軍人達は、青年の寝床に横たわった透明な存在に迫っていく。青年は厳しい声と眼を向けた。
「酷い怪我をしているんだ。通行証だけ確認したら、その後は動かさないでくれ」
「――む?」
透明になってはいても、体や通行証そのものを消すことはできない少年が、横になっているのを准将が手探りで見つけた。厳しい目線の青年に怪訝な視線をぶつけ返す。
「透明な怪我人とは、また異なものを。いったい何者なのだ、ここにいる後一人は」
少年が持つ通行証も、手探りで取り上げた准将は、その名を読み上げた。
「アルター・ルーシッド。ふむ……特に前科の記録はないようだが」
それ以外には、部屋に通行証は見当たらないということで、准将が探知機を下げた。しかし怪訝そうな顔は消さずに、青年を睨んだ。
「何故わざわざ、この怪我人とやらを、我々から隠し立てするような真似をした?」
「そんなつもりじゃない。その子は魔縁だ。力が制御できずに、勝手に透明になっていただけだ」
青年の言うように、自らの力を制御できずに暴発させたり、時に原形も留めなくなる化け物は暴徒や魔縁と呼ばれる。
「子供攫い」と少年の関係を明らかにしたくなかった青年は、実際に「魔」である少年の、一面の真実を告げる。そうして准将の追及の矛先を何とかかわそうとする。
「怪我をしたのもそのせいだ。それ以上刺激しないで、放っておいてくれないか」
完全な嘘ではない青年の言葉に、准将はしばらく、考え込む素振りをみせていた。
「しかし、そのような魔縁を放置するのはいかがなものか」
国の治安を維持する軍人としての准将の追及に、青年は思わず呆れた。
「アンタに言われたくない。アンタがうちの里に捨てていったアイツより、その子はまだ真っ当だ」
軍の手にすら負えなかったある魔縁を、先日青年は、軍の代りに処断させられた。反感を隠さず、吐き捨てるように言う。
「なるほど。貴様らが手を下さないつもりならば、尚更我々が処断するしかないということか」
「やめろ! 触るな!」
「ってちょっと、ライザ!?」
少年を捕らえようとした准将に、本気で立ちはだかった青年に、幼馴染がぎょっとして声を上げた。
「貴様、軍に逆らう気か?」
歪んだ笑みを准将がたたえ、怒気を隠さない青年を見据える。
「何故この魔縁にそこまで拘る?」
「少し前から共に生活していた。それ以外何があるんだ」
「ふむ。それなら――先日の我らの心情とて、貴様には責める権利はあるまい?」
青年はそこで――これは、この准将からの取引であることを、否応なく気付かされた。
「……仲間だから、アイツのことは、自分達で討伐しなかった。アンタ達は――そう言っていたな」
軍の内で生まれた恐るべき魔縁の始末を、准将達は押し付けてきた。そしてずっと、軍の不始末はウヤムヤにされた状態だった。
「これで貸し借りはなし――そう言いたいのか、アンタは」
「はて? 何のことやら、私にはとんと見当もつかん」
あからさまにとぼけながら、准将はそこであっさり、くるりと青年達に背中を向ける。
「魔縁を飼うなど、酔狂過ぎる飛びトカゲには忠告する気にもなれん。寝首をかかれた時には大笑いしてやろう……――行くぞ」
そうして軍人達を引き連れ、通行証の捜索をつつがなく終えた、西部の国境の守護者だった。
しばらく時間を置いて、その家に静寂が戻り、最早異変が戻ることはないとようやく納得できた頃に。
「……とりあえず……リーザも通行証も、何とか隠せたの?」
へた、と、緊張の糸が切れたのか、幼馴染が座り込む。青年の寝床の透明な少年の横で、何故か少年の頭の辺りをさわさわと撫で、気持ちを落ち着けようとしているらしかった。
「……リーザが気付かれないのは、わかってたけど」
以前にも蒼い獣をただの「飛びトカゲ」呼ばわりした准将に、青年も肩の上の弟もひたすら不服気にする。
「ピアの通行証も、守れたみたいだ。良かったな――リーザ」
「…………」
物言わぬ小さな蒼い獣。しかし確かに、微かな安堵――
その人間の女の通行証を手放さずに済んだことに、ほっとする気配を漂わせていたのだった。
まだ座り込んでいる幼馴染の隣に、双子を肩に乗せたまま、青年も少年の方へかがむ。
「すまない、リミット。姿を消してもらったことが、かえってアダになってしまった」
「……」
判断ミスを詫びる青年に、少年は透明なまま、何一つ反応しない。
話があると言って少年を透明にさせた続きとして、少年に向かい、青年はその問いかけをまっすぐに伝えた。
「君は……怪我が治れば、どうするつもりだ?」
「……――……」
その場で静かにあぐらをかいて座り込む。
キョトンとしている幼馴染に眼もくれずに、まっすぐに少年――のいるはずの場所を、痛ましげに見つめる。
「もしも君に、行きたい所が特になければ、このまま――……うちにいる気はないか」
「――ア……?」
そこでス……と、驚きの感情を表すかのように、少年の姿が透明から元に戻った。
痛々しいとしか言いようのない、大火傷の痕。それが大きく残った顔と、傷だらけの全身を包む包帯が露わとなった。
「って――……」
その姿に、少年の額に手を当てていた幼馴染が思わず息を飲む。
「酷い……こんな体で、アナタ……」
しかし幼馴染の上げた声は、少年の異形さではなく、痛々しさに向けられた歎声だった。
「オ……マエ――……」
少年にさも同情を向けるような、哀しげな青年の彩の無い眼に、少年の厳しい紅の目には露骨な怒りが浮かび上がる。
「何の……つも、リ――……」
一カ月以上、青年を監視し、魔縁の少年は命を狙っていた。
情けをかけられる筋合いはない。そもそも少年をここまで連れて戻り、軍人達からもかばうような行動を見せた青年に、不可解、という怒りをずっと抑えていたようだった。
「…………」
それでも青年は、ひるむこともない。
青年がその誘いをはっきり言葉にするまで、少年は何一つ行動には出ず、黙って怒りを抑えていたのだから。
「君は本当に……一本気だな、リミット」
同情というより共感を込めて、紅い目をまっすぐに見返した。
「俺を殺す理由が無ければ、その時は殺さない……殺す理由の言葉や行動がなければ、怒り一つも外に出さない」
少年はひたすら青年を監視し、付き纏っていた。それより本当は、すぐに青年を殺す方が明らかに楽だったはずだ、と青年は嘆息する。
そんな愚直な相手を、とっくに青年は見切っていた。
「それなら、君がうちにいるべき理由は、まだ存在する」
「……ア?」
「ピアが死んでも、俺が『子供攫い』に不利なことを話さないと確証はない。むしろ……うちの里を守るために、あることないこと、ピアの情報を言うかもしれない」
淡々と少年の紅い目を見下ろす。無表情で無骨な、棘の無い普段の声で青年は口にする。
「……ア……?」
少年はただ、見開かれた紅い片目で青年を見上げる。
「俺を監視するのが、君とピアの約束のはずだ」
だから青年は、ここまで少年を連れてきたのだと。事も無げに言う灰色の眼に、それ以上少年は何も言えなくなった様子だった。
上下関係以外に、こんな扱いを受けたことがない少年なのだ。その怒りの理由が何処から来ているか、察していたのはおそらく、青年と人間の女だけだろう。
そんな状況を、幼馴染はわけがわからない……という風に首を傾げていた。
「……アナタ……『子供攫い』、なのよね?」
少年を見つめて、落ち着いた様子で口にした幼馴染。少年は青年の眼から逃れるように視線を向ける。
「私――……『子供攫い』のヒトに会ってみたいって、ずっと思ってたの」
幼馴染は何処か、静かな覚悟を伴った声で、好奇心や憧れとは違う確かな強い感情を向けていた。
「まさかこんなに若いヒトなんて、思ってもみなかったけど。今思えば、ピアともちゃんと、話をしてみたかったわ……私が『五色のケモノ』に入れてもらったのは、『子供狩り』が嫌い――それも大きかったんだから」
昔から幼馴染は、存在を隠された青年の双子を気にかけていた。自身は大きな力を持たず、化け物としては弱い鳥の幼馴染は、自らの姉妹を奪われ、他の家族も殺された経緯を持っている。
力さえあれば「子供攫い」にも加担したかったと語る程、はっきりとした志を青年より持っていた。
そうしたわけなので、その気の強い幼馴染は断言する。
「ライザがいいって言うんだから。しばらくはここにいて、『子供攫い』の復活方法でも一緒に考えない?」
「――いや、ハーピア。さすがにそれは……」
あっさり過激なことを勧める相手に、本来穏健な青年は言葉を濁しかけたものの、
「……まぁ。……それも、アリと言えばアリなのか」
その言葉を否定せずに、幼馴染をじっと見上げる少年の目を見て、言葉を呑み込んだのだった。
ようやく少し、生気が戻っていた紅い目。
いつも通り黙る青年の肩で、双子の蒼い獣も心なしか、うんうんと頷いていたようだった。
+++++
「……はぁ? 今――何て言ったの、リーザ?」
多くの災難から六日が経過し、第五峠は大分と落ち着いていた。
「いや……だから……エアの姐貴に、『占い』を頼みたくて、来たんだっつーの」
第五峠で療養を続ける、同郷の姐貴分の女性がひたすら目を丸くする。その前でバツが悪そうにする双子の後ろで、青年は溜息をついた。
「すみません、レインさん……こうでもしなければ、多分俺達、ピアの通行証を隠し通せませんでした」
「それはそうだけど――……だからって………」
個室のベッドの上で、横座りをしていた女性は、どうにも笑いを堪えられなかったのか、膝を抱えて体を震わせ出した。
「だからって、通行証を飲み込むなんて――……しかもその後、飲み込んだ通行証が、行方不明。ですって?」
半分涙目でぷるぷると震え、双子を見上げる。とにかく双子の弟はあえて理性的な声色で、気まずげに目を逸らす。
「魔法具っちゃ、魔力の塊みたいなモンなんだから。気であれ魔力であれ、何かが満ちてる体内に隠せば、紛れてごまかせるかなって思ったんだよ」
そしてそれは成功だったと、あくまで明後日の方向を見て言う。彼ら双子を幼い頃から知る女性は、言葉の続きを察する。
「それでその後、何処からも出てこないって。私の所にまで、わざわざ相談に来たわけ?」
相当苦悩しただろう双子を察するように、ひたすら大笑いする。そのやり方は覚えとくわ、と、楽しげに一旦まとめた女性だった。
軍の探知機を逃れるために、体内に隠した通行証について、双子はどうしてもそれがどうなったか知りたいようだった。
「レインさんの『占い』なら、リーザの体の何処に通行証が隠れてるか、わかるんじゃないですか?」
「千里眼」の特技をこの第五峠では、女性は他の患者の診療の協力に使っている。それを思い出し、頼らざるを得ない青年達だった。
「そうね。どうしてなのか、心臓の真上に異物があるみたいよ?」
「って、心臓!?」
そしてあっさり、通行証の位置を看破した「千里眼」の後ろで、先程からずっといた医者が、難しげな顔で双子の兄弟を見た。
「……飛竜に変化しつつ、魔法具を飲み込みつつ、更に飛竜を小型化したというなら、そのドサクサで食道から心臓の方へ出ていったんだろう」
下手したら死んでたぞ、と冷静に言う医者に、げーっと双子は胸元を掴む。
「自身でない飛竜を小型化できるような、ライザの特技は大したものだが。完成された個体に介入するのは、そうした危険を伴うことは、理解しておいた方がいい」
「そうなのか……全然深く考えたことがなかった……」
大したもの。という医者の評価そのものが、青年にとってはわけがわからなかった。
弟を小さくできる特技、ただそれだけのささやかな力に。
どうやら通行証があるらしい胸の中央を掴みながら、双子は赤い髪の医者を見つめる。
「ところでコレ、取り出すことってできるのかよ?」
「取り出したいなら、手術が必要だな。そこまでしてわざわざ、軍にも気付かれるリスクを負うことはお勧めできない」
隠すための行動だったのなら、そのままにしておけ、と淡々と医者は所感を口にした。
「取り込んだ結界道具の魔力を、今後は魔道として意識して放て。そうすれば体内にあっても、国境を越える分には支障ないはずだ」
「ってことは――軍にも見つからず、でも通行証としての機能は残ってるってか?」
それは美味しいな、と。青年と二人で一つの通行証を使うことが面倒な放浪好きの双子には朗報だろう。
「そうね。ピアも軍にそれを返すより、リーザが持ってる方が絶対喜ぶわ」
気丈な声で双子に微笑む女性に、双子は淡々と、へぇ。とだけ無表情で返し……掴んだ胸元をただ見つめていた。
場が一通り落ち着いた後に。
「ところで――あの『魔』はどうしたんだ?」
青年が数日前、まだ状態が悪い患者を連れ帰ったことを医者は気にしていたようだった。
「ああ……怪我はまだ、あまり治ってはいないけど」
青年は心なしか、穏やかさも混じった声で先を続ける。
「でもようやく……ご飯を食べてくれるようになった」
あらあら、と。驚きながら嬉しいように反応する女性は、その「魔」が青年が提供する食事をとらない、と愚痴を零していた相手だった。
「自分だけでもサライをやるぞ、って躍起になってるかもな」
双子の方は冷静に口にし、問題が解決したわけではない、とも先を続ける。
「『魔』としての栄養補給も、必ずどっかで必要になるけど。傷を治すって意味だけなら、まぁ進歩だな」
「そうよね。食物の栄養なんて大したことないって、リミット君、効率の悪い食事を嫌ってたものね」
ヒトを栄養とする「魔」にとって、それは当たり前だというが。だからといって、食事が全く無意味なわけでもなかった。
「血をくれてたピアがいないんじゃ、ひとまずはそうするしかないでしょうし。頑張るぞって奮起してるのね」
最早、なりふりかまってはいられなくなっただろう魔縁。しかし何故か、女性は青年の方に振り返った。
「やるじゃないの、ライザ」
「は?」
つい先日に、この世界で唯一の拠り所を失っただろう魔縁――それが立ち上がろうとする力、その出処を知るように言う。
「あの子をそこまで怒らせることができるの、多分貴方くらいよ」
相変わらず、褒め言葉ではない内容で、何故か笑う女性だった。
外は大分日が落ちたようで、暗くなってきた室内に、医者が灯りへ火を点した時だった。
「――あ」
ちょうど扉をノックしようとした人影が、扉の隙間から医者と目があったらしい。医者が何かを言う暇もなく、同郷の女性が声をかけた。
「あ、ミリア、いらっしゃい。入って入って」
その距離では、場の誰もがすぐに、影の主に気が付いていた。
「……こんばんは」
注目が集まったためか、遠慮がちに入ってきた黒髪の少女は、どうやら仕事が終わったばかりらしい。
「最近毎日、顔見に来てくれるのよね、ミリアは」
言う通り、嬉しそうにする女性の元を訪れるのが、少女には習慣化したようだった。
「母さんは大丈夫なのか? ミリア」
元々は、病気がちの母の医療費のため働く少女に、同じ経験のある青年は心配げにする。そんな青年に、少女は事も無げに答える。
「洪水の日から、ずっと意識が無いの……多分、デュラのこと、薄々気づいてるんだと思う」
「……」
第五峠を襲った洪水の正体――大いなる自然の脅威を、かつて伴侶にしたはずの人間の嘆きを、少女は冷静に受け止めている。
「もう長くないと思う……だからピアのことも、何も言ってない」
これ以上その母に、重荷を背負わせまいと。後悔のないよう、独りで重い現実を受け止めてきた少女の目には、多くの決意が満ちていた。
「あまり無理しないのよ、ミリア」
穏やかな微笑みで少女を見る女性に、少女はこくりと頷く。
「何かあれば、私やライザ……――それにリーザを、いつでもこき使いなさい」
「へ」
「え?」
「え……」
呆気にとられる青年達に構わず、にこやかに言い切った女性の前で、少女はキョトンとしている。
「そうそう、リーザ。『占い』の対価に、一つお使いを頼んでいいかしら?」
更にたたみかける女性は、まさに容赦なく、双子の首根っこを掴む勢いでそのお願いを口にした。
「近い内に、ミリアのお休みがとれた日に、ミリアを第一峠に連れていってあげて。勿論、送り迎え両方込みでのお話よ」
「は……? 何でオレが?」
「別に付添いは、誰が何人いても自由よ? 何ならライザにも、お手伝いを頼んでくれてもいいけど」
「?」
そこで首を傾げる青年に、しかし双子は――
「……そういうことかよ」
ちっ、と。面白くなさ気に、女性からも青年からも目を逸らした。
「……」
そんな若者達の遣り取りを、医者は複雑そうに見守っていた。
+++++
騎士団の見習いである黒髪の少女は、災害から大忙しだった。巻き込まれた当初と、それからニ週後にやっと、異例の早さで休みを貰えていた。
「――じゃ。オレは宿で、日帰り温泉でも入ってくっから」
雪山の上の第一峠では数少ない施設に、双子の弟が青年と少女を送ってくれた。少女の用事が終わるまで待つ、と双子とはそこで別れる。
何故か付き添うことになった青年と、少女は二人で、ザイン領の第一峠ディレステア大使館の周囲を歩き回っていた。
「……ミリアはここに、何の用があるんだ?」
青年達の姐貴分と話す内に、少女は第一峠に行きたい、との思いに至ったらしい。事情を全く知らない青年は、ただ不思議に首を傾げる。
「うん……今日はただの、下見みたいなものなの」
その峠がいったいどんな場所であるのか、それを知りたかったという。こうしてぶらぶらと歩くことこそ、目的と言わんばかりだった。
「……」
現在雪は降っていないものの、大使館近辺の平らな銀世界から、白い帽子を被ったような周囲の森まで少女が足を進める。
「――あ」
森の大分奥まで入ると、山上の火口湖に辿り着く前に、火口湖から流れ出る川の一つにつき当たった。
「……キレイ。ザインの水って、こんなに澄んでるんだ」
雪解け水が流れる川は、上流にしては流れが緩やかであり、青年にも無色の玄い水の気がありありと視えていた。
ディレステアとザインの境である第一峠には、広大な火口湖がザイン側にある。ディレステアとザイン、そしてゾレン西部に流れる多くの川の源がその火口湖だった。
「俺達はあんまり、落ち着かないけど……ミリアには、ここの空気は合ってそうだな」
「うん。今までで一番、落ち着く所に来れた気がする」
寒いけど、と少女は、両手を温めるように息をふきかける。
「……」
発火させられる炎の血を体内に流す青年は、昔から寒さ知らずだ。それでも少女の方が居心地良さそうに、玄く厳しい空気を体中に満たしていくようだった。
化け物のほとんどは、その時在る土地によって、土地自体が持つエネルギーの影響を受けることが多い。
「ここは……ザインは本当に、自然寄りなんだな」
自然の脅威として最強と言われる化け物、「竜人」の血をひく少女にとって、純度の高い自然が残る秘境は最も相性が良いはずだ。青年にはよくわかっていた。
「俺達は逆に、ザインではあまり、動けない奴の方が多いよ」
「……ライザもそうなの?」
青年は獣寄りの化け物として、この土地との相性が特に良くはない。それでも全く気配の弱まっていない青年に、少女はそう尋ね返す。
「俺はそれで困ったようなことは、そんなにないけど。リーザやヴァルトは、場所によっては変化も難しくなるみたいだ」
そのため、ゾレンの化け物達は大体ザインを嫌う。争いを好まない――つまり戦う力を捨てた者が集まる場所が、ザインという山岳地帯の真相だった。
「元々ザインで生まれた奴らは、逆に凄く強いみたいだけど」
「……うん。自然の力を制することができれば、大陸でも沈める化け物が本当にいるって……父さんは最期まで、わたし達に、なるべく力を使っちゃいけないって言い残していったの」
少女はそこで、川辺の大きな岩の雪を払う。一休み、といった感じで、川の流れが見える方に腰かけていた。
そしてやはり悲しげに、海辺の岸壁に座っていた時のように、周囲の大気を黒く渦巻かせていく。
「だから母さんは……ずっと、ピアを許さなかった」
「…………」
「わたしは、ピアに帰ってきてほしかったけど。でも母さんの気持ちもわかって……どうしたら良かったのか、今でもわからないの」
自然の脅威の力を持った弟を、「子供狩り」に差出した姉。
その結果として第五峠は災害に襲われ、両親の懸念は現実のものとなった。それでも少女は、ずっとその姉を慕っていた。
白い川の流れだけを見つめ、俯く少女の黒い後ろ姿が、あまりに悲しげだったせいだろう。
「俺は……ピアは、間違ってなかったと思う」
青年は思わず、自分でも思ってもみなかったような言葉を、あっさりと口にしていた。
「『子供狩り』からずっと逃げてきた俺達には、偉そうなことは言えないけど」
それでも――だからこそわかることがある。少女の姉がとった行動を、青年達は断罪できない。灰色の眼を重く伏せる。
「そこで弟を差出さなければ、ピアもミリアも、母さんも……みんな、殺されていたんじゃないのか?」
青年と弟。双子の一人を存在しない者とした長い嘘。それも命がけの選択で、青年達を縛る鎖だ。
青年が徴兵されるのとどちらがマシだったのか、今となっては最早わからない。決断した両親を恨んでも仕方なかった。
「……うん。わたしもずっと、そうだと思ってた」
それでも――と、だからこそ少女は、悲しげなまま言う。
「母さんはそれでも……こんな惨めな思いをするくらいなら、いつか大きな禍を招くのなら、死んだ方がましだって……そうピアに言って、ピアを追い出したの」
「――……」
同じ人間でありながら、少女の姉は、その母の覚悟まで強く在れなかった。後の世の禍より、目前の家族を優先しただけなのだ。
「だからピアは……悪くないのに、ずっと自分を責めてた」
これまで、何度も姉を夢に見たという少女は、確信を持ってそう語る。
「わたしはわからない。ピアも母さんも、きっと間違ってない……それなら、どうすれば良かったのか。でも……」
「……?」
「エアは、ピアが偉いって言ってた。どの道どうしたところで、デュラは連れていかれたって」
それが現実、とあくまで辛辣な「千里眼」、それも人間である同郷の女性は断言したという。
「それならわたしも母さんも、犠牲になることはない。その方がデュラだって今後、自分を責めずに生きていけるって」
「ミリア……――それは」
「そう。母さんもデュラも、ピアを責めれば良くなったから。でもそれじゃ……ピアが本当に、救われない」
「…………」
その姉の助けになりたいと願った「千里眼」。「子供攫い」に力を貸していた女性の顔を思い浮かべ、青年はただ、痛ましさを耐えるしかなかった。
少女はそのまま、自身の気持ちを整理するように、姉についての話を続けた。
「エアは、ピアがうちを出た時、初めて会ったって言ってた」
何度も同郷の女性の病室を訪ねる内に、少女は様々な姉の話を耳にしたようだった。
「行き倒れてたピアを、エアのお母さん達が見つけて助けてくれたんだって。エアのお母さん達も、人間だったから」
話を聞き続けていた青年は、そこで初めて知る。
ずっと同郷であった女性が何処で、「子供攫い」に関わる根本的なきっかけを得たのか――
「子供攫い」を手伝うことこそ本命、と語った女性。それに纏わる、ある不幸な出来事がそこにあった。
――ごめんなさい……ごめんなさい――……。
「うちを出て、当てもなく進み続けたピアはボロボロだった。その頃からエアも体は弱かったけど、それ以上にその時ピアは、弱ってたって言ってた」
「……」
ボロボロの迷い娘は、しばらく女性の家に匿われた。体は少しずつ回復を見せたが、大きいのは心の弱りようだったという。
「ずっと、ごめんなさい、としかピアは言わなくて。それでも、泣き顔で笑ってた、って。エアはあまり笑うことが好きじゃなかったから、びっくりしたんだって」
同郷の女性の両親は、身元が不明の人間の娘を、第五峠の医療施設に連れていくことにした。元々体の弱い女性の受診に共だってのことだった。
「いつも、エアの『千里眼』で安全に道を行くのに。その日は、急に山賊に襲われて……そこでエアのお母さん達は……」
それは、青年も少年だった頃に知らされた、姐貴分な女性の両親の突然の訃報だった。
「山賊は人間だったから。だから、レインさんの眼でも見つけられなかったって……俺はそう聞いてる」
「うん。人間みたいな弱い気配は、エアでもわからないみたい」
安全な道を探せるはずの、「千里眼」の限界。
しかしそれなら何故その時に、体が弱く、逃げる術もない女性だけが、両親の死をよそに一人助かったのか。その頃の青年は疑問に思う余裕もなかったことが、今更、残酷な真実として浮かび上がる。
――ごめん……エア…………。
「山賊は三人いたみたいだけど。どれも特別、鍛えられたことはない人間ばかりで……人間のピアでも、武器さえあれば、何とか殺せる相手だった」
「……」
「子供狩り」で、ヒトを殺すために鍛えられてきた娘の心身。
そこで初めて、正気を閉ざしていた人間の娘は、訓練でなく本当に誰かの命を奪ったのだ。
――ごめん、ねぇ……あたしが、迷ったりしなければ……。
返り血を受けてやっと、まともな言葉が出るようになった。娘はそれまでと同じように、やはり泣き笑うと――穏やかにただ、ごめんと言ったという。
――もっとすぐに、あたしが殺していたら……エアのお父さんも、お母さんも、死なずに済んだのに……。
それからようやく立ち上がった娘は、驚くほどしっかりした様子で「千里眼」を第五峠まで送り届けた。
以後は第五峠で出会ったディレステアの人間に師事し、行方がわからなくなったということだった。
「体の弱いエアを連れて、二人で逃げるのは無理だったから。自分のせいで、ピアはヒトを殺したって……だからこの命は、ピアにあげよう。そう思ってたのにって、エアは残念がってた」
「……」
同郷の女性はそれを、困ったように笑って語ったという。人間の娘はそこで、一人で逃げれば良かったのだと。
両親を失った女性はずっと、願っていたのだろう。自分を救った泣き笑いの娘に、また会うことができたのなら、と。
何故自分だけが生きているのか、その命の意味を尋ねたいと。
「やっぱりピアは……ずっと、いい奴なんじゃないか」
その実の母と妹を、とにかく守りたかった人間。自身の経験からも、徴兵された弟が殺されるわけではないとわかっていただろう。
血縁でなくても、山賊に襲われた弱い者を見捨てることもできず、やはり自身の手を汚す選択をそこでとった。
そうして自らを守る狂気をも捨て、正気を取り戻したのだろうと、青年は項垂れた。
「……ありがとう……ライザ」
そんな姉を、救うことはできなかった。それでも慕い続けた少女は――……少女と同じ所感を持つ青年に、それだけ苦く笑った。
一通り、死んでしまった姉のことを話し終えたようだ。
黒髪の少女は無表情ながら、何かが色々吹っ切れたように、川辺の岩から立ち上がっていた。
「ごめんなさい――わたしのことばっかり、沢山話しちゃった」
「……ほとんど、ミリアのことじゃなかっただろ」
元来青年は、言葉数が少なく、喋るより聞く方が性に合う。しかし軽く不服気に、謝る少女をまっすぐに見る。
しばらく黙って、そうして少女を灰色の眼で見つめる。僅かに不思議そうに、青年を見つめ返した少女に――飾らない気持ちを、青年はそのまま口にした。
「俺は……ミリアのことが、もう少し知りたい」
「…………」
ずしん、と。まさにタイミングは絶妙の状態で――第一峠を何故か揺らす衝撃の正体を知りながらも、青年は続ける。
「いや……もう少しじゃなかったな」
そこでまた珍しく、困ったような顔で微笑んでいた青年は、
「ミリアのことなら、多分……全部知りたい」
「……――……」
ただまっすぐに、その心を、負けた、と思いながら口にした。
潮騒の唄の中では、黒髪の少女はずっと、悲しげな大気と共に在った。
この自然の秘境では、厳しい玄に満ちた水脈を確実に黒く染め上げ、本来の脅威を得た壮麗さを解き放つように見えた。
「ミリアの大切な、ピアを守ることはできなかったから」
「……」
「俺に何かできることがあれば――ミリアの力になりたい」
たった一人で、惨い現実を背負った少女。これ以上負担をかけたくない。青年は迷いなくそれだけ口にし、後は黙って苦く笑う。
少女は無機質な目のまま、少しだけ不服そうにしていた。
「……わたしは誰にも、守ってもらいたくはない」
……それがここまで、少女の歩みを支えてきた原動力で。
幼い頃から頑固な少女がただ一つ、大切な周囲に望んだことは。
「守っていらないから――……いなくならないで」
「…………」
揺らぎなき少女の青い目は、その一念のみを常に訴えてくる。
そうしていつも、自らとそれ以外の間で揺れる青年に、確かな安息を与えてくれる。
「俺もミリアに……一緒にいてほしい」
そう返して、冷え切った少女の手をとった青年に、少女も強く手を握り返し……青年の鼓動を、そのまま受け取っていた。
+++++
「子供攫い」首謀者が潜伏していた山奥の隠れ里には、しばらく「西派」の軍が頻繁に出入りしていた。里一帯の空気があちこちで張りつめていた。
「ライザ師匠……自分達はいつまで、ピア師匠のことは知らないなんて、心にもないこと言わなきゃいけないんスか?」
「……すまない。今はただ、里を守るために我慢してくれ」
長老の一喝で、里の若者は「子供攫い」関係者については硬く口を閉じている。その鬱憤をこうして受け止めるのが、最近の青年の日課だった。
「『五色のケモノ』もあれから、新任務が回ってこないっスし。自分は、自分は何か働きたいでありまっス!」
「ありがとう……第六峠での和平交渉の設定のために、『西派』とどうやって話をするかずっと相談中なんだ」
そこでようやく納得したように、下っ端の若者は頷いたものの。
不意に、里の実力者の一人たる青年を不思議そうにじっと見つめる。それにしても、とまた残念そうにした。
「最近師匠の『飛竜』、見かけないっス。師匠、どっか体調でも悪いんじゃないスか?」
「……」
少し前は、以前より頻繁に見かけられた蒼い獣。青年の肩が定位置の飛竜の不在に、若者は素直な思いを口にするのだった。
死んだ人間の女の通行証をその身に受け取り、双子は最早、二人で一つの通行証を使う必要がなくなった。次はいつ帰るとも知れず、里を後にしていた。
「何かあったら、クランか若祭祀に言ってくれ。オレまで連絡とれるはずだから」
「……」
前者はともかく、里の教会に少し前から赴任した祭祀は、青年にはまだあまり信頼できる相手ではない。
というのも、祭祀というのは仮の姿であり、実際は国王直属「王属部隊」らしい祭祀の目的がよくわからない。「子供攫い」を双子と共に手伝っていたと言うが、青年はその祭祀に自ら近付こうとは思えなかった。
しかしそんな選り好みができる状況は長くないことも、青年は知っていた。
「クランはもう……今年いっぱいで、ザインに帰るんだろ?」
「ザインっつーか、ディレステア国内の第二峠ザイン大使になるっつーてたけど?」
第一峠のザイン大使である兄を持つ医者は、本来、家が勝手に定めた大使の道に反発し、第五峠に飛ばされていた身上だった。
「エアの姐貴も大したもんだよな。それをクランに自分から、家の仕事をやる気にさせちまうんだから」
「……確かに、クランなら本来、向いてそうだと思うしな」
大使館とは、砦に囲まれた国ディレステアの、限られた六つの入国の扉――「峠」の関所だ。入出国者の管理を任される大使の仕事は、誉れが高いとはいえ、基本は年中無休で責任も重い。大使館を通した異国人への責任や、近隣の軍との付き合い、安全管理まで管轄とされる激務だった。
「医療技術も、あの辺は病院がねーから重宝されるだろうしな。物流の要の第二峠だから、第五峠の物資不足にもいくらか貢献できるだろうって、そこまでもう考えてたぜ」
そうした、あまりに有能で勤勉な医者の適性を、同郷の女性は早々に見出していた。生家では異端とされ、軽視されていた医者の価値を誰より誇り、笑って背中を押したのが「千里眼」――その眼に関係はなく、医者個人をただ慕った人間の女性だった。
「多分相当忙しくなるぜ。知り合いにも滅多に会えないだろーな」
「それでもレインさんは……クランと一緒に行く気はないのか」
女性を縛った「子供攫い」の仕事はもうない。それなのに――と青年は俯く。
双子が淡々と冷静に、大きな溜め息をついた。
「そんなの最初から、エアの姐貴の逃げ口上だろ」
「……」
「『五色』がまだ気になるってのも、本当だろーけど。自分はただの現地妻だって、ずーっと言ってたからな。クランには、とことん……この先の負担はかけたくないらしい」
「……里の時と、結局は一緒か」
人間には珍しく、光に嫌われた同郷の女性。儚くも整い過ぎた容姿と、気安さを併せ持つ女性は元々、青年の悪友を始め、里にも女性に憧れる者は多くいた。それを悉く、ただ一言を口に拒み続けていた。
「自分は長くないから――そればっかりだよな、エアの姐貴は」
「……クランはそもそも、いつかいなくなるからって、やっとレインさんのガードが緩んだ相手だったっけ」
人間の身で「千里眼」を駆使し続けてきた女性の身体は、少しずつ削られていく。それを感じながら、それでも女性は、その力だけが自らの役目と定めてしまったのだと、青年達は知っていた。
ああ、そうだ、と。
家を出る直前に双子はにやりと笑うと、青年の方を向き、声色だけはいつになく穏やかに口にした。
「ミリアにオレとの連絡法、教えとくよ。何かあればミリアに言えば、多分大丈夫だろ」
「――……」
騎士団の見習いである少女は、現在「魔道」を勉強している。魔道の術を介し、遠隔でも連絡をとりあえる双子や医者と、頑張れば同じことができるはずだと笑う。
「それは……凄く助かる」
だろ? と笑った双子は、その後は振り返ることなく足を進めた。
ずしん、と。
もう何度目かもわからない、遠くの空から伝わる痛み――
青年はただ、空よりも蒼い獣の、無事だけを願った。
+++++
それから年末までは、驚く程にあっという間だった。
「ライザ、最近はリミットはどうなの?」
魔縁と二人、小さな家で過ごすのに慣れる間もなく、頻繁に出入りするようになった幼馴染が今日も現れる。
「相変わらずだ。毎日川辺で、日がな鍛錬してる」
青年達が和平交渉の設定に走り回る一方、魔縁は寡黙にこの家に留まり、鍛錬の成果らしい魚を日々無表情に持ち帰っていた。それを青年が静かに裁き、二人で無言で食べるという生活が、最近の日常だった。
「ハーピアのおかげで、何とかヒトは食わずに済んでる」
「そう? それならいいけど。私なんかの力でも役に立つことがあって良かったわ」
長老、その孫と共に鳥の家系である幼馴染は、小さな鳥達と魂を介して繋がっている。その感覚を共有して離れた場所の出来事を見聞きし、小鳥をそのまま使役することもできる力の持ち主なのだ。
「でもあれだけ鳥の魂を食べて、その内飛んでっちゃわないか心配だけど」
明確な我を持たない小さな魂を集め、魔縁と同一化させる。ヒトの血肉だけでなく魂も糧とする悪魔のような方法を使い、魔縁を助けることを提案した幼馴染に、初め青年は驚くしかなかった。
「……長老はもう、怒ってないのか?」
「そりゃーね。あの子のために村の家畜一棟分消えるよりは、私がちょっと頑張るだけでいいなら当然よ」
そもそもは、体の弱った魔縁がこの村の数少ない動物資源に、夜な夜な吸血してまわるという怪奇事件が発端だった。
それで咎められた魔縁を、青年と共に庇った幼馴染――戦闘は不向きでも数多な小さな鳥と繋がる化け物に、不思議そうに青年は尋ねる。
「ハーピアは……仲間を食われて辛くないのか?」
双子の弟が時に鳥を実際に食べることも、幼馴染は嫌がっていた。魂が繋がり、感覚を共有するということは、いわば自分の半身が食べられているのと同じだ。
魂だけを食べさせていると言っても、本質は近い。小鳥の体はそこで死に、その都度幼馴染には喪失感があるはずだった。青年に言わせれば、幼馴染の気力――強気さが少しずつ失われていくように視える。
「それがね――何て言ったらいいのかしら。食べられても私の鳥達はちゃんと、リミットとして生きてる感じがするの」
青年が出したお茶に口をつけつつ、青年の密かな見立てを裏付けるように、幼馴染はいつになく穏やかに笑った。
「それに、私はリミットに強くなってほしい。『五色』の若い子達も、リミットに刺激を受けて頑張ってるしね」
年末まで伊達に時間は過ぎておらず、青年の周りでは様々なことが変化をし始めていた。
「年明けにはいよいよ、旧王城で『西派』と話ができるんだし、私達がいなくても、みんなで里をしっかり守ってほしいわ」
「ああ。第六峠はトラスティが前から話をつけてるし、後は王城の『西派』と話をつけるだけだ」
新たな国王の力が及ばない、旧勢力の急進派である「西派」。敵対派閥に青年の心持ちは重かった。
「リーザがもしも帰ってきたら……リミットのこととか、少しでも喜んでくれるといいんだけど」
「……」
もう何ヶ月もの間、青年の双子は帰っていない。
「そうだな。リミットは随分、かっこよくなったな」
「あれくらいの姿なら、戦い慣れた男の子の勲章って感じよね。本当……ピアにも見せてあげたい」
魂を与える代償に、と魔縁は幼馴染に引っ張られて第五峠に何度も連れていかれた。そこで全身の火傷痕の治療を受けた。それもディレステア王女の口添えで、王女と懇意である通称「魔女」の手によるためか、ごく短く尖った白髪、皮膚が硬く張り詰めた顔ながら、人並みの姿を取り戻していた。
「それで――俺は本当に、王城に一緒にいかなくていいのか?」
青年がずっと気にしていた、「五色のケモノ」の相談結果を暗い顔で尋ねると、幼馴染は苦笑する。
「だってリーザが、ピアのことがあった時、『西派』総帥に姿を見られたかもしれないんでしょ? そっくりなライザが怪しまれたら大変じゃない」
「…………」
「ライザは第六峠の自治団や、ディレステア軍と話をつける。それで決まってるんだから気にしないでよ」
こうして妙に優しい幼馴染は、魔縁と第五峠に度々足を運ぶ内、峠にいる者達と会うことが増えたといいう。
「エアもミリアも、いつもライザのこと心配してるんだから。ライザもいつまでもしょぼくれてないで、『五色』リーダーとしてバリバリ頑張ってよね!」
「……俺はそんなに、変わったつもりはないけど」
双子がいないことで、青年の覇気がない。幼馴染はこの家に足を運ぶ理由を、そう言うのだった。
「……」
幼馴染が帰った後、翌日から第六峠に出向く準備をしつつ、青年は苦い色の顔で呟く。
「『西派』に会わないで済むのは――助かるけど」
ずしん、と。今も度々青年の奥を揺らす獣に……いつまでも気が付かないふりをする。
「『子供狩り』の奴らなんて……誰一人、顔も見たくない」
そんな青年を無言で睨む、鍛錬から帰った紅い目で白い鳥頭の少年の姿が戸口にあった。
「……」
「リミット。ちょうど良かった、明日からまた留守を頼む」
「……」
「年明けの王城の件が終わるまで、俺もあちこちに行くから、今度の留守は長くなる。もし里に何かあれば、バルニカス達と協力して戦ってくれるか?」
鳥頭の少年は不機嫌そうに、黙って頷いた。
良かった、と僅かに微笑む青年に、黙って魚を差し出す少年は、毎日難しい顔をしている。
「今じゃリミットが若手のホープだな。武技は俺やヴァルトもとても敵わない」
「……」
見た目は十五歳、中身は十歳というちぐはぐな化け物は、居心地悪そうに食卓の椅子に座る。青年は少年に背中を向けながら、四匹の魚を一つずつ三枚におろしていく。
「軍はあまり、武技は重視しないんだな。リミットもピアも、大きな力は無くても戦闘能力は高いのに」
香料をすり込んで串に刺した切り身を、青年の特技――飛竜たる己の血で燃え上がらせると、簡単に焼き魚が完成する。この方が魔縁の少年も食べる気になるようで、普通の火はあまり起こさなかった。
ついでに釜戸の上で温める薬草湯を混ぜつつ、青年はいつも、こうした料理中には同じことを考えていた。
――早く元気に、いい子になるといいのに。
それは根拠のない願望に近い。人並みの姿を取り戻した魔縁の険しい顔は、気難しいだけの子供に見えるようになった。喋るのが苦手で不器用な弟を持ったような兄心が、青年の中でむくむくと育ちつつあった。
「こう精確に、水中の魚の目だけを射抜くのは俺にはできない。おかげで傷の無い新鮮な魚が食べられるな」
目を合わせようともしない少年が、その武技を褒めるとますます不機嫌そうになることを、密かに青年は楽しんでいた。
この少年がどうして火傷を負い、軍から見放されたのかはわからなかったが、魔道と剣技に秀でた「王属」祭祀の、少年への冷徹な言葉を、青年はふと思い出した。
――粋がるな。脱落者。
そして同時に、連鎖的に違う記憶が呼び起こされていた。
――……そんなの効かないよ。……脱落者。
青年は実際にその敵を見ていない。だから今まで気付けなかった。
その一言は、同じように「子供狩り」にあった子供の言葉――ディレステア王女から聞いた話が今更に、青年を愕然とさせた。
「……――何で……」
「……?」
明らかに突然空気の硬直した青年に気付いて、少年が怪訝な顔をする。
「リミット。君は、ピアの弟には会ったことはあるのか?」
「…………」
少年は黙って首を横に振り、一番懸念された反応に青年はきつく顔を顰めた。
「じゃあ、何で……」
それなら何故その敵は――この魔縁が、「子供狩り」の「脱落者」であると知っていたのだろうか。
「子供攫い」の女の傍らにいたこの少年が、女と同じ「子供狩り脱落者」だと身上を知られている。そうなるとこれまで、少年が「子供攫い」の一員と追求されていないことの方が不自然ではないのか。
そもそもその敵は、殺した女を「子供攫い」と知らなかった様子だったと、青年は王女から聞いていた。
――ボクはただ、臣下の仇敵がいたので、討伐しただけですよ。
女の赤い鎧が、「子供攫い」首謀者のものと似ていた。それで女の正体は知られたわけだが、女が殺された理由はそれではなかったはずだ。
――後は、君のものになるはずだった力を取り返すだけだ。
「子供狩り」に弟を引き渡した姉に、成長した弟が復讐した。それで筋は通っているが、秩序を求めるゾレンの法的には本来アウトだ。その人殺しが糾弾されなかったのは、女が国賊だったからなのだ。
背後にいた西派の総帥たる旧王属は、その子供の力を利用し、「子供攫い」である女を討伐したかったのだと青年は思っていた。しかしそれでは、少年が追求されていない理由がわからなくなる。
あの「旧王属」――国王の腹違いの弟の目的は、いったい何だったのか。
「リミットのことは……攫われただけだと、みなしているのか?」
「子供攫い」。それは本当にあの時偶然知られた、旧王属にはどうでもいい事柄であるのか。
もしくはあえて「子供攫い」の首領だけを討伐し、部下を放置する理由があるのか。
――この女の亡骸はボクがいただきますよ。
女の亡骸を奪った旧王属は……それ自体が目的だったとすれば。
利用価値があるとすれば、女を強者たらしめた鎧に填まり、力を与えた漆黒の「竜珠」に他ならない。それを狙った者が何をする気か、今更ながらに青年は背筋が寒くなったのだった。
各々の目的地に旅立つ前に、翌朝一番に里の入口に集合した「五色のケモノ」に、青年はその懸念を相談してみた。
「そうやな。あの魔縁君に今後、『西派』の奴らが気が付いて追求してくる可能性は確かにあるわな」
「バカが。既に知られてる最悪の可能性を、先に考えろ」
「五色のケモノ」の表の顔である悪友と、その祖母にはとても見えない若々しく筋肉質な体つきの長老が、暮れの厳しい冷え込みにも関わらず、薄着に肩掛け一枚という姿で、両腕を組んで考え込む。
「知られてるのに放置の場合、『子供攫い』に手を出すな……そんな影の意志を感じるね。ピアから『竜珠』とやらを奪える理由、機会は必要だったが、ピアが『子供攫い』と最初からは追求できない……ややこしい事情があるんじゃないか?」
「どういうことですか? マザー」
「考えてみろ。ピアの『竜珠』を欲しい奴が、誰かからピアの情報を得たとして、その情報源、証拠はって話になるだろ。それをとやかく言われないために、ピアを『子供攫い』の姿で誘い出して討伐は可能な形にしたが、他の『子供攫い』については何も知らないことにしておきたいとしたら……だから部下の魔縁のことも気付かない、情報源など無いとアピールしてんじゃないか?」
しかし敵はそれを、幼い子供の脱落者という一言にまでは徹底できなかったのではないか、と長老が口にする。
この国は化け物の大国と言えど、むしろ秩序は整い、理由も無しに互いを害して良いような野蛮な土地柄ではない。
女を殺す大義名分に、「子供攫い」首謀者である確信だけは先に必要だと、長老は見切ったようだった。
幼馴染も眉をきつく顰めて長老を見る。
「じゃあ、情報源を無いことにするために、残る『子供攫い』に手を出せない?」
「アタシはそうみるよ。可能性として、情報源から情報提供の条件として、それを飲まされたんじゃないかね」
「それやと、内通者が誰か、あのねーちゃんの周囲にいたんか?」
「情報源を徹底して知られたくないとすると、傍にいた誰かが確かに怪しいわよね」
誰もがそこで、苦い顔で俯くことになった。
「あの第五峠の大洪水自体そもそも……ピアをおびき出すため、仕組まれたものだった気がしてくるね、こうなると」
殺された人間の女の、不思議な真直ぐさを長老は気に入っていた。重い言葉に幼馴染が痛ましい顔で話を補う。
「ピアの妹やお母さんがいる第五峠で、大洪水なんて起これば……ピアはそこに武装して『竜珠』を持って向かうだろうって、誰かがピアを罠にかけた?」
「ついでに第五峠で騒ぎを起こせば、敵方……『西派』には、和平交渉なんてものも潰せてちょうど良かっただろうね」
長老はそして、当事者であった青年を尋問するように改めて見た。
「あの日、どうしてアンタ達は第五峠に行った? 誰がピアに誘いをかけたんだ、ライザ」
「……レインさんから連絡が入ったんだ。第五峠でミリアが、洪水に巻き込まれていると」
「連絡って?」
「レインさんからクラン、クランから――若祭祀を通してだ」
口にしながら青年はまたも、愕然とする事実に気が付く。
「脱落者」という単語を、青年の前で初めて口にしたのは、紛れも無くその祭祀だ。女が「子供攫い」の首謀者だと、間違いなく知っていた相手なのだ。
祭祀が王属部隊で「子供攫い」関係者と知らない他の者達は、疑う発想はないようだった。
「何やねん、それならレインさんかクランが怪しいっつーことになるやんけ、このアホババァ!」
「アホはてめぇだ! エア・レインがそうしても当たり前ってくらいアタシはわかってる!」
そうなると、と長老は悩ましい顔をする。
「若祭祀が、エア・レインから連絡があったと嘘をついたんでない限り、こっちの線からは探せそうにないね」
「……――……」
黙り込む青年は、その祭祀――「王属」がそうした状況に乗じ、女を罠にかけたという疑惑を拭うことができなかった。
「とりあえずアイツのことは……信用しない方がいい」
確信はないため、重い声色で一応警告に留める。余所者である相手を元々良く思っていない場の面々は、納得したように頷いたのだった。
+++++
中篇・転
旧王都に向かう「五色のケモノ」を見送った後、第六峠に向かうはずだった青年は、里の教会へと足を向けていた。
「おや、ライザ君? どうしたんですか、ミリアさんとの通信がご希望ですか」
にこにこと青年を迎える祭祀は、今日も頭まで祭儀衣で包み、人の好さそうな翠色の垂れ目で、筋肉質な痩せ型の若い男なのだが……。
「……今日は、アンタに訊きたいことがあって来た」
遠隔通信のような魔道だけでなく、仕込み杖の剣を持ち、非常なる戦闘力を持つ男は国王の数少ない「王属部隊」の一人だ。「子供攫い」の女を信頼していた国王の意に反することを企むとは、あまり思えなくもあった。
「アンタはどうしてこの里にいるんだ? トラスティは何故、アンタをずっとここに置いている」
元々怪しい相手が更に怪しい者になった。その疑念は払拭できるものではなかった。
「また唐突ですねぇ。『五色』幹部さん達が里を空けるから、急に私のような余所者が気になってきたんですか?」
門前で掃き掃除をする祭祀は、図星をつかれて不服げな青年に楽しげに笑う。
「ふう。国王様もお気の毒です。私がここにいる理由、ライザ君は気付いてないんですか?」
「……アンタは俺達のために、ここにいると?」
「他に何があるんですか。西に東に、国の団結と忠臣を求めて国政をほっぽり走り回る国王様に、今何が一番必要であるとお思いですか?」
――お前達が私の『王属部隊』とでもならない限りは。
真面目で常に余裕の無い国王の物憂げな表情を思い出し、思わず青年はう、と息を飲む。
「トラスティは、国政をほっぽってるのか?」
「あれだけ不在が重なると、実際の国政は祭祀長――いけ好かない我らが上司が牛耳ってますよ。政務部はほぼ、あのクソジジイの手中にあります」
珍しく祭祀が、素直な感情を声色にのせて言った。
「ここは国王様が『王属』に迎えたい二人もの誰かの故郷で、オマケにもう一人が殺される直前まで滞在してたんですよ。私に様子を窺わせるのも当然でしょう」
「……だからって、アンタがずっとここにいていいのか」
「私は情報収集と説教、剣しか能がありません。西部の様子をついでに監視するのに、旧王都や第六峠に近いこの里はもってこいの場所ですしね」
この祭祀は魔道を嗜んではいるが、通信や遠見など足場固めの系統が主だ。化け物としての力はそう強くないのだと、真面目くさって語る。
その点祭祀は嘘を言っていない。強い「力」は視えない相手に、青年は黙り込んだ。
「そういう意味では、ライザ君は私と対極をなすタイプですね。君は強い力を持っていますが、魔道も無理の上、ヴァルト君達のように効率良く解放できる『意味』を持っていない」
強力な魔道を扱える双子とは違い、青年はそちらの才能は無い、と過去に見放された経緯がある。
「君みたいに『気』は豊富でも、そこから魔力等の原動力を造れない者は、だから通信のように簡単な魔道すら扱えないんです」
ぐ。と、第五峠の少女との通信に祭祀を頼るしかない青年は、弱味を捉まれるように顔を顰める。
そこで祭祀は、不意に微笑みを消した。
「魔導の適性たる魔力がなくとも、生まれながらに『意味』を持つ者は、『意味』に沿う『原理』は利用できます。恐ろしいことに君の眼は、その『意味』に非常に敏感ですね……ともすれば『意味』の拡大解釈・応用までできてしまう」
「?」
そうして青年は実の所よくわかっていない「意味」などについて、改めて説教を始めてしまった。
「『意味』とはつまり、君がここにいる理由――担う『力』、適性や血統、才能のことです。ヒトは生まれ持つ素質しか本来育めませんが、それを可能な範囲で代用するのが魔道であり、魔道とは世界を動かす『原理』に働きかける力です」
「……」
「魔道も勿論ヒトを選びますし、原動力も体系も様々ですけど。ミリアさんのように血統通りの使い方を学ぶのが一番適切で、上達も早い……ヘルシャ氏も驚いているようですよ」
少し前からその竜の血をひく少女は、母が亡くなったのを契機に騎士団の見習いを辞めた。第一峠の大使、魔道の大家で広く治水を司るフィシェル家に、当主の弟の勧めで留学を始めたのは青年も知る所だった。
そのため少女は、以前に青年と第一峠を下見に訪れたのだ。
その少女のことが話に出たせいか、祭祀は不意に嘆息していた。
「しかし……ピア・ユークを失ったのは痛恨でしたね」
「……――」
そこで青年は改めて、ここに立ち寄った目的――祭祀への不信感を思い出し、タイムリーな台詞に言葉を呑む。
「国王様は気落ちされています。和平の件も『西派』と話など、国王様がお元気ならもう少し早く決着したでしょうが……今は君達に動いてもらうしかなさそうですね」
心から残念そうな祭祀に、青年は当惑するしかできなかった。
この祭祀を疑うべきか――何が起きているかわからない現状に。
教会を後にした青年は、予定通りに第六峠へ歩き出した。
「リーザは……アイツを信用しているのか?」
未だに祭祀には、双子のことをきかれても青年は白を切っていた。
「アイツに弱味を認めたら、利用される気しかしないぞ……」
しかし留学した少女と連絡をとるには祭祀に頼るしかない。それで教会を訪れる機会が増えた青年だった。
「……第五峠ならまだ、会いに行きやすかったのに」
ふう、と青年は、少女が留学する直前にかわした話を思い出す。
――デュラを止めるために、わたしが強くならないと。
第五峠に大洪水を呼び、今も謎の災害として騎士団の追及から身をかわす弟。少女は必ず見つけて償いをさせる、と青年に決意を打ち明けた。
――でもミリア……ピアはそんなこと、望んでいないだろう。
竜の血をひく少女をなるべく荒事に巻き込みたくなかった姉と同じように、青年も少女には、騎士団という力の中に隠れていてほしかった。
――……ピアは、死なないでねって、わたしとの約束を破った。
姉が過去に家を出る時、それだけは必死に、少女は声をかけたという。
――だからわたしも……ピアとの約束は守らない。
姉も母も失った少女は、震える声を絞り出す。最早戦いを拒む理由はないと、青い目にただ悲しみをのせて。
「……みんな、頑固な奴ばっかりだな、俺の周りは」
青年の頭にはもう一人、その場にいた同郷の女性の達観したような声が響く。
――大丈夫よ、ライザ。考えようによっちゃ、ミリアにとってはこれ以上安全な行先はないわよ?
「ザイン」という争いを嫌う中立地帯で、有力種である治水の「フィシェル」家は、そもそも水脈を司るタイプの竜には、力の系統が最も近い化け物になる
――ザインでは異国、異種間の揉め事は最大の禁忌よ。ミリアは今後、基本は同じゾレン人にだけ警戒すればいい。
だからこそ「千里眼」も、主治医でフィシェル家の直系である赤い髪と目の男も、少女に第一峠へ留学を勧めたことは青年もわかっていた。
「そこまで言うなら自分も……クランの所に行けばいいのに」
年明けにザインとディレステアの後一つの国境、「第二峠」に赴任してしまう主治医の誘いを、同郷の女性は頑なに断っていた。それでこの寒い季節に、山奥の里という過酷な環境に虚弱な女性が戻ってくることを、青年は心から悩ましく思うのだった。
あくまで心を許せる所は故郷しかないのだと――色無き女性の虚ろな微笑みを。
同じ源から流れる川、第六峠と里にも繋がる川沿いを北上し、様々な思い出がよぎる中、青年は第六峠に辿り着いた。
誤算としてはたった一つ――川辺の道からは、第六峠の要所である砦のディレステア大使館に近道があると、少し前に第六峠に詳しい国王から教えられており、何の気無しにその近道を使ってしまった。
「貴様、何者だ!? ゾレンの化け物か!?」
「――あ」
青年の知らない言葉を喋り、どう見てもディレステア正規の軍の一団が、極秘である潜入路の一つに現れたゾレン人に警戒しないわけがなかった。
「この道を知った以上、生かしてはおけん!」
「え?」
一斉に銃口を向けられ、ディレステアの言葉を話せない青年にできるのは、諸手を上げて、更に怪しまれることだけだった。
「その手の印、やはりゾレン人か!」
生まれた時に、ゾレン国民の証として刻まれる「Z」の印を持つ青年と、ディレステア人の証「D」の印を持つ人間はそもそも敵対者だ。色々な人間と関わり、敵愾心を持たなくなっていた青年の感覚こそ特殊なのだと、青年はここにきて突然自覚させられる。
「悪く思うな、ここだけは敵に知られるわけにはいかんのだ!」
「――」
わざわざそれをゾレン語で言った相手は、殺される理由くらい伝えよう、という意志が伝わる。これだけ銃撃を一時に受ければ、双子と違って一般的な体の強度の青年は一溜りもない。
そんなに重要性の高い抜け道をあっさり教えた国王に、トラスティのアホー! と頭の中で叫ぶしかない。
本当ならそこで、あまりに間抜けに、志半ばで青年は倒れていたのだろうが。
「やめな、アンタ達! 無抵抗の奴には化け物だって、簡単に命を奪ったりするんじゃないよ!」
声質は涼やかながら、片言のゾレン語で叫んでいるせいかガラの悪い感じの女性の一喝が、場に響き渡った。
「銃を下ろしな! コイツがあたしを傷付けなきゃ使うな!」
まるで一般の男っぽい軽装で、何かのペンダントを首に下げ、赤い目で一団を睨みつける女性。その出現で一団が慌てて銃口を下げる。
女性はその後すぐ、呆気にとられている青年の方へ向き直った。
「大丈夫かい? 悪かったね、驚かせただろ」
「……あんた……」
「喋りはコレだけど、ゾレン語、言ってることはわかるよ。アンタ、何者か教えてくれないか?」
「……」
色々な衝撃にまだ茫然としつつ、青年は何とか、質問に答えた。
「俺は、ライザ・ドールド……あんたの妹の知り合いだ」
「――へ?」
特に「力」はないものの、天上の系譜の人間の末裔と言われるディレステア王家。それと同じ赤い目を持った女性に、その気付きだけを口にしたのだった。
長年の冷戦でボロボロの、ディレステア大使館のロビーにて。
「申し訳ないことを致しました。まさか貴公が、アウグリス様の仰られていた『飛竜』、ライザ・ドールド殿とは」
「……」
青年を保護した重鎮らしき巨体の男と、最初に現れた金色の短い髪の女性は、その時の強気とは打って変わり、大人しげに青年の前に立っていた。
「何しろ、第五峠の二の舞にならないようにと、警備には厳重を期しているの。どうして正面から来ずに、わざわざ秘密の抜け道を使って来たの?」
巨体の男を通訳に、金髪の女性はディレステアの母語でそう言っていると伝えられる。
「……すまない。遅くなったから急いだら、そうなった」
教会に寄り道して費やした時間を悔やみつつ、金髪の女性と巨体の軍服の男を交互に見つめる。
「あの道のことは、何故知っておられるのです、ライザ殿」
「知り合いにきいた。知られて困る所なら、もう使わない方がいい」
よりにもよって、敵国の王に知られているとは思いもしないだろうが、それだけ伝える。
「それにしても、どうして……あたしが王女だと?」
バツが悪そうに青年を見る金髪の女性は、紛れも無くディレステア第一王女のアヴィス・ディレステアだと、改めてゾレン語で名乗ったのだった。
さっぱりした短い髪の第一王女は、王女として表に出るわけにいかず、一般人の偽装をしたようだった。片言のゾレン語のガラの悪さもそれを助けている。
「わかっていればあんな……恥ずかしい姿は見せないのに」
とても不服そうに母語で何かを呟いている様子は、突然命を狙われた青年から毒気を抜くには充分だった。
「アヴィス様。そもそも滅多なことでは大使館の外に出ないで下さいと、先日もあれ程……」
「わかっているわ、セルヴィ軍曹。でもせっかく、ゾレン王の御厚意で仮の通行証まで発行してもらえたのだから、ゾレンがどんな所か少しでも見ておきたいの」
?? と首を傾げる青年の前で、王女は青年には、悪態をつくような言葉で言う。
「アンタも本当、ホイホイ危ない橋渡ってんじゃないよ」
青年の知る第二王女とはかけ離れた姿に、青年は少しだけ困ったように笑った。
巨体の男――この峠の前線で戦う軍曹、口髭と顎鬚の似合う軍人は、むさ苦しい容姿とは裏腹の丁寧な物腰で青年に向き直った。
「第五峠を襲った『悪魔祓い』のような横槍が、ここでも入る可能性は第五峠以上に高いでしょう。我々は和平交渉のために、ゾレンの者に対してどういった警戒態勢をとるべきかライザ殿の意見をききたく、今日はお越しいただいた次第です」
第六峠に来て長いのか、ゾレン語を自在に操る軍曹に青年は気を引き締めて、勧められた長椅子へ座る。
「『五色のケモノ』はアヴィス王女を守る。それを目的に必ず、交渉の前後は第六峠に結集する。けれど『五色』以外の者は、誰が敵で誰が味方か、全くわからない状態だ」
「やはりそうなりますか。それではどなたが『五色のケモノ』かを我々が確実に見分けるための、目印を作っていただけませんか」
「相談しておく。和平交渉が実際に可能で日時が設定されたら、その前にまた俺がここに来て結果を伝える」
ゾレン人とディレステア人自体は、先刻の青年がそうだったように、手の甲に刻まれる印で判別できる。そうした形で、驚く程スムーズに打ち合わせは進んでいく。
青年は改めて、人間は話をすればする程、様々な細かいことを普通の化け物よりよく考えていると気が付かされた。
「ライザ殿の立場は悪くならないのですか。現在ゾレン軍とは停戦で手打ちをしていますが、第六峠の宿場町全体が、今でも当然我々を敵視しています。ゾレン王は和平派だと伺っていますが、その威光も西部には及ばないとききます」
「そうそう、あたしもここに来てみて、人間ってだけで何処にいっても睨まれたよ。兵士達も化け物にはすぐに銃を向けるし、ディレステア国内に住む化け物も、人間に囲まれてると居心地悪そうだからね」
「……俺は元々、睨まれてるので。俺の母は人間で、父はこの峠や王都を荒して回った飛竜なので」
淡々と答えながら表情を硬くした青年に、王女がうっ、と何故か息を飲んだ。
「ごめんね、悪いこときいたね。混血だってことはきいてたのに」
片言でも心から申し訳なさそうに、気さくに謝る王女だった。
様々な現状を互いに話した後で、改めて軍曹は青年にそれを尋ねた。
「……それでは現在、特に注意すべきは『子供狩り』の軍部と、『悪魔祓い』の人間であると?」
「ああ。第六峠に常在する軍と、旧王城の軍は全然別部隊で、『子供狩り』は後者だ。この峠にいて長いアンタ達から見て、見かけないゾレン軍の奴がいれば警戒した方がいい」
それ以外に敵を見分ける方法のない現状に、軍曹も頭を唸らせる。
「『悪魔祓い』は、ゾレン人でも人間ばかりだけど……それもまずアンタ達には見分けがつかないな?」
「ええ。我々人間にはゾレン人は皆、化け物ではないかという恐れがあります」
化け物からすれば、気配の違いで人間と化け物の差は明らかだ。しかし人間から見れば、同じヒト型をした生き物と、その疑心はゾレンに住む者全てへの嫌悪に繋がっているようだった。
「……」
規律を遵守する軍人はある意味警戒し易い。余程のことでない限り、突拍子もない行動に出ないと予測できる。相手が単純な者の多い化け物であれば尚更だ。
悪魔を排除するため、とその意味も本当にはわかっていない人間の集団が、まさかの中立地帯たる第五峠で多発爆破事件を起こしたような、予測のつかない相手こそが怖かった。
青年の今の結論、「悪魔祓い」を何とかすべきという思いは、その後、思ってもみない所で後押しを受けることになる。
+++++
――へ? と。それぞれの成果を話し合う最初の集会で、青年は大きく目を見開くことになった。
年が明け、旧王城で「西派」と会談を行った「五色のケモノ」幹部が帰り、第五峠で長く療養していた「千里眼」も帰郷した当日だった。
「だから言ってる通りや。和平交渉に口を出さない条件として『西派』の奴ら、そんな風に言ってきよったんや」
「って……本当に、それで話は決まったのか?」
「五色のケモノ」代表として主に話をしたらしい悪友の言を、見た目は豪快でも聡明な祖母と、悪友のまたいとこである幼馴染が裏付ける。
「バカ孫の言う通りさ、ライザ。『西派』は和平には反対だが、国王に表立って反抗するなんて滅相もない、って感じだね」
「……………」
「『西派』も『悪魔祓い』の動向は懸念してるって言うの。第五峠みたいな騒ぎを、王都に近い第六峠で起こされたくないって」
幼馴染に続き、だから、と改めてその条件を悪友が説明する。
「『悪魔祓い』の首謀者をとっ捕まえて、『西派』の奴らも安心できる状況になるゆーなら、和平交渉の設定に文句は言わんて、ダウテッド総帥直々のお達しやったで」
その旧王属の名に、青年の表情が固まり呼吸が止まった。
「本当に……ソイツが自分で、そう言ったのか?」
でも――と、青年は顔をきつく顰める。
「『悪魔祓い』は第五峠で――和平に反対で、事件を起こしたわけじゃないのに?」
騎士団に捉えられた実行犯は全て、「洪水を起こした悪魔を討伐に来た」と証言していたという。仮にもそうした信念下の行動なら、和平交渉の場の妨害をしても彼らには何の利益もない。
幼馴染も悪友も首を傾げる。
「それは表向きでしょ? アイツら、ディレステア王女に凄い反感持ってたみたいだし、和平に反対だって見てたらいいんじゃないの?」
「……何で『悪魔祓い』が、そもそも王女に反感を持つんだ?」
「――お?」
「人間を守るための奴らが『悪魔祓い』だろ。ディレステアの王女だって人間のはずなのに……何が問題なんだ?」
様々な因縁のある青年は、誰よりおそらくその集団を嫌悪している。だからこそ、あまりに不透明な状況に、「悪魔祓い」だけを敵とすることに何かがブレーキをかける。
「そうね……何か、良からぬ企みに乗せられそうね」
ずっと黙っていた女性、帰ったばかりの「千里眼」が共に、難しい顔付きで一つの事実を提示した。
「だって、洪水を起こしたのは、『西派』の奴らじゃないの」
その中立地帯で惨劇を起こしたのは、悪魔を祓わんと爆破を繰り返した人間達だ。人間達が狙っていたのは、悪魔のようにそこに洪水を呼んだ主のはずだ。
「ピアを殺したのは間違いなく、洪水の主よね? でもそれは『西派』の仕業で、それなら『悪魔祓い』の標的は『西派』となるはずなのに……どうしてどちらの行動も、和平を妨害するという点で一致してるのかしら」
「ったく。相変わらず深慮だね、エア・レイン」
「千里眼」ほど考える方ではないが、頭の回る長老が楽しげに、食卓の向かいに座る女性を見つめた。
「言いたいことはわかったよ。つまり、和平を妨害したって結果だけ見れば、『西派』に『悪魔祓い』は目障りな存在でなく、警戒する理由がないこと。そして『悪魔祓い』も『西派』を敵視してなく見えるってことだろ」
でも、とそこで反論を投げかける。
「『悪魔祓い』の奴らに、『西派』が洪水の黒幕なんてわかるわけがない。所詮人間の集団なんだ、思い込みの正義感で動いてるだけで、それを体よく『西派』が泳がせただけじゃないか? 現に実行犯達は、ディレステア人が第五峠の惨劇を起こしたと言ってるんだろ?」
「……――」
爆破事件が起きた時、これはディレステアの人間からの攻撃であると、誰かが叫んでいたことを青年は思い出した。「千里眼」もある違和感を再び提示する。
「それならマザー。洪水を起こした『西派』が、黒幕をディレステア人と思い込んだ『悪魔祓い』の過激化に便乗して、惨劇を起こしたってことになるでしょう」
「ああ、そうだね。現にそういう結果になったんじゃないか?」
「でもね。『悪魔祓い』が最初から『西派』に利用されていたとしたら?」
「……ん?」
珍しくぴくりとも笑わない女性の後に、青年が声を続けた。
「……レインさんの言う通りだ、マザー」
それは何より、現場に居合わせた青年だからこそわかることだった。
「爆破が起き始めた時には、洪水じゃなく爆破の方が、人間の攻撃だって騒がれていた。爆弾作りなんて得意なのは人間だけだし……その後で洪水も人間の攻撃だって話になったというけど、その場合、竜でもない人間にどうやって洪水が起こせるんだ?」
「おかしいわよね。爆破を起こしたのは『悪魔祓い』よ? それは彼らも認めてるのに、じゃあ爆破がディレステアの人間の攻撃と騒いだのは、いったい誰なのかしら」
そこまで状況をきいた長老は、険しい顔付きを浮かべた。
「……確かにそれは、どれもタイミングが良過ぎる話だね」
まずもって、惨劇が惨劇となったこと自体のおかしさに、そこで気が付いたようだった。
「洪水の悪魔に対応したって『悪魔祓い』の反応も早過ぎるね。まるで……洪水が起こると、あらかじめ知っていたように」
多発爆破事件自体、計画性なくして弱小な人間に起こせるものではない。騎士団を手こずらせた異例の惨劇は並ではないのだ。
ということは、と――長老はそれまでの話を上手くまとめる。
「『西派』は『悪魔祓い』に、第五峠に洪水が起こされる……悪魔が現れるとでも先に唆す。『悪魔祓い』は実際に起きた洪水を見て、悪魔の仕業だと対応を開始した。それで動かした『悪魔祓い』に便乗して、『西派』の目的の和平の妨害を成し遂げた?」
「……何かがまだ、足りてない気はするんだけど、それは考えておいた方がいいと思うわ」
「それやったらここで『悪魔祓い』をおれらに潰させるんは、トカゲの尻尾切りみたいなもんか?」
「私達と、と言うか国王様と表立って敵対はできないから、『悪魔祓い』を利用したってこと?」
ふむふむと、鳥の化け物の二人が悩ましげに顔を見合わせる。
「ややこしいわね。どうして自分達で直接戦わないの?」
「ほんまやで、おれらみたいな真っ当な組織には、到底そんなん思いつかんわ」
……と黙る青年に、確かにね、と長老も両腕を組んだ。
「軍部は大体、目的も下心も単純でわかりやすい奴らが多いんだがね。あの西派総帥……国王の腹違いの弟、母親が人間っていうアイツは、何だか妙な薄気味悪さがある」
「……」
「人間の血を持つ奴らは、根は単純な化け物と違って、時にはかなりえげつないことをする。心しておいた方がいいだろうね」
それでも現時点では、「西派」の条件通りに『悪魔祓い』首謀者を探すしかない。そうした結論に、この後の話し合いで至った。
「しっかしどーやって、『悪魔祓い』を探したもんやろ?」
それがさっぱりや、とあっさり降参の手を上げる長老の孫に、くすくすと「千里眼」が普段の微笑みを見せた。
「ヴァルトは最近、第五峠と第一峠を飛び回ってるけど、何もおかしなことはなかったのかしら?」
「へ?」
「ザインの物流をヴァルトが担当してくれてるでしょ。でもね……第一峠には、『悪魔祓い』も出入りしてるはずなのよ」
女性のその台詞に、青年もやっと、ある事実を思い出す。
「そう言えばレインさん……第一峠に行った時――」
「ええ。『悪魔祓い』の渉外を名乗ったあの化け物の気配なら、ちゃんと覚えているわよ」
少し前に青年と女性が第一峠に出向いた時に、「千里眼」は「悪魔祓い」の関係者と出会っていた。僅かに話をした中で、人間の集団のはずの「悪魔祓い」に、化け物が混じっているとそこで気が付いていた。
「どうやら早速、私がお役に立てそうね?」
そしてそれは――「千里眼」である女性に、更に負担を強いることをも意味した。
「そうだね。『悪魔祓い』の奴らの居場所を、ソイツを探して見つけ出してくれ、エア・レイン」
「って、マザー、それは……」
「ゾレン中をくまなく『千里眼』で探すんだ。まず西部からでいいと思うが、見つからなければ東部も含めて、ゾレン全土を」
当然のように言い切った長老に、当たり前のように笑う女性。この場では青年は、何も言うことができなかった。
会合が終わり、集会所である長老宅を出て帰路についた時に、青年は唐突に言うしかなかった。
「俺がまず、第一峠に行ってみます、レインさん」
「――?」
「第一峠のディレステア大使なら、取引のある『悪魔祓い』のことを何か知ってるかもしれない。次の取引の日時を訊き出して、『悪魔祓い』の誰かを待伏せしたっていいはずだ」
「うーん。どう考えても、それより私が頑張る方が早く済んで、不要な手間が色々減ると思うわ?」
ふわりと女性は、長老の孫に対した微笑みとはまた違う笑顔で青年を見つめた。
「ライザが第一峠に行きたい気持ちはわかるけどね。ミリアもいるし、確かにそうした直接の収穫もありそうだしね」
「……レインさん」
なるべく女性に「千里眼」の負担を増やしたくない。青年の意図に女性は気が付きながらも――
「でも私は……ライザには、あの渉外に会ってほしくないわ」
「……――」
「『悪魔祓い』の他の面々とも、できれば会ってほしくない。サラム様が亡くなった時みたいなことを、もう心配したくない」
その集団はかつて、暴徒化した飛竜の息子である青年を、悪魔の仔として殺そうとした。そうして青年の生き筋を縛る強い楔となったことを女性は知っていた。
「私の力だけで何とかなることなのに。私が少しでも貴方の力になれるかもしれないこと……私の仕事を取らないで、ライザ」
冷え込んだ林道で、隣をゆっくりと歩く女性は、医者の誘いを振り切り、一人で故郷に帰ってきた。いつもより何処か弱気なのか、光を嫌う赤い目で、困ったように笑いながら青年を横目で見上げる。
「私……大切なヒトの足手まといにだけは、なりたくないの」
「……」
「何もできることがないなら、何処にいればいいかわからない。私も貴方と一緒で――自分の居場所を守りたいの」
暴徒と化した危険な化け物の子供である青年は、自らは真っ当であると、行動で示すしかなかった。「五色のケモノ」をも含めた様々な手伝いのように。
それでも青年は、静かな声で哀しげに反駁する。
「……それは多分、一緒じゃないです」
これ以上女性の体が冷えないように、握り締めた手に滲んだ血から、かすかな火を起こして周囲の空気を温める。
「俺は……コレをやってても、別に嬉しくないです」
青年は自らの血を炎と化す方法以外、化け物として有効な戦う術を持たない。自身を削って闘うしかないことを、女性のように、心から微笑んで続けられそうにはなかった。
「……それでいいじゃない。だって、貴方は……」
ふふふ、と、女性は青年を斜め下から覗き込むようにして微笑む。
「貴方は自分に嘘がつけない、優しい化け物だから」
そこで不服な青年こそ良しとする。そんな、複雑な人間の女性だった。
すっかり日も暮れた頃、女性を自宅まで送りつつ、医者との最後の話も青年は思い出していた。
――もしもあいつに何かあったら……あいつが何と言おうとも、必ず俺に連絡しろ、ライザ。
元々青年と年の近い医者は、女性曰く青年と似た所があるという。それで通じる何かがあるのか、青年には本心を伝えてくることが何度と無くあった。
「クランも本格的に大使職に就くのは、春からみたいだけど。それまでに和平の件が固まって、少しでも先行きが明るくなるといいのにね」
玄関口で女性は青年に礼を言いつつ、世間話のように医者の名を出す。
「まぁ、クランなら乱世でも何処でもうまくやれそうだけど。ああ見えてそのまま凄く真面目で、努力家だものね」
「……その上、一度キレたら容赦ないですしね、アイツ」
ふふっと女性は、共感するように心から楽しそうに笑う。体の弱い女性のために、青年があらかじめ庭に運び込んでおいた薪の間を抜けて、木の家の中に帰っていった。
そしてこれが――いつもいたずらっぽく笑いながら、自らの色に乏しい赤の眼を見た最後の時間になることを、今の青年は知る由もない。
+++++
異変に気が付いたのは、翌日の夕方のことだった。
「――え? 今、何て……リミット?」
「……千里眼、いなかった」
滅多に口を開かない紅い目の同居人が、近所である体の弱い女性に分けにいった魚を持ち帰り、難しい面持ちで話し始めたことにまず青年は驚く。
「珍しいな……この寒いのに、何処かに出かけてるのかな?」
「薪……減ってない」
鋭い目でまるで青年を咎めるように言う。青年もはっと、女性が温かく過ごせるように少年と共に、大量の薪を運んだことを思い出した。
「そんなバカな――」
半信半疑で少年と共に、女性の家へと直接行ってみる。少年の言う通り庭の薪は全く減っておらず、元々屋内にあった分だけが僅かに減った程度だと確認する。
「この地図は、確か……」
そして女性宅の床に広がったままの、ゾレン全土に加え周辺地域も描かれた大きな地図の敷物。それは女性が「千里眼」を使う際の愛用道具だった。
「レインさんが万一、一人で遠出するにしても……」
両親の形見であるその地図を、女性が置いていくことは有り得なかった。
「何があったんだ、レインさん……!?」
青年は動揺する心を必死に抑えながら、少年を連れて、急いで長老の家へと向かった。
緊急招集がかけられた「五色のケモノ」は、それぞれに顔をひきつらせながら食卓の椅子に着いた。
「――ウソ。エアがあの体で、何処に行けるっていうの?」
「有り得へんやろ! こんな山ん中、一人でどうするねん!」
念のために女性宅を確認に行った長老を待つ間、幼馴染も悪友も青年達に詰め寄る勢いだった。
「もしも誰かが連れ去ったとしたら、夜の間のはずよ。日中は私の鳥が里中を見張ってくれてるもの」
「レインさんを送った時、何か変な気配とか無かったんか!? ライザ!」
「…………」
青年は元々、気配探知には鋭い方ではない。「力」にのみ敏感である青年の眼は、夕闇などの視覚遮断や、「力」の弱い相手の探知を苦手としている。
「レインさんはしばらく家で『悪魔祓い』を探してたはずだ……でもそれ以上のことは、何もわからない」
硬く張り詰めた顔で、震える重い声を絞り出す。この状況はあまりに不甲斐ない、としか言えない。
青年の内の激した感情に、付き合いの長い者は気が付いたのか、思わず息を飲む。
女性宅から帰ってきた後、つとめて冷静に長老が話し出した。
「そう言えば気になることがあったよ。旧王城に入って、総帥に目通りしてすぐ、今日は『千里眼』はいないのか? って突然きかれてね」
「――え?」
「そういやそうやったな。あったわそんなこと」
「この三人だけですって言ったら、幹部は後何人かときかれて、二人ですって答えたら、それで話は終わったんだけど」
その時は特に気に留めなかった彼らだが、よく考えればそれはいくつもの、おかしな点を孕む言及だった。
「『千里眼』なんて、『五色』内と、第五峠だけのレインさんの通り名だ……噂くらいはあったかもしれないが、レインさんはそれ以外、そんなに力を使ったことはないはずなのに」
第五峠に多いのは主に人間で、「西派」ではない。他に女性の能力を知るのは、女性が手を貸した「子供攫い」とそれに関わった国王、祭祀くらいのはずであるのだ。
「エア・レインの能力を知り、また『五色』の一員であるとも知っていて、わざわざそんなことをアタシらに尋ねたとしたら……あの総帥は、何処でそれを知った? いったい何を考えてる?」
「ピアを殺させた奴でしょ? もしもあのヒトが関わってたら、エアだってただでは済まないんじゃないの!?」
その私怨には、和平交渉の談義のために「五色のケモノ」の誰もが蓋をしていた。それもここにきて限界が近かった。
「レインさんに何かあったら、おれはアイツらを許さへん!」
「やめな! まだあのバカ共が黒幕と決まったわけじゃない!」
しびれを切らす若者達を、長老はただきつく睨みつける。
「もう和平交渉の設定は日時のレベルまで動き出してんだ。今のアタシらの最優先事項は、『悪魔祓い』を探すことなんだよ」
今はそれしかできることはない。無情な現実を冷静に口にする。
突然消えてしまった女性を探す手がかりは何一つ無い。それなら「五色のケモノ」は、その活動通りに今後も動くしかない。
「悪魔祓い」探しの頼みの綱「千里眼」が消えたため、慌ててそれぞれ役割を分担し、探索を開始することになった。
「――何ですって? エア・レインが行方不明?」
「…………」
「悪魔祓い」探しのために、青年は再び第一峠に行くことになった。その前に真っ先に、色々な目的で教会を訪れていた。
そこで祭祀は、驚くべきことをすぐに口にする。
「それは昨夜の相談後、帰りがけを狙われたのかもしれません。迂闊でした……私がここに在りながら、何と言う無様な」
「――何?」
ぎり、と悔しそうに顔を歪める祭祀に、青年は呆然とする。
「レインさんは昨日、ここに来たのか?」
「ええ。『悪魔祓い』について相談に来られました」
「!?」
祭祀は重苦しい祭儀衣を何故か脱ぎ捨てると、祭杖だけを手に、全身を覆う外套を羽織る。おそらく出かける準備をしながら説明を始めた。
「彼女が探すことになった『悪魔祓い』の者が、何故か旧王城にいると言って、私に相談に来たんです。『西派』と『悪魔祓い』には何かの繋がりがあるはず、尻尾を掴みたいということでした」
「え……!?」
「『五色』としては和平交渉の件があるため、『西派』に対して迂闊に動くことができない。私に余裕があるなら私が動け、その方が国王様も今後、西部で動きやすくなるのではないか、とね」
祭祀もその話に納得し、しばらくの間、調査に出るつもりだったと言う。
「旧王都へ行くのか? アンタは」
「ええ。国王様が信頼された協力者を、これ以上失うわけにはいきません」
青年は思わず、自分もと祭祀に言いそうになった。
「しかしまだ、エア・レインが旧王城に連れて行かれたという確証はありません。帰ったばかりのエア・レインに、あまりにタイミングも良過ぎますし……まず私がそれを調べます」
迷い無き祭祀の眼光に、青年は改めて言葉を呑み込む。
山奥の里に女性がいることを知り、里の者に気付かれず女性を連れ去れるとすれば、この祭祀こそ最も疑いから外せない者だ。他にある程度、里の勝手を知る裏切者がいるとは、どうしても思いたくなかった。
この雰囲気では祭祀もシロに思える。しかし状況は予断を許さない。
悩んだ末に青年は、当初通りの来訪目的を祭祀に伝えた。
「……クランとヘルシャに連絡してくれ。レインさんの行方がわからないことと――俺は今から、第一峠に行くと」
「わかりました。私の方も何かわかれば、そこに連絡します」
祭祀は今や、赤い長髪を括る翠眼の剣士という佇まいで旅支度を整えていた。
「後ですね……」
一つだけ頼みたいと、青年にまたも驚くべきことを口にし、教会を後にしていったのだった。
すまないな、と青年は、突然の依頼に不服そうな少年に頭を下げる。
「子供攫い」協力者、「千里眼」のためと聞いて頷いた魔縁の少年に、改めて事情を説明した。
「リミットは旧王城のことをよく知ってるだろう。若祭祀と一緒に、レインさんの情報を王都で探ってみてくれ」
「……」
祭祀は一人で旧王都に向かうつもりだったというが、事態は差し迫っていると、急遽紅い目の少年の協力を青年に依頼したのだ。
「アイツは信用できないから、リミットが目を光らせてほしい。ただし……」
青年はそれを勝手に了承しておきながら、矛盾することを言い含める。
「絶対無事に帰ってくるんだ。リミットの情報を待ってるから、死ぬような無茶は決してするな」
「……――」
危険なことをさせながら甘さを口にする青年に、少年の不機嫌レベルが一桁は上がったと気付きながら、今はそれが青年にも精一杯だった。
旧王都に分岐する地点で祭祀と少年と別れ、青年はひたすら、ゾレン西部北端よりも北の第一峠へと向かった。
「ミリアに会えたら、リーザに連絡をとって……若祭祀のことをまず訊かないと」
青年は現在、二つの可能性を考えて状況を整理しなければならなかった。
「若祭祀の言うことが本当なら、『西派』と『悪魔祓い』はグルだ。第一峠にいた『悪魔祓い』の奴が、レインさんが『千里眼』と気付いたなら、『西派』に情報も流せるし……レインさんに自分のことを知られてないか、恐れていた可能性もあるよな」
「悪魔祓い」の渉外と第一峠で、女性は「五色のケモノ」として話をしている。女性は相手が化け物だと気付いたが、同じように相手も、ただの人間である女性が「五色」を名乗ることに違和感を持ってもおかしくない。そこからその人間が「千里眼」だと調べることまでは誰でも可能だろう。
「でも嘘なら、レインさんに何かしたのは若祭祀だ。何処までアイツを信じていいか……リーザならわかるかな」
とにかく青年に必要なのは、祭祀の信頼性の情報だった。
「アイツが嘘をついていたら、レインさんはアイツの向かった旧王都に確実にいるはず……リミットが頼りだな、これは」
青年としては祭祀の依頼より、その確認のために少年を祭祀に同行させたが、それが危険な賭けだとは承知していた。
「後は……何としても……」
青年が第一峠へ向かう、本来の目的――
「悪魔祓い」に物資を供給する仲立ちをする、第一峠のディレステア大使から必ず何か情報を掴む。それだけを思う。
「何をしたって――……レインさんを、探す……」
ずしん、と。灰色の目に赤く走る獣の鼓動に後押されるように。
人間には有り得ない速度で、北へ北へと向かう青年だった。
+++++
青年の里から第一峠には、どれだけ化け物の速度で急いでも三日はかかるはずだったが。
「そりゃ多分、祭祀はシロだぜ。アイツ剣持つと豹変するけど、その他は意外に裏表ない奴だからな」
「…………」
青年が魔道士見習いの少女に第一峠で会える前に、祭祀から連絡を受けた双子が道の途中で青年を捕まえ、あっという間に雪山の第一峠に青年を連れていったのだった。
「オレはすぐに旧王都に行く。アニキはここで『悪魔祓い』の情報、なるべく掴んでくれよ」
青年を乗せてきた飛竜からヒト型に戻り、久々に会った双子は何処か空ろだった。
からっとした様子は変わらないが、所々の裂け目などの服装の傷みや、全身に生傷が絶えないような様相に見えた。
「……武者修行の旅でもしてたのか? リーザ」
「似たよーなもんだ。他に特にすることないしな」
一見は青年よりもずっと双子は冷静に見えた。彼らの大切な姐御的存在の失踪を知っても。
「エアの姐貴にまで手を出すなんざ……まじ、胸糞わりぃ」
「……旧王都でまだ無茶はするなよ。もっと情報がほしい」
わかってる、と双子は、逆に鋭く青年を見返す。
「アニキこそ――熱くなるなよ」
ちらりと、青年達の後方にあるディレステア大使館を振り返り、何度か出入りした場所について改めて青年に釘を刺す。
「第一峠ディレステア大使は、こんな雪山の頂上にいるわりに、欲の皮の突っ張った人間だ。ザインの物流で何かといい思いはしてると思うが、大それた悪事を企むような奴じゃない」
「……」
「『悪魔祓い』と関わりはあっても、大使自体はこの件には多分関係ない。だから――」
雪を溶かしそうな程強張った顔の青年に、双子が溜め息をつく。
「殺すなよ? アニキが苦労して築いてきたディレステアとの関係、ぶち壊したくなければな」
「……」
「ミリアの立場だって下手したら悪くなる。心しとけよ」
双子がそこまで言い含める程、青年はどうやら、その目に怒りを滾らせているように見えるらしかった。
双子はそこで、そうだ、と淡々と話題を変える。
「武者修行中に、北の島の師匠からわりと面白い話を聞いたぜ。アニキのその眼、意外に色んな使い道があるかもしんねー」
「――?」
「オレを小さくしたり、血を燃やしたり……アニキの力は――」
青年に時に、小型の飛び蜥蜴に変えられる飛竜。しかし双子は自力では小型化できない。その後そこで、俄かには信じられないことを青年に語る。
双子が事前に、散々言い含めてくれた効果だろうか。
「リ、リーザ君!? お、落ち着いて、落ち着いてくれたまえ!」
以前から出入りしている双子を騙り、第一峠ディレステア大使館に踏み入った青年は、ロビーの壁に勢いのまま風穴を開ける。血を流す手に炎を纏いながら、拳を振り上げる程度で何とか自身を圧し留められた。
「『悪魔祓い』の居場所を教えろ。連絡方法だけでもいい」
「あ、悪魔祓いかね!? 何でまた!?」
「知る必要はない。ゾレン内紛に巻き込まれたいか?」
明らかに脅迫と血走った目とは裏腹に、静かに尋ねる青年に、コロコロとした体型の大使が震え上がった。
「いつも彼らが気ままに訪ねてくるんだ、私は何も知らない!」
「……」
「私が彼らに頼まれたのは後は一つだけだ! 彼らのご神体を預かってほしい、それくらいだよ!」
怯えて辺りを見回す大使は、おそらく助けを待っているのだろう。しかし中立地帯ザインを維持する三大勢力、警備隊はおろか、付近に配備されたディレステア軍すら音沙汰が無い。それはひとえに、同じ第一峠のザイン出身大使、ヘルシャ・フィシェルの根回しによるところが大きかった。
「ご神体……だって?」
これ以上ザイン大使に迷惑をかけないため、青年は拳を下ろす。
「最近は留守にしていることも多いようだが、第一峠にある私の管轄の山荘に、長く滞在させているんだよ」
「ソイツは……『悪魔祓い』の関係者か」
「そうだと思うよ、それどころか神聖な存在なんじゃないかな。こ、これも最重要機密なんだから、勘弁してくれるかね?」
「…………」
ひとまず怒りは、自覚できる範囲で治める。
無言で人間の大使を見つめた青年の灰色の眼に、ちょうど大使の後ろで、ディレステア大使館とザイン大使館に繋がる連絡通路に続く扉から、パタパタと出てきた黒髪の少女の姿が不意に映った。
「……――」
「ライザ……大丈夫?」
騒ぎを起こしてしまったので、少女に会うためにザイン大使館には通してもらえないかと、青年が諦めかけた矢先だった。
「……ミリア……」
魔道を介して通信は何度かしたものの、直接会うのは久しぶりだった。青年は、思わず息を呑んで立ち尽くしていた。
「何だね……君達二人は、いい仲なのかね?」
一瞬で無害化した青年を肌で感じたらしい。ディレステア大使は笑顔で、最近目にかけていた少女を喜んで迎え入れたのだった。
一刻も早く、失踪した女性の行方を捜さなくてはいけない。和平交渉のためにも「悪魔祓い」を何とかしたい青年は、第一峠に長く留まることはできなかった。
「ミリアは随分……何だか、しっかりしたな」
「うん。ここでは本当に、沢山のことを教えてもらえるの」
毅然とした様子で青年を見つめる少女は、相変わらず悲しげな顔ではあるが、以前よりずっと大人びていた。
「騎士団にいた頃は仕事の合間しか、魔法も習えなかったから。でもヘルシャ大使は本当に強くて、周りのヒトもみんな優しい」
青年を大使館の外に送りがてら、大使館の扉を一歩出た時点で少女はピタリと青年にひっつく。無表情でも心から嬉しそうに腕を組んできたのだった。
「……」
無言で無表情に、少し赤くなる青年に比べ、少女は以前よりも随分と積極的によく話すようになっていた。
「エアのおかげでわたしはここに来れたから。少しでも何か、わたしにもできることがあれば――絶対に言ってね、ライザ」
青年は、傍らから伝わる少女の温かさに、束の間の安らぎをようやく取り戻し、苦く微笑む。
大使館の正門で、塀を背に立ち止まり、少女は青年が見えなくなるまで見送るつもりらしい。
青年はただ一時――その温もりを確かめるように、最後に抱き締めていた。
第一峠ディレステア大使に教えられた山荘は、頂上の峠から遠くなかった。火口湖から流れるいくつもの川の一つに沿って、孤高に建てられた広場付きの大きな宿という感じだった。
「……え?」
山荘をまず遠目から観察した青年は、そこで信じられない光景を眼にする。
山荘を覆う暗い大気。それは「悲しげ」としか言えない、有り得ない空気の再来。
こうして再びそれを視るとは、完全に想定外だった。ただ強く、一人でここに来たことを後悔する。
あまりヒトの気配を感じない山荘から、雪原の広場を歩いていた小さな人影が、林道から山荘を見つめる青年に気が付いたようだった。
「……あれ?」
人影はこんな雪山で、ヒトの姿があったのが嬉しいらしい。青年を認めた瞬間、にこりと微笑んで、ざくざくと雪を踏んで向かってきた。
青年の目には、雪の白さに混じって灰色に包まれる山荘は、気配を遮断する魔道の結界の内にあるとわかった。
「こんにちは。旅のヒトですか?」
そんな所に現れた青年を警戒もせず、小さな人影は結界を出て、広場から青年の方へとやってきた。
悲しげな大気を纏う、有り得ない存在たる幼い子供。それが今、青年の目前へと初めて具現される。
幼いながら祭祀のような服の、黒く短い髪で青い目の子供が、雪の森の中で青年を見つめた。
――デュラ……ユーク……!?
青年は咄嗟に言葉が出せず、子供を見つめることしかできない。
「力」を視る青年の眼は、同じ「力」の血を持つ者達なら、会ったことのない誰かの血縁を見抜くことができた。この子供の姉二人が姉妹だとわかった時のように。
「……――」
しかし青年は、自身の特技を自覚して尚……今ここにいる幼い子供が、ディレステア第二王女から伝え聞いた、実の姉を殺した「竜人」とは信じられなかった。
それもそのはず、十歳にも満たない幼い子供は、話に聞いたような烈しさは微塵も感じられなかった。
「よくここがわかりましたね。こんな所誰も気が付かなくて、いつも寂しくって」
妙な折り目正しさはあるが、にこにことした表情は年齢相応で、小さな全身からは人懐っこさが溢れてやまない。
「お兄さんは……とても、優しそうですね」
何も答えられず、ポカンと子供を見つめるしかできない青年に、ヒト恋しいと見える子供は好感を持ったようだった。
青年の前で木にもたれた子供は、むぅ、と素直に心配そうな顔を浮かべた。
「ここは怖いヒトばっかりなんです。お兄さんも、これ以上は近付かない方がいいです」
「……え?」
「みんな、強いヒトがえらいんだって、何をしてもいいなんて思ってるんです」
それを伝えるために、自ら結界を出て近付いてきたのだ。見た目通りにヒトの好さそうな子供に、青年はやはり自身の眼を信じられなかった。
不満そうに俯き、帽子に押えられた前髪が少しずれた子供の額に、青年はある「力」を見つけた。
――……あれは……何なんだ……?
まるで第三の目のような、漆黒の薄い菱形の何か。それが髪に隠れて、その額に目立たないよう存在している。
――第五峠の時には……ずっとあったのか?
王女から子供の容姿について、額の何かのことは特に聞かなかった。確かに気が付きにくい所にはあるが、これだけ特徴的なものを王女が見逃したのか、と青年は訝しむ。
幼い子供は、澄んだ青い目で改めて青年の方を見つめ、嬉しそうに笑った。
「ぼくもここから出れたらいいな……お兄さんみたいに、旅をしてみたいな」
「……――……」
子供の声は、嬉しそうな顔と裏腹に諦観に満ち、二人の姉とよく似た悲しげな響きをしている。
「君は……帰りたい、のか?」
青年が思わず、このまま子供を共に連れ去ろうかと――そして第一峠の少女に託したいと、本気で思ったその時だった。
幼い子供の顔が瞬時に強張り、その半瞬後にそれは起きた。
「――!」
青年のいる場所へと、川面から巨大な蛇の如き水が踊りかかった。有無を言わさず青年を飲み込み、冷たい水中へ引きずり込んだのだった。
青年を喰らって川へ戻った水蛇に、子供は血相を変えて川辺へ走った。
「ひどいよハイドラ! あのヒトが何をしたの!?」
「デュラ。ワタシはあれ程、勝手に出歩くなとアナタに忠告をしましてよ」
場に現れた声の主は、何と――子供と年恰好が大きく変わらない、魔道士然とした恰好の、木杖を持つ幼い少女だった。
「アナタを見たヒトは始末する。相手がゾレン人なら特にそう。時も迫ってますし、ここは引き払えとのお達しですの」
「そんな……! どうして――」
「言うことを聞きなさい。悪いのはアナタですの」
「――」
幼い魔道士が一睨みすると、子供は泣き出しそうな顔で黙る。とても痛恨の様子ながら、静かな川面を見つめることしかできないようだった。
「それで良くてよ。こんな程度のことで、他の者まで呼ばせる手間をとらせないでくださる?」
冷然と子供の手をひいて、幼い魔道士が山荘に戻る。幼いながら強い水系統の力を持ち、水脈を司る「竜人」の監視者たり得る何かの化け物なのだ。
そして山荘には他にもそのレベルの化け物がいるのだと、水蛇に飲み込まれた青年は悟るしかない。
その化け物が幼く、詰めが甘くなければ、水蛇に飲まれた青年が見逃されることはなかっただろう。
「何だここは……有り得ない子供ばっかり集めてるのか……」
自身を飲み込んだ水蛇を、水中で何とか青年は――
つい先刻に双子からきいた、自らの特技の新しい生かし方を試し、「無意味」に変えて消化されることから逃れていた。
「それでも――どう見ても、あのコの方が強いのに」
双子は攻撃には武器を主に使うため、魔道の徒として一見強く見えない。しかし魔道の力を武器に乗せるのは、一点を狙うやり方としては最も強い方法の一つだと言われる。
「リーザの攻撃だって防げるデュラ・ユークが……何でなんだ?」
その双子を難無く撃退した「竜人」が、幼い魔道士一人に黙らされる。そして何より、青年の双子を撃退した時とは別人のような弱気さに、青年は顔を歪める。
「あんなコが……ピアを、殺したって言うのか……?」
何よりそれが最も納得いかなかった青年は……幼い子供達が消えていった山荘を、しばらく睨むことしかできなかった。
第一峠にすぐに戻り、幼い子供の実の姉である少女に、青年は事の次第を伝えようしたのだが……。
「――お、ちょうど良かったわ、ライザ! 大変や!」
「……は?」
何故かディレステア大使館には、怪鳥の姿から戻ったばかりの、裸体に外套を羽織る悪友が待ち構えていた。
とにかく少女に幼い子供の存在だけ伝え、少女は師匠たるザイン大使と共に山荘に向かった。ディレステア大使に借りた部屋で、暖炉の前に座った悪友が状況を説明する。
「一旦みんな、里に帰るで。オレはオマエを迎えに来たんや」
「何があった? ヴァルト」
「びっくりやで! 第六峠で何と一週間後に、和平交渉の場が持たれることになってもーたんや!」
「……は!?」
唖然とした青年に、悪友はぶるりと体を震わせながら話を続ける。
「よりによって、旧王城の『西派』の意向で、とんとん拍子に話が進んでしもうたらしい。最近第六峠に秘密裏に滞在してるディレステア第一王女さんは、一刻も早い和平交渉が叶うなら願ってもないって言うし、第六峠ならうちの国王さんも一番来易い場所やっつーて、即OKしたらしい」
「何で……『西派』――『子供狩り』の奴ら、何を企んでる?」
「わからん、色々あって展開が速過ぎてもうわけがわからん! 『悪魔祓い』もまだ見つかってへんのに、どないせーゆーねん」
「……――」
青年達はてっきり、「悪魔祓い」の者達を捕らえた後から、和平交渉の話が先に進むものと考えていた。見切り発車もいいところな「西派」の思惑に、青年も混乱するしかない。
そうして、山荘は無人化していたという少女達の探訪結果を聞いた後に、青年はすぐに第一峠を後にしたのだった。
朝一番に、またも「五色のケモノ」は緊急招集される。一人一人分担した仕事を果たせていない状態での帰郷だった。
「どういうことよ! ずっと仲立ちをしてきた私達そっちのけで、そこまで突然話が進むなんて!」
「あんたの言う通りだが、ここで反対意見を述べようものなら、和平の流れに逆らう勢力になっちまう。こういう時、一番頭の回るエア・レインがいないことがつくづく辛いね」
そんな形で、「千里眼」だけではない女性の価値を、改めて認識した化け物の一団だった。
「差し迫る問題は目印や。第六峠の軍曹さんから、『五色』を見分ける目印を用意してくれって言われたんやろ? ライザ」
「ああ……それは、ハーピアに頼むのがいいんじゃないか」
え? と首を傾げる幼馴染に、気配り細かな人間の血を持つ青年があっさり提案する。
「峠の守りに当たる『五色』の奴全員に、ハーピアの鳥を傍につかせられるか?」
「そうやな。ハーピアやったら絶対、『五色』以外を間違えることなんてないわな。上手いこと考えよるやんけ、ライザ!」
なるほど、と、幼馴染も感心したように何度も頷いた。
「手紙のやり取りや里の見張りくらいしかしたことなかったけど……確かにそういう使い方もありよね、これ」
言いながら幼馴染は、何故か突然――そこでハッとした顔で、口元を両手で押えて黙り込んだ。
「ハーピア? どないしたんや?」
「……――」
僅かに青冷めたような相手に、悪友が首を傾げる暇もなかった。
「お邪魔します。ちょっと一刻を争いますので、混ぜて下さい」
バタンと突然、長老宅に侵入した二つの人影に、全員が振り返った。
「アンタ――若祭祀!?」
「何や何や!? 説教なんて今は聴いとる暇はないで!?」
この祭祀が「王属部隊」だという正体を知っているのは、この場では青年と紅い目の少年だけだ。祭祀について入った少年もちょうど旧王都から帰ったのだろうが、それを隠して話を始める。
「リミット君から大変な懺悔を聞いてしまいまして。越権行為ですが皆様には、お耳に入れておかねばと思いまして」
「ええ!? どうしたのリミット、何があったの!?」
幼馴染は先程の表情を忘れたように、祭祀についてきた少年の肩を掴み、面食らった少年は何も喋れずに後ずさる。
「いえ、リミット君には以前から、姿のみならず気配も透明にできる力があるのは皆さんご存知でしょう?」
「それがどうした? 誰かのヤバイ秘密でも覗いたってぇのか?」
「秘密も秘密、何と彼は、旧王城に忍び込んだらしいんですよ。どうしてもエア・レインを探したかったとのことで、その結果を私だけに懺悔に来てくれたんです」
!? と、場の全員が一斉に、祭祀と少年を凝視する。
「結論から言えば、エア・レインは旧王城に囚われています。しかし、透明なリミット君に気付いた恐るべき『千里眼』は、ほんの僅かだけ、リミット君に伝言を託したのです」
同郷の女性の行方がようやくわかり、ひとまず「五色のケモノ」が、胸を撫で下ろしたのも束の間。
「エア・レインは近々公開処刑されるので、自分は気にせず、必ず和平交渉の第六峠を守れと――既にかなり衰弱した彼女が、それだけを必死にリミット君に伝えたというんです」
「……はぁぁぁ!?」
何でやねん!? と悪友が、全員の思いを代表して叫んだ。しかし祭祀は悩ましげな顔で、両腕を組むのみだった。
「何の理由があって!? エアに限って有り得ないわ!」
「それも処刑当日に明かされると、口にされなかったようです。リミット君は、エア・レインを救出も説得もできなかったと、私の元に懺悔に来たのですよ」
そうして知らぬ存ぜぬで通す。何処までが脚色かわからないが、紅い目の少年を使い、祭祀がその情報を得たのは確かなようだった。
場には僅かの間だけ、重苦しい沈黙の時間が流れた。
「……バカ言うなや、どいつもこいつも……!」
わけのわからない急激な展開の連続に、怪鳥の時の炎の翼まで出しかけた悪友を、黙って青年が制止した。
その姿に長老は、きつく顰めた顔で青年を見つめる。
「ライザ、どうする。アタシら『五色』は……どう動くべきだ?」
長老の問いに青年は……全く迷い無く、それを答えた。
「……決まってる。第六峠も守って……レインさんも助け出す」
それは真リーダーとして、全員の想いを問う言葉だと知りつつ。
「千里眼」の公開処刑がいつかもわからない状態で、青年は改めて、各々の役割分担を提案する。
「元々第六峠の守りはマザー以外の全員に、その間の里の番はマザーに頼もうと思っていた。それは今も変わらない」
「そうだね。わざわざ和平交渉の時に、こんな山奥のうちの里を狙うなんて暇な奴、早々いないだろう」
「一番まずいのは、交渉の前に処刑がある場合だ。『五色』がそこで暴れれば、和平への妨害とみられるかもしれない」
それでも、と青年は、一つの覚悟をたたえてその先を口にする。
「『五色』の顔はマザーとヴァルトだ。二人は動かずにいてくれ。レインさんは俺が何をしても助ける。俺はその後に糾弾されて、追っ手もかかるだろうが、『五色』からは破門だとして切ってもらうといい」
「そんな、ライザ……!」
この場に祭祀がいたので、青年はあえて口にしなかったが――それは青年だけでなく、同じように黙っていられないはずの双子の力も、青年は借りる気でいた。
「レインさんに処刑が決まってるんだ。誰も汚名を被らずに助けることなんてできない」
青年は淡々と、僅かに俯きながらも言い切る。
「その後の和平は、残った『五色』に頑張ってもらうしかない……俺はもう手伝えなくなる」
双子と共に女性を助け出す。それは青年達が双子であると知られる可能性をも意味し……長い嘘から解放される代わりに、居場所を失う展開だった。
「処刑が和平交渉の後なら、『五色』を捨てても助けたい奴が、そのままレインさんを助けに向かおう。ディレステア王女との約束は、今回の和平交渉で果たせるはずだ……和平が叶っても叶わなくても、俺はそれでいい」
「……ライザ、オマエ……」
「何と思われても、俺は初めから――一番大切なのは『五色』より仲間だ」
……と、「五色のケモノ」の若者が黙り込んだ。
「……ったく。エア・レインを見殺しにするって選択は、誰も思いつきもしねぇか?」
対して長老が、にやりと茶化すように言う。年の功か、何処か吹っ切れたような顔で若者達を見回していた。
「まぁ、当然だがね。『五色』は元々、てめぇらが平和で穏やかに暮らしたい願いの組織なんだ……それがまずてめぇらの仲間を見殺しにしちゃ、本末転倒だわな」
「それじゃ、マザー……」
「どう転んでもライザとエア・レインを、『五色』から失うことになりそうなのが痛いがね。それだけの成果……此度の和平交渉を、何が何でも守り通してやろうじゃないか」
景気良く一喝する長老に、ようやく場の若者達は、それぞれで静かに頷いていた。思い切りの早い長老の厚意に、青年は感謝するしかなかった。
唯一最後まで、煩かったのは悪友だった。
「くそぉぉー! 王女さんとの約束やけど、和平交渉まではレインさんを助けに行けんのが腹立たし過ぎるわ!!」
それは全員の想いの代弁と、誰もがわかっていたのだった。
全てがドサクサの中にあった。それでも「五色のケモノ」としての方針はそうして何とか定まった。
その後青年は祭祀と紅い目の少年と共に、改めて内密に自宅で詳細な説明を受けた。
「これは、エア・レインが『子供攫い』の協力者と知っている君だから話すことです、ライザ君」
「……」
「おそらく君も気が付いているでしょうが。エア・レインの処刑の理由は、『子供攫い』の烙印です」
青年はそこで、ぎり――と歯噛みする。
「『西派』は何処で……その確証を手に入れたんだ?」
「それはわかりません。しかし『西派』には、エア・レインが目障りな存在であることは明らかになりました」
祭祀は珍しく笑み一つ浮かべず、説明を続けた。
「エア・レイン曰く、『悪魔祓い』の現在の実質的な支配者は、渉外役を請け負う人間のフリをした化け物だそうです。オマケにソレは『西派』の総帥らしく、『子供狩り』と『悪魔祓い』はグルどころか、同じ組織とすら言えそうですよね」
「……何、だって?」
「西派総帥」とは、あの時「子供攫い」の女を殺させた張本人だ。それが「悪魔祓い渉外」として第一峠に来ていて、「千里眼」に会ってしまっていたとは――まるで思いもしない、取り返しのつかない悪夢だった。
「なので『悪魔祓い』を捕らえろと言った『西派』の条件は、初めから当てになりません。彼らの目的は完全に、和平を叩き潰すことにあります。国王様にもそうお伝えしましたが、妨害を恐れていては和平は叶わぬと、最大限の供の軍備と共に、峠を訪れられることになりました」
祭祀は断言する。「千里眼」以外に「西派」と「悪魔祓い」の関連を証言できる者はおらず、それ故に女性は捕らえられた。二つの集団はあくまで別個に行動を起こし、和平を妨害する心積もりなのだと。
「これは要するに――国王様と『西派』総帥の、直接対決です」
「……和平交渉が、無事にできるかどうかが、ってことか」
「何かあっても『西派』は『悪魔祓い』に責を負わせ、更には第六峠を守る約束を違えたと『五色』をも追求する気でしょう。生き証人たるエア・レインは口封じされる……証言の信憑性を、魔道の儀にて審問する土俵にも上がれないままで」
「――……」
じわじわと、青年達を絡める包囲網が完成しつつあるようだった。いつから何処でその網にかかってしまったのか、青年は未だにさっぱり掴めなかった。
「どうして……『五色』に全て、話さなかった?」
「いったい何処で情報が漏れているか、私にも掴めていません。『五色のケモノ』の方々を信用したいのは山々ですが、私には、貴方達の方こそ怪しく見えるのです」
しかし、と、祭祀は暗い展望ばかりではないと、軽く微笑んだ。
「この件が終わり、和平交渉が無事に執り行えたなら……君とエア・レインを『王属』に迎えたいのが、国王様のご意向です。それが一番、『五色』も君もエア・レインも、生かせる道筋だと私は思いますよ」
「…………」
それは何処か、誰かを犠牲にする気はないとも聞こえる、祭祀の言葉だった。
疲れ切った心身で、紅い目の少年を連れて帰った青年は、部屋に入るなりパタンと寝床に倒れ込んだ。
だらしない。と言わんばかりの冷たい目で傍らに座る少年に、枕に頭を突っ伏したままで青年はぼやく。
「……そりゃ……『悪魔祓い』のご神体がデュラ・ユークなら、『西派』と『悪魔祓い』は完全にグルだ……」
「……」
「必ず何かが起こると、王女に伝えに行かないとな……君は、どうする? レインさんを助けようとすれば、『子供攫い』の一員だと『西派』に確証を与えることになるぞ……」
「……」
最早ただの愚痴にも近い状態で、青年はハハハと自嘲する。
「君はそれでも本望か? どの道お互い近い内に、この家……この里にはいられなくなりそうだな」
「……」
黙り込みを続ける紅い目の少年は、何より「子供攫い」を一番大事に考えている。その延長で「千里眼」のことを協力してくれたのはわかっていた。
しかし青年にとって、いつの間にか慣れていたこの少年との生活、ひいては生まれた時から住んでいる里を後にする覚悟は、そう簡単に割り切れることではなかった。
そうして突っ伏したままの青年を、少年は黙って見下ろしていたが。
「ライザ……ハーピア、来てる」
「――……へ?」
突然初めて、名前を呼ばれた衝撃にポカンとする青年の前、少年は戸口まで行くと、乱暴に扉を開けた。きゃっ、と驚く幼馴染の声が聞こえた。
「リ、リミット!? わ、私は別に……!」
何故かここまで来て、家に入るのを躊躇っていたらしい。ぼやっとしていた青年よりも、少年は敏感に気付いたのだ。強引に幼馴染を引っ張り込み、青年の前まで連れて来たので、青年も寝床にあぐらをかいて座り直す。
「……どうしたんだ? ハーピア」
「…………」
既に日も暮れ、珍しい時間にやって来た幼馴染。見たことのないほど暗い顔で、青年からも目を逸らして俯いている。
「朝には……とても、言えなくて……」
「?」
いつも強気の幼馴染らしからぬ弱い声に、ひたすら首を傾げる。幼馴染はただ、どうしよう、と、震えながら口にした。
「ピアが死んだの……私のせいかもしれない……」
「――な……?」
そして青年は、いくつもの布石を敷いて、和平交渉の日へと臨むこととなる――
+++++
中篇・結
一週間とはあっという間だ。青年にとって、いくつかの相談を幾人かの要人と終えるには、ギリギリ十分な時間だった。
「いよいよやな、ライザ……ここまでは順調やったけどな」
「ああ。今日は多分――長い一日になる」
その間に旧王都に動きはなく、女性の公開処刑が執行される様子はみられなかった。第六峠に「五色のケモノ」がほぼ結集し、里は長老に任せ、若手は全体的に町に散らばり、幹部は交渉場所で待機の状態だった。
ディレステア大使館を中心に、背後にそびえる外壁が二国の国境だ。それを囲む半円形の宿場町である第六峠は、国境と並行に第一峠から流れる川が町を二分している。
「川向うは自治団に固めてもらっとる。『五色』はみんな川のこっち側で、ライザの指示通りちゃんと、黒い襟巻を全員にさせとるで」
中心の川を境に、峠側が長い冷戦の激戦区、旧王都側がまだしも治安の良い土地になる。旧王都側に在る盛況な街道――第六峠、旧王都、第一峠に分岐する要所にある大きな宿で、和平交渉は行われることになっていた。
「五色のケモノ」幹部の持ち場として、悪友は宿の屋上、幼馴染はディレステア第一王女の傍に控え、青年は自由行動という手筈だった。
「ハーピアの鳥の声はおれはわかるが、ライザはわからんやろ? 大丈夫かいな?」
「わかる奴の方が少ないだろう。わかる奴でちゃんと連携して動いてくれ」
はいはい、と、表向きは組織の顔の悪友が笑う。双子の存在を隠すために目立つわけにいかない青年に、苦笑うように肩を竦める。
「すっかりリーダーらしくなってきたやんけ、ライザ。オマエやっぱ、こーいうの向いてるんとちゃうか?」
「何処がだ……ずっと一杯一杯だぞ、俺」
「だってなぁ、不器用っぽいのに意外に色々やる奴やし。何より人望あるしな。力だけやと悪いけど、おれの方が断然強いのにな」
自身の血を燃やして炎とする青年より、炎の怪鳥は余程自由に「力」を操れる。最強の獣に継ぐ実力者である悪友は、からからと笑った。
「レインさんのこともそうやけど……ライザはほんま、仲間を大事にするからな」
「…………」
「オマエやったら何処でも重宝されるで、ライザ!」
「……既に追放前提で話をするな、ヴァルト」
ぐははと笑う悪友は、そうやって笑い飛ばすことで、何とか様々な怒りを抑えているらしかった。
青年はずっと、ずしんと胸を揺らす獣の咆哮を、遠ざけることしかできなかった。
だからそれが限界に近いことに、気付く余裕すらもなかった。
初めて会った時には、ガラの悪い女性のイメージのディレステア第一王女だが……。
「ライザ殿、ハーピア殿、他にも『五色のケモノ』の皆々様。ここまでのご協力を心より感謝致しますと共に――どうぞ良き明日を迎えられますよう、よろしくお願い致します」
王位継承者の証である紋章入りペンダントと、白一色の礼装の王女は、金色の髪が白い服によく映え、赤い目には溢れる気概と気品が宿っていた。
静かな勇気と根性を持つ妹、第二王女とはまた別の、王たる風格を備えた女性であることが伝わる。
「王女は決して、この交渉場から外には出ないで下さい。何が起きても俺達やディレステア軍の対応に任せて下さい」
「わかっております。第五峠では妹が大きなご迷惑をおかけしたと伺っております……私もまだまだ若輩者ですが、ディレステア国民を代表する者として、今日はここに立っているつもりです」
……と青年は、謙虚な台詞とは裏腹に不敵に微笑んだ王女に、思わず戸惑っていた。
「迷惑って、あれは俺が勝手に……」
「いえ、命を救っていただいた大使館の事変だけではありません。国に縛られず、気侭に想い人を連れ回すような妹に対して、ライザ殿はいつも寛容にご対応下さったと聞いております」
……と、今度こそ反応に困り、黙り込んでしまった。
王女は楽しそうに、和平交渉当日とは思えない面持ちで、控室の長椅子に通訳と品良く腰掛けている。
「私には国の都合で許嫁が決まっているのですが。妹は騎士団長殿と幼い頃から仲が良く、自分らしくずっと第五峠で頑張っています。そうでなければあの過酷な生活を続けることは難しいでしょう」
「はぁ……」
「私には真似できません。あの子にはあのまま、幸せになってほしいものです……本当に、妹をお助け下さり有難うございました、ライザ殿」
そこで深々と王女が頭を下げ、不意の事態に青年は恐縮する。
「いや……一番危ない時を助けたのは……」
それはもう、今はいない人間の女だ。青年が口にしかけた所で、幼馴染が口を挟んだ。
「王女様、そろそろお時間です」
あら、と残念そうに、王女は通訳を連れて立ち上がった。
「それでは――……皆で、闘いに参りましょう」
……この、僅かばかりの和やかな時間が、いっそ無ければと思ってしまう程に。惨劇と呼ぶに相応しい一日は、こうして幕を開ける。
その日、沢山の誰かの運命が変わりゆくことを……今は誰も知らないままで。
+++++
セレモニーを始めましょう、と。その仲立ちの責任者は、不自然な程気安げに――無邪気な顔で微笑んだと、後に幼馴染は語った。
窓が壁の大半を占める見通しの良い部屋で、大きく方形に並べられた重厚な木の机に、二つの国の王族が向かい合って座る。片側にはディレステア第一王女、もう片側にはゾレン国王。
そして間になる端で立った王族の男――この仲立ちである「西派総帥」が、一方的にその会合の開始を宣言していた。
「両国の記念すべきこの日のために、ささやかながら余興をご用意させていただきました」
「……?」
キョトンと仲立ちの方を見るディレステア王女と、顔を顰めるゾレン国王の間で、西派総帥が窓に目をやる。仲立ちを自ら買って出た総帥、国王の腹違いの弟は、窓の外へと楽しげに視線を移した。
それは「五色のケモノ」幹部達が、想定し得る最悪の場合の状況として――……最も懸念していた事態だった。
「なっ……!?」
「――……!!」
王女が心から不快気に、口元を押えて声を殺した。王女の隣につく通訳と幼馴染も声を失って絶句する。
同じく通訳が傍についた国王が、がたんと椅子から立ち上がった視線の先では、「セレモニー」が今や始まりつつあった。
交渉が始まる前に部屋から出て、悪友のいる屋上に戻っていた青年も、幼馴染から鳥を通じて事情を聞く悪友に促されて、川辺の方向でそれを目にした。
「……――」
その光景は、数百メートル先の川辺に今まさに引っ立てられ、磔にされている人影。それは確実に、青年達の顔見知りであり――
「少し前に討伐した大罪人、『子供攫い』首謀者に引き続く、参謀たる人間の女です。『悪魔祓い』に負けず劣らず、西部の治安を揺るがせた集団に、相応しい末路をお届けしましょう
明かされた意味のわからない事実に、幼馴染が言葉を失う。その対面で、国王が窓から目を振り切るように西派総帥へと向き直った。
「ダウテッド――貴様……!」
「おや、どうされました、兄者? 何か不都合なことでも?」
「あの人間の女が『子供攫い』などと、何処に証拠があるのだ。何故……あのような惨い仕打ちを行った!」
最早歩く体力も無いような女性は、抱えられるように木製の十字型の柱に連れて行かれた。鎖で両手と足首をまかれ、その上手首を釘で打ちつけられた凶行を誰もが目にする
あまつさえ、類稀に端整な女性の顔には、見るも無残な生々しい火傷……その両眼を無慈悲な業火で、とことん焼き潰された痕が刻まれていた。
「取り調べ中に女が自ら、『子供攫い』だと白状しましたよ? 少々手荒であったかもしれませんが、証言の信憑性についてはボクのお抱え魔道士達のお墨付きですし――そもそも『千里眼』などと、怪しげな力で国を乱している女でしたのでね」
西派総帥は、そこでただ、誇らしげに綺麗に微笑んでいた。
その数百メートルを、飛ぶこともできない青年がいかにして一瞬で超えたか、青年は覚えていない。
元いた所で炎の翼を出現させて叫んでいる悪友がいるので、辛うじて、その力の暴発を後押しにしたのは状況としてはわかった。
「レインさん……!!!」
公開処刑がもしも、和平交渉の日に行われた場合。青年達の注意を逸らす手段として「西派」がとりえる最悪の行動を青年はきちんと想定していた。
しかし女性がこれだけ、痛めつけられた状態で現れる事態は思いたくなかった。あえて意識から外していた不甲斐なさに、青年は自らを叱咤する。
「貴様ら――……!!!」
女性をここまで連行した精鋭の兵士達は、うろたえながらも、突然現れた青年を取り囲む。あまりの怒気に兵士達を圧倒させるもの――青年の彩無き眼に走る赤い獣を彼らは直視する。
しかし青年がその獣を解放するより前に、場に訪れたのは、いつしか暗雲に包まれた空からの無慈悲な白い使者。
それはただ――静かで冷たく、蒼い殺意だった。
「……!!!」
咄嗟に青年が両手で頭上をかばい、全身を硬くした瞬間。
あまりに唐突な事態に、反応できなかった全ての兵士達に、まるで尖った隕石のような、無数の氷柱が降り注いだ。
川辺の半径数キロ以上を襲った氷柱の嵐は、和平交渉の場も巻き込み、悪友がいる屋上にも流れ弾が飛来するほどの規模だった。
「……リーザ……!!」
唯一、磔にされた女性だけを中心点として避けている氷柱は、青年がよく見知った蒼い色を纏っている。
集中砲火を受けた兵士達の血に染まる赤。巻き込まれた他のディレステア軍やゾレン軍、「五色のケモノ」の血までを吸うその「力」。それは確実に――実の双子が放った兇気だった。
やがて全てが、張り詰めた空気の中に熔けて消えていき……その収束を待つ暇など無く、青年は磔の女性の下に駆けつけ、手首の釘は抜かずに鎖を解いた。柱を破壊して女性を地面に横たえ、その上半身を抱きかかえる。
「レインさん、レインさん……!! レインさん――!!」
体中に赤い衝動を今も尚走らせながら、ぴくりとも動かない女性に必死に呼びかける。今の青年に、周囲を窺う冷静さはカケラもなかった。
そんな空隙も許さないと示すかのように、突然巨大な地鳴が、世界を割るように響いた後で――
その黒い竜は、あっという間に青年と女性を呑み込んでいった。
+++++
第一峠から旧王都に向かった双子は、その後久しぶりに家に顔を出した。互いの情報を合わせ、そこで女性のことを相談しあった。
「旧王城の警備は伊達じゃねぇ。公開処刑の時にしか、エアの姐貴を助けるチャンスは無いと思った方がいい」
たとえば紅い目の少年が、気配を消して忍び込むことはできても、ヒトを連れ出すのは不可能だと双子は伝える。
「『子供攫い』は本当に、囚人ではない子供に対して、ピアの直感があってこその成立なんだ。あの城から囚人を助けるのは不可能だよ、アニキ」
「でもそれだと――レインさんはこの瞬間も、どんな酷い目にあっているか……」
「『五色』でも方針は、処刑の日に助け出すで決まってんだろ? てーかアニキが動く必要すらねーよ、オレが顔を隠して動けばいいだけだろ」
青年を咎人とさせまいとしてか、双子はあくまで冷静に、単独で女性を助けると言い張ったものの。
「いや……公開処刑が、何処でやるかもわからないんだ。俺とリーザで手分けして第六峠と王都を張って、遠い方が近い方の援護をする、それでいかないか」
「……」
「レインさんの命がかかってるんだ――リーザ」
一触即発の空気を隠しもしない青年に、生傷だらけの双子は、静かな嘆息をもらし……わかったとだけ、小さく頷いていた。
「オレが援護の場合、アニキがいても容赦なく魔法は使うぜ。アニキはこないだの要領で耐えしのいでくれ」
「ああ、大丈夫だ。リーザの力なら一番俺と近いから、誰より『無意味』にしやすいと思う」
青年が先日に双子から助言された力の使い方は、普段青年が自らの血を燃やす時、血の中に視える炎を発火させる特技の応用と言えるものだった。
「自分の火を消す時みたいに、相手の力を消せばいいんだろ? 第一峠で試してみたけど、リーザが言った通り、本当にできた」
青年はそれは、自らの血――「力」にだけ通じるものだと思っていた。
「ああ、でなきゃオレを小さくできるわけがなかったからな。アニキの特技はアニキ自身だけでなく、他の奴らの力にも通じるもののはずなんだ」
飛竜に変化する双子の弟を、弟自身では成れない小型へ青年は変えられる。その特技の本懐を双子は淡々と助言した。
そしてそれは、今まさに、青年と女性を飲み込んだ黒い竜をも「無意味」とする――荒ぶる河川を青年の周囲だけでも静止させる、異端の「力」だった。
「このっ……!! ふざけるな、デュラ・ユーク……!!!」
川辺にいた青年と女性を飲み込んだ、あまりに突然の黒い洪水。それが第六峠を流れるその川だけではなく、ゾレン西部中の河川で起こっていることを、その時の青年は知らなかった。
「何で邪魔をする――! こんな力の使い方は馬鹿げてる!!」
爆流には明らかに、見知った子供の色が満ちている。青年が掲げる両手の真下――女性が横たわる地面だけは、その自然の脅威が「無意味」とされ、台風の目のように洪水の難から逃れていた。
「せめてレインさんだけでも……!!」
青年達を助けんと、飛竜の姿で洪水に挑んでは弾き飛ばされる双子を、青年は感じていた。
火を継がなかった飛竜――氷の魔道を得意とする双子に、この爆流から青年達を助ける術は無いだろう。早くも容赦なき現実を悟りつつあった。
それ程までに、「竜人」が呼んだ黒い竜の力は強い。自然の脅威の力を司る化け物に、獣の脅威に留まる化け物は敵わない、それがこの世界の定常だった。
今の青年のように触れた力そのものを「無意味」にするといった、化け物の範疇から飛び出た暴挙でなければ、僅かな抵抗すらも難しいものなのだ。
「くそォ……!!」
そして、青年の体力にも限界が近付きつつある。このまま爆流に飲まれれば、人間である弱り切った女性は確実に死ぬ。自身の全身の消耗から、青年はタイムリミットを突き付けられる。
それは許せない、大切な人を守れないことだけは受け入れられない――
爬虫類の眼を真っ赤に見開く獣。掲げた右手にかかるあまりの負荷に、全身の血管がぶちぶちと切れていくようだった。
自らが命尽きるまで、獣は決して諦める気はなかった。たとえ暴徒と化してでも、この腕を下げることはないと誓う。
ごうごうとわめく黒い竜の腹を引き裂き続ける。最早言葉すらも忘れて、青年は呑み込み続けた赤い咆哮を上げ……――
……――、と。
己を失った獣と黒い竜の、嘆きの轟音しか存在しない世界で。
その根強く純粋な化け物の呼び声。悲しげな誰かを映す昏い鈴の音は、確かに青年の深い所へと届いた。
女性を救えない現実に、体より先に心が折れかけた青年に、それは最後まで闘い続けるための火を再び燈した。
「……え?」
声は確かに青年の名を呼ぶ。永遠のように長く感じる同じ時の中、女性を呼ぶ声にも青年ははっきりと気が付く。
そして青年は、自らの役目をそこで悟る――
この黒い竜を鎮めるべき者は、決して青年ではないのだと。
「……!!」
爆流に向けていた手を下ろした。強い流れに飲まれる直前、青年はひしっと女性を抱きかかえた。
「無意味」でなくなった黒い竜が、今度こそ足下の青年達を喰らわんとした瞬間――
「……クラ、ン――……」
治水の化け物でありながら、異端者とされていた炎――赤い髪と目の男。青年の赤よりも激しく深い、憎悪に狂った赤い竜。そうとしか見えない程に強い炎が、黒い竜に喰らいついた。
剋される火でありながら治水を司る矛盾に堪えるだけの、あまりに異例で強力な炎。それは最早、「魔」の域に達すると思われ……。
そうして黒い竜を圧し返し、叫喚の場を一瞬の間に静寂に戻していった。
洪水と、それを爆散させる程の炎から何とか女性を守り、青年は付近の林に女性を連れて身を隠した。そこへその赤い髪と目の男は、ゆっくりと近づいてくる。
青年以上の殺気を纏い、黒い長剣を片手に、普段は束ねる髪を肩に下ろしている。全身の服があちこち裂けて血が滲んでいる。洪水の一角を一瞬で飛散させることに、総力を一時に暴発させたのだろう。乱れる呼吸と激しい憎悪を押し殺すように静かに歩いてくる。
そうして辿り着いた元医者を、同じように満身創痍で座り込む青年は、今にも閉じそうな灰色の眼で見上げた。
「……すまない、クラン……」
「…………」
片膝をついた医者に、抱えていた女性を引き渡す。ザインに赴任した元医者がこのタイミングで表れたのは、彼なりに女性の公開処刑の日を探っていたのだろう。
無言で女性を強く抱きしめ、医者は俯いて動かなくなった。その姿を見て、いっそう青年は胸が締め付けられ、ただ詫びるしかできなかった。
「すまない……俺には、レインさんを、守れなかった……」
「…………」
「大切な……ずっと、大切な家族だったのに……」
そこですっと、医者は青年を制すように、顔を上げる。
「……引き受けるべきは、オマエじゃない、ライザ」
深い赤の目には確かに、青年への労いと、哀しみ以外は浮かんでいなかった。
「俺と共に来なかったエアの咎と……こいつをいつまでも解放できない、俺の咎だ」
震えている声に、青年は尚更俯いてしまう。全身の消耗に意識を失いそうな青年を見て、医者は共に連れてきた誰かを振り返って呼び付けていた。
「ひとまず当分、追撃は無さそうだ――……ミリア」
「――え?」
青年がまさに驚愕で顔を上げた時、医者の背後には、黒く悲しげな大気の渦が押し寄せていた。
「ライザ……! 良かった、無事で……!!」
すぐにも駆け付けたかったが、洪水の再燃を警戒して見張っていた者。洪水の主と同じ竜の血をひく少女が走り寄ってくる。
座り込む青年に飛びついた少女は、青年を強く抱きしめると、堰を切ったように嗚咽をし始めた。
「ごめんなさい、エアやライザにこんな酷いこと、本当にごめんなさい……!!」
「……ミリア……」
「許せない、わたしデュラが許せない、あの子のことがもう何もわからない……! どうして!? ピアだけじゃなくて何でライザやエアも!? 他にも一杯巻き込まれた、沢山のヒトがあの子に飲み込まれた……!!」
「…………」
その、ゾレン西部全土で起きた洪水。それが歴史に残る大災害と後に呼ばれるようになることを――少女は既に知るかのようだった。
「こんなの絶対、こんなのって……! あんまり、酷過ぎる……――!」
泣きじゃくる少女を、青年はただ、弱々しく抱き返すことしかできなかった。
「……必ず……俺達であのコを止めよう、ミリア……」
青年自身の決意と共に、それだけを重く口にしたのだった。
+++++
一週間以上の投獄と、王都からの旅路、両手への打ち釘など、同郷の女性は最早虫の息だった。それでも何とか意識を取り戻した時には、応急処置をした医者の赤い目が硬く潤んでいた。
女性を囲んでいた医者、青年、少女の内、青年と少女は女性の生存を確かめると、少しだけ距離をとった。
両眼に渡る大きな火傷。それを覆うように、白い包帯で目隠しを施された女性に、医者の姿は見えていないだろう。
「…………」
細く呼吸する女性は、自身を抱える赤い髪の男の顔に、釘を抜かれて止血された手を弱々しく当て……じわりと、眼元の白い包帯が赤く滲んだ。
「……どうし、て……?」
「……」
消えそうに弱った拙い声で、女性は沈痛だけを浮かべる。
「どうして――……クランが、泣くの?」
指一つ動かせず、触れられただけの女性の手は、それが限界で力無く落ちる。
それでも震える声を絞り出してまで、女性は真っ先に、場にいる全員への詫びを口にした。
「ごめん、なさい……みんなに迷惑、かけちゃったね……」
女性を膝に乗せて抱える男の肩が強張る。再び先程の赤い竜を具現せんほど怒りを圧し殺していることを、青年も少女も感じていた。
青年と少女は、だから少しだけ、それぞれ声をかける。
「それはエアのせいじゃない。悪いのはエアを攫ったヒトよ」
「レインさん。レインさんを助けるために、リミットが初めて俺と協力してくれたんだ。みんな、レインさんが好きなんだ」
何も応えられないほど、女性は弱っている。答を待たずに再び距離をとった。
それは女性に、女性をここまで助けに来た男と、少しでも真に向き合ってほしかったからだった。
喋ることも命に関わる重態の女性が、それでも泣き出しそうに、かすれた声を拙く上げた。
「……クランの……――ばか……」
「……」
「私は――……アナタに、助けてほしくない……」
女性はこれまで、男に何も、自ら求めなかった。
ただ一つ、男と同じ名前で、短い時を呼ばれること以外は。
――姓だけ名乗らせて。それだけで私、幸せ。
黙ったままで、女性を強く抱き締める男に、まるで子供のように、息も絶え絶えの女性は駄々を伝える。
「違うの……誰にも、私は……もう、嫌なの……」
その想いは女性に――眼を焼かれる拷問すらも耐えさせたもので。
「私のせいで、傷付くの、見るの……もう、嫌……」
だからこの現状こそ、女性が最も拒んだ呪い。彼女の願いを無意味とする無力な現実だった。
「何もできないから……アナタとは、行けない……」
男はただ、たった一言だけを、血を吐くような面持ちで答える。
「あんたの大切な奴らが死んだのは……あんたの咎じゃない」
自らのための旅路で、両親を失った女性。彼女がその命の意味をずっと願っていたこと。それを男は、とっくに知っていた、と。
再び意識を失った女性を抱え、医者の男は立ち上がった。
とりあえずは有無を言わせず女性を連れて行き、傷の治療をすると青年達に伝える。
「その後のこと――俺が正式に大使になってからは、また考える……しかし少なくとも、ゾレンにはエアは戻れないだろう」
「ああ。ここにいても、命を狙われるか利用されるだけだ」
「ミリアはここに残れ。後はヘルシャと連絡をとって決めろ」
「うん。連れて来てくれてありがとう、クラン」
医者の視線の先で、青年に負けず劣らずボロボロの飛竜が、医者と女性を待ち構えているようだった。
「クラン……レインさんのこと、頼む」
「…………」
医者は軽く、長い溜息をつき……僅かに青年に微笑むと、飛竜の背に乗り、早々に飛び立ってしまったのだった。
「……エアは……もうちょっとだけ、優しくなればいいのに」
その姿を少し寂しそうに見送る少女を横目に、青年は改めて、重い表情で川辺を見回していた。
「……死体は全部……何処かへ流れ去ったか……」
洪水が起こる直前に、氷柱の嵐で命を落としたのはおそらく、この場にいた兵士だけだ。しかしその後の洪水で、「五色のケモノ」も命を落とした者がいるだろうと思い至る。
それらの酷薄な現状が、青年を今、暗鬱とさせている理由だった。
「俺の知る限り……リーザがヒトを殺すのを見るのは、初めてだ」
長く放浪に出ている双子は、旅先で揉め事に巻き込まれれば、誰かを手にかけていることもあるのかもしれない。それでも青年の前で血生臭いことは一切しなかった。上着を汚したくないと言っていたが、双子は青年より余程、弱い者には甘かったのだ。
それが、直接の敵の兵士だけでなく、周囲を巻き込む規模の力を使い、目的のために手段を選ばない非情さを見せた。青年は、その咎は双子でなく自分が引き受けたかったと、それが辛かった。
「リーザは俺より……ずっと、いい奴なのに……」
多くの仲間の無事や、和平交渉がどうなったかも気になる。悪友は青年の方針通り、青年達がどうなろうと決してこちらには来ず、和平交渉の場へと留まっているようで、心中で賛辞を送る。
「多分来ても、無駄だっただろうし」
あの黒い竜に対抗できるとすれば、ザインという土地、自然の脅威の中で生まれた化け物か、神の名でも持つ者くらいだろう。じかにその脅威に曝された青年は重く項垂れる。
青年がそうして、少しの間少女から目を離していた隙のことだ。
「――きゃ……!?」
「動くな――ミリア・ユーク」
――!? と振り返った先では、黒い襟巻を着けた同年代の男。青年も少女も顔見知りだった者が、突然現れて少女を羽交い絞めにし、刃物を突き付けていた。
「オマエ……!!」
驚く青年を嘲笑うかのように、顔見知りの男は歪んだ微笑みを浮かべた。
「この娘に近付くなと言っただろう……ライザ」
「……シーレスト」
男は第五峠の自治団の一員で、第五峠にいた少女とも、手伝いをしたことのある青年とも顔見知りだ。騎士団の見習いだった少女や、第五峠で「占い」をした「千里眼」のことも知っている相手だった。
「まさか……レインさんを攫ったのも、オマエなのか?」
元々第五峠の自治団自体、ほぼ「西派」で占められている。旧王城に集う「子供狩り」よりずっと穏健ではあったが、その総帥に協力を行ってもおかしくはない存在だった。
「レインさんが第五峠を出て、里に帰って一人のタイミングを知れるとしたら……峠の自治団のオマエなら、可能だろうな」
「『子供攫い』などにかける情けはない。あのような国賊に、少しでもかまけた奴を含めて思い知ればいい」
自治団の男が言う通りに、「子供攫い」は、幹部は少数でも西部中に密かなる協力者が存在していた。だから「西派」には目障りな集団であり、今回女性が公開処刑とされたのも見せしめの要素が大きいのだと、男の歪んだ笑顔が語る。
「『東派』はおろか、この娘は『子供攫い』首謀者の妹だった。総帥に差し出せばさぞかし、喜んでいただけるに違いない」
「貴様……!」
「一歩でも動けばこの場で殺すぞ。それともお前も『子供攫い』なのか? ライザ」
自治団の男はそこで、生来の真面目な顔に戻っていた。
「おれはお前を、この娘に関わるまでは買っていたんだが。エア・フィシェルにしても、この娘にしても、お前の周りには『子供攫い』だらけだな」
「……!」
言葉を呑んだ青年に対し、男はその理由には気付かず疑問を続ける。
「それでお前達の里に、『子供攫い』が潜伏したのか?」
その男のすぐ近くに迫っていた紅い違和感。「力」を視る青年は当然のように気が付く。元々、そのために打っておいた布石が生きていたとここで悟る。
そうなると、青年のするべきことは単純だった。
「オマエこそ……『悪魔祓い』とは関係あるのか、シーレスト」
「――何? 『悪魔祓い』が、何だと?」
意識をひきつけようと言葉を返すと、男が目を見開いて青年を見た。その僅かな隙を確実に見逃さず、男の背後に忍び寄っていた透明な紅い目は――男の武器を精確に弾き飛ばし、男から少女を奪い返していた。
「何だ――何者っ……!?」
「……よくやった、リミット。そのままミリアを守ってくれ」
「……」
青年の指示通りに男を見つけ、監視していた少年に青年は賞賛を送る。
信じたくはなかったが、自らの布石が正しかったことを青年は確信していた。
「シーレスト……レインさんやピアの情報を『西派』の奴らに流したのは、オマエと――マリーナだったんだな?」
もがく男を睨みつけながら、男とよくコンビを組む自治団の女のことも引き合いに出す。
「ハーピアと何度となく手紙を交換していたマリーナなら、ハーピアの鳥が手薄な時間も知ってるはずだし……うちの里に『東派』ピア・ユークが現れたことも、知っていただろう」
それは青年の幼馴染が心から後悔し……そしてその疑いを確信するため、青年と相談して決めた一つの罠だった。
――ピアが死んだの……私のせいかもしれない……。
「マリーナはレインさんを嫌っていたな、そう言えば」
「千里眼」を良く思っていなかった自治団の女。それが「千里眼」の仲間の幼馴染と交流を保っていたのは、いつからか利用するためになっていたのだろう。
――エアのこともそう。私、マリーナには確か、エアが帰ってくる日のことを話したわ……ピアのことも随分前に話したし、だから二人のこと、『西派』に伝わっちゃったのかもしれない。
それを確証するために、青年は一つの罠を仕掛けた。
「シーレスト。オマエは何でそんな黒い襟巻を着けているんだ?」
「……!」
「それは今日ここで『五色』を見分ける目印と、ハーピアからマリーナに話してもらった嘘の目印だ。本当の目印は別にある……だから、その目印が無く、襟巻だけを着けている奴は……ハーピアの世間話を、これまでもそうやって、利用してきた奴のはずだ」
そして青年は、その偽物の目印だけを持つ相手を探すように、紅い目の少年に頼んでいたのだった。
「『五色』に化けて何をする気だったんだ? シーレスト」
「…………」
黙り込む相手に青年は短刀を抜く。本来は真面目な男、そして大した力は無いと知る者に、女性を助ける直前までのような強い殺意を持つことはできなかったが……その迷いが男にも通じているのか、男は黙り込みを続ける。
しかし青年のそうした甘さを、淡々と否定するように、男の背中を後ろから無言で切り付けた者がいた。
「ぐっ……!?」
倒れた男を見下ろし、無機質な顔で佇む知り合いの剣士。冷たい翠の目には非情さしかなく、青年をも見下すように白んでいる。
「その真相は持ち場で探れ――持ち場に戻れ、『五色のケモノ』」
「……――」
剣士は剣を鞘に納めると、途端に苦い顔から、いつもの祭祀に戻って微笑んだ。
「この男は私が尋問します。交渉場に戻って下さい、ライザ君」
「……どういうことだ?」
ほぼ普段通りになった祭祀は、いつになく渋い面持ちをしている。青年の内を瞬時に、嫌な予感が走り抜ける。
祭祀は一度辺りを見回し、人目も気配も無いことを一応確認し、まずは現状から青年に伝えた。
「君がエア・レインを助けたことはまだ知られていません。多分姿はうっすら確認されていますが、短い時間のことだったので、その後の氷雨や洪水に今は紛れています」
だから今なら戻っても大丈夫だと、青年に助け舟を出した上で続ける。
「……ディレステアの王女が、行方不明になりました」
そこではっきり、戻るべき理由を口にした祭祀に、青年の全身を戦慄が襲った。
その交渉の場自体は、滅多なことでは争いにならないだろう。それは「五色のケモノ」もディレステア軍も同意見だった。
「化け物達はいつも約束は守ります。話し合いをすると決めている日は、決してその場での戦いはしません」
長く第六峠で戦う人間の軍曹が言うのだから、それは相当の、信頼性のある事柄だった。
「そうだな。国王も『西派』総帥もいるような場所で、戦闘を起こして巻き込みかねない事態はみんな避けるはずだ」
だから王女も、交渉の場を離れなければ基本は安全のはずだった。戦闘力の低い幼馴染を傍につけ、青年と悪友は外周を守るのが護衛の方針だった。
交渉の場所、分岐の宿の屋上に一人戻った青年に、下の階で幼馴染と話をしていた悪友が気が付いたらしい。人目を避けて屋上まで戻って来た。
「大変や、ライザ! オマエがそっちで頑張っとる間、こっちも交渉は中断で、動ける全員が洪水相手に必死やったんやけど――」
ディレステア王女とゾレン国王は、西派総帥の配下が結界を施したというこの宿で、洪水を辛うじて回避して留まっていた。
周辺地域の被害を可能な限り救うために、ゾレン軍もディレステア軍も「五色のケモノ」も自治団も、どの勢力も必死にできる限りの活動を行っていたという。その矢先のことだった。
「いつの間にか王女が、控室から消えてしもーたんや!」
「何――だって?」
「あれほどここからは動くなゆーたんに、お供の兵士さん何人か連れて、洪水が少し弱まった時に外に出たみたいなんや!」
それは現在、幼馴染が付近の鳥を総動員して集めている情報の一つだった。
「その上最悪や! どうやらあの洪水、里まで流れて巻き込んで暴れ狂いよったらしい!」
「……は?」
「里を守ろうとしてババァも行方不明や! たった一人で洪水に立ち向かったゆーから、多分無事では済まん!」
青年はその時――悪友が何を口にしたのか、咄嗟にわからなかった。
自らの身内について喋りながら、冷静さを保つ悪友を茫然と、不思議そうに見つめる。
「里だけやない! ここより北の被害が特に酷くて、要するに西部中の川をあれと同規模の洪水が襲ったんや!!」
「……――……」
「これは大変なことになるで……! 万一王女さんの身に何かあったら、色んな意味で取り返しがつかん大惨事や!!」
和平交渉に訪れた敵国の王女が、災害に巻き込まれて命を落とす。そして災害自体が化け物の力なら、それはその国の同国者すら犠牲にした卑劣な罠であり、両国の亀裂になると悪友は予見する。
「もう和平どころか、ディレステアからはゾレンへの敵意を、ゾレン側だって巻き込まれた奴らがディレステアへの憎しみを募らせかねん!」
「――」
たとえ罠を仕掛けたのはゾレン側でも、巻き込まれた者達は、誰かわからない黒幕よりも先に標的を憎むだろう。無言の青年にもそれはわかり切った見通しだった。
悪友はどうやら、色々な事が起き過ぎて既に許容量を越えているようで、逆に全ての衝撃を麻痺させた冷静さで対応に当たっていた。
「ヴァルト……レインさんは無事で、クランが保護してくれた。俺達の情報を『西派』に流したのは予想通りシーレスト達で、そっちはリミットがシーレストだけ捕まえてる」
「――ホンマか! そら良かった、さすがはライザや!」
青年側の状況を手短に伝えると、僅かなりとも微笑んだ悪友は、肩の荷が少しでも軽くなってくれたらしい。
「おれも『五色』、おれの鳥達を総動員して王女を探しとる! 人間やから気配で探せんのが厄介やけどな!」
行方不明の人間の王女を探す。いつかの第五峠を思い出した。その時は迅速に王女を見つけてくれた、人間の女。青年はまたずしん、と……重い胸の内に、あの赤い姿をよぎらせる。
あまりに様々な凶報が入る中で、効率よく情報を集めて救助活動に加わるため、幼馴染は王女を控室に待機させて外に出たという。
それから後に、王女に付けさせていた小鳥から得た光景を、厳しい面持ちで悪友にすぐに報告していた。
王女の傍らにいた小鳥は、その一部始終を、全て見ていた。
「助けて――……お母さんを助けて、おねえちゃん」
「……子供?」
少ない供の兵士と控室で、洪水の状況を見ながら待機していた王女の下へ、突然宿の廊下に現れた人影があった。
「お母さん、さっき外に出たの……帰ってこないの、助けてぇ」
幼い人影は涙ながらに、偶然叩いた扉の中にいた王女に懇願してきた。秘密裏に和平交渉を行ったこの宿に、他の客が泊まっていたのかと、王女はどうやら思ったらしい。
「ついさっきなら遠くには行ってないはず。洪水もさっきより弱まってるし、まだ助けられるかもしれない。一刻を争うわ、行きましょう!」
そうして子供に連れられ、ほんの少しだけだと控室を後にした王女は、兵士と共に外に出てしまい……。
舞い込む情報があまりに多過ぎたため、幼馴染はリアルタイムでその重要な情報を捉えられなかった。気が付いた時点で王女を追おうとしたが、王女に付けた小鳥はその時には、既に何者かに排除されてしまっていた。
それらの話を聞いた時点で、悪友も青年も――そして事の顛末を話した幼馴染も、おそらく誰もが事態をわかっていた。
「どう考えたって――罠だ」
悪友は幼馴染の方へ戻った。宿の屋上から青年は一人、王女の色を探して町を見回す。それも最早、無意味とわかり切っていた。
「王女は多分……もう……」
人間も化け物も、沢山の者を飲み込んだ暗い川の流れを見つめる。
そして今更に。ある人間の女の覚悟の、悲しさを思った。
その禍を解き放ちかねない者達の元へ、大いなる禍の子供を引き渡してしまった、弱い人間の娘を拒絶し――
こんな思いをするくらいなら、死んだ方がましだと、傍に残る化け物の娘に言ったある母。無力な人間がその覚悟を持たなければいけない、化け物との共生の悲しさがそこにはあった。
「こんなの初めから……誰にも、何とかできるものじゃない」
「力」の強い者こそが正しいと。
それは化け物には当たり前の、世界の共通認識である中――それでも人間のような秩序と平穏を求め、人間と共に創った人間と化け物の国。それこそが「ゾレン」のはずだった。
「アンタ達こそが、悪魔だろう……『悪魔祓い』――……」
人間と化け物の血を持つ青年の重たい声は、ただ無情な風に消え……。
そうして洪水が完全に治まり、町全体に秩序が戻って程無く。
この近辺のほぼ全ての鳥が、総力を尽くして探した人間は、日が暮れる前に見つけ出されることとなった。
「そんな……アヴィス、様……」
愕然と膝をついた軍曹の前で、力無く横たわる、人だったもの。
身元の証となる紋章入りのペンダントだけが、胸元に唯一無傷で残っていた。
それは確実に、洪水に巻き込まれたのだろう。遺体を検分した両国の軍医が、やがて共に証言した。
「いや、残念です。まさかの災害に、王女が巻き込まれるとは」
それでは護衛にも自分にもどうしようもない、と責任の追及を見事に逃れた仲立ち――人間と化け物の血を持つ西派総帥が笑う。
誰からともなく、人間の国の今後を考える声が上がり始めた。これで王位は、第五峠に常駐する第二王女へ移ると。
それは妹の王女に、姉の代りに嫁ぐ先が決まったことを意味した。
二国の未来と、自らの妹の幸せを願った王女の希みが、永遠に失われたその日……――
化け物の国と人間の国の、長い暗闇が始まる。
中篇 -了-
幕切:蒼い獣
長い時間を床に臥す、病み人の町を黒い水と炎が蹂躙したある日に。
その日から度々、ディレステアの西側でたまに感知される、不思議な震動の現象があった。
周縁を堅固な外壁に、空高くまで囲まれている砦の国で。
ずしん、と今日も、国の何処かの壁を、謎の何かが揺らす。
アああアアあああああ!!!!!
己の無様さに声は尽きずに。
人の無力さに衝動が滅びず。
心の無残さに獣は魂を失う。
天上にあっては、見えない壁として存在する古代の砦に、羽を生やした獣が激突を続ける。
決して破ることのできない壁は、獣の全ての赤熱を受け止める。
獣はそれを、普段は自覚することができなかった。
突然衝動が襲い来た時、それを空へと還すことが、獣にできる精一杯の抵抗だった。
傷だけが増えていく獣を、そこに駆り立てる赤い記憶。
――来ないで、と。最後にそれだけ小さく叫び、獣を永遠に拒絶した赤まみれの誰か。
何も残せず、誰にも知られず囚われ続ける誰かの痛みも、今の獣には遠く。
後篇・序
その砦の名前を、第六の峠――
ある戦いを繰り返す地と、誰もが忌避する宿場町だった。
「……ついに――ここまで来たのか……?」
国の周縁を囲む砦を持った人間の国と、争いを続ける化け物の国は、第四から第六の峠までを国境とする。
長き戦いに再び終止符を打たんと、第六の峠に闘う者が集う。
ずしん、と。
高くそびえる砦の麓、空をも別つ獣の叫びが響く。
「それじゃ……全て、終わりにしよう……」
冷え切った獣を赤く染める、もう取り戻せない蒼い記憶。
獣はその蒼を失い、彼らの赤い鼓動を清算するために牙をむく。
獣はこれまで、自らヒトを害したことはなかった。
辿ってきた道筋上、誰かを手にかけたことはあるが。
それは決して、獣が望む結果ではなかった。
けれどあの日――魂を失くした獣は自ら、奪うことを決める。
その赤い変質を全て受け入れた獣の、初陣が第六峠だった。
+++++
ふむ、と。ある怪鳥の女の葬送に訪れた、ごく珍しい旅人が息をついた。
気落ちした怪鳥の孫を避け、別なる友の息子である青年の元へ、女が死に至った経緯を尋ねに来ていた。
「なるほど。三種の宝器を揃えた竜の子供――竜人による水災か。それでは確かに、あいつほどの鳥でも、一溜りもなかっただろうな」
「…………」
男のような口調で、さっぱりした短い黒髪の旅人は、目を疑う程に端整な鋭い顔立ちの女性だ。青年の父とも親しかった、金色の眼の珍しい化け物だった。
普段は北の小島に存在する「聖地」とやらにこもっているが、死んだ怪鳥の女の古い友人だと青年は知っていた。
これだからな――と、金眼の女性は無表情で苦い溜息をつく。
「相変わらずこの『地の大陸』は物騒だが、それ以上の問題は、世界中でそうして、竜が野放しになっていることだ」
「あんなに強い力が……まだ他にも?」
「私も一匹、近いのを囲ってはいるが、アイツらの個体としての『力』の大きさは洒落にならない。バリエーションが多過ぎて『純血』とは言い難いのが竜だが、『純血』並みの世界からの強化――自然界からの力のバックアップと、それに『雑種』としての個体の強靭性があると思えばいい」
「純血」や「雑種」等、世界の様々な化け物の研究をしている女性は、女性自身が「純血」に属する化け物でもあった。
「あんたほどのヒトがそう言うなら、余程なんだな」
「正確にはヒトじゃないがな。まぁ、ヒト型をとって長いから、今更どうでもいいことだけどな」
博識な女性は金色の眼をつまらなさそうに細め、改めて葬送の中心地である広場に振り返る。女性が今いる山奥の里の、長老であった怪鳥の死に、大きく嘆く人だかりを眺める。
人だかりの誰かが、神よ、何故ですかと嘆声を漏らした。その声にまた大きく女性は溜め息をつく。
「知るか。私だってそれを訊きにここに来たんだ」
「……俺に説明できるのは、さっきのことまでです」
わかってるよ、と。「神」寄りの化け物である女性は、証たる金色の眼で、不服気な顔で改めて青年を見つめた。
「サラムが息子に丸投げした『五色のケモノ』に殉じたんだろ。単に山里を襲った洪水に巻き込まれたわけじゃなく」
「五色のケモノ」。青年の住む化け物の国「ゾレン」と、人間の国「ディレステア」二国のみならず、周辺地域の平穏をも目指す活動組織を継いだ青年は、憂いげに項垂れる。
「それで、あいつらが目指したディレステアとゾレンの和平は叶いそうなのか? それとも完全に望み無しになったか?」
「……」
「和平交渉の場で竜人の水災が起きて、ディレステアの王女がそれで死んだとなれば――明るい見通しは予想し難いがな」
そして青年は、つい数日前の惨劇……和平交渉の場となった二国の国境、第六峠で起きた一部始終を改めて思い返す。
後篇・起
――天罰でしょう。
世にも稀な大洪水に襲われたゾレン西部全土へ、西部の軍を現在統括する総帥の男は、そんな言葉を言い放った。
「現在のゾレンが歩む道が、天意に反しているのではないかと、ボクは考えますがね?」
王族として二国の和平の仲立ちを務めながら、庶民的な恰好で癖の強い茶髪をそのままに、顔立ちは整った総帥が言う。和平交渉の場となった第六峠で、最も大きい宿に集った者達――ゾレン軍、ディレステア軍、ゾレン第六峠自治団、そして「五色のケモノ」を前に、にこやかに言葉を続ける。
「一度目の和平交渉の地、第五峠に引き続いて、第六峠までをこうも大規模な洪水が襲うとは……こんな不自然な自然災害を引き起こしてしまえる恐るべき存在は、それくらいしかボクは思い当たりません」
「ふざけるな、ダウテッド。天意など我ら『雑種』には何一つ関わりのないこと――そして秩序正しき我らには、天罰を受けるべき咎など、間違っても存在はせぬ」
西部の総帥とは腹違いの兄にあたる現国王が、刺々しい眼光を向ける。普段の物憂げな貴賓の雰囲気が消え、あからさまな敵意がそこにはあった。
「兄者がそう仰っても、ゾレン西部の民はきっと今頃、各地で畏れ慄いていると思いますがね?」
全く物怖じしない総帥は、無邪気な微笑みを国王たる兄に向ける。
「天はおそらく、『雑種』と『人間』が手を取り合おうなどと、おこがましく思っているのではないでしょうか? この先また、和平などと言い出す度に、再び天罰が下らないか怖れなければいけない民は、さぞかし不安で一杯のことでしょうねえ」
「何の根拠があってそのようなことを言う。もしこれらの災害が意図的なものであるとすれば、その咎の所在を必ず明らかにし、然るべき処置を施すのみであろう」
自然の脅威の化身、「竜人」を隠し持つ目前の総帥こそ黒幕であると、国王は疑っていない。ひたすら断罪する視線を総帥に向ける。
しかしその疑いこそが――この総帥の狙いとは、この時点で誰がわかっただろうか。
「どうしても我らと人間は相容れぬというか、ダウテッド」
人間の国と和平を進める化け物の国の王は、腹違いの弟を厳しく睨みつける。
「貴様とて母親は人間のはず。我が国の人口は元来、半ば以上が人間であるのだぞ」
「嫌だなぁ。だからあくまで、天意だと言っているでしょう? ボクには別に、兄者の仰る通り、人間への恨みはありませんし?」
和平への妨害を否定も肯定もせず、ただ自らの脅威を現国王に知らしめるように、総帥は言葉を続けた。
「でもねぇ、軍でも自治団でも、見回り一つ満足にこなせない人間を目障りに思う民草は、ゾレンには多いんですよ、兄者」
「……」
「ほとんどの人間は実に弱小です。力はおろか、気配の探知もさっぱりできない者がほとんどだ。だから彼らは大概、何かがあれば化け物に頼り、その悪知恵だけは豊富ときたものだ……これでは天意から人間を庇おうなんて化け物は、この西部には存在しないと思いますね」
総帥の言う程、極端な形ではなかったにせよ、人間は弱小で化け物の負担となる存在――その上人間を庇えば災いが起こる、とゾレン西部の者は怖れを刷り込まれたはずだった。この後、西部は東部よりも、強く人間の排斥を行っていく未来を迎える。総帥と同様人間の母を持つ灰色の眼の青年は、化け物だけでなく人間にも植え付けられた認識に既に直面していた。
――私の仕事を取らないで、ライザ。
化け物と人間の混血である青年を、本当の弟のように目をかけてくれた人間の女性は、自らの体力を削る「千里眼」の特技に固執していた。その根本的な理由は、それだけが化け物達の役に立てる道だと見出していたからだ。
足手まといを自覚する女性は、異国の要所の赴任に同伴を求めた化け物の男の誘いに、決して頷くこともないままだった。
――何もできないから……アナタとは、行けない……。
その拒絶の根深さは、無力な者を負担とみなす化け物の国で生まれ育った人間ならではの部分がある。ここに来て青年はそれを、総帥の演説から一端を悟る。
人間の血を持つ総帥は更に、人間側の心情までをも推し量る。
「弱小な人間の方も、好んで化け物と関わりたいはずがない。大概の人間は化け物をただ恐れ、話ができるとは思ってません。だからディレステアとゾレンで住み分ければ良いだけの話が、何故に未だ両国共、化け物と人間の共生が、割合は違えど続くのでしょう?」
「知れた話だ。我ら化け物は世界に縛られる――生まれ育った地を離れれば、人間並みに無力化する化け物も多い」
「ええ、あくまで化け物の方はね。しかし人間はそうじゃない……なのに何故、人間は危険な化け物の国を出ないのでしょうか。それは単に、感情的な問題なのですよ、人間の場合は」
その時総帥は、あからさまな侮蔑を浮かべたようだった。
「だから天は、人間に警告を与えているのですよ。これ以上、化け物の国には関わるなと……たとえそれが王族であっても、無力な人間が踏み入ればどうなるかは、もうよくわかったでしょう」
つい先刻に、大切な王女を失ったディレステア軍の人間は士気が落ち、何も反論することができなかった。他にこの場で生粋の人間はおらず、総帥に言葉を返せる者はいないはずだった……その局面に。
「……いいえ。天意など決して、わたくし達には関係ありません」
隠しようのない気品に加えて、静かな勇気を感じさせる気丈な声色。この場で唯一、王族の総帥と対等に話せる人間が、凛としてその地に降り立っていた。
ざわざわとディレステア軍が動揺し、ゾレンの者もほとんど呆気にとられていた。そのような中で、第六峠に降り立った成人直前の女性……ふわふわとした金色の髪で赤い目の人間は、先刻亡くなった王女と同じ髪と目色をしていた。
「……ディレステアの第二王女か……!」
表情は動かさずとも、国王の声は驚愕を隠せなかった。その斜め前で、黒髪で赤い目の騎士――女性をここまで連れて来た男を横に、第二王女が真正面から総帥に対峙した。
「……!!」
「何やぁ!? あの王女さん、第五峠からここまで、わざわざ飛んで来たんか!?」
遠目でそれを目の当たりにした青年と悪友は、医療施設の集まる峠に常駐する第二王女の出現に呆然としかけてしまった。
「ヴァルト、俺達ももう少し近付くぞ! ここで第二王女まで失うわけにいかない!」
「お、おお! そうやな!」
「五色のケモノ」の真のリーダーである青年と共に、悪友である代表は、人知れず演説の場の裏に回り込む。
第二王女は凛と厳しい面持ちで、初対面のにやにやとした総帥をまっすぐに見据えた。
「国の行く末を決めるのは、天意ではなく人為です。わたくしとゾレン王が共に、和平の道を模索せんと志を持つなら、そこには必ず道が存在するのです」
ほほぅ? と総帥が、最早あくどさを隠さない顔付きで笑う。
「それで貴女の国の民が納得しますか? 仮にも王女が一人、命を落としたのですよ?」
「姉も覚悟の上だったはずです。そしてわたくしは姉の志を引き継ぎ、必ず和平を叶えるためにここに来ました」
そうした王女の厳しい眼差しを嘲笑うように、総帥はざわつくディレステア軍を横目で見ながら反論する。
「気高い貴女方はそれで良くても、民意は決してそうではない。ディレステアの民には必ず、王女を死なせたゾレンへの反発が起こる。そしてゾレンの民にも当然、ディレステアと関わったことで起こされた災いへ、恐怖が刻み付けられたことでしょう」
「……」
「最早貴女方ディレステアの者は、この国では存在するだけで罪です。敵国の王女の死は天罰だと皆が受け止める。それでも貴女は、この化け物の国との交渉を続けるとでも?」
人間側としての反論はできても、化け物の国の民については王女は口にできない。そのため黙って総帥を睨むしかなかったが。
「――違うわ! 亡くなった王女は、ゾレンの子供を助けようとしたのよ!」
ゾレン側で、それも化け物の女から上がった強い声に、場の全ての者の視線が集中することになった。
「交渉場にいれば王女は安全だったのに、自分の身を省みずに化け物の子供の願いを聞き届けて外に出たの! それで王女はあの洪水に巻き込まれたのよ!」
その声を発したのは、「五色のケモノ」幹部三人の最後の一人、代表のまたいとこにあたる鳥の化け物の女だ。真リーダーの青年とは幼馴染で、命を落とした王女の近くに、一番最後までついていた者だった。
明るくふわふわとした短い茶髪を揺らし、強気な灰色の目で、幼馴染は集まる全ての視線を弾き返す。
「仮にも私達ゾレンの子供を守ろうとした王女を、災いとみなす恥知らずの化け物がここにいるの!? 敵対国の子供のために命を落とした人間を、弱小と笑える化け物がいるなら出て来なさいよ! 私の言葉が信じられないと言うなら、魔道審問にだってかけるといいわ!」
化け物としては弱小である幼馴染の言葉。しかし表立って反論する度胸のある化け物は、そこには現れなかった。
そしてその姿に感銘を受けたのか、ディレステア軍にも動きがあった。
「我々ディレステアの者も……我が国の王女がそこまでして、守ろうとした二国の関係を……生半可なことで、決して否定などさせはしない」
王女の死に強く気を落としていた軍曹の声に、人間の軍人達のざわめきも静まっていく。
「……」
そうした人間と化け物の姿に、国王も総帥も各々の思惑で、難しい顔を見せて黙り込んだ。
第二王女は改めて、王女がそこに来た一番の目的――その要求を彼らに突き付けた。
「姉に代わり、わたくしが今ここで、和平交渉の継続に応じることとします。本日中の再開が難しいと言うのであれば、再開が可能となる日までわたくしは第六峠に留まります」
――へ? と総帥は、交渉の再開を求める王女にそこで露骨に嫌そうな顔をした。
「それは願ってもない話だ。一刻も早く交渉が再開できるよう、こちらも手配しようではないか」
いち早く反応したのはゾレン国王で、それに意見できる者など、そうそう存在するはずもなかった。
「多忙であれば仲立ちは貴様でなくとも良いのだ、ダウテッド」
「いえ、それは――しかし……」
想定外の事態に、咄嗟にどう出るべきか決められなかった総帥の隙。それを国王は承認の意として、一律に強引に定めるように……この場の総意として、交渉の再開をそこで決めていた。
そして、この地にしばらく留まると言った王女は――
「もしも天意が存在すると言うのであれば……あくまで人間を邪魔だと言うなら、わたくしを消してごらんなさい」
この場にいる全ての化け物に対して、そこで一つの宣言を行う。
「わたくしは必ず生きて、この交渉を最後までやり遂げます。そして、天罰などないことを証明してみせます」
それは決して、災害の黒幕にだけ当てた言葉ではない。今後、災いを恐れるだろうゾレンの者全てへの、弱い人間の宣戦布告だった。
+++++
無茶だな、と。旅人は、心から愉快という顔で笑った。
「余程護衛を信頼しているか、怖い者知らずなのか。それなら第二王女が生きている限り、天意は和平を拒絶していない、と良い報知になるな」
「……」
天意を強調した総帥が目論んだ、ゾレンの民への暗黙の脅迫。かつて和平交渉の場の第五峠を襲った「悪魔祓い」という集団の襲撃理由も、それを見事に反映したものだった。
「洪水を起こした悪魔を排除する……つまり、洪水という天罰を起こさせた、天意に沿わない邪魔者を排除する。『悪魔祓い』にとってその対象はディレステアの人間であり、そして『五色のケモノ』を始め、和平に賛成の者達だったというわけだ」
しかし王女の宣言は、その脅迫と闘うという姿勢に他ならなかった。
「そもそもからして明らかな人為的妨害だ。敵方に竜人という、洪水を起こす強大な力があるのが頭が痛いがな。王女を守る成算はあるのか? 『五色』」
洪水で死んだ、「五色のケモノ」長老の葬送のために帰郷している場合ではないだろう、と旅人が青年をじっと見つめる。
「……王女にはある意味、本当の天意……ヒトになった天使、騎士団長が常に護衛についてる」
それで青年達は、他にも命を落とした「五色のケモノ」の弔いも含め、一日だけ猶予をもらうことができていた。
「騎士団か。しかしアイツらは、第五峠だけが管轄だろう?」
「いいや。騎士団長は第五峠も襲った洪水の原因を捕らえるために、同じ洪水が起きた第六峠にしばらく留まれるらしい」
なるほど、と旅人は、再び楽しげな顔に戻った。
「第五峠にも手を出したことが仇になったか。仮にも元天使が守護する人間を殺すのは並大抵のことじゃない……それならオマエ達は、竜人相手に集中できるな」
「……そのつもりだ」
厳しい面持ちの青年に、ならば、と旅人は真面目な表情となった。
「旧知のよしみだ、竜人について教えてやろう。それで対策になるかわからないが、オマエならできることもあるかもしれない」
「――?」
「オマエの双子からオマエの話は聞いたよ。力の使い方を助言してやったのも、元々は私だ」
その双子とは、生まれた時から存在を隠された実の弟だ。常に放浪に出ている双子は様々な土地に出入りしており、また、この女性に魔道を幼少時から習っている。
今は青年の同郷の女性を逃すため、青年と共に流れる血の本性「飛竜」の姿で、遠い地へ飛び立った状態だった。
「私の腐れ縁にも、同じ力を持った奴がいるんだがね……」
そして旅人は青年に、青年のある特技の真意を語る――
+++++
うわぁぁぁおぁぁと。
長老を始めとする同郷者の葬送後に、内々の酒席で長老の孫はやっと、激しく涙を流す状態となった。その席にいる青年、幼馴染の前で初めて大声を上げる。
「何でババァが死ななあかんねんー! おれまだ、ババァから受け継いでない奥義が沢山あるんやー!!」
孫である悪友に負けず劣らず、泣き腫らした顔で座り込んだ幼馴染も、ひたすら項垂れている。
「マザーは私にもヴァルトにも、本当の親だった……ずっと、『子供狩り』に殺されたみんなの代わりに、可愛がって鍛えてくれてたのに……」
青年達の里があるゾレン西部には、「子供狩り」と呼ばれる徴兵制度が数十年前から存在している。二人以上の子供が生まれた家から長子を軍に差出させるのがその「子供狩り」だった。
それによって一人目の子供をとられた幼馴染と悪友の両親は、長老の制止もきかず、子供の行く先である旧王城に殴り込み、返り討ちにされてしまった過去があった。
そして双子の存在する青年も、その制度とは無関係ではなかった。
「……リーザを隠して育てるのは、長老の協力があってこそ、できたことだった」
自らの子供や甥夫婦を失った長老は、青年の両親には決して、「子供狩り」に表立って逆らうなと助言した。そのために青年の双子は存在しない者――飛竜の血をひく青年の一部として、事情を知る数少ない者達をのぞいて隠され、基本的に飛竜の姿で育てられた。頻繁に魔道の修行にも出され、そうして辛うじて存在を隠し、青年達は「子供狩り」の目を逃れることができていた。
「リーザが帰ったら、何て言えばいいか……俺も、わからない」
「……そうよね。それでなくてもリーザ……ピアが死んでからずっと何処か、張り詰めてるみたいな感じなのに。その上に、エアまで『子供攫い』として処罰されて――『五色』の子も、何人も犠牲になって。もう私達、みんなボロボロだわ……」
「子供狩り」に反発する集団として、数年前からゾレン西部には「子供攫い」という、旧王城に徴兵された子供を攫う謎の組織が暗躍するようになっていた。その「子供攫い」首謀者の女に偶然出会った双子の弟は、「子供攫い」に手を貸すようになった。
そして「子供攫い」が内密に青年達の里に潜伏を始めた頃に、密かに女と懇意になっていたらしいことを、女が第五峠の洪水の時に死んでから青年は確信していた。
「許せへん! 『子供狩り』がおれは許せへんー!!!」
旧王城に集い、例の総帥を筆頭とする軍部に、この場の誰もが同じ心をおそらく噛み締めていた。
現国王が即位する前には、本来は西部に王都があった。それを新国王の意志で、東部へ王都は遷されていた。
しかし西部の軍は西部に王都を戻すべき、と「西派」として新国王と対立するのが現状であり、長年冷戦状態の隣国、ディレステアとの徹底抗戦を続けんと、「子供狩り」をしてまで軍備を充実させる急進派が旧王城の総帥達になる。
「こうなったらおれは戦うで! 不戦派『五色のケモノ』は解散や、『西派』の奴らに目にもの見せたる!」
「ヴァルト……! 本気なの!?」
「アイツらが洪水の黒幕という証拠はないぞ……俺達がアイツと戦えば、先に国賊になるのは俺達だ」
現国王と「西派」は、一触即発の状態で均衡を維持している。ほぼ化け物の国でありながら秩序を重んじるゾレンでは、大義なく「西派」を糾弾することは、国王でも難しい状態だった。
「ライザ君の言う通りですね……ねぇ、国王様?」
「……」
しん……と。
突然現れた闖入者に、誰もが驚いて戸口を振り返り……そして絶句した。
「……トラスティ?」
その有り得なさに免疫のあった青年が、何とか初めに口を開く。
「内々の席に失礼するぞ……『五色のケモノ』」
「な、何で仮にも一国の国王サンが、こんな隠れ里に現れんねん!?」
慌てて涙を拭い姿勢を正す悪友と、衝撃が大き過ぎて時間が止まったらしい幼馴染。二人を横に、食卓の椅子を無言で青年が、国王のためにひく。
「あ、私は国王様の後ろにいますので、お構いなく」
「……」
一人の付き人は、青年達は若祭祀と呼ぶ顔なじみだ。普段はこの里の教会で祭祀を務める祭儀衣の男で、悪友と幼馴染が目を丸くする。
「アンタ……国王サンの知り合いやったんか?」
「我らが祭祀長はゾレン政務部のボスですからね。教会は基本、国王様には逆らえないものと思って下さい」
本当は国王直属の「王属部隊」である祭祀だが、国内の諜報屋という活動性質上、身分は隠したいようだった。
突然現れた国王は、物憂げな顔で重々しく口を開いた。
「これまでの働き、誠に感謝している――『五色のケモノ』」
「……」
「エア・フィシェルの件と、その他の『五色のケモノ』の尊い犠牲については……我が無力さに、慙愧の念に堪えない」
以前から秘密裏に、国王は「子供攫い」や「五色のケモノ」の青年、「千里眼」と接触し、各々を強く信頼していた。その国王にも、この状況は辛いものと、声色だけは示して余りあった。
「それでいったい国王サンが、こんな山奥に何の用やねんや? まさか、ババァに手を合わせるために来たわけやないやろ?」
当然のことを尋ねる悪友に、国王もうむ、と頷く。
「それも目的の一つだが、差し当たっては当然和平交渉の件だ。交渉再開の日程が決まった――一週間後だ」
「何やって!? そんなに早いんか!?」
「仲立ちは我が愚弟が続けるが、『五色のケモノ』も介在してもらう約束を取り付けている。何の企みがあるかは知らんが、それには奴は快諾した状態だ」
へ。と場の「五色のケモノ」全員が、信じられないという顔で国王を見る。
「当初は第六峠の今回の受難に、『五色のケモノ』の責を問おうとしていたようだがな。まだ交渉の流れが続いたために、今後他に、何かの責任を押し付けようとしているのかもしれない。この一週間、奴は全力で、ディレステアの王女を殺しに来るだろう」
「……――」
あまりにはっきりと言う国王に、場の全員の顔に緊迫が走った。
「ここで第二王女までが失われようものなら、ディレステアの我が国に対する敵意は未来永劫、消えない禍根を残す。私には全力でそのような禍を阻止する責務がある」
そこで後ろの祭祀が、ぱちんと指を鳴らす。
!? と驚いた青年達を余所に、戸口に二人の若い化け物の女が入ってきていた。
「紹介しましょう。国王様の知人にして相談役の、武人として誉れも高い獣使いと魔道士のお二人です」
おそらく他の「王属部隊」なのだろうと青年は思ったが、一応口には出さずに成り行きを見守る。
「アタシらは当面アンタらと協働して、ディレステアの王女を共に守る。アタシら以外の軍部の奴らは、和平の日まであまり信用できないと思っとけよ」
ムチを持った獣使いという女は、短い灰色の髪で体の線のよく出る服を着ている。とても端麗な容姿であるのに、ガラの悪い言葉づかいがアクセントといった女武人だ。
「皆様の足を引っ張らないよう、ゆめ尽力致したいと思います。何かあればご相談下さい、戦法でも料理でも、育児についても」
もう一人は青白いとしか言いようのない、頭まで覆う外套を着て短い杖を抱え、いかにも魔道士という女だった。
「料理や育児でも、って……」
唖然とする幼馴染に、あははと祭祀が楽しげに笑う。国王は一つ咳払いをして、場の空気を再び引き締めたのだった。
「確認しておくけど、アタシらの敵は『西派』と『悪魔祓い』でいいんだな?」
尋ねる獣使い――まるで長老のような言葉遣いの女に、無意識に警戒が緩むのか、悪友と幼馴染はあまり喋らずに素直に頷いた。
青年達の住むゾレン西部の二大集団の名。しかし青年は言葉を濁す。
「今、俺達『五色のケモノ』の目的の和平を潰そうとしてるのは、大体は旧王城の『西派』――『子供狩り』だけで、ソイツらが『悪魔祓い』の人間を利用した形だと思う」
「それ、一々分けて考える必要あんのかい?」
「そうですよねぇ。この先ワタクシ達の前に現れるとすれば、それは敵の『西派』さん、敵の『悪魔祓い』さんでしょう」
それに、と魔道士の青白い女は、女達がここに動員された大きな理由を口にした。
「『子供狩り』の総帥さんが『悪魔祓い』の実質的な支配者で、徴兵された子供の『竜人』が『悪魔祓い』のご神体ときいております。それならもう、『西派』も『悪魔祓い』も、一緒くたに考えて良いのではありません?」
「……そういう意味では、完全な敵を作るなら、『子供狩り』と考えてもらった方がいい」
歯切れの悪い青年に、獣使いは不服そうな表情、魔道士は顔は笑いつつ、目は笑っていない不信で反応する。
「お二方。ライザ君が彼らをまとめたくないのは、『西派』はこの西部全域の、西部の発展を願う者というイメージだからですよ」
まるで仲介役のように、にこにこと祭祀が割って入った。
「先日ライザ君達が捕らえた『西派』の一員も、彼らの総帥と『悪魔祓い』が関わっているとは夢にも思ってませんでした。『悪魔祓い』も本来は、ただの人間の集団ですしね」
「……問題は我が愚弟――『子供狩り』総帥にどの程度の兵力、影響力があるかだ」
そこで国王が厳しい表情で、青年を睨むように見る。
「『竜人』のデュラ・ユークと共にいる、強い力を持つ子供を、第一峠で見たと言ったな、ライザ」
「ああ。多分その女の子一人じゃなく、他にも沢山の強い力が近い所にあったと思う」
「愚弟め。幾人もの子供を神隠しとして報告したのは、やはり、私兵を育てるためか……」
「神隠し?」
苦り切った顔の国王に、「五色のケモノ」全員が首を傾げる。
「『子供狩り』で徴兵された子供達は、訓練が終わればゾレン全土、何処でも配備されるんですけどね。脱落者でもないのに途中で消えた子が、いくらかいるんですよ」
それも素質のある子に限ってね、と、祭祀が更に続けた。
洪水を起こしただろう「竜人」の子供は、徴兵されて早い段階で消えたと、少し後に青年は国王から聞かされる。
「幼子ばかりを私兵として囲うとは、総帥さんも相当いやらしい性質ですのねぇ」
「奴は昔から、自身は表立たず、他者ばかりを利用している。御しやすい相手を考えれば当然の結果だろう」
「なら『悪魔祓い』も御しやすかったってーのか? そっちは人間で、更にれっきとした大人の集団だろ?」
「その通りですよ。人間は一見化け物より賢そうに見えますが、弱小なためか、感情や環境に実に流されやすい。『悪魔祓い』の人間にはそもそも、ディレステアの人間への反感があるようで、ゾレンという危険地帯に住む自分達と、安全圏でのほほんとした人間達という対立構造を吹き込まれたようですね」
「それは一概に、否定はできん。だからこそ我が国の人間には、安全性の高い他地域への移住を勧めてきた経緯があるが、それでもゾレンに住む人間達は中々移住しようとはしない」
これまでの国の方針通り、国王は人間と化け物の分離政策自体は進めている。その点では、人間と化け物の共生を否定的に語った「子供狩り」総帥と、近い意見であるようだった。
そうした形で、突然の増援出現に何度となく置いてけぼりになりかけた青年達だったが。
「神隠しとして報告された子供達について、なるべく情報を探っておきます。お二方は『五色のケモノ』――特にライザ君の指示に従って、当面は動いて下さい」
「へ?」
何で俺が? と、見知らぬ相手の指揮まで振られた青年は当惑する。
「大丈夫です、怖くないですよ。これでも一人はドSに見えてちょいM、一人はMに見えてちょいSくらいですからねぇ」
「……ちょっと待て。今の何語だ、それ」
しかし謎の言葉で評された獣使いと魔道士は、獣使いは僅かに赤面して目を逸らし、魔道士はふふふと笑うばかりだった。
そんな妙な空気を作る祭祀に、国王はただ物憂げに溜め息をつく。
「そこの痴れ者も含めて、私にはこれだけしか信頼の置ける手数がないのが心苦しいが。我ら悲願の和平に向けて――今後も共に、戦ってくれるか? 『五色のケモノ』」
そうして青年だけでなく、ほとんど口出ししなかった覇気のない鳥達にも、改めて覚悟を尋ねていた。
「……当たり前や。ここで引き下がれば、ババァが浮かばれん」
悪友は、突然現れた者達を信用し難い様子ではあるが、はっきりと答える。幼馴染もそれに頷き、国王はそうか、とだけ、物憂げな顔のまま頷いたのだった。
+++++
突然の有り得ない集会が終わった後で。悪友、幼馴染は「五色のケモノ」の総員の緊急招集を行っていた。
若手でリーダー格の少年が、驚きの声を上げる。
「ええええ!!? 自分達は里に残れってどーいうことっスか、師匠達!!!」
「すまんなバルニカス。『五色のケモノ』活動は本日を以って解散……少なくともおれらは、ここを出て行く」
うぇぇぇ!? 若手達のざわめきに、悪友は一団をまとめて見据えた。
「おれらはこれからは下手したら、お尋ね者になる立場になってもーたんや」
「『五色のケモノ』は不戦派の集まりでしょ? まだ和平を諦めるつもりはないけど、私達と貴方達の『五色』は、違うものであってほしいの」
既に徹底抗戦の心を決めていた悪友達は、これ以上里を巻き込まないよう、幹部だけでの第六峠行きを決意していた。しかしそれは幼馴染の言う通り、「五色」本来の理念ではなかった。
「ええか? 今後おれらについて誰かに訊かれても、里を出て行った無法者やってオマエらは答えて、絶対に里を守るんや」
「で、でも、ヴァルト師匠、ハーピア師匠! 自分達も仲間や長老の仇をとりたいっス、戦いたいっス!」
若手達は一様に、その訴えに頷く。
「ライザ師匠も何か言って下さい! 自分達だけ置いてけぼりなんてあんまりっス、師匠達!!」
「……………」
これまでも何かと、青年は若手達から、話しやすい幹部と慕われていた。しばらく痛ましい顔で、若手達をざっと見回す。
「……大人数である方が、敵の思うつぼなんだ。わかってくれ……あの洪水には俺達だって、太刀打ちできないんだ」
仕方がないので、青年が把握している実情を可能な限り、そのまま説明を続ける。
「沢山の仲間が既に死んだ。和平を進める者を、敵は洪水に巻き込んで消そうとしている。それは他のゾレン人への警告にもなる。だからこれ以上、犠牲を増やすわけにいかない」
「でも、師匠……!!」
「洪水から逃げる力を持つ者だけが、第六峠に向かう。他は皆、『五色のケモノ』であろうとしてくれるなら――頼むから、自分達の平穏を守るために闘ってくれ」
幼馴染の言葉をより強く伝えた、青年の厳しい表情。滅多に見せない痛ましい険しさに、若手達は顔を見合わせて沈黙していた。
暗に伝えられた、足手まといという現実を受け止めたのだろう。悔し涙を流す者も多くいるようだった。
「……頼む。長老の代わりに、みんなで里を守ってくれ」
最後にそれを俯きながら言った青年に、若手達はこくこくと無言で頷き――悪友と幼馴染も涙を浮かべながら、場の者達が家路につくのを、ずっと見守っていた。
そうして「五色のケモノ」が集まっていた一方で、国王は祭祀に連れられ、内密に弔いの場へと赴いていた。
それを知ってか悪友は、複雑そうな顔で呟く。
「あの国王サン、ホントに真面目なんやろーけど……何でか、おれはイマイチ、信用する気になられへん」
「ちょっとヴァルト。そんなこと言ったら私達の方針、根本から崩れちゃうじゃないの。何がそんなに気になってるの?」
「いやなぁ――冷戦中の敵国の王女を守れって、仮にも国王がそれ言うんは、おかしないか? って。そこまで仲良うしたいんなら、絶対王政のこの国で、何で未だに冷戦が続いてんねん?」
その違和感はまっすぐな化け物の悪友は、受け入れ難いものがあるようだった。
「誰も彼もええ顔しとるんとちゃうか、あの国王サン。本気で目的を遂げたいんなら、できる権力はありそーやのに」
「でもまだ、即位されて二年もたたないじゃない。エアだって、国王様は足場固めの時期だって言ってた気がするし」
同郷の人間の言葉をそこで、人間の血を持つ青年が引き継ぐ。
「力ずくの改革は、その時は派手でも、結局は浸透しない……俺の親父が、何も変えられなかったように」
青年の父は飛竜の直系で、「五色のケモノ」の創始者だった。しかし病死する直前に第六峠、旧王都で「子供狩り」に反発して暴れ、その影響もあって王都が遷都したことを彼らは知っていた。
「ライザ……サラム様のことは……」
「でもなぁ、あの後に王都が東に遷ったやろ? 結果的にはそれは、サラムのおっちゃんの勝利なんちゃうか?」
「親父は遷都のために動いたわけじゃないし……トラスティは地道に努力して、多くの賛成を得て遷都を決行した。だから、東部は西部より平穏だと言うし――きっとそれは、今後も続く」
「まぁなぁ。少ししか行ったことあらへんけど、確かに東部は、たった一年で偉い発展しよったしなぁ」
悪友と幼馴染は顔を合わせ、うんうん頷き合った。
しかし、そのような国王をしてもこの化け物の国は、人間との根本的な溝を抱えている。
――我が国で少しでも隙を見せれば、容易に見限られるだろう。
常にその国王を物憂げにさせる、「力」の価値観。それは国王自身が非常な強さを持つ化け物であり、それ故に認められている限り、覆し辛い現実であるだろう。
――必ず非情さは必要とされる――私もお前も。
それなら逆に、生粋の化け物がそうした化け物らしくなさを持った国王は、どのような苦悩の下に生きてきたのか。その一端を、この少し後に青年は聞くことになる。
犠牲者の墓前から帰った国王が、何故か第六峠に帰る前に、青年の住む場所が見たいと言い出していた。
悪友と幼馴染は一足先に祭祀達と里を出て、青年は国王と謎の同行をすることになってしまった。
「いいのかアンタ……王なのに、一人でうろついてて」
「護衛は必要ない。あの中で一番強いのはそもそも私だ」
化け物の国の王の言葉に青年は頷くものの、現在何故青年の家に向かうのか、全く要領を得ていないのだ。
「気付いていないのか?」
「え?」
「オマエは気配探知を軽視し過ぎるな、相変わらず」
このまま行けば気付くだろう、とそこで国王は言葉を止める。
不意に、普段以上に難しい顔付きで、足取りの遅まった国王が夜空を睨み上げた。
「あの人間も、気配探知は苦手としていた……と言うより、全くできなかった。人間だから、普通ではあるがな」
立ち止まった国王の痛ましい目に、青年はそれが、第五峠で死んだ人間の女――「子供攫い」首謀者の話だとすぐにわかった。
「アンタとピアは……知り合いだったんだよな」
国賊とされている女と国王との関係という、あってはいけない問いであると知りつつ、あまりに国王が物憂げだったためか、つい口にした青年だった。
国王はしばらく立ち止まって、夜空を見上げ続けていた。
「……ピア・ユークは……私の、唯一の幼馴染みだ」
この青年になら、話しても危険ではないと判断したのだろう。自身と国賊のことを俯いて話し始めた。
「旧王城で、彼女はよく秘密裏に一人で鍛錬をしていた。兵舎を抜け出し、誰もいない場所をいつも探り当てていた」
「子供攫い」の女は元々、「子供狩り」に女自身が徴兵された身だ。国王も遷都前は旧王城で暮らしていただろう。
「私も一人になれる場所を常に求めていた。だからだろう……いつしか彼女と、顔を合わせる機会が増えたのは」
国王は何度も、彼女の自主鍛錬に付き合ったという。それもあって、彼女はあの戦闘力を身につけたのだ。
しかし人間という弱い生き物の女は、どれだけ武技を鍛えても、最終的に気配探知ができないことで軍に送られず、自宅に帰された状態だった。
そうした人間は、同じく「子供狩り」に徴兵された化け物の子供達には、見下げられ続けた。弱小のために逃げ腰が普通の人間の子供達からさえ、異端として孤立していたという。
「彼女は人間にしては才能が有り過ぎた。私は化け物にしては脆弱過ぎた。彼女は私に、まるで人間みたい、と、私が王子と知りながらはっきりと言ったのだ」
孤高な女は、子供ながら冷然としていた。後の「子供攫い」首謀者としての才気の片鱗を既に見せていたらしい。
自称脆弱という国王の、情けない姿を、青年も出会いの時に目にしている。だからこそ、国王は内心を言えるようだった。
「私は常に……苛烈な父に怯え、機嫌を窺っていた」
それは前王が亡くなった今ですら、恐れが残るような声色で口にする。
「ダウテッドは違う。奴は人間嫌いの父に都合の良い教育を受け、人間の母を苛めて楽しむ外道だった」
「……」
「奴や父に彼女が目をつけられぬように、私も表立って彼女の力になることはできなかった。……不甲斐ないと歎く私を、彼女はいつもその時だけは、嘘のように笑って励ましてくれた」
――ありがと、トラスティ。トラスティは、マジメだねぇ。
でも、と毎回必ず、幼い人間はそこで言葉を付け加える。
――そんなにマジメだとしんどいね。ホント、人間みたい。
それは褒め言葉ではないが、決して侮蔑でもなかった。
何より軟らかく微笑む人間の姿が、掛替えのない唯一の癒しだったことを……その人間が家に帰されてから彼は知る。
「……我々人間と化け物は……同じ場所で生きれば、人間が犠牲となることが多いはずだ」
「……トラスティ」
「人間が武装し、力を得た所で同じことだ――それは却って、人間同士でも争いを呼ぶ。彼女のように化け物と渡り合い、命を落とす者も多く出るだろう」
そうしたことを女の死から、国王は更に強く思ったようだった。
「人間と化け物の分離は……人間の国との和平を得た後にこそ、着実に進めていくことができるだろう」
あくまでその方針は揺るがない。そう言いたげな国王だった。
「オマエのような混血には、この国はどうなのだ? ライザ」
「…………」
国王の問いの重さを思い、青年はしばらく、ひしと言葉を呑む。
「……うちの親父は、人間と共に生きたくて、多分『五色』を創ったんだ」
「……」
「きっと親父も、アンタみたいに――人間との方が、一緒にいて楽だったんだ」
だから混血の自分がここにいる。青年は慎重に国王に答える。
「俺にはどちらがいいのかわからない……わかるのは、ただ、アンタが無理をしてるってことくらいだ」
「……混血らしく、定見がないな、相変わらず」
生粋の化け物から青年は、どうやらそう見えるようだった。それ以上青年に答えられる強い思いは確かになかった。
その後の国王は、しばらく黙って青年と共に歩みを進めた。
そして近付いてきた青年の自宅の、近所にある木造の家に、明かりが灯っているのを青年は目にした。
そこはもういないはずの「千里眼」の家だ。驚きと共にその家に在る二つの気配にやっと気付き、ここまで来たいと言った、国王の言葉の意味を知る。
+++++
「え――?」
勝手知ったる相手の家とは言え、慌てて不法侵入した青年を、同じく侵入していた者達が気付いて出迎える。
「――あ。ライザ、やっと帰ってきた?」
「おっせーよ。てか、国王サマ連れかよ」
青年の帰りを待っていたらしい二つの人影。一人は青年の双子の弟と、もう一人は「子供攫い」首謀者の女の妹で、竜の血をひく混血の少女だった。
「二人共……何で、レインさんの家に?」
無言で後ろに佇む国王の前で当惑しながら、青年とそっくりで適度に尖る銀色の短髪、灰色の目の双子を見る。
混血の少女を連れて来た張本人の双子は、お気に入りの縦襟の上着を直しながら、手にした大きな荷物を掲げる。
「エアの姐貴の荷物を取りに来たんだよ。ゾレンじゃ今ん所、洪水に巻き込まれて死んだっつー見解みたいだが、しばらくはザインで療養になるし――どの道ここには、もう帰ってこれないだろーしな」
「それはいいが……何でミリアまで? リーザだけで別に……」
「駄目よ、女のヒトの荷物なんだし。それに元々、わたしがリーザに、連れて来てほしいって頼んだの」
混血の少女は、石竹色の布で肩の高さで束ねた、長い黒髪を背中側に軽く払う。そのまま暗い青の目に微かな澱みを浮かべ、青年を見つめた。
「ライザに相談したいことがあって……リーザも急いでて用事があるのに、わたしが無理を言ったの」
「――え?」
「オレは第一峠で、若祭祀に頼まれ事があるんだよ。話が済み次第、ミリアを連れて第一峠に帰る」
日頃から放浪に生きる双子は、その時何故かちらりと国王を見て、国王も事情を知るように双子の方を見ていた。
「俺に相談って――わざわざ、何だ?」
ここしばらく、混血の少女は第一峠に魔道を学びに留学していた。その目的は洪水の主――竜人たる弟を止めることだ。
しかしなるべく少女を荒事に巻き込みたくない青年は、少女を嫌な予感と共に見つめ返す。
ところがその相談は、嫌な予感は的中しつつも、違う方向の内容だった。
「あのね……リーザの力を、わたしに貸してもらってもいい?」
「――へ?」
暖炉に勝手に薪をくべる双子を横目で見つつ、青年はポカンとする。
「ヘルシャ大使は、わたしの力とリーザの力を合わせれば、危険だけど、デュラに対抗できるかもしれないって言うの」
しかし危険なのだ、と。それに双子を巻き込むことを躊躇うように、少女は僅かに目を伏せながら問いかけていた。
青年はそこで、辛いような難しいような顔を浮かべざるを得ない。
「……リーザのことは別に、リーザが決めたなら、俺は構わない」
でも、と、願うような視線で少女を見つめた。
「ミリアがあの洪水に、同じ竜の血を持ってても、対抗できるとは思えない……ピアの二の舞にならないように、ミリアには、俺は隠れていてほしい」
まだ魔道を学んで一年もたたない少女に、大層な事はできないはずだ。青年は躊躇いだけを口にする。
しかし、青年の無意識の誤魔化しをまるで断罪するように、双子があっさりと後押しに出た。
「できるんだよ。『竜の眼』を使えば、今すぐに」
それはこれまでにない冷然とした色の、双子の空ろな声でもあった。
「けれどそうすれば、ミリアからは万が一の保険が失われる。自動で発動しなくなるだけで、使うことは可能だけどな」
その双子の言葉は青年に、旅人に聞いた話を否応なく思い出させた。
――いいか? 竜人が何故竜人と呼ばれるか……そもそも竜とは、個体もバカ強い上に、宝を持って存在する化け物なんだ。
そして竜と呼ばれる化け物は、洪水などの自然の脅威そのものの竜人、龍神と呼ばれる蛇に似た化生、飛竜と呼ばれる青年達が代表的だと旅人は語る。
――竜人はちょうど、概念としての龍と、獣としての飛竜の間の存在だ。龍の中でも自然の脅威の力を持った竜が、獣としての存在、ヒトの形を得たもの、それが竜人で……。
この辺で青年は理解の限界に近付きかけ、呆れたように旅人は言い直してくれた。
――つまり竜人は、龍たる強い力に、飛竜たる頑強さを持った化け物と思えばいい。龍神は竜珠と逆鱗の秘宝、飛竜は炎の血に耐え得る体を持つが、その全ての性質を持ったような三種の宝器を、生粋の竜人は持っている。
だからこそ最強と言われる種族が竜だ、と、難しい顔で項垂れる旅人だった。
――竜人の条件は、自然の脅威たる己を頑強なヒトと化す『竜の眼』が必須だ。加えて神たる龍に近付く程に、『竜珠』や『逆鱗』など他の宝も増える。
そうなるとそれは――「竜の眼」を戦いに使うというなら、それを持つらしい混血の少女から、頑強さが失われる危険を意味していた。
「眼は二つあるから、一つ残せばヒトではいられる。それならわたしは……わたしも戦いたいの、ライザ」
その少女の確かな「力」になる物が、第一峠にはある。そのことは青年にも心当たりがあった。
だから青年は、少女は第一峠で強くなれることはわかっていたが、それを伝えず言葉を呑んできた状態でもあった。
「…………」
あくまで少女を危険に巻き込みたくない青年の葛藤を、それと知るように双子は、青年を見ずに淡々と言う。
「あの竜人の力はアニキも知ってるだろ。アレを止めるなら、同じ竜の力を持ってくるしか方法はない」
そして双子は、まるで青年を挑発するように――
「オレはミリアを戦わせる。文句があるならオレに言えよ――オレは何をしてでも、竜人に勝ってやる」
「……!」
冷たい声で言い放った双子に、青年はカチンと顔を上げた。
双子はそのまま、何の意図があるのか、冷徹な言葉を続ける。
「戦う力があれば、化け物に女子供は関係ない。使えるものは使えばいいし、戦う意志があるなら殺し合えばいい」
「リーザ……オマエ……」
青年はその内容より、青年に向けられた双子の敵意に、厳しく双子を睨み返した。双子は僅かにそれから目を逸らして言う。
「アニキもオレを使えば、強くなれるんじゃねーの?」
それは両親が生きていた頃に、青年に何度となく勧められた禁忌。
双子とは違って、頑強さは一般的な青年に対して、両親がずっと迷いを持っていた事柄だった。
「アニキが嫌がるからやってないだけで。そんな感じでいつも、アニキは甘くて――危なっかしいんだよ」
そうして銀色の髪の青年が二人、入り口と暖炉で立ったまま睨み合う。暖炉側にいる少女は俯いて黙り、入り口側の国王が難しい顔で、間に入った。
「……まるで獣の理屈だな。リーザ・ドールド」
青年の後ろに立ったまま、気難しい声で割って入る。
「否定はせぬが、八つ当たりはよせ。己の非力さから逃げるな」
「……」
双子は人が変わったように無表情のまま、しばらく国王のことも睨み付ける。
不意に全員に背を向け、無言で勝手口から出て行った双子に、青年が静かで長い溜息をついた。
「リーザは……長老のこと、きいたんだろうな」
「……うん。でも、それだけじゃないの」
「――?」
少女は躊躇いがちに、青年を見ながら上着を軽く掴む。
「わたし今、第一峠でしばらく、リーザの近くにいるけど……」
洪水の日に第六峠に駆けつけた少女は、その後に第一峠という山上に飛竜――青年の双子と向かい、共に滞在していたというが。
「リーザは――……ヒトだよね? ライザ……」
青年に相談したかった、本当の話はそれだと言うように、少女は青の目を憂いに染めて、思いもかけず俯くのだった。
+++++
第一峠に帰る双子と黒髪の少女を後にし、青年は国王と、第六峠へ向かう街道に入った。
ほとんど無言である青年に、国王は不意に、溜息をつくように尋ねた。
「気になるのか。先程のあの娘の話が」
「……」
それしか頭に無かった青年を、わかりきったことだと国王が頷く。
「それは双子であるオマエが一番、感じていただろう」
それでも何もできていない青年の無力さを突き付けるように、厳しい声を投げかけてくる。
――リーザ、第一峠でもほとんどの時間、飛竜の姿でいるの……まるでヒトの形の方が、仮の姿に思えるくらいに。
双子の弟の変化は、「子供攫い」の女が死んだ時から少しずつ始まっている。双子とその後に初めて会った少女は、元々の双子がどのような者かわからないため、当惑気に青年に尋ねたのだ。
――わたしとの特訓のためかもしれないけど、でもわたしがいなくても、リーザは飛竜の形でばかりいる……さっきライザと話した時以上に、張り詰めたみたいな感じで……。
それはまるで、己以外の全てを警戒する獣のようだと――
青年の前には基本ヒト型で現れる双子の、今まで通りの姿の不自然さこそ、青年も強く持っていた違和感だった。
「せいぜい気を付けてやれ。オマエ達程に近い双子なら、様々な方法で互いを補うことができるはずだ――たとえこの先、どのようなことがあったとしても」
淡々と言う国王に、青年は不可解気に声色を低くする。
「俺とリーザは、全然似てないのに?」
「似ていないことこそ近い証拠だ。オマエ達は同じ生き物の、違う部分を分け合った存在なのだろう?」
国王の言う通り、人間の血をひいて生まれた双子の兄弟は、それぞれが互いに、欠けた所を持つ化け物だった。
「魔道においても、双子程に互いの強化因子になるものはない。オマエが危なっかしいというあの男の言葉は、私も賛成だ」
「…………」
それは弱小ということかと、青年が不服げに黙り込んだ所で、国王は現在、最も恐れるべき話を加えた。
「……エア・フィシェルをオマエと飛竜が助けようとした所を、おそらく愚弟はあの時、見ているはずだ」
ぐさりと、青年を最も追い詰める可能性のある事柄。大罪人とされた女性への、飛竜の幇助の事実を口にした。
「この先何処でそれを持ち出すかわからん。奴はいつも、様々な駒を使える時まで取っておく……油断するな」
その後の国王はほとんど喋ることもなく、青年もただ押し黙った。
辿り着いた目的地では、驚くべきことを揃って知る。
+++++
……は? と。前回の和平交渉場所だった宿に、後から着いた青年の茫然とした顔に、待ち受けていた悪友と幼馴染が状況を説明してきた。
「有り得へんたら有り得へんで!! 今度の和平交渉の場は、ここやのーて、屋外でやるなんて決まったゆーんや!」
「それも川辺に緊急で会場を作るっていうの、信じられる!? いかにも洪水起こしますよって、完全に脅迫じゃない!」
和平交渉の表向きの仲立ちを再度引受けた総帥は、そうした事柄を決定する権限こそが目的だと、露骨にわかった。
しかしそれ以上に有り得ない、と悪友達が騒いでいるのは――そんな条件を二つ返事で引き受けた、第二王女の対応だった。
「断れば交渉自体を白紙にするとか、そういう暗黙の圧力でもあったのかしら……」
「無理難題を越えてるやろ、それ! おれらだって一応介在の権限があんのに、何で相談無しに決めてもーたんや!?」
川辺での和平交渉という、馬鹿にされているとしか思えない状況。それもより命の危険が増す条件を受けた王女の真意を、しばらく立ち尽くしていた青年と国王は、顔を見合わせて悟っていた。
「……大したものだ。それでも王女が生き残り、和平が進めば、西部の民も納得しやすいだろう」
「天意なんて関係ないって――本気で証明する気なのか」
同時にその無謀さと勇敢さに、二人して唸る。
「それじゃあ今、王女はディレステア大使館に戻ったのか?」
「ええ、リミットにずっと護衛をしてもらってる。騎士団長は凄く嫌そうだけど、王女は喜んでるわ」
幼馴染が口にした少年の名は、元は「子供狩り」で徴兵された者の一人だ。大火傷を負って脱落し、軍には送られず「子供攫い」に攫われ、その後に「子供攫い」の一員となった――一見十五歳、本来の年齢は十歳という少年のことだった。
「まぁ、元天使サンと魔縁の組み合わせなんて、基本は完全に敵同士やもんなぁ。騎士団長サンもよー我慢しとると思うで」
その少年は、姿や気配を透明にできる特殊能力を持ち、武技も秀でた方だったが、軍が求めるのは「力」自体の大きさなのだ。火傷のためにろくに体も動かなくなった少年は、それでも再起するために「魔」と呼ばれる生き物――ヒトを喰うことで今まで以上の力を手に入れる存在へと、自らを堕としていた。
……と、青年もつい最近までは認識していたのだが。
「ヴァルト。ああ見えてリミットは、本当にヒトを喰ったことはないのよ。『魔』だって偏見で見ないであげて」
「子供攫い」として少年は幾人もヒトの命を奪ったが、それを喰らうことは基本的になかったという。「子供攫い」首謀者の女の血や、女が死んでからは青年の幼馴染が与えてくれる鳥の魂を糧に、「魔」の力を繋いでいる。
それが明らかになったのは、少年を護衛として一人で第六峠に残すのを躊躇った時に、自分はヒトなど喰わないと、初めて不服げに言ったからだった。
そうして少年は青年と幼馴染、そして顔見知りの王女には、言葉数が増えてきた状態なのだと幼馴染が語る。
「王女はライザが、リミットの悪魔を祓ったんだって、とても喜んでたわ。亡くなったアヴィス王女のことで、騎士団長と二人の時はずっと泣いておられたけど……リミットについてもらってからは、大分元気になられてきたの」
難しい顔を少しだけ和らげた幼馴染は、数多の小さな鳥と魂を介して繋がり、それらが得る情報を共有できる化け物だ。王女や少年にも常に鳥を付かせ、見守っている状態だった。
「……そうだな。王女も……ピアが守ろうとした相手だった」
それでも確実に少年が変わりつつある理由は、少年を何かと構う幼馴染の影響ではないかと、青年は何となく思っていた。
国王と別れ、国境である第六峠のゾレン側に存在している、ディレステア大使館に一行はつつがなく辿り着いた。
大使館は俄かにざわめいており、青年達にディレステアの軍曹は手短に事情を説明した。
「実は――第一峠のディレステア大使が行方不明となったと、緊急の一報が先程入ったのです」
「第一峠の……ディレステア大使が?」
咄嗟に怪訝な顔となった青年は、その大使に直接会ったことがある身だった。
「これは天罰だ、次は王女の番だろうと、既に第六峠でも噂が広まりつつあるようで……これから数日が山場ではないかと、私は考えています」
「……そうだな。『悪魔祓い』が、動き出したのかもしれない」
青年にとって、思い当たることは一つあった。第一峠大使は「悪魔祓い」とザイン地方の通商業者を取り持ち、「悪魔祓い」に属する者の顔を知っている人間であることだ。
「口封じをされた可能性がある……これからする何かのために」
顔を苦く歪めた青年の推測が、正しいと裏付けるように――
それから様々な作戦会議をした数日後、「悪魔祓い」は突然姿を現すことを、青年達は目の当たりにする。
+++++
その訪問はあまりに早朝だったために、見張り以外はまだ誰もが、淡い微睡みの中にいた。
朝靄が立ち上がる中で、ふっと、壊れかけた呼び鈴が鳴った。
国の周縁を外壁で囲まれる砦の国ディレステアの、限られた六つの入り口の一つである大使館。その石造りの正門に、小さくも確かな訪問者の自己主張が響く。
「――何だ?」
交代前の衛兵が数人で正門に向かう。長い冷戦でボロボロの塀で、鋼の扉から格子ごしに訪問者を確認する。
「こんにちは。『悪魔祓い』だよ」
「!!」
衛兵達に一瞬で緊張が走る前で、その幼女は無邪気に笑った。
「神託を届けに来たの。ね、オル」
衛兵達が緊迫するのも当然だった。肩までの褐色で内巻きの髪の、全身を覆う防寒具を羽織った幼女は、何と――頭が二つある山犬のような異形の獣にまたがり、大使館を訪れていた。
扉ごしに咄嗟に銃を構えた衛兵達を、幼女は楽しげに見回す。
「ひどいなぁ。イタイケな子供に銃を向けるなんて」
明るい柑子色の外套の内から、何やら手の平サイズの透明な塊をすっと取り出し、幼女と衛兵達を隔てる正門に向けた。
そうした異変を知る由もなく、護衛と仲介を請け負った銀色の髪の青年は、王女の滞在する部屋の隣室で仲間と共に眠る。その夢の内には、数日前の黒髪の少女が現れていた。
――リーザは――……ヒトだよね? ライザ……。
それは実際、とても残酷な問いかけだった。
双子は生まれた時から存在を隠され、青年の飛竜――獣としてのみ自由に動けた。この国ではそもそも、ヒトとして在ることを許されない身上なのだ。
――力を貸して。アナタの双子の弟……リーザのように。
青年を誘った「子供攫い」の女――出口も退路も無い国賊に、青年と違って双子は頷いた。それは隠れて放浪に生きていた双子が、初めて自ら見出した居場所のはずだった。
それを突然失った双子に、彼らの姐貴分だった人間の女性は苦い顔をしていた。
――……落ち込めるなら、まだいいんだけど。
今までと変わらずに強く生きる双子を、見守ることしかできない……兄たる青年も同じ気持ちだった。
誰にも何も求めない双子は、戦うことだけを考えている。青年にはそうとしか見えなかった。
それは、嫌な胸騒ぎだけをもたらすもので。
母が流行り病で死んだ後、暴徒のような行動をとった父。冷静な双子は違うようでいて、父も、そんな行動をとる直前まで普通に見えていたことを、今更夢現に思い出していた。
そうした微睡みを突然、大使館全体の一瞬の震動が妨げていた。
「!?」
震動は大したことがないが、この大使館へのそんな異状自体に、青年はがばっと飛び起きる。
「――何か来た」
同じように仲間が起きていた。紅い目で白い鳥頭の少年が、ぎらりと鎖付きの錐型の短剣を抜いて立ち上がった。
「ヴァルトとハーピアを起こしにいってくれ、リミット」
王女の滞在部屋を挟み、反対側にいる仲間のことを言う青年に、少年はこくりと頷く。
「一瞬だが第一峠の時と同じ色が見えた。もしも前言った敵に出会ったら、教えた通りにしてくれ」
「……わかった」
硬い顔でも素直に少年は頷き、部屋から静かに出て行った。
それを見届けると青年は、廊下に出てすぐ窓から飛び降りた。それに飛びついてきた小鳥を肩に、正門へ駆けつける。
そこで起こっていた異状に、一瞬で激しく胸が悪くなった。
「あ。やっと少しはマシなのが来たね」
大使館の建物に震動を起こしたと思しき、巨大な透明の水蛇がいる。更にはその内で苦しそうにもがく、数人の衛兵に青年はすぐ気が付いた。
「貴様――!」
爪を立てて血の滲んだ手掌から即時に炎を出現させ、衛兵達を飲み込んだ塊に、炎の手で風穴を空ける。
「残念、もう少しでご馳走様だったのに」
塊自体は止められないが、衛兵達だけは穴から引きずり出した。正門の外にいる、二つ頭の山犬に跨る幼女がフフフ、と無邪気に笑った。
「でもいいや。ちゃんと神託、伝えてもらわないとだし」
「!?」
幼女がぱちんと手を鳴らすと、途端に小さくなった透明な塊が幼女の手に戻る。
「王女様に、こんな所に隠れてないで、『悪魔祓い』の審判を受けに来てねって言って。じゃないと王女様の代わりに、この西部のヒトがまた罰を受けることになるよ」
「な――!?」
「川辺で待ってるね。半時以内に現れなければ、神様に降りて来てもらうから」
一方的に言いたいことだけを口にすると、幼女を乗せた二つ頭の山犬がくるりと背を向けた。
塊に飲み込まれていた衛兵の生存を確かめるので精一杯の青年を、そうして軽々と後にしたのだった。
「審判だと……――ふざけるな」
「悪魔祓い」と名乗った幼女の目的は明らかに、大使館から王女を外に出すことだと悟る。
「西部のゾレン人全体を、人質にする気か――」
騎士団長だけでなく、魔女、魔道士、様々な者による結界で、今の大使館は強固に守られていることに気付いたからだろう。
青年と衛兵達から報告を受けた王女は、すぐにもその決断を下していた。
「川辺に参りましょう、マイス殿」
「…………」
強固な砦と化させた大使館から、みすみす王女を外に出す。常に無口な騎士団長が苦い顔で沈黙するのは当然だった。
「『悪魔祓い』とそれで対面できるなら、それを捕らえるのがわたくしと貴方の役目です」
短い黒髪で鋭く赤い目の騎士団長を、同じ赤い光の目で、王女はまっすぐに見つめ返した。
紅い目の少年に起こされた幼馴染が、すぐにも配下の鳥を青年の肩につかせて、状況を確認していた。
「間違いないわ。先日の洪水の時、アヴィス王女に声をかけて連れ出したのは、ライザがさっき見た女の子よ」
先刻の幼女自体に青年は、大きな「力」は感じなかったものの、人間でないことはわかっていた。連れていた水蛇は幼女の「力」でなく借り物だろう。
「大使館と衛兵を襲った水の塊は、俺が第一峠で一度飲まれた水蛇だ。『竜人』デュラ・ユークと共にいた、子供の魔道士が使ったものと全く同じだった」
まず間違いなく、その幼女、竜人、幼い魔道士は仲間だと、全員が結論する。
ロビーに集まった青年、紅い目の少年、悪友と幼馴染、王女、騎士団長に加え、新たな人員が大使館に駆け入ってきた。
入ってきた四人の男女の内、黒一点の男は祭祀で、女二人は祭祀の連れる魔道士と獣使いだったが、
「王女。相手が子供とは言え、甘くみられてはいけません」
後一人は、幼馴染と紅い目の少年だけが知る女だった。魔女と呼ばれる、黒い外套に頭を含め全身を包んだ真面目そうな女だ。
「彼らの司令塔が気になります。仮にも神託と口にする者が存在するのは、捨て置けません」
祭祀が連れる女魔道士と、魔女がどう違うかと言えば、回答は簡単だが見分けは難しいらしい。
「『純血』が暗躍している可能性があります。二つ頭の獣など、そう簡単に存在してよいものではない」
世界に存在する数多な化け物は、大きく「純血」と「雑種」に分かれる。魔道士とは魔道を後天的に学んだ「雑種」または人間で、魔女とは先天的に魔道を理解する「純血」だという。
つまりその魔女は「純血」であり、今回同じ系統の化け物が関わってきたことに対して、この場で警告を発しているのだ。
ゾレンは主に「雑種」という、多様性があり血筋は古くない化け物が営む国だ。それに対して、神や鬼、妖など血筋が古く、存在型の固定した化け物が「純血」と呼ばれる。
本来「雑種」には不干渉主義で、住処も違うはずの「純血」が動いた危惧がそこにはあった。
「それでも半時と言われた以上、迷う時間などありません」
王女はきっぱりと言うと、外出用の白い外套を羽織り、場の全員に対してそれを告げた。
「敵は『悪魔祓い』だけとは限らないようです。おそらくこの中の誰もが、各々に因縁を持った相手があることでしょう」
「……」
青年達には「子供狩り」が。王女と騎士団長には「悪魔祓い」、祭祀達は「旧王属」など、この数日で個々の思惑を多少なりと把握したらしい王女が宣言する。
「目標は一つです。皆さんが、それぞれの守るべきものを守り、生き残って下さい。わたくし達は洪水を止めに向かいます――同じ目的を持つ方は、どうぞ共に」
以前青年がその勇敢さに呆れた王女は、全くためらうことなく、騎士団長と魔女を引き連れるように、ばさりと外套を翻して大使館を後にしたのだった。
そんな姿に、結局場の全員が続くことになった。
「おそらく今日が山場ですね。交渉日より前に決行するのは、余程交渉が天意に反していると主張したいんでしょう」
ひそひそと囁く祭祀に、その本来担うべき役割を不意に思い出した青年は、つい下らないことを訊き返していた。
「……アンタの神は、本当は何と言ってるんだ?」
世界で広く神を讃える一員、原理教会の祭祀は楽しげに微笑む。
「我々は『神』が与えたもうた秩序を維持することが役目です。世界は『力』同士の拮抗で成り立っている。それを大きく乱し、『意味』を超えた力を振るう混沌こそが我々の敵なのです」
この状況でも妙な説教をのたまう祭祀に、青年はふと、唯一知る「神」寄りの化け物の言葉を思い出した。
――私達は別に、殊更人界に介入する気などない。それぞれ勝手に己の持ち場で楽しくやってるし、力を貸せという不躾者は多く存在するが、私達にできることはごく限られている。
里の長老の知人であり、双子の弟の師であり、父の友人たる旅人の女。
――私のようにこうして人界に降りてるのも、余程の好きものだ。それも己の『意味』、真名を体現できる器があってのことで、その通りの『力』しか使えないが……この世界で生まれた化け物の竜人の方が、私達より好き勝手できる分、余程脅威でね。
旅人曰く、竜というのは、神にすら制御できない化け物だとあっさり明かされていた。
――だから神からは、奴らに首輪たる宝が与えられた。奴らの力を増すことにもなるが、それが『逆鱗』で……さて、今回はそれこそが、オマエ達を追い詰めているとみた。
旅人の言についてはその後、竜人の実の姉の少女にも青年は尋ねてみた。少女もそこで、悲しげに頷いていた。
――うん……デュラは元々は、優しい、いいコだったよ。
第一峠で青年が出会った竜人は、まだ十歳にもならない幼い男の子で、見知らぬ青年の安否を親身に心配してくれた。
しかしその幼子こそが、黒い髪の少女が慕っていたもう一人の姉、「子供攫い」の女を殺したのだ。
――ねぇ。ピアは……デュラに、殺された?
水脈を司る竜人、洪水の化身。女が「子供狩り」に差し出してしまった、この世の禍。
青年の眼は、その禍も、自身の血に潜在する炎の「意味」もありありと見える。旅人曰く、「力」を視て「力」に介入できる眼なのだという。
大勢で辿り着いた最寄の川辺で、青年はその彩の無い眼で、またしても有り得ない光景を直視することとなった。
「……デュラ・ユーク……」
川辺には二匹の異形の獣と、その背に横向きに座った二人の子供が待っていた。一人は先程青年が出会った幼女だが、もう一人は悲しげな黒い大気の渦を纏う、祭祀のような恰好をした幼い子供。青い目をした黒く短い髪で、同じ色合いの少女が姉である「竜人」だった。
「…………」
子供はただ、無機質としか言えない冷たい横目で、川辺に来た大人達を黙って睨むように見つめていた。
後篇・承
川辺で青年のすぐ前にいた王女が、厳しい面持ちで振り返りながら尋ねた。
「あの方達が――先程大使館に?」
「ああ。来たのは女の子の方だけだが……」
「一人はデュラ・ユークですね。わたくしが第五峠で見た方と、確かに同じです」
「そうだろうな。俺も一度会ったが……でも今の状態のあのコには、多分初対面だ」
会ったが、初対面。青年のその、言葉の意味を話す暇はなかった。
「こんにちは、王女様。あたし達、『悪魔祓い』だよ」
にこりと、二つ頭の山犬に座る幼女が口を開いた。
傍らの三つ頭の山犬に座る子供は、厳しい目のまま何をするでもなく、無言で幼女にその場を任せる。
しかし幼女に応えたのは、王女ではなかった。
「――『悪魔祓い』を名乗るは真か」
しん、と……まるで空気を切るような、滅多には口を開かない騎士団長の鋭い声が発される。
騎士団長と魔女の間にいる王女は、ただ厳しく物憂げな顔で幼女と子供を見つめている。
「なーに、貴方。見たところ『純血』っぽいけど、あたし達に逆らってもいいことないよ?」
子供はフフフ、と騎士団長のきつい視線にも全く構わず、背に座る獣を宥める余裕すら見せて一行に対峙する。
その様子を眺めながら、青年の後ろで悪友が頭を抱えた。
「子供がたった二人と二匹って、何を考えとんのや、敵は……」
数だけを見れば、大人側は化け物の男が四人、少年が一人、化け物の女が四人。守るべき弱小な人間の王女が一人いても、不利とは到底思えない状況だった。
騎士団長はただ、長く大きな剣を抜いて目前の敵に向けた。
「黒幕を出せ。出さないなら貴様達を捕らえる」
「ひどいなぁ。こんな子供二人に、大人が大勢で来るの?」
しかしそこで、幼女はにやりと――奇怪な笑みを浮かべた。
「そんな悪魔は祓わなきゃね。ねぇ、デュラ?」
羽織った外套の中から取り出した複数の塊を、背にしていた川に投げ入れる。同時に傍らの子供が、三つ頭の山犬から降り、正面を向いて一行を見据え、再び幼女は語り出した。
「神託を伝えるよ。王女様には天罰が下る。芯から人間なのに化け物に取り入って、化け物を相手に苦しむ人間のことなんて、知ろうともしていない」
「悪魔祓い」とは本来、ゾレン国内で化け物から身を守るため、人間が集まってできた集団だった。だからこれが、ゾレンの人間をまとめる常套句なのだろう。
「そして人間に苦しめられた化け物のことも知らない。悪知恵はよく働く人間に、大きな力無き化け物は何度も騙され利用され、道具みたいに使い捨てられたの」
傍らの子供はともかく、幼女自体に大した力がないのは青年も見えていた。だから自分が、人間に利用された化け物だとでも言うつもりなのだろうか。
「デュラもね、人間の女にヒドイ目に合わされた、可哀相なコなの」
「……!」
すぐ反応する青年、紅い目の少年に、悪友と幼馴染が背後から制止をかけた。
「辛かったよね。家族から捨てられて、ずっと独りぼっちで、ねぇ?」
幼女の声に反応するかのように、幼い子供はそこで俯く。
いつの間にか川面からは、巨大で透明な水蛇が噴泉のようにいくつも立ち上っていた。川を背にする幼女と子供越しに、一行を強く威嚇するように睨んでいる。
「手数はあれだけでしょうかね。どう分担しますか?」
至って呑気に提起する祭祀だが、翠の目にはあまり余裕は無かった。
「あれに洪水が来るんだろ? 意外にきついぜ、こりゃ」
獣使いの女が言う通り、川面も徐々に黒く染まりつつあった。
祭祀のもう一人の連れの青白い魔道士の女は、顔も見せない魔女の黒い外套をむんずとつかまえる。
「ちょっとよろしい? あの二匹の、二つ頭と三つ頭の獣は、『純血』の貴女には覚えがあるのではない?」
「雑種」とあまり関わりたくないらしい魔女は少し嫌そうな空気を醸し出したが、ここに来たからには仕方ない、と諦めの息を軽くついた。
「あれは有名な魔獣に似ていますが、実に中途半端です。おそらくは最も忌まれるべき、『純血』と『雑種』の交配種……水蛇の方もその類でしょう」
川面から四つ頭をのぞかせている水蛇に、なるほど、と魔道士も頷いた。
「ということは、両方の特性を持ち得るわけですねぇ」
「どうやら困る相手がいるようですね、あなたにはあの中に」
敏い魔女に、魔道士はまぁね、と、短い杖をしっかり持ち直していた。
そうした隣の話を聞いてか、祭祀が仕込み杖の剣を抜く前に提案する。
「蛇は私達が、獣はライザ君達にお任せでどうでしょうかね」
「ばか。あのガキはどうすんだよ、それじゃ」
四つの水蛇と二匹の獣以外、竜人の幼い子供がどう出るかの懸念が、一行の足をその場に留めていた。
一行は数瞬後、予想以上の事態に、息を飲むこととなる。
「……人間は……嫌いだ」
幼い子供が無機質に、それだけ呟いた後。
場にはまさに――川が起き上がったとしか言いようのない有り得ない光景が、地鳴りを伴いながらあっという間に子供の背後に展開していた。
「あれは……あの時と同じ、黒い竜……!」
一つの川程に巨大で、透明ながら暗い玄の――黒い竜。
そうとしか見えない流体を背後に、それから分離した四つの水蛇も左右対称に引き連れ、幼い子供が王女を睨んだ。
同じじゃない、と、青年は自ら口にした台詞をすぐに否定した。
「前よりもっと、凝縮されてる……!」
先日に黒い竜に喰われかけ、すんでの所で助けられた青年は、それがどれ程強大な力か、しかと視ていた。西部中を襲った洪水の力を、一つに纏めればこれだけ強くなるのかと、「力」を視る眼をもって誰よりも思い知る。
幼い子供の憎悪の視線をまっすぐ受けた王女は、ただ、口を細く引き結んだ。
騎士団長の隣に出るようにして、幼い子供に全身で対峙する。
「……嫌いであれば、殺しても良いのですか?」
この場で唯一の人間として――子供の犠牲者として、それだけを問うために。
「私の大切だった姉様も……あなたのお姉様も」
強い痛みを噛み殺した赤い目は、そこで憎悪ではなく、憐れみをたたえていた。
「それではあなたは、ずっと、一人ぼっちです」
その声のあまりの哀しみに、青い目の子供が不意に息を飲んでいく。
「それは本当に――あなたが望んだのですか?」
王女は子供を本当に憐れんでいる。それだけはおそらく、伝わったのだろう。
しかしそんな一分の隙を、「悪魔祓い」が許すわけもなかった。
「デュラ。人間の諫言に耳を貸さないでね」
フフフと幼女は、子供の肩をぽんと叩く。
「あたしを守ってくれるよね。ここには怖いヒトが沢山いるの」
子供は僅かに顔をしかめたが、すぐに諦めたように視線を逸らした。
冷静に、幼女が取り出したもう一つの「力」……子供自身が更に戦う力になるための苦行を、諦めて受け入れるために。
「――!」
「何!? あの子、食べられちゃったわよ!?」
幼馴染が驚いて叫んだ通り、幼女がまだ持っていた水の塊を子供に向けた直後に――子供はその塊に頭から包み込まれた。
水蛇に取り込まれた幼い子供は、初めの内はごぼごぼと、ひたすら苦悶の顔を見せ続けていた。
「可哀相。デュラがそんな苦しい思いをしないといけないのも、あの人間の女のせいなんだよ」
それは王女というより、子供の実の姉を指していた。
「あの女がデュラの宝を取っちゃったから。だからデュラは、こうでもしないと――竜にはなれないんだよね」
もがく子供はその内、自らの形をなくしつつあった。
呑み込んだ水蛇を暗く染め、場で二番目に巨大な水竜化させる。場には透明で四つの巨大な水の蛇、子供を呑み込んだ暗い水竜、一番大きな川サイズの黒い竜と、六つの巨躯が出揃っていた。
戦略を相談する暇などなく、まず黒い竜が一行を丸ごと飲みにかかった。
「ああくそ! おれはいきなり攻撃役離脱かい!」
悔しげな悪友の叫びの理由は、怪鳥となって青年を背に乗せる必要があったからだ。屈指の配下の大きな鳥も四匹呼び、紅い目の少年と幼馴染を一番大きな鳥に、祭祀、獣使い、魔道士を残った鳥の背に一人ずつ乗せ、黒い竜の直撃を回避させる。
「悪いな『五色』! アタシの鳥は後は気にすんな、上手いこと調教してやっから!」
それは初めから打ち合わせしてあった。悪友が一度に使役できる鳥の数にも制限があるため、第六峠に向かうメンバーは絞った理由でもあった。
「王女! ご無事ですか!」
何やら空飛ぶ竹箒の上に立った魔女が、王女を抱えて飛んだ騎士団長の傍へ向かう。黒い竜は王女を狙って暴れ狂っていた。
「――まずい、避けろ!」
「力」に敏感な青年が、王女を抱える騎士団長に踊りかかる暗い水竜の攻撃を警告する。透明な翼を広げる無言の騎士団長は、そのまま王女と、暗い水竜の直撃を受け……。
……やだなぁ、と、地上に残った幼女は、一行が飛び回る空を見上げながらつまらなさげに呟いた。
「それは――反則じゃない?」
暗い水竜の直撃を受けた騎士団長が抱える王女は、全く無傷だった。
どんな化け物でも貫く強固な力を受けたにも関わらず、それらを全て透明な――大きく広げた光無き翼で受け止めている。
最早聖なる存在ではなくなったからこその騎士団長の姿に、青年は呆然と息を飲んだ。
「……何だ、あの……青い炎は……――」
「力」を視る青年にはそう見えた。それはまるで――
天上の聖火、赤い光の輝きを失った翼が、代わりに地獄の業火をその背で燃やしている。光無き自らを燃やすために、周りから熱そのものを奪う青い炎……動き出した「力」の勢いだけを喰らう、魔性の翼がそこにはあった。
「まさか竜人の力すら、喰らい切るなんて……」
それを一箇所に集中すれば、王女だけは守り切れるだろう。余波を受けて自身は傷付いた騎士団長は、その翼を当然のごとく、王女のためだけに使う所存のようだった。
王女を狙う敵の巨躯達は、空を飛べない。一番巨体の黒い竜の体を通り、空中の王女と騎士団長に自在に飛び掛かっている。
大きな鳥の背で、獣使いの鞭の援護を受ける祭祀が、水蛇の一つに狙いを定めた。
「――目障りだ、交配種」
細い剣を足場の悪い中で巧みに操り、最寄りの水蛇の頭を見事に斬り落とした、のだが……。
「……増えた」
冷徹な顔のままながら、僅かに不服そうに祭祀は呟いた。
「ってこら! 増えた。じゃねぇ、責任とれ責任!!」
祭祀が斬った水蛇は、一つの体に二つの頭が再生するという、ともすれば脅威が増えてしまった状態となった。
そんな中、最初に戦果をあげたのは紅い目の少年だった。
「――よし、リミット!」
この水蛇は斬ったり穴を開けても無意味そうだと、初対面から青年は思っていた。だから少年にあらかじめ指示を出していた。
「凄いわリミット! 何て精確なの!?」
唯一、透明な水蛇の中で透明でない部位、獲物を狙う目だけを狙えと青年は言ってあった。細い鎖を付けた錐型の短剣を投げつけて、少年はそれを確実に射抜く。
水蛇の一つは地上に倒れ込み、苦しげにのたうちまわっているようだった。
しかし水蛇も知能があるのか、目を守って動くようになった。
「――やばい!! 全員一度離れろ!!」
地上で苦しむ水蛇の姿に感化されたのか、暗い水竜は怒り狂うように、全身から水の槍を大放出させた。
「何でなんだ――……やっぱり、アイツ――……!」
自身の「力」たる黒い竜を具現させながら、暗い水竜として自らも動く子供。水の槍など魔道の力すら同時制御できる幼い子供は脅威だ。青年の父のように、飛竜と己を同時に制御し、自らが飛竜となった時には更に強大だったあの姿を見るようだった。
青年は反撃の機を見出せず、悪友と空を避け回る。
一方では、地上の幼女に、青白い魔道士が鳥の背から杖を向けた。
「自分だけ蚊帳の外なの? いけない子供ねえ、あなた」
「……」
その姿に、暗い水竜が咄嗟に地上の方を向く。本来最も得意としているらしい、地下水脈への働きかけを一瞬で執り行った。
地中から吹き上がった熱の霧と無数の水の杭に、魔道士は乗った鳥ごと、全身を貫かれていた。
「――デスリー!!」
「!!」
獣使いと祭祀がそれに気付く。しかし水蛇の猛攻に駆けつける余裕がなかった。
「……!!」
配下の鳥が一つ殺され、悪友が怒りで勢いを増した。
「くそ、このどちらか一つでも何とかなれば…!!」
青年は黒い竜と暗い水竜をきつく睨みつける。
暴れ狂う黒い竜の脅威は、とにかく巨体で屈強なことにつきた。
暗い水竜は二番目に巨体な上に、次々と恐るべき水の力を放ち、青年独特の特技もこの規模の戦いでは焼け石に水だった。
その中で、水の凶刃に倒れたと思われた魔道士だったが。
「――きゃ!?」
「……うふふ。捕まえたわ、お嬢ちゃん」
二つ頭の獣から降りて寄ってきた幼女を、傷だらけの魔道士は突然がばっと抱き寄せていた。
「あの坊やを止めなさい? ダメよ、子供がおイタしちゃ」
魔道士は、全く生気の無い青白い顔で不気味に微笑む。隙だらけの状態で距離を詰めたのは、この奇襲が目的のようだった。
「な、何あんた、死んだはずじゃ……!」
「ええ、死んでいるの。ワタクシはもう、とっくの昔に」
「!?」
冷たいばかりの魔道士の体に、幼女がぞくりと、全身に悪寒を走らせる。
それに気をとられたのか、暗い水竜の動きが一時的に止まった。気付いた青年がそちらに向かおうとした――その時だった。
「……――まずい!!」
悪友を駆る青年を、黒い竜が完全に標的として捉えた。
それは、隙を見せてしまった青年へのチェックメイトだった。
黒い竜が、注意力をそこに集中した瞬間、
「近付くな!!」
助けに来ようとした仲間を、青年は大声で制した。
仲間を巻き込む必要はなかった。ある冷たい蒼を中心に渦巻く、悲しげな大気の到来を感じた。
いつも誰よりも早く、青年はその相手を見つける。
黒い竜の隙をただ待っていた、蒼い獣――
誰の攻撃も通じなかった黒い竜に、その冷たい蒼の光だけは、悲しげな大気の力を得て銀の弾丸となる。
一筋の流星が、刹那の一瞬に遥かな空から落ちてくるように。
黒い竜を斜めがけに、袈裟斬りのように貫いていった。
+++++
和平交渉のために多くの軍が集まった第六峠は、大洪水の後、元々少ない人口が更に減っていた。一般のゾレン人は王都側に避難するか、峠自体を去った者も多い。青年達が交戦する川辺は特に、近付く者もいなかった。
黒い竜が地響きをあげて倒れ込んだ直後に、青年は蒼い流星の姿を探して声を張り上げた。
「リーザ! ミリア!」
蒼い飛竜と、飛竜に跨る竜の血をひく少女の特攻。悲しげな大気ですぐにわかった。
「ライザ――……大丈夫!?」
黒い竜を貫いた後、勢いのまま再び上空へ転じていた飛竜が、青年達の高さまで舞い降りてくる。
「何でここに来た、ミリア!」
飛竜の背に乗る普段着姿の黒髪の少女は、青年が思わず声を荒げるほどに無防備に見えた。といっても青年も、簡易な胸当て以外に特に武装はない。
「俺達を守ろうなんて考えるな、自分に集中しろ!!」
しかし少女は、青年の言を否定するように硬く見つめ返し――
むしろある防具の存在があるからこそ、以前に飛竜が弾かれた黒い竜を貫けたことを、程無く青年は知る。
水蛇の目を穿つ機会を狙っていた少年と、同じ鳥に乗る幼馴染が、倒れた黒い竜を見て声を上げた。
「何あれ、帯電してない!?」
「……!」
のた打ち回る黒い竜は、まるでいくつもの光の蛇を植え込まれたように、所々で激しく電光を走らせていた。
「だからライザ、近付くなって言ったのね」
それは黒い竜に触れるもの全てに伝播している。黒い竜を基盤とする水蛇達も苦しげに咆哮をあげた。
「効きはしてるが、アイツは底無しだ……」
青年が苦い顔をする通り、川と連結する爆流の黒い竜は、やがてダメージを下流へ捨てて、ゆらりと再び立ち上がっていく。
しかし黒い竜と水蛇達の猛攻を、一度でも間を置くことができたのは大きかった。
「この、汚らわしい『雑種』……!!」
「貴様は何者だ。神隠しの子供ではないな」
冷酷そのものの目で幼女に細い剣を突きつける祭祀が、鳥から地上に降り立つ余裕ができたのは、この一時だからこそだ。
「ほら、こっち乗りな。奇襲人質作戦は失敗だ、あんたは上へ」
「ごめんなさいねぇ。お役に立てなくて」
魔道士が捕まえていた幼女は、二つ頭と三つ頭の獣を助けに呼び寄せた。その内三つ頭の獣を見て、魔道士は幼女を置いてひかざるを得なかったらしい。
「しゃーないよ、あの三つ頭は冥界の番犬もどきだろ。いくらあんたでも、下手したら昇天させられちまう」
確実に全身を水で貫かれながら、今も平気そうな魔道士は、三つ頭の山犬相手にだけは及び腰だった。「冥府へ送られる」と言って、止む無く祭祀が地上に降りて割って入ったのだ。
彼らは元より、魔道士が簡単には滅びないことは知っていた。
「アンタが調べた通り、あの三つ頭はデスリーの天敵だろ? やばくなったらあっちに行けよ」
それで、地上に降りた魔道士を気にしていた祭祀達だが……。
「ほら、アタシは大丈夫だから! 獣使いの名にかけて水蛇の相手くらいお茶の子だし、こっちを手薄にできないだろ!」
「……」
何故か祭祀は、無表情でも不服げに獣使いを見つめ、その様子にあっさりと獣使いは折れていた。
「わかったよ、アタシも行きゃいーんだろ、行きゃ! そりゃ確かにあっち相手の方が本職だけどね!」
そうして獣使いが二つ頭と三つ頭の獣を共に牽制し、祭祀は遠慮なく幼女に剣を向けていた状態だったが。
「いやあ! 助けてぇ、デュラ!」
幼女の叫びに敏感に反応した暗い水竜が、黒い竜から離脱してその場に突っ込んだ。祭祀が乗っていた鳥は魔道士を、獣使いが乗っている鳥は無理矢理に祭祀と獣使いを乗せ、再び空へ退避しなければいけなかった。
致命傷を受けても平然としている魔道士は、手にする杖から何か「力」を受けて、そうなっていると青年には視えた。その姿はこの黒い竜――ダメージを全て流し、爆流を衰えさせない敵と何処か重なっていた。
「竜の『宝』も、宝杖を持つ魔道士も、不滅……なのか――?」
タイミング良く黒髪の少女が、少女側の現状を伝えた。
「ライザ、お願い! デュラを止めるために第一峠に行って!」
「!?」
「ヘルシャ大使からの依頼なの、第一峠では大使は動けなくて――でも、この洪水の根本は第一峠で起きてるの!」
近くを飛んでいた王女と騎士団長も、どういうことですか、と事情を聞きに近付いてきた。まだ本調子でない黒い竜と水蛇を魔女に牽制してもらう。
「ザインのヘルシャ大使、中立地帯の管轄者が動けないとは、もしや……」
「うん。ゾレンの子供がゾレンに向けて、洪水を起こしているの。でもそれは自分には介入できないって」
「なるほど……第一峠は完全に、ザインに属しますものね」
中立地帯であるザイン地方やエイラ平原は、異国・異種間の争いが禁じられている。逆に言うなら同国同士の内輪揉めに、中立地帯の維持者は関与してはならない暗黙の制限が存在している。
第一峠のザイン大使は、第五峠の洪水を除き、洪水の起点は一つと以前から見切っていたらしい。
「ゾレン西部中に洪水を起こせるとすれば、西部の水源……第一峠の火口湖を掌握すれば、そこから流れる川は全部操れる。だからデュラは、第一峠に隠されていたんだろうって」
「でもミリア、あのコは今は、ここにいるのに?」
祭祀達が暗い水竜を、黒い竜と水蛇を他の者が必死に牽制する中、青年達は話を続ける。
少女は青年から以前聞いていた話を、そこで続けた。
「ライザが言った通り、デュラの『逆鱗』だけがそっちに別にあるの。それを使ってるのは、デュラと同じくらいの女の子だった」
洪水を起こしながら、自身も暗い水竜として戦う幼い子供のカラクリ。二重の闘いの秘密を改めて裏付ける。
「じゃあ、やっぱりこれは――」
「うん。デュラの力を暴走させる、その子達が起こしてること」
かつて青年が出会った時、額に黒い宝石を宿す幼い子供は言った。
――ここは怖いヒトばっかりなんです。
だから、恐るべき子供達の巣窟に近付くなと親身に伝えた。その幼い子供は全てを諦めたように笑っていた。
――ぼくもここから出れたらいいな……。
既に自らの「宝」――「力」の主導権を子供は仲間に明け渡しており……そこだけが自身に許された居場所と知っていたのだろう。
青年はその後黒髪の少女に、竜人の弟について尋ねた。
――デュラの額の……黒い宝石?
子供の額にあった薄い菱形の何か。強い「力」がそこにはあった。
――うん、ずっとあったよ。前は額じゃなくて首だったけど……でも、滅多に出てこなくて。デュラが力を使おうとした時だけ、いつもうっすらと見えた気がする。
そしてそれこそが竜の「宝」の一つ、「逆鱗」であるのだと、双子の弟の師の旅人が教えてくれた。
――父さんは、それは外せるけど、誰にも取られちゃダメって言ってた。外したら、デュラの力が暴れるかもしれないのと、誰かが勝手にデュラの力を使っちゃうって……。
ここに現れた幼い子供の額には、その黒い宝石は無かった。
それは最早、とうの昔に、子供の「力」を利用する者達に奪われていたのだ。
――それで改めて、逆鱗についてだが。
「竜人」について教えてくれた旅人の声が、再び青年にこだまする。
――アレは要するに、竜人が下手に暴走しないよう、神がつけた首輪と言える。『力』の制御装置なんだが、困ったことには、一つの人格……自己保全機能も持っていてな。
更にその「逆鱗」は、相性の合う他者が起動することも可能であるという。
――逆鱗に触れる……その自己保全の人格を起こせば、自らだけを優先する暴走者になってしまう。古より、龍の逆鱗には決して触れるなと言うだろう? つまりはそういうことだ。
その竜人は優しい子だったと言った、黒髪の少女の言葉。ようやく青年の中で、一つの真相が繋がりつつあった。
優しい顔で青年に笑いかけた幼い子供と、実の姉を手にかけた冷酷な子供は、半ば別人といっても良いものなのだと。
黒い髪の少女は悔しそうに、飛竜の背で両手を握り締める。
「わたしとリーザ、先に火口湖に行ってみたの。でも術士の女の子は、三つの水蛇と魔獣みたいなのに守られてて。火口湖自体、竜みたいに渦巻いて、力の中心地だから全然近付けなくて」
黒い竜を貫けた飛竜と少女すら、それ程脅威を感じたと口にする。そのために少女は、青年にその意思を託す。
「こっちのデュラは、わたしとリーザが何とかする! だから……デュラにこんなことをさせるヒトを止めて、ライザ!」
出会った頃は、魔道士見習いでしかなかった少女。
今では竜に騎乗して機動力を補う魔道士――竜騎士として、双子と特訓を続けていた少女が毅然と青年を見た。
「ライザなら止められる――ううん、ライザしか止められない」
いったい何処に根拠があるのか、信じ切った顔で少女は言う。
「……そんな事情があったというのですね」
話を一通り聞いた王女は、自身をずっと抱え続ける騎士団長と目を合わせた。その後ほとんど迷いも無く、きっぱりと青年に言った。
「ライザ殿。どうか第一峠に行かれて下さい」
「……しかし、王女の方が手薄になります」
「大丈夫です。わたくし達は皆、命がけで戦う覚悟でここに来たのです」
騎士団長にしがみつくだけでも、弱小な人間の王女は相当消耗していた。その上王女達は、自らを囮として、黒い竜の動きを予測しやすいものにすべく、ギリギリで逃げ回っているらしい。
「大元を叩いてもらわなければ、おそらく勝ち目はありません」
「…………」
それは青年も感じていた。ちらりと、黒髪の少女が駆る飛竜の灰色の目を見つめ……躊躇いを振り切るように、自身の眼も一度、そっと閉じる。
「……気をつけてくれ、リーザ」
それだけ呟いた直後、怪鳥の悪友の背を叩いてから、少し離れた幼馴染と紅い目の少年に強く声をかけた。
「ハーピア、リミット、ついて来てくれ! 俺とヴァルトは、今から別行動をとる!」
え!? と彼らが、心底驚いたように青年達に振り返る。
「こっちの戦況をハーピアが鳥づてに教えてくれ、リミットはハーピアを守ってくれ! 連携しないとコイツらには勝てない!」
紅い目の少年はそこで、少し躊躇うように王女の方を見た。
「大丈夫ですよ、リミット君。私と騎士団長が揃って、王女を守れないなんてことはありません」
かつて大火傷を負った少年の傷痕を、ヒトらしい姿に戻した経緯のある魔女が、穏やかに少年に笑いかけた。
「連絡役の彼女をしっかり守りなさい。それに透明になれる君の特技も、役に立つかもしれません」
「……わかった」
少年はこくりと、少年らしい声で答えて頷く。更には同乗する相手に振り返った。
「ハーピアは……絶対、守る」
「えっ!? あ――うん……」
大真面目に言った少年に一瞬戸惑いつつ、頷いた幼馴染だった。
戦う力の乏しい幼馴染をのぞけば、三人もの戦闘力が抜けてしまう状態。それでも王女と黒髪の少女が、毅然と青年達を見送る。
「大丈夫――こっちのヒト達は、誰一人、死なせたりしない」
ようやく本調子に戻った黒い竜が、まさに王女を標的に捉え、傍にいる少女もろとも喰らいつこうとする。
「何か策が、お有りのようですね」
襲い来る黒い竜を、飛竜の背でまっすぐ見据える少女の決意に、騎士団長までが信望を見せたのを青年は見る。
水脈を司る竜の血をひく少女は、混血である自身には「竜の眼」という、竜人として最低限の宝しか持ち合わせていない。
「わたしはまだ、魔法もそこまで、上手くは使えないけど……」
それでも少女が修行を重ねた確かな「力」。一番最初の攻撃にも使った少女の武器……大切なものを守ることを望む少女の、願いの防具を掲げる。
少女が取り出したのは、大きな凧型の、蒼く薄い菱盾だった。表面の対角線の交点に小さく透明な玉を填め、それ以外はごくシンプルな、特に屈強にも見えない蒼い盾だ。
しかし青年はその菱盾に、強く見覚えがあった。
「あれは……第一峠の、ヘルシャ大使の――」
治水を司る魔道の大家の当主が、客人の控室に飾っていた宝の盾。悲しげな大気が微かに纏わりつく古の秘宝なのだ。
飛竜の首に斜めに跨る少女をちょうど覆える大きさの菱盾は、何言かの拙い詠唱を口にすると、光がちらつき始めた。
「ちゃんと放つのはまだ難しくても、呼び出すだけなら……どんな大きな力だって、耐えてみせる」
輝く菱盾を突き出す少女も光を纏い、額には謎の紋様が浮かぶ。それは少女自身が菱盾と共に、魔道の媒介となった瞬間だった。
「リーザ、行こう!」
「――!」
その状態で動くことはできない少女の代りに、魔法そのものとなった少女を乗せる頑強な飛竜が黒い竜へ特攻する。黒い竜にまた多くの光の蛇を植え付け、その巨躯を貫いていった。
「……!!」
遠めに再び確認できた、少女と双子の大きな「力」。
今や少女と飛竜は、炎を吐けない飛竜と、魔道士としては未熟な少女を互いに補う、二人で一つの竜騎士だった。
「……あれが――……解放した『竜の眼』の力なのか」
少女は水脈――水の流れという自然現象に適性がある。その応用で、水中では正負が分かれて流れやすい電荷を集め、操れるはずだと師たる魔道の大家は見定めていた。その助けとして、家宝の盾を使わせている。
「竜の眼」とは、自然の脅威たる竜にヒトの形を与えて竜人とする、根本的な力であると旅人も言った。
――俗称は「鈴」とも言うが、竜の眼とは自然現象をヒトに変える、つまり自然の力とヒトたる実体を相互転換できるものだと思えばいい。竜人は体自体が自然の塊だから、竜の眼でそれを力に変えることができるんだ。
そうした「力」を効率良く使うため、竜人の持つ宝を何かの道具に組み込む武具は、古代には開発が盛んだったのだ。
――ヒトに収め切れない力の結晶、『竜珠』を填める鎧なぞは、古代の秘宝の最たるものだ。竜の眼なんかは、所詮竜人が使ってこその宝だが、竜珠があれば人間でも竜の力の恩恵を受けられるだろう。
そうして少女の姉は、竜珠の力で無敵の鎧を手にした。
少女は自らの力を解放するため眼の力を分離し、魔道の媒介たる盾に填め込んだのだと青年は知る。
そして青年が戦いに向かう相手は、解放された竜人の力を高度に制御する宝――逆鱗を使い、黒い竜を起こした者なのだ。
そうは言っても、竜珠の力を借りる人間は、本体の竜人には敵わず命を落とした。それを考えると、竜の眼だけで少女が黒い竜に対抗できる時間は、そう長くはないはずだった。
「俺に――本当に止められるのか……?」
旅人から聞いた話や、少女の信頼の眼差しを以っても、青年の内心は戦慄を続ける。
――オマエなら、できることもあるかもしれない。
それでも今は、ひたすら時間が惜しい。戸惑う心は関係なしに、青年を乗せる悪友も第一峠へと向かった。
最強の獣と言われる飛竜の血をひく青年は、本来、何一つ戦う術など持たなかった。
――丈夫さは全部、リーザが持ってったんだから。
体の頑強さも、空を駆ける飛竜となる力も双子が継いだ。魔道の適性もなかった青年は、何の取り得もない混血の化け物だ。
それでも今日まで、戦ってきたのは――幼い日に、初めて大きな怪我をした時、流れる自身の赤い血が炎に視えた。その時にそれを、ただ願ってしまっただけだった。
これが本当に炎なら、自分も強くなれるのに、と。
雪山たる第一峠の頂上を間近に、幼馴染が険しい顔付きで叫んだ。
「見て、ライザ! 火口湖から第六峠に続く川だけに大量の水が流れ込んでる!」
「本当だ。これじゃ、他の地域が干上がってしまう」
火口湖は今や、不自然な黒い渦が全域に渡り、他の川から水が逆流している程の荒れようだった。
まだ上空にいる段階で、唯一の武器である短刀を取り出し、青年は自身の左腕を切りつけ、その刃を血で染める。
「これも下手したら、山火事になるけど――」
短刀から滴る血を可能な限り、これから彼らが突入する場、火口湖に向かって空からばら撒く。
そうして短刀と、それに纏わせた血を振りまき、素早く細かに動く軽業師のような武技が青年の戦い方だった。
「ハーピアは空に残れ。リミットは透明になって、状況を見て加勢してくれ」
更に怪鳥たる悪友を機動力に、とにかく一度湖畔に飛び込む、と青年は同行者に伝える。
「ハーピアが危なくなればそっちを優先しろ。ハーピアも何かあればとにかく伝えてくれ」
「わかったわ。今の所、第六峠は何とか黒い竜を圧し留めてる……でもミリア、魔法を使うごとに凄く消耗しているわ」
「……――」
ぎり、と青年は、わかり切っていた状況に歯を食い縛る。
「ミリアとリーザがアレを牽制できなくなれば、形勢はかなり悪くなるわ……何としてもここで、元を断たなきゃ」
普段は内に留めている「力」を、少女は竜の眼で解放している。それは自らの体を、直接「力」に変えているも同じだった。
「――行くぞ、みんな」
怪鳥の背で短刀を逆手に構え、青年はそれだけ静かに口にする。
黒く渦巻く広大な火口湖の一角――悲しげな黒い大気が集うように視える場所に、悪友と共に飛び込んでいった。
+++++
「!!」
「……」
突然空から襲い来る怪鳥と、その上にいる知った顔の青年。火口湖に向かって小さな木の杖を掲げる幼い魔道士が、傍らの異形の獣に素早く指令を出した。
「キマ! 応戦なさい!」
獅子や山羊、蛇など複数種の頭を持つ獣が、幼い魔道士を守るように怪鳥の突撃を弾き返した。
直前に怪鳥の背から湖畔に降り立った青年を、湖面から顔を出した三つの巨大な水蛇が瞬時に取り囲んだ。
水蛇の喰らいつきを一つ一つ、青年は素早く回避する。外套に包まれ、外巻きの朱い髪を帽子に詰めた幼い魔道士が、睨むような灰色の目を向ける。
「やっぱりアイツ、生きてたんですの!? さっきからずっと、おかしいとは思ってましたの!」
以前に会った時、水蛇に喰らわせたはずの相手が現れたこと。幼い魔道士は憤慨しながら水蛇達に喝を入れる。
「デルにまたバカにされるのはごめんでしてよ! 今度こそ、必ず死骸までボロボロに喰らい尽くすんですの!」
異形の獣を怪鳥が、水蛇を青年が応戦する形となったが、それは幼い魔道士にある危機感を持たせる事態だった。
「どうして……この場に来られたんですの!?」
その火口湖付近には、竜の血をひく少女と飛竜は近付くことができなかった。それというのも、渦巻く暗い湖から溢れる霧で、近付く者を全て傷付ける「力」の溜まり場であるからだ。
「よりにもよって炎の鳥が!? この水の場に、どうやって!?」
惜しげなく炎の翼をはためかせ、獣と幼い魔道士に熱い風を叩き付ける怪鳥。異形の獣は口から嵐のような勢いの炎を吐いて、炎同士で怪鳥と獣が激突する。
「何ですの! 何でワタシの毒も効いていないんですの!?」
更に言えば、敵を傷付ける霧には毒の効果が付加されている。しかし悉く効かず乱入した青年達に、心底の混乱の目を向けた。
「おかしいおかしい、おかしいですの! ワタシにそんな介入なんて、このワタシが普通の魔法に、負けるわけなんてないのに……!!」
幼いながらに、卓越した「力」を持っている魔道士。だから現状は、有り得ない状況としか言いようがない。
半ばパニック状態の幼い魔道士に、全ての仕掛け人である青年は水蛇の攻撃を回避しつつ、静かに彩の無い眼を向ける。
「……こいつらの本体は、お前か」
「……!」
縦に走る鋭い瞳孔は、まさに兇獣。青年の声に少しでも棘があれば、幼い魔道士は更なる恐慌に陥っただろう。
「デュラ・ユークの力を渡せ。この洪水を止めろ」
「な……アナタ――……何者なんですの!?」
本来この幼い魔道士は、自らの分身である八つもの水蛇を全て自律機動させられる、破格の才能の持ち主なのだ。
その上「逆鱗」という竜の宝を流用し、洪水を維持する役目もこなす天才に、それは初めての脅威だった。
しかし青年はとことん、兄気質で根が甘い。怯える幼い魔道士を対等に視ることが、無意識にできなかった。
「これ以上あのコを利用するな。お前達、仲間じゃないのか」
「……!」
その甘さに気付いた幼い魔道士は少しだけ、勝気な己をそこで立て直す。
「デュラを……利用してる、ですって?」
魔道士の背後で、湖面からゆらりと、一風違う暗い水竜が立ち昇る。
そうして魔道士に明け渡された、竜の宝を遠慮なく具現させ――
「デルはどうか知りませんけど、ワタシとデュラは運命共同体でしてよ。ずっと二人で、助け合ってきたんですもの」
「……!!」
その暗い水竜は、実際は水蛇の一つに過ぎない。ところが青年の眼には、額に黒く薄い菱形の宝石を付けた子供が視える。
確かに幼い魔道士の一部でありながら、ある竜の子供の嘆き……「禍」たる己の運命への怒り。それをそのまま、水蛇を背にする幼い魔道士が再生した。
肩書きはご神体。しかしその実態は、多くの命を飲み込んだ自然の禍。暗い水竜が何故か人語を放つ。
「僕は……閉じ込められなきゃ、いけないんだ……」
それはかつて、悪魔の仔と呼ばれた青年にとっても、他人事でない真情だった。
「ここは好きじゃないけど……ここしかないから……」
ここは怖い所なのだ、と。ぼくもここから出れたらいいな、と諦め切った顔で口にしていた子供。
そこに集められた彼ら全てが禍であると、気が付いていたのかもしれない。
その逆鱗のことを尋ねた時、黒髪の少女は、悲しげに口にしていた。
――ねえ、ライザ……デュラは、許されるのかな……?
もしもそれが、本当は優しい子供が、逆鱗に触れられたせいで起こした禍であるなら。それなら子供に、罪は無いと言えるのか、と。
何で――と。
黒い宝石を付ける暗い水竜が、幼げな声を震わせる。
「何で――ピア姉さんは、僕を助けてくれなかったの……!?」
「……!!」
「だって姉さんは、『子供攫い』だって……! それなのに僕のこと……迎えに来てくれなかった……!!」
実の姉を殺した子供。ただひたすらに、自らを保とうとしただけの逆鱗――その内に潜む、どうしようもなかった心。
「僕を売った姉さんが何で、『子供攫い』なんてするの!? 僕のことはいらなかったのに、他の子供達のことはいるの!?」
それは最早、復讐ですらなかったのだ。
「僕が禍だから!? ハイドラの言うことをきかないと、生きる価値もない化け物だから!!?」
己が持った「力」のために、ただ利用されてきた純粋な子供。その子供が唯一、心を抑えられなかった相手がいるとしたら。
慕っていたのだ。生まれた時から傍にいて、普段は緩い笑顔で優しかった姉。
だからその冷徹な裏切りが、子供は何よりも辛かった。それでも「子供攫い」となった姉を、誰よりもその子供は求め、待っていたはずだった。
「……デュラ・ユーク……」
青年は束の間、苦しげに叫ぶ暗い水竜を、哀しげに見つめるしかできなかった。
「誰なんだ……君にそんなことを、吹き込んだ奴は」
わかり切った問いを、それでもせめて……もう弟に応えることができない姉のために、無駄と知りながら口にした。
「ピアはずっと……君への償いを、望んでたのに」
――これは……あたしの――……。
その女なら、弟は悪くない――それは自分の咎だと言うだろう。
待ちくたびれた弟は、周囲に促されるまま、逆鱗――一つの心そのものを明け渡した。そうして、いつまでも叶わない望みを絶つために、実の姉を手にかけてしまった。
少し前に、共に夜を歩んだ時に。国王は人間の女の嘆きを青年に伝えた。
「私とピア・ユークが再び会ったのは、彼女が『子供攫い』となり……弟の行方を探すために、私を襲ってきたからだった」
どんな手段を使っても、どれだけ非情なことをしても。幼馴染みの国王と言えど殺す勢いで、女は冷然と現れたという。
「旧王城には弟はいないと、彼女は勘良く感じ取ったようだった。私は彼女の弟が『子供狩り』にあったことすら知らず……調べた結果は、神隠しの一言で、行方を掴んでやることすらできなかった」
国王は自身の無力さを噛みしめ、「子供攫い」の後方支援に回る。
そして弟は、己が神隠しと呼ばれる状態だったことを知らなかった。
そのように禍の力を持った子供の心を、子供の代わりに水蛇が口にしたのは僅かな時間のことだった。
「ライザ、危ない! どうしたの、動いて!!」
その心が聴こえて――視えていたのは青年だけだった。
青年にまさに襲いかかる暗い水蛇の源、渦巻く水の内の黒い宝石に、その心が映し出されていたらしい。
「っ、くそ――……!!」
暗い水蛇に喰らわれかけた青年を、透明な仲間が突き飛ばした。
「すまない、リミット……!」
「何ですの!? まだ仲間が何処かに!?」
「逆鱗」を預けた暗い水蛇を隠すように、幼い魔道士が湖に戻す。ずっとこの場の様子を伺って飛ぶ鳥を見上げ、青年の仲間の存在を捉えてしまった。
「邪魔したのはやはり、あの鳥ですの!?」
それに危機感を持ったのか、それとも、子供を相手に無意識に躊躇う青年の甘さを知っているからか。
透明になれる少年はその利点を最大に生かし、幼い魔道士に確実に……自らの必中の間合いへ、気付かれずに踏み込んでいた。
……え? と。
幼い魔道士はポカンと、自身の胸に突き立った短剣を見つめ……抜いて返り血を浴びた者の僅かな輪郭を、真っ白な顔付きで見た。
「……い……」
膝をつく相手から、透明な少年はすぐに距離をとる。しかしその足は何故かいつになくもたついていた。
「痛ぁい……」
「――!」
青年も幼い魔道士の異変と、ある緊急の事態にすぐに気が付いた。ふらふらと後退する透明な少年を追うように、なるべく湖面から距離をとった。
「痛い、ですの……デュラ……おにい、さま……――」
神隠しの子供の中では、群を抜いて才能があった魔道士。黒幕に可愛いがられ、竜人の宝までを制御してしまえる絶対者だった天才。
「怖い――……嫌ですの、頑張るの、でも、怖い……!!」
常に分身である水蛇に守られ、幼い魔道士は優位に立ったことしか無かった。それが目前には未知の脅威と、敗北の可能性。二重の恐怖と純粋な痛みに苛まれ、ヒトとしての理性を完全に失いつつあった。
「負けたら捨てられる……! 嫌痛い怖い怖い、痛い……!」
そしてそれは、ヒトたる姿を失うことと同義だったらしい。
年端もいかない幼い魔道士が、渦巻く湖に溶けるように倒れ、脆くも崩れゆく一方のことだった。
「リミット、大丈夫か――!!」
「リミット! しっかりして!」
地上に降り立った幼馴染と、駆け寄った青年の前で、透明となる能力すら解除された少年が、苦しげに顔を歪めて倒れ込んだ。全身の至るところで、幼い魔道士の返り血から黒煙が上がっていた。
間髪入れずに、青年は自身の手掌に短刀を突き立てた。流れ出す血を少年が浴びた返り血に重ねる。
「ライザ!? 何をする気!?」
「あの子の血は猛毒だ――消してやらないと」
今や湖の方では、幼い魔道士は首領格の水蛇と化しつつあった。我を取り戻せずに暴れ狂う今だけが、少年を助け、これからの作戦を相談できるチャンスだった。
「毒ってそんな、リミットは大丈夫なの!?」
それに、と幼馴染は、苦しむ少年に振りかけられた青年の血に慌てる。
「毒を消すって、まさかそのまま焼く気!?」
飛竜の息子である青年が、その血を炎にできると幼馴染は知っている。そんな無茶な、と顔を引きつらせる。
「違う……イチかバチかだが、できるはずだ」
それはそもそも、この毒の霧で守られた魔道士の縄張りへ突入できた青年には、必ず可能なはずだった。
「この毒は『力』だから、『無意味』にできる」
あらかじめ上空から自身の血を振りまき、青年は場を己のものとした。その場が危険な「力」の内だと上空から視るだけでわかり、そして――それに介入できる特技の持ち主だからだ。
わけのわからない幼馴染も、返り血がまるで、青年の血に消火されるよう鎮まっていくのを確かに目にする。
死を約束された猛毒を、青年は自身の血を介して猛威を消し去る。
脳裏に響く声は、その特技の本質や、竜人の宝について教えてくれた旅人の不敵な宣言だった。
――オマエの目は万物の『意味』を見出し、手を加える心眼だ。
だから青年は、「力」あるもの全てに介入できる、と旅人は言う。
――『意味』は『力』の在り方に過ぎない。大元の本質『力』を視られるなら、後の意味付けはオマエ次第だろう……飛竜の血という『力』の中に、炎の意味を視つけたようにな。
自身の願い――心によって炎に視えた血を、本当に炎へ変えられる特技。それは「力」の核である「心」を、視るだけでなく具現できる才能だった。
今の所青年は、血や気を介する以外特技の発揮方法を知らない。おそらく血の方がより強い介入力を持つようだった。
――本質から大きく外れた意味の付加や改変は難しいが、意味そのものを無視する無効化は手っ取り早い。竜人の逆鱗は言ってみれば、外付けの『意味』だ。その本質となる『力』……ヒトで言えば心を視つけられるなら、介入できるかもしれないな。
簡単に言ってはいたが、それにはどれだけの血が必要かは、見当もつかない状態だった。
先程幼い子供の「心」を視て足を止められた青年は、それが自身の役目であると、初めて真に納得していた。
「……俺が視てたのは、いつも……そうだったのかな」
「――?」
少し落ち着いた少年を、幼馴染が座り込んだままで抱き起こす。
彼らから少し離れた湖で、四つの頭を出した水蛇を見て、青年はようやく、覚悟を決める――
+++++
炎と風の鳥の悪友が、雪山の火口湖で湖畔の雪をほとんど溶かしていた。炎の嵐を吐く異形の獣と、未だに鎬を削り戦っている。湖から首をもたげる水蛇に睨まれる青年は歎息するしかない。
「ヴァルトが手こずるなんて相当だな、あっちも」
「そうね。ここからどうするの? ライザ」
黒い竜に加え、全ての洪水の要であるこの場に配置された幼い魔道士と異形の獣は、第六峠に現れた幼女や獣とは一線を画す強さだった。
「あの水蛇、頭を落しても増えて再生するし、心臓を貫いても死んでないみたいよね」
「殺す必要はない。リーダー格の奴が付けてる黒い宝石だけ、何とかおさえることができればいい」
また甘さを口にする青年の代わりに手を下し、毒の血を受けた少年はさぞかし不服だろうと、座り込む方を青年はちらりと見たが。
「…………」
片手で頭を抱える少年は、不思議と穏やかな無表情だった。
何故かすぐ攻撃に移らず、青年達を睨むだけの水蛇を、青年は改めて睨み返す。
「ヴァルトに頼れない以上、二人には悪いが……二人の鳥を俺に貸してくれ」
「まさかライザ……一人であそこに飛び込むつもり?」
「あいつらが湖を出ないなら、空から仕掛けるしかない。多分あいつらは、怯えてるんだ。でも仕掛ければ反撃が来て、ここもまたすぐに危険になる」
だから、と青年は、苦渋の顔で幼馴染と少年に振り返った。
「二人はとにかく、逃げてくれるか?」
空への回避という、最も安全な道を奪いながら、そう言うしかない。申し訳なさそうな青年に幼馴染が苦く笑う。
「危険なのはみんなよ。ライザも私達も、ミリアも王女も……第六峠、もう消耗し切ってるわ」
「そうか。それじゃ、相談してる時間も惜しいな」
この中では最も弱小である幼馴染が、まるで死を覚悟したような笑顔に、青年は大きな鳥の背に乗り込みながら俯いた。
「……すまない。俺がもっと、しっかりしていれば」
単身で四つの水蛇、それも逆鱗という力を手にする本体を相手に、この方法以外に勝算は見出せない。逆鱗が最も近くに現れた時、動けなかった甘さをつくづく悔やむ。
そこに思ってもみない声が、硬くも穏やかにかけられていた。
「……ライザは……それでいい」
……え? と。青年だけでなく幼馴染まで、声の主を茫然と見つめることになる。
「フォローするのが……仲間の役目」
そこにいたのは、白い鳥頭で紅い目の少年……ではなく。白く短い髪で紅い目の、憂い気な面持ちの同年代の男だった。
呆気にとられる青年を前に、立ち上がった男はおもむろに、きゃあ!? と驚く幼馴染を抱き上げる。
服の丈が至る所で足りずに、露出した背からは何と、白い羽が生えた状態だった。
「ハーピアは守る、だから……アレ、ライザしか止められない」
舌足らずな言葉と、紅い目は少年の面影を残す男。青年の内によぎった記憶は、かつての双子の言葉だった。
――コイツ多分、姿を変えられる化け物なわけだな。
そもそも最初に出会った時は、大人の姿をしていた少年。それとはまた違う姿で、同じくらいの年恰好に戻ったらしい。
「リミット……ちょっと、ホントに、飛べちゃいそうなの……?」
「魔」であった少年に鳥の魂を与え続けた幼馴染は、おそらくそれがもたらした男の姿と、男に抱えられている自分に、知らず真っ赤になっていた。
「何て言うか――……騎士団長、みたいね、リミット」
男は本当に少しだけ、ぎこちなく微笑んだようだった。
昔から常に強気な幼馴染の、初めて見るようなしおらしさ。思わず青年も珍しく顔が綻ぶ。
「……ありがとう。それなら俺も心置きなく戦える、リミット」
心からの信頼を込めて、男をまっすぐに見て伝えた。
「ピアの無念を晴らしてくる――……俺自身の願いのために」
男も本当は、それだけを願ったのだと慮るように。
大きな鳥と再び空へ上がった青年は、自らの敵を今一度臨む。
昇り切った太陽の下、真っ白な雪山で悲しげに渦巻く、黒い火口湖……そこから頭を出す透明な蛇は、いずれも何処かで、沢山の誰かを害しただろう化け物の幼子だった。
――あなた達は、何も悪くないんだから。
「子供狩り」にあった子供を攫い、その度必ずそれを伝えた人間の女は、最後まで茨の道を歩み続ける。
――自分がもっと許せなくなっていくのは、何でかしら。
そういう仕事は、やりたい奴だけがやればいい、と青年は言った。それは決して馬鹿にしていたわけでなく……女の姿があまりに痛ましかったからだ。
国賊である女に関わったことで、双子も彼らの姐貴分も、おそらく生まれ持った以上の茨の道へと誘われていった。
「ピアは無理に……強くならなくても良かったんだ」
火口湖に向かう青年は、また自らの血を飛ばす。「力」の色がひたすら濃い中、隙間を見て敵に近付けるのが青年の強味だった。
「……俺は弱いから。自分にできることしかできない」
ずっと、自分に嘘は付けず、言葉だけを呑み込んできた青年は――
暗い水蛇の、普通ならわからないだろう一点。核だけを冷静に視定める。
黒い宝石を付ける水蛇の元へ、あまりに的確に飛び込んだ青年は、全てを「無意味」にする短刀の一太刀を振るう。
刃に伝う血。
直後に、逆鱗と呼ばれる「力」の塊は、跡形も無く砕けていった。
「……すまない、ピア」
青年は元々、甘い所があるのは否定できない。しかし、水蛇を殺す必要が無いと言ったのは、それが青年の実力では不可能だと早々に視切ったからだった。
本当は助けてやりたかった。逆鱗に潜む幼い子供の心は失われた。
自らの半身と言える逆鱗を失い、竜人の子供がどうなるのかもわからない。
それでも水蛇を相手に取り返せる算段はどうしてもつかず、それなら壊すことでしか、禍を止める方法はなかった。
壊せてもその後、青年が水蛇に喰われるとはわかっていた。もう飛び込むだけで精一杯だった。
黒い竜を生み出す湖の渦が急速に鎮まっていく。これなら幼馴染達が逃げられる可能性はあると安堵する。
血を使い過ぎて暗くなる視界のままに、全てを手放しかけた青年に――しかし運命は、決して安息を許さなかった。
「ライザ、大変!!! リーザが――……!!!」
……それはついに訪れた、恐れていた現実の姿で。
青年は暗闇の中、がむしゃらに、捕われた水の檻を無効化していく。
未知の脅威に怯える上に、逆鱗を壊されて心が折れたのか、水蛇は火口湖から川の方へと消えていった。
合わせて異形の獣も撤退を決めたのか、手の空いた悪友が青年を掬い上げていた。
そうして何とか、誰もが負傷しつつも再度集まった。
とにかくまず帰路につく。空の中、隣の大きな鳥の背で幼馴染が、声を張り上げて第六峠の状況を説明した。
「あの黒い竜は治まって、女の子は水蛇と川の中に逃げたんだけど、獣達とピアの弟だった水竜はそこに残って――」
神託を告げに来たという幼女は、撤退する直前まで不敵な笑みを絶やさなかったと言う。
――王女様が死ぬとは言ってないよ。罰はもう下ってるでしょ?
二つ頭と三つ頭の獣を盾に離脱した幼女。洪水の矛を失くした暗い水竜も、最早用無しと置き去りにしたらしい。
――洪水の犯人はそのコだから、好きにすれば?
フフフ、と幼女は最後まで、無邪気にそんなことを言ったという。
「獣達はすぐに取り押さえられたけど、リーザは消耗したミリアを置いて、一人であの水蛇に立ち向かって……それから……それからリーザ、様子がおかしいの!」
「……!」
目端に涙を浮かべて告げる幼馴染に、悪友の背で青年はぐっと、倒れそうな体に気合を入れ直す。
「もうあの水竜のコは抵抗してないのに、リーザ、戦いをやめないの……!」
――ずしん、と。獣の大切なものを沢山奪った暗い水竜へ、抑え切れない憎悪をぶつける……我を失う滅びの声が、青年にも聴こえた。
「早く止めなきゃ!! リーザが暴徒になったとしたら、もう私達にしか止められないわ!!」
「――」
その飛竜は、場にいる誰をも構わず、暴れ狂っているのだという。
「泣いてるミリアの声すら聞こえてないの! もうあの男のコ……ミリアの弟は、ヒトに戻って息をしてないのに!」
その復讐を半ば遂げても、正気に戻ることは無く――
幼い子供に更に止めを刺さんとする飛竜に、洪水の参考人にそれは不可と、騎士団長が抗戦に入った状態だった。
「リーザ……オマエ……」
既に限界を超えた状態の青年は、血の足りなさを心臓の回転で補うように胸を強く掴みながら、唐突にその真実を悟る。
「自分じゃ……戻れないのか――」
ここの所、その双子は飛竜の姿でばかりいる、と黒髪の少女は語った。それはヒトの意志を手放しつつある、確かな危機の前兆だった。
――女子供は関係ない。戦う意志があるなら殺し合えばいい。
私情を抜きにしても、幼い子供がどれだけの禍を起こしたか、青年も双子も目の当たりにしている。
それでも逆鱗を壊すことを躊躇った青年以上に、双子の弟は本来、口は悪いが根は甘い所がある。
しかし先日、彼らの姐貴分を助ける時に容赦無く多くの命を奪った双子は、見えない所で大きな変容を遂げていたのだ。
「デュラ・ユークはもう……戦う気も、無かっただろう……」
そもそも幼い竜人は初めから、実の姉に向けた憎悪以外は、仲間を守り、従おうとしただけだった。
「ピアだってそんなこと――……望んでないだろうに」
飛竜の変容のきっかけである女や、共に戦った黒髪の少女の声も届かない程、憎悪に支配された獣。それは、弟自身が望んだ姿では絶対にないはずだった。
何がそこまで、あの優しかった双子を駆り立てるのか。
その留め金はどうして外れてしまったのか……呼吸さえ苦しみの青年には今は、思い至れる思考の余裕はなく。
青年達がやっと、第六峠に辿り着いた時には、場はまさに惨状だった。
ボロボロの飛竜と、同じようにボロボロで翼を大きく広げた騎士団長との一騎打ち。止めに入ろうと、力を使い果たして倒れた黒髪の少女を王女が介抱し、祭祀一派は敵の獣を押え、逃げた幼女達を追って場を離れた状態だった。
「リーザ……!!」
上空から誰よりも早く、我が身を省みずに悪友から飛び降りた青年は、立っているだけでも精一杯だった。
互いを牽制し合う飛竜と騎士団長の間に、飛竜の方を向いて苦しげに降り立つ。
「リーザ、もうやめろ! 戦いは終わったんだ!!」
「……」
騎士団長の厳しい視線を背に受けつつ、青年はとにかく飛竜に叫びかける。
王女が少女、魔女が少女の弟を抱える方へ、悪友と幼馴染が守りに入るように降り立つ。
「……酷い。このコ、やっぱりもう……」
幼馴染が、完全に事切れている幼い竜人を確認して声を震わせる。竜人のためというより、それを行った双子を痛むように顔を伏せる。
「聴こえないのか、リーザ……! 目を覚ますんだ――!!」
おそらく飛竜を小さくできれば、解決は一番早い。
気も血も余裕の無い青年は、叫ぶだけでも意識を失いかねない。そんな青年の前に立つ飛竜は、青年が誰かもわからないように、咆哮をあげて突然襲いかかった。
「――いけません!!」
「え!!?」
その飛竜は、青年にまで危害を加えるはずがない。そう信じていた同郷者達の甘さを、運命は嘲笑うかのようだった。
王女が強い焦り声を上げた前で、まるで青年こそ真の標的と言わんばかりに、飛竜は短い距離を一跳びで詰め――
誰もが想定外の事態に唯一対応できたのは、初めから青年のフォローに回る気だった、紅い目の男だけだった。
……――と。
一瞬、青年は、何が起こったか全くわからなかった。
青年の代わりに飛竜に喰らいつかれ、血煙をあげた誰かの姿だけを、茫然と直視する。
「ウソ――……リミット……!!!」
幼馴染が絶叫する中、突き飛ばされて座り込んでいた青年は、ぽたぽたと自分をかばった者の血を受け止めることになった。
「……嘘、だろ……」
そのあまりにも鮮烈な、混じり気の無い赤――それに激しい衝撃を受けたのは青年だけではなかった。
その赤の味を知った、本当は蒼いはずの獣。その衝撃は青年以上のはずだった。
「――……――」
どさりと力無く、喰らいついた相手を、飛竜が静かに離した。
そうしてようやく、正気を取り戻したように……ぐらぐらと揺れるように後退し、ボロボロの羽を静かに広げる。
そのまま双子は、それ以上惨事を起こさないよう、一人で飛び去ってしまった。
青年は受け止めた男を抱え、真っ白になった頭のまま、見送ることしかできなかった。
+++++
とにかく手当を、と、ディレステア大使館まで消耗した全員が運び込まれた。
「リミット君とデュラ・ユークはすぐに第五峠に運びます。王女、私と騎士団長がしばらく離れますが、良いのですね?」
魔女の迅速な応急処置で、紅い目の男は何とか命だけは保っていた。
「はい。一刻も早く、この方達を救って差し上げて下さい」
完全に事切れたはずの幼い竜人も、何故か自ら息を吹き返していた。水蛇と同化したことや、飛竜の突進を受けてボロボロだった体まで、ヒトらしい姿を取り戻した状態となっていく。
それこそが「竜の眼」の本来の力――二つある内の一つを代償に、死に至る負傷でもヒトの姿を取り戻す蘇生が可能な宝なのだと、青年は知ることになる。
「……」
逆鱗を失ったことも関係しているのだろう。その幼い竜人の姿には最早、これまでの悲しげな大気の色は視られなかった。
傷を治す程度なら保たれる竜の眼も、死からの蘇生となると、完全に一つは失われるようだった。その状態で子供が今後再起できるとは、青年には正直思えなかった。
「ライザ。ミリアはヴァルトに、第一峠に送ってもらうので、本当にいいのね?」
座り込んで動けない青年の元へ、幼馴染が気丈な顔でやってきていた。
「……ああ。第一峠の土地自体が、ミリアには合ってるから」
大使館の一階、ロビーに続く狭い客間は長い冷戦でボロボロの殺風景な中、青年は階段も上がれない程消耗した状態だった。
「大使館の守りには、若祭祀達がついてくれてるから安心して。ライザもしばらく……ここでゆっくり休んで」
気を使われているのはわかる。それでも青年は、幼馴染に少しだけ苦く微笑んだ。
「……俺は大丈夫だから。しばらく――一人にしてくれないか」
「……」
心配そうに黙って傍らに佇む相手に、棘の無い声で口にする。
「ハーピアも休め。連日の力の酷使で、相当疲れてるだろ」
「そんなことないわ……みんなに比べたら、これくらい」
数多の鳥を使役し、周囲の見張りや仲間の様子を見守っている幼馴染。「千里眼」もきっと大変だったのね、と拙く笑う。
客間を後にする幼馴染に、青年は一言だけ、尋ねずにはいられなかった。
「……なあ。俺達は……勝ったのかな?」
「今日はね。まだ交渉は終わってないし、今日以上の危険はなかなかないと思うけど、油断は禁物よ」
あくまで気丈にする幼馴染に、そうだな、と青年も静かに頷く。
「ありがとう、ハーピア。もう一踏ん張り、よろしく頼む」
幼馴染も穏やかに、ライザもね、と返して部屋を出ていった。
植物油の灯りも少ない、寂れた大使館の一階に、すっかり夜の帳が訪れた中で。少ししてから青年は、おもむろに根性で立ち上がった。
「……」
当面は誰も、近くに来そうにない。きょろきょろとそれを確認してから、ゆっくり部屋の片隅の窓辺に近付く。
「……いるんだろ、リーザ」
どれだけ気配を隠していても、青年はいつも気付くことができる双子。壁の反対側にいる弟に、窓を開けて静かに声をかけた。
「…………」
闇に溶け込むように、外側の壁にもたれかかる双子は、青年の方を見ようともせず黙り込んでいた。
「リミットとデュラ・ユークは無事だ。治療には時間がかかるそうだけど、二人共、ちゃんと生きてる」
淡々と青年は、双子が最も気にしているだろう、大切なことを最初に伝える。
その甲斐あってか、双子は少しだけ顔を上げていた。
「……入って来ないのか? 寒いだろ、そこ」
「――るせー。どの面下げて入れってーんだ、バカアニキ」
あまりにこれまで通りの双子の反応に、青年は肩の力が一気に抜けて、苦く笑うしかなかった。
共に戦ったはずの者達に、会わせる顔がない。それは元々、存在を隠して生きる双子は、身内以外も多くいる場所でヒトの姿を見られるわけにいかない事情でもあった。
「リーザがミリアと駆けつけてくれたから……勝てたのにな」
仲間達がゆっくりと休む大使館の外で、暗い夜に、窓の外で独り、立ち続けている双子。この温かな壁の内に、双子を迎えるわけにはいかないのだと――今更青年は、長い嘘の冷たさに改めて胸を衝かれる。
青年は誤魔化さずに、今の双子の核心を問いかけていく。
「やっぱりオマエ、あのコを殺したいわけじゃ、なかったんだな」
「……」
傷付けた相手の無事を安堵する双子を、青年は初めから信じていた。穏やかに尋ねると、双子は腕を組んで壁にもたれながら、戸惑いをまとうように俯いていた。
「……正直……オレにも、よくわかんねーんだ」
ぽつりとそれは、珍しく――少しだけ弱気な双子の声色だった。
「最近はこうして、ヒトでいる自分の方が、不思議に感じるんだ」
「……リーザ」
「だから多分、オレは……下手したらまた、同じことになる」
闇の中で双子はフっと、自嘲的に笑ったように見えた。
「当分、アニキ達にも近付かない方がいい――最後の用事だけ今度済ませたら……オレはもう、二度と、ゾレンには帰らない」
「……――」
……もしもこの時、双子を傍に引き止めていたなら。
長い嘘に抗って、この壁の内に弟を迎えていれば、彼らの運命は変わったのだろうか……この先何度も、青年は思い返すことになる。
「飛竜の気が弱まる土地を探して、少しずつ――ヒトに戻るさ」
俯きながらも冷静に言う双子に、青年は何も返すことができなかった。
それより、と、話題を変えたいように双子は初めて青年の方を向いた。
「エアの姐貴、まだまだ予断は許さねーけど、少し持ち直したみたいだぜ」
「そうなのか――それは良かった」
色々な意味で大きく安堵した青年に、双子は良くない情報も伝える。
「早いとこクランの私邸から出て、ザインの山奥で隠遁するために治療頑張ってんだと。頑固過ぎてクランが嘆いてるって、ヘルシャが苦笑いしてたけどな」
「……相変わらずだな、あのヒトは。まだ一人で暮らす気なのか」
青年もそこで、彼らの姐貴分が両眼を焼かれ、視力を失っているはずだと惨い記憶を思い出した。
「……無茶だろ」
「ああ、無茶だな」
苦り切った顔で言う青年に、逆に双子は軽く笑った。
「エアの姐貴、眼自体は元々悪いし、『千里眼』に視力は関係ねーみたいだけど。まぁ、クランの頑張りに期待ってとこだな、本当」
「……クランはずっと、頑張ってるけどな」
いやいや、と双子は、甘いなという顔付きでにやりとする。
「アニキもうかうかしてんなよ? ミリアとの特訓、正直オレ楽しかったぜ? 放置してたら攫うぜ、多分」
「む……それは、どういう――」
「義姉さんって呼ぶより妹にしたいタイプだな、ありゃ」
双子の際どい発言に、むむむと更に難しい顔をする青年に笑う。
「オっちゃんなんか今だに、リーザ君とミリア君はどれくらい進んだ仲なんだね? とか、楽しげにきいてくるしな」
「ちょっと待て……それは誰だ、何でそんな話になるんだ」
これだけ騒いでも気付かれる様子がないのは、こういう時はいつも、双子が人払いの魔道を施してくれるからだ。幼馴染の鳥も、夜は感知力が落ちる賜物でもあった。
そもそもこうして、双子との他愛のない会話自体が、かなり久しぶりだった。青年は体力が零に近かったことも忘れ、窓辺に立ち続ける。
色々なことをしばらく話した。日中の惨事を一時忘れた。まるで両親が亡くなる前に戻ったような心地だった。
用事でまた来るから、そろそろ行くと、双子が背中を向けた。
「まーとにかく、アニキは熱くなんなよ。我が身全く省みずで隙だらけになるしな、ハッキリ言って」
「……リーザもヒトのこと言えるのか、それ」
壁から離れ、窓の前に初めて姿を現した双子は、青年に気を付けるようにと笑う。
薄い色のお気に入りの上着を、襟を立てて着こなす姿は、元々青年より大人びて見える……いつも通りの双子だった。
その後ろ姿を黙って見送り、最後に青年は小さく呟いていた。
「これで……精一杯の時間なのか、リーザ」
遠ざかる影はすぐに、飛竜の色に飲み込まれていく。
ヒト――魔道士であり、飛竜である弟。当たり前に併存していた二つの色に今更気付かされた青年は、双子が消えた闇をしばらく見つめていた。
+++++
後篇・転
和平交渉が間近に迫る中、先日現れた「悪魔祓い」の幼女については、結局足取りを掴めなかった。
洪水の主因たる幼い子供は目を覚ます気配がなく、騎士団長は「悪魔祓い」を探す名目で第六峠に留まり、王女達には至って安全な日々だった。
「え? ミリアは十六歳になったのか?」
うん、と少女は無表情に頷く。魔女が貸してくれた魔法の鏡で、第一峠で静養する少女と通信する青年も、そんな話ができる余裕を持てていた。
「そうか。せっかくだから、一緒にお祝いしたかったな」
「ううん……今みんな、大変な時だから」
まだ本調子でなく、起きたばかりという少女が淡々と口にする。
「もう、何年もお祝いなんてしてないよ」
「そうなのか……それじゃ、次こそはだな」
青年は何だかんだで、お節介な幼馴染やお祭り好きの悪友、さりげなく世話焼きの姐貴分など、誰かしらが毎年祝い合って来た。その日には必ず、ちゃっかり家にいる双子を含め、思い出の多い大切なイベントだった。
しかし少女は、そこで何故か、面持ちを暗くする。
「次……あるのかな……」
「――え?」
鏡の向こう、青い目を澱ませて俯く、黒髪の少女の姿が映し出される。
見た目より頑固な普段とは違い、少女はぽつりと、いつになく弱気な声でそれを口にした。
「ねぇ……いなくならないでね、ライザ」
「……?」
「ピアの生まれた日は、年末に近かったけど……わたし、もう祝えないって、去年が始まった時にはわかってたもの……」
「……ミリア?」
「ごめんね――……苦しいの知ってるのに、ごめんね……」
夢現のように胡乱な声色の少女。その目端には、涙すら滲んでいる。
その時青年によぎったのは、ある一つの不思議な記憶だった。
――ミリアが泣きながら目を覚ましたと思ったら。ピアが死んだ夢を見た、なんて言うんだもの。
今の少女も何処か、意識の灯があやふやで、これまでで一番悲しそうに視えた。
「次は絶対、一緒に祝おう、ミリア」
苦い顔でも珍しく微笑んで言うと、少女はじわりとまだ涙を浮かべながら、青年を見つめる。
「わたしのせいで……ごめん、なさい」
その涙の理由はわからない青年だが、一つだけ、確かなことはあった。
「ミリアが謝ることは何もない。俺がそうしたいんだから」
それが少女の、いつも悲しそうな原因に思えてならなかった。
何かの意味がそこにあるなら、少女の願いだけは叶えたいと。
何処か様子のおかしかった少女は、少し休む、と言って通信はそこで終わってしまった。青年もまだ貧血が強く、本調子でないため、リハビリ程度に軽く外を歩くことにした。
大使館の庭をぐるりと、見張りがてらに青年はふらつく。
「……ミリアも、人間との混血だっけ」
以前双子は、青年や「千里眼」、「子供攫い」の女など、人間の血をひくものは特殊な力を持ちやすいと言っていた。
「ピアが死んだって、あの時わかってたのは……そう言えば、予知夢みたいな感じだよな」
しかし先程のような弱気な様子は、普段の少女からはほとんど見られない姿でもあった。
「そうだな……もしも夢なら、すぐに忘れるだろうし」
あくまで例えばだけど、と。戯言のように一人で呟く。
洪水という、最も強大な相手がいなくなったことで、今の青年は気が抜けていたのは否めなかった。
「……――え?」
だからその時気が付いた、変わった「力」――この「雑種」の国では珍しい、「純血」の色が視界の端をよぎった時、咄嗟にそちらを振り返った。
大きく崩れた塀を鉄の柵で補修した隙間から、フフフ、と……神託の幼女が異形の獣に跨っているのを青年は眼にした。
「……――!!」
本来なら先に、誰かにそれを告げておくべきだった。
しかし青年に見つかった幼女と獣は、すぐ背中を向けて去り、追いかけることを青年は優先する。
「待て……! 『悪魔祓い』……!!」
夜であるため、幼馴染の鳥も付いてこない中で、まさか標的が自身であることなど思いもよらずにその敵を追う。
幼女は先日第一峠の方にいた、異形の獣に跨っている。独りきりで誘い出せた青年に振り返りながら、満足げに微笑む。
「後は渉外君にお任せかな。あたし達はどうしよう? キマ」
「……」
「エイラにまっすぐ帰る? それとも第三峠に寄ってく?」
青年には聞こえないよう、くすりと素性を口にする。
目的の場所に近付いたため、手持ちの水蛇を地面に投げつけ、霧を起こさせて追手の青年から視界を奪う。
「和平なんて――潰れちゃえば、楽しいのにね」
それが一番の目的と言わんばかりに、無邪気な微笑みを浮かべる。
そのために手を取った者に、この場を引き継ぐ。霧の中でゆらりと蛇のような姿を垣間見せつつ、最後の神託を口にした。
「あたしの神様は、本当にね……アナタ達が仲良くしちゃうと、嬉しくないのよ」
その真情は、この国の王が現在、人間よりも脅威とみた者達の意向で――
天意というより、神意、と。「力」の根源たる存在に傅く一人に過ぎない幼女は、表舞台から退場したのだった。
+++++
幼女達を追いかけて森の広場に出て、「力」の霧に包まれた青年は、それがあの水蛇の起こしたものとはすぐにわかった。
「何のつもりだ……?」
その霧には目晦ましの機能しかない。そもそも水蛇は第一峠以来、まず青年に近付きたくないようだった。
「逃げるための捨石か……? でも――」
それなら何故わざわざ、大使館の近くに姿を現したのか。最早あの守りの中で、王女を殺せる相手がいるとも思えず、戸惑いながら青年は立ち止まる。
その時、カツ、カツ、と。
木の構造物が多いゾレンでは、珍しく平らな石が敷かれた広場で、鋭い足音が霧の中から青年に届いた。
「……!?」
足音と同じように鋭い色合い。国王の剣山程に多くはないが、トゲトゲとした「力」の主の到来に気付き、思わず驚愕する。
足音の主は、やがて顔が見える位置まで青年に近付いてきた。
「やあ。君、ボクと何処かで会ったことない?」
「――」
「あんまりヒトの顔、覚えないからなぁ。気配も知らない感じだけど……最近ボクの周りで、うろちょろしてた奴だよね?」
現れた「西派」総帥、国王と同じ「力」の血筋である実弟。「子供狩り」張本人の男が親しげに笑う。
わけがわからない状況に絶句する青年を前に、男は親切に、青年が置かれた事態をわざわざ説明する。
「君、『五色』の一人だろ? 目立たないようにしてたけど、よくよく見たら、かなり重要なメンバーっぽいよね」
「……――」
「調べてみたら何と、うちのブラックリスト入りじゃないか。ライザ・ドールド。最強の獣、飛竜の直系サラム・ドールドの一人息子……でも人間との混血なんだよね、君ってば」
ここにきて、青年もようやく、これが自身を誘い出す罠だったと悟る。
「ボクもそうなんだ、奇遇だねぇ。君とならサシで話もできるかなって思って、ここに来てもらったんだ」
「……!」
場には確かに、男以外に「力」を持つ生き物の気配は、既に離れた水蛇以外にはない。霧で全体的に「力」がぼやかされているが、男が一人で青年と対峙しているのは確かだった。
なので青年も、ひとまず男の目的を確かめにいく。
「……何のつもりだ」
「何、簡単な話だよ。君……『千里眼』を助けようとしたよね?」
脳裏に、警告を発した国王の姿が浮かぶ。
――エア・フィシェルを助けようとした所を、愚弟は見ている。
この先何処で、それを相手が持ち出してくるかわからない。国王の忠告がまさに具現されていた。
「あの女を助けようとした飛竜、確実に君のでしょ? これ、どういうことなのか、君に直接訊いてみたくってね」
男は底意地の悪い顔で、青年を見て楽しげに微笑む。
「どういうことって……どういうことだ」
しかし青年は、それに関して言い訳をする気は初めからなかった。
「あのヒトは『五色』の一員だ。俺の大切な家族で仲間だ……助けようとしておかしいのか?」
「ふぅん? お国の意向に逆らってまで?」
「そもそも罪状は何なんだ。いきなり公開処刑なんて言われて、納得できるわけがないだろう」
おやおや、と、男は軽妙に驚いて見せる。青年は確かに、男がそれを喋った場にはいなかった。諭すような口調で問いに答える。
「彼女は『子供攫い』なんだよ。西部を騒がせた一大国賊さ」
「……そんな証拠が、何処にあるんだ」
男は女性の眼を焼くという、悪質な拷問でその自白を得ている。それも青年の全身を憤怒が走る理由だった。
「何、知り合いからのタレコミがあってね。残念ながら物証は無かったから、尋問で自白してもらったんだけどね」
「……!?」
それはここまで、明かされなかった謎の一端――
「子供攫い」の女や「千里眼」が、そもそも「子供攫い」関係者だと情報を与えたのは誰だったのか。
男がどの程度の事情を知っているのか、青年の背筋が冷える。
暗い霧の森の中、にやにやと男は歪んだ微笑みを浮かべた。
「楽しかったよ? 人間の女をいたぶるのは、昔から趣味でさ」
「……!」
自身の人間の母すら虐め抜いたという男に、青年は吐き気を催す。
「あの女を助けようとした君は、君も大罪人だ。でももしも、君がボクに力を貸すなら、咎は不問に付してあげてもいい」
「な……?」
「混血同士、仲良くしようよ。ボクもちょうど、いい手足になる化け物がほしかったんだよね」
だから飛竜、気に入ったよ、と男が無邪気な顔で口にする。
「嫌だと言うなら君は大罪人さ。そんな奴がいる『五色』に、大切な和平交渉への介入なんてさせていいと思う?」
「……!」
それは、青年達があらかじめ想定していた脅迫に過ぎなかった。
「生憎だが、俺は直接仲立ちに関わってない。問題があるなら『五色』は俺を破門するだけだ」
「へぇー。なるほど、君を切れってもしや相談済み?」
男は感心したように、ひゅう、と口笛を吹く。
「さすがは混血。普通の化け物よりは頭が回るみたいだねえ。それじゃ、大罪人の君を今から捕らえるしかないなぁ。まさかボク直々の捕り物になろうとはねぇ」
「……」
「ま、最強の獣相手じゃ仕方ないよね。せいぜいいかに、君の飛竜だけでも活用できないか、研究させてもらおうかな」
ちょいちょい、と、かかってこいと男が指を立てる。仮にもこの国の王たり得る化け物の血をひく相手であり……それも青年を捕らえる大義がある限り、男には何の咎も存在しなかった。
これでは誰の力も借りられない。青年だけが咎人となる選択は、想定内の話だ。
――……こんな奴に、捕まってたまるか。
同じ咎人であるなら、抵抗の限りを尽くすことをすぐにも決意する。
――でも今の俺で……アイツに対抗できるのか?
国王の力の半端ない強さは青年も知っている。腹違いの弟の男に、消耗している今の青年が、逃亡にせよ反撃にせよ可能であるのだろうか。
その選択の時。逃げるか戦うか、それを選ぶ運命の岐路は、あまりに考える猶予がなかった。
「……っ――……」
そもそも冷静に考えようとした思考は、男のにやにやした顔を見た瞬間、理性と共に塵と消えてしまう。
――楽しかったよ? 人間の女をいたぶるのは。
「西派」総帥。弱小で虚弱な人間の女性の両眼を焼き、手足に釘を打ち込んで磔にした化け物。どうせ咎人になるのならば、それをどうして、見逃す道理があるのだろう。
この男は、青年達の目的である和平交渉を潰すため、沢山の者を巻き込んで爆破事件や洪水を起こした黒幕のはずだ。
――許せへん! 『子供狩り』がおれは許せへんー!!!
「子供狩り」の首謀者。青年と双子を縛る長い嘘の発端となり、竜の血をひく少女達の運命を狂わせ、故郷から多くの命を奪った相手の総元締。今決着をつけずに、いつ戦えばいいというのか。
もしも青年が本調子であれば、逃げるべきだ、と普段の穏健な判断を下せただろう。
しかし最早、その赤い鼓動には抗えなかった。古来より続く兇獣の血をひく青年は、そこで初めて、内なる獣の呼び声に耳を傾ける――
そこはいったい、第六峠の何処であるのか。
珍しく石の足場が敷かれる、舗装された広場で、青年はただ男を睨みつけて霧の中で対峙する。
「来ないのかい? つまんない奴だな、意外に」
回復していない体力で、攻めに回るのは無理だった。男の出方を窺う青年に男はしびれを切らし、片手を宙に掲げた。
「ハイドラ曰く、毒とか効かない妙な体らしいけど、体力はボクより少ないね。本当……混血は大変だよね、お互い」
「――!!」
男が手を振り下ろした瞬間、「力」である透明ないくつもの杙……槍のように鋭い力が青年を目がけて降り注ぐ。
鋭いだけでなく、貫いた後に衝撃の力として破裂する特性の杙が、同時に五本、青年に向けられたようだった。
「こんなに弱い体に生んだ人間を、君は恨まないの?」
上から下に襲い来た杙を、青年は右に跳んであっさりやり過ごした。
「あれ、結構勘が良いのかい? 気配探知は鈍そうなのに」
不可視の杙をたやすく的確に避けた青年に、男が目を丸くする。
「単純な攻撃じゃ駄目ってことかな」
今度は上と左右から二本ずつ、青年を囲み狙う杙が発されるが、前転してそれも躱す。背後から、地面を突いた杙が起こす衝撃波が青年を吹き飛ばした。
「っ――!」
ごろごろと転がり、男がいる場所に近付いた青年は、回避に専念するために短刀も抜けなかった。
――霧のせいで動きにくい……!
「力」に敏感な青年は、杙のように狭い範囲に集中する力は視え易く、対処もしやすい。ところが広範囲に渡った力の霧の方は、物理的にも「力」としても、様々なものを覆い隠す障壁だった。
――優位に立たせておかないと、水蛇を呼ばれたら負ける。
男と一対一である間に、迅速に勝負をつけなければいけない。無駄な力は使えず、それならいかに男に隙を作るかが肝要になる。
透明の杙は、あまりに「力」の密度が濃く、無効化が難しい。そのために回避に専念する青年に、男は苛立ちを感じ始めていた。
「往生際の悪い奴だな。まず避けられないのが我が家の力なのに、君はいったい何者なんだ?」
「……」
せっかく男が沢山杙を放っても、青年は隙間を縫うように避ける。それは透明な杙の気配だけを探知する化け物には不可能なはずだ。杙を放つ男自身すら、厳密な位置は把握していないのだ。
「大体何で、飛竜を呼ばない? ボクをバカにしてるのかい」
飛竜の息子たる青年を傍から見れば、そう思われるのも当然だろう。
「……今の体力じゃ、飛竜は使えない」
相手を優位に思わせるためにも、しれっと嘘を口にする。
「確かに弱ってるみたいだけど、それでボクに勝てるとでも?」
「アンタに捕まるくらいなら……刺し違えてやる」
「おお怖い、やだねぇ。これだから化け物は、直情的で」
青年は、不器用でまっすぐな性質でありながら、長い嘘だけはずっと守ってきた。嘘のつき方は慣れたものがあり、これ以上言葉数を増やせば不自然だともわかっている。言葉を呑む癖もそれからのものだ。黙って男を睨み返す青年の代わりに、男がどんどん口を開く。
「さっきも訊いたけど、そんな弱小な体に生んだ人間を、君は一度も恨まなかったのかい?」
「……」
「ボクは恨んだけどね。混血の君ならこの思い、わかってくれると思ったんだけど」
人間の母と化け物の父を持つ青年は、母を溺愛する父に苦笑こそすれ、それが不幸だと思ったことはない。戦えば貧血が続く体も、それでも闘うと決めたのは青年自身だった。
「でもねぇ、人間の血も悪いことばかりじゃない。混血のボクだから持てる能力がある、それにも早いこと、ボクは気が付いたんだよ」
くくく、と男は攻撃を一時停止し、喋りを続けたいようだった。
「素朴でバカな『雑種』の化け物共も、縋る相手を求める弱い人間も、ボクにはどちらのこともわかる。穴だらけのゾレンの法治も、ボクには非常に、愚かしく見えてならないんだよね」
だから男は、「西派」という化け物多き集団も、「悪魔祓い」という人間多き集団も、御することができたというかのようだ。
「ボクの母親は元々、身の安全のために父上に取り入ろうとしたバカな人間の下女でね。口先で父上を操ろうとしたんだ」
男はそれを、ともすれば初めて口にするのか――
これまでの笑みが消えた顔で、昏い思いを露わにし始めた。
「父上は初め、母親に見事に操られた。ところが母親は途中で、それに気付かれるミスを犯すのさ……父上がどれだけ人間への怒りを高めたか、君にはわかるかい?」
「…………」
「可愛さ余って憎さ百倍ってヤツだ。ボクは自分を守るために、父上に全面的に味方した。でも母親も守ってやろうと思って、すぐに殺すんじゃなくて、じわじわ嬲ることを父上に勧めたのさ」
「……――」
それは歪んだ愛だったのかどうか。前王……苛烈な化け物の心情はまだしも、理解できた青年だったが。
「母親は元々、ボクのことなんて化け物に取り入る道具だとしか思ってなかった。気持ち良かったよ――あいつが泣き叫んで、ボクに助けを請う姿を見るのはさ」
けれどその子供。苛烈な父に与して生き延びた混血の愉悦の根源は、いったい何と呼んで理解すればいいか、青年にはわからなかった。
ただわかるのは、人間の血を恨んだ男の、最も大きな憎悪の心。
「……アンタは本当に……トラスティには遠く及ばないな」
その言葉にピタリと声を止めた、男の引きつった笑顔だった。
青年の弱小さは人間の血のせいだ、と男は何度となく口にしていた。
それは男も、人間の血で弱小の体となった化け物であることを意味する。
「力も体も……運命との闘い方も。アンタは父親に、アンタの母親と同じで取り入っただけだ」
「……――……」
男の腹違いの兄は、生粋の化け物でありながら彼らの父を強く恐れ、常に大人しい臆病な子供だったというが。
――私はただ、父上から逃げたかっただけなのだろう。
男とは違い、現王は誰かを直接犠牲にすることはなく、情けない動機でも見事遷都という大事業を実行した。それは男とは桁が違う上等さであると、青年はあえて混血の男に突き付ける。
力の差が一番、男が忌々しく思うことなのだ。
化け物の「力」を持つ者は、基本的に誰もがプライドが高い。それは「雑種」も「純血」も変わらず、歴史的に刷り込まれた通念なのか、「力」と「心」が切っても切れない故なのかは知らないが、男のような柔軟さを持つ化け物は往々にして、「力」では弱者だと青年は知っていた。
だからここで男を挑発し、勝負に出ると決める。
「トラスティに勝てる気はしないが、アンタ程度の手数なら、避けるなんて造作もないことだ」
「……言うね、混血」
男は怒りに引きつった笑顔で、青年をじろりと不気味に見返してきた。
「確かにボクは――ハリセンボンの兄者ほど、力は多く出せない」
それで青年を、一点集中で少ない杙で狙い続けた男だった。
男をなめた発言をした青年に、後悔させんとばかりに――
「でもね、ボクだってそれなりの化け物なんだぜ?」
現在持てる最大の力を、男は両手を掲げて呼び出していた。
「……!!」
国王は第五峠で、洪水を一つ鎮静化した力を持つ。そこまでではないにせよ、弟の男の言う通り、男の力も王族たる強大さだった。
反論する暇すらもなく、青年の四方八方から、避ける隙間のない大量の杙が飛来する。
「くそ、硬いな……!!!」
「無意味」にするにはあまりに密度の濃い力。この本質は、こうして透明な杙に「力」を凝縮できる化け物の制御力であり、「杙」という「意味」を受け継ぐ血筋の強みでもあり――
それなら青年に、その「意味」に従う以外に抵抗はできない。
男の本気の力で集中砲火を受けた青年を、退屈げに男は見守る。
「全く――跡形もなくなれば、利用しがいもないのにな」
それで今までは手加減していただけだ、と。化け物としての自尊を取り戻すように、小さく呟く。
しかし次の瞬間起こった事態に、目を見張ることになる。
「……え?」
黒い竜を極一部、僅かな時間だけでも圧し留めた時のように。青年を貫く直前で青年は力の杙を止めた。しかしその方法は全く違った。
そもそも全方位から来る杙に対し、手先はごく一部にしか当たっていない。それでも飛竜を小さくする時と、要領は同じだった。
飛竜に同時に存在する「意味」。「弟」という「自分より小さい者」を、青年はいつも重視してきた。重く視つめる――「心で強く想う」ことによって、手掌から気による介入ができた。
それは、自身の血を炎に変えるのとも同じだ。「透明」、「衝撃」と、少なくとも二つの「意味」を持つ杙に想う。それらは重なっていてこそ、有効であるだけなのだと。
標的を貫く鋭さを内包する「衝撃」の力だけ、青年の手で分離された杙が、全て青年を透き通っていく。
青年も生と死の狭間でようやく視えた境地だったが、男はまさに、何が起こったのかわけがわからないようだった。
「ああ……!?」
手元に奪った「衝撃」は消せない。逆に後押しに、青年は男に一瞬で王手をかけた。
瞬時に距離を詰め、男に馬乗りになり首に短刀を突き付けた。男が驚愕の表情で青年を見上げる。
「え――そんな、有り得な――」
力を避けも弾きもできなかった青年が、何故今、目前にあるのか。全く理解できない男に、青年は短刀を両手で振り上げる。
今躊躇えば、二度と機会は訪れない。全てを清算するために、獣の声に従う青年は本能のまま、男の頭蓋ごと叩き割る気でいた。
しかしたった一つの誤算は――倒れた男が背にする地面で、広場を舗装する石には、あらかじめある「力」が描かれていたこと。
――……――な?
青年が冷静であれば、もっと早くに気が付いただろう。何故そもそも、この広場にはこんなに、珍しい石板が敷かれているのかと。
「……!」
その魔法陣を隠すために、この霧は撒かれていたのだ。男の下の魔方陣に気付いた時には遅く、そこに記された呪縛の魔道は、短刀を振り上げる青年を素早く拘束していた。
その場所から男が動かなかった理由。この霧の広場、相手の懐に誘い込まれた時から、青年は負けていたことを知る。
「……ばぁか。ボクが何の保険も無しに、敵の前に立つとでも?」
男にのしかかり、短刀を振り上げた体勢で拘束された青年。それ以上の隙が何処にあるだろうか。
男はただ一本だけの、最も凝縮された杙を遠慮なく放つ。動けない青年の心臓を丸ごと破壊するように貫く。
――ねぇ……いなくならないでね、ライザ。
崩れゆく青年には、最後にその約束だけが、悲しげな少女の声と共に祈り留まっていた。
+++++
それは言わば――魂だけが辛うじて、青年に留まった状態だった。
「本当に単細胞だな、君達化け物は。ボクが本気で、サシで戦うとでも思ったのかい?」
嘲りと歓喜しかない男の声の下で、斜め下から心臓を貫かれた青年は、最後に胸を掴んだ状態で丸まって横たわる。
心臓を失った体は、ぴくりとも動かなかった。それでも聴覚は保たれた状態で、反応はできないまま、自身の敗北の仕掛け人をその後に悟る。
場には、青年が見たことのない誰か――小柄で祭儀衣を着けた老人が、助力者として現れていた。
「ダウテッド殿。まだその者は、完全に事切れてはおりませぬ」
にやにやとした祭祀らしき老人は、狡猾な老獪といった余裕が、薄ら低い声にも滲み出ていた。
「再起は不可能でしょうが、躯体の腐滅や霊魂の乖離が、何かの要因で圧し留まっているようですぞ。この場で全て、消滅させておいた方が無難でありましょう」
止めをさせ、と老人が促す。ふむ、と男は両腕を組んで考え込む。
老人の言う通り、青年の意識はまだ、朽ちたはずの体――そこにいた。老人も青年に、何が起きているかはわからなかったようだ。
――オマエの眼は万物の『意味』を見出し、その核たる力に手を加える神意の心眼だ。力あるもの全てにオマエは介入できるし、オマエに都合良く解釈――運用することもできるはずだがな?
ただ最後に胸を掴んだ瞬間、旅人の言のように、その手から自身に介入を行っただけだ。心臓を潰された体の血流を、血自体を動かすことで維持し、命の火を青年は辛うじて保っていた。
しかしその介入はあくまで、血の内にある気――力に働きかけただけで、物的に心臓の損傷の治癒を行えるほどではない。青年の体を保つために巡り続ける血が、これ以上外に流れないよう、傷口を焼いただけで精一杯だった。
そしてこれはその場しのぎで、血を動かす力が尽きるまでの時間稼ぎでしかないことを、思考すらろくに行えない中では辛うじてわかった。
「全く、害虫みたいなしぶとさなんだな、最強の獣って奴は」
そうした真相を全く理解していない男は、そう口にして無邪気に笑う。
「体を消すわけにはいかないよ、コイツには使い道があるんだ。そもそもそのために、ボクはここに来たんだしね?」
その返答は老人もわかっていたらしい。男は自らの意図を改めて明かしていく。
「『五色』の奴ら、自分から和平の場を潰してくれないかな。エア・フィシェルの時も期待してたのに、友達がいの無い奴らだよねぇ、本当」
「では再び、和平交渉の当日に見せしめにされると?」
「それなら兄者にも思い知らせてやれるだろ? オマエだって、だからボクに協力したんじゃないか」
ひたすら感覚だけが生きている青年は、指一つも動かない体で、事の真相にだけずっと耳を澄ませる。
「『子供攫い』の女や人間の『千里眼』、そして混血風情の弱い化け物を『王属』に迎えたいなんて、あのバカは言うんだから。オマエはヤキモキして、だからボクに接触してきたんだし」
男の言葉が指し示すこと。この老人が国王にとても近い位置にいること、そして「子供攫い」などの情報を男に流した元凶であることを、青年はここでようやく悟った。
「おやおや、ダウテッド様。前王の遺言通り、貴殿に気を使ってきた身に、何とご無体な仰り様であることか」
「いいよ、今更取り繕わなくてもさ。ボクと兄者で、オマエはずっと天秤にかけてたんだろ――どちらがより、オマエに都合の良い国王にしやすいかってね」
そして今回、兄に敗れた弟――和平交渉を続けなくてはいけない「西派」総帥は、腹立たしげに強く息をつく。
「兄者が妙に信頼するコイツらは、オマエには目障りなはずだ。あの真面目バカにオマエなくして王ができるとは思えないけど、ボクに今後も便宜を図ってくれるなら、コイツの始末みたいに、ボクもオマエの手伝いをしてやるよ」
その老人が祭祀の姿をしていること。国王への魔道による通信は老人が手助けしていること、つまり老人は国王の内情の大半を盗み聞いて知り得ること。そんな実状があったことまでは、青年にはわかりようもない。とにかく自らの命を留めることで精一杯の青年は、その程度を思考する余裕すらなかった。黒幕が他にいたのだと、それがわかった程度だ。
死に臨む青年の真っ暗な世界によぎるのは、全身を自律して流れゆく血が、ただよせては返す波のような音で。
――『子供狩り』は……わたしの大事なものを、全て奪った。
それはまるで……いつかの潮騒の、嘆きの唄のようだった。
+++++
潮騒の唄しか届かなくなった青年には、それからどれくらい時間が経ったかは、全くわからなかった。
土地の気を受ける以外に、呼吸も食事も、何一つ補給のない力は確実に減っていく。力が尽きれば訪れる、目前の死には、何かを思う余裕もない。
ただ老人と男の最後の会話だけが、流し続ける血に乗るように、ぐるぐると巡っていた。
「和平が成立したところで、兄者はボクには手出しできない。役立たずでしかなかったピア・ユークの鎧が、こんな形で生きるとはね」
「それではダウテッド殿、あの秘宝で取引をされたと?」
「使えない秘宝に意味はないだろ。オマエが凄いと言うから、わざわざデュラ・ユークを連れてまで回収に行ったのに……とんだ無駄骨だったよ、本当に」
それがケチのつき始めだ、と男が忌々しげに呟いている。
「これで完全に、兄者への憂さ晴らしの材料はなくなったな。和平が潰れれば儲けものか。せいぜいコイツの死体で苦しめてやって、後はボクは、西部で大人しくしてるかねぇ」
楽しみが減った、と歎く声は、無邪気な権力者のものでしかない。
男は結局、自身が国王となる意志があったわけでもないのだ。面白半分で全ての惨劇を起こしたのだと、青年は知る。
どれだけの者が、その禍で平穏を失うことになったのか。
怒りを感じる余分すらない青年の体は、やがて、男に残った配下に渡され、その後は体ごと暗闇に閉ざされていく。
「五色のケモノ」は、突然消えた青年を必死に探しながら、何も手がかりを得ることができなかった。それを嘲笑うように、次に青年の姿が確認されたのは、まさに和平交渉の当日だった。
「……――は?」
「え……ウソ?」
第六峠の川辺という、無茶な会場はそのままになっている。ゾレン国王とディレステア王女が急ごしらえの木製の机ごしに向かい合い、和平の条件を協議している最中のことだった。
「五色のケモノ」と共に仲立ちを務める「西派」総帥が、わざとらしく対岸を見つめた。
「おやおや。どうやら彼は――天意に反したみたいですね?」
彼らがいる川岸に、それは突然現れていた。
水蛇から吐き出されるように、砂利の上へとドサリと落された半死人。胸を掴んで横たわり、ぴくりとも動かない銀色の髪の青年。
「西派」総帥の男は楽しそうに、対岸の光景を信じられず絶句する者達の前で、青年の罪状を高らかに告げたのだった。
「まぁ、仕方がないことでしょう。何といっても彼はこの西部を騒がせた、『子供攫い』の一員なんですからね」
どういうことやねん!? と真っ先に激昂したのは、硬直して対岸を見つめる王女の右隣にいた悪友だった。
「ライザが『子供攫い』なんてわけがあるか! 言いがかりも程ほどにせぇや、アンタら!」
叫びつつ悪友は炎の翼を出現させ、対岸に飛び立とうとする。
「嘘じゃないですよ? あの彼を庇うと言うなら、『五色』の皆さんも同罪として、とてもこの大切な和平の場の仲立ちなど任せられませんけど?」
「な――アナタ……!?」
咄嗟に悪友が止められる。青年の元に彼らが駆けつければ、この場の存続自体が危ういと、にやにやと男が微笑む。
「大体君達も、彼の命の気配は最早感じられてないでしょう? 死体のためにわざわざ、あの天罰の中に飛び込むんですか?」
男が言うように、あまりに微弱な命を悪友達は探知できていない。更には対岸では青年を吐き出した水蛇が、川面から水蛇の全ての体――九つの透明な頭を突き上げて、青年を取り囲んだ状態だった。
その水蛇が先日、青年が殺し損なった「悪魔祓い」の強大な幼き魔道士だと知る幼馴染は、咄嗟に悪友を圧し留めていた。
「駄目よヴァルト、これは罠だわ――! あのコとアナタは相性が悪過ぎる!」
炎と風の鳥である悪友に、水の毒蛇はまさに天敵だった。
「大体、あれがライザのはずなんてない、ライザが殺されたりするわけがない……!」
目前の光景を否定したいように、幼馴染が叫ぶ。傍に付いていた国王は厳しさしかない顔で、対面の王女から視線を完全に外し、「西派」総帥の男の方を向いて立ち上がった。
「ダウテッド……――貴様……」
国王は対岸の死体が青年本人であることを、実の弟のやり口からわかっていた。
「何故――……あの男を、貴様が糾弾できるのだ」
これまでで一番低く張り詰めた声。眼光だけで殺すような激しさで国王は男に問いかける。
しかし男は、悪意に満ちた顔で、ただ笑う。
「おや? 兄者は何か、ボクに落ち度があるとでも?」
その苦渋の目こそが見たかった、と国王に微笑みを返す。
「あんな水蛇、ボクは知りませんし。ボクは単に、彼が天罰を受けて然るべきだと言っているだけですよ」
あくまでそれは、「悪魔祓い」の独断。それでいて、「子供攫い」の青年を容赦すべき理由も存在しないと、これまで一度も表立って敵対していない狡猾な男が笑った。
あまりの怒りに黙した国王に代り、口を開いたのは王女だった。
「ライザ殿が貴国の咎人、『子供攫い』とはいったどういうことなのですか。何の根拠を以ってそのようなことを?」
共に戦い、誰よりも信頼していた青年の無残な姿に、王女は間違いなく強い衝撃を受けている。左隣に立つ騎士団長の服を掴みながら、それでも気を強く尋ねる王女にも、男が嘲りを浮かべる。
「彼の家には、『子供攫い』に攫われたアルター・ルーシッドがいたんですよ。これは既に、国境担当の軍部が確認していることです」
そこでようやく、これまで使わなかった最後の駒を、切札とばかりに出した男だった。
「アルター……ルーシッド?」
怪訝な顔で男を睨む王女に、男はやれやれと両腕を軽く掲げる。
「そのコは、訓練中の事故で大火傷を負った少年兵士でしてね。『子供攫い』に拉致されて、その後は長く行方が知れませんでしたが、どうやら無事にしてくれていたようです」
ずっと男を睨んでいた「五色のケモノ」の内で、そこではっと幼馴染が顔を強張らせた。
「まさか……リミット――……!」
男に聞こえないよう、震える小さな声を聴きとれたのは悪友だけだ。男が言う「子供攫いに攫われた子供」は現在、重傷の手当を受けている紅い目の元少年のことだと、悪友もそこで悟る。
「良かったです、アルター君に何事もなくて。悪いのは彼……アルター君を攫ったあの青年ですからね?」
そして男の言い方は更に、ある暗黙の取引を突き付けていると、彼らはそこで気付く。
「それとも君達は――もしや、悪いのはアルター君だとでも?」
死んだ青年にこのまま「子供攫い」の烙印を負わせれば、その本当の「子供攫い」は見逃す。このまま和平の場も、青年を見捨てさえすれば、無事に続けることができるのだと。
それが本当に青年の死体であるとすれば。そのために和平や、仲間を引き換えにする選択を取ってよいはずがなかった。
「っ――!! ……」
「そん、な…… ライザ……」
呻くばかりの「五色のケモノ」。水の大蛇に取り囲まれて、今まさに喰われてもおかしくない青年を前に、座り込んだ幼馴染がついに嘔吐を始めた。
必死にその肩をさする王女と、同じように座り込んで、悪友が地面を両手で殴りつける。それらの傍らで、国王は呪うような声を最後に絞り出した。
「この……外道にして、下衆の混血が――」
「おやおや。それはこの場の兄者……人間と手を取り合おうという、アナタの台詞とは思えませんね?」
憎悪の視線を受けながら、人間の血を持った化け物の男は……人間とも化け物とも言えない歪な笑顔で、全員に応えた。
「混血のボクには……アナタ達の気持ちは、理解できない」
男は今や、敗者でありながらこの場を制した強者だった。
ただ、化け物と人間の苦しむ様だけが見たいのだと、その混血の微笑みは示して余りあった。
ぴくりとも動かず、力無く横たわる青年。青年達が今日この日まで、闘ってきた目的……ようやく叶いつつある和平を得たければ、青年を見殺せという脅迫。
それが自らの仲間達をどれだけ苦しめているか、対岸の声は青年に届くこともない。力も尽きかけ、水蛇に囲まれた青年は、永い暗闇へと導かれるだけの末路だった。
……その蒼い獣が、自らの色を捨てて降り立つことがなければ。
+++++
……ピシリ、と。
青年を囲む水蛇……もうヒトの形には戻れずとも、兄と慕う混血の男に手を貸し続けてきた幼い魔道士は、蒼い空気の割れる音をきいた。
――……??
眼下に横たわる青年との闘いで、ヒトの姿と理性の大半を水蛇は失った。不思議そうに周囲に在る水蛇……自らの分身を見回そうとしたが。
――……!!
見回すまでもなく、水蛇の世界が白濁した。
最早水蛇は首を動かすこともできず、本体も全ての分身も、その川に釘付けにされた――川ごと凍結させられたことを知る。
――い……いやぁぁぁぁ!!?
氷となった蛇は驚愕し、強い恐怖に大気を切り裂くような唸りを上げる。それが対岸の者達の視線を青年から水蛇に映す。
そんな大規模な魔道の出力に、耐え得る頑強な化け物はそうそういない。
「……とりあえず死ねよ。『子供狩り』の化け物」
何の色も無い声と共に、全ての氷の蛇がそこで砕け散っていた。
「このオレが女子供だからって――容赦するとでも思ったか?」
砕け散った氷の中に、ク――と……形容しようのない虚ろな微笑みで、その白き殺戮者は降り立っていた。
「……何だ?」
全く想定外の異変に、混血の男がポカンと首を傾げ、目をこらして対岸の様子を観察する。
「え……?」
真っ白な川と、そこから頭を出す氷の蛇達が砕け散り、視界が霧の如き氷片で閉ざされていく。
「嘘――……リーザ……!?」
ここに有り得てはいけない、白い誰かの存在に、すぐに気が付いたのは幼馴染だった。
ああ……と。
倒れる青年の前に降り立った、全く同じ姿の銀色の髪の男が、心から不思議そうな顔をして片膝をついた。
青年の体に手を当て、様子を確かめると全ての表情を消した。
「何だ……そっか――……」
唯一、青年と同じ灰色の目に、赤い何かを浮かべて写す。
「オマエも……いなく、なるのか――……」
感情を真っ白に失ったかのような、白い誰かの虚ろな声。それが確かに、当てられた手から青年へと届く。
――……リー、ザ……!!
ガハ、と激しく、初めて青年は呼吸を再開する。
自らの内に残る乏しい力を、たとえ全て使い切ってでも、止めなくてはいけない誰かのために。
咳込んだ青年に気付いた白い誰かは、フ――と嬉しそうに笑った。
「何だ――……まだ少しは、時間、あるのか?」
そこで青年を背に立ち上がり、改めて対岸にいる者を見据える。魔道の媒介である棍を肩にかけて、腕を引っ掛ける。
漠然と虚ろな誰かはただ、蒼ざめた顔色で、儚くも不敵に微笑む。
「それじゃ……全て、終わりにしよう……」
誰か達を縛り続けた、長い嘘を清算するために。
その責任者である「子供狩り」の男を、白い誰かはまっすぐに見つめた。
対岸に現れた銀色の髪の男に、混血の男は不可解そうに尋ねる。
「……君は、何者なんだい?」
男の背後にいる者達は、見知った大事な仲間に、それぞれ驚愕の表情を浮かべる。
「!!」
「あかん、ハーピア! 今は動くな……!」
立ち上がろうとした幼馴染を悪友が押える。
「…………」
ひたすら厳しい面持ちの国王に、王女も声をかけることができない。
この中では「西派」総帥の男だけが、白い誰かのことを知らなかった。
「どうして君は、そこの国賊の彼にそっくりなんだい?」
白い誰かと青年を見れば、誰もがまず最初に、尋ねて然るべきことを口にする。
「それに君の気配は――ボクは、覚えがあるぞ?」
混血の男のその声に、白い誰かはケラケラと、今までの不穏さが嘘のように普通に笑った。
「そりゃ、知ってるだろ? オレとアンタは何度も、第一峠ですれ違ってんだから」
白い誰か自身、それに気が付いたのはつい最近だった。
「なぁ、オっちゃん? アイツ、何度も第一峠に来てるよな?」
「…………」
白い誰かは後ろにいた、コロコロとした体形のある人間に話しかける。倒れる青年の横に茫然と座り込む人間がいることに、ようやく場の者達が気付く。その人間の姿を見て、混血の男が瞬時に強く顔を歪めた。
その人間に覚えがあるのは、混血の男だけではなかった。
「あれは――……第一峠の……行方不明の、オティ大使?」
「……!」
王女と傍らの寡黙な騎士団長が、同時に怪訝な顔付きとなる。
にやりと白い誰かは、底意地の悪い顔で笑った。
「オっちゃんを殺そうとしただろ、アンタ」
その微笑みは、「西派」総帥をここで初めて、追い詰めるために。
「そうだろ? 『悪魔祓い』の渉外さんよ」
くくく、と、白い誰かが笑う。「西派」総帥は表情を出さないように、今までにない調子で応じる。
「……何だって? 何を言っているんだ、君は?」
「何だって、じゃねー。口封じにオっちゃんを殺そうとまでしたアンタを、オっちゃんがここで庇うと思うか?」
白い誰かの足下で座り込んだままの人間。ここまで連れて来られた目的を果たすために、その人間も顔を上げる。
「そうだ……私は、リーザ君に助けてもらったんだ」
「――」
「君は『悪魔祓い』の一員で、何度も第一峠に来ている。私がそれを証言するし、何なら君と取引のあったザインの業者にも、証言を頼んだっていい」
これまで「西派」総帥は表立って敵対せず、「悪魔祓い」と自身の関連も認めなかった。だからその混血の男に、それは確実な一つの危機だった。
――オレは第一峠でしばらく、祭祀に頼まれことがあるから。
足元の人間が行方不明になる少し前に、白い誰かはそんなことを口にしていた。「最後の用事」はその人間を守ることだと、ここで知るのはおそらく祭祀を通して依頼した国王のみだった。
「……はは、はは」
想定外の事態に混血が動揺を始めた。乾いた笑いだけを漏らし、表情を引きつらせる。
「あの役立たずが……だからあれだけ、遺体を探せと言ったのに」
既に氷となって砕けた実行犯に、誰にも聴こえない呪いの言葉を吐く。その後改めて、白い誰かを笑いながら見返した。
「そういう君は、もしや――」
混血の男にはそこで、第一峠よりも新しい記憶が辛うじて飛来していた。
「『子供攫い』の女を討伐した時、確かにボクは君に会っている。他の言いがかりはともかく、それは確かだね」
それを口にしたことは、駄目押しでしかない。それもわからないほど、混血の男は追い詰められていた。
白い誰かは魔杖でもある棍を、肩からくるりと体の前へ、両手に持ち替えた。
「そうそう。それが……オレもアンタに言いたかった」
不自然なほどに爽快さの浮かぶ笑顔。
その後にふっと、両目を閉じる。魔杖を起動させるためか、何言かの詠唱を、まるで謳うように口にする。
小さな詠唱を誰も止めないほど、場の時間は冷え切っており、全て白い誰かの手中にあった。
そこには確かな空気があった。誰ももう、白い誰かを止めることはできないのだと。
「オレが誰かって――きいたよな」
短い詠が終わった後に、白い誰かは足下の青年をもう一度見る。
「コイツは偶然、オレとそっくりな奴でさ? オレが第五峠に預けたアルターを、オレと間違って引き取らされたんだよ」
そこでまた、青年はぴくりと全身を震わせる。げほっと血を喉に絡ませ、青年は必死に声の出し方を思い出す。
白い誰かはそれに気付かず、自らが望む通りの真実を伝える。
「だからコイツが『子供攫い』なんて、アンタは勘違いしたんだろーが」
止めなければいけない。しかしあまりに、今の青年は無力だった。
――や……――
「オレは……アンタが殺したピア・ユークの……」
――やめ、ろ……――
「『子供攫い』ピア・ユークは……オレの……」
そして白い誰かは――その呪いの始まりを口にする。
「オレはピア・ユークの連れ合い。同じ『子供攫い』、リーザ・ドレイク。この胸の内にあるあいつの通行証が、その証だ」
……は? と、混血の男が目を丸くする。その後ろで悪友や幼馴染も呆気にとられ、国王はただ厳しい面持ちをいっそう厳しくしていく。
「それは――……リーザ殿……」
「……」
何故白い誰かが、その呪いを口にしてしまったのか。王女と騎士団長も驚愕の顔色を浮かべる。
幼馴染が哀しげに、不意に冷静に戻り、白い誰かを見つめた。
「やっぱり……ピアと、リーザ……」
幼馴染にとって、その関係性は人間の女が現れた時からわかっていたこと。
「でも――どうして……?」
しかしこの場でそれを口にすれば、白い誰かは青年と共に、討伐されるべき対象となる。それを改めて、涙混じりの目で問いかける。
――……――……。
倒れ続ける青年は、声一つ出せない、決して動こうとしてくれない体を、ひたすらに呪った。
――アニキは甘くて――危なっかしいんだよ。
少し前に、その双子にそれを言わせた、自らの不甲斐なさを罵倒し続ける。
白い誰か――双子の弟がその呪いを口にして、幾許も無い瞬間のことだった。
「あ……あははははははは!!!!」
ピシリと再び、蒼い空気がそこで割れる。
全身を凍りつかされた混血の男が、驚愕と恐怖の声を上げた。
「ボクを殺すか!? ボクは王族だぞ血迷ったのか何オマエ何考えてる『子供攫い』化け物リーザドレイク!!?」
そのまま水蛇と同じように殺す気だろう。王女が慌てて双子の弟に叫んだ。
「――やめてください、リーザ殿! 彼はわたくし達が捕らえ、第五峠で裁きます!」
「悪魔祓い」に多大なる被害を被り、本来その調査に来ていた騎士団長も険しい顔で押し黙る。
「お願いです、どうかお気を確かに! こちらを向いて下さい、リーザ殿!!」
数日前と同じある危機に、王女は誰より早く気が付いていた。必死の声をかける人間の王女に、最後にふわりと、双子は一瞬だけ振り返って微笑む。
「……ついに――ここまで来たのか……?」
不意に、獣に変わりゆく手と、倒れている兄をもう一度見つめる。双子の兄弟をつなぐ炎の血の鼓動。その赤が獣に流れ始めた。
それが先程の詠唱の効果。獣の蒼は失われる。破れ散っていく上着が拘りの品だったことすら、獣は最早思い出せなくなったように。
これで全て、獣の役目は終わった。
ある長い嘘の結末を、その赤い獣は、黙って受け入れた。
+++++
――あたし達の父さんは、竜と言われる化け物だった。
その人間の女の素性を、女の数少ない友人「千里眼」から、山上の第一峠で銀色の髪の青年は耳にした。
同じ折に、奇しくも近い話を、双子の弟と人間の女が交わしていたこと。中腹の山小屋で、青年の仕事が終わるのを待っていた彼らの優しい時間を、青年はずっと知ることはなかった。
赤く染まりゆく獣の足下、青年は倒れ続ける。
まるで獣の、失われる魂を受け取ったように。蒼い誰かの大切な思い出を、走馬灯のように束の間に夢見る。
山小屋から少し離れた泉で、青白い月の光の下、双子の弟は沐浴する人間の女の番をしていた。
「竜って……あの、竜かよ?」
身を守る鎧を外した女は、その時は心の鎧も外したように、双子に笑いかけていた。
「うん、あの竜。リーザみたいなケダモノじゃなくて、自然と一つの、あの竜だよ」
ケダモノってゆーな。と、獣寄りの竜――飛竜である双子が呆れて言う。
それでなくても、薄着で水の滴る女の姿に、目のやり場に困っている。近くの木に持たれて女から目を逸らしつつ、面白くなさそうにする。
だって、と女は、にへらと嬉しそうに笑った。
「リーザ、下手したらケダモノになっちゃいそうなんだもの。気をつけた方がいいよ?」
「――は?」
「自分で気付いてないのが一番怖いよねぇ。ライザなんてまだ、ぷっつん来たら暴走しちゃうぞって、自覚してそうなのにな。リーザは案外冷静に見えて、ライザよりホントは冷静じゃなく見えるな、あたし」
人間の女は、曖昧な虫の知らせという形で、現状を的確に把握する直感の才能を持っていた。だから全く根拠はなく、不服そうな双子が心配、といった顔でまた笑った。
しかし双子が最も不服だったのは、話の内容にではない。
「……そんなケダモノの前で、無防備にしてんなよ、あんたは」
そうしたことを話しながら、彼を警戒せずに鎧まで外し、何度も反応に困る緩い笑顔を見せる女と、
「随分あんた……アニキのこと、よく見てんだな」
女の口から最近よく、兄の名前が出ることだった。
いつもそうして、双子は素直でなかった。他者には敏感なわりに、女の言う通り、弟自身の心には鈍い所があった。
だからこそ、生まれながらに存在を消され、隠されて生きた嘘の中でも歪まなかった。
そして女が死した痛みも封じていられたのだと、分身である青年は今更に悟る。
それでも女への想いについては、色々あって双子は自覚していた。逆にそれは気付けない鈍い女が、長い嘘の歪みだけを淡々と伝える。
「リーザは本当、ライザのことは聞き逃せないんだねぇ」
「……」
「エアのこともそうかな。数少ないリーザの居場所……リーザがいるって知ってる家族だけは、リーザは何をしたって、守りたいんじゃない?」
だから双子は、「子供攫い」などに手を貸すようになった。女はそう言って苦く笑いながら双子を見つめた。
しかしその「家族」は、蒼い獣から失われ続ける。
今まさに赤い獣として具現しゆく、孤高な飛竜の強過ぎる痛み……両親に加え、幼い頃からかばってくれた長老も失った悲痛が全て赤く染まる。
そして極めつけは、己と分身である双子の兄。飛竜が全ての嘘に堪えて、一番守ろうとしてきた存在が消えそうになっている気配。
それこそが、数日前のように、飛竜の最後の留め金を外した駄目押しだった。
「ライザ以上にリーザは、ヒトを傷付けたくはないヒトなのに……あたし達みたいなヒト殺しに手を貸した代償は、いつかリーザ自身に還ってくる」
駄目押しは兄の危機だが、飛竜をそもそもむしばんでいた痛みは別だ。幼い頃から姐貴分の人間を酷く傷付けられたこともあった。
その上、青白い月の下で出会った赤まみれの悲しい女を、失った痛みは大き過ぎた。
「リミットみたいに魔になっちゃうヒトって、素質があるの。暴走する程の心を、それまでは耐えれちゃう才能みたいなもの」
女が攫った子供の一人は、「魔縁」と呼ばれる生き物になった。それは本来の姿を失い、魂をすり減らし、烈しさに呑まれた化け物と言える。
「それでもリミットは、よく自分を制御できてる方だけどさ。リーザは違うと思うな……何せ、堪えてること、多過ぎるんだもん」
――? と双子は、それと自身との関連をまるでわかっていなかった。
「ほら、全然気付いてない! 仮にも十八年隠れて生きるって、どんだけ辛いか――たった五年、隠れてたあたしが言うのにさ?」
女はただ辛そうに、誰かからフっと目を逸らし――
「……リーザが痛いと、あたしも痛い……。リーザは初めて……あたしが『子供攫い』なこと、怒ってくれたヒトだから――」
そうして、命の次に大切な通行証まで貸した、女の心を口にした。
「あたしは……リーザになら、何をしても助けになりたい」
不意に赤面した誰かは……自身の負けだけを、衝動的に悟る。
「……オレは……」
月の下で切なげに潤む女の青い目に、蒼い己を忘れて告げる。
「オレは、ただ――……あんたが、ほしい」
そして、長く溜め続けた赤熱を解放した獣は、赤く変貌する。
「リー、ザ………」
獣の蒼を受け取った青年は、ようやくうっすらと眼を開けた。
そのまま現実を直視し、彼らの終わりが始まったことを知る。
川辺に現れ、慟哭の咆哮を上げた赤い飛竜。元の蒼い獣を見慣れていた同郷者達は、最早周囲を構わずに叫んだ。
「何やアレ!? 飛竜ってことは、リーザやんな!?」
「嘘、まさかリーザ、魔縁に!?」
そして次の瞬間、それが最早、蒼を失った魂無き獣であることを身をもって知る。
「やめてリーザ!! 私達よ、正気に戻って!!」
「リーザ殿、お気を確かに!! このままでは……!!」
幼馴染を悪友が、王女を騎士団長が抱えて空中に避難する。飛竜が川辺にいる者に突撃を始めたのだ。
おそらくは凍り付いた混血を目がけて、狙いも定められずに突っ込む飛竜に、交渉場を囲む両国の兵士が次々、跳ね飛ばされていく。
「……リーザ……」
眼を開けた青年は、そのただ赤い獣……魔性の紅に染まる手前の、まだ暴徒に留まる双子の弟を必死に見つめた。
「やめ、ろ――……リーザ……」
それはいっそ、紅く染まってしまった方が、魔として自衛ができただろう。頑強な体で飛び立ち、暴れ狂い始めた獣から、青年は全身に最後の蒼い力を受け取る。
「…………」
誰彼構わず対岸に突っ込む赤い獣に、国王が顔をきつく歪めていた。
ゆらりと、魂を留め続けた青年は、動くはずのない体で、全ての秩序に背を向けて立ち上がる。
「……何処にいるんだ、リーザ……」
対岸で、二国の兵から刃を向けられる赤い獣だけが、完全に彩を失った青年の眼に映る。
「自分から……誰かを、傷付けるのか――……」
そこには、青年が守りたかった誰かはいない。生粋の蒼い獣は魂を失った現実を、赤い鼓動を失った眼が視る。
――そうしなきゃできないことだって、あるだろ。
生まれた二人を一人と偽った時から、それは決まっていた。
いつか長い嘘は本当になり、どちらかがどちらかを失う――
それを拒んだ蒼い獣は、自らが先に消えることを願ったのだと。
「俺は無事だって……わかってたんだろ……?」
消えそうに拙い青年の声。まるで呼応するかのように、対岸で暴れ狂っていたはずの赤い獣が、ふっと青年の姿を捉えた。
心臓を掴んだまま立ち上がり、そのまま動けず獣を見つめ続けていた青年の前に、赤い獣が降り立ってくる。
「……――……」
おっせーよ、と。
青年を見下ろす灰色の目だけは、今までと同じ赤い獣に、青年はそんな声を聴いた気がした。
それは対岸の者達が駆け付けることもできない程、刹那の一瞬でありながら……青年にはとても長い時間に感じられた。
「何処行くつもりなんだ……オマエ……?」
その速さに追いつけないのは……そもそもわかってはいた。
心臓を潰された青年の抜け殻を、獣が失わずにいられる道はそれしかなかった。そうして結果だけを求め、最後の魔道を使った獣の赤い変貌。
「そんな……! やめて、リーザ!!」
立ち尽くして赤い獣を見上げる青年を、赤い獣は今まさに、大口を開けて喰らいつくための雄叫びを見せた。
「……!!」
ちっぽけに佇む青年の前に降り立った獣は、本気で青年を喰らわんとしている。双子の事情を少しでも知る者は、おそらく瞬時に理解していた。
飛竜になれず炎の血を持つ青年と、炎を継がなかった飛竜。
二人で一つのものを使う――それはこの国では、命の次に大事な通行証を始めとして、双子には当たり前のことだった。
だから飛竜は、青年の体が滅びる前に、同一化せんとしているのだと。
「己が双子を取り込む気か――……赤い獣よ」
たとえそれが、正気の沙汰ではなかったとしても。強く信頼した相手を、二人も獣に奪われることを、国王は拒否した。
「貴様がピア・ユークの連れ合いと言うなら……私がこの手で、彼女の下へと送ってやる」
国王は獣との約束を覚えている。赤い獣が全くそれを、忘れてしまっていたとしても。
――あの人間は必ず、私が探し――……貴様らの元へ帰す努力をすると、ここで約束する。
自らもささやかな希みを永遠に失った日、そう約束していた国王は。最早躊躇うことはなく、化け物の国の王たる力を赤い獣へ向ける。
これまでの獣の猛攻に、既に心の準備を整えていた物憂げな国王は……そこで己が決意を、一息に解放した。
その優しい記憶は不意に――
流れ込んだ蒼の下、温かな煌めきで再生された。
――リーザに身長抜かれるのだけは、いやだな。
飛竜を小型化することができる青年の特技。
弟を小さくできる力は、思えばそんな心が始まりだった。
……ぼた、ぼたと。
赤い獣の直下にいた青年は、ただ不思議そうに……。
抵抗しなかった青年を真っ赤に染める、赤い獣の血。数多の透明な杙に貫かれ、命を流す体を真っ白な頭で見つめた。
「……トラスティ……?」
青年は、自らが食われて終りで良かった。それなのに、茫然とこの現実……総身から血を流す赤い獣を撃った、最強の獣すら突き通す力。獣越しに、対岸の厳めしい力の主を見つめる。
「何で――……リーザを……」
全身に双子の血を浴びながら、赤まみれの青年はそれだけをやっと、無情な現実の中で口にする。
対岸では悪友がまさに、青年の衝撃を代弁するように、非情な国王に掴みかかっていた。
「国王サン!? アンタ――リーザを殺す気か!?」
「……」
「元はと言えばそこの弟のせいやろ!!? これ以上おれらの大事なもんを壊す気やったら、おれはもう誰相手でも容赦せんからな!?」
声も出ない他の者達を横に、厳しい顔の国王は、掴みかかる悪友をまっすぐに睨み返した。
「……馬鹿者が。もうとっくにあの男は、事切れている」
その赤い変貌の真実と、確かに死体だった青年が動けている理由に、悪友達は気付いていない。それを幸せな者だと、断罪するように言う。
それだけ体を貫かれながら、獣は再び雄叫びを上げ、自身の邪魔をする対岸へ飛び立とうとした。
「……リーザ……!」
その体に咄嗟にしがみつき、青年はただ……。
「やめろリーザ!! お願いだやめてくれ、もう十分だ!!」
全く動かなかった体に、確かに渡っていく力の熱さに、青年はただ――泣き叫んだ。
「俺は無事だから正気に戻ってくれ! オマエの命はこれ以上いらない、俺はこれ以上、オマエから奪いたくない!!!」
魔杖たる棍を使えば、本来双子は、魔道を扱う際に詠唱など必要としなかった。なのに珍しく、真面目に詠唱した最後の魔道は、初めて使うものだったのだ。
同一化。心臓を失った片割れに対して、誰より近い双子だからできる禁術。己の心臓を二人で使うための「力」の共有――
命たる心を明け渡す、そう簡単には使用できない「双子」故の秘術だった。
だからこそ青年は、双子の記憶をかいま見ていた。
双子の今の姿は、元々危うかった魂が、禁術の代償についに自らを失ったこと。取り返せない現実を悟りながら、青年は呼びかける。
「俺はずっと、オマエから奪い続けてきたのに……!! まだ何も返せてないのに、いなくならないでくれ……!!!」
長い嘘の犠牲者はいつも、隠され続けてきた弟だった。
最早青年の制止も振り切り、飛び立とうとする赤い獣には、先日に暗い水蛇を喰い殺したような憎悪の鼓動しか残っていない。
その澱みは命がけで守ろうとした片割れにすら向くと、獣の憎悪を察していた国王は、ずっと対岸で顔を歪める。
「ライザ! オマエがそれを止められないならそこをどけ!」
「――!?」
滅多に大きな声を出さない相手が、対岸まで届く程の剣幕で発した叫びに青年は硬直する。
「わからんのか、このままでは和平の儀は台無しとなるぞ!? それはその者が望んだ未来ではあるまい!!」
「――」
既に二国の兵士はかなり傷付いている。まだ交渉の調印も行われていない状態で、ここで赤い獣が暴走を続ければ、取り返しのつかない事態がすぐそこに迫っていた。
傷付き倒れる数多の者達の姿に、国王はただ叫んだ。
「オマエにできないなら私がする!! だからそこをどけ!!」
「トラスティ……!」
「どの道その者は死罪だ! ピア・ユークの通行証を持つと、自ら口にしたのだから!」
だから国王に、その双子を庇い切ることはそもそもできない。むしろそれを覚悟に、最後に言い残しただろう双子の思いを、的確に汲んだ国王は青年に現実を突き付けていた。
それはただひたすらに――切実な心を、双子に代わって叫ぶ男の厳しい声だった。
「オマエは咎人ではないのだ!! だからどけ!!!」
青年にかけられた嫌疑、全ての咎を、赤い獣は既に引き受けたのだ。
「ミリア・ユークのことを考えろ、オマエまで失えばあの少女はどうなる!? オマエ一人の感情で全てを不意にする気か!!」
「――……!」
自身と引き換えに、帰りを待つ者がいる青年に、未来を残したい。それが赤く変貌した獣の、最後の長い嘘。
「――ライザ! あんな奴の言うこと、きく必要あらへん!」
飛竜を押さえつけるため、悪友がこちらに降り立っていた。飛竜は全身を貫かれて弱りはしたが、翼をばたつかせて強く抵抗し、青年一人では止められなかった。
何匹かの怪鳥と共に、飛竜を取り押さえた悪友のおかげで、青年はようやくマトモな思考ができるようになったが、
「何としてもリーザは元に戻すんや! 今はとにかく動きを止めて連れて帰る!!」
それは不可能、と、誰より青年自身が知っていた。
そこにはもう、青年の弟はいない。その「心」は失われたと、青年の眼は現実を焼き直し続ける。
うわああと驚く悪友を、怒りに満ちた飛竜が、全ての怪鳥を悪友ごと振り飛ばした。先日に紅い目の男を殺しかけたように、そこには何の遠慮もなかった。
そうして同郷の者まで、容赦なく傷付ける赤い獣。
それが青年にとっては、最後の引き金とならざるを得なかった。
――トラスティ……と。
その時青年は、不思議な程に、気持ちが静寂に落ちていった。
蒼く冷え切った声で、対岸の国王へ、沈痛な無表情で語りかける。
「トラスティ……俺はアンタに……誰かに、誰も殺されたくはない……」
「――!?」
「殺される仲間を見殺しにするのは……俺にはできない……」
怪鳥から解放された飛竜は、まずは青年から喰おうと思い出したらしい。咆哮して青年を睨む赤い獣に、青年は俯いて対峙する。
青年は確かにそこで、赤い獣の内に、自らと同じ赤い光――
「じゃあ……トドメをさすのは、俺の役目か――……」
彩のない眼に赤く走った、最強の獣の呼び声を聴く。
「簡単なことだった……俺が、リーザになればいいんだ」
ここからそれができるのは、他ならぬ青年だけ。飛竜と青年、どちらが本体であるべきかは、わかりきった答だった。
じわりと。
青年と双子を揺らし続けてきたはずの、赤い鼓動……心臓を潰された青年を生かす、新たな力の在処を知る。
「俺達は元々――……二人で一つの、飛竜なんだから」
それは青年が拒み続けた、獣としての本性だった。
この赤は命であり、また、永く燃え盛る憎悪。何かを愛せば愛すほど、裏腹に積もっていく命の鼓動。
生き物とはきっとそれ故に生まれ、そして滅ぶ。彼らの父が愛する人間を失い、自滅した時のように。
青年を喰らうために、まさに飛びかかる赤い獣。青年はただ、弟を小さくしてきた今までのように、獣の前に右手を掲げて、獣の憎悪の全てを迎え入れ……――
「飛竜」とは、最強の獣であると、周りは口を揃えて言った。
――アニキもオレを使えば、強くなれるんじゃねーの?
頑強で赤く巨大な、炎を吐く獣を操り、変化もする化け物。
その血には炎が流れ、血を浴びた者を焼き尽くす。しかしそれに耐え得る者には、逆に強靭な躯体を与える獣でもある。
かつて両親はそれを迷った。弟の血を少しでも兄に与えれば、兄は強くなることができるのではないかと。
「初めからこうしていれば……オマエは消えなかったのかな」
双子の血を浴びた青年には、今や飛竜本体の喰い付きですら、通すことのない頑強な躯体が得られていた。
その可能性を知っていて、拒み続けたのは青年だ。だから双子は、ただ弟を傷付けたくないという、青年の甘さを責めていたのだ。
「でも……オマエは、俺の心臓になることを選んだんだ……」
得られた頑強さを以って、青年は自らを餌に、飛竜の懐に進んで入った。そうして飛竜の核たる心を、確実にその眼に捉え――
全力をまとわせた右手だけで、飛竜の胸を青年は貫いた。
何より大切だったものを、自ら貫くその感触。憎悪の鼓動が赤い右腕に全て遷されていく。
まるで、赤い獣ごと、その右腕に吸い込まれていくように……「力」の一つの形である、飛竜の姿が薄まっていく。右腕はそのまま震源となり、飛竜の血が心臓を固め、赤い右腕と共に再び鼓動を始める。
そうして、自らを失った赤い獣は最後に――
最強の獣の血を浴びた青年の内へ還るように。
彼らの長い嘘……存在しなかった者へと、戻ったのだった。
+++++
その後、いったい何があったのだろうか。青年は全く、よく覚えていなかった。
「愚かな……暴徒を自らに取り込むなどと……」
次に目を覚ましたのは、何故かゾレン東部、それも王城の一室だった。
難しい顔をして青年を見守る国王が、起き抜けに面前にあって驚く。
「おはようございます、ライザ君。気分はどうですか?」
「……は?」
「あ、ちゃんと心臓は動いてるみたいですね? どうなるかと思いましたが、さすがに丈夫ですねー、飛竜」
隣でにこやかに控える祭祀にも、ポカンとするだけではすまなかった
「ライザ……!! 良かった、目が覚めた……!!」
ベッドに横たわる青年に飛びついた人影。それは第一峠でしばらく療養していたはずの少女で、顔は涙でくしゃくしゃだった。
「本当に死んじゃったと思った……! いなくならないでって約束したのに、バカ……!!」
泣きじゃくる少女曰く、一週間前の和平交渉の後、青年は心臓が止まった状態で川辺で発見された。
しかし体は無傷で、魔道の徒の多い東部に運ばれ、原因不明の仮死状態の治療を王城で受けていたという。
「飛竜が貴様に馴染むまで、マトモに動くことはできないそうだ。せいぜい束の間の休暇でも謳歌するといい」
「……は?」
休暇……? と、わけがわからず首を傾げる。
「君は本日付で、私の下で監視生活兼、表向きは教会系列での雑用に従事していただきます。住居は東部で用意しますので、西部に帰ることは諦めて下さい」
「――は?」
「本当は『王属』に迎えたかったのだがな……『子供攫い』の疑いなど、一度でもかけられた者には、他の要職を与えることすら叶わん、と内々で煩くてな」
国王はかなり不服そうだが、完全に青年を置いて、色々何か話が進んでいる。さすがに嫌な表情を浮かべずにはいられない。
何故かそこで、少女が絶妙なタイミングで話を補いに入った。
「このヒトとさえ一緒にいれば、ライザ、今まで通りに普通に暮らしていいって……凄く嫌だけど、トラスティが頑張って、そうしてくれたの」
青年は一度、国賊である嫌疑をかけられている。その上に、多くの者を傷付けた飛竜を身の内に取り込んでいる。そんな化け物を庇うためにはそれしかなかったと、国王の苦渋の采配を伝える。
「凄く嫌って、ミリアさんは本当に、裏表のない良い方ですね」
一国の王をも呼び捨てにする少女に、国王は苦い顔、祭祀は楽しげに、後ろに控えているのだった。
まだ本調子ではない青年を、少女と二人にしてくれるように、多忙な国王はすぐに退室していった。祭祀も共に、バカな言葉を残していった。
「しかしいやぁ、ライザ君の監視というおかげで、私も晴れてまた東部に戻れますねー」
「……は?」
「我が妃の妹になど手を出すからだ。全く、私が信頼する者はどうしてこう、世知への配慮に欠けているのか……」
それは暗に、青年のことも含んでいるらしい。反応する気力の無かった青年は、フォローも無く黙って国王達を見送る。
そして真っ先に、ベッドの傍らに座っている少女に、全ての気がかりを一言で尋ねた青年だった。
「……あれから、どうなったんだ?」
「うん。リーザと飛竜は関係なくて、リーザ・ドレイクは行方不明でライザも関係ない他人だって、表向きにはなっちゃったのは……トラスティが言った通りなんだけど」
その名を口にした少女は、じわりと目端に涙を浮かべながら、他の事柄の説明を続ける。
「ヴァルトとハーピアは、リミットの所にいるの……二人共、難癖つけられたら嫌だから里に戻る気はない、ディレステアで一から頑張ろうって、そう言ってた」
「……――」
ということは、と、少女をまっすぐ見つめる。常に悲しげな顔をしている少女は少し誇らしげに、小さく微笑んでいた。
「二人が、和平後の移住者第一号だよ。と言っても本当なら、ディレステアに住んでる化け物がゾレンに、ゾレンに住んでる人間がディレステアになるべく行くようにって条件なのにって、トラスティは難しい顔をしてたけど……」
「……――……」
青年は、隠し切れない安堵を浮かべる。
青年がずっと闘ってきた仕事……「五色のケモノ」として父から受け継いだ業に、ようやく終止符をうつことができたのだと。
「デュラはずっと……第五峠で、まだ眠りについたままみたい」
「……」
「デュラを利用したあのヒトは、騎士団長に連れていかれた。多分生きて帰ることはないって、トラスティは言ってた」
一つ一つを、少女はあえて、淡々と説明を続けていた。
「わたしは……ヘルシャ大使からあの盾をもらって、第一峠は卒業で、東部に住むことになった……ら、いいな、って」
「――へ?」
ちらりと少女は、無表情でも、はにかむように青年を見つめる。
「……わたし……東部に来ちゃ、ダメ? ライザ……」
「……――」
それは紛れも無く、少女が何処に来たいかは明白だった。
「わたし……ライザと一緒に、生きたい……」
青年は答える前に、ただ勢いで少女を抱き寄せたのだった。
看病してくれる少女が少しの間退室し、今まで見たことのない部屋で、一人でフウ、と……青年が細く、息をついた時のことだった。
じわりと。
赤い右腕が発し、胸の奥に伝わる震えに、不意に青年は息を飲んだ。
「ぁっ――」
胸を右腕で強く掴み、全身に力を入れるように体を折り曲げる。
その赤い鼓動を一人、全身を汗ばませて、呼吸を止めて必死に堪える。
聴こえるのは、ただ懐かしい山奥の里の、仲間達の声。
――ちょっとライザ! リーザは何処よ、隠さないで教えて!
――アイツよりによってまた、おれら直属の鳥を喰いよった!
もう戻らない誰かを探す、痛いだけの記憶。きっと現在、仲間達も同じように痛みを感じているだろう。
それでもこれは、青年が一人で堪えるしかない咎だった。
右腕に封じられても、気を抜けば全身を侵すだろう誰かの記憶。それを全て受け入れてしまえば、その時はおそらく、青年も赤い獣と化する。
「……ああ……俺は……――許せない、んだ……――」
その痛みに名前をつけるならば。
それはただ純粋に赤い、憎悪という「意味」。内なる獣の消えない呼び声。
後に英雄と呼ばれる青年を戦いに導く禍が、ここから始まる。
+++++
後篇・結
それで、結局――と。「神」を讃える祭儀の場、厳正な教会同盟の一角で。
「ライザ・ドールドは、国賊ではないのかのう?」
法治国家ゾレンで行う、証言の真偽を追求する魔道審問。それを受ける一人の祭祀に、笑顔ながら苛立ちを隠し切れない声の老人が、何度目かの問いを口にした。
「『子供攫い』を名乗った、リーザ・ドレイクとの関係については?」
「いいえ、祭祀長殿。彼はそのような男は知らない、とずっと同様に申し立てております」
仮にも祭祀長たる司教が用意した審問の場では、偽りを述べれば必ずそれは、儀式の滞りとして検知される。そのため魔道審問こそが、ゾレンにおける裁判の要と言えた。
「ディレステアとの和平交渉の場を、大きく乱した赤い獣は、ライザ・ドールドの使役する飛竜の暴走と言うが。現在彼はどうした状態なのかのう。最強の獣たる力の暴徒など、決して生み出すわけにはいかぬよのう?」
「はい。確かに暴徒たる飛竜が常に彼を脅かしております。しかし私が監視を始めてから、顕在化したことは一度もない程に、封印が行き届いております」
何一つ祭祀は、嘘をついたつもりはないのだ。元来の二重人格に近い性質が手伝い、こうした審問を非常に得意とする手練れでもある。
この祭祀を国賊疑いの男の監視者とした国王に、祭祀長はただ苦い顔だ。引き続き祭祀長からは、厳重な監視を申し付けるしかない。
――そんな風に、今回もまた訊かれました、と。
定時報告の内容を、監視対象にわざわざ説明する祭祀に、毎度の如く銀色の髪の男は呆れ顔をするのだった。
「アンタは結局、二重スパイなのか? それとも三重?」
「失礼な。私はいつだって、国王様一筋ですよ」
ようやく慣れてきた新居。気候の調節が山奥の丸木小屋より良く、袖のない黒衣でも男は一年を過ごせる。木造でも石と鋼を密に使い建てられた家で文明的な王都での生活は、既に二年と半ばに近付いていた。
「幸いにも、私はライザ君から直接に、リーザ君なんて名前をきいたことが無いのは本当ですし。あのクソジジイはリーザ君が飛竜だと知りませんから、これ以上難癖はつけさせません」
「……だから、俺は……そんな奴は知らないって」
男の双子であった飛竜。ごく一部の者しか知らない長い嘘を、今も男は硬く守り続ける。それが意外に功を奏したことを、こうして定時報告の度に聞かされるのだった。
「それにしても本当に、ライザ君はよく自分を保っていますね。最初は正直、一年もたないかと思ってたんですけどねぇ」
「それで俺は、アンタとはまだ同居しなくちゃいけないのか?」
「当然です。それが飛竜を暴走させた君への罰ですから」
……と、露骨に不服な顔を向けるが、祭祀は心から楽しげに笑った。
「まーまー。最低月イチは旅行に出させてもらいますから」
実に不真面目な監視者に、男はいつも軽く息をつくのだった。
教会関係の雑用――下働きに近い扱いを受けている男は、とても頑強な体を持つ化け物だ。一時期、西部で暗躍した「悪魔祓い」とは違う、ある意味真の悪魔退治に近い仕事を、教会からは度々回されていた。
「ふーん。東部ではそんなにも、エイラからの侵入者が何気に多いんやなぁ。通行証もないんによーやるな、『純血』の奴らも」
男を訪ねてきた同郷者に、久しぶりに会った。玄関の横に備え付けの、外路に面した小さな円卓を挟んで、互いの近況を語り合う。
「でもそんなん、国境担当の軍部の仕事やろ? ヒドイ時には西部まで行ってるゆーやんけ、オマエ」
「ああ、おかげで、すっかり軍部とは険悪だ。でも獣に擬態して侵入する奴らは俺が一番よく視つけられるから、不審な反応があった国境付近は、一通り調査に行かされる」
「なるほどなぁー。見つけるだけ見つけて、後は軍部に任せろっちゅーことかー。おもろないなー、それ」
面白い面白くないよりも、と、男はふうと溜息をつく。
「家を留守にすることが多いのが、嫌だな」
「何やねん、このマイホーム男が! くうう、ハーピアと言いオマエといい、おれの周りはどーしてこう、幸せモンばっかりやねん!!」
「……」
何やら間違ったスイッチの入った悪友に、男も苦笑混じりに気が付く。
「大体なぁ、リミットとハーピアが毎日ラブラブ過ぎやねん! 頼むから半同居のおれに、少しでええから気を使ってくれ!」
「……それは、邪魔してるヴァルトが、逆に罪だろ」
親戚だからって甘え過ぎだ、と厳しくさらりと伝える。
「ディレステアの通商庁で私室も用意されてるんだろ? 何でそっちより、ハーピア達の方で寝泊まりするんだ?」
悪友は今では、ディレステアとザインの物流を管轄する要職に就く。時には揉め事にも介入して戦う長官に任命されているという。
「だってなぁ、元々あんまり言葉も通じへんし。第二峠、人間多過ぎやねんて。クランもよう、あないなザワザワしとる所に常駐して頑張っとると思うわ」
ああ、そうそう、と。その男の名前が出たことで思い出した件を、悪友は楽しげに話し始めた。
「大きな声では言えんけど、こないだ、レインさんに会うたで。最近極秘で、第二峠に一時滞在しとったんやけど……びっくりやで! 何と――一児の母になってもーた!」
不意の知らせに男は、思わず息を飲み――
「それ……本当か?」
握りしめた腕から、胸に赤い鼓動が走りかけたが、それは悪くない戦慄だった。
「よくあのヒトに……子供なんて持てたな」
その相手がどれだけ虚弱体質か、男は誰より知っていた。
「そらもう、クランとレインさん両方の頑張りやで。ライザに伝えてくれ言われたんやけど……もう、自分の気になること以外『千里眼』は使うてへんから、心配するなって笑ってはったわ」
「……――」
それで何とか、子供を産める体力を取り戻したらしい。大きな胸のつかえを撫で下ろすことができた男だった。
「ライザのこともよー知っとったで。何や知らんけど、飛竜に負けたらあかんでとか、これもそういや伝えてくれ言われたな。相変わらずどころか、普段使うてへん『千里眼』は、使う時には絶好調みたいやな」
……それは怖い話だな、と、一瞬男は肩をすくめる。
「普段はクランが、少ない休暇の度にザインに通うてるみたいやけどなぁ。レインさんも本当頑固やな、もう第二峠に住んでまえばいーのになぁ」
「……自分はゾレンの罪人だからって、そう言ってるんだろ?」
「そうそう。ディレステアでもレインさんは、第五峠の占い師エア・フィシェルとして、有名やから行けへんやろうしな。もう『子供狩り』は、完全に廃止されたんになぁ」
「子供攫い」としてその同郷の女性は、過去に公開処刑を施行されかけた。それならこのまま死んだことになっている方が、無難ではあった。
「俺も未だに監視されてるからな……『子供攫い』の国賊指定だけは、トラスティもどうにもできないらしい」
「っつーても、ライザは結局違うかったやろ?」
「だからこうして、生活はできてる」
面白くなさそうに言う男に、悪友もつまらなさげに息をついた。
「国王サンも問題続きやな。第五峠テロ事件とか、それにほら、あれやろ? 少し前、王妃さんが亡くなりはったんやろ?」
「…………」
それについては男も、大きく心を痛めていた出来事だった。
「まだ王子も小さいのに……本当に急だった」
男は数える程しか謁見したことがないが、王妃は非常に我が強く、国王をばりばり引っ張っるようなタイプだった。それが急逝して後、国王はこれまでの物憂げに加え、トゲトゲが進行しているように視えた。
「人間のディレステア移住もなかなか進まないと、最近、よく苛々してる」
「そーやな。おれらもヒトのこと言えんけど、ディレステアから出る気は今んとこないしな」
人間と化け物の分離政策を相変わらず進める国王には、腹心の配下が大きく増えていない。ただ疲れだけが溜まっているようだった。
話題が話題のためか、少し空気がしんみりしたその時に。
「……あ」
ちょうど噂をした頃合いに、道の向こうから元気に駆けてくる、とても幼い人影に男が表情を和らげた。
「何や何や? あの貴賓風の幼児の坊ちゃんは何者や?」
「ああ。だから――トラスティの王子だ」
は!? と。その有り得なさに未だに免疫のない悪友が絶句する。
「おじさん!! こんにちは!!」
「お、おじさんて、事もあろーに、オマエ……」
玄関先にいた男に嬉しげに飛びついた幼児は、まだ三歳を軽く過ぎたばかりの、れっきとした唯一の王子だ。
「あかちゃんは!? おばさんはどこ!!?」
無愛想な男は珍しく僅かに微笑み、すぐに扉を開けたのだった。
……なんっちゅーこっちゃ、と。
家内に招き入れられてから、悪友が痛く不服気に男を睨む。
「まさかレインさんだけやのーて、オマエにまで、既に子供ができとるやなんて……」
「……だから、留守が多いのが嫌だって言ったろ」
「ああああ! 今やからわかる、レインさんの妙に幸せげで、そしておれを哀れむような微笑みの意味がぁぁ!!」
「それは多分……オマエの妄想だと思う」
同い年の子供がいるのは嬉しかった。男は台所で、食卓に突っ伏す悪友にお茶を用意する。隣室に駆け込んでいった王子と、そこにいる二人……生まれて間もない青い目の息子と青い目の連れ合いに、知らず口元を綻ばせる。
「トラスティが忙しいから、キルは寂しがってうちに来るんだ。一般の民家に出入りするのは褒められたことじゃないが、王妃も亡くなったばかりだし、優しくしてやってくれ」
珍しく多弁になってしまう男は、その王子がただ不憫で、とても気にかかっていた。
「オマエ、何ちゅーか……相変わらず、面倒見えーなぁ」
うるうると悪友は、温かいお茶を両手で器を抱えて飲み干す。
「くぅぅ、えーなぁ、まさに順風満帆って感じで」
「……」
やっかみをこぼす相手に、苦く笑って男は言葉を呑み込む。
――本当に、ライザ君はよく自分を保っていますね。
王子が来る時には大抵、留守にしている王子の世話係――王妃の妹と共に、遊びに出ている不真面目な祭祀の声が、脳裏に響く。
祭祀が定時報告している、男の中に暴徒の飛竜がいるという言葉は、全くの真実だった。
右腕から発し、時には男の心臓を止めかける程の赤い鼓動は、死線から帰った代償と思えば安いものだが、困るのは本当に――その狂える赤い獣は、常に外に出たがっている衝動だった。
――正直、一年もたないかと思ってたんですけどねぇ。
男は一度も、この飛竜を外に出したことはない。
戦う時は相変わらず血を炎と化し、体の頑強さと相手の力を「無意味」にする特技で、大概の化け物とは渡り合えた。
だから、使わないつもりならいっそ本気で震源の右腕を切らないか、国王からは度々打診された状態だった。
男はただ、国王に「NO」を答え続ける。
一度は確実に潰された男の心臓は、頑強となった体でも、その時貫かれた部位だけは脆いままで。右腕の赤い鼓動は、その弱点を守っている気がした。
まずもって、双子だったものを手放す気は男には無かった。
たとえそれが、度々男の憎悪を呼び起こして、脆い心臓を止めかけたとしても。
悪友と王子が帰った後、改めて連れ合いと子供のいる部屋に入る。
質素な揺り籠の横の、肘掛け椅子で連れ合いはうたた寝をしていた。男は向かい側の、背もたれのない椅子に腰かける。
「…………」
僅かに生えた髪は男と同じ銀色で、目の色は母親似の小さな子供。「力」はどうやら母親寄りに視えるが、男の彩のない眼をもってしても、どちらと断言できない曖昧さがあった。
そもそも確実に、何かの「力」はあるにも関わらず、その心を決められないような不定さ。それが普通の化け物の子供とは違い、ずっと気にかかっていた男だった。
「混血と混血の子供は……いったい、何になるんだ?」
まだ笑う時期でもないというが、幼い息子の悲しげな表情は母親によく似ている。しかし顔形は男にそっくりだ、と連れ合いはいつも口にしている。
「……じゃあ、リーザにもそっくりになるかな」
じわりと――その双子を少し思い出すだけで、すぐに現れる赤い鼓動を、胸を掴んだ男が黙って抑える。
この子供はそうした時は必ず、何かに怯えるように泣き出してしまう。
「……あれ……ライザ……?」
せっかく休んでいた連れ合いも、目を覚ましてしまった。
それ自体は、申し訳なくもよくあることだ。
「――どうしたんだ? ミリア」
今回は何故か、連れ合いは普段以上に悲しそうに――目端に涙まで溜め、泣き出していた子供を揺り籠から抱き上げてあやす。ただぎゅっと、その温もりを確かめるように強く抱きしめ、立ち尽くしていた。
「わからない……きっとまた、嫌な夢を見ただけ……」
「…………」
どうしていつも、悲しそうなのか、と。
男が初めて連れ合いに会った時の思いは、変わらず続く不思議の一つだった。
出会った当時には、連れ合いは様々な逆境の中で生きていた。けれど現在、こうしてささやかながら文句無く幸せと呼べる生活を得た後でも、その悲しみの色は変わらなかった。
ただ無愛想なわけではなく、確実に連れ合いは悲しそうで。
男を赤い鼓動が襲う時に、子供が必ず泣くように。それには理由があるように思えてならなかった。
……同じ青い目を持った連れ合いや子供には、いったい何が見えているのだろうと。
「ごめんね――……ライザ……」
「――?」
子供を抱き締めたまま連れ合いは、立ち上がった男の胸にもたれかかり……何故かそれだけ、小さく口にしたのだった。
+++++
男は何故か、難しい子供に昔から縁があるらしい。
「安心して下さい。確かに少し特別な感覚を持った子供ですが、この分ならヒト並みの自我は、その内持てるようになるでしょう」
ふう、と安堵の息をつく。旅用の外套を羽織ったままの男に、旧知の「魔女」はふふふ、と、まるで母親のような顔で笑いかけた。
この医療施設の集まる第五峠に、今日は男は、三歳になった息子だけを連れて来ていた。
「五感が鋭過ぎるようなので、一番柔らかい刺激で、他の感覚をまめに邪魔してあげてもいいかもしれません。スキンシップが一番でしょうね――自分と周りの境も、そこから知るでしょう」
「そうなのか……確かにいつも、ヒトに抱っこされてると、一番落ち着いてたような気はするな」
白い部屋で白衣を着て、見た目は人間の女医のような魔女。魔女曰く、幼い息子は周囲と自身の区別が難しい程に感覚が鋭いという。
三歳になってもあまり笑わず、逆に言葉や行動は周囲の大人が驚く程早い息子。幼児にしては的確で、とにかく全く子供らしくない息子を、常々心配していた男だった。
しかも何故か息子は、男以外には大体大人しく従順なのに、父親である男には頑固な面を見せることが多かった。
それについて、男が魔女に尋ねると、
「それはミリアさんを映しているのでしょう。ライザさんには甘えられるということです。一番長く一緒にいる相手ですから、ミリアさんの感性や心が、このコの自我の基盤になることは避けられません」
更に言えば、記憶に近いものまで共有している可能性もあると、魔女はキョトンとした息子の銀色の髪を撫でながら口にした。
「見た目はライザさんそのものですけどね。外的な面、意志や行動指針は、ライザさんを真似るようになりそうですね」
「……そんなもんなのか?」
「こういう敏感なコは、自分に合うものをすぐに取り入れます。なので身の振り方には気をつけて下さいよ、お父さん」
……、と困ったように黙った所で、魔女も矛先を変えた。
「私も近い年の娘達がいるので、皆でいつか、遊ばせたいですね」
「それって――あの事件の時の……」
「ええ。私は元々、後継者探しにこの地まで来ましたが、あれ以来すっかりみんなのお母さんです」
ちょうどこの息子が生まれた頃に、第五峠では、中立地帯で今だ休戦中にも関わらず、ディレステアにゾレンの者が侵入する事変があった。それで親を亡くした女の子達を魔女は引き取り、今では王女付きになったような子供もいるという。
「……それで、いい後継ぎは見つかりそうなのか?」
「魔女」はどのような種であれ、適性さえあれば継げるらしい。
「それがさっぱり。でもまぁ、可愛いから良いのです」
元々ディレステア王妃の友人である魔女は、そうして王妃と共に第五峠に居ついていた。
せっかく第五峠に来たついでに、男はずっと気になっていたことを、魔女に尋ねる。
「王妃は最近はどうだ? 元気にされてるのか?」
「ええ、相変わらずです。ディレステア王妃となられてからも、アヴィス王女が生まれた後も、ずっとこの第五峠におられます」
「……」
議会と王家の両立治国を行うディレステアでは、代々女系の王家と議会の統治者が婚姻を行い、国を守るのが習しになっている。
「専属の護衛は騎士団長から私へと変わりました。しかし私はアヴィス王女を主に守ってほしい、と王妃からは申しつかっています」
「……本当に相変わらず、気丈な人間だな、あのヒトも」
はい、と魔女は、男と同じで苦笑するように頷いた。
話が暗めの流れになった途端に、息子はじんわり、青い目の端に涙を浮かべる。抱き上げて膝に乗せて、男は話を続ける。
「それで――デュラ・ユークの方はどうだ?」
「ええ。身分は一応何とかなったのですが、記憶はほぼ真っ白ですね。このコよりも赤ん坊のような状態ですから、気を長く持ちながら見守っていかなければ」
「……そうか」
長くこの峠で療養する少年、連れ合いの実の弟は、少し前に長い眠りから目を覚ましていた。
そちらも中々前途は多難な様子に、男は深く息をつきながら……そのまま息子を抱えて、第五峠を後にしたのだった。
第五峠から王都まで、子供連れでは一日といった所だ。
海沿いを歩く男の外套内の、腕の中で大人しくする息子は、魔女の言う通りに、人肌の居心地が良いようだった。
「それならオマエも、遠慮せずに甘えたらいいのにな」
「……」
どちらの親にも、息子は自分からはあまり寄って来ない。放っておいてほしいのかと思いかけていた男は、頭をわしゃわしゃ撫でながら歩みを続ける。
銀色の髪で青い目の息子は、ぽつりと――小さな拙い声を出した。
「……父さんは、いたくて。母さんは――こわいゆめをみるよ」
子供は腕を伸ばし、男の首にぎゅっ、としがみつく。
「どうして……父さんは、いたいの?」
第五峠を訪れ、様々な旧い痛みを思い出した男。それをそっくり映すように、じんわりした目で父親を見上げる。
「…………」
悲しげな表情が多いせいか、息子は男の双子には似ていなく見える。それでも同じ顔をした息子に、男は、誰にも言ったことのない思いを不意に口にした。
「……俺があの時、憎しみに駆られたりしなければ。こうして、アイツを失くして……オマエ達を怖がらせる獣を、宿すことはなかったかもしれない」
それは男が、内なる獣の呼び声に初めて耳を貸し、己が殺意の返り討ちにあった日への思いで――
その時貫かれた心臓に赤い鼓動が起こる度、顔を暗くする息子に、静かに伝える。
「俺は多分、逃げるべきだった。熱くなるなと言われてたのに、アイツの言うことをきかなかったから……そのせいで、アイツがもういないのが、今も許せないんだ」
「…………」
遠い日の双子の声を、今も男は忘れることができない。
――アニキは熱くなんなよ。隙だらけになる。
もしもその時、双子を蒼く小さな獣として引き止めていれば。男は双子と共に戦い、双子が消えることはなかったのではないか。
現実的にはそれは難しかったが、その後せめて、男が戦っていなければ。
無意味な感傷とわかりつつも、いつも男の心臓を止めかける赤い鼓動は、決して消えることはなかった。
何も話がわかったはずのない幼い息子が、その時、心から悲しそうな顔を浮かべた。まるでその母が見た、母だけが知る真実を映すように。
「……にげてたら……父さんは、いなくなったよ」
その空ろな夢を、長く留めることができない母の代わりに。常に悲しげな母を映して、男に一つの答を伝える。
「そうすれば……だれもなくさない。なにもうばわない。でも…………母さんは、ひとりになった」
「……?」
男の赤い鼓動を、幼い息子は共に感じている。それだけでなく、母を悲しげにする夢をも我が事と観ている息子を、男は知る由もない。
「それで……これで、父さんはひとりになった……」
ぐすりと子供は、男にしがみつく両手を強めてポロポロと涙し、
「だから……ごめんなさい……」
「……――……?」
男に苦しみの生をもたらす者達の、この先は謝ることができない嘆き。それを何の自覚も無く、悲しい夢の通りに口にした。
男は正直、ほとんどわけがわからないままだった。
「……謝ることなんて、何もないだろ」
泣きながらウトウトし始めた子供を、あやすように抱き直す。小さな背中を温めるようにさすって撫でて、心からの幸せを感じて笑う。
「オマエ達とこうして、ここにいられる時間を貰えて……俺は本当に、良かったんだから」
それは、何を捨てても手に入れる価値のあったもので。
そのためにこの赤い鼓動が必要であるなら、それすら既に、男は受け入れた上でのこれまでだった。
「これがアイツの贈り物なら。少しくらいオマケがあっても、俺はこれで良かったんだ」
許せないと感じる赤い鼓動も、これからの男を苦しめ続ける獣の呼び声も――ずっとそのままで在り続けながら。
痛みも喜びも、全てを呑み込む男のクセこそ、穏やかなこの日々を続けていられる最大の理由だった。
間近に触れる男の穏やかさを映すように、やがて子供は拙く、安らかな顔で眠りに落ちていった。
「山道に入る前に、今夜はもうここで休むか」
陽も沈み切らず、まだまだ歩く余力はあったが、あえて腰を下ろす。山育ちの男には、海辺の一泊は、ささやかに新鮮な場面なのだ。
「危ない気配もなさそうだし……海の色も、いい感じだし」
特に好きなのは、その連れ合いと初めて出会った時のような、潮騒の静かな唄声だった。
更にもう一つ、しばらく忘れていた好きだったもの。その道具を片手に、男は子供を膝の上で寝かせ、平らな石の岸壁に座る。
「ホントにオマエは小食だからな。沢山はいらないから、良い魚が釣れるといいんだけど」
単身で仕事に出かける時は、思い付きすらしなかった趣味。久しぶり過ぎて慣れない手付きで、男は釣りの仕掛けを作っていく。
そうして、夕闇の薄暗い岸壁で、思う存分潮騒の唄を聞く。
幼い子供を膝に、穏やかな無表情で釣り糸を垂らし続ける。
不意に――そんな男に近い何処かで。
同じ岸壁の上、寂しげに海面に足を投げ出して座る誰かがそこにいる、と突然男は感じた。
「誰か、いるのか?」
思わず声を出したものの、不思議と、辺りを見回す気にはならなかった。
その不思議な、一度も会ったことのない気配。しかしそれは、誰よりよく知った色のはず、と男の眼には視えていた。
「……君は、誰だ?」
―……――……―
ここに有り得るはずのない誰か。それは、子供を膝に座る男をじっと見ている。
その内不意に、口にしたこと――男は、鎖でがんじがらめだ、と誰かは言った。
もしもこの膝の子供が、鎖に観えているとするなら。
男が守ろうとしてきたもの、その全てが鎖だった。赤い獣を縛る男は微笑む。
その拙い誰かは、迷いだらけといった風体で男に尋ねた。
……男はどうして、戦うのかと。
そうだな、と男は――未だに定見や志の拙い己に、苦く笑う。
「戦うというよりも……俺は、守ろうとしてきただけだった」
男の答に、それは不服らしい。それでもこれ以上は言い訳になるように感じ、次の一言以外、全ての言葉を呑み込む。
「理由なんて――ない方がいいかもしれない」
それはおそらく、男が闘い続けた果てに在った誰かで。
理由という鎖に縛られて冷え切っていく獣が、最後に残せた希みだった。
「……君に会えて、良かった」
だからそれが……消えない憎悪と鎖への、男の答だった。
雑種化け物譚 A -了-
始:赤い獣
潮騒の唄が聴こえた気がして。男は長い夢から目を覚ました。
「お目覚めになられましたか――ライザ殿」
「……?」
見覚えのない一室。そこにいた顔見知りの軍人。
ここは? と男は、胡乱な頭で尋ねる。
「第六峠のゾレン大使館です。ライザ殿のおかげで……我々は大使館を奪回することができました」
「……――……」
そこで男は……これが、ある終わりの先である現実を知る。
男は全てを終わらせるために、たった一人でそこへ来ていた。
――『解放』しなさい。アナタの中の赤い獣を。
身の内に巣食う憎悪を解き放つ時、男は自らを失うだろう。それを恐れて、男は赤い鼓動を封じ続けた……そのはずだった。
――アナタにとっては、『解放』が全ての終わり。
しかしその後に待っていたのは、見知らぬ部屋でのこの冷たい目覚め。
――けれど『解放』こそ、本当は全ての始まり。
世界とは、終わってからの方が長い。切なる現実を男は知る。
「ライザ殿……今後も我々と、戦っていただけるのですか?」
「……――……」
言葉を呑んだ男はようやく――その幾重もの棘の鎖を思い出す。
「俺は……そのために、ここに来たんだ……――」
生涯を戦いの中で過ごす男の、獣を縛る長い嘘が再び始まる。
Czero CPA -THE END-
FIRST UPDATE:2015.1.25
オマケ❖カップル掌編集・下
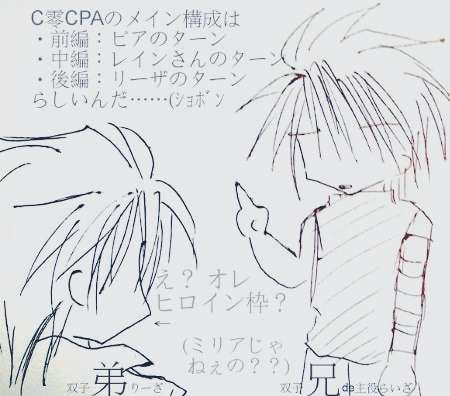
「上」では「①クランとエア」「②騎士団長と第二王女」「③祭祀と獣使い」を収録しています。
④リミットとハーピア
・本編より数年後
⑤リーザとピア
・本編の前篇中
⑥英雄ライザ
・続編C零CPR直前
④リミットとハーピア
鳥になった少年は、空に溶けていくことを望む。
昔から透明であることだけが、少年の良い所だったのだから。
+++++
「ねぇリミット、今日のご飯は美味しい? 今日はねぇ、いいお野菜が手に入ったの♪」
「…………」
黙々と家主の手料理に箸を進めながら、白い髪の鳥頭の青年は力強く頷く。
「何やねん、それきくの何度目やねんハーピア。リミットもな、一々全部大真面目に頷かんでえーんやで?」
「だって貧乏舌のヴァルトと違って、リミットが食べてくれる時は本当に美味しいってことなんだもん。ヴァルトの手料理なんて見向きもしないじゃない、ねぇ?」
「それはおれのせいやない、全然違う要因混ざっとるから!」
よく食事を世話になりにくるまた従兄弟と、家主は今日も煩く喋る。気難しげな青年の前で実に騒がしい。
「あ、おかわり? 今日はねぇ、ご飯の水加減も、いつもより1ミリ気を使ってみたの!」
にこにこ嬉しそうな家主が、何も言わない青年から茶碗をひったくる。強気な善意は全く無邪気で、その信頼の強さだけが青年を地上に繫ぎとめる。
「……ありがとう。ハーピアの気持ち、いつも、嬉しい」
この家主にだけは、青年は遠慮なく透き通った笑顔を見せる。それでますます、家主のテンションは上がる一方なのだった。
「全く……本当、自分がない奴っちゃなー」
居候その二に近い、透明になれない男は、今日も一人ごちるしかない。
-了-
⑤リーザとピア
「あたし達の父さんは、竜と言われる化け物だった」
ある人間の女の素性を、女の数少ない友人だった「千里眼」から、飛竜の息子はザイン山上の第一峠で話されていた。
奇しくも同じ話を、ザインとゾレンの境に当たる中腹の山小屋で、その双子の弟である青年と人間の女は交わしていた。
「竜って……あの、竜かよ?」
山小屋から少し離れた泉で、月の光の下、人間の女は身を守る鎧を外して沐浴をしている。薄い肌着は身につけたままだが、まるで心の鎧を外したように青年に笑いかける。
「うん、あの竜。リーザみたいなケダモノじゃなくて、自然と一つのあの竜だよ」
ケダモノってゆーな。と、獣寄りの竜――飛竜そのものである青年は、目のやり場に困り、そっぽを向きながら答える。近くの木にもたれて女から目を逸らしつつ、視界の端の、水の滴る女の姿に呼吸を飲み込む。
だって、と女は、にへらと笑いながら言う。
「ライザなんてまだ、ぷっつん来たら暴走しちゃうぞ、って自覚してそうなのにな」
青年が最も不服だったのは、話の内容にではない。
「……そんなケダモノの前で、無防備にしてんなよ、あんたは」
そうしたことを話しながら、全く青年を警戒せずに鎧まで外し、反応に困る緩い笑顔を見せる女が理解できない。そして――
「随分あんた……アニキのこと、よく見てんだな」
女の口から最近よく、青年の双子の名前が出ることが、何よりも気に食わなかった。
「リーザ、下手したらケダモノになっちゃいそうなんだもの。気をつけた方がいいよ?」
「――は?」
「自分で気付いてないのが一番怖いよねぇ。リーザは基本冷静に見えて、ライザよりホントは冷静じゃなく見えるな、あたし」
人間の女は、曖昧な虫の知らせという形で、現状を的確に把握する直感の才能を持っていた。不服そうな青年が心配、といった顔で、呆れたようにまた笑う。
「?」
「ほら、全然気付いてない! 仮にも十八年隠れて生きるって、どんだけ辛いか――たった五年、隠れてたあたしが言うのにさ?」
双子の兄を守るために、青年は生まれた時から存在を隠されて育った。しかしそんなことくらい、とっくに受け入れて生きていたつもりだった。
女はただ辛そうに、青年からフっと目を逸らし――
「……リーザが辛いと、あたしも痛い。リーザは初めて……あたしが『子供攫い』なこと、怒ってくれたヒトだから――」
この場に来る前に、命の次に大切な通行証まで貸し出した、女の直向きな心をそこで口にした。
「あたしは……リーザになら、何をしても助けになりたい」
不意に赤面した青年は……自身の負けだけを、衝動的に悟る。
「……オレは……」
月の下で女の青い目が、切なげに潤む。赤く大きな鼓動を抱え、蒼い己を忘れて告げる。
「オレは、ただ――……あんたが、ほしい」
+++++
それは本当に、青年にとって、負けたとしか言いようの無い告白だった。
「……へ?」
ポカン、と目を丸くして、鈍い女が足首までつかった泉で立ち尽くしている。
わけがわからない。といった青い目で青年を見つめてくるので、青年はある意味、不思議な覚悟が決まった。
「――だから。オレはあんたがほしい」
「……え?」
「何でもしてくれるなら、あんたをくれ。オレはあんたと……共に生きたい」
「え……って、それって……」
曇り無き眼差しと言葉に、女はようやく、何が起きているかを悟る。
水上でばっと体を竦め、最大レベルで慌て始めた。
動揺した女はばしゃばしゃと、泉の中へと大きく後ずさった。
「そ――そーいうことじゃなくてっ、いやなくないけど違うの、リーザ絶対何か誤解してるっていうか何ていうか!!」
もたれた木から泉の方に青年は向き直る。女がよく見えるように虚勢で顔を上げながら、ふんぞり返るように水際まで行く。
「嫌ならそれだけ言えよ。アニキが気になるならオレも考える」
「違うのそれ絶対誤解、っていうか何それ何処からそんな話になってたの、ええぇぇっっ!!?」
慌て過ぎて全身を硬直させ、女はひたすら真っ赤になっている。
青年は思わず顔が緩み、女が落ち着くまで黙って待とう、と思えるくらいになった。
この青白い月夜に、青年を後押ししたのはひとえに、双子の兄から抜け駆けできるなら今、という思いだ。
そうして、本当に欲しいものは兄に気兼ねせずに手に入れてきた。だから兄とも、上手くやって来れたのかもしれない。
マジメな顔で静かに女を見つめる青年に、女は何度か深く息を吸って、何を言うべきかを必死に考え込んでいるようだった。
「…………」
口を引き結んで俯き、憂いげな顔を続ける女。良い返事は期待できないのかと、青年も憂鬱になりかけた頃だった。
「あ……あのね、リーザ……」
「……?」
「何て言えばいいか……あたし、全然わからなくって……」
そこで女は本当に、これ以上は言葉を続けられないと――
突然くしゃっと、両目に大粒の涙を滲ませながら顔を上げた。
「ホントならあたし……幸せ過ぎて、信じられない……」
両手を胸元で強く握り締めて、嗚咽混じりに、女は何とかそれだけ口にした。恥じらう赤面の破壊力が凄まじかった。
青年も今更頭が沸騰を始め、顔が激しく赤くなった。黙ったままで息を吸い直すと、立ちすくむ女に思い切って更に近づく。
俯く女も今度は逃げない。両手を組むように縮こまって、硬く震えている華奢な体。この寒空の下なら当然だろう。
全身が熱い青年は、そのまま女の両腕ごと、冷たい体を包み込むように抱き締めていた。
……何で……? と。
無言の青年の腕の中で、女が尋ねる。これまで聞いたことのないような拙い声で、恐る恐る青年に問いかけている。
「リーザならいっぱい……いくらでもイイ人、いると思うよ……」
「……」
「わざわざあたしみたいなの……関わらなくたって……」
肩を震わせながら、女がきゅっと青年の服を掴んだ。鳥が停まったような感触だった。
竜の血をひきながら、ただの人間である女。それは実際、こんなにも弱々しい存在なのだと、化け物の青年は生々しく感じ取る。
「……『子供攫い』だよ? どう考えても……先行き暗いよ」
竜人である弟を、女は家族を守るため軍に差し出した。そして弟を取り戻すために始めた国賊活動を続けている。それで弟を取り戻せることはなくても、後にはひけない状態なのだと青年も知っていた。
「そんなの――先が無いのはお互い様だろ」
つい先程までの沐浴で、冷え切った女の体温が青年に移る。軽い体をひょいと抱えると、わっと慌てる女に構わず、猫を膝に乗せるようにして岸辺に座り、斜め向きの視線をじっと合わせた。
「……――」
横向きにもたれる女の体は、青年からじわじわ温められる。なすがままに座りながら、まだ両目に涙を浮かべ、まるで駄々っ子のような顔で青年の鋭い目を見つめる。
「オレもあんたも、この国で歓迎されないのは一緒だ」
「……」
背を抱えていた手を腰に下ろすと、少しびくっと驚きながら、女もまっすぐ見つめようとしてきた。
ずっと、涙目で戸惑っている。それでも確かに青年の温かさを求め、体の力を抜いて距離を縮めていた。恐る恐る青年の上着を掴み、懐に向かって俯く。
だから青年も、最早遠慮はなしに、女の肩に頭を置くようにして、小さな体を思う存分抱き寄せていた。
「でもオレは……あんたにそばにいてほしい。あんたがそれを、どう思ったとしても」
青年は、存在しない化け物。あり得ないものとして、自らを隠し続けた。しかし決して、己を卑しめることはなく生きてきた。その意味で言えば、青年を犠牲にした、と罪悪感を背負う兄こそが囚われ人だろう。
――アニキもピアもそうだけど……。
その兄と女は、何処かが似ている、と青年は感じた。
どちらもおそらく、何かに縛られ続けているところが。
「あたしは……」
どうしても女は、微笑むことができないままでいた。
「ほしいって……思っちゃってもいいのかな、あたし……」
それでもぎゅっと、青年の服を掴む両手の力が、女の素直な希みを映して余りあった。
「あんたはどうすれば……『子供攫い』をやめる?」
腕の力を緩めて、女の青い目をもう一度見つめる。
そして尋ねた青年に、女は何も口にすることができず――
代わりに、己の希みと青年の望みを合わせるように、互いの呼吸がそっと止まった。
そのまま静かに閉じられた瞼と、灰色の目が重ねられていった。
-了-
⑥英雄ライザ
その連れ合いは本当に頑固だ、と、連れ合いと短い旅へと出る度に男は思った。
「だから、本当に……危ないから、俺の仕事についてこなくていいんだぞ? ミリア」
「嫌。危ないなら尚更、ライザ一人で行かせるなんて嫌だもの」
連れ合いと暮らし始めた頃は、男は体が本調子でなく、危なげな所が多々あった。しかしその後は、それまで以上に頑強な化け物となっている。
「俺を殺せる奴なんて、もうそうそういないよ」
今では却って、連れ合いに何かあったら、という方が気になり、こうして仕事先に連れ歩くのは不本意でもあるのだった。
「大丈夫。わたしもわたしのことくらい守れるから」
水の力を司る宝の盾を、連れ合いは魔道の媒介としている。まさに鉄壁の守りを持つと考えて良く、それを貫ける相手はほとんどいないと男もわかってはいた。
「それに、こういう時しか二人にはなれないもの……期限さえなければ、もうずっと、お仕事してたっていいくらい」
彼らの家には常に、監視の名目による居候がいる。
連れ合いが難しい顔で見上げるのも無理がないことで、男も結局、二人旅という誘惑に負けて頷いてしまうのだった。
こうした二人旅は、連れ合いが身ごもるまでの間は何度となく続く。
危なげながらも大切な時間だったと、男は後に思い返す。
+++++
「――ライザ様? 何を考えてらっしゃるんですか?」
ふと、最近行動を共にしている若い娘の声で我に返った。
十年以上前の淡い記憶は、冷えた体の奥にすぐにしまわれていく。
気丈で聡明ながらまだ幼さも残る娘が、力強い赤い目で、護衛である男を横から覗き込む。男の腕に娘の長い金色の髪がさらりとかかる。
娘の傍らで黒装束に身を包む、常に覆面姿の付き人の少女も、心配げな赤い目で男をじっと見つめていた。
「……いや。何でもないよ――アディ、シヴァ」
懐かしさというよりは、呪わしさが先立つその地。「第四峠」に娘達と踏み入ってから、男の胸には赤い鼓動が絶えず、ともすれば意識を失いかねない強さで男を侵していた。
「ただ少し……昔を思い出しただけだ」
今回の男の役目は、ただ、この娘達を守り通すこと。それだけ男は自らに言い聞かせ続ける。
金髪の娘が朗らかな顔で、男の腕を両手で取りながら声を弾ませた。
「ねぇ、ライザ様はお母様のお友達だったんでしょう?」
「……あまり大きな声では言えないが、まぁ、そうだな」
苦笑う男に、娘は嫌味のない大人びた顔で微笑む。
「またお話して下さい。魔女のこと、王妃のこと……ライザ様達の、昔の尊い戦いの話を」
「……」
今では英雄と呼ばれている男を、娘達は心から信じるよう両側からしがみつき……男は久々に、少しだけ安らかに拙く笑った。
-了-
雑種化け物譚❖Cry/A. 完結篇
ここまで読んで下さりありがとうございました。
この話は星空文庫にUP済みの、Cry/シリーズ千族化け物譚・千族宝界録の過去話のC零CPAシリーズ完結篇です。
かなり暗いので完結篇の本作は不定期公開としています。ノベラボで既に全て掲載は終わっているので、本作の公開が終了していればweb版はノベラボをご覧下さい。
初稿:2014.8 最新改稿:2019.9
ノベラボC零A▼『雑種化け物譚❖A』:https://www.novelabo.com/books/6331/chapters
ノベラボC零R▼『雑種化け物譚』:https://www.novelabo.com/books/6333/chapters


