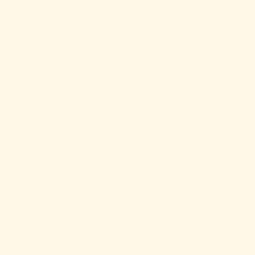額縁
わずかに開いた扉、その隙間から覗く闇が、クマのような身ごなしでこちらへと歩いてくる。連れ去られる人々。私はその成り行きを観察している。悲鳴を上げる者はいない……誰もが上の空で虚ろな表情のまま、クマによく似た闇に喰われていく。その光景はなんともうっとりさせられるものだ。ああ、私とよく似た志を持った者が、額縁というものを発明したのだろう……。
忘れ去られた廃駅にこそ可能性は潜んでいる。恐ろしく寒い冬の季節には、ぽつりぽつりと、淋しい駅に降り立つ者が現れる。その場景はまるで、ウツボカズラの罠を見ているかのようだ。心が凍り付いてしまった者にのみ分かる熱を発して、温かい光で包み込む。
この廃駅は時折泣いていることがある。ただ淋しさの穴を埋めるためだけに、近しい者たちを引き寄せるのだ。ああ!なんと甘美で扇情的な、蠱惑的な、神秘的な空間なのだろう。
陰鬱な冬にはこの廃駅に集まる者たちも多くなる。私は困っている。来客の一人を連れ去ってしまいたいという欲求に!私は廃駅から連れ出してきた者を手厚くもてなす。廃駅を支えている朽ちかけの木の柱の色をしたマグに、腹の底から沸き上がる重苦しい欲望の色をしたコーヒー。満天の星から注がれるミルクと、甘い三日月のお砂糖を添えて。
映画が終わり、汚れたノートの一ページが文字で埋め尽くされたとき、マグを持ち暖まっている者の後頭部に一撃!私にも冬が訪れる。植物のツタが私の首に巻き付いて、呼吸もままならないほど力強く締め付けてくる。もう一撃。引いた拳が真っ黒に染まる。赤いカラスたちが私の上に集まり、ケラケラと笑い始める。もう一撃。無数のサソリが私の腕に毒を注入する。夜空が落下して歪んだ笑顔をこちらに向けてくる。もう一撃。もう一撃。一撃。一撃。一撃。一撃!
私は手を止める。血で額の汗を拭い、辺りを見回す。見ろ、まだ夜は明けていないというのに、太陽が私に視線を向けている。私の心臓が胸を突き破って足元に転がっている。空が地下深くに潜っている……星が曲がっている!落涙と同時に私の静脈から花が咲き始める。おお、花たちよ。私の身体を喰らい尽くして大きく育つがよい。
目を瞑る。意識が遠退いて心地がよい。私は目を閉じたまま、鮮麗な世界を見渡す。遠方に大きな窓が見える。私が立っている大地をも飲み込むかのような、大きな……私が最も憧れ、愛してやまなかった、大きな窓が……。
額縁