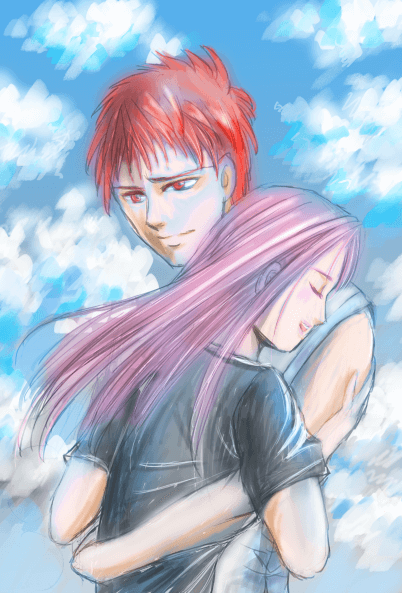
OVER
2017年~2020年作品
発端
もう何年前になるだろう。桃井は昔のスケジュール手帳を見返す。今ではめったに開くことのないページ、桐皇高校のバスケット部のマネージャーをしていた頃のもの。その手帳の高二最後の夏休みに、スケジュールに空白がある。約一週間分の予定が書いていない日付。私が蒸発していた時。彼と――赤司くんと・・・・。
その一か月ぐらい前にあの、アメリカから来日したジャバウォックとの試合があった。あの試合中に彼になんらかの「変化」があったのだった。それは彼から後で聞いた話だ。それで彼はある能力に目覚め、あの男をあんな場所まで追い詰めたのだった。あの試合がなければ、彼はああしなかった。そして今私がこういうことになることもなかった。
桃井は自室の机の引き出しを開けてみた。彼からのプレゼントの小さな指輪ケースが入っている。それはこっそり贈られたもので、彼の父の征臣はまだ知るところのないものだ。彼の父は私を許すだろうか。彼には理解のない父親だと言う。彼が勝手に決めた私との婚約も、彼の父はきっと反対するのだろう。それでも彼はいいのだろうか。桃井は暮れなずむ夕焼け空を眺めている。彼もどこかでこの空を見ている。そう信じたい。桃井は膝を立てて座り、部屋の壁によりかかって考えた。今あのころのことを思い出してみる――高校二年生のあの夏を。
「地球岬?変な名前の場所ね。」
「室蘭市にあるんだ。この前の春休みに行ってきたんだよ。」
「そう。北海道まで。京都からは遠いでしょ。」
「うん、急に行きたくなって。」
「どうして?」
「地球の丸みが見えるぐらい開けた場所があるんだって聞いてさ。断崖絶壁が13キロも続いているんだよ。自殺の名所かな。」
「やだ、赤司くん、変なこと考えたんじゃないんでしょうね。」
「まさか。室蘭本線の母恋(ぼこい)駅から車で10分だよ。北海道だけどまだ寒かったなあ。」
「ふうん。ウィンターカップのこともう引きずってないのね。安心した。」
「ああ負けたこと?いつまでもぐじぐじ思っていてもね。」
「そうそう。」
赤司への電話は久しぶりだった。七月に入った第一週ぐらいの電話だった。その数日前にリコから、ジャバウォックが来日する話を聞かされ、リコの父親が彼らの来日試合をプロデュースする話を聞かされていた。リコの父親は帝光のキセキのメンバーを集めたがっている。その話をされ、桃井がリコに頼まれてかつてのメンバーの連絡を個別に取っていた。そのやり取りで、赤司とも連絡するようになった。
あのウィンターカップの別れ際に会ったことで、最初はぎこちなかった二人だが、何度か電話をするうちに、こういう日常的な会話もするようになった。桃井はもちろんまだ自分の気持ちを赤司には打ち明けていないし、赤司からもそのようなことは言われていない。だからそれは、昔の帝光時代の主将とマネージャーのつながりが復活したようなものだった。桃井はメールは打たないようにしていた。何か勘違いされたら困る。それぐらい慎重にしていた。直接電話で話をするだけ、そういう実りのある関係にしておかないとと思った。黄瀬とは赤司はメールでやり取りがあると聞いていたが、それも自分には荷が重かった。友達が聞いたらなんて歯がゆいと言われるだろう。それでもよかった。何よりも中学の卒業式で「そんな赤司くんは嫌いだ」と言ったことを、桃井は非常に気にしていた。その時は、黒子がクラブをやめるきっかけになった試合の事件の責任感からそう言ったのだった。桃井にとって、赤司はそんな試合でゾロ目狙いなどしない、清廉潔白な人物でなければならなかった。それでその時赤司にそう叫んだのだった。彼女の愛していた赤司征十郎という人物は、そういう清い人間であった。
しかし当の赤司からそんなに気にしていないよ、あのころは俺も少し軽率だったからね、と電話口で言われて桃井は安心してしまった。
「赤司くんはやっぱり気にしていないんだ。」
「だって中学の頃だからね。桃井さんだってあの頃とは変わっているだろう?俺もそうだけど。」
桃井は受話器の前で赤司が目の前にいないのに、うんうんと大きくうなずいてしまった。
「ごめんね、ごめんね。もう二度とあんなこと言わないから。私どうかしていたんだよ。」
「そう?桃井さんらしいと思ったけど俺は。」
「私らしいってどういう意味?じゃあね、またいつか電話するから。」
桃井はそう言って電話を切ったが、頬が自然と緩んでくるのを止められなかった。赤司くんがあの時の私を許してくれた。どうしてこんなにうれしいんだろう。あのウィンターカップのバス見送りの時に昔の写真を渡した時も、思えば赤司に対して恥ずかしい気持ちでいっぱいだったのだ。でもあの時はどうしても写真を手渡したかった。それで元マネージャーの顔をしてそっと渡した。赤司くんはでも、それを厚顔無恥だと思っていなかった。それが心底から嬉しいと思った。
その赤司と再会できるチャンスをくれたのだから、あの疫病神のアメリカから来た連中にも、桃井は感謝しなければならなかった。しかしこの時はまだそれも予感すらしなかったことだ。電話の向こうの赤司が実際はどう思っているのか、桃井の知るところではなかった。桃井はひとりつぶやいた。
「北海道か・・・。どうして行ったんだろう、赤司くん。一人だったのかな・・・・。」
今年のインターハイの結果については、すでに知るところだった。洛山はいい成績で終わったのだが、それでも優勝ではなかったのだから、赤司にとってはウィンターカップに続いての不調だったのかもしれない。でも、もういい。電話口の向こうの赤司は明るい声だった。あの帝光時代の写真を渡したことも、嫌に思っている風ではなかった。いつまた会えるのだろうか。桃井はそれだけを考えた。未来は明るいものだと思った。
(赤司くんががんばっているんだから、私もがんばるんだ。青峰くんも故障、治ってきているんだし。)
そう桃井は思った。
洛山の寮の部屋でスマホの電話を切った赤司は、相部屋の同室の者に「少し出かけてきます」と声をかけて外に出た。夕刻、学生寮から出て裏山の裏道を上ると、視界が開ける場所がある。散策の場所に決めている地点だった。見降ろすと、京都の東山の街並みと東寺の五重塔が見える。あの場所もこんな崖の上だったな、と赤司は思う。ポケットから北海道のネットで印刷した地図を取り出す。スマホの画面では書きこみができないから、印刷したもので検討する。行ったのは春休みのはじめだった。
あいつの所在を突き止めたのは、ウィンターカップの終わった後だった。借金逃れで転々と住所を変え、東京の近郊の古ぼけたアパートにその中年の男は住んでいた。あのトレーラーの運転手だった。もともと賭博にはまって多額の借金をこしらえて、首が回らずトレーラーをあの時高田晴美の言うとおりに動かすことを承諾したのだった。もうあれから十年はすぎていた。彼はしかし警察には書類送検だけで法の裁きは何も受けず、こじんまりとした小市民生活を営んでいた。独身、身よりはほとんどなし。そういう地方から出てきたおこぼれものの吹き溜まりの一人だった。赤司は遠目にスーパーの袋を下げて歩く男を目視で確認しただけである。会って話すつもりは最初からなかった。高田晴美の時のようにおびき出して殺すのも、赤司には面倒に思えた。自分の気持ちが萎えたのではない。自分の知り合いでも何でもない男。できれば他人のまま葬りたい。そう思った。接触すれば足がつくのも理由のひとつだったが、気持ち的に腫物に障るような感じがしたからだった。母を殺した理由がはっきりとあった高田晴美に対しては、あの時燃えるような殺意を感じたのだが、この男はただ単に借金の片に母の殺害に手を貸しただけだという気持ちがあった。それでもその存在は打ち消したい。そういう、赤司の心の染みか影みたいな存在がその男の存在だった。
人の気持ちを動かすことは自分には無理だ。でもあのウィンターカップの試合中で、自分はアンクルブレイクを仕掛けたつもりはなくても、派手に敵選手たちは転んでいた。あれが自分にはできないか?もう一度。木立の中で、赤司は精神を統一してみようとした。しかし念じたところで、林の中の木の葉ひとつ落ちなかったし、「彼」も赤司には何も話しかけてこなかった。「彼」には「消えろ」と言ったこともあったのだった。こういう時には出てこないのか。赤司は唇を噛んだ。
赤司は今「彼」の協力で、この男を北海道の崖の上から突き落とすことを計画している。偶然学生食堂のテレビで見た番組で、「母の日なので母恋駅にやってきました」、というバラエティ番組があった。ネットで調べてみると、近くに日本有数の断崖絶壁がある。母恋駅というネーミングで動かされた自分が軽いとは思ったが、北海道の僻地なら警察にもわからないという目論見があった。どうせ殺すならそういう場所がいい。男のアパートからほど近い東京湾から突き落とすだけだと、想定内の出来事でつまらない。あの母のための、一生にもう一度しかない復讐行なのだ。幸い軍資金は父からの通帳振り込みで潤沢にある。詩織の死後おかしくなった赤司を持て余して放任主義になった征臣は、赤司が親の元を離れて京都に行くと言った時から、以前にも増して赤司に冷淡になっていた。愛情の代わりに金さえ与えておけば安心といった態なのであった。だから殺(や)るなら北海道だ。
それは桃井には決して言えないことであり、ましてやキセキの仲間らには言えない話だった。でも今度こそ完全犯罪にしてやる。古賀さんだってもうこの京都にはいないのだし、俺ひとりの裁量でやりきる。その時こそあのおかあさんの魂は浮かばれるんだ。もう古賀が何と言おうと知ったことではない。夏冬連覇でバスケットで日本一にはなれなかったことで、赤司も意地になっていたのか。そうではなくて、赤司自身ももう中学生ではなかった。彼が今考えていることは、自身が日本一になって箔をつけることではなくて、真に母の魂が鎮められることだった。どう考えても母の死にざまはひどすぎた。そして父はそんな母に一顧だにしない。だから自分が死んだ母の喜ぶことをして恨みを晴らす。赤司の今考えていることはそれだった。ウィンターカップで敗北したことで、彼は確かに一皮むけたのだが、しかしまだまだ発展途上にあった。
その夜、赤司は夢を見た。自分はあの北海道で見た海岸線の端に立っている。どこまでも続く茫漠とした砂浜、その足元に白い木の棺がある。おかあさんの棺だと思って赤司は中を見て驚いた。中に眠っていたのは桃井だった。桃井は棺の中でたくさんの白い百合の花に包まれながら、ゆらゆらと揺れて赤司の目の前からゆっくりと沖に向かって流されていく。風に揺れる百合の花が見えなくなるところで、待ってくれ桃井さん、と大声で叫んだところで目が覚めた。赤司はがば、と起き上がったがまだ深夜だった。同室の者は暗がりで静かな寝息を立てていた。自分は今実際に声に出して叫んだのではなかろうか。赤司はびっしょりと寝汗をかいている頬を掌でなでた。そう言えばこんな小説を最近読んだような気がする。夏目漱石だったか三島由紀夫だったか・・・大学生になった黛からラノベ以外の本も読んでいるんだぜ、と言われて貸されたものだったと思う。
黛はもう引退式を、欠席はしたが過ぎて高校も卒業したが、たまに会うこともあるのだった。どういうつもりか知らないが、黛は時々思い出したように連絡してきた。ほとんど赤司にとっては使い捨てみたいなスカウトだったのに、黛にとってはそうではなかったようだ。気にかかる後輩ということで、彼は赤司にどうしている、と言って会いたいんだけどと言うのだった。そう言われると赤司は何となく断れず、出向いて行って会って話をする。それは黛を試合で利用したという負い目もあったのかもしれない。黛にはもちろん桃井の話はしたことはないし、赤司も自分の桃井への気持ちを黛に相談などするつもりもない。何と言っても「林檎たん」などというキャラが出てくる小説を愛読している黛に、実際の恋愛を相談など考えただけでもおかしい話だった。だからその夢は偶然見たものだ。
赤司は起き上がって部屋の本棚を物色した。黛から貸された本は漱石の「夢十夜」だった。途中まで読んで、そのまましおりを挟んで忘れていた本だった。ページを繰っていくと、「第一夜」にもう今にも死ぬ女に百年墓の前で待っているように言われるという話があった。あいつ、ひょっとしてわかっていて貸したのではないか?黛に母が死んだ時の話はしていないが、母がすでに他界していることはウィンターカップのあとにカフェで話したことがあった。黛の行動にはそんなところがあった。黒子と同じく影の特性がある彼は、人の気づかない影を踏んで生きているようなところがあった。「会いたいんだけど・・・・。」と電話越しに言う黛の湿った声は、そんな感じの日陰の声だった。自分は今そういう影たちに付きまとわれているな、と赤司は思った。そして肝心の、いてほしい影の「彼」は俺の傍にはいない。こんな状態では桃井さんにはとても会えない。桃井さんに会うとすれば、俺が完全犯罪を成し遂げた後でなければならない。
桃井に旅行の話をしたのは軽率だったかもしれないが、桃井さんには自分の行動の軌跡をどこかで知っておいてもらいたいと思う気持ちがあった。あの中学の時、クラスの教室で錯視の本を見せびらかしたのも、そうした赤司のデモンストレーションのひとつである。ストーカー的な犯罪心理の一種と言っても過言ではない。それで足がつくかもしれないということよりも、桃井に知っておいてもらいたいという気持ちが弥(いや)増さった。それだけ赤司にとって桃井は、母に連なる重大な人間だと言えた。桃井さんにはこれからも俺が殺(と)ってきた獲物をそれとなく見せるさ。「彼」のあいつも、またバスケットの試合中に出てくるに決まっている。猫のようにやつの首根っこを押さえて俺の言うことを聞かせる。あいつは考えてみても、俺に手を貸し続けているんだから、きっと俺に気があるんだ。桃井のことをうらやましそうに言っていたからな。
赤司はそう考えると、漱石の「夢十夜」の文庫本のページをぱたんと閉じた。もう顔の汗はひいて、いつも通りの、自己采配の見事な赤司であった。桃井がその犯罪を実行することでどう思うか、赤司の脳裏にはないのであった。そればかりか事情を知れば桃井さんも一緒に喜んでくれると赤司は考えていた。
たとえ復讐という言い分があったとしても、犯罪を犯すことに少しも疑いを持たないこと、それはやはり間違いと言える。だからその夢は、赤司の深層心理からの、あるいは「彼」からの警告だったのかもしれない。しかし赤司はそれを考えることはなかった。赤司は本を棚に戻すと、また寝床で横になって寝入ってしまった。
桃井が母のように死ぬようなことはないとそのころ赤司は思っていた。桃井は彼にとって、母詩織の生きている現身のようなものだった。それは保護者や依存者としての母というのではない。幼いころからの厳しい家庭環境のせいで、赤司は年相応以上に独立心のある青年である。つまり言うならば母と紡いでいた昔の途切れた時間を、桃井と過ごすことで赤司はまた再開して続けているのである。そういう、時の渦のような時間の流れの中を彼は生きていた。しかしそういう、時の流れに逆らっているようなことから桃井が好きだということは、彼は桃井に打ち明けるつもりはなかった。自分が桃井に母親を重ねていることも、自分自身の勝手な思い込みに過ぎないと赤司もよくわかっていた。そして、自分も含めて桃井も同じ時の流れをどんどん進んでいく存在なのだということもわかっていた。押し流されていくと言った方がいいかもしれない。その時の歩みの前には自分は無力であり、ちっぽけな存在だ。しかしせめて母詩織のことだけでも、決着をつけておきたかった。晴美を殺そうと計画したことも、バスケットで日本一になろうとしたことも、結局は赤司なりにそういう無情な時の流れに歯止めをかけたかったのかもしれない。
翌朝、黒子から「黄瀬くんから聞いたので」とメールで連絡が入った。
「リコさんの御父さんが、帝光時代の仲間を集めたがっているそうです。対戦相手は来日した向こうでの優勝した高校生チームだそうです。先発の選抜チームが当たるみたいですが、予備で用意しておきたいとのことです。東京に出てこれますか?試合はテレビ中継されるとかいう話で。赤司くんはそういうの好きじゃないと思いますけど。」
と書かれていた。桃井が電話してきたことが現実になったと赤司は思った。桃井は電話では小出しに話に出していて、はっきりそういう手弁当の試合だということは言わなかったのである。つまり、これは公式戦ではない。赤司の脳裏に、冷静に判断して断った方がという声が響いたが、計画に利用できるのではないかという考えが瞬時に浮かんだ。試合中にしかあの「彼」は姿を現さないのだ。それはこの京都でしている練習試合のようなものでは、決して出てこない。あのウィンターカップの激戦でだったから、「彼」はあの時あの力を見せたのである。強い相手ならば本望だ。それは早い方がいい。そう思った。ウィンターカップ以降の試合では「彼」は出てこなかったからだ。赤司は承諾のメールと、日時を尋ねる旨を黒子に送った。仲間たちは来るだろうか。たぶん来るだろう。彼らは互いに会いたがっている。また同じチームで戦いたいと思っているに違いない。帝光中では決裂したのだが、その後のことでそうなっている。ただ自分はまた違うがな。赤司はまたあの見下ろせる高台に来ている。赤司の目は眼下の地上を眺めている。目下には平穏な京都市街の街並みが広がっているだけだ。ここからやつを突き落とす。あいつの力で。そう思った。
テレビであのジャバウォックチームが映しだされたのは、その一週間後だった。先発のチームで、リコの父景虎が集めたチームである。キセキのチームは、その後の隠し玉として景虎は考えていたのである。景虎は黒子の帝光時代の話を聞いた時から、黒子の中学時代のキセキの世代の一同に会した試合を一度は見たいと思っていたのだった。景虎は言った。
「ウィンターカップではばらばらだったからな。テレビ屋の向こうのディレクターと話をして、ショーアップしたものだが、それなら集められるんじゃねぇかと思ったのよ。学校からの各校代表でだとまず不可能だからな。来日したチームとのドリーム試合ってやつだと、こういうマッチは組めそうだと思った。まずはお手並み拝見と願おうじゃねぇか。」
リコは父の話に顔をしかめた。
「お父さん、見世物じゃないんだからね?高校生ウルトラクイズとは違うのよ。」
景虎は言った。
「わあってるよ。来日したやつらはまあそれなりのやつらとは聞いている。」
リコは少し不安になって言った。
「実際の実力は聞いてるの?向こうでの評価はどうなの?」
景虎は言った。
「ストリートバスケのリーグ戦の優勝者たちだと聞いてる。まあそれぐらいのやつらなら、いいかなと思って・・・・。」
リコは画面を見ながら言った。
「こいつらってほんとに高校生?なんか年食っているように見えるんだけど。」
景虎は鷹揚に答えた。手には缶ビールをはさんでいる。
「向こうのやつらはでかいからな。日本人より育っているんだろ。」
「そうだといいけど・・・。」
と、リコが見ている間に点数は開いていく。日本人チーム、今吉翔一、樋口正太、宮地清志、笠松幸男、岡村健一、とウィンターカップでも活躍した選手を集めたものだが、苦戦を強いられているようだ。リコは言った。
「ジャバウォックの名前の由来は?」
「さあな。連中のリーダーのやつ・・・・そらあの金髪の背の高いやつだ。そいつに尋ねたら、"I like game." とだけ言いやがった。」
「ゲーム?」
「もとはルイス・キャロルの『鏡の国のアリス』に登場するドラゴンだが、向こうのRPGゲームではよくボスのドラゴンで出てくる名前らしい。つまりそういうことだ。」
「ドラゴン?なんだか不気味ね。」
「それで俺も、じゃあこっちには『ヴォーパルの剣』があるぞ、と言ってやったら笑いやがったよ。」
「ヴェスポワール・スワードとかいうあのチーム名?ショーアップはいいけどね。」
「そのドラゴンの首をはねたという剣だ。ゲーム好きには通じる名前だろう。」
景虎はそう言ったが、その時テレビ画面では敵ジャバウォックチームのリーダーが激しいドリブルをしていて、笠松はそれを止めようとしていた。リコは言った。
「笠松さん、カットするわね。」
しかし笠松の前からボールが消えて、次の瞬間パスコースに行き、すかさずシュートが飛んでいた。リコは叫んだ。
「あいつ、今どうやったの?」
「ボールを手玉に取るのはストリートバスケの特徴だがな。こいつら慣れてやがるな。」
と、景虎が言うまでもなく、ジャバウォックのメンバーの一人が、ボールをユニフォームの中に入れ、腹回りで回転させてみせた。試合とは関係のないプレイに、リコは憤った。
「なにこれ。なめられているんじゃないの。」
景虎も苦々しそうに言った。
「パフォーマンスを入れてくるとはな。」
その後もそのようなプレイは散見された。点数差はそれからも開き、結局試合はジャバウォックの圧勝に終わった。リコは言った。
「このテレビ、専門チャンネルだからいいものの、こんなもの全国に流れたら笠松さんたち、いい恥さらしだわ。お父さん、どうしてこんな試合をOKしたのよ。キセキの人たちをこいつらと試合やらせるの?」
景虎は言った。
「あいつらならやつらを倒せる。」
「冗談じゃないわよ。」
「全国一になったことがあるんだ。」
「お父さん!」
と、その後テレビはヒーローインタヴューでジャバウォックのリーダーを映し出した。金髪の紳士然として見える若者だった。インタヴュアーの女性と翻訳者が、マイクを若者に差し向ける。女性は言った。
「しあさってにはもう一度試合がありますよね。今度は日本一になったことのあるチームです。」
若者は両手を広げるジェスチャーをした。明らかにおどけている。そして次の瞬間、彼は驚くべきセリフを吐いた。
「今日の試合で思ったよ。お前らを見ていると、俺は心底ヘドが出る。」
マイクを持った女性の顔が引きつった。
「え?」
若者はにやりと笑い、あたりを見回して言った。
「ここにいる奴ら全員、いやこの国でバスケごっこをしてるやつら全員、いますぐやめるか死んでくれ。お前らだってサルと相撲はしないだろう?だが俺たちはした。プレイヤー気取りのサルとバスケをやらされたんだ。まずは自分たちがサルだってことを自覚しろ。サルにバスケをやる資格はねぇよ!」
翻訳者の機械読みの声がし、バックスクリーンに字幕で写し出されると場内はしん、と鎮まった。水を打ったような沈黙。試合後整列して、相手チームを待っていた笠松たちは顔面蒼白になった。
「なん・・・だと?」
「サルってどういう意味だ?!」
口々に日本チームのメンバーが叫ぶ中、若者はべっ、と地面に唾を吐いた。そして片手をあげて言った。
「Good luck.」
立ち尽くすメンバーを後目に、ジャバウォックチームは悠然と立ち去った。
「おそろしいぐらいのレイシストだな。相手チームは?」
東京への出発前、赤司は見送りの黛や小太郎と逢っていた。三人は新幹線の時間待ちで喫茶店で話している。黛の言葉に、小太郎は言った。
「その、レイシストってなんですか、黛さん?」
赤司は横から答えた。
「差別的蔑視者という意味だな。黛さん、本は返します。」
赤司はかばんから夏目漱石の文庫本を取り出し差し出した。黛は言った。
「読めたのか?」
「はい。一応は。」
「ならよかった。名文で心が落ち着いただろう。」
「そうですね。漱石の文体は平易ですから。」
黛は赤司の言葉を聞くと、いつものふーんとした顔で、上から目線で言った。
「俺を呼び出すほど、レイシストたちが怖いのか。」
黛の言葉に赤司は薄く笑った。黛を呼び出したのは、他でもない「彼」の発現を早めるためである。ウィンターカップの試合では黛がいた。しかし黛が卒業した後は「彼」は出てこない。少しでも可能性のある枠をしらみつぶしにしていく必要がある。だが残念なことに、黛はキセキのメンバーではない。それなので東京に旅立つ前に黛に逢ってみておこうと思ったのだった。小太郎も呼んだのは黛に怪しまれないためである。赤司は答えた。
「怖くないと言ったら嘘になります。あの試合、敵の戦力は相当上だったですから。」
小太郎は横から言った。
「それにウィンターカップでは敵同士だったやつらと組むわけでしょう?赤司さんも大変だと思うぜ。」
黛は言った。
「中学の時のクラブね。同窓会気分では負けるかもな。」
赤司は黛を見返して言った。
「ただの同窓会ではありませんよ。それは黛さんも試合で戦ってよくわかっているでしょう?」
「そうだな。」
小太郎はとりなすように言った。
「赤司なんか丁寧語で話してるね。主将だったのに。」
「黛さんは俺の先輩ですから。その本貸してくださりありがとうございました。」
黛はうなずいた。赤司の言葉にやや気をよくしたらしい。
「うん。」
「ただ一言言わせてもらえば、俺なら百年も待てませんね。しかも相手の女性は死んでいる。その時間に意味はあるのですか。漱石の修辞句は大げさです。」
「漱石にケチをつけるとはな。」
「彼は精神疾患があった作家でしょう。」
「作家と作品は別だ。」
「黛さんはそうでしょうね。ラノベとかも読みますからね。」
黛はカチンと来たらしかった。
「ラノベを馬鹿にすんなよ。俺はおまえと最初に会った時、ラノベを屋上で読んでいただろう。」
「それが何か?」
小太郎がすかさず横から言った。
「黛さん、それはやばかったっすよ。あそこ洛山でも、不良グループがシケモクふかすのによくいることがある場所じゃないですか。そんなところで文庫本なんか広げてたら。」
「ああ。赤司に会う前にからまれたよ。実際二三発頭をはたかれた。お勉強は目障りだからやめろってな。」
赤司は言った。
「馬鹿じゃないですか。黛さんはいったい何のために?」
黛は答えた。
「だからおまえは馬鹿なんだよ。俺の性格がわかっていなかった。黒子ってやつの代用品だったわけらしいがな。俺はあの時、ある女に見てほしいからそういうことをしていたんだ。おまえに言ったろう、俺は自分が大好きなんだと。それでわかるだろ。」
小太郎が言った。
「え、全然わかんねぇ。」
赤司が言った。
「わかりました。ふられたわけですね。それでその女性に見せつけるために、屋上でパフォーマンスをしたというわけですね。」
黛は言った。
「そうだ。俺はあの時目立とうとしていたんだよ。それで図書館でラノベを何冊も借りたというわけだ。そういう恰好の悪いことをして悪目立ちしたかったわけだ。つまり自分が好きだからそういうことをしたんだ。俺はそういう男だったんだよ。それを影のシックスマンの代わりにね。おまえの思い付きをあえて俺は止めなかったが。」
「つまり相手の女性が心象を害してもいいということで、あえてロリコンと見られてもよかったというわけですね。しかしその後試合に出て、相手女性に見直してほしかった。」
「そうだ。それと、そういう女性の心理を研究するためにラノベを読んでいたのだ。」
赤司はへえと笑った。
「つまり一石二鳥だったわけですか、黛さんにとっては。林檎たんで女性心理を研究できるとは思えません。だいたいそのラノベは男性作家が書いている小説ですから。」
「しかし俺よりはわかっていると思った。それで林檎たんの心理を研究していた。」
赤司は黛の言葉をさえぎるように返した。苛立った時、難しい言葉を言うのは彼の特徴である。
「林檎たんの思考や行動で現実の女性の心理を予測できるのですか。無理ですね、林檎たんは単なる小説の中のキヤラクターです。しかも記号化された少女ですよ。一般的な女性の心理をそこから予測できるとは到底思えません。」
黛は言った。
「林檎たんはたとえ記号であったとしても、現実の少女の心的特性は備えている。俺はそう読み取った。林檎たんで来るべき未来を予測するのは無駄ではないよ。貴様はさっき百年も待てないし、その時間に意味はないと言ったな。」
「そうです。俺に言わせれば無駄な時間です。その男はよりよい未来を予測できなかったから、彼女は死んでいたんですよ。待っているだけで何もしなかったから、その結末なのです。」
「なんだそれは。」
「そういうことがある本に書いてありました。俺はそういう考え方です。漱石はきっとそう言いたかったのですよ。」
黛は赤司の言葉に我が耳を疑った。彼は文学を愛していたので、このような考え方は到底容認できないのだった。そして、こういう赤司がずっと気になって、何度も呼び出していたのだと気づいた。黛は叫んだ。
「馬鹿なことを!情緒も何もあったもんじゃない。いいか、貴様は母親に死別されているそうだが、しみじみとそれを思い出したりして死者を悼むこととかあるのか?」
赤司は黛の顔をにらみつけた。
「俺にも心の傷はありますよ。その言い方は不快だな。時間ですね。ではそろそろ行きます、先輩。」
腕時計を見て立ち上がった赤司に、黛は手を差した。
「おい、待てよ。」
小太郎はおろおろとして言った。
「ええ、それで行っちゃうの?なんかさ、言い合いになっちゃったな・・・。」
赤司は答えた。
「言い合いではないよ小太郎。ディベートだ。じゃ、黛さん。」
黛はそれでも赤司が改札口に消えるまで、小太郎と一緒に見送った。黛は思った。
(『俺なら百年も待てない』、か。『鳴かぬなら、殺してしまえ不如帰(ホトトギス)』か。大丈夫じゃないぞ。)
赤司を試合先で待っているのが、日本人をサルと呼んではばからない男だということも、彼には悪い予感しかなかった。
東京駅に着いて、赤司は地下鉄をいくつか乗り換えて、スマホにメールで通知されていた宿舎に行った。安いビジネスホテルに毛が生えたような施設だった。見たところどうも宗教関係の宿泊所ではないかと思った。こういう場所は学生などがよくクラブ合宿や社外研修に利用させられると聞いている。これもリコの父親の景虎が某テレビ局側から用意された場所なのだろう。その背景については赤司は深く考えない事にした。入ってすぐに横にシューズや荷物のロッカールームがあり、そこに荷物を預けて掲示板にマジックで書かれたホールに行くと、すでにキセキのメンバーや先行試合に出ていた笠松たちが待機していた。急造のトレーニングジムの器具が置いてある。なるほどと思い、赤司はスチール椅子に薄いシャツの上着を脱いだ。
「お久しぶり、あかしっち。」
と声をかけてきたのは黄瀬だった。肩からタオルをかけて、先にトレーニングで汗を流している風だった。
「ああ、久しぶりだな。元気だったか。」
「まあまあってとこっすかね。」
「よう、来たか。えーと赤司くんだったかな。」
景虎が部屋の奥から出て来た。
「お世話になります。」
赤司が軽く頭を下げると、景虎は笑って言った。
「娘のリコから話は聞いてるよ。みんな地方から出て来てもらって、悪い。でもドリームマッチを見たいってやつが多いから。」
「帝光時代の事を知っている人が、そんなにいるとは思えませんが。俺たちはまだ中学生でした。」
赤司が言うと、景虎は首を振って言った。
「いやいや、それがいるんだなあこれが・・・。ま、ま、その話はいいか。みんなそろそろここに集まってくれ。今後の相談だ。」
と景虎が言うと、ジムの器具を使っていた仲間が部屋の真ん中に集まって来た。青峰、緑間、紫原、黄瀬、そして黒子。そして・・・。
「なんでおまえがいるんだよ。」
と青峰が言うのに、火神が「いちゃわりぃかよ。景虎さんに頼まれたんだぜ」と答えた。景虎が言った。
「我が誠凛の両巨頭だからな。欠かすわけにはいかねぇんだよ。そうだろう、黒子くん?」
「あ・・・はい、そうですね。景虎さん。」
「あたしたちマネージャーもお忘れなく。」
と、リコがその横からぴょこんと出て来て言った。桃井もその横にいた。桃井はにっこりと笑って皆に言った。
「みんな昔のメンバーだね。昔に戻ったみたいだよ。またみんなで戦えるなんて思ってもみなかったよ。景虎さんのおかげで、夢が実現してうれしいよ。」
青峰が言った。
「昔はいいが、もうあんなまるごとのレモン漬け食わすなよな。」
「うるさぁい。もうやりませんよーだ。」
桃井はかわいく舌を出してあかんべーをした。その様子に黄瀬と黒子がははと笑った。桃井は黒のキャップをかぶっていて、薄ピンク色のTシャツを着て黒の短パン姿だった。あいかわらず、わりと美人なのにかっこは構わないのは中学時代と同じだった。髪の毛もあまり念入りに手入れしていなくて、そのピンクのロングヘアはぼさっとしていた。マネージャーの仕事が忙しい時は、無造作にヘアゴムで後ろにくくる髪の毛だった。半年前のウインターカップの時とあまり変わっていないと思い、赤司は一瞬安堵したが、よく見たらやはり以前よりは胸など大人っぽく変わっていることに気づいてどきっとした。そして今ツーカーの呼吸で会話した同じ桐皇高校の青峰に軽く嫉妬した。自分はやはり置き去りにされていると思った。夢で見た海の彼方に遠ざかる桃井の映像が思わず脳裏に浮かび、あわてて赤司はその妄想を頭から追い払った。そして目の前の景虎の会話に集中した。景虎は言った。
「ジャバウォックチームとの試合は三日後だ。」
「えーっ、三日後っすか?練習時間がねぇじゃん・・・。」
「仕方ないだろ。それだけの日数をとるだけでも、テレビ相手じゃ大変なんだ。放送スケジュールがあるんだよ。」
「全国放送っすかそれ?」
「いや、専門チャンネルだ。」
黄瀬が不満を漏らすのに、青峰が横から言った。
「そんなもん動画サイトに毛が生えたぐらいじゃねーか。融通がきかねぇのかよ、おっさん。」
「仕方ねぇんだ。相手チームも早く帰国したがってるんだ。とりあえず、この施設の横に付属体育館があるから、そこでおまえらみっちりと練習しろ。いいな。」
「はーい。」
黒子が不安気に言った。
「これいったいなんの施設ですか?景虎さん?」
「深く考えるな。ただの○○教だ。じゃあな!」
「どこに行くんですか?」
「ちょっとした野暮用だ。ああそうそう、あとでおまえらもいいところへ連れて行ってやる。じゃあな、練習しろよな。」
景虎が部屋から出て行くと、黒子たちは指示どおり体育館の施設に移動し、自主練をはじめた。思い思いの練習メニューでの練習になった。なにしろ今まで各高校でクラブをしていたのである。それを見ていて、リコと桃井は相談をはじめた。
「二日間で全体の息を合わせられるかしら。桃井さん、何かいい策はない?」
「彼らはみんなうまいから、大丈夫だと思うけど・・・。」
桃井の言葉に、リコはため息をついて言った。
「けどじゃだめよ。あなたのそういうあいまいなところが、あの時うちに負けた理由よね。」
「はい・・・・。でもうちの青峰くんも、怪我治ってきてるんです。」
「青峰くんひとりの話じゃないの。あなたの知っている中学の頃の彼らのデータは?持ってきているんでしょうね、資料?」
「あ、はい、ここにあります。」
「出して。見るから。」
リコは桃井の出してきた古いファイルばさみを繰った。そして、「ふーん、やっぱりね。」と言った。そして言った。
「個人主義のチームだったの?」
桃井はどきりとした。あの中学時代のことがとっさに思い浮かんだ。桃井はしどろもどろになってリコに説明した。
「え・・・、あの、学校の方針として勝たないとだめだったので、そんな感じで、練習メニューもそんなにみんなで一緒では・・・・。」
「そうなの。あなたの学校の青峰くん、欠席が多かったのね。試合には出ているけど。よく勝てたものねぇ。」
「強い・・・人たちなんです。」
「うん。わかるけど。強豪の子ばかり集めてた学校だって聞いてる。」
と、リコは言うと、桃井に向かってこう言った。
「一番だめな女って言われる女って、わかる?花形運動部のマネージャーになりたがる子。それがあなたよ。もう少し考えてね。」
「はい・・・・。」
「じゃ、私練習メニュー組むから。」
と言うと、リコはコート上の火神を呼んだ。
「火神くん、いつものAのメニューでやってくれる?」
「わあった。」
火神はOKのサインを出すと、皆に指示を出しはじめた。二人一組でのパスの練習などをしている。普通の練習、と桃井は思った。しかしそれもリコさんにはうまく伝わらない。だってあの時のことこの人は知らないから。
桃井はそう思ったが、リコさんはこれからの試合のことを考えてああ言ってくれているんだ、と自分の否定的な気持ちを打ち消した。そしてしっかりしろ桃井、と自分を励ました。
大丈夫、あんな事はもうない。あんな事は・・・。だけど、どうしてこんなに不安なんだろう。彼らは見たところ今仲がよさそうなのに。桃井はそう思った。そして見るとはなしに、コート上の赤司の方を見た。どうして彼なんだろう、と桃井はぼんやりと考えた。今はすごく遠くの京都にいるのに、どうして彼のことを思うと、私は幸せになるんだろう。いいところのおぼっちゃまだから?違う、そんな理由じゃないよ。そして思った。私はきっと、彼が青峰くんたちより背が低いのに、とてもがんばっているから好きなんだ。きっとそうだ。そんなところが好きなんだ。だってバスケって、背が高ければ高いほど有利になるんだもの。今度の試合の外人選手だって・・・。と桃井は思った。でもそんな話は誰にも言えない。それは桃井の胸の内だけのモノローグだった。その日の練習は遅くまで続いた。
その後控えの日向たちも交えて、オフェンスディフェンス攻撃のモーション練習を交代でやった後、その日の練習は一応の終了ということになった。その頃、体育館にまた景虎がやって来て、「これからみんなで六本木に行く」と言い出した。全員目が点になった。黄瀬は言った。
「六本木っすか?俺もたまにバイトの仕事で行く事もあるけど、あさって試合っしょ。」
「ちょっとまずいのだよ・・・。」
「景虎さん、どうしてなんですか。」
黒子の問いに景虎は答えた。
「俺の自腹でジャバウォックの連中を遊ばせている。あいつらは練習をまったくやっちゃいねぇ。場所が六本木なんだ。おまえらもちょっとついて来い。」
赤司が言った。
「試合前ですが。」
「お前らも少し遊んでけ。」
景虎の言葉に、青峰と緑間が文句を言った。
「おっさん、なんか面倒な事になりそうだから、俺らも加勢に行けっつぅことかよ?」
「御見通しなのだよ。」
「いいから来いよ。やつらの顔見とくだけでもいいだろ。」
黒子は答えた。
「テレビ画面で見ただけでもういいですよ。」
「いいからな。おまえらも親睦が深まるだろ。」
「わざわざそんな店に行かなくとも、旧交を温めるにはこれで十分です。」
「そう言うな黒子。俺もひとりで行くのは不安なんだよ。店から追い出すのに行くんだからな。深夜までチャージされちゃ、遊興費がバカにならん。」
景虎はそう言いながら更衣室のロッカーを閉めた。目にはサングラスをはめていた。景虎は言った。
「最初はバーみたいなクラブだったんだが、そこを追い出されて今はバニーの店で遊ばせている。ま、ちょっとお子様向けでおまえらが入ってもそれほどじゃねぇから。」
「本当ですか?僕、すごく不安です。」
「そうだろうな。ふだんはマジバで茶ぁしばいているからなあ。」
「そうです。シェイクとハンバーガーしか食べた事ないです。」
「うん。ドリンクはジンジャーぐらい頼んどけ。ノンアルコールだ。」
「当然です。」
彼らは景虎の家の大型ワゴンで、六本木に向かった。リコや桃井たちの女性陣は危険なので乗り合わせていなかった。車の中で黒子は尋ねた。
「なんで彼らはクラブにいるんですか?」
「連中の希望でな。じゃないと、試合には出ねぇと言いやがった。」
火神が言った。
「ふざけた野郎だ。」
景虎は運転にしながら、停止中にハンドルの上にアゴを乗せて答えた。
「リコも怒ってるよ。わが家の家計にも響くってな。ま、それも今夜俺が釘を刺す。おまえらも拝見しとけよ。馬鹿にされたんだからなあ。」
「そうですね。」
黒子が答えた。
六本木近くの駐車場に停めて、彼らは問題の店に向かった。ピンクのネオンの小さな看板が出ているほかは、煉瓦パネルの外壁の目立たない外観のビルだった。外人向けというか、そんな感じだった。景虎が彼らの気に入るように合わせたのだろう。看板の英文字は「Pussy cats」と読めた。
扉から入ると、奥の観葉植物に囲まれたソファー席に、ジャバウォックの連中が陣取っているのが目に入った。大型テレビの前で、バニーの女性たちをはべらせている。しかし明らかにセクハラまがいの事をしているようだった。嬌声がこちらまで聞こえてくる。青峰は「ちっ」と舌打ちしたが、景虎は「まあ座れ」と言って、手前のテーブル席に七人を押し込んだ。バニー姿の女性が、回遊魚のようにテーブルに近寄って来た。
「なんになさいます?」
と、バニーの女性が床に膝をついてメニューの目録を差し出すのに、七人はちょっと目のやり場に困った風だった。黒のビスチェにはさまれて、女性の豊満な胸元が見えている。黒子はうわずった声で答えた。
「あ・・・・それじゃ、ジンジャーで。」
「かしこまりました。」
女性がいなくなった後、青峰は水を一口飲んで、こう切りだした。
「ストバスのプレイで相手をおちょくったりすんのは、珍しくもなんともねぇ。むしろハイテクニック、決めたらクールってなもんだ。しかしあいつらはそれしかやってねぇ。見下しる感じがモロに出てんぜ。そうだろ、火神?おまえも向こうでそういう事あったろ。」
「あ・・・・まあ、あったというか。青峰はストバスの経験があるのか?」
「まあ少しはな。」
「え、日本にいて?」
「るせぇ。」
その時、奥のソファーから一人の男がばっ、と立ち上がった。仁王立ちになっているのは、ジャバウォックチームのシルバーという黒人の男性だった。シルバーは叫んだ。
「聞こえたぞ、そこのこそこそしてるやつ!おまえら、今度の試合の対戦相手か?そうだな、ナッシュ?」
横の金髪の男性が薄笑いで答えた。
「俺の『目』にはそう見えているからな。俺たちの陰口をたたいているようだ。」
そう言ってナッシュはウィスキーグラスを豪快にあおった。シルバーががらがら声で叫んだ。もちろんそれは英語だが、黒子たちにもそのおおまかな意味合いは伝わった。
「帰んな、ボクちゃん!ここはおまえらがいていい場所じゃねーぞ?子供は帰ってミルクでも飲んでろよ。」
そう言うと、シルバーは横のバニーの女性の胸とお尻を乱暴にわしづかみにした。女性の悲鳴があがった。シルバーは巨体をゆすって笑った。
「お子様にはこんなまねはできねぇだろ?がははははっ。」
「・・・・もう、我慢ができません。」
黒子がすっ、と立ち上がった。
「お、おい、黒子。」
火神がびっくりした顔をする前で、景虎も立ち上がった。つかつかとソファー席に歩み寄ると、景虎は言った。
「おい、おまえらその辺にしとけ。そろそろ切り上げてくれないかな。ここは俺持ちで・・・。」
「あやまってください!」
景虎が言う横で、黒子が一声高く叫んだ。一同しん、となった。黒子は続けた。
「ここにいる人たち全員、いや日本でバスケをしている人たち全員にあやまってください!そしてあんな言葉取り消してください!」
ナッシュが黒子の言葉に反応したようだった。ぴくっと眉を動かすと、驚くべき事に、彼は流暢な日本語で黒子に返事をした。
「あやまってください・・・、それは、あのサルがバスケをするなと言った俺の言葉のことか?」
「そうです。あれは、ひどすぎます。」
「ふん、ひどいね。まあそう聞こえるように俺も言ったよ。それで闘志が余計に湧いたんじゃねぇか?おまえら黄色いサルにも。」
「また言いましたね。」
「言っちゃ悪いかよ。サルはどこまで行ってもサルさ。」
「取り消してください!」
「うるせぇっ!」
黒子の顔に巨漢のシルバーの拳がさく裂した。黒子はもんどりうって、テーブルをこかして床に倒れた。店中で悲鳴があがった。
「黒子!」
青峰と火神が憤って駆け寄った。青峰が押し殺した声で言った。
「てめぇら、俺らのチームメートになんてことしてくれんだよ?ああ?」
シルバーが含み笑いをした。
「おお、相手になってやろうじゃねぇか。ここでやんのかよ、てめぇ?」
「なんだと・・・。」
「やめろ。」
横から赤司が言った。
「騒ぎを大きくしない方がいい。黒子の手当ての方が先だ。景虎さん、店を出ましょう。」
「あ?ああ・・・。」
景虎はようやく事態を把握したようだった。
「すまん。おまえらを連れて来るべきじゃなかった。」
頭を下げる景虎に、赤司は言った。
「後悔先に立たずです。とりあえず行きましょう。」
「黒子は信じられない事をするのだよ。今ので口を切ったのではないか。」
「緑間くん、大丈夫です。」
緑間の助けでハンカチを貸してもらって立ち上がった黒子に、シルバーは罵声を浴びせた。
「なんだ?そんなことをしにわざわざこの店に来たのかよ?帰んなボク。ママのおっぱいでも飲んでろよなあ。ぎゃはははは!」
「Shut up! You scum.(黙れ!下司が。)」
赤司が言った。こちらも流暢な英語だった。赤司は続けた。
「You guys just be ready to lose.(お前たちこそ首を洗って待ってろ。)We’re gonna mop the floor with you tomorrow.(明日は地べたを舐めさせてやる。)」
シルバーは赤司の言葉におどけて舌を出した。ナッシュはやはり薄く笑っただけだった。かすかに「Sure.」と言っただろうか。そして座が白けたと言い、彼らは店を後にした。
帰りのワゴン車ではみな一様に無言だった。景虎は一言言った。
「・・・・・悪かったな。敵情視察のつもりが、とんだ事になっちまって・・・。」
黒子はハンカチで切った口を押えながら、言った。
「いいんです。僕がまたみんなの足をひっぱったんです。ただどうしても我慢ができなかったから・・・・。」
赤司が答えた。
「おまえはいつかもそうだった。おまえが言ってくれたからこそ、俺たちにもわかった事もあった。」
「赤司くん・・・。それはあの中学の時の・・・・。」
「おまえの言うことは、いつも正しい。」
そう言うと、赤司は黙り込んだ。
緑間は言った。
「このリベンジは試合でなのだよ。」
青峰も言った。
「ああ。見せてやろうじゃねぇか。サルの試合をよ・・・・。」
車外で街の灯が、遠くでぼんやりと点滅していた。
ラストゲーム
リベンジマッチの会場は、以前の屋外コートではなくて、屋内コートのショーアップした会場で行われた。リコはその会場を見て目が点になった。
「なにこれ・・・・。まるっきり鉄人番組みたいなノリじゃない。やっぱり見世物みたいね。」
会場の中央にはCMタワーが設けられていて、そこに日米チームの映像が映し出されている。会場も、観客がどこからか集められてたくさん入っている。四日前の試合では、それほど観客はいなかったのに、今回はまるでスタジアムだ。 煽るように、アナウンサーがマイクでアナウンスしている。
「ジャバウォックの前代未聞の侮辱から、高校生ドリームチームが名乗りをあげたぞ!その名も『ヴォーパル・スワード』! 『鏡の国のアリス』に登場する、怪物ジャバウォックを倒す剣だ!とくとご覧あれ!」
リコは景虎に言った。
「お父さん、とにかく第一クォーターはセンター中心で配置するわ。紫原くんね。」
「そうしてくれ。敵もでかぶつがセンターだからな。」
その通り、ジャバウォックのセンターは巨体のシルバーだった。リコの言葉に、ベンチの紫原が反応した。
「俺がセンター?俺ひとりでいいのにあんなの・・・・。」
「そうはいかないのだよ。」
と、緑間が言った。
桃井も心配そうにリコの配置図を見ている。ポイントガードが赤司、バワーフォワードが青峰、シューティングガードが緑間、スモールフォワードが黄瀬、控えにいるのは黒子と火神。これは、うちの総力戦だわと桃井は思った。これでだめなら後がない・・・・。
双方整列してのティップオフ(試合開始)前に、シルバーは煽るように言った。
「よう、腰抜けども。おむつはちゃんと履いてきたか?」
周りのジャバウォックの選手たちが歯をむいて笑った。キセキのメンバーたちは固い表情のままだ。そのままボールを審判が高く持ち上げた。GOのホイッスルが鳴った。紫原がシルバーとボールの第一投を取り合った。先制を制したのは意外にも紫原だった。シルバーは油断していた。紫原が鋭くはじいたボールは赤司に渡り、そのまま赤司はドリブルでナッシュを巧みにかわし、ノールックのバックハンドパスで青峰に渡した。青峰は華麗にダンクシュートを決めた。巧みな速攻だった。ナッシュの表情が少し曇った。意表は突かれたようだ。先制点に会場は一様に湧いた。青峰が言った。
「英語わかんねーつーんだ、ぼけが。プレイでわからしてやるよ。」
ジャバウォックからの攻撃になり、ニックがシュートをしたが、ゴール前で黄瀬のブロックにはばまれてしまった。黄瀬がはじいたボールは赤司に渡り、赤司は着地しないでパスを出すタップパスでまた青峰に渡した。青峰はガードに回ったアレンを抜いて、追いすがるザックにドリブル移動でボールを守り、隙を見てゴールに背面投げでシュートした。二度のダンクに会場は大歓声になった。リコは思わず叫んだ。
「お父さん!息が合ってる!」
「ああ。出だしは上々だ。」
景虎もうなずいた。
火神も言った。
「よぉし!行けるぞ!」
「青峰くん・・・・。よかった・・・。」
桃井は思わず涙ぐんだ。しかし次のジャバウォックの攻撃で、波乱の予兆はあったのだった。
「おい、早く出せ。」
と、ナッシュがジェスチャーでニックに言った。エンドラインのニックからナッシュにパスが出された。その前には赤司がガードを固めていた。赤司は「Come on」と言った。
「ちっ、サルが・・・・。」
とナッシュは英語で言うと、右、左とドリブルの向きを交互に素早く切り替えした。赤司はその乱れ打ちのドリブルに張り付いてくる。なるほど、こいつも少しは俺のように予測するようだ・・・とナッシュは思った。さっきから見ていると、こいつはルーズボールになりそうな球を、地道に拾って味方にパスを出している。この背の小さい赤司という男がいなければ、今の二度の青峰のダンクは実現しなかった。そういうやつか、とナッシュは思い、まったくのノールックからバックの方向にパスを出した。これには赤司もついて来れなかったようだ。意表を突かれたという形になった。
「赤司くんが抜かれた!」
とベンチの黒子は思わず拳を握った。ボールはシルバーの手に渡り、「あまいぜ!くたばりやがれ!」とジャンプしてアリウープに持ち込もうとするのを、紫原がブロックしてはじいた。それを緑間が拾い、エンドラインの手前からスリーポイントのロングシュートをした。ゴールまでは28メートル、普通ではまず届かない。
「甘いぜ、なにやって・・・・。」
と、ニックとアレンがにやついて見守る中、ボールはストンとゴールシューターにポストインした。
「ばかめ、今朝のおは占い一位は俺の蟹座だ。ラッキーアイテムのリモコンもベンチに装備、万に一つも落ちるものか。」
緑間が余裕でつぶやいた。ここで第一クォーターは終了、ヴォーパル・スワードが20でジャバウォックが8、リードは日本チームだった。
「みんなよくやったね。」
リコと桃井はベンチに戻った五人にタオルやドリンクを渡していたが、桃井は皆の憔悴ぶりに驚いた。帝光時代はもちろん、ウィンターカップでもこんな疲れた表情の五人は見たことがない。
「正直、驚いたっすわ。本場仕込みっていうのか・・・マジやばかったっす。ラストのみどっちのスリーに救われた。」
と、黄瀬がタオルで汗を拭きながら言った。
「ああ。相手にとって不足はねぇな。」
と、青峰が強がりを言った。
赤司は息を切らせながら、無言で向いのベンチを見ている。いや、その向こうだろうか。彼はその時呆然としていた。予想もつかない人物が観客席に座っている。いや、片方は予想していた人物だった。黛と小太郎たちだ。京都からわざわざやって来たのかと思った。しかし緑間の仲間の高尾も観客席には来ているのだから、当然なのかもしれない。問題は、その黛の近くの席に、あのトレーラーの運転手の男が座っていることだった。なぜだ、と思った次の瞬間男はこちらに回ってきた。と、ベンチの外側に座っている桃井の後ろまで男はやって来た。
「あ、すみません。」
と男がしゃべるのを赤司ははじめて聞いた。桃井に何か投げている。なんだ?と振り返ると、桃井は何かを拾って、男に手渡している最中だった。キャラクター商品の小さなぬいぐるみのようだった。赤司の心にざわざわとしたものが浮かんだ。母詩織を轢き殺した男。「すいませんね。」と言いつつ、男は桃井の腕を触っていた。桃井が困ったように笑って腕をふりほどくと、男は頭を掻いてまた「すみません」と言いながら、黛たちの席へと戻って行く。しかし。
赤司はその時、思わずベンチから立ち上がりそうになった。男が去りながらスマホのレンズで桃井を撮影していたからだ。
「?あかしっち、どうかした?」
「いや、何でもない。」
赤司はうつむいた。今は目の前の試合に集中しなければならない。黄瀬は少し赤司に不審に思ったように声をかけたが、すぐに紫原が不満げに「だーかーらー」と言っている方を向いてしまった。
その頃、ジャバウォックのベンチでは、ナッシュが「思った以上にやりやがるようだ」と言いながらドリンクを飲んでいた。シルバーは「そろそろ教えてやらねぇとな。力の差ってもんをよ・・・・。」と言って笑いながらドリンクホルダーを握りつぶしていた。やはり点差には腹立ちが収まらないようだった。そのシルバーにナッシュは軽くうなずいた。
「ま、今のは前座だ。これからだぜ本番は。少しはあいつらにも花つけてやらねぇとな。」と言うと、ナッシュはゴミ箱にドリンクをほうり投げた。
第二クォーターではシルバーが不気味に動き出した。まずシルバーは青峰とワンオンワンで対峙し、ドリブル攻撃で揺さぶりをかけ、進行方向を巧みに切り返して青峰の追いすがりを抜いた。
「なっ・・・・、青峰くんを抜いた?!」
黒子が瞠目する。青峰は速攻が得意な選手で、高校レベルではトップクラスと言っていい。その青峰が追い付けないシルバーとはいったいどういう選手なのか。見たところ彼は巨体で太っているのだが、その体は筋肉がほとんどなのかもしれなかった。しかしシルバーのゴール前で、同じく巨体の紫原がブロックに立ちはだかった。
「このぉっ!」
紫原は高くジャンプし、シルバーのボールを激しくはたいてブロックしようとした。しかしシルバーの渠力はそれを上回った。ボールは押し返され、ゴール縁にバウンドしながらポストインした。紫原はシルバーに押し出されて、その場で倒れた。
「あのアツシが押された!」
と、観客席の陽泉高校の面々も驚いている。水を打ったようにシンとしている観客席に向かって、シルバーは英語でがなり立てた。
「おいおいおいおい、ちょっと本気出したらそのザマか?つくづく貧弱でまいるな、サルは!ケガしねぇように、気をつけてやらねぇとな!」
がははと高笑いするシルバーに、キセキのメンバーたちも眦(まなじり)を決した。
「ここは絶対におさえねぇとな・・・。」
青峰が片腕で頬の汗を拭いた。
しかしシルバーの単独での猛攻は続いた。ヴォーパル・スワードの攻撃、パスが回り、ノーマークフリーだったポジションからボールを打った赤司だったが、フローターでボールを浮かせてシュートしたはずが、ボールを見てからジャンプしたシルバーに追いつかれた。バレーボールのAクイックのように、ブロックまでの時間差はあったはずなのに、シルバーはその瞬発力でボールに追いつき、赤司のシュートを阻止したのである。恐るべき俊敏さだった。それは赤司にとっては想定外の出来事だった。その体型から小回りは利かないものと決めつけていたのである。おまけに頭の方も機に応じて回転している。認識を新たにする必要があった。
ルーズボールとなったボールをナッシュが拾い、またシルバーにパスを回した。
「いけねぇっす!」
黄瀬と緑間があわてて後を追った。二方向からの挟み撃ちの追撃でシルバーを追う。普通ならばこの二人に追いすがられれば、ボールロストしていいぐらいである。しかしシルバーは軽く振り切った。シルバーが叫んだ。
「なんだなんだ、それで全速力か?!いいから指くわえて見てな!」
そして、フリースローラインから高くジャンプした。
「あのラインからのウィンドミルダンク・・・・!ありえねぇ!しかもボースハンド(両手持ち)で!」
火神が驚いて身を乗り出す。シルバーはボールを手の中で一回転させながら、ゴールポストにガゴォンと高らかな音をあげて放り込んだ。ものすごい勢いだった。彼はそのままゴール縁にぶら下がって、ポストを揺らしてからゆっくりと着地した。ゴールポストがシルバーの体躯で軋み、悲鳴のような機械音をあげた。
「俺の場合はワンハンド(片手持ち)でしかアリウープはしてねぇ。ボースハンドだとパワーは出るが、ジャンプの時の高さが出ねぇ。しかしやつはレーンアップしてあのダンクを・・・・。あんな離れ業、俺もやった事がねぇ・・・・。」
「火神くん・・・・。」
黒子も火神の驚きに同調した。
その時シルバーが両手を大きく広げて叫んだ。
「見たか!サルども!努力なんかでは絶対に埋められねぇ、これがおまえたちとの絶対的な力の差なんだよ!」
その時、審判の笛が鳴った。
「ヴォーパル・スワード、タイムアウト。」
景虎が休憩タイムを申請したのだった。
「あいつ、ムカつく~、ひねりつぶしたい・・・。」
ベンチ入りした紫原が、桃井の差し出すタッパーのレモンスライスをもぐもぐと食べながら言った。お菓子好きな紫原には休憩のレモンは必需品だった。景虎は言った。
「まあまあそれはこれからだ。とりあえずメンバーチェンジだ。赤司と緑間は、火神と黒子に交代だ。」
紫原が眉根を寄せた。
「えっ、それってさぁ・・・・。今の五人のままの方が・・・・・。」
「火神を入れてインサイドを強める。黄瀬、おまえが赤司の穴を埋めてボール運びだ。」
「え、俺っすか。」
黄瀬が自分を指さした。景虎はいたずらっぽく笑って言った。
「スーパーコピー人間なんだろ?」
「ま、そうっすけど・・・・。俺あかしっちほど手先が器用じゃねぇすから。」
「黒子もいるからな。二人でうまく連携しろ。」
「はい。」
黒子が答えた。紫原はまだ腹の虫が収まらない様子だった。
「俺ひとりであいつ倒す・・・。」
「紫原、監督の指示に従え。」
と、赤司が紫原に言った。
「おまえひとりだけでは絶対に勝てない相手だ。チームとしての勝利しかない。判断しろ。」
紫原は答えなかったが、赤司はきっと紫原もわかっていると思った。そしていつになく紫原が饒舌なのは、紫原の背丈と釣り合うシルバーという強敵が現れたものによるものと思った。いつもはほとんど袋のスナック菓子をもぐもぐやっていて、たまにしか口を開かない紫原なのだ。それが今日は試合開始時から言い募っている。赤司はひょっとしてこの試合、紫原にとっては水を得た魚なのかもしれないと思った。いつか帝光時代に、マネージャーだった桃井から言われたことがある。むっくんは、相手に不用意に怪我させないようにプレイしているんだって、と。その時はふうんと生返事をしたキャプテンの赤司だったが、今回そんな風に気遣わなくていい相手と遭遇したことは、紫原にとっては嬉しいことだったのかもしれない。表面上はむかつくと連発している紫原だが・・・・。
その時、赤司は向いの観客席にいるあの男の方をちらりと見た。そしてはっ、とした、男は赤司の方をまともに黒のキャップ越しに見つめている。気づいている・・・?そんなバカな、と赤司は思った。しかし桃井にあんな事をしていた男が、赤司の事も見張っていないはずはないのだ。そのつもりでこの試合を見に来たに決まっているのだ。と、男が右腕を中空に突き出し、指で何かのサインを作り赤司に向けて送った。「2―2―1」と読めた。赤司にはすぐにわかった。
「ゾーンプレス」・・・・。あれは、ゾーンプレスの数字指示サインだ。ゾーンプレスとは、ゾーンディフェンスの戦略方法で、コート上をゾーンで分けて攻防する。そのディフェンス方法に割り振られた数字だ。以前、「ゾーンに入る」という独特の言い方で、京都市内の喫茶店で緑間が文句を言ったことがあった。その時は赤司も不勉強だったが、バスケ用語のひとつなのである。しかし監督らは、禅の境地のような使い方であの頃「ゾーン」と言っていたから、赤司もすぐには気づけなかった。そして、有名なバスケ漫画にもゾーンプレスで攻めている場面が登場しているのである。あの男は、おそらく監督気取りで、赤司に見せつけるように「ゾーンプレスで攻めてみろよ」、とあざけっているのだった。その事実は認めないわけにはいかなかった。赤司の眉間が険しくなった。しかし今はベンチ入りしている身だから、黙って男からの嘲笑に耐えなければならなかった。
タイムアウトの後、試合はジャバウォックの攻撃から再開された。コート上に立つ黒子を見て、ジャバウォックのアレンとニックは「店に来てイチャモンつけたガキだぜ」と笑った。
「あんなチビっ子にいったい何ができるんでぇ。ショボすぎ。」
と、彼らは言った。しかしゲームが始まると彼らは黒子の姿をすぐに見失った。紫原がシルバーとボールの取り合いをはじめたからである。互いの隙を狙って押し合い、シルバーがなんとか紫原の左を抜いてドリブルし、ダンクを決めようとした。しかしそこを火神がブロックした。だがシルバーの手は強引にボールをポストへと押し戻す。そのままボールがシルバーの手でインしそうになった時、横から青峰が高くジャンプした。ダブルブロックである。
「誰がひとりでやれっつーたよ?おまえだけじゃ無理。」
青峰が言った。二人の手でボールがシルバーの制御から離れて、ポストからはじき出された。そこへ紫原が来てルーズボールを拾い、マークされていたセンターライン上の黄瀬にではなく、サイドラインに向かって投げた。ナッシュは一瞬パスミスかと思ったが、すぐに黒子の姿を目の端で捕らえた。
「あんなところに・・・・。」
黒子が完全に気配を消していたので、わからなかった。黒子は紫原からのパスを鋭くイグナイトし、先行してゴールに近づいている黄瀬へとつなげた。
「ナイスシュー、黒子っち!」
「ちっ、そういうわけかよ。」
とナッシュはつぶやいた。あの黒子というガキを常に視界の射程内に入れないとな、俺とした事が、と思った。瞬間ナッシュは黄瀬に向かって全速力で駆け戻った。
「戻り早ぇ!」
と観客席にいる誠凛の選手たちが目を剥いた。
「黄瀬、まだ戻せ!」
と青峰が言った。黄瀬にはアレンがマークについている。そこへナッシュが加わり、ダブルガードされそうになっているのだ。青峰の前にもナッシュが立ちはだかっている。しかし二対二のそこへ、火神が滑り込んだ。黄瀬は青峰に渡すと見せかけて、火神に向かってバッククハンドでパスを出した。赤司の得意技をまねた、それらは一瞬のことであった。
「よし、回せ!」
誠凛の選手たちが歓声をあげた。彼らは火神がインするとわかっているのだった。その通りで、火神は威勢のいい掛け声とともにポストインした。
「やったぜ!」
と観客席が湧いた。
青峰が言った。
「なんで俺に渡さなかったんだよ?」
黄瀬は答えた。
「だって青峰っちはあの時マークされてたじゃないっすか。」
横から火神が言った。
「俺が決めちゃわりいのかよ?まったく・・・・。」
コート上ではジャバウォックが口論ぽくなっていた。アレンが言った。
「おいシルバー、戻りおせぇぞ。紫のやつとやりあっていて、熱くなってんのはわかるが、ナッシュさんのディフェンスに加わるべきだったぞ。」
するとシルバーは「ああ?」と目玉をひんむいた。
「てめぇにそんな事言われる筋合いはねぇよ。さっきから俺ひとりでやつらをぶちのめしているだろう?」
と、見る見るうちにすさまじい形相になった。それを見てアレンは恐怖して黙り込んでしまった。シルバーは言った。
「いいから次もとっととボールよこせや。俺ひとりで十分だって思い知らせてやる。」
今度もジャバウォックからの攻撃で、またシルバーからボールが渡った。紫原と火神がマークするが、マークしながら口喧嘩をしている。
「ああやだやだ・・・よりによってこいつと共闘?ウィンターカップの時のこと思い出す・・・。」
「なんだよ、黙って合わせられねぇのかよ?」
シルバーがその会話を聞いて切れた。
「おい、てめぇら、なめてんじゃねぇぞ。」
しかし行く手をふさがれてしまったので、横からザックがシルバーに「こっちだ」と合図を送った。だがシルバーはぎょろりと目を剥いて、「手助けなんざいるかよ!」と叫んだ。
「こんなやつら、まとめて・・・ああ?」
シルバーはそのままゴールに向かって直進したが、
「だろうな、てめぇはパスしないと思ったぜ。単細胞が!」
バシィッと青峰がシルバーのボールをスチールした。シルバーも焦っていて、ボールを持つ手が緩くなっていた。シルバーは悔し気に叫んだ。
「クソザルが!」
「そのサルに出し抜かれてんじゃねぇか。お?」
青峰はそのままインしようとして、ナッシュのマークがすかさず入ったのでたじろいだところ、背後から「青峰くん!」という黒子の掛け声を聞いた。青峰は一瞬躊躇した。やはり自分でポストインしたかったのだ。しかし青峰はバックハンドでサイドラインに立つ黒子にまでボールを戻した。それを黒子が中継して、また黄瀬につないだ。黄瀬がゴールを決めて、ヴォーパル・スワードは連続得点となった。そこで第二クォーターは時間切れとなった。
「青峰くん、パス下手すぎです。」
「なっ?黒子、ちゃんと通ったからいいじゃねぇか。」
「いやいや、今のは黒子のおかげだな。」
「火神まで言うじゃねーか。」
「誰か俺のダンクほめてほしいっす!」
ベンチに戻るのも和気合い合いのヴォーパル・スワード側に対して、ジャバウォック側のベンチは荒れていた。
「クソザルがぁっっっっ!」
と開口一番、シルバーはスチール椅子を頭上に高く振り上げてぶち壊した。ナッシュが言った。
「シルバー、その辺にしとけ。経費が高くつく。」
「ああ?」
「まあ座れ。やつらの攻守がこの前半戦でわかった。後半戦はこうはいかない。俺が風通しよくしてやる。要はあのディフェンスを散らしゃいいんだ。」
「ナッシュさん、何か策が?」
とアレンが言うのに、
「今まで全開でなくて悪かった。後半戦は俺は全開で行くつもりだ。俺も『体調』があるからな。」
と、ナッシュは落ち着いた声で言った。そして全員に試合指示を出し始めた。
その様子を向いのベンチからじっと見ている緑間と赤司がいた。
「ナッシュ・ゴールド・ジュニア、どれほどの選手なのだよ・・・・。あのシルバーという男を今一瞬で黙らせた。あんなやつを黙らせるには、相当の実力がないとできない事なのだよ。」
緑間が言うのに、赤司もうなずいた。
「おまえもそう思うのか。」
「ああ。やつは前半戦では全力を出し切っていない。俺にはそんな感じがするのだよ。」
「同感だ。」
赤司は緑間にそう答えると、観客席の方をも観察した。あの男がまた指で数字を差し示し、拳を返してno goodのサインを示していた。男の表情は笑っていた。俺はあいつにもなめられている。今はまだ二ゴール差だが・・・。赤司の孤独な戦いは続いていた。
十分間のインターバルの後、第三クォーターが始まった。黄瀬はナッシュに対峙していた。そのワンオンワンでマークしていた時、ナッシュはまったくの予備動作なしに味方にパスを渡した。黄瀬はその時、ナッシュが何をしたのかわからなかった。ただ見ているだけだった。
「予備動作がまったくない・・・・。第一クォーターで俺が抜かれた時の技だ。」
と、見ていた赤司が言った。
緑間は言った。
「そんな事が可能なのか?普通ならば必ず制動の動作は出てくるはずなのだよ。」
「いや、あいつにはそれがない。やつはストバス育ちの選手ではない。おそらく正規のバスケの鍛錬を積み重ねている。あのストバスみたいな技は、そのカモフラージュだ。やつのサルという発言も・・・・・。」
と、赤司は言い淀んだ。緑間は尋ねた。
「何かあるのか、赤司?」
赤司は少し笑って言った。
「中学の時に、あの床の固い体育館で、足をがに股のように広げてジャンプする練習をした事があったろう?ジャンプ力を養うための訓練だった。」
「ああ。あったのだよ。あれは苦しかった。うさぎ跳び並みだったのだよ。」
「うさぎ跳び以上だ。あれは、向こうでは『モンキー・スタンス』という呼び名なのだそうだ。」
「モンキー・・・、なんだって?」
「だから、そういう事だ。やつは俺たちの実力を試している。こちらのディフェンスがあの技でラインから崩れるぞ。相手の動きが予測不能なんだ。」
「そんな・・・・・、赤司、貴様は冷静すぎる。」
「事実を指摘したまでのことだよ。」
「予測不能・・・・、しかしお前は俺との試合の最中、『エンペラー・アイ』で俺たちの動きを予測した事があった。おまえが出れば事態は改善されるのではないか?」
「予測できればの話だ。その俺の呼び名はおかしいし、俺にはそんな予知能力はないよ。つまり、出口なしというわけだ。これから点差は開く。」
「赤司、おまえは・・・・。」
緑間はうなって黙り込んだ。コート上ではシルバーがさらに勢いを増して、ナッシュからのマジックのようなパスを次々とダンクに決めていた。紫原や火神がブロックしようとするが、ゴール前でシルバーに蹴散らされた。これまでと圧がまったく違っていた。火神はこれが野生というものかとほぞをかんだ。黄瀬・青峰・紫原は三人でナッシュにマンツーマンでついたが、無駄だった。彼らをあざ笑うかのように、背後にいるシルバーに巧みにパスが回された。紫原はそんなシルバーを止めようと、ゴール前で無理にブロックして、シルバーに弾き飛ばされ額に軽い怪我を負った。審判の笛が鳴った。
「レフェリー・タイム!」
怪我の応急処置のため試合が中断された。中断の時、ナッシュはヴォーパル・スワードを見回しこう言った。
「さすがにサルでももうわかったろう?俺がちょいとパスを出しゃ、それでもう終わりなんだよ。おまえらがあの手この手であがこうが、俺たちを止められねぇ。要は格が違うってことさ。ここからは思う存分歯ぎしりして、絶望してくれ。」
黒子がにらみつけて言った。
「紫原くんを怪我させておいて、その言い方って・・・・・。」
「怪我しないのも、技術のうちだよな?」
と言って、ナッシュははっ、と笑った。
その時、景虎が審判に言った。
「ヴォーパル・スワード、メンバーチェンジを申請する。黒子、赤司と選手交代だ。」
「え・・・・。」
黒子は驚いて目を見張った。
「遅きに失したな、今頃かよ。ま、がんばれよ。」
と、ナッシュは言うと向こうへ行った。赤司は無言で立ち上がった。緑間は言った。
「赤司、できなくとも先読みはしてくれ。あの時のように。」
緑間が言っているのは、赤司に敗北したウィンター・カップの試合の時のことだった。緑間の必死の気持ちに、赤司は答えた。
「ああ。努力してみる。」
赤司は黒子と交代して、コート上に立った。ジャバウォック61、ヴォーパル・スワード42。その点差は19。
発現
試合再開前、景虎は言った。
「黄瀬と青峰、おまえたちはダブルチームでシルバーに当たれ。黄瀬はスーパーコピーで・・・・。」
「それ、まがいものって意味っしょ?俺のはパーフェクトコピー。」
「ああ、それだな。それで当たってくれ。」
「簡単に言ってくれちゃいますね。あれ時間制限あるんだよな。」
「ゾーンプラスパーフェクトコピーでなんとかしてくれよ。」
「ゾーンね、入れるかどうかわかんねぇすけど。」
と、黄瀬は言いながら軽くウォーミングアップした。紫原の手当ての時間をはさんで、再び試合開始になった。
ベンチに戻った黒子は緑間に言った。
「赤司くんには、コート上のメンバーをゾーンに入れるだけの力があります。」
緑間は答えた。
「そのゾーンには俺は懐疑的だ。そんなあやふやなもの、どうやって信じる?所詮バスケ技術の実力しかないのだよ。」
「あの対洛山戦の時、赤司くんたちは確かに変わりました。」
「それは精神論だろう?黄瀬の精神力がどこまでもつかという話ではないか。だいたい赤司から伝染してそういうものが他人に乗り移り開眼するなど、非科学的としか思えん。」
「緑間くんはそう言うますね。」
「当たり前なのだよ。俺に言えるのは、赤司の試合に対する予想見が当たることだけなのだよ。それは俺自身も洛山との試合で、しかと目にしたからな。」
緑間はそう言うと、不機嫌そうに黙り込んだ。試合は前半と同じく、ジャバウォックのリードで始まっている。ただし、赤司が入ったことで、空気は変わったようだ。シルバーは前半戦のように力押しで行こうとしているが、マンツーマンで黄瀬と青峰が張り付き、さらにバックに赤司が固めていて、やりにくい事この上ない。黄瀬と青峰はシルバーのドリブル移動に、互いに前後しながらついて来る。そのディフェンスラインの後方に赤司が存在する。と、青峰に気を取られた隙に、黄瀬はシルバーの隙をついてボールをスチールした。鮮やかなバックチップだった。
そのボールは赤司に渡ったが、その時ナッシュが赤司の前に立ちはだかった。赤司は紫原への連携をあきらめて、黄瀬に渡した。パスを出しながら、
「戻れ!」
と赤司は鋭く叫んだ。見ていたリコは怪訝そうな顔になった。
「赤司くん、どうしてあきらめたのかな・・・。」
桃井が答えた。
「赤司くんはああいう時、安全策を取る人だから・・・。」
「そうなのかな。あのナッシュをよけたんじゃないかな。臆しているんじゃない?」
「そんなこと・・・・。」
桃井は不安になって、コート上の赤司を見た。故障が治ったばかりの青峰の方ばかり第一第二クォーターは気を取られていて、赤司がベンチに下がったこともあって、桃井はよく彼を見ていなかった。そう言われれば不安になった。緑間とさっき何か話していたようだが、その内容は深刻そうだった。赤司をいつもじっと見ていなかったのは、赤司に対する羞恥心だった。大切に思い過ぎて、目に入れるのがためらわれるのだった。しかしそれではいけないと、桃井は意を強くした。これからは彼の一挙一投足を見ていなければと思った。
と、コート上のニックが進行して来る黄瀬に対して、立ちはだかろうとして足をもつれさせ、尻もちをついた。
「まさか、アンクルブレイク?!」
とリコが叫んだ。
「洛山戦の時の・・・・。パーフェクトコピー?」
黄瀬がコート上で気勢をあげていた。
「俺にもできたっす!」
「行かせるかよ!」
ナッシユが素早く横に着く。青峰がその時手をあげ、黄瀬からパスをもらい、シュートに入った。
「がぁあああああっ!」
シルバーが叫びながらブロックで視界いっぱいまで迫ってきたが、青峰はそのシルバーをよけて斜めに倒れながらバックゴールの背面からボールを投げた。ボールはゴールを飛び越えてから、見事にポストインした。
「やったあ!」
と、観客席の日向たちは湧いた。
「なんだかさっきと空気が違うわね。どうしてかしら。彼が入っただけで・・・。」
リコは言った。まだ点差は開いているが、少しでも反撃ができたのだ。それは奇跡と言ってもよかった。桃井は少し涙ぐんでいた。彼女には赤司が入ったことで反撃できたように思えたのだった。
「うん、そうだね・・・・。」
「がんばれ、黄瀬くん!青峰くん!」
と、桃井の前のベンチから、黒子がコート上に声援を送った。
(なんだ・・・。さっきと違うな・・・・・。俺が封じているつもりなのに、封じられている・・・?)
ナッシュはコート上に立つ赤司を見た。さっきパスを回そうとしていたのを、妨害したらあっさりと後方に赤司は渡した。そういうトライアングル攻撃はよくあるパターンだが、赤司のそれはほとんど考えている暇がない。こいつは考える前にすぐに次の動作をしている。俺の予測不能のパス回しのひょっとして上を行くのか・・・?いや、そんなはずはない。だいたいダブルチームでシルバーに当たって、開いたディフェンスの穴を、センターの紫のやつだけで埋めるのは難しい・・・いくらガタイがでかいやつでもな・・・。
ナッシュはボールをキープしながら、赤司の目の前で、やはり予備動作なしでサイドラインのあいたエリアに立つアレンに渡した。ほら見ろ、今も手も足も出なかったろ、とナッシュは思った。この程度で音をあげているやつに、臆する理由なんざ何もない。そう考えた。アレンはバックステップで華麗にシュートを決め、さらにまた得点した。この第三クォーターの後半はこのような互いの点取り合戦になった。
「これじゃらちが開かねぇ。」
と、青峰が言った時、黄瀬が言った。
「ダブルチームはここまでで解消っしょ。俺さっき赤司っちのコピーが成功したから、やれるような気がするんす。」
「やれる気がするっておまえ・・・。」
「そ。ゾーン解放。全力でやってみるっす。パーフェクトコピー。それで五人分がんばるっす。」
青峰は黄瀬の言葉に動揺して言った。
「やめろ、おまえそんなことしたら、二度と出られなくなる・・・・。」
黄瀬は笑ってこう言った。
「いいんす。この試合で終わっても別にいいんす。だって俺、馬鹿にされて黙ってられないって、みんなに言われたから・・・スマホで試合前に。」
「俺みたいに故障になるぞ?」
「俺っちのラストゲームっす。見ていてくれっす。あざっす。」
黄瀬は言うなり、全開で突進をはじめた。シルバーの追撃のブロックをかわし、次々と得点していく。それはすさまじい勢いだった。見ている黒子たちにも、その技が、青峰・紫原・火神などの得意技のパーフェクトコピーなのは、すぐにわかった。黒子が驚嘆して言った。
「今の黄瀬くんは、無敵です。」
「だがもって数分なのだよ。あんな攻撃の仕方、スタミナがもたないのだよ。しかし今コート上で最強なのは、ジャバウォックのやつらではなく、間違いなく黄瀬だ。」
緑間は沈痛な面持ちで言った。
「・・・・っ!」
ついに黄瀬が一歩も動けない状態になった。これ以上は無理だと黄瀬自身も思った。しかし彼のおかげで点差は縮まっていた。そして第三クォーターは終了した。
「よくやった。選手交代だな。黄瀬の代わりに緑間だ。」
と、景虎は言った。その後ろでナッシュたちが軽口をたたく。
「結局ガス欠かよ?ざまぁねえな。」
黄瀬は赤司に言った。
「なんかできる気がして・・・・・俺でもがんばれたっす。ここまでしたんだから、勝ってくれっす。」
「わかっている。」
赤司は黄瀬の肩に手を貸して答えた。そのコート上の様子を、観客席で見ていた黛千尋は言った。
「俺の時と同じだな。」
小太郎がけげんそうな顔をした。
「同じって何がです?」
「あの黄瀬という選手は相手の技を盗む特徴のある選手だった。今赤司はそのきっかけを与えてやった。」
「え、赤司さんは何もしていませんよ?」
「おまえにはそう見えるな。」
「黛さんにはそう見えるんですか?」
「見えるな。」
「どうしても試合を見たいと言うから、黛さんとわざわざ京都から来たけど、これは負け試合になるのかなあ・・・・・。」
「勝敗はどうでもいいんだよ。俺は試合中のやつを見たかっただけだ。」
「そうなんですか?京都でも練習試合で見ていたでしょ?」
「馬鹿、それとは違うんだよ。」
黛はそう言うと、眼下の席に座っている男を注視した。さっきこいつはベンチに座る赤司に、ゾーンプレスらしい数字サインを送っていたな。ひょっとして知り合いか?赤司も少し動揺していたようだ。あれで赤司が揺れなければいいが。いや、そんな事はおそらく全然ないだろう。今の黄瀬の使い捨てみたいなやり方は、本当にあいつらしいやり方だ。しかしその考えは黛は小太郎には打ち明けることはなかった。あいつらしい・・・・・、黛だけはその赤司を知っている。手段を選ばないところが赤司にはあるのだった。そして桃井や黄瀬のような人のいい連中は、それには決して気づけない。やはりこの試合でも口を開けたか、と黛は思った。そのぞっとするような魔の口を見たくて、俺はあいつにこだわっているのだろうな、と黛は思った。それは黛にとっては目をそらせばいいのに、つい見てしまうような何かだった。京都駅前の喫茶店で赤司と会話した時に、その片鱗を感じたので、彼は上京することにしたのだった。それでバイト代何日か分かが旅費に消えても、黛にとっては惜しくはなかった。
さて、その黛の観点では赤司はそうした人物であったが、当の本人はそんなつもりはなかった。今言った事は非常に黛らしい話と言える。彼はもともとそうした狭量な視野の持ち主だったので、美少女系ライトノベルという偏った文学ジャンルに過剰なこだわりを見せたりしたのだった。そして己れの観点が少しいびつであるという事は、なかなか当人にはわからないものである。ただ黛が思ったことは百パーセント間違いではない。しかし正しくもないものである。赤司が黛が感じたようなある種の殺意を持った人物であるというのは、状況から見て確かに正しい。だが黛が考えている赤司の人物像は、赤司本人とは微妙にずれている。そのような人間関係で彼らは最初からつながっていた。言うなれば、人間への不信感と絶望感のようなものが、黛の心のどこかを覆っているのである。従って彼は、普通ではリアルな人間には「到底見えない」美少女のキャラクターの出てくる小説を愛読しているのだった。赤司の前では強がって見せても、それが黛の真実であり、赤司もそれを見抜いているので、京都駅前の喫茶店では言い合いになったのだった。そしてそういう具合に人間への不信感が通底にあるので、赤司の挙動にもすぐに不信感を抱いたと言ってもよかった。
では赤司は黄瀬のゾーン発動の時一体何を考えていたのだろうか。彼はもちろん、黄瀬を使い捨てになどするつもりはなかったし、彼としてはかねてからの懸案事項である、「彼」と呼んでいる何者かに、必死でコンタクトを取ろうとしていた。このような熾烈な試合中での想念であるから、常人ではほとんど無理なことである。しかしそのかけらのような想念の夾雑物を感じた時、黄瀬が自分のウィンターカップで発動した、あのアンクルブレイクを仕掛けることができた。赤司としては、それで黄瀬が限界まで発動できた事は、試合の流れから言っては喜ばしいことであったが、彼としても真の目的は試合の勝利ではなく、「彼」との共闘関係を築くことであったから、黄瀬が限界値を超えてしまう事は嬉しいことではなかった。黄瀬がこの事で故障などの怪我に陥る事は、赤司にとっては悲痛に思えることだった。従って彼はインターバルで移動中に、黄瀬に肩を貸したのである。自分の異次元の何者かとのコンタクトのせいで、黄瀬に「何か」を及ぼしたというのならば、その責任は自分にあった。それを「乗り越えて」でも自分はあの男に復讐がしたいのか、と思った。だがあの男はまだ自分をあざ笑っている。赤司はひとり、「何者か」に心の中で語り掛けた。おまえはなぜそんな風にしか俺に手を貸さないのか、と。おまえは俺に悪意があるのか、と。あのウィンターカップの試合中でもそうだった。おまえは俺を手の内で転がして、喜んでいるだけなんだろう、と。
と、その時赤司の心に何者かが語り掛けてきた。その声は甲高い少年のような声だった。声はおろおろと言い募った。
(――だって君は、殺人したいって願ってるだろう?それはやっぱりいけない事だよ。詩織さんは果たしてそんなことして喜ぶかなあ?確かにあいつは悪いやつだけど・・・。)
赤司は必死に心の中で言った。
(おまえ!手を貸すのなら俺にしないか!黄瀬がつぶれたらどうする?!)
(わかったよう・・・・。ボクも困ってるんだけど・・・・。君はこの先いろいろと・・・。)
(かあさんを知っているのか?)
(知ってるよ。ボクの飼い主だったもの。詩織さんは優しかったよ。ボクを大切にしてくれたんだよ、すごくね。)
(かあさんは何も飼っていなかったけど・・・。)
(君の生まれる前さ。詩織さんが高校生の時だよ。その時の、ボクは飼い猫さ。)
(猫なのか?!)
(そうだよ。君が詩織さんがいなくなって寂しいって思った時にね、やって来たの・・・・。どうしてかボクも知らないけど・・・・。ボク、ピート。じゃあまたあとで。試合、まだあるでしょ?)
「待て!俺に力を・・・・!」
この最後の言葉は、赤司は思わず口をついて出たので、周りにいたメンバーが不審な顔になった。「なんでもない」と赤司は口を押え、心の中で言った。
(第四クォーターでは俺に味方しろ。頼む。おまえの意図はわかったから。)
(じゃあ、ちょっとだけだよ・・・・。ゾーンディフェンスで攻めてみて。それなら君にもできるでしょ?)
(ああ。)
(君の力は君自身の力だよ。ボクはそれを少しドアを開けるだけ。ボクにたよらないでね。じゃ。)
ピートというのか、と赤司は思った。母詩織の飼っていた猫だったとは。それで最初に出会った時、食い殺すといいよ、などと言ったらしかった。ピート、どこかで聞いたな、と思い思い出した。ハインラインの『夏への扉』だ。詩織もあの小説が好きだったのだろう。赤司の胸の内に、高校生の詩織が高校の教室の窓際で楽しそうに、猫の表紙のSF文庫のページを繰る姿が思い浮かんだ。それはつかの間のほっとするような陽だまりだった。
第四クォーターが始まった。ナッシュはコートに立つ赤司を見て、少し異変に気付いた。左右の眸の色が違っている。確か両目とも赤色だったはずが、左目がわずかに琥珀色に色づいている。肉食獣の眸の色のようだった。雰囲気も少し違うようだ。しかしナッシュは打ち消すように赤司に言った。
「・・・・残念だったなあ。これで状況は元通りだ。ムチャしたところで結果は変わらねぇのによぉ。無意味な努力、ご苦労様だぜ。」
赤司は相変わらず、ナッシュに対して丁重な英語で答える。
「元通りでも無意味でもない。涼太は次につながる仕事を十二分にしてくれた。」
「そうかよ。手も足も出ねぇくせに!」
と言うなり、ナッシュはキープしていたボールを、予測不能のパスで送り出そうとした――そのはずだった。次の瞬間、ボールは赤司の手によって素早くアウトサイドに弾かれていた。目にも止まらぬ速さだった。
「なっ・・・・・?!」
「アウトオブバウンズ、黒ボール!」
判定の笛が鳴った。ナッシュは呆然となった。自身が絶対の信頼を置いていた、あのパス回しがたった今破られた。そんなバカな、予備動作なしで、予測不能のはずだ!
赤司は言った。
「アウトにしてしまったか。しかし次は殺(と)る。絶対は『僕』だ。」
「なんだと?てめぇ・・・・。」
口をゆがめたナッシュに、赤司は冷然と答えた。
「頭(ず)が高いぞ。」
「てめぇがチャチなんじゃねぇのか?なめるな!」
その時ナッシュの脳にとある「可能性」が出現した。もともとこれは、内うちには「そのための」試合だったのだ。しかしこんな小さいやつがという思いがあった。自分がこいつの能力を目覚めさせるための、単なる「触媒」だというのは認めがたい話だった。今破られた予備動作なしのパスだって、ナッシュは人知れず血のにじむような努力をしてきたのだ。その頃のトレーニングを思い出したくもなかったから、「モンキー・スタンス」にあやかって、日本人選手を「サル」呼ばわりしてきた。それがこんなやつに破られる。それだけは、ナッシュの「あの忌まわしい過去」からの沽券にかかわることだった。
とにもかくにも、こいつにも俺同様の能力があるか、試してみないとな・・・、とナッシュは思い、ドリブル態勢から巧みに赤司の横をすり抜けてシュートしようとした。しかし赤司はぴたりと横に張り付いて来る。やはりついて来やがるか・・・、しかしこれは獲れまい?と、ナッシュはものすごい速さで飛び上がった。その瞬間、バシッと音がして、ボールは赤司の手にスチールされていた。
「なにっ?!」
弾いたボールをそのままキャッチして、赤司は猛全とドリブルでダッシュした。
「行かせるかよ!」
その前にザックが立ちはだかる。しかし、赤司は「どけ」と言った。ザックは自分の膝が動かなくなったことを感じた。まさかの脱力だった。がくりと膝をついたザックに、赤司は冷たく言い放った。
「これは命令だ。『僕』の命令は絶対だ。」
「う・・・・、あうう・・・・・。」
ザックは膝をついた態勢で力なく呻いた。
ナッシュはその様子を見て思った。やはり持っていやがる・・・俺の「ベリアル(魔王の)・アイ」同様のあの目をこいつも?!ナッシュは括目して見た。しかもこいつの場合は、相手を意のままにする能力まで備えているのか?そんなバカな、ありえるはずがない。いくらこいつにだって、できない事があるはずだ・・・!
その通りで、赤司の前方にアレンが立ちはだかり、ブロックしたので、赤司はタップパスで火神にパスを回した。火神はがら空きになっていた空間でゴールを決めて、得点できた。
ナッシュはそこで仲間に言った。
「次を警戒しろ。前半戦でスリーをやりやがった緑のやつが出てくる。ダブルで貼り付け。早くしろ。」
素早くザックとニックが緑間にダブルチームで張り付いた。ゴール下にはシルバーが立った。その後は赤司から火神にパスが回され、赤司と紫原がシルバーのブロックを越えて二人の時間差攻撃でシュートを決めた。得点は10点差にまで縮まった。そこで二度目のタイムアウトが取られた。
景虎は言った。
「緑間は警戒されているな。できるか、スリー?うちの長距離砲で縮めるしかなさそうなんだが。」
緑間は答えた。
「人事は尽くすのだよ。」
火神は言った。
「しかしダブルチームで来られているからな。」
そこで赤司は言った。
「できるか、真太郎?」
「無論だ。おまえも調子が戻ってきている。」
「ああ。なんとかな。」
赤司は答えた。その時、赤司の頭上でピートの声がした。
(ちょっと飛ばし過ぎだったかも・・・・・。あの「頭が高い」って君のお父さんのセリフだよね?子供の頃君を叱った時のさ。)
(そうだけど?やつらにはあれぐらい言ってもバチは当たらない。)
(僕はさ、君の能力を操舵しているけど、あんまり解放しない方がいいんだ。君のキャパ越えになるし・・・・。そうなった場合帰ってこれないかも・・・・。)
(黄瀬のようにか?)
(ううん・・・・。それと、バスケの試合ならいいけど、人殺しはだめだからね?)
(おまえは詩織かあさんが轢き殺されてもよかったのか?)
(だって詩織さんはあの時ね・・・・。あ、今は言わない・・・・。)
ピートはそういう具合に赤司の心を触ると、またぱっ、と横に逃げた。本当に猫みたいなやつだなと思った。しかしピートが加勢してくれたので、不安だった赤司の心は落ち着いてきていた。何よりも自分の味方がいるという事は心強いことだった。能力の方も、赤司が思ったように反応してきている。これならいけそうだと思った。
ゲームが再開されて、観客席の高尾は「っとに勘弁してほしーわ」と言った。隣の者が不審げに高尾を見ると
「俺、わかっちゃったんすよね、この先の展開が。ま、この局面ならそれしかねぇか。」
と高尾は腕組みして言った。
「ひょっとして、おまえと緑間の空中装填式パス・・・・。」
高尾は大きくうなずいた。
「それっすよ。しかし緑間と俺との息がぴったり合わねぇとできねぇ事が、敵だった赤司なんかにできるのかねぇ。できたらできたで腹が立つっつうか・・・・。あの洛山戦での試合での事が。」
「なるほどね。」
「真太郎はどう思っているのかねぇ。やっぱ帝光でのつながりが強いか。」
と、高尾は言った。
緑間にはやはり二人のダブルチームがついている。その周りには誰も味方は寄り付くことができない。が、不意に緑間は空中にトスをあげる要領でポーズを取り、ジャンプした。その踏み込みは高い。ナッシュは思った。ボールもないのに無駄な動き、と。
その時後方でうまく赤司がボールを確保して、緑間にパスを出した。それはナッシュたちの一瞬の隙をついた出来事だった。というか、ラインあたりでジャンプした緑間に一瞬気を取られてしまっていたのだ。まさかボールがスチールされているとは思わなかった。赤司のパスは緑間の手にすっぽりとはまり、そのまま緑間はスリーポイントシュートを決めた。まるで手品だった。
「完璧だっつーの!今日の真太郎は落ちねぇぜ。」
と、高尾は緑間のシュートに誇らしげに言ったものだった。
その後は緑間と赤司の連携でのスリーポイントシュート、火神のシュートなどで点差がじりじりと縮まってきた。ナッシュは思った。ここらで俺も「本当に」全開にならないといけねぇな、と。
「・・・・おい。」
と、クォーター後半にさしかかり、ナッシュは赤司の前に立ってドリブルしながら言った。
「おまえには確かに何かの力があると見た。しかし俺のような目はねぇ。俺には予備動作がない、そして俺はおまえたちすべての動きの予測が可能だ。おまえには『エンペラー(帝王の)・アイ』があるらしいな。調査書にはそう書いてあった。」
「調査書?」
「そうだ。俺のはそれに相当する『ベリアル(魔王の)・アイ』がある。そう名付けられた。忌まわしい禁忌の眼だ。おまえのもそうだろ?俺のはおまえ以上だ。」
「・・・・・・。」
「俗に言う、邪眼で見られた者は呪われる。おまえも呪われるといい!」
言うなり、ナッシュはバックチェンジから右にボールを持ち変えようとした。赤司の判断ではそうだったが、ナッシュは素早く切り返して左にボールを移して赤司の傍を抜いた。それは一瞬の出来事だった。俺が予測された?赤司はナッシュが手を持ちかえる瞬間スチールしようと手を伸ばしていた。その針の穴を通すような一瞬を、ナッシュは回避したのだった。そしてそのまま移動して、ナッシュはニックにパスを出した。そのパスも、予測できないもので、紫原は手前にいたのに出し抜かれた。
(これからはこの調子になるのか・・・・。)
赤司は唇をかんだ。今のニックには緑間がついていたのだ。その一瞬の隙をついてナッシュはパスを出していた。それは赤司の目にははっきりと解析された。普通では見落とすような事であった。ナッシュの今言ったことは、決してはったりではない。コート上の俺たちの動きすべてを分析し、それに応じてオフェンスを出している。赤司の見ている前で、ジャバウォックはまた得点した。
そして次の攻撃では信じられない出来事が起こった。赤司がナッシュにアクルブレイクでこかされたのだった。その脱力は突然の出来事で、赤司も自身に何が起きているのかわからなかった。無様に尻もちをついた赤司にナッシュは言った。
「おまえの未来予測はせいぜいひとりだけだろう?俺は試合全部を予測できる。俺にはこの試合の未来が見えている。」
「なに・・・・。」
「ありえないって顔だな?だがありえるんだよ!おまえらの努力は無駄なんだよ!」
赤司はナッシュの顔を思いきりにらみつけた。
その時、後ろで見ていた紫原が片手をあげて、「ちょっとタイム」と言った。そしてベンチに向かって「リコに桃ちん、ゴム貸して」と言った。桃井は今の白熱した試合に呆然と呑まれていたが、はっ、と我に返り、上着のポケットから髪ゴムを取り出して紫原に差し出した。桃井は渡しながら尋ねた。
「むっくん、どうして?」
「髪がさっきからばさばさだったんだよねー。伸びすぎてて。」
と、紫原が言った。しかしそれは口実だったのだろう。
「よし、これでまとまった。」
紫原はそう言って髪を後ろでくくると、元のポジションに戻っていった。そして驚いている赤司に手を伸ばして起き上がらせ、こう言った。
「らしくないよ、赤ちん。次から俺にボール回して。あのシルバーだけでも止めてみせるから。」
「できるのか?」
「あんなやつの言う事、真に受けちゃだめだよ。赤ちんは英語できるから、いちいち理解してショック受けてるんだよね~、無視だよ、無視~。」
と言った。そして、
「桃ちんの前で尻もちつくのはカッコ悪いよ~。俺と中学でやりあった時みたいだよ~。」
と言った。
「そうだな・・・・。」
と赤司は紫原に笑った。
その後の展開は、緑間と赤司の装填式スリーポイントシュートがナッシュに完全に封じられ、ボールは紫原に渡ることになった。紫原はゴール近くでシルバーと執拗なブロック合戦を繰り広げた。どちらもボールをゴール前で押し合い、譲らないのである。その力と力のぶつかり合いは、すさまじいものだった。仲間が思わず呑まれて見ているうちに、シルバーは「なめるな、サルがぁあああっ!」と力任せに紫原を叩きのめした。しかし紫原は渾身の力を振り絞って二度のダンクを成功させた。
もう一度のダンクを成功させた時、シルバーは紫原がシュートから着地した瞬間に大きく腕を振って、それは紫原の顔に当たった。紫原は態勢を崩して左腕を下に着地し、全体重を受けて骨折してしまった。それは突然の出来事で、誰もが予想していなかった事だった。
レフェリーストップがかかり、あわててベンチから駆け寄ったリコと桃井、景虎が紫原の腕を診る。
「だめだ、骨折してやがる・・・・。」
景虎は首を振った。
「すぐに救護室へ!」とリコが言う。それを紫原は押して、コートに戻ろうとする。横で火神が切れていた。
「ざけんな、わざとやりやがったな!」
シルバーは首を傾げた。
「ああ?事故だ事故。勝負ってのはな、最後まで立ってたもん勝ちなんだよ。」
「なんだとてめぇ・・・・。」
火神が怒って言うのに、紫原も同調する。
「まだ俺やれるよ。あんなやつ、たたきのめしてやる。」
その時、二人の前に小さな影が立ちはだかった。
「だめです。紫原くん、火神くん。紫原くんはその体で試合を続けるのは危険です。取返しのつかない事になりますよ。」
黒子だった。
「キレているのは僕も同じです。僕が出ます。いいですね、景虎さん?」
「あ、ああ・・・・。」
景虎は黒子に鷹揚にうなずいた。黒子の気迫に呑まれたのだった。
「なんだチビ、おまえが出るのか?」
ナッシュが言うのに、黒子はうなずいた。黒子は言った。
「あなたが試合の未来が見えるというのはなんとなくわかりました。英語でしたが。しかしそれは、確定された未来ではありませんね?」
「なんだ?確定された未来だと?」
「そうです。あなたの見ているものは、単なる予測です。たくさんある未来のうちのひとつの結果に過ぎない。これからそれを証明して見せますよ。赤司くんと。」
「なに?」
「そうでしょう、赤司くん?」
赤司は答えた。
「あ、ああ・・・・。」
ナッシュは眉をそびやかした。
「なんだ?多次元宇宙論か?」
「日本語なかなかうまいですね。」
「うるせぇ。こっちが絶対に勝つって決まってるんだぜ!」
その通りで、再開後の試合はしばらくは黒子が入ってもナッシュたちの優勢だった。ウォーパル・スワードは紫原のセンター中心が抜けたので、3―2のゾーンディフェンスで守りはじめた。しかし黒子のいる手薄のサイドにボールが回り、そこから徐々に糸口が開いていく。赤司は敵陣のラインを崩すべく、相手の間合いに入るようにした。ニックはその素早さに目を見張った。
(あの距離から一瞬でここまで・・・・、あの新しく入った5番とこいつ、小さくて見失いがちだ。)
相手にやりづらいと思わせたらしめたものである。
「こいつ、いつの間に・・・・・!」
見ている間に黒子が必殺技のファントム・シュートでゴールを決めた。姿が見えないと思ったら、何時の間にかゴールしていたのだ。ナッシュは舌打ちした。
(つまらねぇミスしやがって・・・・・、だがあの赤司とかいうやつは俺を抜けねぇ。)
ナッシュはまた、赤司の前に立ちはだかった。ナッシュは言った。
「あの黒子とかいう小僧は、今まで休憩していたからな、スタミナがまだ切れてねぇからある程度はできるだろうよ。しかしてめぇはそろそろ限界だろう?てめぇでは俺は抜くことはできねぇからな。」
赤司の眉根が寄った。赤司はピートに心の中で必死に呼びかけた。
(僕のこの目がエンペラー・アイだと言うのなら、おまえは力を貸してくれ!すべての未来を見ることはできないのか?こいつのように?)
(それ、できるようになれるけど、そうしたら情報の洪水が起こって、大変だよ。)
(それでも僕はかまわない。僕は、こいつらに勝ちたい。今力を得たいんだ!)
(わかった。君の中の蓋をどけるよ。ただ、衝撃が来ると思うけどね。君のレンジ幅はあいつより大きいみたいだから、たぶん・・・・。)
赤司の心の扉を、ピートはひらりと飛び降りた。その瞬間、衝撃が走った。ドクン、と赤司の体に反動が起きた。
(未来が、今視えている・・・・・?)
赤司の前に、たくさんの未来の片鱗の映像が渦巻いた。ありえるべき未来、そうでない未来、それをいちいち上げていくとキリがないほどだった。その中で、赤司自身にとっては最良の未来というべきものがあった。それを選べ、と光の渦がその方向に向かって指し示していた。そのためにはどうすればいいか、そのためにはどう動けばいいか。それを光は示していた。赤司はその方向に向かって意識の手を伸ばした。
ダンッ、とナッシュのボールがその瞬間赤司にスチールされた。
(ばかなっ?この俺が抜かれた!?)
そのままボールは緑間に渡り、スリーポイントシュートを決めることになった。緑間は言った。
「これで王手だ!」
ナッシュは呆然となった。ありえない事が今起こったのだった。
(俺の最大出力の未来予知が・・・・。それ以上のものをこいつは視ているのか?)
ナッシュが破られた事から、ジャバウォックは足並みが乱れはじめた。シルバーのブロックも、火神が崩してゴールを決めていく。
(ありえねぇ!俺より強いやつが、いちゃいけねぇんだよ!)
歯噛みするシルバーだったが、勢いを止められなかった。
(風向きが変わった・・・・?未来を、こいつが未来を今「動かした」のか?)
ナッシュは赤司の方を見た。特に変わったところは別になかった。こんな小さいやつに未来を「動かせる」はずがないのだ。そんな事のために、俺が日本で、よりによって日本で試合をするはめになったなど、絶対にあってはならないのだ!
ナッシュはその持てる技のすべてを使いきって、一度はまたゴールを決めてみせた。しかし、ヴォーパル・スワードに勢いがついているのは会場内でも確認され、「ディーフェンス!」の大合唱となった。ナッシュは焦った。何かが、この会場全体の何かが、さっき赤司と対峙した時から違ってしまっている。それは変更はきかないのだった。それは運命の女神が加担したとしか言えないものだった。それからのヴォーパル・スワードの追い上げはすさまじかった。
タイムはあと十秒ほどだった。最後のゴール争いが起こった。その前に青峰がゴール裏からシュートを決めたりしていた。完全に波に乗っていた。赤司はナッシュからボールを奪い、弾いて黒子にパスした。まさに幻の一手、それを火神と青峰がシュートしていく。ダブルシュートだ。
「させねぇぇぇっっっっ!」
シルバーが伸びあがったが、届かない。ナッシュが猛追して、跳びかかった。
「クソザル、てめぇらにはっっっっ!つけあがるな!」
「おれたちはひとりじゃねぇ!勘違いすんな!」
青峰が叫んだ。
ダンッッッッ。三人のゴールの争いで、先に火神と青峰の手がボールに触れた。そのまま二人の手はボールをポストに押し込んだ。ナッシュは二人にはじかれて、ゴール下に転倒した。
「試合終了!」
その瞬間ヴォーパル・スワードに2点が得点され、90対92でヴォーパル・スワードの勝利が確定した。
「やった・・・!」
「勝ったぜ、俺たち!」
仲間たちが勝利に集って喜ぶ中、赤司はくらりと、天地がひっくり返るのを感じた。やはりあまりにも大きなものを動かしたせいだ、と思った。しかしそれは一瞬の思惟だった。
「赤司くん!?」
黒子が思わず叫んだ。
桃井はその瞬間、ベンチで立ち上がって大声で悲鳴をあげた。
「赤司くん・・・・!」
赤司は桃井の見ている前で、コート上で転倒して気絶していた。
行人
「試合は大盛況で終わったが、三人も病院送りじゃあなあ・・・・。」
試合の後の二時間後ほどだった。すでに時刻は夜九時を回っていた。東京都内の総合病院の他に誰もいない待合室で、景虎とリコ、桃井が座っている。景虎はぼんやりとした顔で、ペットボトルのジュースを手に待合のテレビを見ている。
と、廊下の向こうからキセキのメンバーたちが現れた。
「黄瀬くんが一番軽いんですか?」
「そうだな。あいつの場合は身体疲労だから、点滴で三日もすれば元通りだそうだ。」
「それはよかった。」
「問題は紫原の左腕の骨折と、赤司だなあ。なあ、なんで赤司は面会謝絶なんだ?あれそんなにひどい怪我とかしていたか?」
「さあ・・・・僕には・・・・。でも試合終了後、担架で運ばれましたから。」
黒子と火神が話しながら歩いて来る。
「桃井さん、大丈夫ですか?」
黒子が桃井に声をかけた。
「え・・・・あの・・・、大丈夫です・・・・。」
桃井は消え入りそうな声で答えた。青峰がぽん、と桃井の頭に手を乗せて言った。
「そんなに心配すんなよ。ただちょっと故障しただけだぜ。俺ん時みたいに。」
「そうだけど・・・、心配で・・・・・。」
「なんだ泣いてんのか、おまえ?」
「・・・・・・。」
黒子が横から言った。
「桃井さんは優しいから。」
「まるであたしが冷たいみたいな言い方ね?」
とリコが言った。リコは特に取り乱してはいない。いつもの冷静さだ。
「お父さん、ここもテレビ局の人から紹介されて?」
「あ・・・ああ、そうだな。局の人がツテのあるところということで、救急があるからってここを紹介されたんだ。ま、あの競技場のホールからも近かったしな。」
「ふうん。なんだか怪しいわね。」
「なんだ、気になってんのか。」
「だって赤司くん、そんなにひどい怪我だった?」
「まあ名のある病院だから、心配はいらねぇよ。」
「しばらく入院するのかしら。まあ今は夏休みだからいいけど。京都の高校の方には連絡しないといけないかしら?」
「そうだな。でも赤司んちは東京じゃないのか?」
「それもそうだったわね。」
と、その時桃井が顔をあげてリコたちに言った。
「私、連絡先を知ってます。」
「それは助かるわ。実家に連絡しましょう。」
「そうだな。」
と、景虎も言った。
桃井は古いアドレスブックを取り出した。帝光時代のものだ。「あの時」も赤司の家に電話した。そのアドレスの番号にスマホで電話をかけた。リコや景虎たちが注視している中、桃井は話し出した。
「あ・・・もしもし、赤司さんのお宅ですか?」
桃井が言うと、くぐもった男性の声が答えた。
「そうです。うちは赤司です。」
「あの・・・・・、そちらの息子さんの征十郎さんが、都内の○○総合病院に今入院しています。こちらでバスケットの試合に出場していた事は御存じですよね?」
「いや、知りませんが。」
「あ・・・そうなんですか。いえ、今日試合があって、勝ちました。」
「それはよかった。」
「それで怪我をして、今入院しています。」
「そうですか。わざわざご連絡ありがとうございます。」
「あのっ、あのっ・・・・・、それだけですか?」
「何か問題でも?」
「いえあの・・・・・・。赤司くんのお父様でいらっしゃいますか?」
「そうですが。」
「心配じゃないんですか?」
「心配していますよ。息子のことはね。じゃ、私はこれで。」
「あのっ・・・・・。」
通話はそこで途切れた。リコが言った。
「いいとこのおぼっちゃんだって聞いているけど、相当ね。もっとばしっと言ってやらないとだめじゃないの。」
「はい・・・・・。」
桃井は涙の残る目でスマホの電源を切った。景虎が言った。
「赤司んとこはもう連絡したからいいだろう。紫原のとこは陽泉の連中が残っていたな。そいつらに連絡だ。紫原の都内の実家もわかるか?」
黒子が答えた。
「あ、僕知ってます。」
「じゃそこに今からかけろ。おまえらもそれが終わったら帰れよ。桃井さん、あんたも帰宅しなさい。じゃあな。」
と、景虎は言った。
赤司は例の海岸線に立っていた。あの冬の終わりに訪れた砂浜だ。ここならかあさんを思っても大丈夫だと思った。ともすれば母の思い出は日々の雑事に紛れて、薄れてしまいそうになる。北海道の雪まじりの風は赤司に容赦なく吹き付け、海岸線の波頭は大音響で砕け散っていた。赤司は風に逆らいながら立ち、思った。ここであいつを葬るんだ。だってかあさんはあんな風にして死んだんだ。あんな風に・・・・。あいつがあのままふつうに生きていていいはずはない。赤司の目の前に地球岬の一番端の絶壁がそそり立っている。その塔のような岬の先には白い灯台があり、そこから突き落とすのが最善策だと思った。この近くの室蘭市は、かつて大きな工場が栄えた町だったが、今は廃屋が立ち並んださびれた町だ。こんな場所なら誰の人目にもつかない。そのありきたりな田舎町の風景は、母詩織の葬送にふさわしいように思った。かあさんにはこんなひっそりとしたところが似合ってる。誰も知らない思い出、誰も知らない町、誰も知らない・・・・僕の思い。警察に証言しようと行ったのに、誰も掛け合ってくれなかった。僕があまりにも小さかったから。僕があまりにも無力だったから・・・。赤司は砂浜でポケットに手を入れて立ち尽くしていた。と、その時岬の先に人影が動いた。誰かいるのか?と、見ている間にその誰かは、ピンクの長い髪を振り乱して崖から海に転落した。
「桃井さん・・・・?」
赤司の息が詰まりそうになった。その人影は間違いなく桃井さんだった。
なんで桃井さんがあそこから落ちるんだ?僕は夢を見ているんだ。僕は・・・・。
(それは確定されていない未来だね。だけど、そうなる可能性がある。あの男はそれができるから。)
ピートの声が耳元に響いた。はっ、と赤司は我に返った。見知らぬ天井が頭上に広がっている。なんだここは・・・・、試合会場じゃない。どこかの部屋の中だ。
(ここは病室だよ。君は閉じ込められたんだ。今君の脳波を調査中だ。さて、ここから逃げ出さないと。)
と、ピートが言った。赤司はベッドの上で動こうとしたが、拘束されているのか、体が動かない。赤司の横で規則正しく、医療機械がグラフと記録文字を映し出していた。
(力まかせにひっぱってみて。)
ピートが言うとおり、赤司は体に張り巡らされたコード線を引き抜いた。体が自由になった。そのままベッドから滑り降りた。
「なんで僕はここにいるんだ?」
(君は今要注意人物なんだ。試合を君は君の意のままに動かしただろう?それはちゃんと記録されてしまったんだよ。それで君の体を調べたいやつらが、君をこの集中治療室に閉じ込めたっていうわけ。よくあるSFだね。)
「冗談じゃない。それよりもさっきの夢の映像は、僕の見た未来予知なのか?」
(おそらくそうだね。例の君が殺したい男からの未来確定メッセージだよ。)
「そんなバカな。あいつにあの場所がわかってたまるか。それにどうして桃井さんを知っているんだ?」
(君もうかつだねぇ。相手も君を見張っていたんじゃないか?桃井さんの事もどうにかして気づいていたんだよ。それは君も試合中に見たろう?)
「とにかくここから出ないと。」
赤司は病室のドアを開けた。幸い鍵は中からかかるドアだった。容易に外の廊下に出られた。廊下は灯りが少なく真っ暗だった。
「時間は今何時ごろだろう?」
(おそらく深夜だと思うよ。しかしここにいない方がいいね。)
「そうだな。」
赤司は廊下を走って、非常口のランプがついているドアから外に出て、病院ビル横の非常階段を足音を忍ばせて降りて行った。足はスリッパ履きなので、どうしようかと思った。しかし病院の外に無事なんとか出られた。植え込みから見てみると、やはり○○総合病院、と看板ネオンが出ていた。
「○○・・・・・景虎さんの用意した、宿泊施設の宗教団体みたいなビルの名前と似ているな・・・。」
(ま、今はそれどころじゃないから。とりあえず、君の家に行こう。この近くじゃないのかな?)
「僕の実家?入れるだろうか。」
(君の家じゃないか。)
「今鍵を持っていない。」
(あ、深夜タクシーが来た。あれを止めて!)
「財布もないぞ。」
(いいからいいから。)
ピートが言うのに、赤司は道路を流してきたタクシーに乗り込んだ。タクシーの運転手が赤司の病院着の服装に一瞬不信そうな顔をしたが、「○○町○丁目まで」と赤司が言うのに、なぜか普通に応じた。そのままタクシーで移動し、ピートがせかすのに赤司は金を払わずに降りてしまった。しかしタクシーの運転手はそのまま何も言わずに走り去った。
「おまえ、何かしたのか・・・・?」
(さあ?君の力のまねごとだね。あの運転手さんは、空気を運んだと思ってるよ。)
と、ピートはすまして言った。
久しぶりに帰る実家の門だった。赤司は春休みに北海道旅行した際にも実家には立ち寄っていないし、帰省もしていない。ほとんど彼は京都にいたのだった。久しぶりに見る鉄門は、変わらず洋風の一見しゃれた門構えだった。それを赤司は開けた。ふだんは鍵がかかっている。赤司はちょっと驚いた。そのまま主屋に移動して、裏口の勝手口から中に入った。そこも鍵は開いていた。
「用心が悪いな。父は使用人に何も注意していないのか・・・?」
(でも、無事に入れたね。)
と、ピートは言った。
赤司は母屋から広い廊下を渡って、寝室のある棟の方へ歩いて行った。廊下は宮殿風に似せたつくりで、父征臣の趣味で集めた彫刻などが置かれている。歩きながら赤司は言った。
「おまえの言うままに実家に来てしまったが、浅慮だったのかもしれない。あの宿泊施設に僕の普段の持ち物や着替えは全部置いてある。ここに戻ってきてもいいことは何もない。宿泊所で身なりを整えてから考えるべきだった。」
赤司の普段の冷静さが戻りつつある発言だった。ピートはしかし答えて言った。
(そうかなあ。僕はここに来た方がよかったと思うよ。だってね。)
と、ピートが言った時、廊下の向こうで人影が動いた。灰色の髪。
「え、黛さん・・・・?」
赤司は目を見張った。
「黛さんがどうしてここに?」
黛は言った。
「あ・・・・、おまえなんだその恰好。病院からか?」
「ええそうですが。抜け出してきました。」
「なんだと?いったいどこの病院だ。」
「○○総合病院です。」
「戻った方がいいんじゃないのか。試合中に倒れたんだろ?」
「そうですが、別に僕は今異常はないんですよね。それより、どうして黛さんが僕の実家にいるんですか?」
「おまえの父に試合後連れて来られた。押しの強い人だな、おまえの父親は。俺に用があるんだと言った。」
「え・・・・どういう事ですか?」
「知らねぇよ。とにかく、小太郎たちと別れてここに連れて来られた。おまえの話を聞きたいと言われてな。夕ご飯をごちそうになったが・・・・。」
「それでうちに泊まっているというわけですか。」
「そ、そうだ。俺も今晩夜行バスで京都まで帰るかどうかってとこだったからな・・・・。」
黛はそう言って頭をかいた。その様子に赤司は少し笑った。
「別にそれはいいですよ。それより、どうして父がそんな事を言いだしたかわかりません。」
「それだ。俺はその時、ちょっと不審な物を見つけて手に取って確かめていたんだ。ちょっと来い、こっちだ。」
と、黛はあてがわれている部屋に入り、一冊の古本を手にして出て来た。
「この本だよ。これが、おまえに何かゾーンプレスのサインを送っていた男の観客席に置かれていたんだ。それを手に取って調べて見ていたら、おまえの父親にとおせんぼで立たれてな。『黛千尋さんですね?』と言われた。どうして俺の名前を知っているのかも不審に思ったよ。ま、俺のことをおまえが実家でぺらぺら話していたのかと思ったがな。」
「そんなことはまったくしていませんよ。僕は去年の夏から実家には戻っていません。僕が黛さんをスカウトしたのはその後です。」
「そ、そうだろう。」
「その本を置き去りにしてあの男が帰ったということですか?」
「おまえの知り合いか?試合中におまえにサインでやじっていたなあ。おまえも反応していたが。」
「黛さんには関係ありません。その本ちょっと見せてください。」
「あ?ああ。」
赤司は黛から本を受け取り、確かめてみた。古い児童向けの本で、背に蔵書シールが貼られている。図書館の本みたいだった。奥付を開いてみたら、貸出カードが糊付けされていて、図書館のスタンプが押してあった。都内の○○区図書館蔵と読めた。赤司は言った。
「図書館から勝手に抜き取ったみたいですね。しかしこれは古い・・・・。昭和の頃でしょうか。」
「そんな感じだなあ。初版昭和六十二年発行、とか発行年月日に書いてあるぞ。」
赤司はぱらぱらと本をめくってみて、おやと思った。
「落書きが書いてありますね。図書館の本に、よくないなあこれは。鉛筆で何か書いてあります。」
「そういうの昔の図書館の蔵書にはよくあることだったんだよ。昔は携帯とかなかったからな。伝言板がわりに書くやつがいたみたいだ。」
「なるほどね。黛さんはさすが読書家です。」
「俺もその落書きは見つけたんだが、おまえにはその意味はわかるか?」
「なんだかそういうことが書いてありますね。何かの変なマークの落書きの下に、『静一くん、そういう事を書いてはいけません』と書いてある。その下に矢印で『先生も書いているくせに!』とあるな。この66ページに書いてあります。黛さんにもこれはわからないでしょう。」
黛は赤司から本を受け取って言った。
「ビールのバドワイザーのマークか?」
「子供が書いているみたいなんですが。バドワイザーでしょうかね。」
「たぶん何かのラベルの模様だな・・・・。なんだろう、これは?俺にはわからんが、見覚えが・・・。」
黛は眉根を寄せた。とにかく何かわからないエンブレム文様が、子供の稚拙な絵で引きうつされていた。
「どこかの海外のスポーツチームのエンブレムでしょうか。」
「かもしれんな。しかし昭和の時代にそんなものがあったのか?Jリーグが始まったのは90年の頃だろう。」
「ですね。」
「待て、俺も興味が出て来た。スマホで写しておこう。」
と言って、黛はスマホを取り出して落書きのマークを撮影した。
「黛さんが好きそうですね。」
「おまえだって、これが何か知りたいんだろう?調べてみといてやるよ。」
「それはそうと、僕はこの本にちょっと見覚えがあるんです。かあさんの部屋で似た本を見かけたことがある・・・。」
「かあさん?おまえの死んだおふくろか?」
「ええ。こっちの部屋ですよ。確かあったはずだ・・・・。」
と言って赤司は廊下を歩いて、黛を母の部屋へと案内した。
「お、なんだ?紙の城か。おまえが作ったのか?これ?」
と、入るなり黛は、部屋のサイドボードに飾られたペーパークラフトの大きな城に目を見張った。
「ええ。僕が小さい頃にね、古賀さんという人と一緒に作りました。」
黛は感心したように首を傾げた。
「へぇ。さすがおぼっちゃんだねぇ。やる事が庶民とは違うな。これだけのセットだと何万円・・・・?」
と、赤司は本棚を見上げていて、「あった」と言って棚の隅から一冊の本を取り出した。
「ほら、これも背に蔵書シールが貼られているでしょう?小さい時から見ていて、いったいなぜここにあるんだろうとずっと思っていたんです。でも母には聞きそびれていました。母の本棚だったから。」
「ま、他人の本棚というのは、得てしてそういうものだな。」
と、黛は見て、「なんだ」と言った。そして赤司に言った。
「おまえこの本は、図書館から払い下げになった本だよ。要するに在庫処分で出された本だ。ここの蔵書シールに黒のマジックで印がついているだろう?これは図書館が処分した印だよ。」
「あ、リサイクル図書ですか。」
「たぶんそうだな。それをそれぞれ持っていたっていう事かな?」
「そうなりますね。でもこっちの最初の本は図書館から抜いた本みたいです。」
「うーん、そうだな。これには落書きは書いてあるのか?」
「あっ、やっぱりありますね。ただこれには落書きのマークが書いてあるだけです。やはり66ページですね。」
「うん。この本も昭和の終わり頃に発行だな。なになに・・・・江戸川乱歩全集?あ、怪人20面相シリーズか。」
「さっきの本もそういうシリーズみたいですよ。」
黛は本を閉じて言った。
「なんだか『てるくはのる』とか『酒鬼薔薇聖斗』みたいだなあ・・・・。」
「てるく・・・なんですか、それ?」
「おぼっちゃんは知らないのか?少年Aの事件だよ。一世を風靡した神戸市の傷害殺人事件さ。おまえの生まれた頃だったかな。そいつも殺人予告に、こんなわけのわからないマークを描いていたそうだ。」
「うん、聞いた事はありますね。」
「おまえなんかもそうなりそうで、俺は見ていられないんだよ。」
「僕が?僕はそんな事はしませんよ。」
「そうか?俺にはそんな感じに見える事が多いぞおまえは。」
「そうですか。ところで黛さんは明日には京都に帰るんですか?」
「ああそうだよ。夜も遅いから、そろそろ休むよ。おまえはその体だから、しばらくはこっちにいるんだろう?」
「え?ええ。そうですね。」
「明日のバスの便で帰るよ。まあおまえに関する謎がひとつわかって、俺がこっちに来たのも収穫だったかな。おまえの生家も見物できた。」
と、黛は言った。赤司は黛につい礼を言いたくてこう言った。
「京都駅では黛さんに、失礼なことを僕は言いましたね。」
「あ?なんか言ったっけおまえ?」
「ええ。黛さんは現実の女性を研究するためにラノベを読んでいるという話を、僕は頭から否定しました。それはやはり間違っていました。黛さんは、現実にないものをラノベに求めているんです。しかしそれは僕の言った現実逃避とは少し違う。黛さんは、現実を理想化して純化して、ラノベの中に見ているんですよ。それが黛さんが『りんごたん』を好きな理由です。」
赤司が静かに言葉を紡いで言う意味を黛は一呼吸おいてわかって、見る見るうちに『りんごたん』のほっぺのように赤くなった。黛は、舌をもつれさせて言った。
「や、や、その、俺がラノベを読む意味はぁ、その、箱ゲーの・・・・。」
「それじゃもう休みましょう。明日は東京駅まで黛さんを見送りに行きますよ。」
と言うと、赤司は部屋をぱたんと閉めて出て行った。
「は・・・はい?」
黛はひとり部屋に取り残された。
翌朝、食堂で朝食を取った後、赤司は黛と東京駅に出た。赤司の父親は朝食の時にはいなかった。ので、赤司が病院から抜け出して、今実家にいる事を知っているのかもわからなかった。黛は不審に思ったが、赤司も何も言わずに朝食を食べているので、それにつきあってホテルのような豪華な食事を取った。そういう家庭なんだろう、とおぼろげに思った。黛の家ではこういう場合、もちろん両親が何かを突っ込んできて、それに対して反発するというのが日常茶飯事だった。上流階級、となんとなく思った。もちろんご皇室というほどではないのだろうが、この水臭さは上流階級特有のものだと思った。
赤司とは東京駅で別れるつもりだった黛だが、知らないうちに赤司は新幹線の切符を自動券売機で買っていた。
「自由席ですが。」
と、渡してくるのに黛は仰天した。
「黛さんには世話になっていますから。」
と、赤司は言った。
「あ・・・、それじゃもらっとくが・・・・、いいのかおまえこういうの・・・・。」
「あのウィンターカップの時に、僕は黛さんには多大な迷惑をかけました。これはその慰謝料です。」
「はあ。」
黛は京都の下宿には夜行バスで帰るつもりだったから、悪いとは思ったがここは赤司に甘えることにした。それにしてもこのおぼっちゃんは数万円の金を捻出するのにもためらいがない。黛は切符を見てまた驚いた。
「うひゃー、この切符、のぞみかよ?」
「早く帰れていいでしょう。」
「俺なんかこだまに乗るぞ、こういう場合は。」
「黛さんは『夢十夜』に浸れる人ですからね。」
改札口で黛と別れた後、赤司は素に戻り、ピートに心の中で言った。
(おまえの言うとおり、紐をつけて返したぞ。僕の小遣いから出したからな。)
(だってあのわからないマークの模様、調べてくれるって言ったでしょ、あの人。こういう場合は賄賂だよ。ひとつでも可能性は多い方がいい。)
(猫の悪知恵だな。)
(それはふつうサル。)
(うるさい。)
と、ピートに言いながら、赤司は駅の電光掲示板を見た。東北新幹線の発車時刻が表示されていた。以前に北海道に行った時は大阪の空港から飛行機で行った。あの男をおとなしく「連行」して行くのは今の状態では難しいかもしれない。敵も僕と似た能力を持っているのではないか?ピートは赤司の考えに応じて返事をした。
(そうだね、僕も飛行機は危険だと思うよ。列車の方がもしもの場合の逃げ道があるから、まだいいような気がするねぇ。ただ時間がものすごくかかるけど・・・・。)
(おまえ、僕に殺人させたくないんじゃなかったのか?)
ピートは赤司の言葉に、頭上でぴりっとひげを震わせた。
(そうだよ。殺人なんてだめだめだ。だけどさ、北海道に行って、その未来を確定させないようにしなければならないんだよ。そうでないと・・・・桃井さんはあの男に呼び出されて、北海道の崖から突き落とされてしまう。)
(なんだって?そんなバカな話があるか。)
(だってそうなんだもの。君は今その、あの男が敷いたレールの上を進んでいる。その確定した未来に向かって進んでいるんだ。それを君は阻止しないといけない。それには、桃井さんと北海道に行くしかないんだ。あの男は必ず関与してくると思うけどね。)
(そんなバカな。)
(だって君と同等かそれ以上の『力』の持ち主なんだもの。君はそれを認めなければいけないよ?)
(僕の夢に予知夢を紛れ込ませているからそう言うのか?)
(それもある。それ以上に、君の先日の試合を君が勝つように動かした可能性もあるんだよ。君だけの能力ではないのかもしれない。僕にはそれはわからない。それを証明するには、君があの男の用意した未来を書き換える必要があるんだ。)
赤司はその場で黙り込んだ。ピートの言う意味はわかる、しかしそれは状況証拠ばかりだ。あの男の事を自分はまだあまりよく調べていない。
「ピート、危険だがあの男の住む家をもう一度調べてみよう。」
ピートはばっちりと目を開いて驚いた。
(危ないよ?)
(おまえの言っている事が本当かどうか、確かめたい。何か証拠がつかめるかもしれない。あいつが僕の計画を知っているはずがないんだ。もし知っていたら、僕のような能力者だと証明されることになる。)
と、赤司は言った。
しかし赤司がこの後最初に向かった先は、○○区立図書館だった。いくつか電車とバスを乗り継いだ先にその建物はあった。途中、御昼になったので牛丼屋で腹ごしらえをした。洛山の根武谷と入って以来、牛丼屋は赤司の気に入った場所のひとつである。何よりも他人が何を食べていようが一切詮索しない場所が、赤司の個人主義に合っていたのである。実家の父や父につながる親類縁者の好む高級レストランではそうはいかなかった。区立図書館に行った頃は午後一時を回っていた。
「この本はこちらの図書館のものですね?これと同じシリーズの本はありますか?」
と、赤司は司書のレファレンスコーナーで図書館員に尋ねた。女性の図書館員は一瞥して、
「それは古すぎて、書庫にもない本です。」
と言った。しかし赤司が「どうしても」とねばったので、
「それなら、処分用コンテナの中に類似の本があるかもしれません。」
と言い、役場の中を案内してくれた。それは廊下の突きあたりのコーナーに置いてあった。
図書館員が言ったコンテナというのは、プラスチックの大型の書類入れで、その中に雑然と古い本や雑誌が押し込んであった。廃品業者に渡す前にとりあえず整理して置いてある状態のものだった。図書館員は「この中になければ、もうありません」と言って、赤司にあとは託して退出してしまった。
赤司はそれから三十分ほど古本の束と格闘した。やっと見つけた古ぼけた江戸川乱歩シリーズは、積まれたコンテナの下の方に突っ込んであった。
「66ページ・・・・、あるか・・・・・。」
と、何冊か引きだした中の最後の一冊に同じような落書きがあった。今度は黒のボールペンで黒々と描かれていた。
「なんだ?前のと違って目がついているぞこれは。掌の形に目・・・・。僕にも見覚えが・・・・。」
黛と見た本のものでは、鉛筆で雑に描かれていたのでわからなかった。この本のものは比較してはっきりと描かれている。赤司には確かに見覚えがあった。持っているスマホでネットの検索機関を呼び出し、検索してみた。赤司は言った。
「ピート、わかったぞ。これは『ハムサ』だ。それの『ファーティマの手』『ファーティマの目』と呼ばれるものだ。護符だな、アラビア地方の。」
(護符?お守りなの?)
「そうだ。邪視から身を守るために、体につける文様なんだ。邪視というのは、妬みの視線のことらしい。」
と言って、赤司は黙り込んだ。あの先日の試合中にナッシュが自分に言ったセリフを思い出したのである。
『俗に言う、邪眼で見られた者は呪われる。おまえも呪われるといい!』
(あいつの目はベリアル・アイと言った。僕の目は誰が言うともなく、エンペラー・アイということになってる・・・・。関係があるんじゃないか?)
赤司は本のイラストを写真に撮ると本を戻し、その図書館を後にした。歩きながら赤司は言った。
「ピート、黛にあんな旅券を渡すべきではなかったのかもしれない。おまえの薦めはコンコルド効果だ。僕の調査だけでこのネタはわかった。」
(コンコルド効果って何?)
「コンコルド社は経営が赤字だったのに、巨大旅客機の生産を止められず、巨額の負債を抱えることになった。その経営手腕について言われていることだ。効果が期待できないのに、出資することだ。父が好きそうな言葉だ。」
赤司が征臣の息子らしくそう言うと、ピートは尻込みして困った風になった。
(そ、そう言われると・・・・困ったなあ。これからあの男のアパートに行くの?)
「行かざるを得ないだろう。あいつは僕のことを何か知っている。そして、詩織かあさんとも接点がある。あいつが母さんを轢き殺したのは、単に高田晴美に頼まれただけじゃない。何か遺恨があるんだ。この町は、結婚前母さんが住んでいたところだ。おまえ、何か知っているんじゃないのか?」
ピートはそう言われると、力なくうなだれた。
(君に今まで言わなかったんだけど・・・・・詩織さんはね、実は君みたいな能力があって・・・そのきっかけは僕だったんだ。ある時僕が自動車に轢かれたんだよ。それを見て、彼女は自らの能力を発動した。例の試合中の君みたいなものだね。)
「おまえじゃあもしかして・・・・。」
(そう、僕はとうの昔に死んでいるのさ。君が昔に僕のことを『シュレディンガーの猫』と表現したのは当たっているよ。僕の霊は詩織さんの強い願いによって、この世にとどまった。そして彼女とともに歩んだんだ。君が死にそうになったあの時まで。)
「死にそうになった・・・・?」
(そうだよ。詩織さんはあの時、君の命と自分の命の未来を引き替えたんだ。それぐらいあの男の未来確定能力が強かったからね。かろうじてできたのはそれだけだった。だからだよ・・・・僕が君に詩織さんの仇討ちをしてほしくないのは。それぐらい君のことを考えて詩織さんは自分の命を使ったのに、君は・・・。)
「ピート、今の話は本当か?だったらなおさら、僕はその男をどうにかしないと。」
(ちょっと!それだと詩織さんにもらった君の命が!あの時の君は、ほとんど彼女には、自動車に轢かれた時の僕に見えていたのに!)
と、ピートはギャーギャーと赤司の頭上で走り回って鳴き叫んだ。
「静かにしろ、ピート。あの男のアパートの前だぞ。中を見てみたいが、無理なんだろうな・・・・。」
赤司はごくふつうの軽量鉄骨のアパート棟の前に来ていた。男の名前が小さな表札シールでドアに貼られている――『筧静一(かけいせいいち)』。
赤司はドアノブに手をかけた。ドアはかすかに軋みを立てて中に開いた。開いている・・・?
中に人の気配はまったくしない。無音だ。
(中にそいつがいるかもしれないよ。入らない方がいい。)
と、ピートがさらに騒ぐのを無視して、赤司は中に足を踏み入れた。
「埃臭い・・・。この部屋、人が住んでいる感じがしないな・・・・。」
と、赤司は言った。雑然と物が積まれているが、倉庫みたいな部屋だ。
「なんだここは、セカンドハウスか?」
と、赤司は2DKの部屋の中を見て回った。と、赤司は異物に目を留めた。奥の部屋の一角に海外のバスケット選手のポスターが貼られている。かなり大きいサイズだ。B全ぐらいはあるだろうか。赤司は四隅のピンに目を留めた。
「少し浮いているな紙が。はずしてみよう。」
(あわあわ・・・。)
赤司は上部のピン二本を引き抜いてみた。ポスターがだらんと手前に垂れ下がった。と、その下から地図が出て来た。
赤司は我が目を疑った。それは北海道の室蘭市の地図に他ならなかった。国土地理院の縮尺二万五千分の一の地図だ。大型書店などで手に入るものだ。しかしこれはどうやらプリンターで印刷したものみたいだった。地理院のサイトで入手したものらしかった。その地図の地球岬の場所にマジックでペケ印がしてある。そして、そこに桃井の盗撮したらしい写真が貼ってあった。日時も書きこまれていた。今日から三日後の日付が書かれている。
赤司はあわてて、ポスターを全部はがしてみた。地図の下部には、桃井のやはり盗撮したらしい写真がびっしりと貼られていた。道を歩いている桃井、コンビニで品定め中の桃井、学校の階段を降りていってる桃井、などなど。どうやって撮影したのかは不明だが、写真の中の桃井は撮られている事に気づいている様子はまったくなかった。
赤司はその西日の照らす部屋でしばらく立ち尽くした。赤司の脳裏に忌まわしい五文字が浮かんだ。『サイコパス』。桃井が筧に狙われているのは明白だった。自分は決断しなければならない。一刻を争うのだ。
赤司は筧の部屋から急いで出て、近くの公園で歩きながら桃井のスマホを呼び出した。
「もしもし、桃井さん?」
「あ、赤司くん。今病院かな。もう体の方はいいの?」
「桃井さんは最近、誰かに呼び出されたりしていないか?」
「え、呼び出されたり・・・・?」
「例えば青峰にとか。」
「あ、青峰くん?ああまあ青峰くんからは電話がある時もあるけど、いつも一緒にいるわけじゃないし・・・・・。」
「新しい知り合いができたりとか。」
「しないしない。あ、そうそう明日ね、東京駅に親戚の人を迎えに行くんだよ。夏休みで東京見物に来るんだって。」
「それは何時?」
「あ、朝の九時・・・ぐらいかな。」
「東京駅に行くのか?」
「ああまあ・・・・行くっていうか・・・・。赤司くん、急にどうしたの?」
「東京駅に行くな。いや、行ってもいいが・・・・。わかった、なんでもない。桃井さん、でも気をつけて。じゃあ。」
「赤司くん?病院にいるんだよね?赤司くん?もしもし?」
赤司はスマホを切った。そしてピートに言った。
「実家に帰って用意する。桃井さんを連れて行く。それしか方法がないんだろう?」
(おそらくね。筧が桃井さんに接触する前に会って、保護して連れて行く必要があるね。)
「筧が桃井さんに接触したらどうなるんだ?」
(言いたくないけど、君のアンクルブレイクみたいな事が起こる可能性が大だね。そのまま北海道まで筧について行くことになるよたぶん。)
「冗談じゃない・・・。」
赤司は握りこぶしで何かを殴りたい衝動を抑えた。今はジレンマに陥っている暇はないのだ。赤司は実家まで無言で電車に乗った。
「どこへ行っていたんだ。」
実家の重い扉を開けたとたん、玄関で待っていたのは父だった。父征臣は腹立ちが抑えられない顔をしていた。征臣は言った。
「病院を抜け出したそうだな?体がまだ治っていないのに、ふらふらとほっつき歩いて。」
「母さんの住んでいた町に行っていました。」
「なに。」
「父さんは僕に隠している事がありますね。筧という男をご存じなのではないですか?」
「筧?知らん、そんな男は・・・・。何を言っている。」
「それは嘘だ。隠している事を全部話してください。」
「おまえに話す事は何もない。」
「いつもそれだから。」
「待て、どこへ行く。」
「父さんには関係ない。僕は自分の部屋へ戻るんです。」
「待て、征十郎!」
赤司は征臣から逃げるようにして部屋に戻った。そして、ロッカーから荷物を出して、北海道行の用意をはじめた。ピートがおずおずと赤司の後ろを回って話しかけてきた。
(桃井さんに、君について来るように魔法をかけるんだね?)
赤司はピートの言葉にしばらく無言だった。作業の手を動かしながら、しばらくしてから彼は答えた。
「魔法なんかじゃない。それは桃井さんが僕を好きになったことにはならない。それでも、やらなければならないんだ。」
と、赤司は言った。
翌朝、赤司はリュックを背負い東京駅に向かった。桃井が来る場所は「予知」でだいたい検討はつけていた。午前八時から駅構内で待った。と、スマホが鳴り、赤司が電話を取ると、相手は黛だった。こんな時間に、と思ったが、電話に出た。
「赤司、この前の画像のことがわかったぞ。」
「『ファーティマの目』でしょう。僕もだいたい見当はつきました。」
「そ、そうか。そうだよな、おまえんちにもネットはあるしな。それで検索してみたか。」
「まあだいたいは。あのマークはチュニジア沿岸地方でつけるもので、魔除けです。」
「うんそうだが、フリーメーソンの『プロビデンスの目』のマークも、それに関連しているんじゃないかって話だ。」
「そうでしょうね、あれは発祥があのあたりです。この前のバスケの試合も、ある宗教団体が関与していたような形跡があります。」
「そ、そうなんだ。俺も気になってて・・・・。おまえ、あの男と何かあるんじゃないのか?ああいうマークを携帯していたところから見て、怪しいぞ。おまえもな。」
「黛さん、今僕はちょっとたてこんでいるんです。悪いですがその話ならまた今度で。」
「え、あ、おま。」
赤司は電話を切った。それから約二十分間、赤司は構内の柱の影で桃井の家族がやって来るのを待った。桃井はしばらくして、家族とともに駅構内に入って来た。予定どおりだった。改札口で親戚の人物と会い、彼らがひとしきり談笑しているのを見計らってから、赤司は桃井に近づいた。
「桃井さん。」
「え、赤司くん・・・・。」
桃井は突然の赤司の出現にびっくりした顔をした。その瞬間、二人の周囲の空間が「移動」し「定着」した。瞬時に赤司の意志で改変されたのだった。今は赤司も自らのその能力に疑いを持たなかった。しかし彼にできたのは、桃井が自分について来ることを可能にしたところまでだった。「予知」では以前として、あの×印の日付の桃井殺害の事項は、改変されていなかった。それは赤司にははっきりとわかった。まるで将棋や囲碁などの攻略のようだった。
赤司は「行こうか」と桃井に言った。桃井はかすかにうなずき、赤司と歩き出した。桃井の周囲の家族たちは、桃井が消えたことに異変を感じている様子はなかった。まるで桃井がはじめからいなかったように談笑を続けていた。
しかし赤司はオールマイティになったわけではなかった。ふつうに乗車するように券売機で二人分の切符を買うと改札を通り、赤司は桃井の手を引き東北新幹線のホームに来た。ひっきりなしに構内アナウンスが流れる中、乗車しなければならない「はやぶさ」がホームに来ていた。赤司は桃井の手を引き、自由席の列に並んだ。と、周囲を見渡した。いた。いくつか列を置いた先に、筧が列に並んでいるのが目に入った。今は素知らぬふりをしている。筧はこうして見ると、思っていたよりも若い。中年と思っていたが、まだ二十代後半から三十代前半ぐらいだ。北海道までの七時間余りの旅路に、筧は張り付いてくるに違いなかった。
赤司は桃井を自分の後ろにかばうようにして、新幹線に乗り込んだ。桃井とは同列で横になるように座席を確保した。桃井はおとなしく赤司に従った。それも自分が桃井の自由意志を奪ったからだと思うと悲しかった。席に座ると桃井は赤司に尋ねた。
「赤司くん、私たちどこに行くの?」
「うん。少し遠いところだよ。行って戻るだけだからね。」
「そうなの・・・・。どこか聞いてもいい?」
「母恋駅だよ。」
「あ、試合前に電話で言ってた・・・・。」
「そう、そこだね。」
「どうして行くの?」
「うん。僕のお母さんの思い出の土地なんだ。」
「そう・・・、お母さんの・・・・。」
桃井は赤司の抑え込みによって、ふつうの精神状態なら声をあらげるところを、夢遊状態のように受け答えをした。赤司は列車が発車してしばらくしてから席を立ち、隣の車両に筧が乗っていることを確認した。ピートが赤司の横にふわりと降り立ち、心配そうに赤司に言った。
(函館までに筧はこっちの席にやって来るかな?)
(それはないだろう。新幹線の中ではやつも動かない。問題は室蘭にまで行った時だろう。)
(桃井さん、大丈夫かな・・・。)
(僕が守るしかないんだ。)
赤司はそれから桃井に昼食の折詰弁当を薦め、自分も食べ、座席で休息を取った。ふつうの時なら楽しいデート旅行のはずだった。何よりもかねてからの想い人だった桃井さんが隣にいるのだ。しかし今はそれに没頭している場合ではなかった。赤司は筧が乗っている座席に全神経を集中した。幸い筧は今は動く気配はまったくなかった。嵐の前の静けさだった。
新幹線はやがて仙台から青森を通り、長い青函トンネルを通り函館に着いた。そこからは函館本線に乗り換えで、赤司と桃井は人目を避けるようにして特急列車に乗った。室蘭駅に着いた時は午後七時を回っていた。もう夜だ。赤司はその日は地球岬に行くのは断念し、市内の宿を取った。桃井とは別の部屋にした。市内のビジネスホテルだった。
筧の足取りは、やはり着いてきているのを感じた。市内のどこかに潜伏している。明日、その地球岬に行って、因果律を書き換えなければならない。筧の張った未来確定要素は強い。いくつかの未来予知の断片が赤司には見えた。その地球岬の近くの売店での接触もありそうだったし、もっと早い段階で筧に捕まえられる恐れもあった。それらの要素を排除し、隠れ鬼遊びのように筧が殺害するつもりの日時を、あの場所でやり過ごさなければならない。そんなことは自分も無意味だと思いたい。しかし、そうしなければたぶん桃井は筧に殺害されるのだ。赤司はいろいろな世間を騒がせた事件で、そうした「紙一重の油断」でそうなった事例を見てきた。地球岬まで来たのは、東京で待機していた場合、まず筧の現地での行動の阻止が難しいからである。アウェーにあえて行くことにしたのはその為なのだった。
赤司は思った。自分には、ピートが言ったような、詩織母さんが自分に起こした勇気ある行動のような事は可能だろうか?ナッシュが確定した未来を、試合中では自分は書き換えることができた。自分も詩織母さんの子供だからできたのだろう。だったら、桃井さんが狙われたその時に、その未来を書き換えることは可能だろうか?筧のやつの裏をかいて。
「もし僕にそれができたなら・・・・・。」
赤司は室蘭市の夜景を眺めながらそう思った。桃井さんは隣の部屋で休んでいるはずだった。そこまではさすがに筧はやって来ないだろう。赤司は桃井の寝顔を見たい衝動を抑えた。明日もし僕が死んでも、桃井さんが生きていればそれでいいじゃないか?僕の生きていた事も、少しは何か意味があったんだ。そう思わないと・・・・・。
赤司はそれから、走馬灯のように桃井のその後の人生を想像してみた。桃井さんもいつかは誰かと結婚し、子供を産むかもしれない。そしてその子供が成長して結婚し、孫ができて、その孫に囲まれて、そしていつか連れ合いをなくして、桃井さんも死ぬ・・・・・。そういう穏やかな、ささやかな人生。
「僕はそれを、桃井さんのために用意できるんだ。こんなにうれしい事はないじゃないか。こんなに・・・。」
赤司はそう言ったきり、言葉を詰まらせてしまった。瞳から涙があふれた。母さん、ごめんなさい。母さんが命をかけて救ってくれた僕の命、明日僕はよくない事に使います。僕がもし人を殺したとしたら、母さんは僕を許してくれますか?母さんを殺した男を殺したとしたら、許してくれますか?
赤司は桃井の安らかな眠りを思った。
翌朝は晴れた一日だった。筧が×印をしていた日時だった。質素なホテルの和定食の朝食を済ませると、赤司は桃井を連れて地球岬まで行くことにした。足はタクシーしかなかった。帰途はどうなるのかわからなかった。もしだめな場合は、一番近い母恋駅まで徒歩ということになる。そこまでは数キロの距離があり、舗装道路はあるとは言え山道だった。しかしそうなったとしても、歩くしかないだろう。タクシーの車中で赤司はこうなった原因を考えていた。
要するに筧のやつは僕の殺人計画を読心したのだ。そうとしか考えられない。計画は京都でしていたし、この現地には一度しか来たことがなかったのに、筧はそれを見抜いたのだ。いったいどういうやつなんだ。考えられることは、筧には僕同様の能力があるということだった。桃井さんを狙うのも、結局は僕がターゲットなのだ。一番怪しいのは、父征臣だった。あの本を書棚に置いていた母詩織は、筧と旧知の知り合いなのだ。父も知り合いなのに違いない。父は今回の僕の行動を本気で阻止しようとしなかった。何か裏があるに違いない。父には隠している事が多すぎる。
タクシーが駐車場に着いて、二人は車から降りた。駐車場から地球岬の海岸までは、だらだらとした草原の続く遊歩公園だった。小さな売店が少しだけ立っている。赤司は桃井のために、そこの自販機で缶ジュースを買った。
「赤司くん、遠くまで来たね。」
と、桃井は受け取りながら目を細めた。桃井の脳裏では、東京から千葉県あたりにまで来たぐらいにしか思っていない。桃井は楽しそうにその場でぐるぐる回ると、赤司に言った。
「あの岩、すごいね。」
と、地球岬の断崖絶壁を指さしている。と、赤司も手に持っている缶ジュースに何か風圧のようなものを感じた。
ピシッ。
缶がわずかにへこんだ。赤司はその瞬間、その風圧の方向に「気」の塊を送った。その先に筧はいるはずだ。
めこっ。
赤司の前方に立つ道路標識の軸が、その瞬間ぐにっ、と横に曲がった。
「あ、あれ、今風で曲がった?」
と、横で見ていた男性が声をあげた。
「あら、曲がったわねぇ。どうしてかしら。」
おばさん風の女性も当惑して標識を見ている。赤司は足早に桃井を連れて、観光客たちの群れから離れるように歩きだした。ピートは赤司の殺気立った気配に遠慮してか、昨晩から話しかけてこない。赤司にそのような「能力」があるという事も、ピートは告げていなかった。しかし赤ん坊が自然に立つように、赤司は筧が仕掛けてきた力に応じて、自らの力を使いだしていた。疑問を感じている暇はなかった。桃井さんを守るためなのだ。
赤司は岬の方向に沿って移動して走った。桃井の手を引いて走ったが、道路が不自然に埃が立って石が飛び跳ねた。と、桃井が悲鳴をあげた。桃井の腕に斜めにさく裂した傷が走っていた。赤司は「気」の塊を素早く手で押して飛ばした。動く人影に当たったように思った。徒手空拳でつかんだ、バスケの要領だった。赤司は叫んだ。
「出て来い!卑怯だぞ、桃井さんを攻撃するな!やるなら僕にしろ!筧!」
「彼女のナイト気取りか。なんでも手に入れたおまえらしい・・・・・・。」
筧静一だった。植え込みの木陰から現れた。長身で黒のサングラスをしていて、はっきりとその顔はわからないが、端正な顔立ちの男だった。赤司は叫んだ。
「なぜこんな事をする?桃井さんは関係ないじゃないか。桃井さんを、いや僕の母さんを殺そうとした理由はなんだ?返答によっては、おまえは容赦しない。」
筧は答えた。
「なぜ?それはおまえが赤司征臣の息子だからだ。赤司詩織の息子だからだ。そういう人間は俺にはいらないし、邪魔なんだよ。恵まれた家庭、スポーツ環境、俺から見れば反吐が出そうだ。」
「だからって人を殺していい理由にはならないぞ・・・・。」
赤司のにらみつけた表情に、筧は口元をゆがめて笑った。
「そうかな?おまえだって俺を殺そうとしていたんじゃないか?俺はそのおまえの一手先を読んでみただけの事だ。これからおまえの好きだった女は死ぬ。そして最後におまえも死ぬ。それで俺の復讐の完成だ。母詩織のための復讐だなんて、おぼっちゃんの考えることだな。おまえにはこんな事は無理だろう?病院で促進剤を打たれたみたいだが、俺の力の前では無力だ。」
その瞬間、赤司の頭上から巨大な風圧が覆いかぶさってきた。道路脇のガードレールの表面が泡立ち、ねじ曲がっていく。桃井は悲鳴をあげた。赤司は叫んだ。
「桃井さん、俺から離れろ!」
「赤司くん!」
赤司は「気」をためて、筧に向けて手で発した。筧はよけたが、少し頬にかすったみたいだ。筧は頬を手で少しこすると、赤司に言った。
「やるじゃないか?エアバスケか?ゾーンプレスもできないようなチームに、勝利など百年早い。あの時おまえが未来を動かしたんだよな?」
「僕だけの力じゃない。みんなの力だ。ゾーンプレスで攻めるには、みんなへの事前の打ち合わせが必要だった。あの時はそれができなかった。」
筧は赤司の四角四面の答え方に、気障な調子で鼻で笑った。
「いや、おまえが動かしたんだ。その力が目障りなんだ。俺の未来確定能力を覆すおまえの能力・・・・、未来予知から換算して未来変動させる力・・・・。」
「・・・・。」
「おまえの父征臣が、詩織に見た能力だ!」
筧は言うなり、赤司に次々と「気」を発した。赤司はすれすれでよけた。そして筧に対抗して、黒子のイグナイトのように「気」を返した。しかし桃井をかばいながらなので、どうしても劣勢だった。三人は次第に地球岬の突堤の先端のところへと移動していた。筧が赤司たちを追い詰めて、そこから突き落とそうとしているのは明白だった。三人の攻防はしかし、他の観光客たちからは気づかれていなかった。筧が張ったバリヤーのせいらしいかった。
赤司と筧は岬の先端の灯台下へ続く階段にまで来た。桃井を突き落そうとしている筧を阻止しなければならない。赤司はついに、相手に対して石を集めてぶつける方法を取り出した。そうしなければやられる。あたりに石の破片が飛び散り、岩が崩れだしていた。と、筧が手近な岩を破片にして、桃井目がけて空中から放った。赤司はそれを、寸止めにして送り返した。さらに上から岩の破片を筧目がけて放った。それは見えないゴールポストだった。あらゆるバスケの技を使って、赤司は空気の球と石の破片を筧に対して放った。それを筧は送り返す。しばらくその応酬が続いた。と、桃井の体が不意にふわりと空中に浮いた。
「危ない!」
赤司は桃井の体に手を伸ばして、桃井が落ちるのをはっしと食い止めた。下は目のくらみそうな高さの海だ。桃井は青ざめた顔で赤司の手にしがみついた。筧が笑いながら近づいてきた。
「その態勢ではもう攻撃はできまい?二人仲良く海中に沈むといい。俺の勝ちだ。おまえのくだらん同級生との恋愛ごっこもおしまいだ。征臣父さんも、それは認めたくないと言っていたからな。」
「征臣父さん・・・・?」
「落ちろ、赤司征十郎、おまえさえいなければ・・・・・!」
赤司が筧に足で蹴落とされようとしたその時だった。赤司のつかんでいた岩の周辺のあたりがぼこっ、と大きく割れて、筧目がけてせりあがってきた。重力の法則に逆らった、ありえない岩の落下運動だった。
「なにっ?」
その瞬間筧はその体に岩盤を圧されていた。そのまま地面の上に筧はずしん、と岩ごと倒れた。赤司は桃井と灯台下に倒れていた。僕は瞬間移動したのか?赤司は立ち上がって、足をひきずりながら近づき、筧の倒れたあたりを見た。筧は今ので死んだのか・・・・?僕は殺してしまったのか・・・・?
と、後ろで桃井の気配がした。桃井がいつの間にか横にいた。桃井は今までとは雰囲気が違っていた。赤司は思った、これは『いつもの桃井』だ。
「赤司くん、死なせてはだめ・・・・、赤司くんに殺人はさせない・・・・。」
桃井はそうつぶやくと、筧に向かって手かざしをした。その瞬間あたりに光が満ちた。何の光だ?桃井の後ろでピートがたっ、と駆けるのが見えた。光の渦があたりに満ちた。まさか、桃井さんに何か能力が・・・・?
はっ、と赤司は我に返った。夜の舗装道路に自分は桃井と倒れている。どこだ、ここは?遠くに赤色が点滅している信号機が見える。さっきまで昼間の午前中だったはずだ。時間がおかしい。赤司は立ち上がった。病院の建物が見えて、その裏に小さな駅舎がある。
「母恋駅だ。」
赤司はわが目を疑った。自分たちは夜の母恋駅に瞬間移動していた。しかも時間も経過している。赤司は自分の腕時計を見た。アナログ表示の日にちが出るものだ。ビジネスマン向けの時計を彼は実用性から気に入って、ふだんから使っていたのだった。日にち表示が数日経過していた。まさかタイムスリップしたのか?
その時、今まで黙っていたピートが出て来て言った。
(君はうまくやったんだ。筧はあの場所からひとりで東京に帰った。君たちの姿が突然見えなくなったからね。母恋駅にも来たけど、いつまでたっても君たちは現れない。それでしびれを切らせて帰ったのさ。)
「筧は死ななかったのか?」
(そう、残念ながら・・・。でも桃井さんは君に人殺しをさせたくなかった。僕もそうだったからね。タイムリープしたのは桃井さんの能力のせいだよ。彼女は君の母の詩織さん同様に、タイムリープができるようになったからね。彼女はそれを願った。君の能力のオーバーフロー現象だ。あまりにも一方向に未来を推し進めると、それに反するベクトルの力が作用するのさ。彼女は君の改変しようとした未来を修復した。あふれてしまった水を、元のコップ内に戻した。それだけの話さ。)
「オーバーフロー現象・・・・。それは僕のせいなのか?」
(そうだね。君の近くにいたから、彼女は変えられてしまった。それは君のせいなんだ。)
「そんな・・・・。」
(起こってしまったことは仕方がないよ。桃井さんも君同様に組織から狙われるかもね。気をつけないと。)
「そうだな・・・。」
赤司は桃井の体を抱えて抱き上げると、駅舎に向かって歩き出した。駅舎は夜間だが鍵はかけられていなかった。赤司たちは中に入った。駅舎内にはひとつ電灯がついているだけだった。
よくある、JRの田舎の無人駅だった。片隅の机に駅ノートが置いてあった。
(君の来たかったところだね。)
赤司は答えず、桃井をベンチに下し、自分も座った。
「筧はどうして父さんを父征臣と呼んだんだろう。」
ピートはしばらくしてから赤司に答えた。
(・・・・それは、君のお兄さんだからね。)
「お兄さん・・・・、やっぱりそうか。詩織母さんの子供じゃないんだな。」
(そういうことだね。)
「どうして今まで言わなかった?」
(君は心が優しいから、お兄さんと思ったら戦えなくなるんじゃないかと思ってね。筧は君を殺そうとしていたのにね。)
「筧・・・というのは母方の名字か?」
(そうだね。筧の母親は筧糸都子(いとこ)と言うんだよ。精神病院に入っていたんだ。征臣が筧の家庭教師だった詩織さんを、正式な相手に選んだからね。詩織さんの能力に目を留めて。)
「そうだったのか・・・・。」
(君も筧も征臣の子供だったから、能力者の遺伝的体質者だった。それを組織に言われて征臣は試していたんだ。これはその実験だったんだよ。君は無事切り抜けた。しかしこれから先、君はますます狙われるだろうね。)
「父と話をする。」
(それがいいね。)
ピートは赤司の傍に寄って来た。桃井はぐったりとしている。この母恋駅の駅舎までなんとか運んだが、ここで一晩夜が明けるまで待つしかない。幸い、施錠されていなかったのが運がよく、赤司は桃井を連れて駅舎に入りベンチに座れた。無人駅で、ほこりっぽい空気の匂いがした。壁に夜間灯がひとつ灯っているだけだ。それも腕時計が十時を指すと消えてしまった。桃井はまだタイムリープ能力の発揮から、完全に目覚めていない。小さな駅舎の中は、駅舎前の普通の市道の街灯に照らされて、薄ぼんやりとしていた。時々車が通り、ライトが駅舎の中をサーチライトのように奥まで照らして消えた。その中で、赤司はただ黙って座っていた。ピートがにゃあと鳴いた。そして人間語でこう言った。
(エッチ、しないの?)
赤司は答えた。
「しないよ。ここはそういう場所じゃないからね。僕はおまえのような猫じゃないんだよ。」
(だって、うまく二人きりになれたんだよ?)
「そうだけど。桃井さんの都合もあるし、そんなのは嫌なんだ。彼女が弱っている時につけこんだみたいでさ。僕だって性欲はあるけど。」
(ふうん、そうなんだ。ややこしいんだね。)
そこでピートはぴょん、と桃井の頭の横に飛んで首をかしげて言った。
(桃井さんは東京に戻ったら、君のことどう思うかなあ?今回の旅は彼女にとってどんなものかな?君の事を恐れるのが普通じゃないかな。だとしたら、チャンスは今だけだよ?それでもいいのかい?)
「おまえは人をあおるやつだな。」
(だってそうじゃないかあ。)
とピートは言って、またにゃあと鳴いた。赤司は答えた。
「僕は・・・・桃井さんとは別に生きなければならないんだ。桃井さんがこんな風な能力を暴走させたのは、僕のせいなんだ。だったら僕は、その責任を取らなければならない。」
(別れるの?)
「彼女は僕のお母さんじゃないんだ。こんな事に巻き込んでよかったはずがないんだよ。」
(そう言いながら、桃井さんに触ってるね。)
「髪を撫でているだけだよ。それ以上の事はしない。」
桃井さんが早くよくなるように、と赤司は横たわった桃井のあまり手入れされていないピンクの髪を繰り返しなでていた。死んだ母もこんなロングヘアだった。
「明日になったら、医者に連れて行った方がいいな。保険証がないから、面倒だな。」
(君はとことん現実的だねぇ。)
「おまえが楽観的すぎるんだ。これから東京まで帰らないといけないし。」
(キスぐらいすれば?眠り姫のキス。詩織さんが持ってたディズニーの絵本にあったやつ。)
「まったくおまえは・・・・っ。」
と、赤司は言ったが、不意に真顔になり、桃井の寝顔にそっと顔を近づけた。
(・・・・あ、やっぱし・・・。)
とピートが言った先で、赤司は桃井の額にそっと気づかれないように口づけた。昔母さんがしてくれたような優しいキス。思い出のキス・・・・。さようなら桃井さん・・・・。
(それ、唇じゃない・・・・・。)
と、ピートが言った時、ぱちんと桃井の目が開いた。桃井は「赤司くん、私から離れていくの?」とつぶやいた。そしてゆっくり体を起こした。
「あたし、赤司くんと似た者になったのに・・・。赤司くんは私を置き去りにして、向こうに行くんだね・・・・?」
赤司は桃井が気づいた事に狼狽して言った。
「だって僕といると、ますます桃井さんはおかしくなってしまう・・・・。僕はいない方がいいんだ。」
逡巡する赤司に、桃井は起き上がって叫んだ。
「それでもいい!それでもいいんだよ!赤司くんはひとりで今までがんばってきたんでしょう?それでそんな運命まで背負ったのに、それでもひとりでいいなんて・・・・・。赤司くんがかわいそうだよ!」
「僕はいつもひとりきりというわけじゃない・・・。」
「それは嘘。私が東京駅に来なかったら、ひとりで北海道まで行くつもりだったんでしょう?あのお母さんを殺した男を追いかけていくつもりだったんでしょう?赤司くんはなんでもひとりで決めて・・・ひとりで背負って・・・・それで傷ついて・・・。私はそんな赤司くん見ていられないんだよ!」
桃井はそう叫びながら、いつの間にか泣きじゃくっていた。
「私じゃだめかな?赤司くんのそばにいるの。赤司くんとは釣り合わないのはわかっているよ。だめだめマネージャーなんだもん。だけど、私は赤司くんの事が好きなの。好きなの・・・・!」
「桃井さん・・・・・。」
赤司はそっ、と桃井の頬を両手ではさんだ。赤司は静かな声で桃井に尋ねた。
「僕のお母さんのこと、どうしてわかったの?」
「詩織さんって人・・・・夢で今見たの・・・。私に赤司くんを助けてあげてって・・・・。」
桃井の言葉に、赤司は涙を浮かべた。
「ありがとう、桃井さん・・・。こんな僕を・・・助けてくれて・・・・。僕も、前から桃井さんのことが・・・・。」
桃井は涙顔で少し笑って赤司に言った。
「ね、キスして・・・。」
誰もいない夜の母恋駅の駅舎で、赤司は桃井にそっと顔を近づけて行った。
翌朝、母恋駅のプラットフォームから普通電車に乗り、赤司と桃井は列車を乗り換えて東京にまで帰った。「いつかいつもふたりでそばにいるように」と二人で約束をして―――。
時の回廊
夏休みが終わろうとしていた。青峰は桃井と連絡が取れない日があったが、まさか東京からいなくなっているとは思っていなかった。彼らは日々平穏に暮らしていた。変化は目に見えないもので、「彼ら」がいなかった時間は、時の流れの中で修復され過ぎていった。時がそれ自体何かの意思を持っているかのようだった。時は突出した事件を地ならしし、平凡な日々に変えていった。従って黄瀬や紫原も無事退院し、それは最後の冬のウィンターカップに向けての準備期間だった。彼らは高二だからクラブ活動は最後の冬ということになるのだった。その夏休みの最後の週、青峰は仲間たちから連絡を受けた。
「成田空港に集まれって?」
「そうだ。火神がどうもアメリカに行くらしい。あいつ、もともと帰国子女だったからな。NBA狙いじゃないかって噂だ。アレックスさんがお膳立てしたようだ。」
電話の主は緑間だった。青峰は当惑して答えた。
「何も今渡米しなくても・・・・・・。」
「先を越されたと思ったのか?あいつ、英語はわかるのにこの前の試合でも、俺たちキセキに遠慮してあまり出しゃばらなかった。そういうやつだからな。せめて見送りぐらいしてやった方がいい。黒子がかわいそうだ。」
「そうだな。明日の何時なんだ?」
「明日の午後四時の便だそうだ。」
「わかった。」
次の日、青峰が家が近所の桃井と一緒に成田空港に行ってみると、すでに皆は集まっていた。火神がその中心にいた。
「あー・・・・俺のためにわりぃ。急な話になっちまって・・・。」
頭をかく火神に、仲間たちは声援を送った。景虎が言った。
「おう。行ってこい。絶対NBAに入れよ。」
青峰は火神をこづいて言った。
「ったくなんでおめーなんだよ。実力的には俺だろ?」
「おまえが来るのも、向こうで待ってる。」
「言ったな、こいつ。」
青峰が火神の頭をぐりぐりしている横から、黄瀬が言った。
「あの試合の前からその話があったんすか?」
黒子がうなずいた。
「はい、僕は知っていましたよ、火神くん。これで火神くんとは最後かもしれないっていうことも。」
火神は少し驚いた様子だった。
「え・・・そうなのか。」
「そうです。アレックスさんから電話がありました。僕の高校のチームメイトだからって。」
「黒子はそういう事は胸にしまっておくタイプだからね。」
と、赤司は言った。
「そ、そうなんだ・・・。実はあの試合も、アレックスさんが向こうの高校との打診で試合中のビデオを見せる約束で・・・。」
と、火神が焦って言うのを、赤司は押し止めた。
「火神くんのためだけじゃないよ。あの時のみんなの思いのために、やつらと試合をしたんだ。」
「そう言ってくれると助かる。あんな思いを皆にさせたんだからな・・・・。」
「じゃあ、がんばって来い。あの試合でおまえに箔がついたんなら、いい事だ。」
緑間が言った。
火神はやがて手を振ると搭乗ゲートの列に立った。
「黒子だけにしてやれ。」
と、そっと景虎は言った。彼らは黒子を残してゲートを離れた。
火神はイヤホンを耳につけると、スマホの音楽を聴きながら出国審査を待った。列は長くて時間はかかりそうだった。火神は思った。
(やっぱ・・・・バスケ選手としては、ちっせぇよな・・・・。)
最後のジャバウォックとの試合で見た黒子の試合中の様子を、耳で音楽を聴きながら反芻した。あいつは俺のようにアメリカにまでは来ないだろう。日本でこれからもバスケをして、いつかは社会人になって、その先は・・・・。
ふと、声を黒子に最後にかけなかったと思った。火神は後ろを振り向いた。黒子が搭乗ゲートの遥か向こうの、人込みの中に立っていた。黒子は右手の拳を突きだしていた。火神もそれを見て拳を突きだした。黒子の唇が動いた。
『ぼ・く・は・き・み・の・か・げ・だ・・・・・、ど・こ・に・い・て・も・・・。』
黒子はそう声を出さずに口パクで言うと、大きく火神に向かって両手を振った。火神はそれを見た瞬間顔を伏せてしまった。目から熱い涙がぽたぽたと流れた。
「これで長のお別れじゃねぇ・・・・・、俺、何、泣いてんだ・・・・。」
火神はかろうじてそうつぶやくと、黒子に後ろ姿で手を振り、搭乗ゲートの列に戻った。人々が三々五々と動き出していた。
黒子を待つメンバーたちは、見晴らしのいいベランダの送迎デッキで待機していた。火神の乗るらしい飛行機も滑走路に見えた。
「そういや、やつらも今日アメリカに立つそうだよ。東京の病院で故障を治してなあ。」
と、景虎がタバコを吸いながら、誰に言うともなしに言った。
「やつらって?」
と紫原が言うのに、緑間が答えた。
「ジャバウォックの連中じゃないのか。そうでしょう、景虎さん。」
「そうだ。負けたら筏(いかだ)でアメリカまで帰れよとか言ってたんだがな。」
「筏・・・・、ハイエルダールなのだよ。」
「緑間はよくもそれだけ、七十年代の事をよく知ってるっすね。」
「俺の趣味はアナクロなのだよ。」
緑間と黄瀬が言い合っている後ろで、赤司が言った。
「僕、少し用事があるので、抜けさせてもらってもいいですか?黒子によろしく言っておいてください。」
「次は冬だな。今度は負けんぞ赤司。」
「受けて立ちますよ。じゃあ。」
緑間にそう言うと、赤司は送迎デッキを後にした。後ろで桃井が不安げに自分を見ているのがわかった。しかし皆の見ているところで、桃井と親しくしてみせる赤司ではなかった。彼が向かったのは火神の搭乗手続きをしたウィングとは反対方向の場所だった。ヨーロッパ方面のゲートに赤司は向かった。人は少なかった。時差の関係らしかった。目的の人物はその待合ロビーのソファに所在なげに座っていた。手にメンソールの煙草を持って、茫然としていた。ナッシュ・ゴールド・ジュニアだった。ナッシュは赤司が近づいて来るのを見て言った。
「よくここがわかったな。」
「景虎さんがジャバウォックが今日立つと言ったので、少し意識の範囲を広げて探ったらここでした。」
「ふん、おまえも人間兵器に近づいてきたようだ。」
と、ナッシュは言った。
「そういう黒子人間・・・日本ではニンジャとか言うらしいな?それを養成する組織に俺はいたよ。おまえは普通の高校生活を送っていたのか?うらやましい限りだ。」
「それで俺たちをサルだと・・・。」
「そうだよ。モンキー・スタンスは俺も小学生の頃バスケで習った。いまだにお前たちはそれを続けているんだろう?」
ナッシュはそう言うと、煙草を吸い殻入れでもみ消した。赤司は言った。
「あなたがそう言ったのはそれだけが理由じゃなさそうですね。あなたは日本人全体を憎んでいる・・・・。」
「俺がただのレイシストではないと?」
「そうです。僕の目の話をあなたはどこで聞いたのですか?そして自分の目も僕にそうだと言った・・・。話してください。もし差支えなければ。」
ナッシュはしばらく沈黙していたが、やがて重い口を開きだした。
「俺の名前はジュニアってことでわかると思うが・・・・。俺の爺さんはある財閥の御曹司でな。俺はその孫にあたる。俺は爺さんの名前を名乗らされている。爺さんは俺にその手の才能があると見て、ある組織に俺を預けた。それは俺が五歳ぐらいの時だった。その時・・・俺の母親が・・・。」
ナッシュはそう言ったきり、言葉を詰まらせたが、やがて言いなおした。
「俺の母親が・・・・日本であったあの宗教事件みたいな騒動に巻き込まれて・・・・殺されたんだ。日本の宗教組織のやつらに・・・・。神経系の毒ガスでな。それ以来、俺は日本人が憎くてたまらない。なんであんな団体がある事を放置したんだ。しかし俺が今所属させられている組織も、そういうやつらとつながりがあるのさ・・・・。」
「バスケもその一環でしていた訓練だという事ですか?」
「そうだな。おまえも気づいているように、バスケは全神経を使うスポーツ競技だ。しかし学校で習うような、誰でもしているスポーツでもある。やつらのカモフラージュには持ってこいだったんだろう。」
「僕の過去の事も、書類で調べたんですね。」
「そうだ。俺と似たような境遇・・・・。だけどまだ覚醒はしていない。その方がひょっとしたら幸福かもしれないのになと俺は思った。しかしおまえもあの試合で覚醒してしまった。」
「それで試合中にことさらに僕を妨害するような事を・・・。」
「あの時は俺も余裕がなかったからな。おまえに一言忠告しといてやる。その俺やおまえの目の障害は、永遠の母性喪失から来ているんだ。生まれたての赤子は母親の後追いをするからな。決して見失ないたくない対象を求める本能を、無理やり人為的に引き延ばしたんだよ。そういう、これは言わば黒ミサみたいなもんだ。俺もおまえも、悪魔の供物として捧げられたんだよ。」
「・・・・・・・・・。」
「俺はこれからアラブ方面に行かなければならないんだ。おまえとはもう会うこともないだろう。それを祈る。」
「シルバーたちは一緒じゃないんですか。」
「あいつらはただの囮だよ。俺と違って用済みだから、ストリートギャングに逆戻りだ。ちょいとバスケができるやつらだから、拾ったんだよ、組織がな。」
そこでナッシュは言った。
「最後に記念に握手してくれ。俺は当分バスケはやらないだろう。おまえとの試合がたぶん最後だ。」
そして言った。
「お互い幸せにはなれなくなったが・・・・、どこかに見つけるんだな。おまえなりの幸せを。」
「ええ。そうします。」
「じゃあな。二度と逢うこともないだろう。」
赤司はナッシュと握手をかわすと、空港ロビーを後にした。あたりには夕闇が迫ってきていて、寂寞とした空間だった。ウィングデッキから見える夕陽は燃えるような赤だった。
それから数日後、赤司は父征臣とさる料亭に会食に招かれた。まだ京都には帰っていなかったし、父の要請は断れなかった。重要な会合だという話なのだった。赤司は特に何も思わずに、出席した。親族として出なければならないのは、父の後継者としての建前なのだろうと思った。そのような会食の席は珍しいことではなかった。
父は赤司が一週間ほど北海道に行っていた事も、不問だった。それは不気味なまでの放任主義であった。あの玄関でのいさかいを父は忘れたのだろうかと赤司は思った。しかし父の気分による自分への扱いの違いは日常茶飯事だったので、赤司は気にかけず父に着きしたがってその日会合に出向いた。自家用車から降りると、駐車場の向かいに赤司家のものよりも大型の黒いキャデラックが停まっていて、そこから高級ダークスーツに身を固めた長身の男がすらりと現れた。赤司は目を見張った。それは筧静一だった。やはり黒のサングラスをかけている。着き従う者らに人払いの仕草をすると、筧は赤司に向かって少し微笑みを返した。横に立つ征臣の顔がこわばった。
「征十郎、礼をしろ。我が一族よりも上だ。」
と、征臣は小声で赤司を叱咤した。赤司はあわてて頭を下げた。とっさに赤司は頭の中が混乱した。自分が興信所を使って、筧について調べた情報は嘘だったのかと思った。思えばあの筧のアパートも人が住んでいる形跡は少なかったのだ。すべては自分を罠にはめるための芝居だったと赤司は瞬時に理解した。
筧は地球岬でのあの時怪我をしていたと思ったが、見たところ元気そうだし、赤司に対して遺恨がある風ではなかった。前に立って会食の場に入る筧の折り目正しい正装姿は、ほとんど以前に見かけた浮浪者のような筧とは別人だった。
「さて。お父さんとお呼びするべきなのかな。」
と、席に座って筧は言った。征臣は額をハンカチで拭いている。征臣は答えた。
「いえ、赤司さんで結構です。」
「そうですか。その方がこちらも都合がいい。うちを出て行った人間を、そのようにお呼びする言われはこちらにはありません。」
「そ、そうです。」
「ところでご子息はなかなかの能力者に成長したようです。赤司コンツェルンも前途は開けたようですな。我が縣(あがた)財閥に今後も助力は惜しまぬように。」
「は、もちろんであります。」
そこで筧は赤司に視線を移して、冷ややかな調子でこう言った。
「征十郎くんと言ったかな?君は私とは母親の違う弟だが、私はそう思っていない。そこの事情を君はよく知らないようだから、御父上から話をよく聞き給え。では本題に入ろう。」
筧の話は会社関係の話に移り、それから席には高級食材を使った季節の料理が運ばれてきたが、赤司はよく味を覚えていない。筧の様子に目が釘付けだったからである。筧が自分の腹違いの兄であるという話は、ピートから聞いて知っていた。しかしこれはあまりにも思っていたものと違い過ぎる。
帰宅してから、赤司は食堂で父征臣と対峙した。
「話してください、本当のことを。」
征臣はサイドボードからウイスキーとグラスを取り出してテーブルに並べたが、手酌をしたがグラスに手をつけずにしばらくぼんやりとしていた。が、やがて赤司に言った。
「おまえにはすまなかったと思っている・・・・。」
赤司は窓際に立って外の景色を眺めていた。父と向き合うことはできなかった。
「どうして詩織母さんの前に女性がいたんですか?詩織母さんが生きている時も、高田晴美とつきあっていましたね。それは何故ですか?」
征臣はしばらく黙っていたが、やがて赤司に答えた。
「・・・糸都子とは政略結婚だ。能力ゆえに私が先方の家に入った。しかし糸都子は精神を患ってな。私とはだんだん話が合わなくなっていった。糸都子は上流貴族らしい気位の高い、気難しい女性で・・・・。そんな時、私に同情してくれたのが、当時静一の家庭教師だった私の大学の同級生の詩織だった。バイトに来ていた詩織と手に手を取って、私はあの家から抜けだした。抜け出せたと思った。息子だった静一は跡継ぎだというので、先方にとられた。」
「それで?」
「詩織はしかしおまえを産んでから、私を遠ざけるようになった。おまえには普通ではないところがあって・・・・・。私と結婚したせいだと思ったのだろう。それで、大学時代の友人の古賀とつきあうようになり、私も晴美と付き合いだした。」
「父さんにも能力がある?」
「そうだ。古い話をするようだが、平家物語の那須の与一の話を知っているか。ここぞという時に見事に的を射抜いた・・・・そのような歴史の変換点の機運を動かす能力だ。昔から皇帝に必要な能力と言われた。中国あたりでは、本気で信じられていたことだ・・・。この赤司家はそのような歴史の黒子の家系だったのだ。おまえはうちを大財閥と思っていたみたいだが、とんでもない事だ。上には上がいる。うちは黒子で、ただの使い走りなのだ。」
「あのエンペラー・アイという僕の呼び名も父さんが?」
「それは私ではない。誰か知らない人間がそう呼んだのだ。おそらく、おまえも気づいている宗教団体が、おまえにつけたコードネームだ・・・。先の日本で大事件を起こした新興宗教団体のそれではない、世界史を歴史の影で操っていると言われている団体だ。」
「黛にもその話はされましたよ。」
「ああ、彼だな。おまえと京都で親しくしているという話を聞いて、あの晩一緒にごはんを食べた。京都でのおまえの話を聞いた。おまえは何も話してくれないからな。」
そこで赤司は父に振り向いて言った。
「母さんが死んだのも、僕のこの目のためだったんですか?僕の能力を発現させるために?」
「・・・・・その話はしたくなかった。私もおまえの因子には腫物に触るような扱いだったのは認める。寂しい家庭だった。いくら謝っても足りないぐらいだ。」
「筧は僕の家庭を憎んでいたんですね。筧の家も寂しかったのかもしれない。」
「ああ。しかし筧については、今後も用心した方がいい。あれは・・・恐ろしい男だ。」
「そうですね。」
と、赤司は言うと、父の横に立ち、ひざまづいて手を取った。
「父さん、よく話してくれました。父さんにとってはつらい話だったでしょう。」
征臣はそこで肩を震わせて言った。涙ぐんでいた。
「征十郎、おまえをだますつもりはなかった。ただ、私は・・・・詩織に愛されていなかった。それを認めるのがつらくて・・・。」
赤司は父に優しく言った。
「お父さん、母さんは古賀さんとは何でもありませんでしたよ。母さんは父さんのことを愛していたんです。だって、自分の身をもって子供の僕を守ったんです。それはきっと、僕が父さんの子供だったからです。母さんは筧の落書きした本だって持っていたんです。それはきっと筧が父さんの子供だったからです。」
「征十郎・・・・。」
「僕が能力者になれないと困るから、僕にずっと厳しくしていた・・・、そうですね?」
「わかってくれるのか・・・・おまえは・・・・。」
「これからは僕も父さんと話をしますよ。今まで冷たかった。謝ります。」
赤司の目には、父は急に年を取った風に見えた。父が母詩織に愛されていないと思い悩む弱い男性だとわかったからかもしれない。父のように生きるつもりはないが、父のことは理解しなければならないと赤司は思った。
「父さん、いつか僕も父さんに話すべきことがあります。まだ今は話はしませんが・・・・。」
とだけ、赤司は征臣に言った。桃井のことだった。
それから数年の歳月が流れた。キセキのメンバーも大学生になった。あの後の彼らのウインターカップの試合の結末については、この話では紙面を割かない。それはすでに重要な話ではない。赤司は京都から東京に戻り、大学生活を営んでいた。そして桃井とつきあっていた。
桃井はタイムリープ能力があることは隠していたが、急場で自分の身を守る時しか発揮できないのは母詩織と同じで、知らない人間には気づかれることはまずなかった。しかしたぶん組織はあの時の筧の口から気づいているだろうから、赤司は桃井の傍にいて見張ることを続けていた。そうして一生そばにいるんだと思った。もし桃井さんが自分を選ばなくなっても、そうしなければならないと赤司は考えていた。
自分は何かを越えてしまった。それが自分という人間だった。母詩織もそんな風に思ったことはあったのだろうか。平凡な猫のピートを飼っていた高校生の詩織と、自分の母だった詩織。母さんも越えたように、僕も越えなければならない。それが人の一生ということなのだろう。母の後ろ姿を赤司は思った。ピートはこの頃はごくたまにしかやって来なくなった。赤司が大人になったせいかもしれなかった。
赤司はあいかわらずバスケのクラブ活動は続けていたが、もちろん能力で「ずる」をすることはしなかった。あのジャバウォックの試合での出来事は、例外だった。筧を殺さねばならないと思い詰めていたから、赤司もした事だった。同様に念動力まで発揮することもしなかった。組織の目に留まる事は避けなければならなかった。逼塞して赤司は生活していた。
そして卒業後も院にたぶん進むことになるとわかった年のクリスマスに、赤司は桃井を湾岸沿いのレストランに呼び出した。免許は来年の夏休みに取る予定で、まだ足の車はなかった。だからそのレストランまでは桃井と電車を乗り継いで歩いて行った。桃井は少しだけドレスアップしてやって来てくれた。青峰とは今は疎遠になっているらしかった。桃井の子供っぽさに、青峰が大学の華やかな女性たちの方に目が向いたらしかった。「ふられたってわけじゃないけど、やっぱり青峰くんはそういう人だったから」と桃井は言った。「幼馴染ではよくある話ね」と。
赤司は桃井が青峰の世話を何かと焼いていた帝光時代をよく知っていたから、青峰を一発殴りたい気持ちがあったが、何も言わなかった。青峰が桃井から離れてくれた事を揺らすのはよくなかった。これで一件落着で落ち着いたのだった。
レストランの席につくと、赤司は紙包みを取り出して桃井に渡した。
「クリスマス・プレゼントだよ。開けてみて。」
「今開けるの?帰ってからでいい?」
「今開けてくれた方がうれしいな。」
「そうなの?」
桃井は赤司に言われて、リボンをほどき、包装紙を注意深く開けてみた。中から紺のリングケースとおぼしきものが出て来て、桃井は目を丸くした。蓋をあけてみた。上品なプラチナリングが台座にはまっていた。赤司は言った。
「本当は給料の三か月分だけどね。」
「え・・・・赤司くん、それじゃこれ・・・。」
「クリスマスにはふさわしくないかもしれないけど。バイト代だからその程度だよ。それで今は我慢して。」
「赤司くんがこれ、選んでくれたの?」
「そうだよ。あ、降旗にも選ぶの手伝ってもらったけどね。あいつ、古賀さんのところで今一緒に仕事手伝っているから。」
「何の仕事?」
「キッズバスケのコーチの手伝いかな。あまり金にはならないけどね。」
「バイトってそれなんだ・・・・。」
「そうだよ。」
「子供嫌いだと思ってた。」
「そんなことはないよ。」
「ありがとう、赤司くん。私もプレゼント出すね。私のは普通のものだけど・・・・。」
桃井も席から赤い紙包みを取り出した。
レストランで食事をした後、二人は湾岸沿いの運河のそばを散策した。遠くで東京湾の夜景が見えた。夜景の灯りは宝石のように美しかった。赤司はそれを眺めながら、桃井に言った。
「桃井さん。もし、僕が・・・・・。」
「え、何?」
「いや、なんでもない。」
赤司は言いかけて言葉を飲み込んだ。もし僕が僕でなくなったとしたら。もし僕が死んだら。赤司の中にそれらの災厄の言葉があったが、今この場にふさわしいものではなかった。僕は幸せにはなれない、とあの時ナッシュは言った。だけど僕は桃井さんと幸せを築いてみせる。
赤司はそっと桃井に顔を近づけて優しいキスをした。そしてその髪に手を触れ、静かにささやいた。それは赤司の心からの祈りの言葉だった。
「僕は、僕たちには、恐れるものは何もないんだ―――。」
――完――
あとがき
「黒子のバスケ」での小説はこれで数えて三作目となる。できればこれで完結編としたいのだが、続きは今のところ難しい。改変ものの原作がもうこれ以上は現時点ではないのである。だから、一応これでラストということになるのだろうか。これ以上はまったくのオリジナルになってしまう。というか、今でもすでにもう半ば以上オリジナル要素が強いのだが、これ以上続ける気持ちは今のところ少ない。申し訳ないと思っている。ただまた何かあったら書いてみたい気持ちはあります。
タイトルの「OVER」は大好きなオフコースの五人最後のアルバムから取ったもので、小説のタイトルとしてオーバーな話だとか、力量以上に手を出しているとか、そういった意味にも取られるものだと思う。私に否定的な人には文字通りオーバーな話に映るだろう。特に後半はSFなので、黒バスのスポーツ作品の範疇からはみ出してしまっている。しかしもともと最初の「笥詰めの恋」を書いたあたりから、ちょっとそういうSFじみた展開にしていたので、予想通りのところに落ち着いた感がある。今回書く上で参考にしたものは、「重力ピエロ」「悪人」などの邦画、「Spec」などのテレビドラマ、あと洋画の「ヒッチャー」である。あと、御存じオウム真理教の一連の事件も参考にした。北海道を後半舞台にしたのは、少し思い切ったものにしたかったせいで、母恋駅は検索して見つけたものだ。ただ実際の駅舎や地球岬の動画を見たら、かなり当初の考えと違うものにせざるを得なくなった。当初はながやす巧先生の「鉄道員」の世界のようなものを考えていた。しかし現実はそうではなかったのだった。それに合わせて、内容も変更せざるを得なくなった。季節も夏に設定を変えたりした。はじめは雪の中の話にするつもりだった。しかし駅舎で一晩過ごす話にしたかったので、冬だと凍死してしまうと思い断念したのだ。またナッシュのオリジナル追加設定が、納得がいかないという人もおられるだろう。ただ私としては、日米摩擦を助長する方向にしたくなかったので、変更させていただいた。元の原作のものとは、そういう点でかなり違えてある。何より赤司くんが主人公になってしまっているので、OVAの出だしの帰国子女である火神くんの話から入るものとはまったく違ってしまっている。それも私のわがままで書いたものだ。お許し願えればと思います。
桃井さんとの関係は、この話の中ではやはり性的関係まで進まないようにしてしまった。そこが残念だと思われる人もいるだろう。婚約したあたりまでで終わってしまっている。父征臣がまた、とんでもない人物になってしまったのも悪かったと思っている。もっと心温まる家庭を赤司くんでは想像している人も多かろう。あくまでこれは私が考えた赤司家の物語ということで、お許し願えればと思う。結局赤司くんに超能力が目覚めてしまった点も、「笥詰めの恋」では否定していたのにと思われる向きもあるだろう。ただ、私としては、赤司くんにエンペラーアイがあるという噂があり、そのとおりの予知能力が試合中にすぐにあったという展開は、あまりにも意外性がないという事で長々と前ふりを作らせていただいた。好みの問題かもしれないが、ご了承願えればと思います。
今回書いていく上で支えになったのは、オフコースの「OVER」の中の曲の「哀しいくらい」、山下達郎さんの「風の回廊」「2000トンの雨」「夏への扉」、オトナモードの「空への近道」などでありました。まことにYoutubeさまさまであります。それにしてもややこしい設定にして悪かったかなあ。それではまた、何かの次回作でお会いできれば、幸いであります。
2020年 8月 おだまきまな拝
OVER


