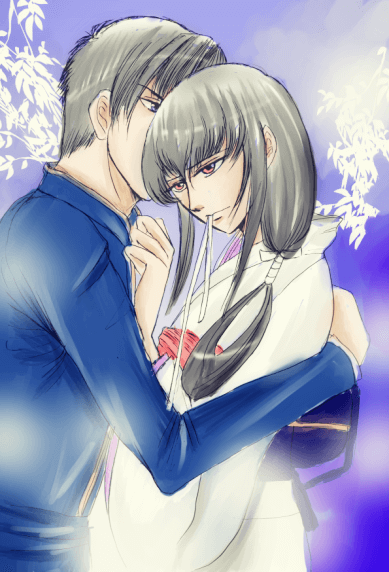
屍乱
2004~2006年作品
序
雪代縁は点々と続く、赤い血の斑紋をの上を、姉の銅筒を持って歩いていた。
もうすぐ、あいつが死ぬ。
あの姉の縁者の清里を殺した男が、姉の手によって惨殺される。
―――大人たちは、自分には黙っているが、ねえちゃんが抜刀斎の嫁になる、っていうことは、つまりはそういう事じゃないか。
抜刀斎は清里を無残に殺しながら、姉の巴に手を出した。
そんな男は死ぬべきだ。縁は単純だが純粋な論理でそう思っている。
剣心の姿は吹雪でよく見えないが、今ごろあいつは姉ちゃんのあの姿を見て、どうなっているだろう。
縁は思った。俺の姉ちゃんは強いんだ、自分の抱いた女に寝返られて、あいつは今頃動揺しているに違いない。
すでに闇の武の配下の者が、あいつの手足を奪っている。
姉は勝つ―――。縁は足元の雪を踏みしめた。
姉の巴が江戸を出た時、縁は待っているように言われたが、連絡が来て、姉の獲物を運ぶように言われたのである。
それは銅筒の中に収められた、二条の槍であった。
その槍を持って、今雪原に巴が黙然と立っている。
吹雪がその周りを舞っていた。
「嘘だ。嘘だと言ってくれ・・・・。」
剣心は我が目を疑った。
闇の武の辰巳はなんとか、今退けることができた。
力技で襲ってくる辰巳に対し、龍鎚閃をかけることに成功したのだ。
剣心はその前に二人の男から攻撃を受けていて、片目が見えなくなっていた。
「ぐっ・・・・若造・・・・、まだこれで終わりだと思うな・・・・。」
辰巳はニヤリと死苦笑を浮かべながら、雪原に倒れたが、その辰巳のもらした言葉、いや今まで対峙した闇の武の者すべてが、巴は間者だと言い放ったのだ。
―――京都にて、清里明良さまが、長州の手によって倒される―――ただただ、悲しく―――。
日記からこぼれおちた、ひとひらの桜の花びらが、残酷な事実を告げていた。
あれは、春の宵だった。
俺は路地裏であの男を討った―――仲間に清里と呼ばれていた。
あの時の男が―――そんな。
巴は大きな白い布をかぶり、布の端を口にくわえて吹雪の中に立っている。
夜鷹がよくやる仕草であったが、布の下に隠されているものを思うと、剣心には悲痛な思いが走るのだった。
うつむいた巴が口を開いた。
「盟主の命により、あなたさまのお命を頂戴します・・・・。」
巴は布をばさりとひきはいだ。
下からは武装した下帯が現われた。
剣心は目を見開いた。
これが、巴の正体か―――。
剣心の声が震えた。
「巴、嘘だったのか・・・・君のすべては・・・・・・・。」
巴は静かに言の葉を継いだ。
「清里さまをあなたに奪われ、でもそれはえにしの発端・・・・・私はあなたの思っていたような女ではないのです。」
剣心は胸をついて言った。
「君はそんなことをする人ではない・・・・君はやさしい・・・・いや、戦いを嫌っていた人だ・・・・・そんなことをするのは、おかしい、巴・・・・君との暮らしで俺はそれを学んだ。巴、君を斬りたくない・・・・。」
巴は答えた。
「わたくしをお斬りになりたくない・・・・・それはたいそうな自信ですね・・・・・わたくしは今絶望の淵に立っております・・・・・これ以上、何ものにも汚されたくないのに・・・・・わたくしはそんな生き方を選んでしまった・・・・・しまったから・・・・・・。」
「巴!嘘だと言ってくれ!」
剣心は叫ぶと刀を引いた。
水眼の構えである。
巴は無言で腰に槍をひきつけ構えていた。
もしも無事帰っても、わたくしは蒼紫との仲は引き裂かれるだろう。それが忍びの世界なのだ。
蒼紫様は否定しておられるけれど、と、先代御頭の孫娘のことは、巴の心に澱となってよどんでいた。
出て行った先代御頭の息子の、武士として生きる者の娘。
何故おわかりにならない―――その娘はきっと―――。巴の頭は哀しく働く。
あなたの御頭への道を決めさせるための罠なのです。
しかし、あの方はわたくしを育てたということで、御頭として皆に認められる道を歩まれるに違いない。
それ以外のことは巴には言えない。言えようはずもない―――二人で逃げようなどと。
抜け忍は死を意味していた。蒼紫は先代御頭の技を破ることができない。
それは冷厳な事実だった。
辰巳が死んだ今、その運命は決定的となっていた。
辰巳は巴の小さな上忍への反抗に、「できるのならば、やってみよ。」と言った。―――「おまえにくの一以外の生き方などできようはずもない。苦界に落とされた身、とっくと思い知るがよい。」と言いのけた。
巴は今必死で思う。
無力―――無力では、生きてはいけない。
抜刀斎の首を討ち、生きて江戸に帰ってみせる―――それだけが、今の巴の望みである。
そのためには、どんな試練にも耐えてみせる。
剣心の顔はしばらくうつむいていたが、隙はなかった。
剣心はやがて顔をあげて言った。
「一度は契り合うた拙者とそなた、しかしそう来ると言うのならば仕方がない。」
刀を握り返すと、剣心は言った。
「・・・・情を移すと、剣先が鈍ると思うてか。」
巴の槍を持つ手が一瞬震えた。
―――蒼紫様!
巴の脳浬に蒼紫との一戦が蘇った。
蒼紫様はわたくしに勝った。でもそれは、蒼紫様を愛していたから。
わたくしはこの者を愛してはいない。
だから、わたくしは勝つ・・・勝てるはず・・・わたくしは・・・・。
巴の心に剣心との寝やの記憶が蘇った。
そんなものにどうして動揺を――と思う巴だったが、巴の心が今揺れたのは確かだった。
巴は思った。
剣心は片目に傷を負っている。それに仲間の攻撃で弱っているはず・・・・。
と、剣心の体が俊敏な速さでこちらに向かってきた。
巴は第一撃を槍で防いだ。剣心はすかさず、前に体を倒して剣を一閃に凪いだ。
巴はあやうく槍で受けた。
続けて畳み込むように斬りあった。
―――そこっ!
巴は身をひるがえし、白い首をのけぞらせて宙に舞った。
剣心の後ろから槍で串刺しにしようというのだ。
「汚い手を使うな!」
ザッ。
剣心は叫ぶと、後ろ足で巴の体を宙で蹴った。
巴は着地したが、手をついてよろけた。だが、気丈にすぐに槍を立て直した。
剣心の頭は今混乱している。
清里を討った―――あれは、幕府のただの勘定方の人間だった。
その男の女が、何故忍者にまで転身して自分を狙うのだ。
しかも自分に、婚姻の儀式までして―――その瞬間、剣心の中で感情が爆発した。
勘定方を殺したのは、自分にとってはつらかった仕事なのだ。
巴はそのつらさをわかっていると言ってくれていた。
巴だけが心の拠り所になっていた。
それが嘘か。拙者の周りはみんな、嘘だらけか。
―――君の若い力が必要なのだ。今日から君は私の抜き身だ。
と、芸妓と酒を飲む桂小五郎が言った言葉に、最初は剣心は疑いを持たなかった。
新時代を切り開くための剣を振るうのだ―――それを最初は心から理解していたが、日を追うにつれ、剣心の中でお題目になっていた。
飛天御剣流は陸の黒船、というのは比古の口癖だったが、寝込みを襲われるような日々であるのには変わりがない。
そして孤独。
重い体を引きずっているような―――剣を手について、鉛のような歩みをしているような毎日だ。
山に帰ればよかったのだ、と剣心は思うが、それは何も成さずに朽ちることを意味していた。
比古は自分に、維新で剣をふるってはならないと言う。何故だ。
拙者は比古師匠にまで試されていたのか―――そう言う時の比古の顔は、笑っていた。
まるで拙者がむきになって出て行くのを待っているかのようだった。
―――拙者は間違ってはおらぬ。
所詮、人斬り、こんなもの―――しかし、これから先もこんな事が続くのか。
巴は槍の先を目の前で交差させていた。
剣心の目が細まった。
明らかに、忍びの技―――やはりではあの、雨夜の最初の出会いから。
紫の藤の傘を持って、雨の中に静かにたたずんでいた白い人影。
雨の中にただ白梅香の香りが匂って―――。
―――本当に、血の雨を降らせるのですね、あなたは・・・・・・・。
剣心の耳に、巴の声のささやきが蘇った。
しかし今は剣を持つ手は冷酷でなければならない。
「巴、君を信じていた!」
剣心は一声叫ぶと剣をものすごい速さで巴に突き、絡めた。
巴の体が剣心と交差した時、巴の片手から何かが剣心の頬をかすめた。
黒塗りの懐刀だった。
剣心の頬の傷の上に、新たに斬られて傷がついた。
その傷は、まるで十字の形をしていた。
ゆっくりと血が剣心の頬ににじんでいく。
剣心は巴の本気を感じた。
―――抜刀斎になりきらねばならぬ・・・・・・・・・・。
剣心は巴の背後にいる者たちを激しく憎んだ。
「二刀を使うとはおろか千万・・・・その刀がその方の泣き所と思え。」
巴は槍と懐刀を両手に持って対峙している。
剣心の気配が動いた。
巴は地を蹴った。
槍が剣心の体に降った。
巴は槍をからめながら、隠した懐刀に全体重をかけて、剣心の体を押し切ろうとした。
剣心の刀が一瞬それをはじいた。
巴が予想した倍もの力だった。
巴はその瞬間、剣心に体を斬られていた。
横ざまに、すさまじい速さの剣が貫いた。
雪原に赤い花びらがぱっと飛び散った。
「・・・・・しさま・・・・・・。」
巴の唇から、その言葉がかすかに震えて漏れた。
一瞬、巴は蒼紫の笑顔の幻影を見た。
あの抱かれた時のすすきの原だった。あの燃えるような抱擁。
―――秋茜が綺麗でしたね・・・・・。
巴の頬を涙が一筋こぼれた。
敗れたと思うさまもなかった。巴の体は黒髪をふり乱し雪原に崩れた。
「巴!」
剣心は剣を置いて巴に駆け寄った。
巴は完全に事切れていた。
剣心は巴の体を抱き起こすと、その頬にすがって泣いた。
「巴・・・・巴・・・巴・・・・君もだったのか・・・・・巴・・・・・・。」
何故拙者を裏切る。何故拙者を裏切る。君だけは裏切らないでいてほしかった・・・・・。
今でも巴は、あの大津の仮の宿で、拙者とだけ暮らしているのが本当の姿だ。
それ以外の姿など、俺は決して認めぬ――――。剣心の頬に、巴に斬られた赤い傷の血筋とともに、涙が流れた。
雪原の向こうに、縁は銅筒を持って立っていた。
姉が死んだ―――姉が。
あんなに剣の練習を積んでいた姉が―――あの優しかった姉が―――。
ブツン。
縁の脳裏に何か黒いものが走った。
今出てはならない――あいつに斬られる。でもいつか強くなって・・・・・・あいつを・・・・!
「巴・・・・さあ、行こう、巴・・・・。」
剣心は巴の体をかかえて、雪原をゆっくりと歩いた。
その体の主が、本当は誰に抱かれたかったのか、彼は知る由もない。
雪原に銅筒がひとつ置き忘れられている。
剣心は気づきもしなかった。
彼の心は、今暗い空虚に満たされていた。
谺声(かせい)
「あーめー、いらんかえー、
あーめー、いらんかえー。」
物売り娘の木魂のような声が響く、さびしい往来、と言ってもそれなりににぎわった帝都の一筋を、今、上京してきた瀬田宗次郎と、刑期を追えた悠久山安慈が歩いていた。
「不二さんも連れてこれればよかったんですけど・・・。」
「不二がどうした。」
「あの人は、案外甘いものが好きだったんですよ。」
「・・・・・・・・。」
「あ、あの団子はうまそうだなあ。」
「それだけ食っても太らないのか。」
「僕は、運動神経が違います。あ、美人画だ。」
瀬田宗次郎は、絵が何枚も並んだ店先の前で立ち止まった。
「ほう。これは、向こうの絵柄ですねえ。柳に美人とくれば、これは牡丹灯篭だなあ。」
「最近は、支那が大流行だな。」
「ええ、でもこれは日本人が描いたものですね。僕にはわかるんです。」
「ほぉ・・・・・。」
すると店の奥から、あの相楽左之助の盟友の、月岡津南が現われた。
どてらに腕をつっこんで、津南は言った。
「何かお探しですか。」
宗次郎は絵から顔をあげて、にっこり笑った。
「あ、あなたはもしや・・・左之助さんの・・・・。」
「おおこりゃ、十本刀の奴じゃねぇか。」
「これはあなたがお描きになったんですか。」
「ははは・・・・そうだよ、最近の時勢にあわせて描いてみたんだ。まあ評判はいいようだがね。」
津南は瀬田の言葉に、軽く肩をすくめた。
宗次郎と安慈は、津南にすすめられるまま、店先に腰を下ろした。
宗次郎は津南に尋ねた。
「左之助さん、いや、剣心さんたちはお元気ですか。」
「ああ、元気でやってるんじゃねぇか。俺もここんとこしばらく会ってねぇ。なにか・・・大陸に渡るとか渡らねぇとかでもめてるみてぇなんだが・・・・。」
「また・・・・山懸卿が?」
「剣心の野郎は大変だよ。左之助の奴は人がいいからなあ・・・・俺は見ていて、ため息が出るね。」
「そうですか・・・・。」
「あんたはどうしてまた、東京に来たんだ?」
「あなたと同じような理由じゃないですか?人恋しいんですよ。田舎はやっぱりどうも、田舎だったなあ・・・・。」
「俺はあんたと違う理由だがね。」
「そうですか。」
と、津南は安慈に尋ねた。
「そっちの人は、刑期は終えたんですかい?」
「ああ・・・・なぜか軽くしてもらってな。」
「恩赦ってやつかい。」
「そうなんですよ。いわゆる、ラッキーって奴です。」
「は、ラッキーねぇ・・・・そいつはよかったなあ。それじゃ俺は仕事があるから。」
津南はそう言うと、店の奥にひっこんだ。
津南は実は、十本刀の騒ぎの時に、わざわざ親友の左之助のために、京都にまで出向いて見舞いに訪ねたのである。
しかし、当の左之助は白べこで翁と酒盛りをしていて、津南をあっけに取らせたのであった。
――あいつは俺と拳で戦ったし、赤報隊時代のことも忘れてねえんだが・・・なんか、見てられねぇな。ああ、くさくさしやがる。
と、ふともう売り物にはしていない、仕事部屋の壁に貼った「相良総三」の錦絵が津南の目に止まった。
「総三さんよ、あいつのこと、見守っててくれるよう、お願いしますよ・・・・か。」
と、ひとりごちて、津南は絵筆を手に取った。
今描いているのは、大作である。
騒乱の町の様子が、仔細に丁寧に活写されている―――ただし、地方の動乱の一場面だ。
最近では、津南はそのような絵柄の人物や馬の動きを、本物のように描くことに苦心をしていた。
最近博物館で見た、西洋画の迫力に、度肝を抜かれたせいなのだった。
対象物への視線が全く違う―――遠近法ということは、津南にはわかっていた。
その驚きが、明治の人々が文明開化で味わったもののひとつなのだろう。
今まで描いてきた、人物画の錦絵が津南には惜しくはある。
その最後の手すさびが、中国画に似せて描いた、あの店先に並んだ美人画の群れなのだった。
「美人は化けて出ると申しますねぇ・・・・そろそろ退散かな。行きましょう、安慈さん。」
「そうだな。」
安慈と宗次郎は店を後にした。
夕暮れの町に、ひとしきり風が吹きつけた。
と、店先に置かれた美人画の一枚が、ひらひらと風で宙に飛ばされた。
それは気味の悪い動きだった―――しかし、もちろん、誰も気に止めるものがなかった。
美人画は、やがて近くの堀の川面の上に落ちた。
ゆっくりと、墨の筆跡が水ににじんでいき、そのまま水面下に白い紙が吸い込まれていく。
やがてそれは完全に消えた。
水面は何も上に乗ったことはなかったように、よどんで黒く沈んでいた。鏡のような水面であった。
その日、神谷薫は久し振りに倉の整理をしていた。
剣心はこのところ、元気だが、山懸卿の訪問を受けて、なんだかそわそわしているように、薫には見える。
――大陸かぁ・・・・。
山懸卿の相談ごとは、どうやら大陸に渡ってもらいたいという事らしいが、剣心は断っている。
薫はそれには半ばほっとしている。
また、十本刀の時のような思いはしたくはない。
剣心が出て行って、心配するのはもうごめんだわ――だって私は、剣心のこと・・・やっぱりその、大切に思っているから・・・・。
薫は自分よりもひとまわり年の離れた剣心のことを、自分の兄のように慕っているのであった。
それにしても剣心、ちょっとは手伝いなさいよ。こういう時は必ず、弥彦と二人で逃げるんだから。
そりゃ食事はたまに作ってくれるけどもね・・・ついでに私よりも上手だけどね・・・・・。
薫は後ろで娘様に縛った髪の上にかけた三角巾を、もう一度縛りなおすと、倉の奥の棚を見上げた。
――お父さんの残した本・・・・・・私には読めなかったわね・・・・。
詰まれているのは、父の残した漢籍の本であった。
と、その棚の上に、見慣れない新しい藤色の冊子がおかれているのに、薫は気づいた。
――何かしら・・・・・。
これ、埃をかぶってないわ。剣心がここに置いたのかしら・・・・。
薫は手にとってみた。古い絵草子のような表紙であり、白い付箋がしてある。「日うつり」と付箋には書かれていた。
開けてみると、日付に沿って文字が連なっていた。
「日記・・・・。」
薫はつぶやくと、ページをめくって読んだ。白い紙はところどころ黄ばんでいるが、墨蹟は今書いたように鮮やかである。
筆文字の特徴であった。薫は読みにくい崩し字を読んだ。
「縁と今日は縁日に行きました。父上の消息はやはり、見つからなくて・・・・・。女の人の文字だわ。剣心に女?ちょっと許せないわね。でも、まさか、ねぇ・・・。」
薫はそうつぶやくと、もう一度その本を見返した。
やっぱり、ここに置いたのは剣心だわ。弥彦じゃ絶対ないわ。倉の鍵はしまっておいたはずなのに、剣心が勝手に入ってここに置いたのよ。
薫は本を胸に抱くと、大きくため息をついて、倉のほこりっぽい壁にもたれた。
「剣心・・・昔のことは何も話してくれないのね・・・・・ごめんね、私にこっそり知らせるつもりだったんだよね・・・・。」
薫の胸は今動揺していないと言ったら嘘になる。
「そうだ・・・・操ちゃんに相談しようかなあ・・・・恵さんだと、ほら見たことか、って言われるし、きっと。剣心は私には過ぎた人だったんだよね・・・・・・もともとは。」
薫はそう言うと、本を持って、暗い倉の階段をきしませて下に下りた。
薫は思った。
この日記をこれから読まなくちゃ。きっと剣心の昔の女の人のことなんだわ。
でも、剣心には面と向かって言えないわ。だって、その、剣心に厳しく問い詰めたら、私はとても嫌な女になってしまう。
そう、あの恵さんみたいに・・・・・。
――あなたのそういうところが、剣さんの足をひっぱっているのよ。
薫の耳に、自信に満ちた恵の声がこだました。
いいなあ、恵さんは、容姿にも頭にも名前の通りに恵まれていて・・・・。
でも恵さんは、剣心に少し距離を置かれていること、気がついてないのよね・・・・・。
薫は倉を出ると、本を自分の鏡台の引き出しの底に隠した。
鏡に写った自分の顔は、やはり恵に比べると貧相だ。
薫は思った。
操ちゃんは今は、蒼紫さんと一緒に東京で暮らしてるのよね。
幸せいっぱいよね。でも、蒼紫さんに女学校に通わされているみたいだけど。
蒼紫さんもほとんど家にいないって聞いてるし。
だからこんなこと、操ちゃんに今相談してもなあ・・・・。
薫の意識下で、無意識での繰言は、えんえんとその日続いた。
東京の山の手に、その女学校はあった。
洋風のミッションスクールは少人数制で、教師は宣教師のシスターであり、授業は最新の英語の授業があるというので、近くの高級住宅に住まう子女らが通っていた。いわゆる、名門校ではあるが、あの赤門ほどでは決してない。象牙の塔には到底及ばず、高給取りの親が、娘を通わせて安心できるというほどのものであった。
その放課後、御堂茜は、同級生である巻町操におそるおそる声をかけた。
操は同級生の中でも、一種独特の雰囲気を持った少女で、あまり話などもせず、いつも一点を見つめているような感じがあり、仲間のうちからは敬遠されていた。
たまにある庭球の授業では、むきになって相手に勝ちに出るところがあり、巻町さんと庭球をすると、面白くない、という陰口を叩かれていた。
また、長い髪をひっつめにして垂らしているのも、シスター達からは評判がよろしくなかった。
「切りなさい。」
と、ある日シスターが教鞭の先であごをあげさせて操に言ったところ、操は敵意のある目でシスターを無言でにらみつけた。
「あなたね・・・・まあいいわ。ここは裏長屋の所帯じゃないんですよ。皆さんと一緒に、勉学に励むための場なんです。あなた、魂だけはそれを肝に命じなさいね。」
とシスターが言って、教壇に立ったのちも、まだ操の光る視線は教師であるシスターをにらんでいた。
その操が、今席を立って、机の中の教科書を革かばんの中に入れていた。
女学生らしい袴姿であったが、色黒なので、ピンクの袴はあまり似合っていなかった。
「あの・・・・巻町さん・・・・ちょっといい?」
「何?」
操は前髪を振り払うようにして、顔をあげた。
同じクラスの御堂茜は、優等生タイプで気の弱そうな少女だ。
「あの・・・・巻町さん、あの・・・・・学校でね・・・陰で噂になってるんだけど・・・・。」
「なんなの。はっきり言って。」
「巻町さん、男の人と暮らしているんだって・・・・・噂になってるの・・・・・・・・・・・。」
操は目を見張った。
「巻町さんって、おばあさんと二人暮らしだよね・・・・確かそう聞いていたんだけど、巻町さんの家に男の人が入るのを見た人かいるの。」
「新聞の集金取りじゃないの。」
「え・・・・そうじゃないもん・・・・そんな御用聞きみたいな人じゃなかったって・・・・・親みたいな人にしては年齢が若そうで・・・・・・夕方の薄暗い時に入っていくのを見た人がいて・・・・・。」
「それが何?」
操は切りつけるように答えた。
「最低ね。人の家がどうだって関係ないじゃない。」
そして、唇の端で笑うように言った。
「あんたたち、私が男と同棲しているって言いたいんでしょう。」
「そうじゃなくて・・・・本当かなって聞いてるの・・・・・。」
「じゃあ嘘よ。私は一緒になんて暮らしてないわ。」
操はそう言うと、かばんから何かを取り出した。
「そんな奴が来ても、私は大丈夫よ。これがあるんだから。」
御堂茜は目を見張った。
操の手には一本の光る苦無が握られていた。
茜はそれが苦無とはわからなかったが、刃物だという事だけは認識できた。
茜は諭すように言った。
「巻町さん、あなたね・・・・学校に刃物を持ってきてはいけないわ・・・・・。」
操は振り払うように叫んだ。
「うるさいわね。あなた一体なに?私に何が言いたいの。私は今ひとりぼっちよ。乳母と一緒に暮らしているだけなんだからっ。」
「巻町さんっ。」
茜が手を差し伸べるのを振り切って、操は外に駆け出した。
―――私―――私、やっぱり京都に帰りたい。じいややみんなのところに帰りたい・・・・。
操は堤防のところまで来ると、苦無を川に投げようとして、思いとどまった。
蒼紫が目の開いた自分を迎えたとき、これでようやくみんなで暮らせると思った操であったが、蒼紫は翁と長談判の末、操をつれて東京に出ることに決めたのである。
操は認めたくないのだが、ついに翁とは決裂したらしい。
そして、操はよくわからないまま、下働きの女中の老婆をあてがわれて、ひっそりとしたしもた屋に今暮らしている。
蒼紫はたまにしか来ず、上京の途上がそうであったように、泊まることは決してなく、操を値踏みするようにしつけて帰る。
そこは、牢獄の家だった。
乳母は田舎から出てきた百姓女で、操と話が合わないばかりか、やはり蒼紫とそういう仲であると見て、いびるように下品な冗談を言う。
この前蒼紫の前でお茶の点前をした時は、最悪だった。
無言で蒼紫は座っているのだが、気にいらないというのは、その空気で操には伝わった。
茶器、器を型どおりに答えた後、蒼紫が言った一言の響きが、今も操の耳には残っている。
「結構な点前だった。」
飽き飽きした、という響きだった。
もちろん、蒼紫はそれだけで帰っていった。
何処に泊まっているのかは操にはわからない。
私は蒼紫に飼われている、と操は思うのだった。
愛情の一滴を与えられるまで、じっと我慢をする犬のようだ。
しかし、自分から蒼紫を求めるのは、操には到底できないのだった。
やはり男が怖いのである。
蒼紫が自分を好きなんじゃない、と思うと頭が壊れそうなぐらいになるのだが、自分から近づくことはできないのだった。
「さびしいよう・・・・・さびしいよう・・・・さびしいよう・・・・・。」
布団の中で丸くなりながら、涙を流して震えながらつぶやく操の姿を見たら、翁は何と言っただろう。
でも、一人でもう生きていかねばならない。
翁だっていずれいなくなる・・・・・・私は耐えなければいけない。
操はそう思った。
蒼紫が心を開いてくれる日まで、ただ待つだけ―――待つだけ・・・・・。
でも、そんな日は果たして来るのだろうか。
私はもう、忍びとして生きるな、と蒼紫はある日突然に言った。
「あっ、それっ・・・・。」
「全部没収だ。」
苦無の束と小刀を操から奪うようにして集めると、蒼紫は庭に置いた箱の中に乱暴に投げ捨てた。
「危険な任務には、これ以上つかなくていい。嬉しいだろう。」
「いやだ。そんなの蒼紫様じゃないよ。みんなと一緒に御庭番衆やるんだから。」
「操っ。」
蒼紫の顔が本当に怒っていた。
「遊びだと思ってるな。」
「思ってないよ、思ってないよ、そんなの。でも、蒼紫様だって忘れてる・・・・・。」
「何をだ。」
「御庭番衆だったこと。」
操の一言に蒼紫の目が暗く光った。
「なるほど。おまえにはそう見えるわけだ。」
「女学校なんて、行きたくないよ。私、御庭番衆でがんばりたい。」
「馬鹿っ。」
「馬鹿って言った・・・・蒼紫様が私のこと、馬鹿って言った・・・・・!」
操は半泣きになっていた。
あとは思い出したくなかった。
蒼紫は不機嫌な荒々しい足取りで、部屋を出て行ってしまった。
「蒼紫様・・・・・ごめんなさい・・・・でも、今の蒼紫様は嫌なの・・・・・・・・!」
操は堤防にうずくまり、膝に顔を埋めて肩を震わせて泣いていた。
「操・・・・ちゃん?」
操の背後で薫の声がした。
お気に入りの白い日傘を差して立っている。
薫は目をぱちくりさせている。
「ひょっとして、泣いてるの?」
操はあわてて、目を手で拭いて立ち上がった。
「え・・・・ええ・・・・何?薫さん。わざわざ山の手まであがってきたの?」
「うん・・・・ちょっと、相談したいことがあって・・・いいかな?学校からここまで探すのに、苦労しちゃった。」
薫はそう言うと、目をそらした操の顔をまじまじと見つめた。
「何か・・・あったの?蒼紫さんとうまく行ってないの・・・・?」
操は大きくかぶりを振った。
「ううん。学校でね、蒼紫様と同棲してる、って噂を立てられて、ちょっとショックだったんだ。」
「なんだー、もう学校って嫌よねー。私も剣心と同棲しているわよ。」
「薫さんたら・・・・・。」
操は苦笑した。
二人は堤防に横になって座った。
薫は言った。
「私はもう、学校には通えないけど・・・・・それであのね、実は剣心のことなんだけど・・・。」
「うん。」
「昔女の人がいたみたいなの。」
操は一瞬ドキリとした。
蒼紫もひょっとして、女が今いるのかも知れない、というのは、操はもちろん考えたことがあったのだ。
絶対に泊まらないのは、女がいるからだ。
その想像は、最悪のものであった。
しかし、操はつとめて明るい顔で答えた。
「剣心はほら、恵さんにもよく迫られているし・・・・そういう事あっても仕方ないんじゃないかなあ。」
「あらぁ、操ちゃん、ひどいわねぇ。私すごーくショックだったんだから。」
「それでね、もう剣心ったら、その女の人の日記をねー、私の目につくように置いていたのよ。」
「なにそれ。」
「だからぁ、男心ってやつかしら。」
「ふーん。剣心ってすけべだなあ。それでその日記は読んだの?」
「まだ半分しか読んでないんだけど・・・・というのは嘘。読んだわよー。なんか一緒に暮らしていたみたいね。ただ・・・・。」
薫はそこで遠い目をした。
「その日記ね、日付がとびまくっているのよ。最後のほうは、文字がすごく乱れていて、読みにくかったんだけど・・・・・なんか監視しているみたいな感じなの。抜刀斎と今日は大津に行った。薬の行商は何文売れた。今日は機嫌がいいらしい、とか・・・・。」
「愛がこもってないのね。」
操の一言に薫は一瞬たじろいだが、答えた。
「そうそう、そういう感じかなあ・・・・。」
「冷たい愛ね。きっと最後のほうはうまく行ってなかったんだよ。それで薫さんにきっと慰めてもらいたいから、その日記を置いたんだわ。」
「そうね・・・・きっと剣心、つらかったのね・・・・・。」
「薫さん、剣心を慰めてやりなよ。」
「うん・・・・・。」
薫は操に相談してよかった、と思った。
恵ならきっと、剣心に対していたらない自分をまた、いろいろとあげつらったことだろう。
薫は立ち上がって言った。
「じゃあ、操ちゃん、私帰るわ。」
「えっ、薫さんわざわざそれだけのために・・・・?」
「いいの。そういう操ちゃんの言葉を聞いたら、ますます剣心を支えないといけない、って思うようになったわ。」
薫は腕まくりをして見せた。
「そう。がんばってね、薫さん。」
薫が去っていく後ろ姿を見ながら、操は思った。
私はまた、あの苛烈な家に帰らなければならない。
それは、薫さんには言えない。
薫さんには・・・・・・・。
蒼紫様と私の問題なんだもの。
何よりも怖いのは、蒼紫がひどすぎる、と薫や剣心たちが乗り込んできて、蒼紫との仲を引き裂かれることであった。
また離れるのは嫌よ。絶対に嫌。
操はそう思うと、堤防沿いの石段を一気に駆け上がった。
蒼紫はその夜、暖簾の店で呑んでいた。
――呑めないお酒なんか、呑んで。
巴のとがめる声が、耳朶に響いた。
蒼紫の顔に苦笑が浮かぶ。
――俺は、最低だな。
操を奪うようにして、東京につれてきた自分だったが、いざ操と顔をつきあわせてみると、巴との比較がまざまざと浮かびあがり、この少女を守るために、自分は島原にまで足を運んだのだ、と思うと蒼紫の中に苦いものがこみあげてくるのだった。
ふるさとは遠きにありて思うもの、と人は言う。
かつては自分にとって操はそうだった。
あの操のためにしてやれる事は何なのだろうと思っていた。
しかし操は―――。
あの翁が甘やかしたせいだ、とわかっている。
いや、もともとあの巴と比べることのほうが間違いなのだ。
自分が操に対して酷薄なことをしていることはわかっている。
しかし、御庭番衆に戻りたいと、まるで駄々をこねる子供のような事を言うのには、蒼紫は憤りを抑えることができなかった。
京都御庭番衆。
それは、あの頃長州の暗躍に手をこまねいて、及び腰で朝廷をさぐることばかり熱心にやっていた連中だった。
その穴の存在には、蒼紫は早くから気がついていたが、どうすることもできなかった。
巴は、そのぽっかりと開いた穴に吸い込まれたのだ。
蒼紫はその翁を観察する意味も含めて、操を預けたのだったが―――。
―――翁は、愚劣だ。
そう結論づけて、翁を処罰することにしたのだが、それは操にとっては信じられない出来事であったようだ。
―――そんな蒼紫様は嫌い、か・・・・・・。
「・・・・・宇治十帖か。」
蒼紫のぼそりと言った一言に、店のおやじがうちわで扇いでいる魚から顔をあげた。
「何か深刻そうだね、あんた。雰囲気が暗いね。」
「・・・・・・。」
「そういう時はぱーっと、女でも抱いたほうがいいよ。あ、おあいそね。へい、二十銭。」
蒼紫の杯を持つ手がびくりと震えたが、おやじは全く気にせずにほかの客の釣りを数えていた。
そこへ、なじみの様子であの男が現われた。
「なんだ。呑めるようになったのか。」
斎藤一だった。
斎藤は蒼紫の横の席に座った。
「まずそうな酒を飲んでいるな。」
「大きなお世話だ。」
「おやじ、俺にも一杯。冷やでいい。」
「まいど。」
斎藤の前にコップ酒が置かれたが、斎藤はそれを取らずに口を割った。
「荒川あたりで、また積荷があがったぞ。中は贋金でいっぱいだ。」
「それがどうした。」
「ふ・・・・おまえ、関係があるんじゃないのか。積荷は上海経由で流れてきたものだ。」
「・・・・・傀王は始末した。」
「ああ。自滅したな。大変な事件だったよ。ところで貴様にはなんで恩赦がかかったのか、俺に聞かせてくれないか。」
「知らん。おまえの調書が間違っていたのだろう。」
「・・・・ふ・・・ん。まあいい。ところで最近女を囲っているらしいな。いい趣味じゃないか。仕事も大変だろうに、その歳でよくもまあ・・・俺がおまえの歳には、まだまだ独身だった。」
「くだらん妻子の自慢話なら、聞きたくない。おやじ、勘定。」
蒼紫は立ち上がって、コートのポケットから銭を取り出して、おやじの手に渡した。
斎藤は立ち上がった。
「待てよ。貴様、警視庁から目をつけられているぞ。」
「貴様に言われなくても、わかる。」
「まあそうだな。乗鞍彦馬の奴は、片腕がきかなくなって、貴様のことを疫病神だと言っている。まあ恨んでいるよ。そんな奴が多いから気をつけるようにご忠告までだ。」
「それはいたみいる。」
「で、外務省には報告はしたのか。」
蒼紫はきついまなざしで、斎藤を振り返った。
斎藤は煙草を口にくわえて、煙を吐き出しながら言った。
「隠密御庭番衆。表向きは解散という形を取ったようだが、まだまだ悪鬼がうごめいているようだ。貴様のように。」
「・・・・・・・・・・・・・・・・・。」
「まあ目につく派手な奴は貴様ぐらいだがな。」
「解散した後の連中のことは知らん。」
「嘘をつけ。手駒にしているんじゃないのか。」
「貴様と俺は違うのでな。」
「どういう意味だ?ああ、沢下条のことを言っているのか。」
「瀬田宗次郎が上京してきたようだ。」
「ほう。もう知っているのか。感心だな。さすが隠密御庭番衆だ。」
「何か役立てる気だな。まあ、あの男は根が単純だから、使いやすいだろう。」
「ふん、さすが敵地で味見しただけのご意見だ。」
「邪魔だな。」
「ああ、俺はおまえの邪魔をするよ。」
蒼紫は顔をそむけると、斎藤を無視して歩き出した。
斎藤はその背に向かって言った。
「なんでおまえは奴らが気に入らないんだ。おまえも抜刀斎の首を狙っていたんだから、同じ穴のむじなじゃないか。改心して素直になったんだから、見直してやってもいいじゃないか。」
「志々雄真実の過去はどこまで洗った。」
「志々雄真実か。元長州の暗殺者。桂小五郎の下で、抜刀斎のあけた穴を埋めた男だ。用済みになって、体ごと石油をかけて燃やされた。その頃おまえは何処にいたのかな。俺は興味があるんだがな。」
「新撰組で貴様が忙しかったように、俺も忙しかった。帰るぞ。」
蒼紫はそう言うと、斎藤を後にした。
斎藤はひとりごちた。
「ふん・・・・・幕府の犬が、出世したもんだ。新撰組は、おまえらにつぶされたんだからな。」
煙草を闇にほうると、斎藤は蒼紫とは逆の方向に向かって歩き出した。
蒼紫は斎藤に会った次の日、定宿にしている裏宿屋から、日本橋にある警察の特務課に出向いていた。
斎藤の勤める部署とは全く違っており、犯罪捜査に関する係りである。
鑑識と言ってもいいかも知れない。
丸眼鏡をかけた、中背のさえない中年男とその部下が、出向いてきた蒼紫を迎えた。
蒼紫はやはり、大刀を手にしていたので、最初その二人は面食らった様子だった。
蒼紫は言った。
「外務省の方から出向するように連絡が入ったので来た。」
「ああ・・・すいません。四乃森蒼紫さんですね。実は、あなたがそういう知識にも詳しいと聞いて、お願いしたいのです・・・・。」
横に立つ青年が言った。
「こちらです。」
蒼紫は執務室から続きの間になった、薬品物が並んだ部屋に入った。
「これです。」
蒼紫の目の前の机の上に、白い紙の上に乗せられた、少量の薬品物がある。
白い粉だった。
青年は声をひそめて言った。
「危険ですから、手ではさわらないでください。」
蒼紫は答えた。
「わかっている。顕微鏡はあるか。」
「倍率は600倍のものしかありません。」
「それでいい。見せてくれ。」
蒼紫は黒の革手袋を、白の医療用のものにはめなおすと、注意深く薬品を匙ですくい、顕微鏡をのぞいた。
プレパラートの上に、整然とした結晶体が見える。
「阿片ではないな。」
「はい、阿片ではありません。もちろん大麻でもありません。」
「そうだ。大麻は樹脂だからな。しかし、抽出したものかも知れない。」
「そんなことができるんですか・・・・・・。」
「設備があれば、できるだろう。」
「・・・・・・・・・・・・・・。」
そこでやっと、中年男が重い口を開いた。
「中毒患者の所持した品から、これが立て続けに出てきました・・・・・阿片騒ぎの時は、あなたは、密造に手を貸しておられたそうですが・・・・・。」
「俺はやっていない。」
「そ、そうでしたな。やっておられなかった。敵情を探るために、その女のところへ行っておられたのです。」
「あがった場所は何処だ。」
「北千住です。」
「昔の四宿のところか。」
「そうです。荒川と隅田川にはさまれた地域です。」
蒼紫は椅子から立ち上がった。
中年男は蒼紫に向かって言いにくそうに言った。
「もちろん、あなたのような方の手をわずらわせずとも、警察のほうで今全力をあげて捜査しております。今回は、阿片密造の時の身の潔白を証明していただきたく、お呼びいたしました。密造者ならば、協力はなさらないだろうと。」
蒼紫は観柳邸でのことを思い出しながら、答えた。
「警察は贋金づくりの方も追っているから、大変だな。」
「その通りです・・・・。」
「残念だが、俺にもこれが何かは全くわからない。新種の阿片かも知れん。」
「心あたりは全くありませんか。」
「多分海外からの密輸品である可能性が高いな。中国、ハノイあたりか。朝鮮アサガオ、アメリカからのペヨーテではないだろう。」
「ペヨーテというのは・・・・・。」
「アメリカ・インディアンが使うサボテンの一種だ。ほかにはペラドンナ、マンドラゴラなどがあるが、それらは大量生産には向かない品種だ。俺が知っているのはこれぐらいだな。」
「御庭番衆時代はどの麻薬に一番、親しんでおられましたか。」
蒼紫は眉根を寄せた。
「どういう意味だ。」
「いえ、乱用していたというのではなく、任務でお使いになったのは・・・・。」
「忍者の里で栽培されていたのは、ご存知の通り大麻だ。俺は使ったことはないが。阿片の原料の一貫種の芥子、すなわち「津軽」はご禁制の品なので栽培はされていなかった。」
「お聞きしにくい事に答えていただいて、どうもありがとうございます。」
「中国人密売組織の線で洗ってみるのだな。元御庭番衆は関係ないだろう。」
「だと、ありがたいのですが・・・・・。」
その時、研究室の戸口に、あの乗鞍彦馬が片腕を包帯でつりながら現れた。
部下を数名、ひき連れていた。
「やあ、おひさしぶりです、四乃森さん。今別室であなたのお話を聞かせていただきました。ずいぶんと、毒関係にお詳しいのですね。僕は驚きましたよ。さすが元御庭番衆、一服盛るのには慣れておられるようだ。」
あいかわらずの、人を馬鹿にしたような言い草の乗鞍彦馬だった。
蒼紫は彦馬の腕に目をとめた。
「その腕は・・・・・。」
「ああ、あなたがいた教会を狙って撃った、海軍と傀王の大砲の破片があたりましてね。この通りです。あなたは五体満足ですか。神の恩寵というのは、あるものなんですねぇ。あなたの場合は恩赦もありましたから、あなたは本当に運がいい・・・・・・。」
彦馬の目の奥では、蒼紫に対する恨みの炎がちろちろと燃えていて、執念深い蛇を思わせた。
蒼紫は黙って彦馬の目を見返した。
彦馬は言った。
「さて、元御庭番衆は関係ないとおっしゃりたいようですが、残念ながら敵の組織の一員として働いているようです。」
「なに。」
「毒に特に詳しかった男ですよ。島原であなたに同行した者たちではないですね。」
蒼紫の頭の中で人別帖のリストが瞬時にくられた。
「土蜘蛛――――。」
「ああ、土蜘蛛と言うんですか。女郎蜘蛛じゃないんですね。なんだ、女ではないのか。」
「女がどうかしたのか。」
「その劇症阿片をばらまいた奴の中に、高荷恵のような女がいるんだそうですよ。荒川沿いの私娼窟に出入りしているようです。暗号名は『蘭』と言いますが、『李花』とも呼ばれています。」
「リーホウ・・・・中国人か。」
「多分そうなんでしょうが、確証はまだありません。私娼窟でときどき客を取っているようですが、士族の男を特に好むのだそうです。」
「そういう男に阿片をばらまいているのか。」
「そうです。日本人の娘にも化けるそうですが、たいていは中国服を着ているのだそうですよ。ただ、つかまえようとすると、必ず逃げられます。」
「逃げ足の早い女なのか。」
ここで彦馬は馬鹿にしたように笑った。
「用心棒がいるんですよ。凄腕の奴が何人かいてね、女を守っているんです。まあ女衒ということです。」
と、彦馬はずい、と蒼紫の前に進み出た。
「あなたにとっちゃ関係ない事件かも知れませんがね、元御庭番衆が関わっているんです。捜査に協力してもらえませんかね。僕は見ての通りですからね。」
「斎藤がなんとかするだろう。」
すると彦馬は大声で笑った。
「あの先生が?あの先生が今度の奴らをしとめるって?そいつは無理な話ですよ。もう一度間抜けに逃げられました。で、別件の贋金の捜査をしているんですよ。まあどうせ裏でつながっていると思いますがね。」
そう言って小馬鹿にして笑う彦馬の様子を蒼紫はしばらく眺めていたが、やがて蒼紫は言った。
「俺も別件で忙しいが、どうしてもやらなければならないのか。」
「そうです。やらなければ、今度こそ刑務所に入っていただきます。今度の敵は強敵ですよ。何しろ、日本剣法ではないんだ。あなたのような、忍術を知っている人間でないとおそらく太刀打ちできないでしょう。という事で、あなたに白羽の矢がまた当たりました。忍術というのは、そもそも中国から渡ってきたものですからねえ。それに。」
ここで彦馬はねぶるように目を細めた。
「観柳邸で阿片を密造していたのを、黙って見ていた罪は重いですからね。是非雪辱を雪いでください。」
「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。」
「それともあの時は、高荷恵と阿片でもやっていたんですか。あなたほどの人が、またなんで黙って見ていたんですかねぇ。」
「勝手にしろと思っただけだ。」
彦馬はあきれたというように、片手をひろげて叫んだ。
「ああ、どうでもよくなったわけだ。世の中というものがどうでもよくなったわけだ。その理由を是非僕にお聞かせください。」
「抜刀斎を倒す事だけが、頭の中にあった。」
「ふふ、緋村抜刀斎ですか。あの人はあなたの一体何です?寝首をかくのは、わけもないだろうに、なかなか決闘もせずに馬鹿正直にあくまで小太刀二刀流で戦う―――本当にあなたは面白い人ですよ。」
蒼紫は彦馬をさえぎるように言った。
「一応、今日のところは帰らせてもらう。荒川沿いの地図はないのか。」
「ああ、ありますよ。×印のところが、警官が奴らに惨殺された現場です。ご参考までに。」
彦馬は蒼紫に小さく折りたたんだ地図を渡した。
地図は隅田川横の向島のあたりで、玉の井の某所に○印が赤鉛筆で囲んであった。
「そして○印のところは私娼窟で、女が出たところです。ひょっとして、あなたはそこで大変面白いものを目にするかも知れません。僕はそれが楽しみだなあ。」
そう言うと、彦馬はポケットから煙草を取り出して、口にくわえた。
「四乃森さん、さっきあなたの話したことには、嘘がありますね。」
蒼紫は出口を出ようとして、振り返った。
彦馬は言った。
「大麻は使わなくても、ほかの植物は使いましたね。そういう後ろ暗さがあるから、高荷恵に同類のにおいを嗅いで野放しにした―――僕は心理学にも詳しいんですよ。」
蒼紫は険しい顔つきになった。
「貴様。」
彦馬は楽しむように言った。
「あなたはかわいそうな人だな。麻薬なんて、弱い人間が使うものです。」
彦馬はそう言うと、蒼紫の立つ廊下の前の扉を、バタンと音をたてて閉めた。
剣心は今、河岸をひとりで歩いていた。
―――薫殿は拙者の残した巴の日記を読んだだろうか。
多分、読んだ。
読んだはずだ。
薫の目が、いつもと違って動揺していた。
もう少しだ・・・・・拙者のことをわかってくれる薫にするのは、もう少しだ。
巴と祝言をあげたくだりも、薫はもう目にしたはずだ。
弥彦の前では、いつも通りに明るく振舞う薫だったが、時々いつもと違って呆けたような顔になる。
その顔を、剣心はかわいいと思う。
そういうかわいい娘のところで、残りの人生を送る―――それは、剣心の心にあいた傷を埋めるに、絶好の機会であり、場所であった。
だが。
剣心は河岸で立ち止まった。
追ってくる――――あの男は、何処までも拙者を追ってくる。
何故本当のことを言わない。
あの四乃森蒼紫という男は―――。
剣心の心が、蒼紫のことを思うと、打ち震えた。
頭の中に、蒼紫のあの時の言葉が、割れ鐘のように反響する。
その声を聞くと、頭が割れそうになる―――誰か拙者を助けてくれ。
「最強の華を手にするためならば、俺は何にでも変わってみせる。」
剣心はその蒼紫を既に半死半生の目に、二度もあわせている。
殺してしまえばいいのだ、と思うのだが、技の上でも殺せないばかりか、あの男がおそらくは巴を変えたのだという予感が、剣心の心を打ち砕くのだった。
背中からいつ斬られてもおかしくない殺意を、剣心は常に蒼紫には感じている。
御庭番衆は恐ろしい連中なのだ。
しかし拙者は、人の道を説いて退けたはずだった。
拙者はけして間違っておらぬ―――悪いのはおまえ達のほうだ。
しかし――――。
巴が愛していたのは拙者ではなかった―――巴は拙者を愛してはくれなかった。
それが明白なものとなるのが、剣心は怖い。
拙者は巴を殺しはしなかった。
拙者は殺すつもりはなかったのだ。
あれは巴が悪いのだ。
巴を拙者はあんなに愛してやったのに、巴は・・・・・・・・。
剣心は足をひきずるようにして、暗い路地に入った。
もう酒は何杯か飲んでいる。
これ以上は酔えそうになかった。
「そんなにおいしそうに、お酒を飲むから。」
「おいしい。あなたに会って、お酒の味が変わってきました。」
「私も昔は、お酒にたよってばかりいて―――。」
くすくすと笑うような巴の声が、剣心の耳元でささやく。
「巴・・・・・・・。」
剣心はその木戸にぶちあたるようにして、中に入った。
「お兄さん、いらっしゃい。いつもの部屋かね。」
「ああ・・・・。」
男が剣心の手を取って、二階の階段へと導いた。
薄暗い木の階段は、暗黒へとつながっているようだった。
最初に見かけたのは、町の往来だった。
―――巴!
確かに巴を見た、とその時に思った。
それが何度かひき続き、剣心はその娘の後をついに尾行することにした。
娘は路地の裏に吸い込まれた。
娘は着物まで巴とそっくりだった。
「あの娘が巴のはずがない。帰ろう。」
と思ったその時だった。
後ろから木で殴られ、剣心は失神し、気がついたときは、その娘が体の上にいた。
朦朧とした頭で、剣心は尋ねた。
「君は・・・・・。」
「雪代巴・・・・・・・・。」
娘の発音が、少し変だった。
しかし、体は動かない。
娘が忍び笑いを漏らしながら、剣心に顔を寄せて尋ねた。
「あなた、私のことが好きか?」
なぜか好きだと言いたくなり、剣心は首を縦に振った。
この娘は髪型ばかりか、顔まで巴とそっくりだ。
あとは、その逢瀬を繰り返して続けている。
まるで坂道を転がり落ちていくかのようだった。
「巴・・・・・今日も待っててくれたのかい・・・・・。」
「はい・・・・・剣心さんのこと、私は好き。」
「そうか・・・・・。」
今では、娘の衣装が中国風のチャイナ・ドレスに変わっていても、剣心はかまわず手を伸ばした。
白い絹服の胸の上に、紫の糸で蘭の模様が描かれている。
「綺麗だよ、巴・・・・・。」
その服をゆっくりと脱がしていく。
白い太ももが割れて、娘の陰部が剣心の目に入った。
赤い炎症が点々と斑紋のように浮き上がっている。
娘が耳元で熱くささやいた。
「私にそんなことしたら、あなた死ぬね。」
剣心の手が震えた。
赤い点は、巴を殺したときに雪に散った血痕のようだった。
いやだ―――拙者は―――もう誰も殺さない。殺したくない。殺せない。
剣心は娘との情事に没入した。
何も考えたくなかった。
甘い煙が部屋中に充満していた。
その次の部屋に、中国服姿のたくましい男が一人、黙然と立っていた。
「ねえちゃん・・・・・・。」
男の気迫は、部屋の中に充満し、今にも爆発しそうだった。
「ねえちゃん・・・・ねえちゃん・・・・ねえちゃん・・・・・。」
それは巴の弟の、雪代縁の成長した姿だった。
縁の握り締めた拳の上に、君の悪い神経の脈が浮かび上がってきた。
と、扉が開いて、一人の短く髪を切った背の高い中国服の男が入ってきて、雪代縁の横に立った。
男は言った。
「あれは君のお姉さんではないよ。王大人のやり方には感謝したまえ。」
「呉黒星・・・・。」
黒星は含み笑いをして言った。
「堕ちるところまで堕ちたところを、君がしとめるんだ。そうすれば、君の姉さんも喜ぶ。」
縁は壁に拳をぶちあてて言った。
「あんたには俺の気持ちはわかんねぇ・・・・・わかんねぇよ!」
「君はしかし、どちらの男を本当に恨みに思っているのかな?」
「どっちも恨みに思っているさ。」
「ふん・・・・しかし、抜刀斎という男は簡単にひっかかったな。」
「あいつはそういう奴だからよう・・・・・。」
「四乃森という男には、君はこの罠は張らないのは何故かね?」
縁は言った。
「あいつはこんな罠にはひっかからねぇよ・・・・それにあいつはねえちゃんのこと、抜刀斎に取られて恨みに思ってやがるんだ。もう一度煮え湯を飲ませてやるのさ。」
「ふん・・・君の悪知恵もなかなか働くようだ。ところで君は、姉さんとは寝ないのかな?」
縁の顔が、黒星の言葉で憎悪に引きつった。
すさまじい速さで拳が見舞うのを、間一髪で黒星はよけて拳銃を縁の頭につきつけた。
「私の早撃ちを、甘く見ないでくれたまえ。縁。」
「いつかてめぇら、ぶっ殺してやる・・・・・。」
「恩人に向かってそれはないね。君が殺す前に、君が組織に殺されているよ。縁。王大人(ワン・ターレン)も、君のことは大事に思っているから、君の姉さんを"作って"くれたんだよ。」
「あんな・・・・病気を持った・・・・姉さんなんか・・・・・。」
「そうだ。姉さんじゃないね。あれは君の姉さんなんかじゃないんだ。はははははは。はははははは。」
黒星はそう縁をいたぶるように言うと、部屋を後にした。
「ねえさん・・・・ねえさん・・・・・楽しいのかい、男に抱かれて楽しいのかい・・・・。」
縁は煩悶しながら、部屋の中でうめいた。
「でも、俺はやってやる。あいつら全員、女の前でぶっ殺してやるからな。待っててくれ、姉さん。」
縁は完全に座った目でそうつぶやいた。
別室の剣心の情事はまだ続いていた。
蒼紫が彦馬に会ってから数日後のことだ。
蒼紫は今、荒川沿いの問題の私娼窟の近くに張り込んでいた。
無駄でも何でも、やらなければならない任務だ。
と、その時である。
―――抜刀斎が現れるとは。
蒼紫は一瞬わが目を見張った。
剣心がふらふらとした足取りで歩いていき、一軒の家の中に吸い込まれるのを目撃したのだ。
―――面白いものが見られるかもわかりませんよ。
彦馬の言葉はこの事だったのか、と蒼紫は思った。
―――緋村。貴様、まさか・・・・・。
剣心はやがて家から出てきた。
着物が着崩れている。
―――女か。
見た瞬間、蒼紫の中で、何かが壊れた。
やはり神谷薫では飽き足らないのか。
蒼紫はゆっくりと剣の鯉口に手をかけた。
今なら簡単に斬れるかも知れぬ。
だが、蒼紫の中でもう一人の自分が争っていた。
巴は、そんな勝利は喜ばない・・・・・・奴が逆刃刀を返して、真剣で戦った状態で勝利することこそ、その剣に斬られた巴に捧げられるべきものだと。
何故なら巴は―――。
ああ、巴。
―――ほかの植物は使いましたね。麻薬なんて、弱い人間が使うものです。
彦馬の言葉が、蒼紫の胸を今深く刺した。
あれは忍びの里にいた頃だった・・・・・。
「まあ、綺麗な花。」
藤棚に一杯に広がってぶらさがった白い花を、巴は目を見張って眺めている。
「あなたさまが咲かせましたの?私・・・・・あなたさまが花を育てるなんて、思いも寄りませんでした。」
二人はまだ師弟になったばかりであり、巴は清里の仇を討つことを、半ば同意したような形だった。
もちろん二人の間にはまだ何もなかった。
そればかりか、巴は縁のところへ返してほしいと懇願していたのであった。
その日も巴は蒼紫にこう言った。
「そろそろ返してくださいませんか・・・・あの・・・・私にはできないと思います。死ぬのは怖いですし・・・・・。」
「あなたには、その才がある。あるから、こうして、目をかけている。」
「冗談ではありません・・・・・あの・・・いつになったら・・・・・。」
巴は消え入るような声で、おどおどと言い募った。
「こちらへ。」
蒼紫は数寄屋造りの小さな茶室に巴を通した。
先代御頭と蒼紫がよく密談をした場所であったが、今は先代はその場にはいなかった。
蒼紫は巴の前で、点前をたてている。
巴はおとなしくその前に座って、蒼紫の袱紗さばきなどの作法を見ている。
やがて茶せんを返して蒼紫は茶器を巴に差し出した。
何の変哲もない、緑色の液体が泡だてて中に満たされている。
「・・・・・いただきます・・・・・。」
巴は静かに一礼をすると、茶器を回して液体を飲んだ。
白い喉が動くのを、蒼紫は食い入るようにじっと見つめた。
「ですから、私・・・・・清里のことは、もうあきらめてもよいのです・・・・・・長州など、私の手に負えるものではありません・・・・。」
「清里を愛していたわけではないのか。」
「私は・・・・私は・・・・清里を・・・・・・。」
言いかけた巴の唇がこまかく震えるのを、蒼紫は美しいと思った。
しかし、その目を蒼紫はすぐにはずした。
触れてはならない、水面に浮かぶ桜の花びら。
風にゆれて、手の届かない水底に今にも沈んでしまう。
巴は触れてはならない花であると思うのは、しかしその頃の蒼紫には耐え難いことであった。
―――だが俺は、巴を汚した。
蒼紫は今はそう思う。
だから、その巴に捧げられるものは、最高の美でなければならない。
抜刀斎が全力で元の姿に戻ったところで、その首を小太刀ではねる。
それは復讐であり、同時に失った過去の記憶の浄化であった。
抜刀斎は神谷道場に向かっている。
薫のところへ帰るつもりだ。
尾行したところで、何が出てくるものでもない―――ただ、薫が出迎えるのを、確認したいとその時蒼紫は思った。
剣心は、夕暮れの神谷道場の門の前で、半ば呆然と立っている。
「あ・・・・ああああ・・・・ああ・・・・・。」
剣心が門を見て、何かうめいている。
そうしてから、剣心はあわてて道場の中へ走り入った。
蒼紫は剣心がいなくなるのを見計らって、陰から躍り出て門の前に立った。
門の前に何か紙が一枚貼ってある。
「人誅――――。」
白い半紙に、墨蹟も鮮やかに、大書されていた。
蒼紫はその時はっとした。
中で剣心が薫を呼ぶ声がした。
弥彦が出てきて、何か剣心に言っているようだ。
弥彦は無事だが、薫はいないらしい―――と考えた時、蒼紫の頭の中である事が組み合わさった。
あわてて踵を返して、蒼紫は操の住む山手に向かった。
「―――操!」
蒼紫は勢いよく引き戸をひきあけた。
家はもぬけの空だった。
戸口に、争った形跡がある。
蒼紫は家の中に入った。
奥の間から血のにおいが流れてくる。
蒼紫は襖を開けた。
使用人の老婆が、畳の上にできた血だまりの上で、こときれて倒れていた。
胸から腹にかけて、一閃した刀傷がある。
その寄りかかった白い襖の上に、老婆の血で血文字が襖いっぱいに大書されていた。
蒼紫の目がほそまった。
その文字は、「人誅」であった。
人誅
漆黒の闇の中に、女が一人座っていた。
周りには豪奢な中国風の調度品がしつらえている。
その豪勢な部屋のある屋敷は、東京湾を望む高台にあった。
闇が揺れて、背の高い中国服の男たちが女のそばに立った。
「薬の量は?」
男の一人が、女の瞳孔の開きを調べている。
灰色にしわがれた、せむしの男が中国服の男に答えた。
「はい。間歇的に与えているので、禁断症状は出ないかと思います。梅毒の進行を麻痺させるにはよろしいかと。」
「大麻が効くとは、毒をもって毒を制するということか。」
「しかし脳にはもう毒は達しています。痴呆症状が出始めておりますな。」
「あと少し役に立ってもらうだけでいいのだ。もともと大陸では、奴隷だった女だ。しかしここまで整形外科が成功するとは、日本の外法忍法の技も、おそるべきものだな。土蜘蛛とやら。」
「恐れ入ります。」
中国服の男が含み笑いをした。
黒髪を後ろに髪油でぴったりと撫で付けている。
端正な表情の男だが、時折見せる表情は驚くほど酷薄であった。
灰色の男は、面倒そうに言った。
「王大人、雪代縁が梨花に会いたがっています。」
「後で通してやれ。」
男たちは、部屋を後にした。
梨花は鼻歌のようなものを、低い声で歌ってベッドに座っている。
その容貌は驚くほどあの巴に似ていた――が、崩れたような印象がやはりある。
と、ドアがすこしずつ開いて、そこに長身の男が立った。
雪代縁だ。
梨花は縁に気づかないで、しばらく歌っていた。
と、梨花の顔が何かの思い出を思い出したように一瞬ゆがんだ。
記憶の混乱であった。
梨花は片手を突き出して、叫んだ。
「旦那さま・・・梨花をお許しください。なんでもしますから・・・・・!」
梨花はベッドから滑り落ちて、床の上にうずくまって、肩を震わせていた。
「罰を・・・・・罰を・・・・罰を・・・・・鞭打ちは・・・・お許しを・・・・・。」
「ねえさん・・・・・・・・・・・・・・!」
暗がりから、雪代縁は飛びだした。
梨花の体をかばうようにして、縁は抱きしめた。
「ねえさん、泣かないで・・・・あんなヤツに抱かれて、ひどい病気に犯されて・・・・・。」
「あ・・・・あ・・・・ああ・・・・・。」
梨花は縁の腕の下でうち震えていたが、縁がおそるおそる指先で顔をあげさせると、やや安心したように微笑んだ。
気のぬけたような、表情だった。
その馬鹿のようなふぬけた笑顔に、縁は一瞬胸をつかれたが、ささやいて言った。
「ねえさん・・・・歌ってくれ・・・・。」
「歌・・・・。」
「そう・・・・・歌だよ・・・・・そのまま、歌ってくれ・・・・・。」
縁の頬に一筋の涙がこぼれた。
この梨花が偽者なのは、縁にはよくわかっている。
しかしそれでも、かりそめの姉弟である「ごっこ」をやめることはできないのだった。
――もう用済みだな。
いつかそう王大人が宣言し、この梨花がもし斬られたら、縁は自分の育て親である、王大人を殺すつもりでいた。
その前に緋村抜刀斎は倒すつもりだが、その後の梨花の運命を考えると、縁は沈うつにならざるを得ない。
梨花が生き延びる可能性の確率は、わずかなものでしかなかった。
今も、高い麻薬や治療薬を使って、「延命」させているのだ。
王大人が縁の復讐に気まぐれのような興味を示し、姉そっくりの間者を用意するまでは、縁も王大人を信用していたが、その見返りに王が自分に終生の隷属を要求するであろうことは目に見えていた。
大陸に流れ着いたとき、九龍島のスラムで放浪していた縁を、拾い上げて育て、技を伝授したのは、ほかならぬ王大人であったのだ。
――君が緋村抜刀斎と四乃森蒼紫という男に復讐をしたいというのはわかった。だが、ただ倒すのは芸がない。私は君に、「姉さん」を作ってあげようと思う。その「姉さん」の目の前で、君は二人の男を血祭りにあげたまえ。
その時は、王大人の言葉を鵜呑みにして、喜んだ縁だったが、巴そっくりの梨花を使っての復讐が始まったとき、縁の心に去来したのは、途方もない虚無感であった。
――それでも、ヤツらには「人誅」を見舞うのだ。それが、死んだ姉さんの仇をとるということなんだ。
縁はそう思って自分を鼓舞しようとしている。
従って、蒼紫のところでは、老婆を切り殺して血文字まで書いてみせたのだ。
それを見た蒼紫が自分のことをどう思うか―――縁はじっとそれを今は考える。
幼いときは、何の疑問も持たずに、蒼紫をただ「姉を手伝ってくれる親切な兄さん」ぐらいにしか考えていなかった。
姉の身を預かってくれて、清里の仇を討つのを協力してくれる、親切な兄さん。
しかし。
――姉さんは、戦いをする人ではなかった。それを、見所があるとか言って、たらしこんだのがあの男なのだ・・・。
縁は今は、姉を斬殺した緋村抜刀斎に相当するぐらいの恨みを、蒼紫には感じている。
その上、姉が蒼紫のことを深く愛していたとなれば、それ以上の恨みと言ってもいいかも知れない。
――姉は、あいつの言うことをなんでも聞いていて、死んでもいいと剣心と戦ったのだ。なのにあいつはのうのうと生き延びてやがる。許せない。
その蒼紫までもが、東京で別の女と暮らし始めた。
縁の心は、それを知った時、復讐に燃え上がったのだ。
ちょうど王大人の「事業」の展開がうまく軌道に乗りそうなので、王も縁が東京で殺しをするのに協力的であった。
こうして賽は振られたのだった。
――まずは、水道橋の某所に誘い込んで、そこで弱らせるんだ。あいつらはきっと、仲間をつれてくるはずだからな・・・・。相楽左之助か。
縁は梨花のそばをつ、と離れると、重いびろうどのカーテンを開いて窓の外を見た。
ここは隅田川の河口堰付近で、箱崎あたりの王大人のアジトのひとつである。
昼間の白い日差しの中に、東京湾の平和なレンガ造りの倉庫の立ち並ぶ風景が広がっていた。
相楽左之助は白法被を羽織った肩で風を切るようにして、路地裏を歩いていた。
剣心の具合が、あの「人誅」の張り紙を見てからどうも良ろしくない。
今も臥せっていて、恵が玄斎先生のところから時々様子を見に来ていた。
恵は剣心の簡単な診察を終えると、左之助に向かって言った。
――剣さん、どうも様子が変ね。薫が連れ去られたショックでしょうけど、微熱がちっとも下がらないのよ。それに・・・・。
恵は左之助に注意深く言った。
――ともえがどうした、とか、ともえに会ったとか、言うの・・・・あなたは心あたりあるかしら?ともえよ、ともえ。
左之助は肩をすくめて答えた。
――知ってるわけねぇだろ。俺りゃ剣心のこと、なんでも知ってるわけじゃねぇんだ。ともえ、ってのは女の名前だな。剣心の昔の女とか・・・・。
左之助が椎の葉を口にくわえて横目で言うのを、恵はむっとしたようにさえぎった。
――ええそうね、きっと剣さんの昔の女の人なんでしょうよ。とにかく、薫がさらわれたんだし、変な置手紙もあったんでしょう。警察に届けたほうがいいわね。どうせ及び腰でしょうけど、女の子が一人さらわれたぐらいじゃ・・・・。
というわけで、左之助は警察に出向くために、今往来を歩いているわけなのだった。
と、その時警察署のレンガ造りの四角い建物から、左之助は見慣れた人物が出てくるのに出くわした。
コート姿の四乃森蒼紫だ。
――なんだ、蒼紫の野郎、警察に何の用事で・・・・。
「おい、待てよ、四乃森。」
左之助が大声で呼んだので、蒼紫は立ち止まった。
「あんた、サツに何の用事で出入りしているんだ?」
蒼紫は落ち着き払って答えた。
「神谷薫の捜索願いか、早く出したほうがいいな。」
「なん―――なんでそれを知ってやがる。」
「俺も調書を取られたんだ。これから帰るところだ。」
「調書。またなんでそんな。」
「操につけた使用人の老婆が賊に斬殺された。操もまだ行方不明なままだ。」
左之助の目が蒼紫の言葉に丸くなった。
「まさか・・・そいつは、『人誅』って野郎の仕業じゃ。」
「そのまさかだ。神谷道場では殺人が行われず、幸いだったな。それでは。」
軽く頭を下げて去ろうとする蒼紫の肩を、左之助は乱暴に引き戻した。
「おい、待てっつぅんだ。なんでそこで、ハイさようなら、できるんでぇ、てめぇはよぅ。てめぇのところもあの人誅野郎に押し入られたんだろう?ここはひとつ共闘作戦といこうじゃないか。あんたんところには、こんな置手紙はなかったのかい?それとも、聞くだけ野暮ってもんか、その態度じゃな。」
「・・・・・・・・。」
「『明後日、水道橋の袂にて待つ。ただ一人で来たれり。神谷薫を生きて返してほしくば、いざ尋常に勝負せよ。これは人誅である。天知る地知る、人誅の報いをその身でもって受け止めるべし。雪代縁』―――あんたんところには、似た文面の手紙は放り込まれなかったのかい?」
「その手紙なら、今朝届いた。」
「なら、俺の言うことがわかるだろう?あんたと剣心は、その雪代縁に何か恨みのようなものを、買っているようだな。」
「昔の話だ・・・・。」
蒼紫が言うのを、左之助は追いすがるように言った。
「俺にそいつを聞かせてもらえねぇかな?剣心の野郎は、今熱で頭もあがらねぇんだ。それでも、その水道橋とやらに行かねぇと、薫嬢ちゃんの命ががやばいときてる。俺ももちろん助っ人はさせてもらうが、事情が全くわからねぇからな。」
「貴様に話すことは何もない。俺と剣心と雪代縁だけの問題なのだ。」
「なんだと。」
「抜刀斎のところへ行く。様子を見たい。」
「おい、てめぇ、秘密主義かよっ、教えろよ、こら。」
先を歩く蒼紫の態度は、まさに木で鼻をくくるかのようだった。
左之助はしばらくその背中に悪態をついていたが、やがてあきらめた。
――こいつは、口を割りそうにない・・・・・ともえって女が関係しているのか。まさに三ツ巴だな。
と、そこで左之助は武田観柳のところで初めて見た時の蒼紫を思い出していた。
――こいつも、剣心のことは恨んでいやがった。口ぶりは、公武合体で慶喜公が帰順したから、自分ら御庭番衆は出番がなくなったということを悔いているようだったが―――果たして本当にそれだけか。しかし、剣心の野郎には恨みに思っていやがるヤツの数が、多いなあ。俺はちょいとゾッとするぜ。あの志々雄真実も、恨みに思っていた野郎の一人だったからな・・・・。そいつと手を組んでまで、剣心を追い詰めやがったんだ、こいつも。やっぱり得体が知れねぇ。
左之助は、さっき蒼紫に手を組もうと簡単に言ったことを、すこし後悔していた。
――観柳邸で剣心を狙っていた時にも、その巴とかいう女が関係していたのかも知れねぇ・・・。
と、左之助は今思っている。
と、蒼紫がふと漏らすように左之助に言った。
「貴様にはこれだけは言っておこう。雪代縁は、姉の巴を剣心に殺されたから、その仇を討つつもりなのだ。」
左之助はやっと蒼紫の返答が得られたので、食いつくように言った。
「姉の巴?やっぱり巴という女かよっ。」
「どうした。何かあったのか。」
「剣心の野郎が、巴に会ったとか、うわごとで言うんだ。その、巴って女に・・・・。」
蒼紫の目が一瞬鋭く光った。
しかし、蒼紫の声はつとめて平静であった。
「そうか。巴に会っていたのか・・・・・。」
左之助は蒼紫にぎょっとなった。
蒼紫の顔は凄愴とでも言うべき薄笑いを浮かべていた。
――今の顔はどういう意味なんでぇ・・・・・。
剣心は、神谷道場の奥の間で布団に横になっていた。
左之助は剣心の枕元に座ると、そっと声をかけた。
「おい、剣心。蒼紫んところもえれぇ具合らしい。操がさらわれやがったんだと。そんで、蒼紫も今来てるぜ。」
「蒼紫が・・・・・。」
剣心は手をついて起き上がった。
「みっともないところを見せてしまったな・・・・蒼紫。拙者、不覚を取った。薫殿を・・・・・・・・・・・。」
剣心は起き上がったが、今は熱も下がり、様子も穏やかである。
剣心が今は正気にあるのを見てとり、蒼紫も普通のことしか剣心には尋ねなかった。
「緋村。水道橋にまでその体で行けるか。」
剣心は蒼紫の言葉に、素直に微笑を返した。
「なんとか、行くつもりだ。そこで・・・・縁に・・・・会わねばなるまい・・・・。」
「そうだな。俺も操を奪われている。取戻さねばなるまい。」
「そうか、おぬしも・・・・縁は、しかし、拙者と一番戦いたいはずでござるよ・・・・多分・・・おそらく・・・・・。」
剣心はそこで、ごほごほと肩をゆすって咳き込んだ。
剣心は言った。
「最近・・・恵殿に気になることを見立てられた。拙者の殺さずの剣は、あともう数回しか討てぬというのでござる・・・・体が、飛天御剣流の酷使に耐えられなくなってきているのだそうだ・・・・そうなる前に、縁とは戦わなければならない。」
「勝つつもりか。」
「ああ。勝たずばなるまい。縁は、間違ったことをしている。それを正さねば・・・・・・。今を生きる人々の暮らしを守ってこそ、正しい剣の道だ。縁はそれを踏み外している。」
蒼紫は剣心の今漏らした言葉に、瞠目する思いでなかったと言えば、嘘になる。
――あと数回しか討てぬだと。
なんとふざけたことを、とは蒼紫は思わない。
己れにしてみても、技の絶頂期は既に過ぎているのかも知れないのだ。
剣というだけではない、体を使う人間のそれは運命のようなものであった。
緩慢にして長い老い先がその先にはあった。
そして。
今自分が剣心に向かって、およそどうでもいいことばかり話していることを、蒼紫は自分でも気づいていた。
本当に知りたいことは、こんなことではない。
しかし。
――俺は、この剣心に巴のことを話すのは嫌だ。
嫌というのは、生理的な嫌悪感であった。
左之助の話から総合すれば、街の娼婦に剣心は巴を見たという。
たとえそれがどんなに巴に似た女であったとしても、蒼紫にはそれが許せなかった。
――本物は、ひとつだけだ。
切るように斜めに垂れた蒼紫の黒髪の下で、落ち着きはらって見える眼の上に、今や別の残酷な景色が写っていた。
その本物、というのは、透徹した純粋なものである。
それは蒼紫があの茶室でかいま見た時の、巴の裸体について思うことであった。
あの時間は一瞬であり永遠であり、二度と同じ時が繰り返されることのない厳粛たる時間であった。
あの時間の持つ純粋さが、似たまがいものによって汚されるのだ。
それは、茶人が、真贋を茶器に問うようなものに似ている。
その茶器の価値がわからない人間には、気ちがいじみた思い入れにしか見えないものだ。
しかし、それが真実、蒼紫という男の本性であった。
――だから俺は、巴のことを剣心に話すすべを持ち合わせていないのだ。
それはこれから先も・・・・。
蒼紫はその日、剣心と左之助に、水道橋で待ち合わせる旨だけを決めて別れた。
帰宅したしもた家には、まだあの血文字の「人誅」の文字は残されていた。
その前に座って、蒼紫は思う。
――縁。俺たちの前から姿を消してから、おまえは何処へ行っていたのか・・・・しかし、その恨みを俺に向けたい気持ちはわかるぞ。
答えてやらねばなるまい、縁に―――。たった一人の姉を殺されたおまえに・・・・。
しかし、縁は剣心にその憎しみをぶつけるのだろうか。
蒼紫の心に、今、縁への思いが交錯した。
「う・・・・ここは・・・・・?」
御堂茜はようやく、気がついた。
暗闇の中に、天窓からの一条の光が差し込んでいて、光の中に湿っぽい埃が舞っているのが見えた。
小さな四角の窓には牢格子がはまっていた。
――牢獄。私は一体・・・・・。
茜はゆっくりと痛む身を起こした。
手には手縄をかけられていた。
そばには、気を失う前に、一緒にいた巻町操の姿があった。
操も手に手縄をかけられていた。
操の凛とした声が耳に響いた。
「気がついた?御堂さん、あんた巻き込まれたんだよ。ごめん。」
操は汚れた頬でぽつりと言った。
抵抗した時殴られたのか、頬が赤くはれ上がっていた。
茜は答えた。
「巻町さん・・・・どうして私たちは縛られているの?」
「悪いヤツらにつかまったんだよ。だから、私の事なんて、ほっといてくれればよかったのに・・・宿題のガリ版なんて、わざわざ届けに来るからさ。」
「巻町さん・・・・・。」
茜はぶっきらぼうな操の優しさを感じた。
茜は、そういう少女だった。
突き放した言葉の中にも、優しさを見つけることができるのだ。
茜は言った。
「巻町さん、私、やはりあなたの事が気になっていて・・・・・だってあなたはいつも一人だったでしょう・・・・・。」
と、その時、操は顔をこわばらせ、茜にどなった。
「シッ、静かに。誰か来たっ。」
その時、茜は自分の入れられている牢獄の鉄格子の前に、誰かが降りてきたのに気づいた。
その足音は何人かいるようだった。
操がその方に向かって、目を光らせてにらみつけている。
背の高い髪の白い男が、二人の前に立った。
「お初にお目にかかるな。巻町操。」
「あんたは?」
「雪代縁―――貴様は俺のことは、何も知らないだろう?」
「知らないわ。それが何?」
「何も知らない――何も聞いていない――ヤツは何も教えなかった。そういう男だ、四乃森蒼紫。」
と、その時だった、操の目の前に懐かしい顔が見えたのは。
「操ちゃん!」
縁の後ろに、両手を縄でくくられて縁に捕縛されている、薫の姿が見えた。
「薫さんまで・・・・あんたっ、一体どういうつもりよっ。」
操が大声で叫ぶのを、縁は懐から銃を取り出し、一発発射した。
轟音が牢内に響きわたった。
「貴様らには、俺は恨みはないから、殺すことはしない。喜べ。」
と言うと、縁は何かを操に向かって放り投げた。
巴の日記帖だった。
「読め。姉さんの日記だ。」
「日記・・・・・・日記?」
操ははっとした。
「薫さん、これ、薫さんが言っていた、剣心の昔の女の日記なんじゃ・・・・・。」
「そうだ。俺の名前は雪代縁、姉さんの名は雪代巴だ。いや、緋村巴というのが正しいかな?」
と言うと、縁は銃口を、薫の頬に押し付けた。
薫の顔が恐怖で引きつった。縁は言った。
「貴様の愛する、緋村抜刀斎に殺された・・・・・。」
薫は悲鳴のように細い声で叫んだ。
「操ちゃん・・・・この雪代縁はね、巴さんを殺されたから、剣心と蒼紫を、殺すつもりなのよ・・・・・!」
「なんですって?」
「でも・・・・・・蒼紫は関係ないでしょ、操ちゃんと、この人は帰してあげて・・・お願い・・・・。」
「薫さん・・・・・。」
「だって、その日記には何も蒼紫のことなんか書いてなかったわ・・・剣心の・・・・・抜刀斎のことは書いてあったけど・・・・・。」
縁の形相が、その薫の言葉に醜く引きつった。
「何故書いていないか・・・それは・・・・姉さんが、抜刀斎を殺すために暗殺者だったからだ!!!・・・・それを仕立てあげたのは、四乃森蒼紫だ!!!姉さんは、四乃森に利用されて、抜刀斎に殺されて死んだんだ。それへの、これは、復讐だッ!!!!」
血を吐くような縁の叫びだった。
その縁の顔に、見るも無残な血脈が走っていく。
両腕の筋肉の上にも、血の蛇のような模様が走った。
狂経脈―――縁が大陸で、会得した技と引換えに与えられた、肉体の変化であった。
薫はヒッ、と身を縮めた。
縁は恐ろしい声で言った。
「巻町操、貴様はこれからそれを読むといい・・・・・・それには、姉さんが剣心とどんなに仲良く暮らしていたかが書いてある・・・・しかし、姉さんは深く苦しんでいた。そうさせたのは、四乃森蒼紫だ。蒼紫は姉さんと関係があった。しかし、それには何も書いていない。貴様も四乃森蒼紫の正体を知って、苦しむがいい!!!」
操は気丈に声をあげた。
「嘘。蒼紫さまは、そんな、女衒みたいなマネはしないよ!」
「そうかな。貴様は御庭番衆のことを、何も知っちゃいない。その癖、御庭番衆の第一の者みたいなでかい顔をしている。貴様の前で、蒼紫をぶち殺してやるよ。」
縁はそう言うと、牢獄の扉を開けて、薫を足蹴にした。
「あうっ。」
薫は悲鳴をあげて倒れこんだ。
「仲良く、足手まとい同士で相談でもするんだな。」
縁はそう言うと、乱暴に牢の鍵を閉めて、去って行った。
「薫さん・・・・。」
操に薫は答えた。
「操ちゃん、そうだったのね・・・・蒼紫さんも・・・・。私、巴って人・・・・・・。」
「ヤツが言っていたのは、確かなの?何も書いていないって。」
「ええ・・・そうだと思うわ。私が読んだ限りでは、何も書いていなかったわ、蒼紫のことは・・・・。」
「待って。」
操はそう言うと、膝を折り曲げた。
手を足の裏にやると、足の下から、細い仕込み手裏剣を器用に引き出した。
忍びの服で、足に巻いている帯の下に、仕込んでいたのだ。
「薫さん、縄を切るわ。手をこっちにやって。」
「・・・・わかったわ。」
操は縛られたまま、まず薫の縄を切った。
それから茜の縄を切り、最後に薫に自分の縄を切らせた。
「この日記よね。」
操は日記を拾い上げて、しばらくぱらぱらとめくっていたが、不意に気がついたのか、本の綴じ代のところを注意深く眺めていた。
「やっぱり。」
と、操は言うと、手裏剣の先で、日記の綴じ紐を切った。
ばらり、と日記がほどけた。
「見て。途中からページが抜かれている。そして、二重になっているわ。」
「えっ・・・・・・。」
薫は目を見張った。
それを見抜く操にも、驚いたが、日記の仕掛けにも驚いた。
やはり、操は隠密なのだと思った。
日記は和綴じなので、一枚の紙を折っているのだが、その中に薄い和紙がさらに挟まっていて、それは一見ではわからないようになっていたのだ。
「驚くことはないわ。忍びの連絡係なら、これぐらい当然よね。というか・・・・すぐに見つかる隠し方よね。見つけてほしかったのかも知れない、その巴って人。」
「えっ、操ちゃん、どういう意味?」
「あのね、本当に隠すのなら、同じ本にして置かないものなの。それぐらい常識よ。」
と言うと、操は日記の束を床にたたきつけた。
薫は操の剣幕に恐れをなして言った。
「読まないの、操ちゃん?」
操は唇を引き結んで言った。
「読まない。どうせ剣心と暮らしていたことや、蒼紫様にいろいろ何か・・・・その・・・・あったことしか書いていないし。でも、もう生きていない人でしょ。そんな人のこと・・・・・・私が知ったとしても、どうしようもないじゃない。第一、剣心と結婚していたんでしょ。」
「え・・・そりゃそうだけど・・・・・。」
「読んで自分が嫌になるのが嫌なの。蒼紫様のこと、嫌に思う自分が嫌なの。私の蒼紫様に傷がつくのが嫌なの。私のこの思いを誰にも汚されたくないの。薫さん、何がおかしいのよ。」
「ううん・・・操ちゃんらしいと思って。そうね、その日記・・・・普通のことしか書いてなかったけどなあ・・・・・。」
「二重になった部分は見ていない癖に。どうせ、蒼紫様のことが熱々の調子で書いてあるのよ。愛してる、とかさ。もう、蒼紫様ったら、そういう過去のひとつやふたつぐらい、あったとは思っていたけど、私に何も言わないんだから。」
「ふふ・・・・・。」
「それより、ここから 早く逃げ出さないとね。薫さん、こっちに来て。」
操は、牢の入り口に張り付いている。
薫もそのそばに寄った。
御堂茜は二人から取り残されている。
茜は床に落ちた日記の束を拾い上げた。
――巻町さんってすごい。御庭番衆って何だろ?
茜はふと、その薄い和紙の中に、色の桃色になった紙を見つけた。
『あなたさまへ―――
追わないでください
たとえ私が死んでも、何もしないでください
あなたが死んでほしくないのです
あなたが傷ついてほしくないのです
何も傷つけずに、ただあなたを思っていたい
雪代巴』
二重になった和紙にその言葉は、かすれた細い文字で書かれていた。
ふと、茜は自分の普段抱いている、寂しさと同じものをその文字の中に見た。
――巴って人がこれを書いたの・・・・?なんだかさびしい人だったみたい・・・・・。
茜はそう思ったが、操が鋭く自分を呼んだので、あわてて二人のそばに駆け寄った。
操は胸元から苦無を取り出しながら、言った。
「いい?見回りが来た時が勝負だから。」
三人は、じっと闇の廊下を見詰めた。
その日の夕刻、縁に呼び出された水道橋へ、剣心、左之助、蒼紫は到着して賊が来るのを待っていた。
弥彦も同行したがったが、左之助が説得し、神谷道場で待つようにした。
橋の袂の瓦斯灯が、淡い銀色に灯りだした頃合いであった。
はるかな橋の向こうから、三々五々にやってくる人影があった。
「奴らか。」
左之助が身構えたが、すぐに拍子抜けした表情になった。
「よう。ヤツらはまだ来ないのかい。」
斎藤が、瀬田宗次郎と悠久山安慈をつれて、飄々とした態で歩いてきた。
沢下条張がいないのが、幸いだったかも知れない。
「てめぇ、なんでここがわかった。」
左之助が食ってかかるのを、斎藤は軽くいなした。
「蛇の道はへびだ。おまえさんたちが襲われた賊が、贋金をばらまいたり、阿片を密売している連中だろうという、俺の見解を確かめたくってね。」
「見解というほどのことでもあるまい。」
蒼紫だった。
「貴様らが邪魔をしに来る事はわかっていた。」
斎藤は蒼紫の言葉に、口の端で笑った。
「邪魔とはひどい言い草じゃないか。俺は、おまえたちの助太刀に来てやったんだぜ。」
瀬田宗次郎が剣を肩にのせて、明るく言った。
「そうですよ。緋村さんは、体がお悪いんじゃありませんか?斎藤さんが、それとなく・・・・助けてやれ、とか。」
ニコニコと宗次郎の笑みを浮かべた言葉を、蒼紫の冷たい口調がさえぎった。
「そこまで知っているのか。」
斎藤は答えた。
「悪いがおまえたちには、俺たちが張り付いていたのさ。何、見張りを立てていたわけじゃない。出入りの御用聞きとかを、洗ったのさ。最近どういう具合だ、とかな。しかし・・・・・。」
斎藤は黙っている剣心に向かって言った。
「抜刀斎。命は惜しんだほうがいい。貴様との勝負の決着もまだついていない。こんな雑魚に気を取られて、具合を悪くされては俺は困るんでな。」
剣心は刀に手をかけて斎藤に鷹揚に答えた。
「雑魚ではござらんよ、雪代縁は―――。」
蒼紫も斎藤から、別の方向に向き直って刀に手をかけていた。
「もう来たようだ。敵は、三人か。」
「それぐらいでござろう。蒼紫、縁には拙者が。」
左之助が二人の様子にあわてて、拳をふりかざした。
「なんだっ、来やがったのかっ、野郎、隠れてねぇで出てきやがれ!」
瞬間、左之助の足元に鋼鉄製の矢が飛んでグサリと地面に突き刺さった。
「ふふふ・・・・・うるさい男だね・・・・・。」
「なんだ、てめぇ?」
水道橋の袂に、上ったばかりの月に照らされた三人の人影がある。
うちの一人は、ひらひらと着物の飾りを暮れなずむ闇にひるがえしていた。
矢はその男の方角から飛んできたのだった。
「乙和さん、軽はずみですよ。」
真ん中のめがねをかけた背の高い男が、いさめるように言った。
と、男は腰からスラリと長い刀を引き抜いた。
雪代縁だ。
縁はゆっくりと剣心らに近づきながら、言った。
「抜刀斎。俺は貴様と蒼紫だけで来るように書いてよこしたはずだが、これはナンだ?何人そこにいる。約束反故もいいところだ。」
蒼紫が答えた。
「貴様も四人で来た。同じことだ。」
縁はふっ、と鼻先で笑った。
「まずは雑魚を片付けなければいけない・・・・・戌亥さん、乙和さん、たのみますよ。」
戌亥と呼ばれた男が、いきなりこちらへ走り出した。
―――鉄甲か。
左之助が思うひまもなかった。
左之助の顔面に、戌亥番神の鋼鉄製の手甲がぶちこんでいた。
「うぉっ。」
安慈があわてて、左之助に向かって走り寄った。
「おせぇっ。」
戌亥番神は安慈よりはひとまわり小さいので、身軽だ。
ようようと安慈の頭上を飛び越えると、後ろざまに安慈の頭を蹴り上げた。
安慈は前のめりに倒れた。
その間、宗次郎と斎藤は乙和瓢湖の暗器の矢の攻撃を受けていた。
縮地の足技を持つ、天剣の宗次郎―――しかし、その宗次郎でさえ、一歩も踏み込めないでいた。
斎藤などは、立ちすくむよりなかった。
牙突を繰り出そうにも、矢はものすごい速さで、立て続けにこちらへ飛んでくる。
乙和瓢湖は楽しそうに言った。
「あなたの技―――聞いていますよ。瀬田宗次郎。」
「なにっ。」
「確か、縮地とかいう、琉球の走法でしょう。でも、この私の暗器にはかないますまい。縮地は封じましたよ。」
乙和瓢湖はそう言うと、朱唇をひきあげて、肩から大きな獲物を取り出した。
蜘蛛の手のような、熊手だった。
斎藤の刀にその熊手がぶち当たった。
「貴様っ。」
「尻尾を巻いて逃げるんですね。そろそろ、最後の仕上げです。」
その間も、剣心、蒼紫と縁のにらみ合いは続いていた。
剣心は縁に言った。
「縁。貴様が殺したいのは、拙者でござろう。薫殿、操殿は関係がないはず。それに、女学生も一人、さらったと聞いている。何故そんな事をする。」
「何故・・・・それは貴様らが堕落し、腐敗したからだ。女と楽しそうに暮らせる身分だと思うな。」
「身近な人々の平和な暮らしを願うこと、それが何故堕落なのか。自分に今出来ること、それの最小限のことをしなければ、と拙者は思い、心がけてきたつもりだった。市井に生きることの大切さを、薫殿は拙者に教えてくれた。その薫殿を、縁、おまえは人質にとって、拙者に人の道を突きつける。まずは、己れが人の道にもとることをしている事を、知ったほうがよかろう。」
蒼紫は黙って剣心の言葉を聞いている。
剣心のこの説教を聞くのは、これで三度目だ。
一度目は武田観柳の館で、二度目は志々雄真実のアジトで・・・・・。
耳障りのよいその言葉は、蒼紫の耳にも心地よい。
しかし。
――そんな綺麗事では、この縁は動かん。
人の道にもとる、か。
蒼紫は縁がどう出るか見ている。
今の剣心の言葉で、縁はさらに猛ったはずだ。
『人誅』という果たし状に書かれた文字は、縁にとっては本気なのだ。
それを、真っ向から否定するような今の言葉―――縁は黙ってはいまい。
縁の技について、蒼紫は縁に倒された娼館の客について調べあげていた。
かなりの使い手であるのは確かだ。
あの縁が、大陸でそこまで成長したのだ―――。
縁は案の定、剣心に対して構えて言った。
「今の言葉、抜刀斎、きさまは己れの姿を見ずして言ったとだけ、言っておこう。」
構えた縁の顔が、歪むように笑った。
縁の第一撃が剣心を見舞った。
――速い!
剣心は間一髪でよけているが、縁の攻めの猛攻は、ものすごかった。
立て続けに剣が打ち込まれていった。
「姉さんを・・・・姉さんを・・・・返せっ!」
縁のうわずった声が、剣心に剣とともに叩きつけられた。
「姉さんを―――――――ッ!」
剣心は縁に押されている。
――助けに行くか。
蒼紫の心に、その時毒のように別の考えが生じた。
この剣心を、俺は見捨てたい。
操のことも、もはやどうでもいい・・・・・。
その時だった、蒼紫の体を縛るように無音の音が鳴ったのは。
――なんだっ?!
ほかの者は気づいていない。
蒼紫の耳にだけ、その耳障りな音は聞こえる。
その音が聞こえると、体の自由が奪われる。
蒼紫の耳は、忍者としての訓練を受けているので、普通の者よりも可聴範囲が広く聞こえる。
その「聞こえる範囲」を狙って、その「音は」飛び込んできた。
抜刀斎と言えども、そのような訓練は積んでいないので、剣心の動きには変わりはない。
蒼紫は戦慄した。
――俺だけを狙っている。忍びの者、土蜘蛛か。
蒼紫は苦悶しながら、苦無を二方向に投げた。
ひとつは、乙和瓢湖の暗器を操っている手首に当たった。
「乙和さんっ。」
縁が驚いた声をあげる。
それに気どられたのか、ふっ、音がやんだ。
縁も音には気づいていたようだった。縁は言った。
「ちっ、四乃森はあいつが・・・・・。」
と、その時、斎藤が乙和に太刀をあびせた。
「ギャーッ!」
乙和瓢湖は斎藤に斬られた肩を押さえた。
血が噴水のように流れていた。
もうひとつの苦無の行き先は、蒼紫だけが知っていたが、手ごたえはなかった。
――はずしたか。
と、その時はじめて、戌亥番神は仲間がやられたのを知った。
「ちっ、乙和の野郎。雪代の旦那、ここはひとまずひきあげたほうがよさそうだぜ。」
戌亥番神は、安慈を一撃で倒したものの、左之助の二重の極みには手こずっていたのだ。
「仕方がないですね。」
縁はあっさりそう言うと、橋の上からひらりと身をおどらせた。
ほかの二人もそれに続いた。
「あっ、貴様ら、待ちやがれっ。」
左之助があとを追おうとしたが、斎藤に止められた。
「さて、あとは瀬田宗次郎にしたがって行ってもらおうか。瀬田の頭には地図が入っている。奴らのアジトは、この橋の下の地下水道の先にあるんでな。」
「なんだと?」
「ここの地下水道は迷路のようになっている。俺はこの負傷した坊主と引き上げるさ。」
「てめぇ・・・・・・・。」
左之助が言うのを、剣心が押しとどめた。
「斎藤の言う通りにしよう。警察の手駒として扱われようと、今は薫殿、操殿の行方を捜すのが先決。」
「罠だぜ、それも見え見えの。」
「左之助・・・・おぬしも来ないほうがいいかも知れぬ。『人誅』の約束をたがえた事を、縁は怒っている。」
「しかし・・・・・。」
「すまぬ、左之助。」
剣心の蒼白になった顔を見て、左之助はしぶしぶ剣心にしたがった。
剣心と蒼紫、それに瀬田宗次郎は、たいまつを手に洞窟のようになっている、地下水道の中に入って行った。
剣心と蒼紫は、先導する宗次郎に従って、暗いレンガ製の地下水道を歩いて行った。
宗次郎は敵がいるというのに、何か楽しそうだ。
蒼紫に向かって声をかけてきた。
「四乃森さん、あなたとこういう処を歩くのは久し振りですね。」
「・・・・・・。」
「やだなあ、僕があなたにしてあげた志々雄さんの話、もう忘れちゃったんですか。」
蒼紫は歩きながら、宗次郎にしぶしぶ答えた。
「この世は弱肉強食が摂理だとか言ったな。」
剣心は聞き始めなので、眉をしかめた。
「弱肉強食・・・・?」
宗次郎が明るく笑って答えた。
「志々雄さんが僕に言った言葉ですよ。この世は強い者が勝ち、弱い者は滅びる、と。蒼紫さん、どうしてあなたは僕の言葉にあの時笑ったんですか。」
「俺は笑ったのか。」
「ええ、笑いました。僕が僕のひどかった生い立ちを話して、志々雄さんのことを話したら、黙って笑っていた・・・・あれはどういう意味だったんです?僕のことをバカにして笑ったんですか?」
「そんなつもりはない。」
「でも、あなたは無言で笑っていた。苦笑したと言ったほうがいいかな。あなたもひょっとして、僕のような目に会ったんじゃありませんか?四乃森さん。」
蒼紫が黙っていると、剣心が横合いから言った。
「はて、どんな目に会ったのだ、宗次郎殿は。」
宗次郎は不意に立ち止まった。
その瞳が手に持ったたいまつの照り返しで、揺れている。
宗次郎は、長い間胸にたまった想いを吐き出すかのように言った。
「・・・・・僕は奴隷のようにこきつかわれたので、そこの家の住人を、志々雄さんにもらった刀で斬り殺したのです。今でも、反省することはあるけれど・・・・・・あの時僕にはほかの選択の余地はなかった。そうしないと、僕は死んでいました。緋村さん、そういう窮鼠が猫を噛むような心境に、あなたはなったことがおありですか?」
「拙者は・・・・。」
宗次郎は剣心が言いよどむのを見て、少ししてから答えた。
「あなたには、ない。僕にはわかる。あなたは他人を裁くことに対して、躊躇や羞恥心といったものがないでしょう。だから、僕は言い負かされた。あなたは強者なのですよ、緋村さん。僕のような負け犬には、あなたの生き方は所詮わかりません。そうですね、四乃森さん?」
「緋村は他人に対して真っ正直なだけだ。」
「そうでしょうか。僕は、緋村さんは残酷だと思うけどな。」
「・・・・・。」
蒼紫は黙り込んだ。宗次郎は、どうも剣心に絡みたいらしいと気づいたのだった。
宗次郎は続けた。
「さっき雪代縁に対して、人の道にもとると緋村さんは言いましたね。でも・・・・縁さんのお姉さんは、緋村さんに殺されている。ずいぶんな言い様ですよね。」
「―――宗次郎殿!」
剣心は思わず叫んだ。
宗次郎は答えた。
「僕は少しは知っているのです。あの斎藤から最近入れ知恵をされたわけじゃありません。」
「まさか・・・。」
目を丸くする剣心に、宗次郎はクスリと笑って答えた。
「その、まさかです。志々雄真実さんを、あなたは少し見くびっていましたね。志々雄さんはあなたと雪代巴とのいきさつを全部知っていました。それであなたが、剣客として、桂小五郎に使い物にならなくなって、自分にお鉢が回ってきたのだと・・・・女にのぼせあがって、ダメになった使えねぇヤツだと、あなたの事を言っていました。」
「それで、志々雄は拙者に対して、あんな事を―――。」
「志々雄さんの野望は大きかったですから、緋村さんへの復讐は、その一歩にすぎなかったのでしょう。でも、緋村さんの事を射程距離内に入れていたのは確かです。俺は俺のやり方で、幕末に対して弔い合戦をするんだと、言っておられましたから、志々雄さんは。そんな志々雄さんを深く理解していたのは、やはり僕よりも由美姐さんだったようですが。志々雄さんが由美姐さんに出会ったのも、僕の知らない幕末の吉原でだったそうですから。」
「そうで・・・そうでござったか・・・・・。」
そこで瀬田宗次郎は、笑ってザッ、と剣心に向き直った。
「そこで安心しないでください。僕は志々雄さんに頼まれて、あなたの顛末を見届けに来たのです。」
「なに。」
「あなたが雪代縁をどううまく納めるか、それに僕は興味があります。亡くなった志々雄さんも、きっとそうでしょう。でないと、あなたに倒された志々雄さんが浮かばれません。僕のように、あの雪代縁をもとの鞘に収めてみてください。できれば、の話ですがね。」
「・・・・・・。」
「それにつき、僕は傍観者という立場に立たせてもらいます。敵が来たらやっつけはしますが、それ以上のことは僕には期待しないでください。緋村さん、あなたが倒れた場合も、僕は雪代縁に対しては、戦いは挑みませんから。僕は雪代縁には、何の恨みもないんです。薫さんと操さんたちを助けはしますがね。」
蒼紫は言った。
「瀬田、貴様の立場はよくわかった。これだけは聞いておく。それは斎藤からの差し金か?」
「まさか。斎藤一は、そんなところにまで僕に干渉しませんよ。僕は道案内を頼まれただけです。」
「貴様。どうして、アジトへの道筋を知っている。」
蒼紫の問い詰めを、宗次郎ははぐらかすように答えた。
「さあ・・・・どうしてでしょうね・・・・そうそう、志々雄さんは、大陸方面ともつながりがあったらしいですよ。斎藤さんには、僕は恩を売るつもりはないんだけど、やはり正義が勝つのは見ていてうれしいものですから。僕はただ、そこにいる緋村さんの罪と罰を見届けたいだけです。」
蒼紫は眉をひそめた。
この瀬田宗次郎という男、とんだ食わせ物だ――――しかし、どこまで巴とのいきさつを知っているのか。この俺のことまで、こいつは勘定に入れているのか、まるで検討がつかない―――。
だが、と蒼紫は考える。
やはり志々雄真実という男、ただの成り上がりの兵法者などではなかった。
ヤツは自分の部下を自在に操り、死後もあの世から抜刀斎の息の根をうかがっているのだ。
ひょっとすると、ヤツの背後にいたのは、長州藩だけではなかったのかも知れぬ。
志々雄真実と一端は切れたと思っていた瀬田宗次郎であったが、旅の空の下で思うことがあったのか、すっかり十本刀の頃の調子に戻っているようだった。
所詮、緋村の説教というのは、その場でしか効力がないのだ―――この俺がそうだったからな、と蒼紫は思った。
人間の本性というのは、そう簡単に矯めることなどできないものなのだ、と―――。
その時だった、前方から仕掛ける気配がしたのは―――。
「来ます。」
宗次郎はたいまつを下に落とすと、抜き払った。
「何人だ。」
「四人だな。」
蒼紫が剣心に答えると、剣心は抜刀術の構えをとった。
まだ剣心の技は落ちていない―――鋭い気合いとともに、剣心は前方の黒装束の男たちに向かって突き進んで行く。
だがさっき縁とともに、現れた男たちではない―――蒼紫は剣心の後ろからやはり抜刀して、斬りかかった。
男たちはしかし、全力で戦わず奥へと退いていく。
瞬間、蒼紫の脳裏に予感が走った。
男らは、剣心らを誘うように奥へ奥へととまた引き返していく。
「―――!」
蒼紫は瞬間、立ち止まった。
前方の暗がりの先に、鋼鉄製の巨大な丸い扉がある。
―――水門!
蒼紫が思う間もなく、男の一人が鉄製の扉の横のレバーを押した。
男は扉の横の鉄の階段を、逃れるように素早くかけあがって行く。
三人が見ている前で、鋼鉄製の扉が開いた。
奔流が三人を襲った。
蒼紫の頭の中で、斎藤が言っていた、贋金作りのことが思い浮かんだが、それは一瞬の出来事だった。
贋金の銅貨の精錬には大量の水が必要だ。
やつらは上水道からそれを引いていたのだ。
―――しかしただの、贋金を作るだけではない、こんなに大量の水を溜め込んでいるとは・・・・!
宗次郎が溺れそうになるのを、蒼紫は手を伸ばして水中で助けた。
「――おい!」
剣心もどうやら壁にしがみついている。
――俺たちを弱らせるためなら、どんな手でも使う気でいるらしいな、雪代縁は・・・・・。
蒼紫は濁流の渦から、咳こみながら壁に這い上がった。
相良左之助は、水道橋から引き返そうという時だった。
「な、なんだこの大量の水は?!」
剣心らが消えた、地下道から先ほどまでなかった濁流が押し寄せている。
「斎藤のばっきゃろう!おい、剣心があぶねぇじゃねぇか!」
左之助は斎藤に怒鳴ると、水路の下に下りようとした。
斎藤は左之助を止めた。
「よせ。歩いて助けに行けると思うのか。」
「てめぇ・・・・・・まさかこうなると知っていたわけじゃねぇだろうな!」
「やつらならなんとかするさ。先回りと行こうじゃないか。おい、行くぞ。」
「てめぇ・・・斎藤・・・・・きったねぇぞ!」
「俺は雪代縁などどうでもいい。大物の首のほうが大事だ。」
斎藤は憤る左之助に、冷ややかにこう言い切った。
虚像
「下の水路が開いたようだ・・・・。」
雪代縁は、遠い水の音を聞きながら、階段を急いでいた。
その様子には、先ほど剣心らと相対した際に見せていた余裕はない。
いや、先ほどは縁の敵に対する威嚇だったのかも知れない。
今や彼は先を急いでいた。
剣心や蒼紫との決着はつける。
それは最初から決めてあるが、どうしても気がかりな事がある。
「姉さん!」
雪代縁は、その一室の重い扉を勢いよく開いた。
中には、あの巴の替え玉の梨花が座っていた。
あの海岸べりの部屋からまた移されたらしい―――地下の一室に彼女は居た。
梨花は、縁のほうを見ないでつぶやいた。
「・・・・・私、あなたのお姉さん、違うね・・・・・。」
「何を言うんだ、姉さん!」
雪代縁は梨花の前にひざまずくと、真剣な顔で手を取った。
真っ白に変わった髪の下から、縁は真摯なまなざしで梨花を見つめて、ささやいた。
「一緒に逃げよう。あいつらを倒した後で・・・・・・姉さんは、俺についてきて。歩くんだよ、隠れる場所に一緒に行こう・・・・。」
「私、あなたのお姉さん、ないね。」
「姉さん、頼む!俺と一緒に逃げてくれ!!!」
梨花は顔をそむけてつぶやいた。
「・・・・あなたと一緒に行くと、お薬、もらえなくなる。」
縁の顔が梨花の言葉に、絶望感にゆがんだ。
「姉さん!!!!」
その時だった、縁の背後に王大人(ワン・ターレン)が立ったのは。
「縁君、君は一体何をやっているのかね?」
「王大人・・・・・。」
王はいつの間にか、乙和瓢湖と戌亥番神らの部下を大勢引き連れていた。
縁は取り巻いた者たちから、梨花をかばうようにして立った。
番神はあざ笑うように言った。
「雪代のダンナの泣き所のひとつだねぇ。アンタ、その女のことは、そろそろ思い切れよ。」
縁はものすごい声で、吼えるように叫んだ。
「うるさいッ!!!!」
王大人は、楽しそうに言った。
「君のお姉さんを思う気持ちは私にもわかるよ。しかし、その梨花は君のお姉さんではない・・・別人だ。」
「あんたらは、姉さんを、抜刀斎に抱かせて、そして殺すつもりなんだ!!!」
「私はそんなことはしないよ。梨花、これをやろう。」
王大人は梨花に向かって、何か黒いものを投げた。
「それで倒せるかな?」
「倒せます・・・・。」
梨花は武器―――鎖のついたヌンチャクを手にしていた。
縁の顔色が変わった。
縁は狂乱して叫んだ。
「貴様らは、姉さんを・・・・姉さんができるわけがないのを知っていながら・・・・・!」
王は諭すように答えた。
「縁君、梨花は大陸で君同様、殺人の訓練は受けているのだよ。ただ・・・・なにぶん、抜刀斎らに対するには心元ない。君が補佐してあけたまえ。いや、これは逆かな?その抜刀斎という男は、この梨花を斬ることもできずに抱いた。その梨花が武器を持って立ち向かってくるのだ。抜刀斎にも十分な隙ができよう。そこを縁君、君が復讐したまえ。私の考えた策は十分な策だろう?」
縁はすぐには答えずに、目をギラつかせて王大人を見上げた。
縁は言った。
「・・・・・・それから、姉さんは、どうなるんだ?」
王大人は、こともなげに一笑に付した。
「君のお姉さんかね?残念なことだが、いずれ近い将来に死ぬだろう。そのことは梨花にもよくわかっている。しかし、その働きが見事であれば、今少しの薬のご褒美がもらえる。そういうことだな、梨花?梨花にも怒りはあるのだよ。梨花、君の体を汚した男を、君自身の手で葬りたまえ。」
すると梨花は何という事か、縁のほうを見もせずに、この冷酷な王の言葉に嫣然と微笑んだではないか。
縁は何としたことだろう、その梨花の微笑に見とれた。
それは、彼が長い間欲してやまなかった、死んだ姉の優しい微笑みであった。
白痴のような微笑みなのに・・・・・・鏡に映った姉の笑った姿を見ているかのようだ。
縁は観念したように、つぶやいた。
「姉さん・・・・・・。」
縁の中で、歯噛みするような思いが駆け巡った。
姉さんは、またしても自分の思い通りにならない。
彼の心は煩悶し、今にも気が狂いそうであった。
その時王と縁のこのやりとりに、飽き飽きしたといった調子で乙和がつぶやいた。
「やれやれ。雪代さんは、お優しすぎますねぇ・・・・・その女に殺る気があるんだから、それでいいじゃないですか。」
番神が言った。
「乙和、肩の傷は大丈夫なのか?」
「おかげさまで。下法の医術の何とやらで・・・・。そろそろ敵が工場にまでたどりついた頃合いですね。」
「その前に、外印がやつらの血を絞り取るさ。」
「で、ぼろぼろになったところを、縁さんが撃つ。復讐というものは、これぐらい念入りでないといけません・・・・。」
乙和はそう言うと、クックッと朱の唇をひきあげて笑った。
彼は男なのだが、べったりと唇の上に紅をひいていた。
血の気のない白い顔の上で、赤い口が暗闇に笑っていた。
王大人は、部屋から出ながら縁に言った。
「外印はまず、君の四乃森蒼紫を始末するはずだ。縁君、準備をしたまえ。」
「ひどい目に合いましたね・・・・・。」
瀬田宗次郎は言った。
蒼紫たちは、やっとの思いで地下水道を出て、煉瓦作りの廃工場のようなところに来ていた。
途中、水を呑んだ宗次郎を介抱してやらなければならなかったし、剣心はというと、蒼白な顔で前をふらつきながら歩いている。
蒼紫は工場の中を見て回りながら言った。
「ブツは移動させてあるが、贋金を作っていたのはここだろう。」
「なんと・・・・敵のアジトは、このようなところに・・・。」
「贋金作りだけではなさそうだ。」
蒼紫の目が隅に置かれた、木箱の上に止まった。
――マーキングに軍使用の通し番号がふってある。
「蒼紫、どうしたでござる?」
「それは弾薬の箱だ。」
「どうしてわかるのでござる?」
「・・・・・・・。」
蒼紫は、まるでこういう事にうとい剣心に、自分とは違うとわかっていたが、いらだたずにはおれなかった。
蒼紫は言った。
「今度は火に気をつける事だな。」
蒼紫の言葉に、宗次郎は明るく答えた。
「水責めの次は、火ですか?ここは、何でもありなんですね。」
「貴様のほうが、よく知っているだろう。」
「やだなあ。僕はこんなところは何にも知りませんよ。僕は、地下水道の地図しか知りません。」
「なに。」
「それも流されて、無駄になりました。もう僕にたよらないでくださいね。」
「貴様。」
瀬田宗次郎がこういう男だという事は、志々雄のアジトでわかっていたが、そのあまりのいい加減さに蒼紫は呆れた。
「しっ、何か来るでござるよ。」
前を行く剣心が立ち止まった。
蒼紫は答えた。
「雪代縁ではないようだ。」
宗次郎が不思議そうに尋ねた。
「どうしてわかるんですか?」
「足音が違う。」
「聞き分けられるんですか。すごいなあ。」
「少し黙っていてくれないか。」
すでに剣心は腰を落として、抜刀術の構えを取っている。
蒼紫も剣に手をかけた。
しかしその瞬間。
「上かっ?!」
音がした。
身を縛るあの無音の音―――蒼紫は今度こそ、相手の顔を見定めた。
―――土蜘蛛が、笛を操っている。
と、剣心の体が呪縛にかかったように動かなくなった。
次の瞬間、剣心の体は宙空に吊り下げられた。
「―――緋村さんっ!!!!」
叫ぶ瀬田宗次郎の体もご同様だ。
蒼紫も腕や足にからみついて引き上げる、斬鋼線を感じた。
―――糸使い。間違いなく、土蜘蛛。
その時、虚空から声がした。
「ひさしうお目にかかる・・・・御庭番衆御頭どの・・・・。」
蒼紫は顔をあげて答えた。
「貴様、土蜘蛛・・・外印だな。」
「覚えておいでとは光栄のみぎり・・・私の躁糸術はいかがですかな。」
暗い虚空に、黒の紋付袴を羽織った髑髏の覆面の男が、すっ、と音もなく現れたかと思うと、胸に手をあて礼をした。
剣心と宗次郎は糸にまったく動きを封じられていて、言葉すら発せないようだ。
老人は言った。
「御頭様については、先代からの恩もございます。ですが、わかっていただきたい・・・・あなた様の取られた道は間違いだったと・・・・・この先にはあなた様には、悲しむべき事態が待ち構えてございます。その地獄を見る前に、この老人があなた様の首を糸ではねて差し上げようという次第・・・・。」
蒼紫の首を糸がぎりぎりと締め上げ始めていた。
蒼紫はきれぎれに答えた。
「俺が取った道が間違いだったと。」
「左様。御庭番衆は、解散すべきではなかった。あなた様ひとり、新政府の飼い犬になるというのは、まことに腑に落ちない顛末でございました。その恨みで、この私のように、闇の配下に下った者も数知れずおります・・・・それも元はと言えば、あなた様のせい。」
「よく言う。」
「闇の者は闇にしか生き方を求めえぬものでございます。それを奪ったのは、あなた様だ。」
「・・・・・外法に落ちた者は、外法の法によって闇に葬る・・・・それが御庭番衆の御頭の最後の務めだ。」
「やってみられれば、よろしかろう。」
言うが早いか、老人の腕がしなり、苦無が蒼紫に向かって飛んできた。
「私の笛の音を聞いてでは、逃れる法はない。」
外印は口に、小さな呼ぶ子笛をくわえていて、そこから超音波が発信されるのである。
音感に敏感な者は、ある音が鳴るとそれに気を取られて、他の動作が手につかなくなるという。
この外印の術も、それを利用したものだった。
しかし、蒼紫はこの苦無をはずすであろう―――外印は、蒼紫の動きを読んでいた。
その、はずしたところを剣ではねる―――蒼紫ほどの術者にも必ず隙ができるはず―――。
しかし。
蒼紫は苦無をよけなかった。
一刀は間一髪で頭の横に命中した。
激しい衝撃が蒼紫の頭に見舞ったが、その瞬間、蒼紫の鼓膜は外印の発する音波から自由になっていた。
わざと三半規管の機能をつぶしたのだ。
次の瞬間、蒼紫は自由な姿勢で地に足をついていた。
―――糸が!!!
外印の顔に、あせりが走った。
やはり糸は、この蒼紫には通じない。
御庭番衆御頭だった男に、斬鋼線が通じると思った自分が、やはり浅はかであった。
さっき糸にひっかかって見せたのは、自分と対話したかっただけのようだ。
外印は必死で剣をふるった。
蒼紫はことごとくその二本の剣を受けて、こちらに向かってくる。
「あきらめろ、外印。」
地の底から響く一声とともに、疾風のような回転剣舞六連が、外印の体を見舞った。
外印は苦鳴とともに、蒼紫に向かって呪詛を吐いた。
「あの女さえいなければ・・・・・・・御庭番衆は解体することもなかった・・・・・・!!!!」
外印の唇から、喉も切れよとばかりに怪音が発せられたが、効果はもはや何もなかった。
ドサリと地に崩れた外印の顔は、仮面をはがすと死に苦笑を浮かべていた。
「緋村、大丈夫か。」
蒼紫は剣心と宗次郎を糸から助け出した。
二人は今しがたの戦闘をほとんど覚えていないのだった。
「ああ・・・助かりました・・・・敵は去ったのですか?四乃森さん。」
「そのようだな。」
「よかった。先を急ぎましょう。今は僕の勘では三里半ぐらいですね。」
「約二千百メートルぐらいだな。今は万世橋の袂付近か。」
蒼紫は思った。
―――あの女さえいなければ・・・・・・・巴のことか。
外印が行った闇の外法について、蒼紫の考えは行き当たりつつあった。
その頃巻町操と神谷薫、御堂茜の三人は、地下坑道に出ていた。
見回りに来た見張りの男を、薫に気をとらせている隙に、操が飛び掛り、うまく倒すことができたのである。
なんとか地上に出なければ―――操は人差し指の指先をしめらせて、風の来る方角を読んでいる。
「空気は、こっちから流れてくるわ。」
「操ちゃん、さすがね。」
「薫さん、さすがはいいから。早く地上に出ないと、あいつらが。」
操の脳裏に狂った雪代縁の姿が思い浮かんだ。
姉さんの復讐とか言った―――それの巻き添えになるのなんて、ごめんだわ。
たとえ蒼紫様が関係があったとしても―――蒼紫様ならきっと、あいつを倒してくれるはず。
操は懸命にそう思った。
巴のことは、信じられないことである。
あの蒼紫様が、私の小さい頃に―――御庭番衆にいた頃に、巴という女と関係があったなんて。
そんなの嫌、でもだから私のことを見ないのかも知れない。
蒼紫様、そんなの嫌・・・・・・。
私を・・・・私を見て・・・・・!
本当は張り裂けそうな胸を抱えているのだが、操はそれを薫たちにはみじんも悟らせなかった。
操の前にそのとき、ぽっかりとした空隙がうまれた。
操ははっ、として駆け寄りあたりを見渡した。
―――井戸の底だわ!
枯れ井戸のくみ出し口の底に、自分たちはいるのだった。
煉瓦積みの壁の上の空に、ぽっかりと丸い月が出ているのが見えた。
操は空をにらんで言った。
「薫さん・・・ここをよじのぼるのよ。」
薫は首を振った。
「そんなの無理よ、操ちゃん。」
「やらないと、あいつらにまた捕まって、ひどい目に会うのよ!」
操はそう鋭く叫ぶと、腰紐につけた小さな袋から、鉤先のついた紐を取り出した。
注意深く鉤先を振り回すと、操はそれを上の壁のでっぱりの部分にひっかけた。
紐を引いて、はずれないのを確かめると、操は言った。
「さあ、薫さん。茜さんも。」
操はそう言うと、先に二人をのぼらせた。
二人とも着物姿で、短袴姿の操に比べると、動作は鈍く、のぼりにくそうだ。
「ああっ!」
茜がつい足をすべらせて、小さく悲鳴をあげた。
操はこんなことは慣れていたが、二人はそうではなかった。
それでも薫はやはり道場で鍛えているせいか、すぐにコツをつかんだようだ。
「そう・・・しっかり・・・・少しずつ上に上がるのよ・・・・・。」
操はしんがりで、二人の様子をサポートしている。
と、そのとき上の出口に人影が動くのが見えた。
――敵?!もうダメか?!
操が一瞬躊躇したとき、影がこちらに向かって叫ぶのがわかった。
「薫嬢ちゃんじゃねぇか!こいつはラッキーだぜ。斎藤よぉ。」
「―――左之助!」
操は思わず叫んだ。
左之助が来てくれたようだ、斎藤もいるらしい・・・・助かった。
操の胸に安堵感が広がったときだった。
チュィーン。
操の前に、銃撃の弾痕が走った。
「そこまでだよ、お嬢さん方。」
呉黒星が、数名の部下を連れて、操たちを穴の底から銃で狙っていた。
黒星は狙いを定めながら、動きを凍らせた三人に冷ややかに言い放った。
「そのまま降りてきたら、命は助けてやる。さっさと降りて来い。手間を取らせやがって。」
「操ちゃん・・・・・・・。」
青ざめた薫にかまわず、操は必死で紐をたぐった。
「貴様、降りて来ない気だな?!」
黒星はそう叫ぶと、銃で紐を早撃ちで撃ち抜いた。
紐がぶつ、と途中でちぎれた。
「ああっ!!!!」
三人は宙に投げ出され下に落ちた。
下は砂地で、怪我がないのが幸いであった。
左之助が上で叫んでいた。
「てめぇらっ!!!斎藤、この入り口がわかってたんなら、早くこっちから行けばよかったんだよ!!!!」
斎藤は左之助に鷹揚に答えた。
「俺は始末が終わるまでは、手出ししたくなかったんでね。」
「何の始末だ。」
「幕末から連綿と続く、因縁の始末さ。抜刀斎はそれを片付けてからでないと、俺とは戦えない。」
「けっ、そうかよ。」
「まあ俺も行くとするか。」
と、斎藤は言うなり、井戸にひらりと身を躍らせた。
左之助があっ、と思う間の出来事だった。
斎藤は井戸の底から言った。
「何をしている、早く来い。一世一代の捕り物が見られるんだ。幕末という、大捕り物がな。そこの坊主も、まだ傷が痛むんなら遠慮したほうがいいが。」
安慈のことを指しているらしかった。
左之助と安慈は顔を見合わせたが、斎藤に従うことにした。
他に道はないのだ。
すでに操たちは、呉黒星たちが担ぎ上げて、いずこかへ運び去った後だった。
「いい線まで行ったのにな。ご苦労、ご苦労。」
斎藤はそう操たちのことを言うと、ついて来い、と背後の左之助らに合図を送った。
蒼紫と剣心たちは、廃工場の坑道を急いでいた。
「なんだか、熱くなってきたようでござる。」
剣心が言った。
空気が重く、ねっとりと熱くなってきていた。
この廃工場の終点に何があるのか―――三人は、闇に目をこらした。
最初に映ったのは、やはり火だった。
赤い点が暗闇の中に見えた。
その火は近づくにつれ、その勢いを増していった。
「溶鉱炉だ―――。」
蒼紫はやがて言った。
剣心は眉をひそめた。
「何のための溶鉱炉でござろう。」
「知れたことだ。銃や贋金の鋳造だろう。」
「なんと―――!銃まで。」
「軍までこの密造を、容認しているとは思えんが――――。」
コート姿の蒼紫は立ち止まった。
巨大な鉄の炉の前に、数人の人影がある。
―――雪代縁―――。
赤い溶鉱炉の吐き出し口の前に、白い髪の男が立っていて、腰の大刀を引き抜いた。
そのさらに後ろの段上に、高い人影が見えた。
中国服の男と女。
王大人と―――。
蒼紫はわが目を疑った。
―――巴!!!
そこに、巴と瓜二つの少女が立っていた。
――そういうことか。
蒼紫はすべてを悟った。
溶鉱炉の炎に照らされて、贋巴のほの白い肌が赤々と燃えていた。
と、蒼紫の横の剣心がそのとき、様子がおかしくなった。
「巴!!!待っててくれたのかい?!!」
剣心がその巴を見てなぜか駆け出す。
「緋村さんっ?!それはマズイですよっ。」
あわてて瀬田宗次郎が抜刀した。
蒼紫はその場に呻くように立ち尽くした。
地面がずぶずぶと沈むような感触―――鉛が入ったように、心が重かった。
認めたくない、贋物―――しかし抜刀斎がまた会っていたのは、今の様子ではこの巴なのだ。
―――大きな悲劇がありましょう。
外印のさっきの言葉はこのことだったのか―――外印が闇の外法を施したのか。
外印を簡単に殺すのではなかった。
もっと大きな苦しみを味わわせてから、殺すべきだった。
二度も―――抜刀斎にはこの苦しみを味わわせられ―――今また俺は、あの巴を斬らねばならない。
俺が斬らねば―――斬らねば―――。
雪代縁が笑っていた。
縁は刀を突きつけて、宣言した。
「来い、抜刀斎。一撃で殺してやる。姉さんの目の前で。」
剣心が抜刀した。
剣をふりかざして、縁に襲い掛かって行く。
しかし、剣に勢いがない。
―――これでは、本格的な九頭龍閃は撃てまい。
蒼紫は見て、心に失望の念が湧き上がった。
病魔はすでに剣心の体を蝕み始めている。
剣心と縁は、ぎりぎりのところで剣で激しく渡り合った。
斬りあいの火花が激しく闇の中を踊った。
と、その時縁の体が地に深く沈みこみ、それから急に上に舞い上がった。
――虎伏絶刀勢!!!!!
縁はその技に絶対の自信を持っていた。
大陸で必ず、抜刀斎の飛天御剣流を破ることができると、言われて会得した技なのだ。
溶鉱炉の炎が、縁の技の風勢に火の粉をふりまいた。
その火の粉がさっと飛び散ったとき、蒼紫は目を見張った。
―――緋村!!!!
剣心は縁にうたれて、ゆっくりと地にのめり、倒れ伏した。
巨人が敢え無くついえたのだ。
それは、蒼紫が長年夢見ていた、結末であった。
――バカな。
蒼紫は目の前の事実を否定したかった。
しかし、抜刀斎は陽だまりの樹のように、すでに内部がぼろぼろに腐敗し、がらんどうになっていたのだ。
剣心が倒れ苦悶しながら、涙を流して何かつぶやいている。
「巴・・・・・巴・・・巴・・・・・拙者はもう誰も斬りたくない・・・・・・拙者はもうだ、れ、も、斬りたくはない・・・・・・・・。」
そのつぶやきの意味を知った時、蒼紫の心に憤怒が沸き起こった。
死んでいない事だけが、剣心の縁に対する地の利と言えるであろう。
すでに剣心は、偽者の巴に会っていた時点でとどめを刺されていたのである。
今まで蒼紫につき従って来たのは、半ば義務感からと言ってよい。
彼の心情の、「苦しんでいる人々を助けること」と、巴を斬った自責感とのパランスが崩れた時、抜刀斎としての剣心は成り立ちえなくなっていたのだ。
しかし―――。
―――こんな貴様を見るために、今まで貴様を容認してきたのではない、抜刀斎!!!!
蒼紫の血を吐く心の叫びはしかし、剣心には届かない。
瀬田宗次郎がかすれ声で言った。
「緋村さん・・・・・あなたが敗れるとは思いもよらなかった。僕は・・・・僕はでも、この時のためだけに・・・・・・・・・・・・・・・・・・。」
宗次郎は顔をそむけ、必死で涙をこらえていた。
蒼紫は蒼白な顔で、縁を無言で見返した。
「勝ったな。俺は、緋村抜刀斎に勝った。次は貴様だ、四乃森蒼紫。」
縁はそう言うと、かすかに笑い、後ろを少し振り返って言った。
「見ていてくれ、姉さん。必ずあいつにも勝つからね。」
後ろの贋巴も笑ったようだった。
蒼紫の顔に、その時不吉なる影がよぎった。
蒼紫は言った。
「確かに貴様は、緋村抜刀斎に勝った。しかし、その勝利は、貴様の姉に捧げられたものではない。」
「なに。」
「姉が死んでいることを、貴様は今一度その胸に刻み付けるべきだ。」
蒼紫はそう言うと、瀬田宗次郎の刀を取り上げた。
「貸せ。」
一声そう言うと、蒼紫はブーメランのように、その刀を闇に放り投げた。
小太刀による飛刀術―――それはまっすぐに、ある一点を目指して、ものすごい勢いで回転しながら飛来した。
蒼紫の怒りを代弁しているかのようなその動き――それは一瞬の出来事だった。
「ああっ。」
縁のそれまで笑っていた顔が、驚愕に引きつった。
蒼紫の投げた剣は、後ろに立つ、贋巴の首を無残にも一撃ではねていた。
空中に巴の首が、高く花火のように舞った。
その顔はまだ、自分が斬られたということを認識しておらずに笑っていた。
その手にはヌンチャクを持って、今にも加勢する勢いであったが、その姿勢のまま贋巴の姿は横に崩れた。
巴の首は、溶鉱炉の灼熱の鉄の火溜りの中にボシャ、と落ちた。
ジュン、と白い水蒸気が立ち上り、跡形もなかった。
それらは一瞬の出来事であり、その時事態を正確に把握していたのは、剣を投げた蒼紫のみであった。
―――これで・・・・・これでいいのだ・・・・さらば・・・・・。
巴と相当する少女の微笑みひとつ引き出すこともなく、たった今手にかけた。
これでいいのだ、と蒼紫の理性は言っていたが、心がどうしようもなく泣いているのが自分でもわかった。
「うわああああああああああっ!!!!!!ねぇちゃんを、ねぇちゃんを、殺すなぁーーーーーーッ!!!!!!!」
雪代縁は絶叫していた。
哀路
「しっ、前に出るな。」
呉黒星の叱咤にその顔をにらみつけると、操は工場の張り出しから身を乗り出した。
縛られて、背中には銃で脅されている。
薫と茜もご同様だ。
だが操は今必死だった。
たった今、惨劇が起こったのだ。
遠目でよくわからないが、蒼紫が女を一人倒したようだ―――。
―――あれは、巴さん、だったの?
操にはわからない。
「あの女はなに?」
呉黒星が面倒そうに操に答えた。
「ボスの作った替え玉さ。雪代巴のな。まあいずれ消される予定だったが、殺されちまったか。」
「・・・・・。」
――蒼紫様・・・・。
操は、蒼紫が泣かないのを知っていた。
あの人は、決して泣かない・・・・・だけど、うれしいはずなのに、私は蒼紫を思うと、とても居ても立ってもいられなくなるのは、何故?
蒼紫さまは、巴さんを愛していたから、偽者を殺したんだわ。
愛していたから・・・・・。
その心を思うと、私はつらい。
だけど、蒼紫さまはもっとつらいはず。私の気持ちなんて・・・・・・・。
その時操は思い知ったのだった。
巴と蒼紫の絆を―――。
私は巴さんには決して勝てない。
薫さんが勝てないと思っているのとは、比べ物にならないぐらい、きっと勝てない。
だって、蒼紫は、偽者の巴さんを殺したんだもの―――そんな愛、私は知らない。
私の愛は、ただ遠くから見ていて、あこがれていて・・・・・ずっと蒼紫さまのそばにいられたらいいな、と思っていて・・・・・そんな愛。
ちっぽけで、甘ったれていて、自己恋着みたいで・・・・・だけど、私も蒼紫さまを愛しているの。
ねぇ、やっぱり私には蒼紫さまは、つりあわないのかな・・・・・。
操の目から涙がこぼれた。
蒼紫が偽者でも巴を消したこと、それは喜ばしいことのはずなのに―――。
操の横の薫は取り乱して泣いていた。
「剣心・・・剣心・・・・・起き上がって・・・・・しっかりして・・・・。」
薫にとっては、剣心がたとえ巴に心を奪われてしまっていようが、剣心さえいればそれで良かったのだ。
操は、薫と自分との違いを思った。
薫さんのは、無償の愛ね―――それに比べて私の愛ってなんて薄汚れて惨めなんだろう。
今だって、私は蒼紫のこと、どこかで突き放して考えている―――どうせ蒼紫には愛されない、と考えている。
だって今まで愛されていなかったんだもの。これからもきっとそうよ。
蒼紫が私のこと、思ってくれることなんてないんだわ。
操は意固地になっていた。
彼女は知らなかった―――蒼紫が、遠い戦火の日、彼女を救うためにどんな気持ちで現れたのか―――。
確かに巴のように、操は蒼紫に愛されることはないかも知れない。
しかし、幼い操を思いやっていたのは、蒼紫にとっては本当だった。
おそらく蒼紫自身も操の存在を欲していたからこそ、一緒に東京につれて出てきたのである。
しかしそれは、操の心には理解できることではなかった。
ただ彼女は待っていた―――蒼紫が自分を助けに来るのを。
それだけが、今の操の望みであった。
蒼紫は、縁の体に狂経脈が浮き上がる様を眺めていた。
縁は贋巴の死を、本当の巴の死と同様にまで考えている。
―――偽者に踊らされていただけだ、貴様も、抜刀斎も。
蒼紫はそう思うが、縁には通じない。
彼は巴が今また蒼紫に殺されたとだけしか、思っていないのだった。
縁の刀があがった。
肩口から気合いをこめている。
一撃必勝の、「虎伏絶刀勢」で蒼紫をも倒すつもりだ。
―――あの技か。奴には回転剣舞は効かぬか。
その時、縁の後ろに立つ中国服の背の高い男―――王大人が言った。
「縁、君の姉さんを殺した男を葬りたまえ。君にはできるはずだ。」
王も大刀を握っていた。
蒼紫は二人が師弟関係にある、とすぐに見て取った。
―――縁を教えた男。
御庭番衆を抜け出した頃、縁はまだ幼かったし、連絡係以外のことは何もできない子供だった。
それを作り変えたのが、おそらく今縁の背後に立つ男なのだ。
―――縁以上の手だれと見た。縁をもし倒せたとしても、あの男を倒さねば意味がない。
蒼紫は小太刀を両腕に握った。
対峙している縁が、ザッとこちらに踏み込んできた。
抜刀斎は倒れたままだ。
―――早い!
縁はその体のしなやかさで、沈み込んでは突き上げる剣戟を仕掛けてきた。
連続技である。
激しく数回、立て続けに蒼紫と打ち合った。
剣と剣とが激しくぶつかりあい、火花が暗闇の空間に飛び散った。
―――縁。
「縁。あれは貴様の姉などではない。」
蒼紫は剣を交えながら言った。
縁の顔が大きくひきつった。
「だまれ・・・だまれ・・・・だまれ・・・。」
「巴は死んだんだ。もう何年も前にな。そこにいる抜刀斎に殺された。貴様はその男に勝った。もう終わったはずだ。」
「だまれ・・・・っ!!!」
縁は刀をはじくと、蒼白な顔で叫んだ。
「貴様が姉さんを引き込んだんだ!!!姉さんは、貴様なんかに使い捨てにされて・・・・っ!!!」
涙が縁のほおを零れ落ちた。
「なのに今またあんたは、俺の姉さんを殺した。殺したんだ。あの優しかった姉さんを・・・・・。」
蒼紫の目に冷酷な光が宿った。
―――俺の姉さんだと。世迷言だ。
「悪いが貴様の世迷言に付き合うつもりはないのでな。」
蒼紫の冷たい言葉に、縁は叫んだ。
「でかい口をたたくな!貴様なんか抜刀斎にも勝てなかったんだ。その抜刀斎に勝てた俺に、貴様が勝てると思うなっ!!!」
「やってみる事だな。その抜刀斎は、貴様らがその女を使って、ぼろぼろにした抜刀斎だ。もはや俺に勝ったときの抜刀斎ではない。」
蒼紫の凛とした怒りに満ちた声が、暗闇に響いた。
瀬田宗次郎がその時、蒼紫がさっき投げた刀を静かに床から拾い上げた。
宗次郎は静かに諭すように言った。
「蒼紫さんの言うとおりだと僕も思います・・・。あなたのお姉さんは、あの今死んだ人ではない。それは冷厳な事実ですよ。どんなに生前のお姉さんに似ていてもね。雪代縁さん。」
縁はだだをこねるように、叫んだ。
「だまれっ。」
「どうしてあなたはそれを認められないんですか?あなたはその後ろにいる人に、態よく利用されているに過ぎないと見ました。違うでしょうか?」
縁はぐっ、と喉に言葉を詰まらせた。
王大人に利用されていることは、既に縁にもわかっていた。
だからそれから贋巴と二人して、事が終われば逃げ出すつもりだったのだ。
だがそれも夢の藻屑と消え―――今贋巴の首をはねた蒼紫の冷酷さが、縁には受け入れられないのだ。
なぜ―――どうして、そっとしておいてやれなかった・・・・・あの生い先短い哀れな女を、姉さんと呼ぶことが何故いけなかったのか。
―――こいつら二人は、俺が苦しんでいる事を他人の顔で笑って、ああして冷酷な言葉を吐いているのだ。
縁の心に憤激が沸き起こった。
―――虎伏絶刀勢!!!
縁は低い体勢から、飛び上がった。
間近に蒼紫の体が迫る。剣をふりかざした瞬間、しかし剣に当たるものがあった。
―――苦無!!!何処から!!!
蒼紫の投げた苦無は、縁の剣に立て続けに二本、激しい勢いで突きあたった。
「ちぃっ!!!」
それでも縁は押し切ろうとしたが、剣先が軌道からすでに外れていた。
―――しまっ・・・。
縁はずれた体勢のまま、蒼紫に斬りかかった。
縁は蒼紫の剣が、自分の頬をかすめるのを感じた。
―――斬られる!!!!
と、恐怖に髪の毛が逆立った瞬間、縁の体には猛烈な打撃が数回見舞っていた。
「くぅうううっ・・・・っ。」
縁はその場にうめきながらよろめいて倒れた。
蒼紫は、縁が倒れたそばで、小太刀を構えた姿勢のまま動かないでいた。
縁は言った。
「今の技は・・・・。」
「今のは技というほどのものではない。陰陽撥止のくずし技だな。」
「なん・・・・だと・・・・。」
「貴様の技は、抜刀斎に対する際に見せてもらったが、滞空時間が長い。その間を苦無でくずした。あとは回転剣舞の基本形で崩せると思った。所詮居合い抜きの技は、抜刀時のそれまでという事だ。」
蒼紫の冷静すぎる言葉に、倒れていた剣心の体がぴくりと動いたが、蒼紫はそれには気づかないでいた。
縁は地に手をつき、倒れたままで、ただ激しい息遣いで敗北をかみしめていた。
―――嘘だ・・・・嘘だ・・・・嘘だ・・・・・!!!俺が姉ちゃんを追い詰めた男に、負けるなんて・・・・・!!!!
と、その時後で立っていた中国服の人影が動いた。
男は低い声で、蒼紫に向かって言った。それはすべらかな日本語だった。
「なかなかやる男であるようだな。君が四乃森蒼紫君かね。お初にお目にかかる。私は王大人だ。」
ゆらり、と立った長身の男は、長剣を手に握っていた。
王大人は蒼紫に言った。
「君は面白い男であるようだ。雪代巴は君の恋人だった女だろう。私はその巴と瓜二つの女を用意した。緋村抜刀斎は、その女に情けをかけたし、弟の雪代縁もその女にはずいぶんと優しかった。しかし君はその女を見たとたん、その首をはねた。君の雪代巴への愛情は嘘だったのかね?君は人間として、果たして本当に巴を愛していたのだろうか。」
「・・・・・どういう意味だ。」
「だから君が今首をはねた女も、たった今この瞬間まで、人間として生きていたという意味だよ。君たち御庭番衆は、そういったものを軽視するきらいがあるようだな。私に言わせれば、野蛮の極みだ。」
「・・・・・・・。」
「偽者だから殺した、それが君の言い分だろう。しかし命というものは、すべて等しいのではないのかね?私はそういう命として、巴という女をよみがえらせた。それは素晴らしいことだ。私は無から有を生み出したのだ。しかし君はそれを、無に帰してしまった。君は本当は、巴という女のことを、さほどは愛していなかったのではないかね。だってそうじゃないか。愛していたら、その命を絶つことはできないはずだ。」
「・・・・・貴様。」
「ほう怒ったのかね?しかしただつっ立っているだけの女の首をはねるのは、いくらなんでも冷酷すぎる。」
蒼紫は、楽しげに言葉を続ける王に向かって言った。
「なら俺にも言わせてもらう。その女にも、偽者の雪代巴としての人生ではない人生があったはずだ。貴様はその人生をその女から奪った。その女の命はあといくばくもなかった。俺はただそれを早めただけだ。」
「君にそんな権利があるのかね?人の命を自由にする権利が。いや、君は今までそうして生きてきたんだが――――。」
ここで王大人は剣を引き抜いた。王は蒼紫に剣先を突きつけて言った。
「君の人生訓がどういうものかは、私は知らない。しかし、君の行く先には、これからも屍が累々と横たわるだろう。君は物の見方が少し正常とはずれているようだ。唯物論、と言ったほうがいいかな。唯物論では人は救えんよ。」
「俺が正常とは違うだと。」
「そうだ。人間的な、血の通った考え方を、君はしていない。君が抜刀斎に勝てなかった理由はその辺にある。たとえ技の上で勝てたとしても、人間としては、君は抜刀斎には勝てないのだよ。」
「人間、か。そんなことは、誰が決めるものでもない。」
「そうかな。君の心は少しも苦しまないのかね。」
「貴様の心は苦しまないようだな。」
「そう・・・私は苦しまないよ。私は愛情においては、人間的に正しいことをしているからだよ。抜刀斎はまた雪代巴に会えた。雪代縁もそうだ。愛情を夢見ることは、人間にしかできないことだ。」
蒼紫の頭の中には、今や真空が生まれつつあった。
王大人が言っていることは、すべて詭弁にすぎないと思う。
しかし、それを突き崩す決定的な言葉が何処にも見つからない。
あんな女を俺の前に立たせるな、というのは幼い感情論だ。
だがこの相手の老獪さを、感情的に突っぱねることしかできない。
俺には―――所詮こんな生き方しかできないのか―――。
蒼紫は慙愧の思いで小太刀を構え、低くつぶやいた。
「貴様の首、貰い受ける。」
「それがありきたりな君の答えかね。」
その時、後ろに立つ瀬田宗次郎はひやりとした。
すさまじい冷気が二人の男の間から発せられている。
宗次郎は残っていた、二の太刀をあわてて引き抜いた。
蒼紫はまず、小太刀で王の腰に打ち込んだ。
そのまま引き込んで、回転剣舞につなげるつもりだった。
しかし受けてたった王の剣には余裕がある。
―――この男の太刀さばき、和式のものではない。
それはさっきの縁に対峙した時に、蒼紫も感じたものだが、くるくると舞を舞うようにして、体ごと回転しながら太刀を受けられては、回転剣舞を見舞う焦点が作れない。
―――九連宝塔を仕掛けるか。しかし。
長身の王には、その隙がなかなか見つからない。まして、王の体はその間にも移動しているのだ。
―――何か奴の動きを食い止める足場を作らないと。
その時、蒼紫は宗次郎が縁に呼びかける声を聞いた。
「縁さん、あなたの主人である男を、四乃森さんが今追い詰めています。加勢してあげてください。お願いします。」
そう叫びつつ、縮地でふりかぶって、宗次郎は王に斬り込もうとした。
しかしその一瞬。
「ホホホ、小僧、おまえの相手はこのあたしだよ。」
宗次郎の前に、操たちのいる張り出したバルコニーから、乙和瓢湖と戌亥番神がひょう、と飛び降りた。
「王のダンナにだけいい思いはさせねぇぜ。小僧、てめぇからぶっ殺してやるよ。」
番神の言葉に、宗次郎の顔に、さっ、と殺気が走った。
「僕を怒らせると怖いですよ。」
「けっ、ひよひよのひよっ子が、一人前に刀が使えるって言うのかよ。」
番神が鉄甲の拳をガシ、と打ち鳴らすと、宗次郎に打ち込んだ。宗次郎は刀で受けた。
宗次郎は番神と斬りあいながら、もう一度、縁に呼びかけた。
「縁さん、早く立ち上がってください。あなたのお姉さんを利用した男を撃つんです。それが正しい、仇討ちの仕方なんですよ。」
雪代縁は両腕を地についていた。
「姉さん・・・姉さん・・・・姉さん・・・・・。」
縁の心は、今さまよっていた。
姉さんを殺したのは・・・・・緋村抜刀斎だ・・・・・・その男には俺は勝てた。しかし四乃森蒼紫には、勝てなかった・・・・。
姉さん、せめて微笑んでくれ、俺に―――俺のために。俺は姉さんのためだけに、今まで生きてきたんだ。
姉さん・・・・・。
その時、縁の目の前に、あの懐かしい姉の幻影が微笑んで立っているのが見えた。
―――縁、縁。立ちなさい。おまえはよくやりました。でも、私はよみがえってはならなかったの・・・・。王大人のやったことは、悲しいことでした・・・・・。
「姉さん!待ってくれっ」
それは縁の心が見せた幻影だったのか―――縁は一声大きく叫ぶと、王に向かって猛然と走り出した。
縁の混乱した頭には、もはや短絡的な思考しかない。縁はものすごい形相で王に叫んでぶつかった。
「やっぱりおまえが姉さんを―――!!!!」
「なにっ?!」
王の顔に動揺が走った。
その瞬間、蒼紫の鬼神のような叫びが縁を貫いた。
「やれ――――っ!!!!」
縁はその声を聞いて、本能的に王の脚を一閃、なぎ払った。
王はしかし、あやうくよけたところを――――蒼紫は見逃さなかった。
―――九連宝塔!!!!
地を蹴って高く飛び上がった蒼紫が王の頭上から、九回の連続技をかけていた。
地に落ちるまでの瞬間、王の体に縦横無尽に赤い軸線が九回、火を噴くが如く走った。
王はその瞬間声もなかった。
二人の男が同時に己れの敵になるとは、王は夢にも思ってもいなかったのだ。
「バカ・・・・・な・・・・・。」
虚空をつかみ、体中から血潮を吹いた王の最後の言葉は、それだった。
「なんと・・・・・。」
乙和瓢湖と戌亥番神はその蒼紫の技を見て、いっせいに総毛だった。
自分たちは、とてもバカなことをしでかしたのではないか。
安全な上のバルコニーにいた方がよかったのだ。
宗次郎も、蒼紫の技のものすごさに目を見張っていたが、すぐに体勢を立て直して、瓢湖に斬りかかった。
「悪は、許しません。あなた達の志しは、あの志々雄さんにも劣ります。」
「なにを・・・・・うがぁっ。」
宗次郎は袈裟懸けに瓢湖の体を斬っていた。
「瓢湖!!!」
そうどなった番神の顔に、蒼紫の拳がめりこんだ。番神は頭をつぶされ、溶鉱炉の前に吹っ飛んだ。
「これでいい・・・・・これでもう・・・・貴様は自由だ・・・・雪代縁・・・・・。」
激しく肩で息をついて言う蒼紫を、縁は亡霊のような顔で見あげた。縁は言った。
「あんたに・・・・・あんたに・・・・姉さんの何がわかる・・・・・あんたは俺の姉さんを・・・・。」
「ああ。俺はおまえの姉を利用した。こう答えれば、おまえは満足か。」
その時だった。
先ほどまで静まりかえっていた、剣心の気配が変わったのは。
「やはりそうでござったか・・・・四乃森蒼紫・・・・・・貴様は最初からそのつもりで、拙者のことを観柳邸で・・・・・。」
剣心がふらり、と剣をついて立ちあがっていた。
蒼紫の目が、その姿を見てせばまった。
剣心は、先ほど取り乱していた時とは異なり、穏やかないつもの調子に戻っていた。
蒼紫はその様子をじっ、と観察している。
――緋村、貴様は・・・・。
剣心は言った。
「蒼紫、最初の出会いの時から拙者はそなたには、不審感を抱いていたのでござる。確かに大政奉還で、維新の志士たちに対して恨みや嫉妬を抱いている・・・それは道理だと思う。しかし、ならば拙者をだけ狙うという理由が見つからぬ。そのような理由であれば、たとえば大久保卿を暗殺した者たちと同じように、明治政府に対して天誅を下すことに賛同して動くはずだ。しかしおぬしはそうはしなかった。拙者のような影武者として生きた者をつけ狙う。そして、おぬしの職業は元御庭番衆御頭・・・・・・・。」
「・・・・・・・・・。」
「拙者はしかし、今日この日まで、そのことを認めるのが怖かった。おぬしが巴の愛人であり、おぬしが巴を変えた男であるということを認めることが怖かった。それは巴が拙者を愛していなかったことを、認めることになるからだ。―――拙者はできればあの、おぬしにとっては偽りかも知れぬが、あの巴と一緒に死にたかった。そう思っていた、それが拙者に残された唯一の道なのだと思った。しかし・・・・。」
剣心はそこで、まなじりをつりあげて叫んだ。
「おぬしが巴を追い詰めて、おぬしが巴に戦いをさせたのだ!!!今はっきりとわかった。この今おぬしが倒した男が申したとおりだ。おぬしは巴を使い捨ての駒にして、捨てた。この拙者に殺させた。拙者の手を汚させたのだ。拙者は縁には詫びるつもりで、縁の剣の前には、倒れることを由とした。しかし、貴様に対しては違う!!!蒼紫、貴様だけは許さん。貴様だけは・・・・・・!!!!」
「わざと―――縁に負けたと言うのか。」
蒼紫の低い声に、うつむいていた縁の体がびくり、とひきつった。蒼紫は続けた。
「勝ちを譲っただと。貴様がそういう男だったとはな。緋村抜刀斎。」
剣心の目は蒼紫の上に完全にすわっている。
「なんとでも言え。縁に対しては、拙者には詫びなければならぬ理由がはっきりとあるのだ。大切なたった一人の姉を奪ったという理由が。しかし、貴様に対しては、それはない!!!」
「俺が・・・・好き好んで巴をおまえの元に送り込んだと思っているのか、緋村。」
剣心が激しているのに対して、蒼紫は冷静だった。その言葉は沈鬱そうに響いた。
「真実を今から貴様に述べてやろう。その頃俺は御頭ではなかった。ただの忍者の青二才で、巴の身柄をどうすることもできなかったのだ。巴はできれば、長州方の貴様の妻なぞにはせず、忍びの里で夫婦として、二人静かに暮らしたかった。ふ・・・・・・・今こうして言葉にしてみると、なんとだいそれた夢だと思う。それが許されない世界、それが忍びだ。」
「なに・・・・。」
「そしてその後、俺は忍びの熾烈な内部抗争に勝って、御頭の座に上り詰めたというわけだ。貴様の言う時系列は間違っているから、今正してみた。だが、御頭になったところで、巴はいない。そして組織の強烈な腐敗。しかも時代の敗者の側の組織だ。俺は二束三文で売り飛ばすことにした。それが御庭番衆の、俺の行った解体だ。」
「・・・・・貴様が本当はどうであろうと、巴を死なせたのは・・・・・死なせたのは・・・・・。」
「死なせたのは、貴様ではなかったのか、緋村抜刀斎。それが俺が追い求めてきた、最強の華だ。」
蒼紫の言葉に、剣心は激して叫んだ。
「卑怯だぞ、蒼紫!!!己れの技が完成していないから、今まで真実を述べずにいたとは。貴様は最低だっ!!!」
蒼紫は剣心の叫びに、苦笑した。
「・・・・・・・・俺も貴様が、女と暮らしはじめなければ、己れの卑小さを省みずに、武田観柳のところで仕掛けることもなかっただろう。緋村、貴様にとって神谷薫という女は一体なんだ?俺は今それが聞きたい。」
「薫殿は今の拙者の大切な想い人でござる。今を生きている人間を救いたい―――その拙者の想いの行き着く先にいるのが、薫殿なのでござる。拙者は、今を、生きている。」
「なるほど。巴は貴様にとっては過去の女であり、神谷薫は現在の女であるというわけだ。それは、おのおの別個に存在しているのだな。貴様の頭の中では。だから、あの偽者の巴に会っていたのは、少し時間を過去にさか戻ってみただけというわけだ。なんと便利な頭だ。」
「拙者を愚弄する気か。」
「愚弄?確かに今俺は貴様を愚弄した。しかし時間というものは、切れ目なく一方向に流れているものなのだ。過去というものは、現在とは別個に存在するものではない。」
「わからぬ・・・・蒼紫、貴様が何を言いたいのか。」
「では簡単に言ってやろう。巴を斬った貴様には、神谷薫と暮らしながら、また巴のような女に手を出す資格がないということだ。まあ俺の感情論だがな、これは。」
「詭弁を弄するなっ。」
「俺の正論が、貴様には詭弁に聞こえるようだ。」
蒼紫の冷静すぎる言葉に、剣心の体は震えたようだった。剣心はそこで、誰に言うともなく、宙を見つめながらつぶやいた。
「確かに・・・・確かに・・・・拙者は巴と過去にさかのぼって会っていた・・・・・それは許されぬことかも知れぬ・・・・しかし拙者は死にたかった・・・・・・・・・・・・・。巴とともに・・・・・・・・・・・・・・・・。拙者に許されるのは、もはやそれぐらい・・・・・そう思った。あの少女の体が、梅毒に犯されているのを見た時から・・・・・・・・・・・・・・・・・。」
「えっ、梅毒?」
剣心の言葉に、宗次郎が驚いて叫んだ。
「緋村さん、それではあなたの体も―――!」
蒼紫は剣心の言葉に驚いていない。
剣心が寝床にふせっているのを見た瞬間から、彼はその病の徴候を見抜いていたのである。
だから、贋巴の体を蒼紫は無残に斬り捨てたのだ。彼にはそうするしか、忍びなかった。しかし、蒼紫はそのことを言わなかった。
あまりの憤怒にである。
剣心は宙空を見据えながら、言葉を続けている。
「しかし・・・・・蒼紫・・・・拙者は貴様だけは許せないのでござる・・・・・巴は拙者の妻だった・・・・・・・妻だったのだ・・・・妻・・・・・・・・・・・・・・でも元はといえば、清里の・・・・・・・・・・そう、おそらくは清里も、貴様のことは許さない・・・・・・・・・・。」
「なぜそう思うのかな?緋村。清里を殺したのも、貴様ではないのか。」
蒼紫の言葉に、びくり、と剣心の肩は大きく引きつった。おそらく限界だったのだろう。
「貴様だけは、殺すぅぅううーーーーーっ!!!」
剣心は一声そう叫ぶと、剣をふりかざして蒼紫に飛び掛った。
抜刀術をかけるまでもなかった。
剣心にとっては、全力をかければ倒せる相手であったのだ、かつて蒼紫は―――。
剣心のまなこは、憎しみで暗い光を帯びていた。
巴とのかけがえのない生活を奪った男、それが蒼紫なのだ。
対する蒼紫は冷静だった。
相手が飛天御剣流で仕掛けてこないとわかると、その太刀は受け太刀にまわった。
二度、三度の剣心の斬り込みを蒼紫は容易に受けた。
―――まだ全力を出し切っていない。しかし―――。
不意に剣心の攻撃がやんだ。
剣心は剣を下手に構えていた。
―――次は、来る。
蒼紫は剣を縦十字の形に構えていた。
―――おそらく、天翔龍閃。
以前に無残にも敗れた技である。
剣心の気合いが走った。
剣は、斜め下から飛来した。
蒼紫は呉鉤十字の形で受けた。
―――巴は、この剣の幼い形に斬られた。
蒼紫は剣心の太刀を受けた瞬間、その猛烈な打撃力に抗しながら、実感した。
剣心は相手に自分の必殺技が敗れたと、実感するまでもなかった。
剣心は巴に必死で呼びかけていた。
―――巴、君のために・・・・・・っ!
剣心の心は今さまよっている。
今、巴の待つ雪道を歩いている。その先には、巴が待っている。―――いや、待っていた。
―――巴、拙者と・・・・・・・っ!!!
巴は、すらりと背を伸ばして、白い背景の中に立っていた。
その表情はしかし、あの雪の日にそうであったように、硬い。
―――巴、なぜ笑ってくれない・・・・・巴っ!!!!
ただ、つくねんと、剣心の罪を責めるかのように、巴はただ、立ちつくす―――。
狂う―――狂ってしまう。このままでは。巴、君に会わないまでは―――。
その瞬間、剣心の双肩から血潮が吹いた。
剣心の目が驚愕して見開かれた。
破れた――――まさか、拙者が―――――。
「あの技は―――!?」
瀬田宗次郎は瞠目した。
さっき、敵の大将を破ったときの蒼紫の技とは違う。
似ているのだが―――剣戟の数が、増えているような気がする。
いや、そんなことよりもあの「天翔龍閃」を破りながら、さらに相手に決まったという今の技はいったい―――。
―――まるで曲芸だ。
楽天的な宗次郎は、蒼紫の技を見てそう思った。
剣心の「天翔龍閃」が決まって、その体が沈み込んだとき、蒼紫はさらに上昇して、上から連続打撃技を加えたのである。
宗次郎は驚愕した表情でつぶやいた。
「おそらくは―――十回、いや、それ以上です。蒼紫さん、あなたという人は―――。」
何者にもとらわれない立場の宗次郎は、ただ単におなじ剣客として蒼紫の技に感嘆し、その場で賞賛を贈りたくなったのであった。
それは自分がかつて敗れた技を、蒼紫が見事に破ったからであった。
蒼紫は激しく肩で息をつきながら、修羅場のひとつを乗り切って、着地した姿勢で固まっていた。
抜刀斎の技は破った。破れるとは思わなかった。
自分の「九連宝塔」の技では、抜刀斎には到底勝てぬと思っていた彼は、さらに剣戟を増やすことを考えていたのであった。
しかし着地までの間に、それだけの剣戟をふるうとなれば、当然体への負担も増す。
それが今、全身を襲っている消耗感なのであった。
この「九連宝塔」以上の技には、古文書には名がなかった。
ただ、到達できる者のみが、その技を成すであろうと―――蒼紫は今、それを為したのである。
しかし勝利の余韻に浸っている暇はなかった。
「おい。」
蒼紫は小太刀を構えると、血潮を吹いて地べたに寝そべっている、剣心の体に向き直った。
ゆっくりと小太刀を、剣心の首根に添えた。
「抜刀斎―――貴様には、ここで死んでもらう。」
小太刀をかまえた蒼紫の眉間には、苦しいものがある。
この男が幕末から連綿と今にいたるまで、自分を苦しめてきたこと―――その過去の歴史が走馬灯のように、蒼紫の胸中を駆け抜けた。
だがあの観柳邸で死んだ四人も、これで浮かばれるのだと。
悪霊にしている、とののしられたことも、今となっては遠い記憶だ。
あれからこの抜刀斎は、人間として最低の行いをした。
巴に似た売春婦を抱き、その業病を背負った。
それ以上抜刀斎を追い詰めたくはない、と思ったこともあったが、今抜刀斎が吐いたセリフで、その思いも消えうせた。
巴との大切な思い出を、これ以上抜刀斎に汚されたくはない。
「ごめん―――。」
蒼紫が静かに刀を滑らせようとしたその時だった。
「やめて――――っ!!!!」
蒼紫の頭上の鉄のバルコニーから、薫の絶叫がした。
「四乃森さん、やめて、剣心を殺さないでっっっっ、なんでもするから、お願い、見逃してあげてっ、だって、かわいそうじゃないっ。」
薫の半狂乱の叫びが、あたりにこだました。
「四乃森、その辺にしておいてやれ。」
薫の横に立つ人影が言った。斎藤だった。
斎藤と左之助たちは、蒼紫らが王大人と戦っている最中に、操や薫の身柄を助け出していたのだ。
斎藤の横には、牙突を受けて気絶している、呉黒星とその手下たちがのびていた。
蒼紫は下から厳しい目つきで、斎藤の顔を見上げた。
斎藤は言った。
「貴様が抜刀斎に女を横取りされていたとはな。何かそういう宿縁があるとは、にらんでいたよ。しかしそいつは、俺にとっても獲物だ。」
蒼紫は刀を構えたまま、哂ったようだった。蒼紫は言った。
「斎藤。貴様には、俺ほどの憎しみが抜刀斎にあるのか?」
「なに。」
「貴様にはない。せいぜい新撰組の露先払いの邪魔をしたぐらいにすぎん。貴様にとって抜刀斎は、しょせんその程度だということだ。」
「ほう。言ってくれるじゃないか。で、その首は落とすのか、落とさないのか、はっきりしたらどうだ?」
「貴様には関係ない。神谷薫―――ここへ降りて来い。」
「は、はいっ。」
薫は必死で鉄階段を駆け下りて、剣心のそばに走りよった。
「剣心、剣心、しっかりして・・・・っ、剣心・・・・・。」
薫は剣心にとりすがって泣いていたが、やがて意を決したのか、首を伸ばして座りなおした。
そして、まっすぐに蒼紫の顔を見上げながら、毅然とした口調で言った。
「殺して。剣心を殺すなら、私も殺して。殺して。」
蒼紫はその様子をしばらく無言でじっと眺めていたが、不意に小太刀を納刀した。
その時蒼紫の心を襲ったのは、やはり薫への憐憫の情であった。
剣心をこの場で殺すことによって、自分は確かに巴の仇を討ったことになるだろう―――しかし、新たに薫を修羅の道に陥れることになる。
巴の仇は―――飛天御剣流を今うち破ったことで、もはや由としてもいいのではないか。
剣心はどの先、病でその命は長くはないのだ。
それを自分は最後まで看取ることもあるまい―――蒼紫はそう考え、刀を納めたのである。
その動作は、なめらかな動きで、何のとまどいもなかった。
蒼紫は言った。
「貴様たちは殺さん。抜刀斎。その女に免じて、貴様を許してやる。二人仲良く死ぬまで暮らすがいい。」
そのまま蒼紫の青い影は、その場から足音を響かせて立ち去った。
操が取り付くしまもなかった。
いや、操はその時、蒼紫に駆け寄ることができなかったのだ。
―――わたしは、わたしは・・・・・・・。
操は固唾をのんで蒼紫が遠ざかるのを、見守るしかなかった。。
蒼紫の背は、何者も近づくことを固く拒んでいるように、操には見えた。
蒼紫は、私を愛していない。そして、愛してくれない―――――。
それが今はっきりと操にはわかったのだ。
蒼紫は巴だけを愛しているのだ―――さっきまでの蒼紫の行動、言葉、そのすべてがそれを示していた。
操は雷に打ちのめされた者のように、そのことをあらためて今思い知ったのだった。
その時、操のそばにいた、御堂茜は、ふところから大切に巴の日記を取り出した。
彼女は一歩一歩、ためらうように、雪代縁に近づいた。
縁はうずくまって、呆然としていた。
この結末が信じられないでいるのだった。
どうしてやつは、抜刀斎を許した――――あんなに憎んでいたはずなのに。技を破ったことで満足して立ち去ったのが、信じられない。
俺ならあいつの首をその場でかき切るだろう―――そのつもりだった。
蒼紫に勝った時点で、俺は抜刀斎と蒼紫の首を斬る予定だった。
あいつはそれをことごとく変えて立ち去って行った。
その縁のそばに、今御堂茜が立っていた。
「日記・・・・・あなたのお姉さんの・・・・・・。」
「?!」
「読んであげて・・・・・・中から紙が出てきたの・・・・・あなたのお姉さんが書いたのよ・・・・・・・。」
「貸せ!!!」
縁は乱暴に茜から日記を奪うと、中身を開いた。
前にはなかったうすい桃色の和紙がはさまっているのに、彼はすぐに気づいた。
縁はその文面に目を走らせた。
『―――あなたさまへ―――
追わないでください
たとえ私が死んでも、何もしないでください
あなたが死んでほしくないのです
あなたが傷ついてほしくないのです
何も傷つけずに、ただあなたを思っていたい―――雪代巴』
その文章が、縁に対して向けられたものではないことが、縁にはすぐにわかった。
蒼紫に向けて、巴が書いたものなのだ―――。
縁は虚空に向かって問いかけた。
ねえさん・・・・・・。
ともえ、ねえさん・・・・・。
ねえさんは、あいつのことを、本当に愛していたんだね・・・・・。
ねえさんたちは、夫婦とかのつながりはなくても、本当に愛し合っていたんだね・・・・・。
茜はその縁にそっと語りかけ、その肩に両手を添えた。
「あなたのお姉さんは、もう何年も前に死んでいるの・・・・だから、ね・・・・・・。」
茜のか細い声に、縁の両眼から涙がこぼれた。
わかっていた、わかっていたさ、そんなことは・・・・・。
ただ、俺はねえさんがあんまりにも哀れだったから・・・・・・・。
だけど俺のやったことは無駄じゃなかったよね・・・・・ねえさん・・・・・抜刀斎は、もう刀が持てない・・・・・。
あいつはそうなってもよかったんだ・・・・・・・ねえさん、これだけは許してくれるよね・・・・・。
縁はただただ、姉巴のことが悲しかった。
彼はいつの間にか、茜を姉巴と思って、その身を投げかけてすすり泣いていた。
高荷恵は、その午後、神谷道場から、蒼紫の指定した寺へ急いでいた。
戻ってきた剣心や薫たちの手当てをしてから、一週間になる。
上海から上陸した、悪の組織は一網打尽になったようだが、剣心たちがさんざんな目にあって―――しかもそれが、四乃森蒼紫もその一方を担いだとあっては、恵の気がすまない。
せかせかせとした足取りで、寺の山門をくぐり、中に入った。
中の方丈に問題の蒼紫は座っていた。
「また、座禅―――?」
恵は来るなり、切り口上でこう言った。
蒼紫はしかし、作法通りに座っていた。
「座禅を組むのにもいささか飽きたか。今日はお手前を披露しておこうと思う。今生の別れかも知れん。」
「まあ、どういう意味かしら。」
「実は、アメリカに渡ろうと思っている。―――というか、上からの命令で渡米しなければならん。」
「えっ?操ちゃんはどうなるの。」
「つれて行くつもりだ。本人の意思がいやならば、俺も無理強いはしないが―――。」
「あの子のことでしょ。地獄の底までついて行くでしょうよ。私はごめんだけどもね。」
「そうだな。」
恵は蒼紫のたてた茶を飲んだ。
茶の味は蒼紫がそうであるように、苦かった。
恵は言った。
「ねぇ―――ひとつ聞いていいかしら。あなたはどうして―――。」
恵は言いかけた言葉を言おうとして、だまりこんだ。
―――どうして、剣さんを殺さなかったの?
巴という女がいた、という事は、左之助たちの話からおぼろげに恵にもわかった。
そして、それが蒼紫の女だったということも・・・・・。
この人は、ひょっとして――――。
観柳邸で私を泳がせるようにしていたのは、私に巴さんという人の面影を、求めていたのかも知れない。
今、操ちゃんをそばに置いているのも、きっとそうだわ―――。
でも、私も操ちゃんも、その巴さんとは似ても似つかない、おそらくは・・・・・。
だからこの人は、自分に近づく女に対して残酷なのだ。
恵はその時のことを覚えている。
蒼紫が元御庭番衆という身の上である、と観柳邸で知ったとき、彼女は「武士じゃない、ですって?」と言って、蒼紫にもたれかかった姿勢をあわてて正したのだった。
そして袂を振って蒼紫から離れたとき、背中に冷たい視線が突き刺さるように感じたのを覚えている。
あれは、女への殺意だった。
恵は操が哀れだった。
あの刃の上を踏むような瞬間を、操はおそらく幾度も耐えているのだ。
しかし恵は言いかけた言葉を訂正するように、明るく戯れ言めいた口調で言い直した。
「―――ごめんなさい、操ちゃんとどうして離れないのかしらねぇ、って思って。あなた操ちゃんのこと、ほんとに好きなのかしらって。」
蒼紫はよどみなく、用意された答えを読むように答えた。
「操は、好きだ。自分の家族に対して思うようにな。」
恵は大きくため息をついて言った。
「そう。あの子はあなたに対してそう思ってないの、承知の上でそう言うのね。あなたらしいわ。ところで、私に渡したいものって、何かしら?」
「これだ。」
蒼紫は脇に置かれた小さな紙包みの袋を、恵の前に置いた。
「これは・・・・。」
「ご禁制の品ではないが、それに準ずるものだ。抜刀斎の病の進行をおさえる働きがある。」
愕然とした恵に、蒼紫は言った。
「抜刀斎を俺は殺せなかった。だから、そう始末をつける。」
恵はただ、吐き出すように言葉をついだ。
「あなたって人は・・・・・!」
恵は言いつのった。
「生きててほしいの、剣さんに。あなたは剣さんを追い詰めて、死地に追いやって、それでもまだ生きていてほしいのっ。」
「神谷薫がかわいそうだ。俺はあの娘が好きだった。人間としてな。抜刀斎の母のような娘だ。」
「そう―――そういうことなの、そういう・・・・。」
恵は紙包みを膝の上でつかみしめた。
動揺している恵の前で、正座している蒼紫の表情は動かなかった。
◆
御堂茜は牢獄につながれた、雪代縁に向けて、手紙を書いていた。
縁は王大人の組織に加担した罪で、投獄されたのである。
茜には、何年の刑になるのかは、わからない。
ただ、時々刑務所で会う縁を見るたびに、少しずつ何かが変わってきているのがわかる。
それが、学校の教会でシスターたちが言っている「神の教え」に感化されてきているのかは、茜にはわからない。
ただ、彼女はあの場で、縁が一番かわいそうだと思った。
この人は救いを求めている人だと、思った。
だから、一月に一度の接見の日には、必ず行くようにしているのだった。
雪の降る日、茜はまた縁を見舞った。
鉄格子ごしに会う縁の様子は、茜にはぶっきらぼうだが、どこかで茜を傷つけまいとしているのがわかった。
「縁さん、お元気?縁さんのお姉さんみたいにはできないと思うけど―――毛糸を編んできました。」
「・・・・・・・獄中だから、受け取れねぇな。」
「そう。でもいいの。牢から出たときに、私、縁さんにこれをかけてあげます。」
「・・・・・・・・・・・。」
「手紙、読んでくださいましたか。」
「・・・・・読んだ。ほかにすることがねぇから。」
「そう。よかった。」
「神の教えは俺にはわかんねぇ。神は善人しか救わねぇもんだろ。」
「そんなことはありません。縁さんは、救いを求めていらっしゃいます。そういう人には、神さまはやさしいですわ。」
「俺が救いを―――。」
「縁さんは、お姉さんの仇を取りたいがために、たくさんの人を傷つけました。その罪から救われたいと願っています。」
縁は茜の言葉に、宙に目をさまよわせた。縁は言った。
「俺はそんないい人間じゃねえ・・・・・あんたにはまだ話してなかったかな。俺が大陸に渡ったときのこと。」
「はい。」
縁は遠い目をして言った。
「俺は御庭番衆では下っぱの使い走りしかさせてもらえねぇ人間だったから・・・・・・大陸へ渡ったのさ。船に乗って・・・・・そう、あんたぐらいの歳だったかな・・・・・・食うものも寝るところもなくて、凍え死ぬところを、親切な向こうの商人に助けられた。」
「それが王大人だったのですね。」
「いや、違う。マトモな商売をしている旦那だった。俺はそこで中国語を教えてもらい、大事にされた。恩人だったんだ・・・・・・でもある日、そういうのがうざくなって・・・・。」
「まさか―――。」
「そう、殺したのさ。殺して金を奪って逃げた。その金で、王のところでやっかいになるようになった・・・・・俺はそういう最低の人間なのさ。どうだ?もう接見に来る気がなくなったろう。」
「いいえ。縁さんは、たくさん苦しんでらっしゃいます。過去の罪をよく話してくださりましたね。ありがとう。縁さん。」
茜はそこで立ち上がった。
「またお話しましょう。私が来ても、いやがらないで会ってくださいね。では。」
縁はまぶしいものでも見るように、茜の帰って行く姿をながめた。
最初は、なぜ自分のところに関係のないおまえが会いに来るんだ、と拒んでいた縁だったが、茜はまるで彼の実の姉・巴のように縁に会いに来てくれた。
その様子は、確実に冷え切った縁の心を溶かし始めていた。
何年か先、自分が牢屋から出たときのことを、縁は考えはじめるようになっていた。
その時には今度こそ「新しき仕事をするのです。そして、過去の罪を償うのです。」と、茜は言う。
それが何かは、まだ縁にはわからない。
ただ、姉につながる宿縁のつながりは、蒼紫によって断ち切られた今、自分に残っているものは何なのだろうと、縁は考えるのだった。
故郷もない、家族もない自分に、今たよれるのは茜しかいない―――。
あんな歳の離れた小娘に、と思う縁だったが、なぜ自分を慕ってくるのかわからず、とまどうばかりだった。
そうこうしているうちに、姉・巴のことは、縁にとっては、望遠鏡で覗いた風景のように遠ざかっていった。
「ねえさん――――。」
毎日牢の中で姉に問いかける言葉も、次第に縁にとっては、経文のように意味のない繰言になっていった。
◆
「結局、幕末からの決着は、ご自分ではくださないんですね。」
瀬田宗次郎がその日すまして言った言葉を、斎藤一は聞き流した。この男のいつもの手だ。
「あの時安慈さんの右ストレートと、斎藤さんの牙突と、どっちが決まるのが早かったんですか?あるいは左之助さんのストレートと。」
「俺だな。」
「やはり、そうですか。」
そういう質問なら、答えるんだな、と思う宗次郎だが、顔には張り付いた微笑みがひろがっていた。
宗次郎は言った。
「ところで、麻薬関係は、うまく収まったんでしょうか。」
「ああ。あれは乗鞍の所轄だからな。俺の指定した倉庫へ連中は行ったのさ。」
そこで、斎藤はマッチで火をすり、タバコに火をつけた。
二人のいる部屋はもちろん警視庁の一室である。
「で、麻薬撲滅には成功したんですね?」
「ふふん。倉庫の中に、くだんの麻薬は積んであったんだが、太ったねずみがその辺を走り回ったので、乗鞍は悲鳴をあげたそうだよ。ヒヨッ子が。まったく千住のあたりはあんな倉庫が多い。俺がつまりそこで『悪即斬』をしたんだよ。」
「でも、見つけたのは蒼紫さんでしたね。軍に横流しの品も、全部蒼紫さんが洗い出して報告したそうですね。隅田川の上をこっそりと、でも堂々と水運で流していたんでしょう?すごいな、あの人は。ああいう人だと、志々雄さんのところでは僕にはさっぱりわかんなかったですが。」
「馬鹿を言え。あのときも、戦艦の横流しで、志々雄を洗っていたんだぞ。あれはそういうスパイ人間だ。昔っからな。」
「新撰組とは違うんですね?」
「当たり前だ。あんなのと一緒にされては困る。」
宗次郎はそこで、大きく息を吸い込んで言った。
「実は、僕は蒼紫さんのところで働きたいんですよ。」
斎藤は宗次郎の言葉に目をむいた。
「なんだと。」
「だって斎藤さんは、たいして仕事らしい仕事もしていないじゃないですか。」
「失礼な奴だな。」
「僕の一番は、だんぜん今でもやはり志々雄さんですが、今回のことで僕はあの人にほれこみました。あの人さえいいなら・・・・。」
「それは無理だな。」
斎藤は、うわずった調子で続ける宗次郎の言葉をむげにさえぎった。
「どうしてです?」
「奴はアメリカに行くんだよ。おまえは邪魔だと。俺に昔そう言った。」
「えっ、それいつですか?」
「さあな。一週間ほど先かな。外務省からの御用達だと。」
「ええ?っ、そんなぁ・・・・・。」
宗次郎は思わず声をあげたが、どうにもならないことであった。
警視庁の建物から肩を落として出てきた宗次郎を、階段の下で安慈は待っていた。
安慈は言った。
「これから何処へ行けばいい?」
「とりあえず、北海道に戻りましょう。本当はアメリカに行きたいんだけど・・・・。報奨金がこれっぽっちじゃなあ・・・・。」
実は宗次郎は、斎藤に呼ばれて金を受け取りに来たのだった。
安慈は答えた。
「また北か。」
「そうです。北海道には、元新撰組だった人がいるんですよ。その人から、斎藤さんの話でも聞ければいいなあ・・・。」
宗次郎は空を見上げた。
澄み切った、晴れ渡った青空だった。
◆
剣心と左之助は、菊の花束を手に、今その寺の墓場の一角に向かっていた。
そこに―――あの偽者の巴の、真新しい墓があるという。
墓を立てたのは、蒼紫だった。
剣心は斎藤から、それを聞いていたのである。
剣心は思った。
あの男はこんなことにも抜かりなく―――拙者が思い至らないところまで手を回す。
左之助はそんな剣心を気遣って、墓の新しい卒塔婆に手を合わせてからこう言った。
「まああいつがこの女を殺したんだからよう。当然ってところか。」
「左之は見ていたのでござるか。」
「俺たちが薫嬢ちゃんを助けに来た時だったかな。やつが首をはねていたのは。無残なことをしやがる。この女はきっと奴の枕元に化けて出やがるぜ。」
剣心は左之助の言葉に、片頬をゆるめて答えた。
「左之助・・・・・それはどうでござるか。蒼紫には巴がいる。巴がきっと、守っているのだ。だから拙者にも勝つことができた。拙者は・・・・・やはり、巴には愛されていなかったのでござる。」
「けっ、勝利者よ、ってところか。」
左之助はそうごちると、剣心に向き直って言った。
「それよりも剣心、おまえの体―――。」
「左之助、拙者と一緒に大陸に渡ってはくれぬか。」
剣心は左之助の言葉を打ち消すように言った。
左之助は目を丸くした。
剣心が強い物言いをするのは、よっぽどのことだ。
いつも自分を抑えた、穏やかな物言いを、左之助にはするのに―――。
剣心は言った。
「山縣卿の話、拙者は受けようと思う。人々への贖罪、それが拙者に残されたただひとつの道だ。その時できれば左之助に、そばにいてもらいたい―――。」
左之助はその瞬間、万感の思いが胸に迫って、何も言えず、ただ剣心の肩を強くかき抱いた。
剣心に残された未来は少ない―――、いや、限りなくゼロに等しいのだ。
その時間を、まだ剣心は人助けに使いたいと言う。
こんなに傷だらけになりながら―――。
こんな男をここまで追い詰めて、あいつはアメリカなんかに渡りやがるんだ。
あいつは―――左之助はその時、心に浮かんだ蒼紫の幻影を憎もうと思った。
しかし、心のどこかに力が入らなかった。
蒼紫もまた巴を殺されて、心に傷があったから、剣心を殺そうとしたのだ。
その連鎖の因縁のつながりは、左之助には到底踏み込めないものだった。
左之助は剣心の肩を抱きながら、元気づけるように言った。
「剣心、剣心よぉ、俺はなんにもできねぇ男だが、おまえが立派なことは、俺だけはいつもわかっているつもりだからな。」
「左之助・・・・・ありがとう・・・・・でござる・・・・・・・・・・・・・・・。」
目を閉じた剣心は、安心したようにつぶやいた。
このところ微熱が続き、体がだるい。
病の兆候はもう出ている。
でも、巴―――君に殉ずることが、今ならば拙者にはできる。
そう、何も為す必要のない、維新の頃ではない、今ならば―――。
剣心は、今は放心する思いでそう思った。
肩を寄せ合う二人の男を、暮れなずむ陽が真っ赤に照らしだしていた。
蒼紫は銀座通りの裏の一筋を歩いていた。
古い店が立ち並ぶ中の一角の、ひとつの古ぼけた店構えの写真館の前で立ち止まった。
戸口にガラスに銀色の蒸着した文字で、店の名前が書かれている。
蒼紫は何の変哲もない、その店の扉をあけた。
中には鉄ストーブが白い湯気を立てて、置かれている。
店の陳列棚のガラスケースには、市井の人々の記念写真がいろいろと並べられている。
楕円形に切り抜かれたカードの中の人々は、皆緊張しながら正装して写っている。
店の奥の小豆色のびろうどの長いすに、店のおやじは腰かけていた。
白髪で鼻眼鏡をかけた和装で、きせるをふかしながら、新聞を眺めていた。
蒼紫はおやじに言った。
「文久年間に撮影された写真があるだろう?」
おやじが新聞から顔をあげた。
「文久年間?江戸時代かね。あるわけないだろう。」
「いや、あるはずだ。これで、譲ってもらいたい。」
蒼紫は、コートの中から札束を取り出し、無造作に陳列棚の上にドサリと置いた。
その時、おやじはやっと、蒼紫が大刀を手にしている事に気づいた。
そして蒼紫の黒髪の下の目は、こちらにじっと、張り付くような視線だった。
おやじは背筋がぞくりとしたが、ある事に気づいたのか、あわてて目をそらし、おびえたように口早で答えた。
「ないものはない。帰ってくれ。昔の写真は、一見さんには売らないんじゃ。」
蒼紫はおやじの言葉を打ち消すように、言った。
「いや、あるはずだ。芸妓を写した写真だ。」
「・・・・・・・・・・・・・・。」
「好事家の間で取引されているようだが、その中の一枚の銀板を出してくれ。」
「銀板は店の命じゃ。渡せんよ。」
「いや、芸妓というよりも、売春婦を写した写真だ。」
「ないものはない!帰ってくれっ。なんじゃ、あんたは一体。」
とおやじが言った瞬間、蒼紫の刀がおやじの耳元につきつけられた。
その拍子で、陳列棚の上の札束が落ちて、紙幣が店の床の上に散らばった。
蒼紫は言った。
「俺はもう一度しか言わん。その写真があるところへ案内しろ。」
「・・・・・・・あっ、あんた、あの写真は、誰にも見せたらいかん事になっとるんじゃ。」
「それは嘘だな。何枚か現像して流したはずだ。」
「・・・・・・・・・・・。」
蒼紫はおやじの背中をどやしつけると、店の奥に入った。
黒いカーテンのさがった現像室には、化学薬品の現像液のにおいがたちこめている。
白いホウロウのトレーが並ぶ小さい現像室の片隅の、銀板の板がぎっしりと並んだ木の棚を、おやじは探し始めた。
やがておやじはその中の一枚を引き出し、蒼紫に差し出した。
「あった、これじゃ、これじゃ、これが文久年間の写真じゃよ。ほら、鶴の上に女が乗っとる。あんたが探しているのは、これかねぇ・・・。」
蒼紫は差し出された写真を、刀の鞘で乱暴にはらいのけた。
写真が壁にぶちあたり、銀板の破片が床にこぼれた。
おやじはあわてて言った。
「あっ、そんなことをすると、写真が割れる。やめてくれ。」
取り乱したおやじの胸ぐらをつかむと、蒼紫は言った。
「俺を怒らせるな。素直に本物の写真を出せ。」
「あっ、あれを渡すと、わしの命が危ないんじゃ。」
「それは何故かな?」
「め、盟約なんじゃ。それ以上は言えんよ・・・・・あああんた、あんたがもしかして、四乃森蒼紫とかいう・・・・・。」
「・・・・・そうだが。」
「わかった、写真は渡す。手を離してくれ。」
おやじは観念したように、手をついて言った。
「そうかい、あんたが・・・・・・あんな写真一枚に、縛られとったんだねえ・・・・・。」
おやじはそう言うと、肩を落として言った。
「わしゃ廃業になるかも知れん。しかし、写真はあんたが会いに来るのをずっと待っとったよ。いろんな悪い奴が、わしを脅して、あれの現像をしては大金を置いていった。あんたも気をつけるといい。ああ、わしゃ何を言っとるんだろうな・・・・・・写真屋の感傷だと思って聞き流してくれ・・・・・・・・・・・・・・。」
蒼紫は言った。
「かつて、御庭番衆にかかわったことは?」
「あるよ。お察しの通り・・・・・しかし縁はなかなか切れん。あの写真も、わしが写したものではない・・・・・預かってくれと頼まれたんじゃ・・・・・。」
「だろうな。」
おやじは蒼紫をさらに店の奥に案内した。
そして、廊下のつきあたりにある、目立たない黒塗りの小さな金庫の扉を開けた。
おやじはつらそうに顔をそむけて言った。
「見なさい。これが文久年間の写真じゃよ。」
蒼紫は紙袋に収められている、銀板とその現像したものを取り出した。
蒼紫は食い入るように眺めた。
一瞬で時が彼方へとはばたいて帰っていく。
―――巴!
蒼紫の取り出した写真の中には、巴が上半身裸で写っていた。
白い腰巻をしめて中膝をついて、不安そうにこちらを眺めている。
背景は日本間のようであり、日本画の松原の絵の襖が半分写っていた。
写真は半分銀板が腐食したせいで、黒い点がいたるところについていた。
おやじは蒼紫を気遣うように言った。
「ああ、あんた、あんたその人とは、恋仲だったんだそうだね・・・・・。それは、その人が京都に来たときに写したものらしい。大阪の宿だったそうだよ・・・・・・・・・・・・・。人別改めのために撮影されたんだそうだ・・・・。」
蒼紫の背中が、おやじの言葉にひきつったように動いた。
悦びと憤りが半ばして、写真を持つ手がぶるぶると震えた。
この写真を撮影した者に対する激しい憎しみと、それに相反する感謝のような念・・・・・いや、俺はありがたいとは思わない。しかし、忘れそうになるのではないか、と思っていたあの巴の懐かしい遺影がそこにはあった。
白い顔、黒い髪・・・・・小さくのみで刻んだような目鼻だち・・・・・・。
あまり大きくはないが、柔らかな白い胸元・・・・・。
巴・・・・・巴・・・・・巴・・・・・・ああやはり、俺はおまえのことを愛している・・・・・・!
「おやじ、感謝する。」
それだけ言うと、来た時のように嵐のように蒼紫は店を去っていった。
おやじはつくねんと、残された店の中でつぶやいた。
「ああ、あの人の江戸は、まだ終っとらんのじゃなあ・・・・・。」
◆
神谷薫は、会津に帰った高荷恵にその日手紙を書いていた。
このところ、微熱が続き、食欲がない。
剣心は大陸に渡ったままだ。
―――剣心・・・・剣心・・・・早く帰ってきて・・・・・でないと私・・・・・。
ごほごほと咳き込むと、薫はうわがけを手でかき寄せた。
「寒い・・・・寒いわ・・・・・・剣心・・・・・・。」
春先の日和はのどかで、桜の花びらが静かに舞っている。
「恵さん、お元気ですか。調子はいかがですか。剣心は大陸で左之助と一緒に、働いているみたいです。私はこのごろ――少し、痩せました。先日ついに、剣心と私は、めおとになりました。でも、式はあげていません。そんなお金はないから・・・・ごめんなさい、恵さん。剣心は私のものになりました。いえ、私が剣心のものになったのでしょうね。
あの事件の後、みんな昔のように話さなくなりました。操ちゃんは蒼紫さんと、渡米したっきり、何の連絡もありません。操ちゃんは今頃どうしているのかなあ。元気に暮らしているといいけど。操ちゃんは最後の時、蒼紫さんと一緒で嬉しいはずなのに、波止場で別れるときに大声で泣いていました。私と別れるからでしょうか。そして蒼紫さんは――――。」
薫はそこで手から筆をすべり落とした。
薫は蒼紫のことを回想した。
―――あの人のことは最初から、私は怖かった。
薫はしかし、もう一度筆を取ると、紙にかきつけた。
「蒼紫さんは何も言いませんでした。あの人は剣心の一体何だったのでしょう。私にはわかりません。恵さんなら、わかるかも知れません。だって観柳邸であの人と一緒だったそうだから。私には、剣心を斬らなかったあの人の心はわかりません。」
薫はそこまで書いて、筆を止めた。
―――私に、うつして。その病気を剣心、私にもうつして・・・・・。
薫の脳裏に、剣心との最初の一夜がよみがえった。
―――拙者は―――。
剣心が言いかけるのを制して、薫は涙に震える目で言った。
―――一緒よ、剣心。あの世までも・・・ね・・・・・。
激しく自分を求める剣心に、薫は必死になって答えた。
―――心太と呼んでくれ、これからは・・・・・。
剣心の低いささやきが哀願するように、薫には聞こえた。
薫は手紙の紙ををよけると、手で顔をおおって言った。
「これで・・・・・これでいいのよ・・・・これで・・・・。」
涙が頬を伝い落ち、あとは言葉にならなかった。
「剣心・・・・あなたが私はかわいそう・・・・・・!」
◆
蒼紫は今、渡米する船の中にいる。
今のところは何もすることはないので、写真館から奪ってきた巴の古い写真を時々出しては眺めている。
この体を俺は斬った。―――いや、厳密には違うのだが、あの中国娘の顔は巴だった。
この写真をもとに中国医法でやつらが整形したのだ。
そして、あの中国娘の業病を知っていながら、剣心は何度も抱いていたのだった。
―――俺ならたとえ抱く機会があっても、抱かずに一刀のもとに斬り捨てていた―――。
それが俺と剣心の違いなのだ。
剣心を惰弱であると思う蒼紫だったが、そんな蒼紫でも写真を見つめていると、巴への暗い情欲の炎が、体の奥底から湧き上がってくる。
斬り捨てたことで、いっそう火照りがともったようだった。
しかし、本当の巴はもう何処にもいないのだ。
斬りたくはなかった―――この腕が。
『―――君にそんな権利があるのかね?人の命を自由にする権利が。いや、君は今までそうして生きてきたんだが――――。』
耳元で、あの時の王大人の皮肉な言葉が響いた。
俺の行く先々は、これからも屍のみなのか。
蒼紫の心の中で今、血の涙が流れていた。
操は船のデッキで、外人客と話をするでもなく、遠くを眺めていた。
―――おおおおい。おおおおい。
波の音が、操にはそう聞こえる。
過去に向かって、一人の男が、やまびこの声を求めて、谷間に向かってひたすらに叫んでいる。
あの人は私を愛しはしない。
体だけでも、愛しはしない。
今夜も、別々の部屋で、別々のベッドで、あの人と私は寝るのね。
心がこうして、離れていくのね。
でも、あの写真を蒼紫から奪い去ったら、私はきっとこの海の中に突き落とされる。
あの人はきっと、そうするわ。
夕暮れのデッキで、操は片肘をついてじっと海を眺めていた。
やがて日が暮れる。
私たちの間にも、日が落ちていくわ―――。
でも私は蒼紫から離れられないでいるのね。
操は思った。
蒼紫の心がこれから先、自分に向くことはおそらくはない――――あの人は、緋村抜刀斎とは別の道を選んだのだ。
その蒼紫の生き方を潔しとして、ともに歩んでいくことを、あの蒼紫が何処まで自分に許してくれるだろうか・・・・。
でもそれが、御庭番衆として私に示された、ただひとつ残された道なのだ。
それを私はずっと見守っていくの、できるところまで、あの蒼紫を守って――――。
操のその決意を知る者は、誰もなかった。
やがて日が暮れて、甲板のデッキを照らす客室の明かりの間を、巻町操は注意深く進んだ。
自分の姿を呼び止める者は誰もいない―――あの蒼紫でさえも。
でも、私はあの蒼紫を愛する。あの人が私を愛さないから、愛する。
そう思い直した操の心は、その時不意に明るくなった。
自分の心の動きのけなげさに、操の瞳は思わずうるんだ。
でもそれが、私の蒼紫様に捧げる愛なんだから・・・・・・。
操は涙を振り払うように顔をあげると、空にかかる白い弦月を眺めた。
その様は、今、生まれたばかりの赤子のようであった。
―完―
屍乱
ようやく終わりました。今回は本当に、いつになったら「完」の文字ところへたどり着けるのか、大変でした。
しかも「完」に相当する章をはじめからアップしていたので、やはりその重圧がすごかったです。こういうことは、やるもんじゃない・・・・と思いましたです。 まあそれでも楽しい苦しみではありましたがね。書き上げた今は、そう思います。剣心や左之助はまだいいんですが、こんなの蒼紫じゃないとお叱りを受けたらどうしようとか思っておりますが。
まあしかし、着想のはじめは、やはりOAVシリーズですねぇ・・・・・これが私も好きではあるんですが、絶賛されるほどいいかというと、追憶編はオチがもひとつだし、星霜編は 戦闘場面が少ないし―――かねてからそう思っていた私は、原作の人誅編をもう少しアレンジしたら、もう少し面白くなるのでは、と思ったんです。四神とか出さない方向でね。まあこれは私・おだまきのアレンジであるということなんですが。でも、冒頭で剣心と巴が戦っているのを見ただけで、もうこの話はいやだと言う人がきっとおられるだろうと思います。ええ。そこんところ、大丈夫という人は、この先もまた蒼紫の小説をひとつよろしくお願いします。はい。
今回はしかしBGMがどうのとか、言える状態じゃなかったですよ・・・・・とにかく最後まで書かないとと思っていたから・・・・・でも今はそうですね、ラフマニノフのピアノ協奏曲の三番なんか、この「屍乱」にはあうんじゃないかと思います。二番ほど華やかな曲じゃないんですが、しみじみといい曲でね。物悲しい感じがいいんじゃないかという事で、これから自分で聞くつもりです。宗教的で美しい、第二楽章が特に好きですね。いやしかし、島原編の時はこんなに悩まなかったですよ。この「屍乱」は、出てくるキャラクターがそれぞれの立場を自己主張しはじめたので、まとめるのに苦労しました。島原編は、なんというか、そういうキャラの内面にはあんまり踏み込んでいませんでしたね。蒼紫以外は特に。活劇に重点を置いていたのでね。今回のものは、心理ドラマみたいな方向性になっています。これから先も、自分が書くのはこっちの方向だなあと思います。おぼろげながらに、ですが。あ、勝手にあの曲がいいなどと言って、ラフマニノフのファンの方およびラフマニノフ先生どうもすみません。恥ついでに言いますと、タイトルの「屍乱」というのも、大沢在昌さんの推理小説「屍蘭」から考えています。なんか響きがきれいで、「かばねらん」と読ませると、ビゼーの名曲カルメンの「ハバネラ」となんか似ているのでいいかなと思って・・・・・・あれも自分を誘惑する恋人を殺す男の話なので、今回蒼紫は偽者の巴を殺す話なので、ね。そんな裏話があります。
最後になりましたけど、御堂茜はどんな容姿だったかと言いますと、原作の「ちゃうちゃうガールズ」の中の、蒼紫のことを「でも暗そうだけど、二枚目」と言っている、めがねをかけたお下げ髪の女の子、これです。このイメージで書きました。ということで、原作のその場面の絵を参考にしてくださいな。
それでは、また新作でお会いいたしましょう。
2006.1.31 おだまきかこ


