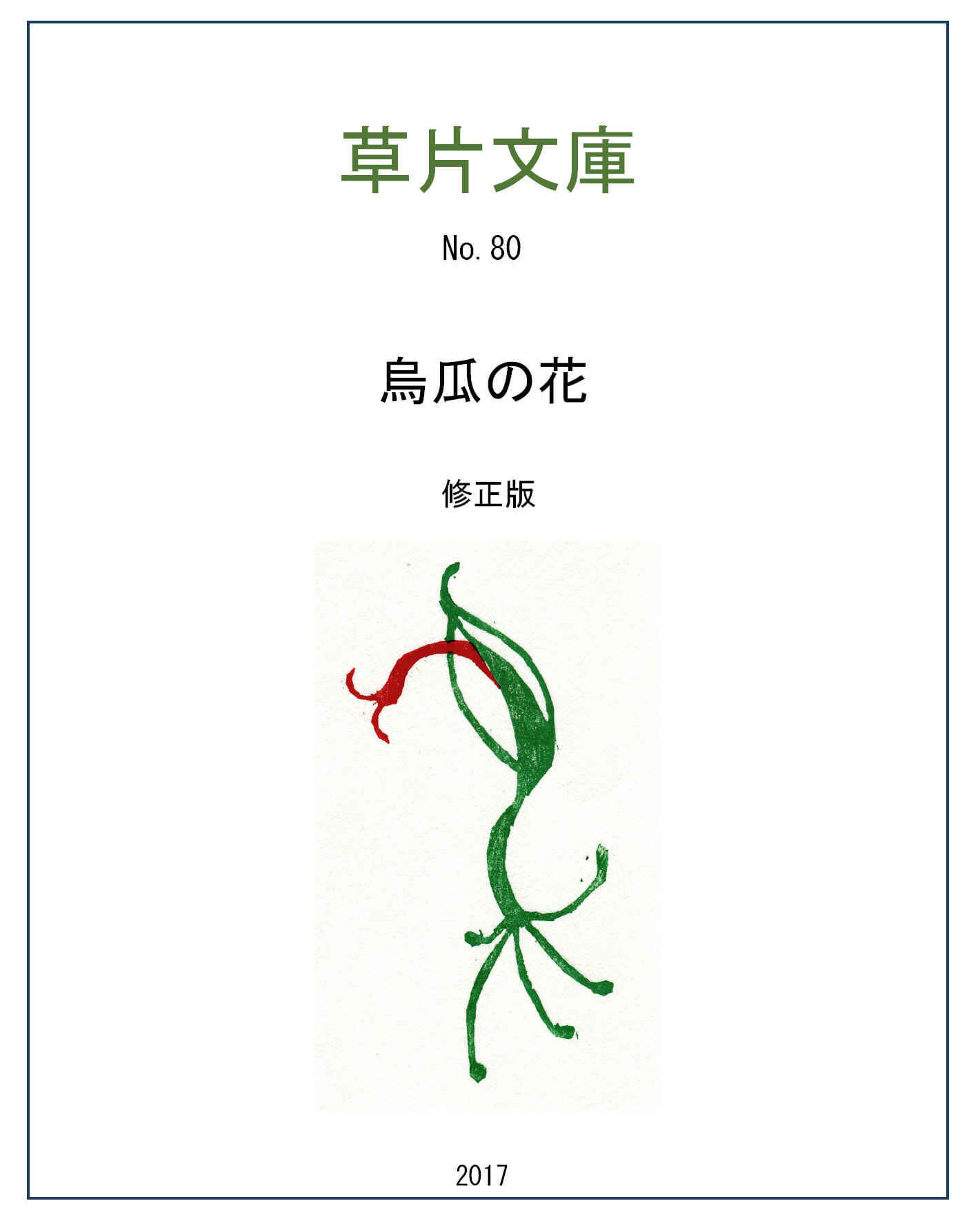
茗荷の舌 第16話(最終)ー烏瓜の花
子狸の摩訶不思議なお話。PDF縦書きでお読みください。
八月八日、今日は僕の誕生日だ。しかも、今日は僕の結婚式の日でもある。
南平の我が家で式が執り行われる。と言ってもいつもの連中が集まって騒ぐだけだ。
もうすぐ夜の八時になる。だけど用意してある座布団の上には誰もいない。座っているのは僕一人だ。みんなのんびりしているな。
庭の柿の木に絡み付いている烏瓜の花が開いた。
レースをかけたような白い花が薄暗くなった庭に白く浮き出ている。柿の木はまるで烏瓜の木のようだ。一人で見ているのもつまらないものだ。
玄関の開く音が聞こえた。
「こんにちわー、おめでとう」
「おめでとう」
多摩子さんと、九茶路子さんだ。
二人で大きな箱を持って居間に上がって来た。若くなって、二人ともますます元気に活躍している。
座布団の上でぼーっとしている僕の前に来るとのたまわった。
「結婚するんだって聞いたときは、びっくりしたわ」
「ほんと、そんな勇気があると思ってなかったわ」
多摩子さんと九茶路子さんの感想である。
「それで、お相手はだーれ」
「へへ、あとできます」と、僕は照れた。
二人は、
「これ、お相手が来たらあげるのよ」
と、大きな箱を脇に置いた。何を持ってきたのだろう。
「おーう、おめでとう」
高尾に住む彫刻家の悼心贈が和服姿で入ってきた。画廊の金燐子さんも一緒だ。
手には木で彫った平目が握られている。
「お祝いの鯛を彫ったら、平目になった」と、僕の前に置いた。
「結婚なんて顔していなかっただろうに、誰と結婚するんだい」
そう彼が聞いたので、やっぱり「へへへ」と笑っておいた。
次にきたのは奥胎内からでてきたジュエリストならぬジュエキストの長井大長だ。
「よー、おめでとう、ほら、最近作った宝石だ、奥さんにあげてくれよ」
彼は、ティシュペーパーに無造作に包んだこぶし大の物を僕にくれた。
開けてみると透明な丸い玉である。
「水晶磨いたのかい」
「いや、水晶じゃないんだ、ピアスで飾ろうと思ってアナコンダを輸入したんだ、部屋の中に入れておいたら、練炭(れんたん)用の炭団(たどん)を丸呑みにしちまった。一月たって糞として出てきたのがこの透明の石なのだ」
「炭がこの水晶に変わったのかい」
「そうだよ」
「それじゃ、ダイヤモンドじゃないか」
「そうなんだ、こんなすごいダイヤを見たことがあるか」
「ふーん、ないよ」
「今、アナコンダの腹の中には炭団が八つ入っている。半月もすれば、次から次へとこの丸いダイヤモンドが出てくるんだ」
「すごいものだ、億万長者じゃないか」
「みんなで分けよう」
長井君も欲のない男である。
子木子堪能と都縞間造が来た。
「よーおめでとう、俺が採取した珍しい冬虫夏草を堪能が佃煮にしてくれた、精力剤だ」と間造が包みをくれた。
女神子さんが来た。
「おめでとう、大鳴子百合のお酒持ってきましたよ」
一生徳利を吊るして上がってきた。
彼女はまるで、ふっくらした信楽焼きの狸のようだ。
僕はみんなに女神子さんを紹介した。
「大鳴子百合を手懐けて、夢のようなお酒を造るひとです、今日の結婚式を取仕切っていただきます」
「女神子です」
拍手が起きた。
玄関が大きな音で開いた。
「遅くなっちゃいましたあ」
明るい声で、赤いスカートに白いブラウスの円美ちゃんが、エコバックを肩にかけて入ってきた。
「あーら、円美ちゃん、久しぶりね」
九茶路子さんが笑顔になった。
「久しくお茶のお勉強に来ないわね」
円美ちゃんはペロッと舌を出すと、
「ごめんなさーい、またちゃんと行きまーす」
そう言って僕の隣の空いている席に座った。
多摩子さんが、
「あー、そこは新婦の席よ」
と驚いた顔をすると、九茶路子さんと顔を見合わせて、
「えええええ」と言った。
僕は、
「お嫁さんの円美ちゃんです」
と皆に紹介した。
「円美です」
円美ちゃんは張り切って大きな声を上げた。
皆が大きな大きな拍手をした。
「びっくりしたあ」
多摩子さんと九茶路子さんは、円美ちゃんの言い方をまねた。
二人して円美ちゃんの前に来て、
「ほんとなね、おめでとう、おめでとう」と、涙を流して喜んでくれた。そして、持って来た箱を開けた。
二人が取り出したのは烏瓜の花で作った長い長いレイだ。
九茶路子さんと多摩子さんは、二人して円美ちゃんに幾重にもレイをまきつけた。円美ちゃんは烏瓜の花に包まれてしまった。
「ありがとう」、円美ちゃんらしくなく少し涙ぐんでいる。
「きれいだねー」みんなが見とれるぐらいかわいかった。
心贈が「いいなあー」なんて言っている。
大長も堪能も間造もみんな同じ顔をして円美ちゃんを見ている。
「さー、結婚式を始めましょう」
女神子さんが、僕と円美ちゃんの前に置かれている盃に大鳴子百合のお酒をついだ。
みんなのお膳に、冬虫夏草の佃煮と、白いご飯に、ドクダミのお茶が用意された。
そのとき、円美ちゃんが両腕を上げて、
「結界、南平」と叫んだ。
六畳の狭い居間がぐーんと広がって、二十畳もあろうかと思われる広い部屋へと変貌した。
しかも僕と円美ちゃんの後ろに床の間が出現し、床の間にはふさふさと伸びた茗荷が植えられている立派な鉢があらわれた。
みんなが驚いて床の間を見ていると、葉の下からにょきにょきと花芽が膨らむと、あっという間に茗荷の花がたくさん咲いた。
そのとたん。
「こんちわ、半崎巌です」
と、見慣れない小父さんが入ってきた。
「おー、これからだな、おめでとう、円美ちゃん、みなさん」
「あ、小父さん、ありがとう」、円美ちゃんが言った。
「久しぶりですな、なんと若返って」
小父さんという人が多摩子さんに挨拶をした。
多摩子さんはなかなか思い出さないようだったが、円美ちゃんが「ほら、目無し不動の秋刀魚の小父さん」と言った。
「あ、あの山椒魚の」と、多摩子さんも思い出した。死んだ秋刀魚を生き返らした山椒魚の小父さんだ。
「円美ちゃんが結界を作ったのでな、こうしてこれたんじゃ」
玄関が開く音がした。
赤ら顔の男と、柘榴石のピアスをした色の白い男が腕を組んで玄関先に立った。
「おめでとうございます、守宮でございます、いつぞやはお世話になりました」
手には野葡萄で作った首飾りを持っている。人間に化けてきたのだ。
「よく来てくれました、ありがとう」
僕は上るように促した。
「それでは、みなさま、おめでとうございます」
二人は僕たちの前に来ると、
「へへ、はずかしいですが」と白い顔の男が首飾りを円美ちゃんに渡した。
「きれい、ありがとう」円美ちゃんが目を丸くしている。
「ありがとう」僕もお礼を言った。
円美ちゃんの袖から守宮が顔を出した。円美ちゃんが大事にしている守宮だ。
男同士の夫婦守宮は「あ、お仲間がいますな、こりゃ今日は楽しくなりそうで」
円美ちゃんの守宮はもじもじしていたが、袖から飛び出し、若い女の子に化けると「よろしく」などと言っている。
また玄関が開いた。
燕尾服をすきっと着こなした、色の黒いりりしい男が、白い布をからだに巻いたかわいらしい女の子とやって来た。
「久しぶりで、おめでとうございます」と、座布団の上に座った。
はて、だれだったかな、と思い出そうとしていると、それを察したように、
「大鴉と蝙蝠にございます」と、自己紹介した。
文学少女の蝙蝠のお嬢さんがポーっとしてしまった顎鬚の鴉だ。
「これ、おいしいの、あたいが作ったの」
蝙蝠のお嬢さんは蛇苺の実のケーキを持ってきた。
「ありがとう、よく来てくれました」、僕も嬉しくなった。
女神子さんが言った。
「さあ、まずは三々九度よ」
僕と円美ちゃんは大鳴子百合のお酒で三々九度をした。おいしいお酒である。
心贈が自分で彫った平目を持つと舞い始めた。
「鯛や平目の祝いの踊り、鯛を彫って平目となす。平目なのに鯛に見える」変な節まわしだ。
そこに、近所の人たちがやって来た。駅前のコロッケ屋のおじさん、写真屋の夫婦、前の家の九十三歳になるおばあさん、雑貨屋さんの叔母さん。目白台の柿屋の小父さんと小母さんも上がってきた。
「おめでとう」
広い座敷に皆めいめいに座って酒を飲んだ。
自治会の会長さんまでもやって来た。
「近頃、楽しいことがなくて、こりゃおめでとうございます」
いい人である。
お酒もおいしいし、佃煮もおいしいし、お茶漬けもおいしい、皆わいわいがやがや、盛り上がっている。
窓の外の月が青く冴えて、柿の木にからんだ烏瓜の白い花が華やいでいる。
多摩子さんと九茶路子さんが僕と円美ちゃんの前に徳利を持ってきてお酒をついだ。
「円美ちゃん、おめでとう、わたしたちもお相手が欲しいわあ」
円美ちゃんのおかげで若くなった多摩子さんと九茶路子さんは話し方まで円美ちゃんに似てきた。
「それじゃ、あたしの兄弟を紹介しましょうかあ」
円美ちゃんが両手を挙げて「いらっしゃーいい」と声を上げた。
玄関がガラッと開くと、顔かたちがそっくりな美男子が二人入って来た。
「こっちよ」
二人の美男子は上ってくると、僕に「姉(あね)さんをよろしくお願いします」と頭を下げた。姉さんということは弟なのだろう。
「私の双子の弟です、円夢(まるむ)と円(まる)藻(も)」
円美ちゃんは九茶路子さんと多摩子さんに紹介している。
「あら、すてき、向こうで飲みましょ」
二人の美男子は二人の若返った美女に連れられて席に座った。
「円美ちゃんに弟がいたんだね」
「ええ、まだいるの。円磨(まるま)、円(まる)芽(め)、今秋田の湯沢にある実家に帰っているの、そのうち紹介します」
「へー、お父さんとお母さんも秋田にいるの」
「ううん、わたしお父さんもお母さんももういないの、東京に出てきて、私たちがちょっと大きくなったとき死んじゃったの、ライオンに食べられて。でもお爺ちゃんとお婆ちゃんが秋田にいるの。もういい年だから、秋田から出てこられないけど」
円美ちゃんが言った。
「それじゃ、新婚旅行は秋田にしよう」と僕は言った。
「うれしー」
あれ、お父さんとお母さんは何でなくなったのかな。ライオンに食べられたと言ったようだが、何かの聞き間違いだろう。あとできちんと聞こう。
間造、堪能、心贈、大長が円美ちゃんの前にやって来た。
「俺たちも嫁さん欲しい」
すると、円美ちゃんがまた両手を挙げて叫んだ「おいでーー」。
とたん、玄関に若い絶世の美女が四人やって来た。
間造たちはびっくりしてきょとんとしている。
「いとこの、円衣、円有、円絵、円緒です」円美ちゃんが紹介した。
もじもじしている間造たちを円美ちゃんの従兄弟たちが席に引っ張っていった。
「円美ちゃんすごいね」
「でも、疲れちゃった」と、円美ちゃんが足を崩すと、ぽっこりとふさふさした尾っぽが現れた。
「あーーまた出ちゃった」
円美ちゃんの大きな声で、みんなが円美ちゃんを見た。
円美ちゃんは一生懸命尾っぽを消そうと頑張ったけれど消えなかった。
「あらああ、円美ちゃん、あの狸の子なのおおお」
多摩子さんと、九茶路子さんが大きな声をあげた。
円美ちゃんは満面の笑みを浮かべて頷いている。
「あはははは、あはははは」
大きな口をあけて笑っている多摩子さんのお尻に銀色の尾っぽが生えた。銀ぎつねだ。
顔をくしゃくしゃにしている九茶路子さんのお尻にも白い尾っぽが生えた。白狐だ。
おや、女神子さんにも尾っぽが生えた。ハクビシンだ。
半崎巌の小父さんも山椒魚に戻り、守宮や大鴉や蝙蝠さんたちも自分の姿に戻った。
おや、心贈、大長、間造、堪能は赤ネズミじゃないか。みんな親戚だ。金燐子さんは、なんと金魚だ。柿屋の小父さんと小母さんは月の輪熊と穴熊になった。姿は戻ったがみんな人間の大きさのままだ。
コロッケ屋の小父さんは蝸牛に、写真屋さん夫婦は蛙と沢蟹になった。前のおばあさんは亀さんだった。雑貨屋の叔母さんは蛞蝓(なめくじ)になった。
玄関に誰か来た。
入って来たのは白い背広を着た大人しそうな二人の青年だ。
「おめでとうございます」
一人が、目をきょろきょろさせて上ってきた。歩き方がぎこちない。
後ろからもう一人が上がって来た。
二人の青年が間造のほうを向いた。後について上ってきた青年の背広の後ろに大きな黒い円い模様が二つあるのが見えた。
猫の白とジンゾウだ。うまく化けたつもりなのだろうが、動きががちがちしている。
「おい、白とジンゾウありがとよ」僕は声をかけた。
青年たちはほっとしたように、猫の白とジンに戻って大好きな間造の膝の上に乗った。初めて人に化けたのだろう。
赤ネズミがあぐらをかいて、その上に二匹の猫が乗っているのは見ものだ。
僕は、そこで、自治会の会長さんが目をまん丸に見開いて、腰を抜かしているのに気がついた。
盃と茗荷で作った酒を持って会長さんの前に行った。
「今日は、わざわざありがとうございます。どうぞ」
僕は、盃を渡し、酒をついだ。
「ど、どうも、酔っ払ったようだ、みんなが動物に見える」
会長さんはぐっと酒を飲んだ。
「うまいですなー」
自治会の会長さんだけが人間だ。化けることができない。茗荷の酒を飲めば明日になると全部忘れる。会長さんは飲んだとたんパタンと寝てしまった。あとで自宅まで送って行こう。
僕が円美ちゃんの隣に戻ると、円美ちゃんが言った。
「しっぽ出してよ」
大きな声なものだから、みんなが僕を見た。
「へへへ」しかたないか、細くてみっともないが、と思いながら、僕もしっぽを出した。
「あーら、長いのね、かわいい」
円美ちゃんが笑った。自分で言っちまったほうがはずかしくないだろう。
「僕は最後の日本川獺(かわうそ)です。今日で九十八歳、皆さんありがとう、円美ちゃんは二歳、こんな若いお嫁さんがくるとは、二人で合わせて百歳、嬉しすぎて」
たぶん僕はにっこにっこでしわくちゃな顔をしていたのだろう。
大きな拍手が起きた。
僕は絶滅種に指定された日本川獺だ。
それから宴会は夜遅くまで続いた。
「円美ちゃん、お父さんとお母さんなんでなくなったの」
僕は気になっていたことを聞いた。
「ライオンに食べられちゃったのよ」
聞き違えじゃなかったんだ。
「お父ちゃんとお母ちゃんは秋田から東京に出てきたの。動物園は楽しいでしょう、だから動物園に住んだの。わたしたちが自分で餌を獲れるようになったら、動物園のライオンの餌を横取りしに行って食べられちゃったの」
円美ちゃんは何気なく話したが、なんと可愛そうな話なのだろう。
「どうして、ライオンの餌を取りに行ったの」
「ライオンの餌のお肉でステーキ作りたかったのよ、ばっかみたい、よしなさいって言ったのよ、それなのに、平気、平気なんて二人で腕組んで行って食べられちゃった」
「かわいそうじゃない」
僕がそう言うと、円美ちゃんも少ししゅんとなった。
「それで、結界作るの覚えたの、今日お父ちゃんとお母ちゃんに会えるの」
みんなが円美ちゃんを見た。
円美ちゃんはエコバックからなにやら取り出し畳の上に置いた。
「これ、お父ちゃんの尾っぽ。これ、お母ちゃんの尾っぽ、これしか残ってなかったの」
円美ちゃんが狸の尾っぽを二つ、畳の上に置くと、それを見た山椒魚は、
「おい、川獺、七輪持ってこい」と、
小父さんに戻って、僕に言いつけた。
「ほいきた」
僕も人間に戻ると喜び勇んで台所から七輪を持ってきて炭を入れ、火を熾(おこ)した。
山椒魚の小父さんはその前に座った。
小父さんが「網」とまた僕に命令した。
もちろん急いで網を用意した。
叔父さんは、ニコニコして、円美ちゃんに「すぐだよ」と声をかけた。
円美ちゃんが尾っぽを叔父さんに渡した。
山椒魚の小父さんは、二つの尾っぽを網の上に載せた。
山椒をたっぷりふった。
ちりちりという音と、毛の焼ける匂いがした。
みんなが真剣な眼差しで七輪の上の尾っぽを見た。
尾っぽはするすると大きくなり、真っ白と真っ黒な狸になって畳の上に座った。
円美ちゃんがかけよって、「お母ちゃん、お父ちゃん」と抱きついた。
みんな、しーんとしていたが、いきなり拍手が起きた。
女神子さんは山椒魚の小父さんにお酒をついだ。
「あたしをつれてって」
女神子さんは山椒魚の小父さんにむかってしなを作った。
小父さんはぐい飲みを落しそうになった。だけどとても嬉しそうに頷いた。
僕は円美ちゃんの両親に改めて手をついて、「円美ちゃんをお嫁さんにします」と言った。
お父さんとお母さんは頷いた。
「こんなお転婆を、物好きですな、あなた、あははは」
「ほんと、おほほほ」
月の光が煌々と差し込んできて、床の間を明るく照らし出した。
床の間で月の光を浴びた茗荷の花たちが背伸びをして鉢から飛び出した。
ぞろぞろと歩きだすとみんなの前にやってきた。
そして、真っ赤な舌を二枚べろーんと伸ばして言った。
「おしまい」
完
「茗荷の舌」所収、自費出版33部 2016年 一粒書房
茗荷の舌 第16話(最終)ー烏瓜の花


