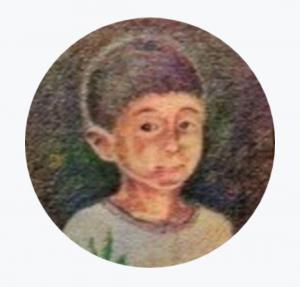短編小説・路地裏
「第43回 埼玉文学賞」応募作品
その日、川本善吉は、いつもは通ることのない、人通りの少ない路地裏を歩いていた。
通りに向かって打ち水をしていた小料理屋の女将が、後ろから歩いて来た善吉に気づかず、盛大に柄杓で水を掛けた。
「あら、ごめんなさい!私ったら何てことを···」
真っ白な割烹着の下から覗く夏の着物には、涼しげな朝顔が咲いていた。詫びる顔とは反対に、鳩が豆鉄砲を食らったように身動ぎもせず、頭からびしょ濡れになった善吉を見てクスクスと笑いを堪えながら、女将は手にしていたバケツを置いて、拭く物を取りに急いで店の中へと駆け込んだ。
しばらく待ったが、女将は中々外へ出て来る気配がない。
痺れを切らした善吉は、
「大丈夫ですよ、もういいですから。この暑さなら歩いているうちに乾くでしょうから。どうか気にしないで下さいよ」
店の奥にいるであろう女将に叫んだ。
「本当にすみませんねぇ。ところで旦那。今夜、都合がつくようでしたら、是非、いらして下さいよ。お詫びにたんとご馳走しますから」
店の奥から女将は叫ぶように言ったが、特にその声に悪びれた様子はなかった。
「気が向いたら寄らせてもらうよ」
何だかバカにされたような気がしてぶっきらぼうに返事をしたが、女将の誘いに善吉は満更ではなかった。
その夜、詫びのつもりでお愛想で言ったであろう女将の言葉は真に受けず、善吉は店には行かなかったが、それから数日後、どういう心変わりか、善吉の足は女将の店に向かっていた。
店に着くと深呼吸し、何も言わずに暖簾をくぐりドアを開けた。
「いらっしゃいまし」
ちゃきちゃきとした、気持ちのいい女将の声が善吉を出迎えた。
「あら、旦那!やっぱりいらしてくれたんですね」
紅子が満面の笑みを善吉に向けた。
「年寄りを邪険にしたあんたさんが、気に病んでちゃ気の毒だと思ってね。そうかと言って、その日のうちにのこのこ来たんじゃ、余りにも節操ってものがないからね」
思ってもいないことを善吉は言った。
店を開けたばかりなのだろうか、善吉の他に客は一人もいなかった。
「流行ってるのかね?」
言いかけたところで、女将が善吉の口を塞いだ。
「本当に、先日はすみませんでした。本来ならクリーニング代を支払うべきところなんでしょうけど、うちはご覧のとおりこんな商売やってますでしょう。ですから、クリーニング代をお渡しするよりか、ご馳走する方がいいかと思いましてね」
女将の詫びは、どうやら嘘ではなかった。お通しのきんぴらごぼうの入った品のいい小鉢を善吉の前に出すと、女将はビールの栓を開け、善吉のコップに注いだ。
「あの時、慌ててバスタオルを取りに行ったんですけどね、私ひとりでしょう。新しいバスタオルなんて、どこの家も大概が押入れの衣装ケースに後生大事に仕舞ってるものじゃありませんか。一生懸命探したところで、すぐには出て来やしないんですよ」
注がれたビールを勢いよく飲んだ善吉は、気をよくした。
「別に新しいバスタオルじゃなくたって、使い古しのタオルで十分だったのに」
「いいえ、そうはいきませんよ。知らない人にわざとではないとはいえ、ねぇ···」
女将は柄杓で水を掛けるジェスチャーをすると、決まりの悪い顔をしてその手をすぐに引っ込めた。
「もういいんだって、女将。私は逆に女将に水を掛けられたこと、今じゃ良かったと思ってるくらいなんだから」
この言葉は善吉の本音だった。
「あら旦那。若い頃は大層、女ったらしだったと見た」
女将が目を細めて冷やかした。
「いやいや、女将が死んだ女房によく似ていたものだからねぇ」
また、本音が出た。
「もう、そんなこと言って、奥さん殺しちゃダメですよ。家で美味しいものを作って旦那の帰りを待ってらっしゃるんでしょう?」
女将は菜箸を持つ手で、カウンター越しに善吉を小突くような仕草をしたが、善吉の話が嘘ではないと分かると、女将の顔から微かに血の気が引いた。
「まぁ、ごめんなさい。私ったら、また失礼なことを言っちゃって。奥さん亡くされたの、いつ」
「今年の春先に。肺がんでね」
善吉の妻の葉子は、学生時代の美術部の仲間たちと、毎年恒例の花見を兼ねた写生会に出かけていた。昨春、写生会から帰った葉子が軽く咳を一つ二つしていたのを目にした時、葉子の異変に気づいておくべきだった。
「寒の戻りで風邪でもひいたのよ、きっと」
こう言って、葉子は心配する善吉を脇目に笑って真面目に取り合わなかったが、手を打つべき時はあの時だったのである。その判断を誤ってから、葉子の病気はまるで坂を転げ落ちるように、あっという間に悪化の一途を辿った。
女将は善吉の話に静かに頷きながら、コップをもう一つ善吉の斜め前にそっと置くと、ビールを注いだ。
「これは、亡くなった奥さんに」
「おぉ、ありがとう。すみませんなぁ。これはこれは、妻の何よりの供養になりますよ。せっかくだから、迷惑でなかったら女将も一杯、付き合ってくれないかね」
「あら、いいんですか?それじゃ一杯だけ」
女将はビールを注いだコップを手に取ると、
「奥さんに献杯」
そう言って葉子のコップに軽く当ててから、続けて善吉のコップにもカチンと当てた。善吉も女将につられて葉子のコップに軽く自分のコップを当てた。
「今夜はもう、看板にしちゃおうっと。旦那の話を聞いてたら私、すっかり旦那に同情しちゃった。今夜は好きなだけ食べて、好きなだけ飲んで帰って下さいよ」
せがむようにそう言うと、女将はしゃがみ込んでカウンターを潜り抜けた。それから入口の戸を開け、下げたばかりの暖簾と赤ちょうちんを店に仕舞い始めた。
そこへ、ひとりの馴染みの客がやって来た。
「あれ、女将。今日は休み?何かあったの?」
女将と言葉を交わしている客の声が、外から聞こえて来た。
戻って来た女将に善吉が、
「やっぱり済まないよ。せっかくだけど私はこれで失礼するよ」
財布から一万円札を取り出すと、カウンターに置き席を立ちかけた。すると、さっきまで穏やかで人当たりの良かった女将が血相を変えて、善吉に食って掛かった。
「何を言ってるんですよ、旦那。それじゃ、私の気が済まないじゃありませんか!それに今日は私の奢り、この間のお詫びなんですからね。こんなお金をいただく理由もありませんよ!」
女将は善吉に一万円札を突っ返した。
善吉は慌てて一万円札を財布ではなく、ズボンのポケットに無造作に引っ込めた。
「これはこれは申し訳ない。今のは私のマナー違反でしたね。どうかこのとおり」
平謝りに詫びたが、そんな潔癖な気性も善吉の死んだ妻によく似ていた。
「分かってくれればいいんですよ。ごめんなさいね、私ったらむきになって。さぁ、旦那、座って座って。ところで旦那。差し支えなかったら、お名前教えて下さらない?」
機嫌を直した女将が善吉に名を訊ねた。
「こういう時に、さっと名刺でも出せたら格好がいいんだけど。生憎もう今はリタイヤして冴えない隠居の身でね。私は川本善吉と言います。年は七十五です」
決まりが悪そうに善吉が頭を下げると、女将はすぐに「旦那」から「善さん」と呼び方を変え、困ったような顔をした。
「善さんの方から年まで言われちゃ、私も答えない訳にはいかないじゃないの」
女将が笑いながら言うと、善吉は思わず「五十一」と、女将の年を言い当てた。
「いやねぇ、善さんたら。私、まだ名前すら打ち明けていないのに、年齢を先に当てられたんじゃやりきれないわ。私ってそんなにいってるように見えて?」
善吉は飲みかけのビールを気管に流し込み、盛大に噎せた。
「ちょっと、いやだなぁ。善さん大丈夫?誤嚥性肺炎にでもなったら大変よ」
「いや、これは、これは、申し訳、ない。ところで、女将、名は、何て」
激しく咳込みながら、目を白黒させて善吉は途切れ途切れに女将に名を訊ねた。
「私、岡﨑紅子と申します。年はもう改めて答える必要はないわね」
紅子は朗らかに屈託なく笑った。
「それにしても、善さんたら凄いのね。初めて会った私の年を意図も簡単に当てちゃうんですもの」
「何、人様より多少は長く生きているものだから。勘てやつだよ」
そう言うと、善吉は少しばかり酔いにまかせて紅子に深入りした。
「なぁ、女将。これも何かの縁だと思って、プライベートなことを話してもいいかね?」
紅子はわずかに怯んだが、今日はできる限りのことを善吉にしてやるつもりだった。
「えぇ、勿論」
紅子が屈託なく返事をすると、それまで上機嫌でビールを飲んでいた善吉が、心なしかそわそわし始めた。
紅子はそんな善吉の様子に気づき、てきぱきと作り置きしておいたポテトサラダや肉じゃがの入った小鉢を善吉の前に並べた。
「何だか、いも尽くしで申し訳ないんですけど、他に何か召し上がりたい物がありましたら、遠慮なくおっしゃって下さいよ」
「ありがとう。それにしても女将もやるねぇ、同じ食材で二品作るとは」
「いやねぇ、善さんたら。私、小料理屋の女将なんですからね。これくらいは」
「あぁ、これは済まない。褒めたつもりだったのに。こういうところはダメだねぇ」
善吉は空いている左手で軽く頭を叩いた。
「それと、私のことは紅子でいいんですよ。紅子って呼んで下さいな」
「それじゃ、遠慮なく」
咳払いをすると、善吉は再び話し始めた。
「紅子さん。私、今は独りなんですよ」
「独りって、奥さんはあれだけど。善さん、お子さんは?善さんの年ならきっとお子さんも私と同じくらいの年でしょう?」
善吉の顔が微かに強張り、返事をするまでにしばらく間が空いた。
途方もない沈黙から、やっと這い出た善吉は絞り出すように、
「紅子さんみたいな娘が欲しかったなぁ」
唸るようにそう言った。
善吉は黙り込むと、ポテトサラダに箸を付け、パリパリときゅうりを噛んだ
「嫌だなぁ、善さんたら。そんな嬉しいこと言ってくれたかと思ったら急に黙り込んじゃって。照れちゃったのかしら、善さんが話さないんだったら、私が話すわね」
堪り兼ねた紅子が口を開いた。
「私ね、娘が一人いるんですよ」
善吉のきゅうりを噛むパリパリが止まった。
「私の母は、私が幼い頃、私を置いて家を出て行ったんですよ。だから、私は絶対、子供を置いて家を出ることだけはするまいと固く誓っていたんですけど。因果なものですね」
紅子は夫の留守中、舅から肉体関係を迫られるのに耐えかねて、誰にも訳を言えずに家を出た。住み込みで働ける仕事を見つけて急いで娘を迎えに家に戻ったが、その間に何も知らない姑は紅子がいないことを幸いに、娘をすっかり手懐けていた。
「あの時からもう、私はあの家には帰れなくなってしまったんですよ」
紅子はぼんやり、コップの中のビールの泡を眺めた。
「それはとんでもない舅だ。旦那に言ってやりゃ良かったのに。何も紅子さん一人が悪者になることはなかったんだよ」
普段は穏やかな善吉が、珍しく怒りを露わに憤った。
「それで、娘さんとは会ってるのかね?」
相変わらず、善吉の口調はきついままである。
「えぇ、お陰様で。今は会いたい時に会っています」
「そりゃ良かった」
善吉の顔が見る見るうちに綻んだ。
「それで、娘さんの名前は何て言うんだい?」
「華子です。私が紅子だから、二人合わせて『紅花』ならぬ『紅華』です」
「華子さんかぁ、いい名前だねぇ。年はいくつ?」
「お陰様で二十歳になりました。そうは言っても、育てたのは華子の父親と姑で、私は遠くから眺めていただけなんですけどね···」
紅子は善吉の空になったコップにビールを注いだ。
「自分を置いて出て行ったとはいえ、やっぱりおふくろさんには華子さんを見せたかったかい?」
「えぇ、そりゃ。今となったらやっぱりね。母の気持ちも全部とはいかないけれど、多少は分かる年に私もなりましたから」
「華子さんは紅子さんに似て、そりゃあきれいな娘さんなんだろうねぇ」
それまで少しばかり元気のなかった紅子が、善吉を見て笑った。
「まぁ、善さんたら。それは母親の私を見たら一目瞭然でしょう」
「いやいや、これは失礼」
「あら、何も謝ることはないんですよ。善さん、良かったら娘の華子の写真、見て下さいます?」
「えっ、いいのかね?」
「勿論ですよ」
紅子はスマートフォンを手に取ると、待ち受け画面を善吉に見せた。そこには、成人の日に紅子の店の前で晴着を着た華子と、着物に割烹着姿の紅子が、華子の肩に遠慮気味に手を添えている姿があった。
それを見た善吉は言葉を失った。
「善さん、どうかして?」
「いや、別に。紅子さんも華子さんも二人とも、とってもいい顔をしているなぁと思ってね。二人とも余りにべっぴんさんだったから、思わず見惚れてしまったんだよ」
「まぁ、善さんたら」
出会った頃の葉子とそんなに年の変わらない、美しく溌剌とした華子の顔を見た善吉は、葉子と出会った頃のことを思い出していた。
それは、善吉の一目惚れだった。
出会って数年後、善吉が葉子にプロポーズをした時、初めは断られた。
翌々話を聞くと、自分には離婚歴があり、前夫との間に子まで成したという。自分は子供は産めない、子供を望むなら自分との結婚は諦めてくれと言った。
葉子との結婚を簡単に諦められる筈のなかった善吉は、身体的な問題かと問い詰めると、心理的な問題だと肩で息をしながら葉子は言った。返す言葉が見つからず、そのままになってしまったが、善吉は葉子との結婚を選び、葉子の望みどおり子供は諦めた。
それでも結婚後、葉子の気持ちに変化があるかもしれないと、善吉は隣に眠る葉子の肩をそっと抱き、行為に及ぼうとした。すると、葉子は申し訳なさそうに、だが、きっぱりと善吉に言った。
「するなら、着けるもの着けてからにして下さいね」
そう言われて、そっと葉子の肩に伸ばした手を引っ込めたことも、一度や二度ではなかった。
「あなたには本当に申し訳ないと思っています。でも、これは私自身の問題なんです。どうしても子供が欲しかったら、私じゃなく、よその女と作って下さい。お願いします」
最後には、いつも決まってこの言葉を善吉は葉子から聞かされた。
その度に葉子は泣いているように見えた。
この日を境に、善吉は子供を持つことをきっぱり諦めたのだった。
「まぁ、奥さんたら。一体ひとりで何を抱えていたのかしら」
「さぁ、女房の問題だから、私には何とも言えんがねぇ···」
しばらく考え込んでいた紅子が口を開いた。
「もしかして、奥さんが善さんとの子供を望まなかったのは、女として家に置いて出て来た子供に、どうしても筋を通したかったんじゃないかしら。どんなに離れて会えなくても、私の子供はあなただけだって」
紅子の思わぬ洞察に、善吉はハッとした。
「どうしても筋を通したかった、かぁ。そんなこと、考えたこともなかったよ。私の子供はあなただけだなんて。やっぱり、子供のいる人は考えることが違うんだねぇ」
善吉は汗を掻いた葉子のコップをぼんやり眺めると、過ぎ去った途方もない日々に思いを馳せた。
「いえね、私も事情はどうあれ、子供を置いて家を出た人間でしょう。だから、奥さんの気持ち、全部が全部ではないけれど、何となく分かるような気がするんですよ」
コップに残ったビールを紅子は一気に飲み干した。
「こんな母親でも、娘にだけは何があっても私は筋を通したかったし、義理も立てたかった。ただの自己満足かもしれないけど。でも、私はそうしたかったのよね···」
紅子は下唇を噛み、感情の昂ぶりに乱れた心を悟られまいと善吉に背を向けた。
「再婚まではいいと思うのよ。でも、子供はさすがに持っちゃいけないと思うわ。だって、理由は何であれ、愛する我が子を置いて家を出たんですもの。そんな女がよそでまた子供なんか作って、置いて来た子供のことを忘れて、一丁前な母親面してその子のこと可愛がったりしちゃいけないのよ」
善吉に背を向けたまま、紅子は割烹着のポケットからちり紙を取り出すと、遠慮気味に鼻をかんだ。
「私、今はご覧のとおり独りですけど、これでも三十代の頃はこんな私でも結婚したいって言ってくれた人があって、プロポーズされたこともあったんですよ」
「ほぉ、それで?」
「相手は子供を望んでいたから、私が産めない理由を話すと手のひらを返したように意図も簡単に『別れてくれ』って言って来ましたけどね」
「へぇ、そんなものかねぇ、男ってのは」
「そんなものよ。善さんみたいな男の人は珍しいわよ。世の中の大概の男は、ううん、違う。女もそうね。みんな自分勝手で我儘だもの。善さんみたいな人と一緒になれて、人生の最期も看取ってもらえて、亡くなった奥さんは幸せね」
それでも、善吉は妻に先立たれた今、唯一の心残りはやはり子供を持たなかったことだった。
「女房と一緒になれたことは、本当に幸せだったと思っているんだよ。でもねぇ、紅子さん。この年になって男ひとりっていうのは、何とも侘びしいものですよ」
善吉の声が震えた。
「どこの女でもいいから、女房の言うとおり、よそで子供の一人や二人、作っておけば良かったかなぁ」
善吉が笑いながらぽつりと言った。
「まぁ、善さんたら。そんな気なんて更々ないくせに。奥さんを愛していたんでしょう。善さんは奥さんを裏切れなかったわよ、きっと。きっとそうに決まってるわ」
紅子は噛みしめるように呟いた。
話したいことをある程度話して、店に来て二時間ばかりが過ぎた十時少し前、善吉はもう少しと引き留める紅子の手をそっと払い礼を言うと、ほろ酔い加減で大きく手を振りながら店を後にした。
しばらく歩くと、善吉は灯りの点いていない真っ暗な家に帰って来た。まだ、この静まり返った漆黒の景色に善吉が慣れることはなかった。ドアを開けて家に入ると台所へ行き、手を洗い、冷蔵庫から麦茶を取り出しコップに注ぐと、窓を開け放し扇風機を点け、仏壇の前に座り込んだ。
「葉子。お前の娘はお前によく似て、本当に素敵な女性だったよ」
善吉は葉子の遺影に向かって、しんみりと話し始めた。
「顔も気性もお前にそっくりだったよ。お前の気持ちも察してくれていたぞ。お前と同じようなことを言っていたよ。そういうところはやっぱり、血を分けた母子なのかねぇ」
小料理屋の女将である岡﨑紅子は、善吉の妻の葉子が前夫との間に儲けた一人娘だった。
紅子が駅前で小料理屋を営んでいることを善吉が知ったのは、葉子が死んで間もなくのことだった。
紅子は三年前、長年勤めた保険会社を辞めて、念願だった小料理屋を母親の葉子が住む町で、そうとは知らずに始めていたのである。
葉子がその事実を知ったのは、昨年の写生会の帰りのことだった。
それは、本当に偶然のことだった。
中学時代には、その美貌から真っ先に結婚するだろうと言われていたにも関わらず、周囲の期待を裏切り、ずっと独身を通している親友の律子に、女一人でも気軽に入れるアットホームな小料理屋があるのだと誘われて、ふらりと入ったのがきっかけだった。
席に着き、おしぼりが出された時、葉子は紅子の指先に目をやった。人差し指の第一関節と第二関節の間に、小さなほくろが二つ並んでいた。ハッとした葉子は、カウンターに無防備に乗せていた手を咄嗟に引っ込めようとした。その時、隣に座っていた律子が二人のほくろを見逃さなかった。
二人の手を勢いよく掴むと、カウンターに並べてまじまじと眺めて言った。
「あら、二人共、左右違うけど同じところに仲良くほくろがあるのね。紅子さんは右手、葉子は左手。こう見ると、あら、何だか顔つきも似てるんじゃない?」
葉子の顔が一瞬引き攣ったが、次の瞬間、
「あら、本当だ。これも何かのご縁かしら。葉子さんておっしゃいましたわね。ぜひ、これからもどうぞご贔屓にして下さいな」
紅子は屈託なく笑った。
確信はなかったが、名前も紅子、手のほくろも同じところにある。
葉子の心にさざ波が立った。
居心地の悪い紅子の店で小一時間程過ごした後、何を食べたのか訳も分からぬまま、紅子の笑顔に見送られて店を出た。
律子と別れて家に帰る間、葉子の頭の中で幼い頃の紅子の顔が止めどもなく浮かんでは消え、消えては浮かんだ。
「もしかしたら、いや、まさか。一度、きちんと調べてもらった方がいいかしら···」
一瞬、頭を過ったが、母親だと名乗れる筈もないのに、今更調べて白黒つけたところで何になるのかと思い直した。
しばらくすると、家が見えた。大分草臥れていたから、つい先日、善吉が業者に頼み壁を塗り替えたばかりである。自分の帰る場所は善吉と暮らしたこの家であり、善吉なのである。
玄関先で善吉が葉子の帰りを待ちきれず、葉子の突っかけサンダルを履いて、じっと立って待っていた。
「おかえり、葉子。みなさん相変わらず元気だったか?」
「えぇ、みんな相変わらず」
葉子の心に様々な思いが去来したが、ふと、善吉の足元に目をやった。
「あなたったら、また私のサンダル履いて。幅が広がってダメになっちゃうからあれ程履かないでって言ったじゃありませんか。何回言っても言うこと聞いてくれないんだから。まったくもう、あなたったら本当に困った人ね」
勘のいい善吉に悟られまいと、思わず小言が出た。
「違うよ、これはお前が中々帰って来ないから。その、たまたまだよ。それより、夕飯まだだったら何もないが、茶漬けくらいならあるぞ。食うか」
いつものように言い訳をしながら、善吉が葉子の顔を覗き込んだ。
「あなた」
善吉の顔を見た葉子は、ホッとして涙ぐんだ。
「どうしたんだ、一体。家へ帰るなり怒ったり泣いたりして。おかしな奴だな」
善吉にそっと肩を抱かれた時、やっぱり調べるのはよそうと葉子は思った。
それから一年後、葉子は死んだ。
自分の死後、しなければならない手続きを記したノートと一緒に、善吉に宛てた詫びの手紙がそっと、長年書き続けた家計簿に挟まれていた。
そこには、子供を頑ななまでに望まなかった本当の理由と、善吉に紅子の店を訪ねてほしい旨が書かれてあった。そして最後に、確証はないが、もしかしたら小料理屋の女将である岡﨑紅子は自分が置いて出て来た実の娘かもしれないと、心許ない弱々しい、いつもの葉子らしくない乱れた文字で書かれてあった。
あの日、善吉はそんな葉子の願いを叶えるべく、紅子の店を、そして紅子の顔を一目見ようと店の近くを歩いていたのだった。
酒は付き合い程度だった善吉が、ひとりで小料理屋の暖簾を潜るのは酷く勇気のいることだった。そんな時、紅子が善吉に盛大に水を掛けたのである。
それは、まるで葉子の悪戯だった。
それからというもの、善吉は週に二回、紅子の店に顔を出すようになった。
紅子がすっかり善吉を気に入り、独りじゃ何かと心配だからと気を揉んでくれるようになった。それはまるで、葉子から善吉への置き土産のようだった。
生前、葉子は紅子を実の娘だと固く信じ、結局、死ぬまで調べようとはしなかった。
再婚後、愛した男の子供を持たなかったことで娘に筋を通し、死ぬ程会いたかった娘に会わなかったことで、夫への義理を立てた葉子だった。
それから三年後、善吉が死んだ。
それは、いつもと何ひとつ変わらない、愉しい酒の席だった。
善吉は紅子の店のいつものカウンターで心筋梗塞に見舞われた。
急いで救急車を呼んだが間に合わなかった。胸を押さえ、額に脂汗を浮かべて苦しんだのは一瞬で、紅子の腕に抱かれながら息を引き取った。妻に先立たれ、子供を持つことのなかった男としては幸せな最期だった。
今は夫婦揃って、桜の木の下で静かに肩を並べて眠っている。
毎年、桜が満開になる頃、紅子はひとり墓地へとやって来て缶ビールの栓を開け、善吉夫婦に供えると、持って来たコップ酒を飲みながら気ままに時を過ごし、またあの店へと帰るのだった。
「ただいま」
「おかえりなさい」
紅子に頼まれて、店の準備をしていた華子が手を止めて、紅子の帰りを出迎えた。
「急にお願いしちゃって、済まなかったわね」
「いいのよ、今日は何も予定なかったし。ねぇ、それよりお母さん。お寺の桜、満開できれいだったでしょう?」
「えぇ、とっても。涙が出るくらいきれいだったわ」
「いいなぁ。今度、私も連れてってよ」
「勿論よ、だって」
「だって、何よ?」
言いかけたところで、引き戸がガラリと開いた。
「いらっしゃいまし!」
紅子と華子、二人の賑々しい声が店に響いた。
今日も紅子の店が開いた。
短編小説・路地裏
初めての文学賞への応募作品として書きましたが、やはり私は長編小説は書くのに向かない人間だと実感した次第です。