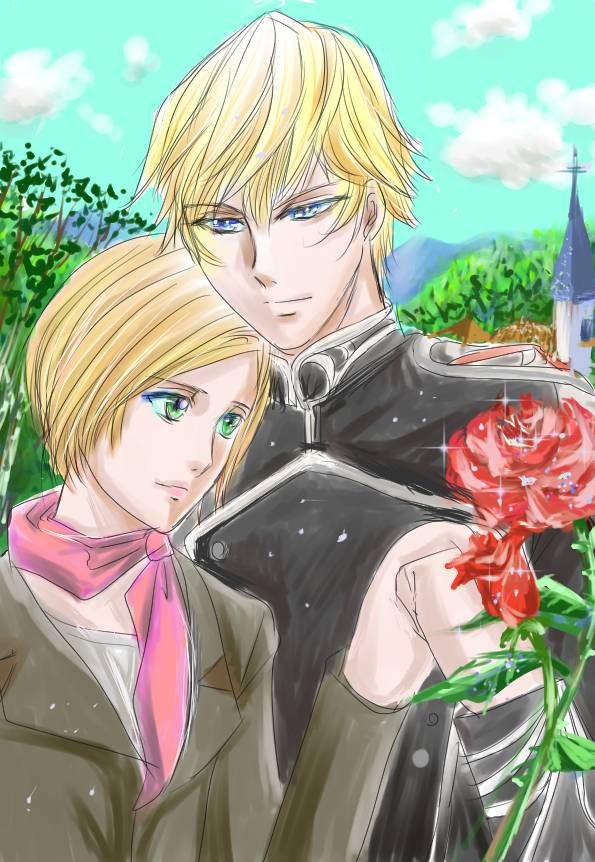
ある街角の物語
2024年作品
1.幼き日に
夕辺の鐘の音が厳かに夕刻の時を告げていた。
ここ帝国領内の惑星の一つ首都星オーディンは古い街である。中央市庁舎のある領域は真新しいビルが建てられているが、それ以外の街角は市民の古い邸宅が並び、それらの住居の街はずれには下町が続いている。いわゆる平民の居住区であり、そこにも階層が存在している。彼らミューゼル家の家はその市民の居住区とのぎりぎりの境にあり、側溝を隔ててキルヒアイスの家は市民の居住区であった。従っておおざっぱに物事を判断するキルヒアイスは、彼ら新しく越してきたミューゼル家も一般市民であると最初は考えていた。事実それほど住居に差があるわけではなかった。しかし内部事情は違っていたのである。
キルヒアイスは同じ校区であったので、隣家の少年ラインハルトとは登下校で一緒になった。市政はそこまで一般市民と平民の学区を区別していなかった。しかしすぐにその違いに彼は気づいた。ラインハルトはその姉アンネローゼとともに、非常に美しい金髪碧眼の外見をしていたが、彼らは身なりがみすぼらしく、靴なども履きつぶしたものを履いていた。しかも近所の奥さん連中の噂によると、父親は少しも働かずに酒ばかり飲んでいて、生活保護を受けているという話だった。そして彼らの家庭には母親はいなかった。
それでもキルヒアイスは、学校での平民いじめに敢然と立ち向かうラインハルトの心意気やよしと思い、彼らの友達になろうと思ったのである。特に姉のアンネローゼはほほ笑んだ姿が教会の天使の座像のように見えて、また彼女のおっとりした態度が非常に好ましく思えた。従って自分はラインハルトほど腕力に自信があるわけではなかったが、望まれれば彼女の円卓の騎士になろうと考えたのである。
アンネローゼはミューゼル家の家事を一手に引き受けていて、年齢のわりに非常に苦労していた。彼女は学校を休みがちで、いわゆるヤングケアラーであった。しかしおとなしい少女であったから、その境遇に甘んじているようであった。彼女は学校を休んだ代わりに家で少年たちに食べさせるパイを焼き、暖かなホットチョコレートを入れてくれた。少なくともキルヒアイスの目にはそう見えたのだが、実の兄弟であったラインハルトにはきっとそうではなかったのだろう。そして学校は休むのだが、毎週金曜日にアンネローゼは近くの礼儀作法を教える塾に通わされていた。これは父親の提案であった。彼は一人娘の容貌が人並みよりも優れていることを熟知しており、いずれどこぞの貴族の館に売り込むことができようと考えていた。そのため学校に行くよりもそういう貴族の室礼を身につける方が先ということで、自然元から備わった性質の上に、ますます高貴さに磨きがかかった。キルヒアイスがその魂を奪われたのもその所以であったのである。
さてその魔の金曜日だが、父と残されたラインハルトは、ひとりで家から下町の坂道の方に下って、そこの食堂で夕飯を食べることにしていた。家で父親に夕飯を作ってもらうということは絶望的であり、また自分で作れるほどの知識が年若い彼にはまだなかった。彼はキルヒアイスの家にお邪魔させてもらい、食べ物を恵んでもらうということを恥だと考えていた。キルヒアイスが聞いたら、なぜ家に来ないのかと言ったであろう。だがラインハルトはそのような考えの少年であった。
安食堂は二階建ての地球のハーフ・ティンバー様式の古い建物で、下町に住む貧しい者たちが利用していた。雑多な人種が入れ替わり席に立ち座る中で、ラインハルトは定食を注文した。食堂には給仕の者が数名いたが、幾人かはラインハルトと同じぐらいの少年少女であった。おそらく彼らは戦災孤児であり、ひっきりなしに客から来る注文を、忙しそうにさばいていた。その一人が後年ヒルデガードと呼ばれる少女であった。姉と同じような金髪をしているので、ラインハルトの人目を引いた。しかし彼女の髪は少しくすんだ暗い色合いであった。ただそれだけで商品価値が下がると父親が言っていたのを、ラインハルトは思い出した。
今ラインハルトの隣のテーブルに、壮年の男たちがどやどやと座りだした。見たところすでに酒に酔っていた。彼らはヒルダつまりヒルデガードに前菜を何皿か注文し、そのあと盛んにジョッキを打ち鳴らして乾杯した。宇宙に出る景気祝いだと言った。志願兵たちだろうとラインハルトは思った。帝国は恒常的に前線の兵を募集しており、派遣軍は領土の先で同盟との小競り合いを常に繰り返していた。それは命と引き換えに博打で儲けるようなものであった。しかしそのような傭兵がどこの街にでも存在したのだった。ラインハルトの耳に、彼らの会話が聞くとはなしに自然耳に入った。
「…それでよ、今度は船旅が長いじゃねえか。そんなに敵さんは多くはねえみたいだがよ、女におまえさんの髪の毛くれねぇかって言ったわけ。」
「で、その女はあっさりくれたのか?まさか下の毛じゃねえだろうなあ。」
「ええ?そりゃ弾よけならそっちの方が霊験あらたかってなもんだけどよぉ、なんせ会ってまだそんなにだったからなあ。」
「けっ、おまえさんにそんなもんくれる女がいるもんかよ。」
「なーに言ってんだ、いるぞぉ。ほらこうして持ってるぞー。」
「何人いやがんだよ、ばぁーか。」
会話は年若いラインハルトの耳を覆いたくなるものであったが、彼は興味深くその様子を観察した。酔っ払いは首にかけた紐の先につけた金具を取り出そうとしていた。どうやら安物のロケットペンダントであるようだった。これ見ろこれ、と酔っ払いは隣の男に言い、その中に一房の金色の髪の毛が収められているのがラインハルトの目に入った。なるほどとラインハルトは思った。戦場の弾除けでそういうことをするという古い伝承を彼は聴くとはなしに文献で見て知っていた。しかし実際に目にするのは初めてだった。
やがてラインハルトは食事を済ませたので勘定を支払い外に出ようとした。隣の席の男たちも席を立とうとしていた。ヒルダがお盆を持ちながら、男たちから勘定を受け取っている。と、彼女が困った顔をした。蚊の鳴くような声で彼女はつぶやいた。
「少し足りません…。」
「あ?なんだ?聞こえんなー。」
男たちはそのまま出ようとした。ヒルダは叫んだ。
「ま、待ってください!お金払ってください!」
「うるせぇ!」
ヒルダは男の一人から殴られて床に倒れた。キャーという客の女性たちの声があがった。と、ラインハルトは片手で手の中の銅銭を器用にはじいた。ヒルダの目の前に銅銭が転がってきた。ヒルダは目を見張った。
「あ、お金…。」
男たちはそれ見ろ、と顎をあげた。
「ちゃんと受け取れようー。」
男たちはそう言うと、げらげら笑いながら店を後にした。
ヒルダは立ち上がり、べそをかきながら銅銭を拾い集めた。ラインハルトが横から言った。
「それで足りる?」
ヒルダはびくっとなった。無言でラインハルトに素早く頭を下げると、お盆を抱えて店の奥に走り去った。店の中は以前の喧噪に戻っていた。彼らは店員のヒルダが殴られたことにしか興味はなかったのだった。
その次の週もラインハルトはその店に来たが、その時はヒルダの姿は見えなかった。彼はまさか額面が足りず店をやめさせられたのだろうかと思って少し心配した。学校での学業の上達事項の片隅に、小さくその記憶は残された。しかしその次に来た時、食事のプレートの片隅に季節の野花が一輪ちぎられて置いてあるのにラインハルトは気づいた。彼は店内にいるはずのヒルダの姿を探した。いた。彼が顔をあげて合図すると、ヒルダは恥ずかしそうに首を縦に振ってそのまま給仕に戻って行った。
そんなようなプレート皿が何皿か続いて、ラインハルトはヒルダと話をするようになっていた。店の横の路地で二人は座って話をした。
「私、親がいないんです。それで、この前助けてもらった時の次の週ぐらいに、いい施設を紹介できるからって、店の主人から面接に行かされたんです。」
「面接?また働くの?」
「そうみたいだけど、私にはよくわかりません…。なんでも皇帝陛下のしている立派なところらしいです。」
「それはよかったね。今のお店だと大変だからね。」
「でも本当は、学校ってところに一度行ってみたかったです…。学校は楽しいですよね。」
「う、うん、まあ。店でこきつかわれるよりはましかな。」
「あのお金返せなくてごめんなさい。私たちお給金て出てないんです。養われているので。雑草なんてちぎって渡しても、と思ったんですけど…何もしないでいるのは…。」
「うん、そんなの全然気にしなくていいよ。どうせ家にあっても親父が飲んじゃうんだ。」
「お父様?」
「そう。だめ親父でね。俺はああなっちゃいけないといつも思ってるんだ。」
とその時ラインハルトは立ち上がって、こっちに来てごらんとヒルダに言った。
「ほら、地面から音が聞こえてくるだろう?これは何の音かなあ。」
ラインハルトが指さした先は、マンホールの鉄板の下から響く音だった。少し鈴の音のような高く澄んだ水音がかすかに聞こえてくる。ちょうど仕組みは東洋の水琴窟のようなものであったが、彼らはそれを知る由もなかった。ヒルダは覗き込んで答えた。
「ほんとに音がしますね。どうしてなんだろう。お店にいても全然気がつかなかったわ。」
「あのあたりに高い山があるから、そこからきっと水が流れて来てるんだよ。雪解け水っていうのかな?」
「学校で教わるんですか?」
ヒルダはしゃがみこんで無心に音を聞いているようだった。ラインハルトは言った。
「施設にはいつ行くの?」
「たぶん来週ぐらいかな。そんな風に役人の人は言いました。」
「う、うん。あのさ…。名前聞いてなかったから。」
「ヒルダって呼ばれてます。ヒルデガードです。」
「僕はラインハルト・フォン…、ラインハルトって言うんだ。」
ラインハルトは本名の下級貴族だった長い名前を言いかけて呑み込んだ。貴族の名前を出したら、きっと今のヒルダの親しい態度が壊れてしまうような気がしたからだ。ヒルダはほほ笑んで言った。
「ラインハルト、いいお名前です。覚えておきます。」
「よくある名前だよ。僕も君の名前を覚えておくよ。」
ヒルダは立ち上がって礼をすると、店の裏の戸口の方に引っ込んで行った。ヒルダが消えると戸口からいつまで油を売っているんだい、とおかみさんのどなり声が聞こえてきた。ヒルダを役人に引き合わせた主人だろうかとラインハルトは思った。
と、その時路地の向こうに男が立って、こっちをにやにや見ていることにラインハルトは気づいた。
むっとして通り過ぎようとした時、男は声をかけてきた。山高帽をかぶったエージェント風の男性だった。男は言った。
「おっと、小皇帝、怒りなさんな。おまえさんにいいことを教えてやろう。」
「なんだおっさん。」
「うるわしい青春の一ページに泥を塗って悪いが、女の処女膜についてはご存じかな?その年ではまだ知らないか。」
「知ってたらどうなんだ。」
「それなら話は早い。来週ルドルフ大帝全宇宙戦勝記念式典が開催される。それは学校でも行事があるから知っているだろう?あの施設はその式典の一環の行事なんだなあ。」
「どういう意味だ?」
「ガキにはちゃんと説明しないとわかんねえか。それぐらい読み取れないようでは、先が思いやられるな。いくらスィーンで高得点を取れても、頭が悪いんじゃどうしようもない。ま、投げ銭で女を助けたのは立派だったよ。しかし今度はうまくいきそうもない。」
「おっさん俺のことを観察していたな。」
「まあな。将来が有望な姉君の弟ともなれば、どういうやつか観察はするさ。だが残念ながら俺は反帝国側でね。情報を売ってやるから、その通りにおまえが動けば俺は助かるってわけだ。」
「式典を邪魔したいのか。」
「端的に言えばそうだ。どうだ。利害が一致しそうか?」
「その情報はいくらだ?」
男は笑って半ピラのわら半紙を差し出した。
「かっこつけなさんな。ガキにはタダでくれてやる。そこに詳しい手順は書いてある。その通りにやってみるんだな。じゃあな。」
ラインハルトは紙を受け取ったが、けげんそうに尋ねた。
「おっさん、なんでだよ。」
「処女膜ぐらいだったらいいがな、殺される可能性があんだよ。そういう趣味だそうだ。」
ラインハルトが家に帰ると、父と姉がトランクを出して荷造りの準備をしていた。父はラインハルトを見るなり、大声で叫んだ。
「貴様どこへ行ってたんだ!塾の先生から今連絡が入ってな。アンネローゼが皇帝様に召されることになったのだ。お部屋付きの女官になるんだぞ。いやもう、たいした出世だ。やはり行儀見習いをさせていてよかった。わしが見込んだ通りじゃ。」
「親父…。」
ラインハルトは今聞いた話と瞬時に頭の中で照らし合わせて、その話が嘘だと思った。ラインハルトは大声で叫んだ。
「親父、姉ちゃんを売るなよ!そんなところへ連れて行くなよ!」
「なんだと。親に向かってその口のききようはなんじゃ。おまえは何を言っとる。」
ラインハルトは処女膜の名詞を出さずになんとか男から聞いた話を父親に説明した。しかし話を聞いて父親はさらに怒り狂った。
「なんだと。そんなやつの言う事がわしよりも信用ができるって言うのか?部屋からもう一歩も出るな。貴様はもうこうだ。皇帝陛下への不敬罪で捕まえられるよりはいいだろう。」
子供部屋にラインハルトは閉じ込められて、鍵をかけられてしまった。
ラインハルトの頭の中で、憤怒の感情が渦巻いていた。父親はだめだ。しかしキルヒアイスなら、と彼は考えた。今たよりになるのは彼だけだった。憤怒の感情を押さえて、男の書いた手順の紙を、ラインハルトは冷静に何枚も別の紙に書き写した。それは細かな文字で、まだ幼い彼には骨の折れる仕事だった。来週と男は言ったが、それよりも前に施設に入れられるかもしれない。その想定は否定できないと彼は考えた。そうなると時間はなかった。
翌日反省をしたなと父親に念を押されながらラインハルトは登校した。父の前ではもうその話はしないと決めていたので、彼は殊勝に父に従った。彼は出しなに姉にこっそりとあの紙の写しと手紙を渡した。たぶんやさしい姉は読んで心を傷つけると思ったが、致し方なかった。姉は自分と一緒になって皇帝のところに行くことを拒否してくれるだろうと思った。それならば仕事はひとつ減るはずだった。
学校で放課後ラインハルトはキルヒアイスにくだんの話を打ち明けてみた。彼はそんなはずは、と言いかけてラインハルトの真摯な瞳に言葉を失ったようだった。彼は言った。
「じゃあ、その謎の男の言った通りに、施設の前で待機していろってこと?中からみんなが出てくるのを待ってるの?」
「そうだ。俺たちにできるのはこの場合それしかないんだ。この図では警備兵がこれだけの数存在しているからな。俺たちには銃がない。しかし出て来たら速やかに作戦行動で偽装しなければならない。幸いなことにこの角に動物病院がある。」
「本気なの?君は皇帝がそんなことすると本気で思ってるの?」
ラインハルトはキルヒアイスの言葉に詰まった。確かに信頼できる確たる証拠は何もない。すべてはラインハルトの見聞きした情報だけで組み立てられた話だ。ラインハルトは静かな怒りに満ちた声で言った。
「たとえ騙されていたとしても、やるんだ。」
ラインハルトが学校から帰宅してみると、やはりまた学校を休んでいた姉アンネローゼの姿が見えなかった。父親は台所のテーブルで酒を飲んでいた。
「親父、姉さんは?」
「昼過ぎに黒塗りの高級ランドカーが来てな。それはすごかったぞ。赤い絨毯を娘の前から車の席まで引いたんじゃ。アンネローゼは侍従に手を引かれてなあ。これでわしも貴族に返り咲きじゃ。」
「親父…っ!」
ラインハルトは体を震わせ拳で父を殴ろうとしたが、父の酔いが回って目を閉じている顔を見るとその拳をおさめた。今はそんなことをしている場合ではないのだ。
外は激しい雨が降り出していた。ラインハルトはヒルダのいる食堂への道を走って行った。全力で走って五分ぐらいだ。間に合え間に合え、と彼は思った。もう行ってしまった後かもしれない。雨粒が顔に当たりびしょ濡れだった。やがて前方に大きな箱型のランドカーが止まっているのが見えてきた。子供たちが役人らしい人間の前で整列させられている。うつむいた子供たちの中に、ヒルダの顔があった。ラインハルトは一声叫んだ。
「ヒルダ!」
そして手の中の手紙を丸めた紙玉をヒルダ目掛けて全力で投げた。それには、施設の手薄になる曜日と時間帯、そして逃げ道の順路が書かれていた。ヒルダは声に驚いてラインハルトの方を見、そして投げつけられた紙玉をあわてて拾い上げた。しかしその背に役人たちの手が素早く回され、彼女はランドカーに乗せられた。雨降りの中ランドカーはラインハルトの目と鼻の先で発進して行った。
箱型ランドカーには窓には全部目隠しの網目がかけられていた。護送車そのものだった。中には中年の眼鏡をかけた女性官が座っていて、床に座らされた子供たちを見まわし、すぐにヒルダの手に握っている紙玉を見つけた。
「それ、出しなさい。」
官吏はヒルダに言った。ヒルダはおびえながら、しかしあることに気づいて、しぶしぶ彼女に紙を渡した。官吏は眼鏡を合わせながら紙を開いて言った。
「子供の字ね。」
ヒルダはつぶやいた。
「あの、それ、読めません…。」
「そうね、あなたたち未就学児童ね。おそらく読めないでしょう。こんなもの。」
子供たちは顔を見合わせ、おそるおそるうなずいた。ヒルダはおびえた声で言った。
「あのそれ、そのまま返してください…。大切な友達からの預かりものなんです…。」
女性官吏は口の端で笑って言った。
「返してさしあげますよ。こうしてね。」
と言うと彼女は紙を八つぐらいにびりびりと引き裂いた。紙は床に散らばった。子供たちの口から声にならない悲鳴が漏れた。彼女は言った。
「逃げようなんて思わないことね。あなたたち無価値な人間は、初めて皇帝陛下のお役に立てるのです。光栄に思いなさい。」
そう言うと、彼女はカーテンで仕切られた前の座席に移って行った。
ヒルダは気づかれないように紙の切れ端をかき集めて、服のポケットに入れた。彼女の横にいる少女が泣きそうな声で言った。
「どうするのさ?読めないんでしょそれ。」
「読めるわ。」
「え、読めるの?」
「しっ、静かに。声をたてないで。あいつは私たちが紙をおじゃんにしたと今考えてる。どこかについたら、手分けして元の紙の状態に戻すの。事はそれからよ。」
ヒルダは店での仕事の合間に、手に入る客の残した新聞や雑誌の切れ端で、こっそりと独学していたのである。そのためある程度までは文章を読むことができた。彼女がラインハルトに学校に行きたいと言っていたのは、そのためだったのだ。しかし今はどこに連れて行かれるかわからない車の中だった。ヒルダは外の様子に聴き耳をたてた。山道ではない、たぶんまだ市街地を走っている。そんなに遠くではない。やはり中央区に向かっているらしい。ヒルダの脳裏に新聞で見たサンスーシー王宮の外観が浮かんだ。あの近くだろうか。しかしヒルダはやはり少女だったので、ラインハルトのように式典行事と施設の存在を結び付けられずにいた。役に立てるってなんだろう、と彼女はぼんやりと考えた。
ラインハルトは翌日から学校を欠席した。教師はラインハルトの名を呼び、なんだ優等生だったのに欠席か、欠点一だな、と言って授業を始めた。キルヒアイスはラインハルトの空席を見つめて、不安そうな顔になった。それなので彼は家に行ってみることにした。
ラインハルトの家に行くと、彼は母屋にはおらず物置で作業をしていた。キルヒアイスが尋ねると、ペットボトルで犬に撒く薬剤の噴射機を作っているんだと言った。
「何の薬剤?」
とキルヒアイスが尋ねると、ラインハルトは調教師が使う興奮剤だよ、ネットで調べたんだと答えた。キルヒアイスは半ばあきれて言った。
「それ、買ったの?もしかして?」
「当たり前だろ。姉さんたちを助けなきゃ。僕は本気だからね。君、手伝ってくれるよね。」
と真剣な顔で言った。キルヒアイスもアンネローゼが連れて行かれたことはショックだったので、ラインハルトに同意はするものの、警備兵がうようよといる場所に、ぺットボトル銃ひとつで立ち向かうのはあまりにも無謀に思えた。しかし彼はアンネローゼへの騎士道精神を思い出して、気持ちを奮い立たせた。
「うん、僕がんばるよ。二人で一緒に君の姉さんを救おう。」
二人は固く握手を交わした。
ヒルダたちはサンスーシー広場から少し離れた施設の建物に移された。監獄の様相であった。牢屋の中でヒルダたちは手分けして、ジグゾーパズルの紙をつなぎ合わせた。それによると、大広間の奥の方に踏み抜くと開く通路があり、そこを伝って外に出られるらしかった。古い水道管の工事跡だったようだ。そしてその大広間の隣に別室があり、そこにも犠牲者が待機していると書かれていた。
「私たち以外にも誰かいるの?」
「そうみたいね。その人も救ってくれと書いてあるんでしょ、ヒルダ。」
「でもそこにまで行くと、逃げられなくない?一気にこの通路から全員で走らないと。」
「そうねぇ。」
と彼女たちは顔を寄せて相談した。
「でもこのクィーンって書かれてる意味はなんだろ?このクィーンさんて厄介よねぇ。」
ヒルダはその頃になると、頭の中でいろいろな意味がつながってきていた。手紙は何枚か丸められていて、そのうちのひとつは明らかにラインハルトから自分宛であったので、彼女は仲間の手から素早く取り上げて隠した。それにはこう書かれていた。
「このクィーンという記号は、僕が書いたのではありません。ある人間から寄せられた情報です。僕にはその意味はわかりませんが、おそらくそれは僕の姉さんです。僕とよく似た顔をしています。とても難しいと思いますが、姉さんも外に連れ出してください。頼みます。」
ヒルダはため息をついた。やはりあの時の検査だ、と彼女は思った。股を開いて検査台に登らされた。貴族たちが余興でそういうことをするという事を、彼女は酒場のようなあの食堂で耳にしたことがあった。このクィーンがその姉という人のことなら、自分たちはその添え物ということらしい。むろん彼女は傷ついたのだが、前向きになろうと思った。彼のお姉さんならきっと美しい人だろう。救ってあげなければならない。さすがにこの頃になると彼女も考えたくなかったが、あのルドルフ大帝の式典の日の夜だろうと考えるようになった。ラインハルトは助けに来てくれるだろうか。彼女は膝を抱えじっと目を閉じ考えた。
式典当日になった。大々的なパレードが広場では行われているらしかった。その音響は施設まで響いてきた。ヒルダたちはそれまで粗末な囚人服のようなものを着せられていたが、この日は白いドレスに着替えさせられ大広間に通された。仲間たちは少し浮足だった様子になったが、ヒルダは浮かない顔だった。彼女は別室までの距離を頭の中で計算していた。あの扉だわ、と彼女は思った。あそこまで走って行って連れ出す。自分にできるだろうか。もし扉が開かなかったら?中には誰もいず私だけが逃げられなくなったら?いえ、そんなこと、とヒルダはいろいろな考えが頭に浮かびかぶりを振った。
夜になった。大広間は灯りが暗くされていた。薄闇の向こうに、回廊の廊下から仮面をつけた男らが続々と入場してくるのが見えた。やはりそうだった、とヒルダは思った。早く逃げようと思ったが、問題の通路はあの別室の扉とは逆方向なのだ。と、その時だった。外から警備兵のぴりぴりという警笛の音がした。仮面の男たちがそちらに顔を向けた時、窓から蹴破ってラインハルトとキルヒアイスが現れた。どうやら施設横にあった鐘楼からロープをかけてはずみで入ったらしかった。そして窓からはたくさんの犬たちが吠えながら入り込んできた。犬たちは興奮して人々を追いかけまわした。ヒルダは叫んだ。
「ラインハルト!来てくれたのね!」
「君は早く逃げろ!通路へ!」
「私はお姉さまを!」
ヒルダは走って行って扉を激しく叩いた。ラインハルトたちはこの広間に入ったばかりだから、勝手がわからないに違いないと思ったのだった。ヒルダが叩くと中からだあれという幼い声がして、扉がゆっくりと開いた。
「姉さん、早く!」
ラインハルトが後ろから叫んでいた。しかしアンネローゼは豪勢な衣装を着てつっ立ったままだった。まるで大きな西洋人形のようだった。そしてヒルダはこの瞬間が生涯忘れられなくなった。というのも、アンネローゼは薄く笑い、扉を自分から内から閉めたのだった。ラインハルトはその時絶望した顔つきになった。彼はその場で絶叫していた。
「姉さん!なぜ逃げない!姉さん!」
むろん横にいたキルヒアイスも非常に驚いた。しかし彼はアンネローゼのそうした姿が彼女本来のものではないかという気持ちがしたので、そっとラインハルトから横を向いた。そしてラインハルトにこう言った。
「彼女は皇帝陛下のものになったんだ。あきらめて行こう。」
ヒルダの仲間たちが大方逃げた後で、ラインハルトとヒルダ、キルヒアイスは通路を無言でくだって行った。貴族たちは追ってはこなかった。もともと皇帝の余興で呼ばれたのであり、彼らにはちょっとした火遊びだったのだ。興がそがれた今、しらけたというわけで自然解散ということになったのだった。
外に出ると、パレードが終わって紙吹雪が散っている夜のサンスーシー広場にあの謎の男が立っていた。
「よう。がんばったな。」
ラインハルトは言った。
「おまえこの結末わかっていただろ。」
「うん、そうだな。俺は彼女の行儀見習いの様子も観察していたからなあ。彼女は乗り気だったよ。クィーンになることにな。」
ラインハルトは一点を見つめながらつぶやいた。
「…宇宙を…宇宙を手に入れれば、姉さんを取り戻せるか?」
「皇帝は高齢だからな。そのうち死ぬさ。」
そう言って男はタバコに火をつけた。ラインハルトは苦渋に満ちた声で言った。
「俺が言いたいのはそういうことじゃない…あいつの考え違いを糺したいだけなんだ…。」
「そりゃおそらく無理だなあ。ありゃああいう女さ。おまえさんには気の毒だが。」
キルヒアイスはおずおずと横から言った。
「あのさ、全然わかんないんだけど…。」
「おまえにもそのうちわかるさ。いやでもな。こいつはちょっとませてるから早くから気づいてしまったのさ。」
ラインハルトは言った。
「あんたを見込んで頼みがある。この子のことなんだけど。」
と、白いドレスが破れたヒルダを前にやった。
男は笑って言った。
「ああ。しかるべきところに保護してやる。連絡はしてやる。時々な。あいつらみたいなことはしないよ俺は。」
2.間奏曲
ヒルダは謎の男に保護されたのだが、彼女が当初危惧したようなことは起こらなかった。しかし最後まで男は本名を一切名乗らず、すべて一人称は俺であった。彼はヒルダを列車でオーディンの地方都市の村の施設に連れて行き、そこの所長のおばさんに彼女を紹介した。ごく普通の公設の孤児院のひとつであった。彼はそこでヒルダの戸籍を作り、入居者証明書を書き、それでは俺はこれでと帽子に手をやりいなくなってしまった。
ヒルダは途方にくれた。ラインハルトたちとずっと一緒にいれるわけではないと思っていたが、生活の心配はなさそうという点以外は心細いものであった。彼女は所長の人に、私の養育費は大丈夫なのですか、とおそるおそる尋ねてみた。すると所長は国から一応補償は出ますからね、と事務的に答えた。彼女にはその仕組みはわからなかった。そしてたぶん、あのお店で働いていたのは、騙されていたということなのかなとぼんやりと考えた。
孤児院では粗末ではあるが、以前よりは人間らしい扱いで、ヒルダは久しぶりにふかふかした肌触りのベッドで眠ることができた。しかし心身が安らいだせいだろうか、彼女は夜に起き上がる夢遊症や夜驚症の症状が出始めるようになった。心配した所長やその職員が、彼女を医療センターに連れて行った。
「心的外傷ストレスですね。何か非常にショックな出来事が過去にあったせいでしょう。」
と、眼鏡の医者は言い、これを飲むと精神が安らぎますよと言って、精神薬をいくつか処方してくれた。しかしそれを飲み続けていくと、ヒルダはオーディンであった出来事の細部が記憶から失われるようになった。彼女はラインハルトの顔はおぼろげに思い出すのだが、名前はどうだったか、だんだんわからなくなっていった。ただひとつ、扉の向こうに大きな木製の人形が立っていて、こちらを笑って眺めている幻影だけが頭に浮かぶようになった。それはとても恐ろしいのだが、それが何だか彼女にはまったくわからなくなっていった。
ラインハルトとキルヒアイスは元通り学校に登校し、彼らは幼年学校を無事卒業した。しかしラインハルトは進学先に士官学校を選んだ。なぜ普通校や職業訓練校を選ばないのか、キルヒアイスは彼に尋ねてみた。
「姉さんからの仕送りを無駄にしたくないからね。僕は国を守る兵士になりたいんだ。」
と、ラインハルトは言い、君も一緒だといいけどと言った。キルヒアイスは内心迷った。士官学校の倍率は高いので有名だった。しかしアンネローゼのいる王宮に近づけるのではないかと彼は考えた。彼女ともう一度会って話をしてみたいと彼は思った。もちろん連れ出すことは自分には無理だけど、彼女の本心を知りたく思った。それにはラインハルトがあのサンスーシー広場で言ったセリフが彼には疑問であるからだった。あいつの考え違いを糺したいとはいったいどういう意味か?アンネローゼは皇帝に連れ去られた気の毒な姫ではないか。ラインハルトの言いざまは、何か売女であるような言い草だった。それでキルヒアイスは、ラインハルトと同じ学校に行くことに決めた。つまり無理をしたのだが、それだけこの兄弟の行く末が彼には気になるのだった。
キルヒアイスが夕飯時にそのことを家族に話すと、おまえ軍人になるつもりなのかい、と母親は心配そうに言ったが、父親はうなずいてそれもよかろうと言った。キルヒアイスはほっと胸をなでおろした。両親に反対されることだけが心配だったのだった。
ラインハルトの家では老女の住み込みの家政婦が雇われて家事をするようになっていた。父親はアンネローゼからの仕送りを、以前のように飲み代に使わず、大切に取っておくようになった。つまり家計は上向いたのである。それも貴族の仲間入りをするのなら、それなりの生活をしていなければだめだと言い出したせいだった。それらの出来事を、ラインハルトは無風状態で感じているようだった。彼の生涯の中での短い無風期間であると言っていい。父親は息子が以前にも増して学業などに専念するようになったので、うれしそうであった。軍部に行くことも、当然であるかのように父は受け取った。
入学試験に合格し、士官学校生になった二人は、成績も優秀で競い合うように学年トップクラスであった。そのような事は後年の彼らの業績からすぐにわかることなので、ここでは省略する。キルヒアイスがその頃気づいた事のひとつに、彼らは国からの奨学金を優秀であるが故に受け取っていたのだが、ラインハルトが月に一度郵便局で振り込みを行っていたことであった。昼休み彼は必ずそこに向かうのである。キルヒアイスが尋ねると、ラインハルトはむっとした顔になったが、すぐにいつもの友達らしい顔つきに戻り、たいしたことではない、姉からの送金を家に振り分けている、と言った。
「それは御姉さんがあの、皇帝陛下のおそば付だからかな?」
と、キルヒアイスが少し言いにくそうに尋ねると、ラインハルトは唇の端で少し笑ってそうだよ、と言った。
それからしばらくして、学年最後の卒業記念パーティがあり、男子ばかりでむさくるしい会合の後、彼らはグラスを片手に夜のバルコニーに出て話をした。もう彼らは子供時代の様相ではなかった。
「ラインハルト、星を見てるのか?」
「ああ。次の赴任先はカプチェランカ だからな。あそこは極寒の星らしい。艦装備のワルキューレでの出番はないだろうが、監督官の仕事は前任者との軋轢が生じやすい。軍上層部に目をつけられないようにしなければな。」
キルヒアイスはもう先のことを考えているのかと思い、話を合わせた。
「そうだな。同じ赴任先でよかった。今まで通り、よろしく頼むよ。」
「ああ。こちらこそだ。」
「俺は故郷にまた電子通信の手紙を書いたんだが。今度は少し遠いところの星に行くって。君はどうかな?」
ラインハルトはキルヒアイスの問いに即答はしなかった。少し間を置いてから彼は答えた。
「…宇宙が故郷と言ったらおかしいか?」
「え。」
「俺はそんなつもりでいる。そしていつか宇宙を手に入れたいと思っている。」
キルヒアイスはラインハルトの言葉に少しどきりとした。眉根を寄せて彼は尋ねた。
「…どういう意味だ?」
そこでラインハルトは少し破顔して、言った。
「子供の頃、おまえと寝台で子供向けの絵本を見たことがあった。中の主人公が、宇宙を手に入れてみんなを幸せにするんだと言っているのが書いてあった。つまり、そういうことさ。」
「あ、ああ…そういう意味か。」
そこでラインハルトはバルコニーの向こうに立つルドルフ大帝の石像を顎で指し、こう言った。
「あの男も最初はそうだったんだろう。初心貫徹とはいかないものだ。階層社会がある限り…いや人間の渦がある限り、それは不可能なことかもしれん。おまえもそう思うだろう?」
キルヒアイスは少し考えてから答えた。
「で、君はそれをやりたいわけだ。」
ラインハルトは笑って言った。
「いつものようにおまえに手伝ってくれとは言わん。俺一人の世迷言さ。忘れてくれ。」
そう言ってキルヒアイスの肩に手をやると、ラインハルトはバルコニーから室内へと入って行った。残されたキルヒアイスは夜風に当たっていたが、何か胸騒ぎを感じてしばらく無言で考えていた。
赴任先では彼らはラインハルトの予言通りワルキューレを出動させることなく、上官の男を職務怠慢で上層部に奏上し、それはなぜか通ったので首都星オーディンに無事帰還することができた。そのような出張赴任先の任務がいくつか続き、ワルキューレの操縦による敵の掃討もまずまずのものだったので、王宮内で彼らに艦隊の指揮をとらせてみてはどうかという意見になった。つまり軍作戦本部内に移動となったのである。むろんそれは彼らの士官学校時代の論文の論理の組み立て方や、科学知識の出来からによるものだった。ただある老査問官は、ラインハルトの書いた論文を読み、「論理の飛躍が見られる」と指摘した。しかし補佐官たちは、それはささいな指摘であり、特に問題とする部分ではないと、彼らの昇進を推奨した。その頃になると、王宮内の口さがない連中が、ラインハルトたちがそのような昇進を年若いのに早く遂げるのは、彼の姉アンネローゼの皇帝陛下への口ききのせいであると噂した。その噂はもちろん軍部にも筒抜けで、ラインハルトの友のキルヒアイスも居心地の悪い瞬間があった。だが当のラインハルトはまったく意に介した様子を見せなかった。彼は堂々とふるまい、キルヒアイスにいつかの夜言ったような信条に基づいて行動しているかのようだった。そしてまた、彼の行動を邪魔できる者も当面は現れなかったのである。
後にアスターテ会戦と呼ばれる戦争が彼らの頭脳戦での初陣であったが、その少し前に彼らは王宮に住むアンネローゼから、彼女のサロンに招待されていた。
アンネローゼは水晶宮と呼ばれる別邸に居を構えていた。なぜそう呼ばれるかというと、皇帝の趣味である薔薇の栽培をする温室があり、その温室のガラスドームの形状からそう呼ばれていたのである。むろん彼女はおそば付の女性としては、最高位に列せられる存在であった。今彼ら二人はアンネローゼから郵送された薔薇の紋章の電子コード入りの招待状を片手に、ドームの廊下を歩いている。
と、ラインハルトがなんとはなしにつぶやいた。
「…あの時もこんな防弾強化ガラスなら、助けることはできなかったな…。」
「は?」
「いや、なんでもない。」
キルヒアイスは前を行く友人の歩幅がいつになく大きいのは、きっと姉のアンネローゼに早く会いたいからだろうと思った。
アンネローゼはキルヒアイスの予想に反して、セレブ風のふつうのカーディガン姿で面会した。あの最後に見た時の豪勢なクリノリンの衣装ドレス姿ではなかった。キルヒアイスは軽く失望すると同時に、やはりあの時皇帝陛下と謁見行為をしていたのだなと思った。しかし彼女は長い金髪のロングヘアを脇にまとめて軽くカールさせており、どこから見ても現代風な妙齢の淑女に見えた。
「姉上、お久しぶりです。お元気でいられましたか。」
と、テーブルについたラインハルトが言うと、
「とても懐かしいです。実家で暮らしていた時以来でしたね。その後音信不通で心配しおりました。お金は送金していたのですが、お父様たちはお元気ですか?」
と、アンネローゼは言い
「あなたたちの好きだった桃のゼリーパイを焼きました。」
と、給仕の者に合図して、ケーキの皿をテーブルに持って来させた。
「姉上にはまだまだ私たちは子供なのですね。しかしいただかせていただきましょう。父上はまだまだ元気ですよ。おかげ様で。」
ラインハルトが軽い笑い声を立てた。と、キルヒアイスはアンネローゼのケーキを切るナイフを持つ手が、細かく震えているのに気づいた。何か非常におびえている様子だった。
「大丈夫ですか?ケーキは僕が切りましょうか。」
と、キルヒアイスが後ろから軽く手を添えると、アンネローゼはびくっとなり、しかし頬を赤らめて、はしたなくてすみません、と消え入るような声で謝った。ラインハルトはその様子を、ソファにもたれてじっと観察していた。
「どうぞ、お召し上がりください。」
と、アンネローゼは皿を分けて、彼女もソファに座った。
ラインハルトとキルヒアイスは紅茶とケーキをよばれた後、しばし彼女と談笑した。とりとめのない世間話、皇帝のことはアンネローゼは陛下と呼んでいた。陛下の好きな薔薇の品種はあれなのですよ、私もその薔薇を育てるのには苦労しました、などなどのこと。と、アンネローゼが言った。
「ラインハルトはどんな色の薔薇がお好きですか?」
「そうですね。血の色の赤い薔薇が好きかな。では、そろそろお時間ですので。お暇させていただきます。」
「あ、あの…。」
「何か?」
「あの時のことを怒ってらっしゃいますか。私も若くて、あまり何もよく知らなくて…。」
「ええ、きっとそうですよね。もう過ぎたことです。今はあなたのお力添えで、皇帝陛下のお役に立てることができて、本当に何よりですよ。では。」
と、ラインハルトが席を立ったので、キルヒアイスもあわてて従った。
帰りの廊下で、歩きながらラインハルトは言った。
「おまえももう少しあの女と話をした方がよかったぞ。出世のためにもな。」
「おい、それはないだろ。お姉さんだぞ。」
「おまえは物忘れが激しいんだな。」
とラインハルトは冷笑すると、先に行ってしまった。キルヒアイスはアンネローゼの邸宅の方に一歩戻ろうとしたが、すぐに思い直してラインハルトの後を追った。ガラスの廊下だ、とキルヒアイスは歩きながら思った。あまりにも危うい均衡で歩く、友。
アスターテ会戦は彼らにとって初戦であったが、帝国軍は同盟軍に対して数の上で優勢であり、作戦司令官としてのお手並み拝見ということで、彼らは上級監督官の監視のもと、旗艦グリュンヒルデで戦闘指揮を執った。それはつまりほとんどの確率で負けることはないと判断されたためであった。
はじめ帝国軍と同盟軍は正面衝突の布陣であった。数の上で優勢なので帝国側が圧倒的勝利に見えたが、同盟軍の遅れて到着する第六艦隊に、ヤン准将が搭乗していた。彼は第六艦隊と早い地点で合流し、数をそろえて帝国軍に側面から攻撃するよう進言した。帝国軍はその時ラインハルトの指揮により、急進型の紡錘体形を取っていたので、側面の薄い部分を攻撃され艦列を分断されることになった。ラインハルトは動揺するキルヒアイスを叱咤し、
「潜航して鶴翼の体形を取れ!早く各艦の深度を下げろ!」
と言い、艦隊の速度と艦の固定ポイントを次々と読み上げ入力したが間に合わなかった。
「同盟第六艦隊、後退して行きます!」
乗務員が叫ぶ中、ヤンの艦隊は集中砲火の攻撃を終え、しずしずと後退した。彼らの逃げ足は速かったが、それは艦首にすでに攻撃を受け、爆発で司令官が死亡してヤンが指揮を執らざるを得なくなっていたからだった。しかしその戦法がヤンの生涯の信条であった。
ラインハルトは常勝の天才ではなかった。むろん彼らは帰還後軍法会議にかけられたが、すぐに放免された。ラインハルトがその時素早くコンピューターに入力した数値が、AIにより勝率が非常に高いものだったと判断されたためである。この時の主な敗因は艦隊が随時潜航することを阻む、浮遊する宇宙物質の存在であった。
3.邂逅
ヒルダは孤児院からしばらくの間は幼年学校に通っていたが、卒業のある時教師から呼び出されて、あなたには特別に寄付金の納入があるから、このまま勉学を続けてはどうか、あなたの意向を聞きたいと言われた。それはヒルダには願ってもないことであり、自分でも図書室で読んだ薬草学に興味を持っていたので、薬学の勉強をしたいですと答えた。できれば大学に行きたいのですが、とおそるおそる申し出ると、それはあなた次第ですねと言われ、彼女は無事試験をパスして上の学校に進んだ。
薬草学に興味を持ったのは、ヒルダはもともと草花が好きであり、その中でも人体に有用な植物に興味が湧いた。それと言うのも学校の授業で銀河征服史を学び、それの半分が貴族階級の間での毒殺の歴史であるということがわかり、そうした痛ましい悲劇が起こることに胸を痛めたからだ。むろん貴族をどうこうという気持ちからではなかった。人としてあるまじきふるまいだと思ったからである。
ヒルダはいずこからか送られてくる寄付金で勉学を続け、大学を卒業し、孤児院をあとにして独り立ちすることとなった。その頃になると子供の頃見続けていた、あの扉に向こうに立つ木製の人形の影は薄くなった。ヒルダは自分に自信がついたせいだと思った。木製の人形は以前よりも背が高くなり、笑顔ではなくなった。そしてめったに夢には出てこなくなった。そしてその頃にはヒルダはもう精神薬を飲まずに眠れるようになっていた。
ヒルダは首都オーディンでしばらくの間は医療事務に携わっていた。それはある総合病院だったが、軍関係のものだった。そこの夜間診療にある時、ハインリッヒ・フォン・キュンメルが運び込まれてきた。全身痙攣で喘息の発作を起こしていた。ヒルダは喘息を押さえる薬剤投与を指示し、つきっきりで見守って看病した。それはその日交代看護婦がたまたま休んでいたからだが、キュンメルの目にはそう映らなかったようだ。目を開けたキュンメルはそばに立つ白衣のヒルダを見て、あああなたは私の天使様ですねとうつろな瞳で言い、激しくせき込みながら、私は男爵の爵位を持つ者ですから、あなたのような方を妻に迎えたいと言い出したのだった。
この病弱なキュンメルの願いは当然ながら周囲の者らに却下された。しかしキュンメルの強硬な願いでヒルダの身柄はキュンメルの館に移され、彼を看病することになり、やがてヒルダに爵位を与えてやってほしいと彼は言い出したのだった。
そのような事は到底無理だと周囲は諭したが、あきらめきれないキュンメルは、親戚のマリーンドルフ伯の叔父に頼み、彼女は優秀な女性だから養女にしてやってくれないかと頼んだ。マリーンドルフ伯ははじめそのような何処の氏素性かわからぬ女を、と言ったのだが、実際キュンメルへの看病の様子を見ていると、非常にてきぱきと処理し、また受け答えも優しいもので、気に入ることとなった。
彼は戦争で子供を何年か前に亡くしていたので、老後の愉しみと自分の来たるべき日の看取りのために、ヒルダを養女に迎えることをついに承諾したのだった。
この事件の顛末について、すべて偶然であると断言できる人間は多いかもしれない。しかし各病院に向かう救急のランドカーが、手配される道筋がそこだとは限らないのである。
こうしてヒルダはマリーンドルフ伯の養女になったわけだが、キュンメルの看病で館にしばらくの間は常駐した。しかしある時、伯宛てに手紙が届いた。軍部からであった。貴殿の養女を軍本部での毒見役として召集したいと手紙には書かれていた。手紙は事務的なものであった。しかし皇帝の署名が入っていた。それでキュンメルが嘆く中、ヒルダは帝国軍統合軍本部に出向くこととなったのである。
ヒルダは公営バスを乗り継いで軍本部前についた。そこはサンスーシー広場からは少し離れた場所で、市庁舎の近くだった。建物はわりと近代的だが、古代ローマ風の円柱も見られるものだった。
ヒルダが階段をあがって行くと、事務官の一人に呼び止められて、ヒルダが通行証を見せると入場を許可された。そのまま案内係に連携され、彼女は建物内に入って行った。
中は殺風景なもので、事務机のある執務室が並んでいた。巨大なパソコンのデータサーバーが並んでいる部屋もあった。そこを通って行くと、ひとつの大きな部屋があって、宇宙の模型図の3D立面図のホログラムがある部屋があった。山脈のような海図である。しかしそれは宇宙空間を示していた。暗い部屋の中で、その緑色の蛍光色の物体は宙に浮かんでいた。
しばしヒルダがその物体に見とれていると、部屋の中にまた中年の事務官がやって来て、毒見役として呼ばれた方でしょうか?こちらにおいでください、と言った。
ヒルダがついて行くと、執務室で彼はまずこれをご覧ください、と言いシートを見せて、こういう献立になっております。各成分表はこの通りです。あなたには検査をしていただきます。そのうちのひとつの皿についてですが、と言った。ヒルダは当惑して言った。
「ひとつの皿だけ検査してもおそらく意味はありません。原材料の検査からした方がいいです。」
と答えた。事務官はそれを聞くと、非常にあわてた様子でハンカチで汗を拭き、いやあなたのような有能な方に来ていただいた方がいいというお話で、お呼びした次第なのです。実は仕事は毒見ではございません。普通の事務からやっていただきます。しかしその方面の知識がある方にいていただきたいのです、と言い出したのだった。
「それはなぜですか?」
とヒルダが尋ねると、事務官は声を潜めて、毒が横行しているのは本当のことです、ですが、あなた様はマリーンドルフ伯の養女であり、ハインリッヒ・フォン・キュンメル男爵と婚約中でございますから、そのように呼ぶようにおおせつかりました、と答えた。
「え、婚約中ですか?」
「そのように聞いておりますが…。」
ヒルダは席を立とうとした。しかし思い直して座り直した。そして言った。
「そのお話は違います。私は婚約中の身ではありません。しかしこれは皇帝陛下のご命令なのですね?」
「そ、そうです。何分内密にしていただくようにと…。」
「それは養父の耳には入れられないということででしょうか。」
「まことに、その通りであります。そのような経歴上で、ここで勤めていただきます。」
「わかりました。ここは御皇室の近くですから、そのように配慮されねばならないということなのですね。」
「はい。遺憾ながら、ここは男性職員が多い職場ですので、そういった肩書で勤めていたただきます。ご理解いただけて何よりです。」
ヒルダは前方に透明な壁があるように感じたが、承諾し勤めることになった。
仕事は本当に地味な事務作業であった。エクセルによる集計や簿記関係の業務、また予定表の書き込み。彼女のいる執務室の衝立の向こうで、軍関係者たちがさかんに出入りしているのが見えた。それらの人物の顔と名前も、次第に彼女の頭の中に入って行った。またそうでなければならなかった。
そのうちの一人に彼女は次第に視線が向くようになった。
誰だろう、なんだか見覚えがある…。
そう彼女はぼんやりと思うのだが、それは彼が白皙の美形の顔をしているからだ、と思い視線をそらせるようにした。
それはたくさんの海図の図面を抱えて、隣の赤い髪の男と図面を見ている金髪の男性だった。やがて彼女はその男の名前が、ローエングラム伯というのだということを知った。伯爵の称号を最近授与されたということだった。それは彼がアムリッツァ海域での戦闘で、作戦を立案し成功させたということでであった。
このアムリッツァ海域での戦闘は、後の同盟軍による侵攻作戦のものとは異なる。第一次などの名称を名付けた方がよいかもしれない。アムリッツァはイゼルローン回廊のハイネセン星側の出口付近の海域であり、回廊内の電子物質の密度が安定せず、艦の巡航には不都合な宙域である。ここでの小競り合いは日常茶飯事であったが、アスターテ星域での会戦の勝利を受けて、同盟側はまた大規模な侵攻を始めた。この時は残念ながらヤン准将は非番であった。そのためラインハルトの策に乗ってしまったようなのである。
同盟側はまず、帝国軍が左右両脇の空間に、縦配列に艦隊を固定したのを受けて、横一列配列で艦隊を展開した。つまり一列で押し返す戦法に出た。そのまま回廊内に突入し、中心に存在するイゼルローン要塞を攻略するように侵攻を開始した。
しかしこれが裏目に出た。帝国軍は左右に展開した艦隊を、同盟の艦隊の後ろに回り込むように進んだ。同盟側の艦隊は自然と包まれるようになり、団子状になって回廊入口から中に突入した。そこにあらかじめゼッフル粒子による電子物質の濃密な散布が行われていて、点火して大爆発したのである。回廊入口付近の惨状はすさまじいものであった。
この惨状をラインハルトはキルヒアイスと表情も変えずに、母艦から観測していた。さすがにキルヒアイスは額に汗を感じたが、作戦が終了するとラインハルトは艦橋からきびすを返し、部屋に引きこもってしまった。
オーディン本星に帰還した彼らには、皇帝から武勲で勲章が授与された。授与式ではひざまづいたラインハルトは、まったくまた表情を変えずに拝領した。この時に彼は皇帝から、皇帝の縁戚であるローエングラム伯の称号も授与され、またキルヒアイスも伯爵の称号をいただいたのである。
軍内部でも口さがのない連中は、むろんラインハルトがグリューネワルト夫人、つまりアンネローゼの弟であるから、姉のように平民から取り立てられたと噂した。それはその通りなのであったろう。そして彼は皇帝としばしば面談する機会も与えられたのである。しかしキルヒアイスが昔危惧したような、皇帝を害するようなことはラインハルトはまったく行わなかった。彼には彼の考えで行動をしているらしかった。ヒルダが目にしたのはちょうどその頃のラインハルトであり、彼は普段は作戦司令室で、職員のように勤務していたのである。
4.陥落
帝国軍からの壊滅情報を受けて、ハイネセンに駐留していた同盟軍のヤン准将は言ったものである。
「ねずみ採りにかかるとはね。ならこちらもねずみを進ぜるとしようか。」
ヤンの軽口にユリアンは眉をひそめたが、彼はおそらく怒っていると思い、そっといつものように紅茶をテーブルに置いた。
「帝国軍にもミラクルヤンのような策士が存在するみたいですか。」
ユリアンの言葉に、ヤンは紅茶を飲み、しばらく答えなかった。ベレー帽を取り髪の毛をかき回した後、彼は言った。
「おそらくそいつにはあざ笑われるだろうがな。艦隊の密集までの速度まで読んでいるとは。アスターテの時とは違うやつだろうか。」
「さあどうでしょう。でも何か考えがおありだと見ました。」
「古代史に学べとは言いたくないが。それぐらいしか方法はないか。」
と、ヤンは立ち上がり、統合本部に行く、と言った。
帝国軍側はその頃皇帝陛下の病を受けて、王宮内が騒然としていた。王宮と軍部はつながっており、皇帝はお飾りに近く、執政は軍内部の二大巨頭のブラウンシュバイク公とリッテンハイム公が兼任している。ブラウンシュバイク公は急進派であり、リッテンハイム公はやや穏健派である。それぞれ皇帝の妃に娘を差し出しており、ブラウンシュバイク公の娘であるベーネミュンデ夫人は五才になるエルウィンを抱えていた。唯一の皇帝の直系後継者であった。それ以外に後継は遠縁の一歳になる娘しかいなかった。
ベーネミュンデ夫人はエルウィンを産む前に三人の子供を死産しており、そのためエルウィンを溺愛していた。彼女は皇帝の寵愛が薄れているのは知っており、グリューネワルト夫人つまりアンネローゼの存在は頭痛の種であった。彼女がいなければ、もう少し子宝に恵まれていたかもしれない。しかしそれを口にするほど軽はずみな女ではなかった。すでに中年で四肢も肥えたこの夫人の元で、しばしばラインハルトとキルヒアイスは幼帝のお相手をすることとなった。それも皇帝のはからいでである。キルヒアイスは内心迷惑であると思い、これがアンネローゼの館であったならとため息をついたものだが、ラインハルトは幼帝と中庭でキャッチボールの練習をしたりした。幼帝も金髪の少年であったので、夫人はあなたがたは兄弟のように見えますね、と言ったりしたものであった。ラインハルトは幼帝にフォークボールの投げ方を伝授したりした。キルヒアイスはラインハルトがすっかり当初の目的を忘れているのではないかと考えた。つまり皇帝に対して絶対に許さないとか言っていたあの幼い日の出来事であり、アンネローゼを連れ去ったことについてである。皇帝はアンネローゼの処女を奪った憎っくき男ではないか。その息子と呑気にキャッチボールとは。しかしそれも命令なのだから仕方がないのか。作戦指令室にいない時の彼らはそのような非番の日を過ごしていた。
そんな矢先、皇帝の病が急変し、死の床に着くこととなった。国内は国葬の厳粛な空気に包まれ、幼帝は六歳で帝位に着くこととなった。この時ベーネミュンデ夫人の特別な申し出で、ラインハルトは幼帝の後見人としての勤めを果たすようにと申し渡しがあった。ラインハルトは一端は辞退した。自分は一介の司令官にすぎません、と言ったのだが、どうしても夫人が頑ぜず、この子はこのままではきっと誰かに毒殺されてしまいます、と涙ながらに訴えた。父親のブラウンシュバイク公もそれはもっともである、と言いラインハルトにその職に着くように命令した。こうしてラインハルトは好まざるを得ずとも、ブラウンシュバイク公側に配属されてしまうことになった。このことを耳にしたアンネローゼの心中はいかばかりであったろうか。憶測するしかないのであるが、彼女が皇帝とかつて栽培していた薔薇の温室を撤去されたあたりから、心が変質していったようなのである。しかしそれでも帝国旗の旗印は、皇帝の好んだ薔薇の紋章であった。
アンネローゼは水晶宮から居を移し、王宮内の小さなサロンで有閑の時を過ごしていた。彼女のサロンにはときたま軍関係者が訪れることがあるとの噂が生じていた。キルヒアイスの耳にもそれは入ったが、まさか彼女がそんな、と幼い日の美しかった時の面影を彼は抱いていた。ラインハルトはそのような事も、我関ぜずの態度だった。彼らはいくつかの小さな作戦の作戦指令を立案し、それは概ね成功させていた。同盟はトリューニヒト首相の
演説の際の内紛騒動で、まだ大規模な軍事作戦は行わないでいた。しかしその陰で、ヤンが次期イゼルローン攻略作戦を練っていたのである。
この頃になるとブラウンシュバイク公は外戚としてほとんどの執政を行うようになり、彼は組閣に近い人事を発案した。つまり自分を頂点とし、下部にラインハルトたち若手官僚の司令官たちを配属することとした。これに異を唱えるのがリッテンハイム公とその貴下の青年将校貴族らであり、彼らは幼帝を国外に追放する計画を発案していた。そこにアンネローゼも加わっていたのである。またそこにフェザーンの中立国も国益がからんで参加していた。要するに、今までイゼルローン要塞を通過して運んでいた積荷の輸出品目を、フェザーン回廊を通ることで通行料や関税を徴収することを旨とした公約を彼らに取り付けたのである。むろんそれは密約であった。
ヒルダが組閣幕僚の秘書官として呼ばれたのはその頃である。またその中にロイエンタール公やミッターマイヤー公も含まれていたし、オーベルシュタイン公もいた。むろんキルヒアイス公もラインハルトと執政官として勤めるようになった。しかしヒルダはまだラインハルトの補佐官ではなかった。彼らはチームとして配属されており、各々の権威はまだ対等に近かったのである。首魁はブラウンシュバイク公であった。そして彼らは軍部の作戦指令部も兼任していたのである。
ヒルダは新任の際に、なぜ私が選ばれたのですか、と尋ねた。すると事務官の返事は、毒に関する知識がおありですからね、ベーネミュンデ夫人は、幼帝に対する毒殺を非常に恐れておいでです、と答えた。でも、私は幼帝のお付きではありませんね、と言いかけてヒルダは言葉を呑み込んだ。何か釈然としないのであるが、別に理由がありそうだと彼女は考えた。そしてついに執政関係と作戦指令部に配属されたのだとため息をついた。軍の執務室で真面目に事務に取り組んでいた時、褒められることが多かった。それでついにこの役になったのだわと思った。
出仕の際、彼女は首にスカーフを結んだ。それは幼き日のあの食堂で、着せられた粗末な仕事着にもついていたものだった。新しい職場はきっと大変だから、あの時のことを思い出そうと思った。気になる彼とも同じ職場だし、と彼女は思った。だんだんその頃になると彼女も昔の記憶がよみがえって来た。しかしまさかその人だとは彼女は考えなかった。
同盟が軍事行動を開始したのはその直後である。帝国軍に対し、当初は数は少ない配置だった。その陰で二隻の貨物船が要塞内に近づいていた。船籍は帝国軍を偽装していた。ヤンの作戦であった。
ヤンの用いた作戦はいわゆる古代史のトロイの木馬作戦であり、特に頭脳を使ったものではない。彼らは貨物船の中の試料のタンクに兵士を隠し、間違ってこの試料を運んでしまいました、と検問をうまくごまかして通過した。むろんその時戦端は開かれていて、外宇宙で同盟と帝国は激しく戦闘を繰り広げていたのだが、ラインハルトはその策に気づかず、艦隊の移動配置に忙しかった。同盟軍は左右両翼の艦隊の隊列を何度もずらし、時間稼ぎをしていたのである。その間にイゼルローン要塞内は血の海と化し、白兵戦で帝国軍は占拠されてしまった。ヤンが非情とも取れる行動に出たのはこの時である。彼は、奪取したイゼルローンの主砲のトゥールハンマーで、味方の艦もろとも帝国軍の大半を一撃で焼き殺した。この時の味方の損害を考慮に入れずの行動で、彼は本星の査問会で心理プロファイル審議をされるはめになった。だがこの時も彼は、自身の潔白を信じた行動を取った。ヤンは漂とした男であったが、心にどこか欠落した部分を持っており、それは本人も気づかないものであった。また彼はラインハルトよりも友人を数多く持ち、円満に人間関係を運ぶことができた。その人間関係の中では、彼のそうした欠落は見えないものであった。
イゼルローン陥落の報を受けて、当然ブラウンシュバイク公らは追及を受けた。しかしまだ毒杯を飲み干すまでには至らなかったのである。ラインハルトらは前線から帰還を遂げていたが、一様に疲れており、室内は重い空気に包まれていた。今回の作戦の立案者はやはりラインハルトであったから、彼は沈痛な表情であった。
「退出する。」
と一言言って、彼は執務室をあとにした。気づかわし気なヒルダの表情を見守るキルヒアイスの顔があった。彼は友に言葉をかけてやりたかったが、こういう時友は拒絶するだろうと思った。彼は幼き日を思い、アンネローゼに会いたく思った。あの懐かしき日が恋しかった。
そう彼が不安に思ったのには理由があった。ブラウンシュバイク公が反撃も辞さないと言い、核兵器の使用も考えていると彼らに言ったからである。
5.湖畔にて
キルヒアイスがアンネローゼのサロン室を訪れたのは、イゼルローン陥落の数日あとであった。電子メールでその連絡は入った。あなた達にお渡ししたいものがあります、と書かれていた。キルヒアイスはラインハルトの控室のドアをたたいて、一緒に行くかと言おうとしたが、まだ籠り中みたいであったので、行き過ぎて呼ばずに出た。作戦の成否にかかわらず、ラインハルトは作戦終了後最低一日ほど閉じこもることが多かった。むろん執務がない場合である。卿は弱気である、と軍人らに噂される所以であった。
キルヒアイスが行った新しいアンネローゼの居住先は、水晶宮よりも小規模であったが、室内はさらに装飾がほどこされたものであった。雑学があまりないキルヒアイスには、それがおそらく地球のアールデコと呼ばれる時代のものであるだろうと思った。そのステンドグラスが陽光にきらめいている中に、白い肩抜きのギリシャ風ドレスを着てアンネローゼは籐の椅子に座っていた。ようこそおいでくださいました、と彼女は結い上げた頭を下げて言い、この度の戦争は大変でしたね、さぞお力を落とされたことでしょう、できれば戦争などなければいいのですが、と言い、キルヒアイスに一冊のアルバムを薦めた。
「やあこれは、昔の写真ですね。」
と、キルヒアイスは相好を崩した。小さい頃の彼ら三人の様子が写されたものだった。
「さるところに保存されておりました。折り入って手に入ったので、あなたにも持っていただきたく思いました。どうぞ。」
とアンネローゼは言い、慣れた手つきでティーポッドから紅茶を注いだ。芳醇な香りが室内に漂った。アンネローゼはカップを薦めて言った。
「陛下がもういらっしゃらなくなって、弟も寄り付かないので、寂しく思っておりました。時々お訪ねくださいますか。」
「は、いや、まあ。来ていいのなら、来ますが…。」
「ええ、わたくし寂しくって…。」
「ああ、次はラインハルトも連れてきますよ。あいつ水くさいな。こんなきれいなお姉さんをほっておくなんて。」
「いえ、もう私は歳ですから。このままひとりぼっちで年寄りになっていくだけで…。」
「いや、まだまだお美しいですよ。そう、あのベーネミュンデ夫人に比べたら。」
キルヒアイスはあまり何も考えずにこう言ったのであるが、このセリフを聞いたアンネローゼは顔を伏せて肩を震わせハンカチで激しく目を拭きだした。
「あの子のことは言わないでください。あんまりで…。」
「あの子?」
「あんな恩知らずな子。だいたい軍に入るなんて考えもしませんでした。恐ろしい。私はあの子のことを思って送金していたんです。私の身を売ったお金でですよ。それをあんな風に使うなんて…。」
キルヒアイスは困惑した。この兄弟には溝があるのだなと思い、おそるおそるアンネローゼの両肩に手を回した。彼女の取り乱し様がひどかったからである。
「あの、僕ももう軍人ですから。でも、お気持ちはわかります。」
キルヒアイスがこう答えると、アンネローゼはひしとしがみついてきた。そして泣きはらした上目遣いで見上げてこう言った。
「みんな私を置いて行ってしまうのね。でもあなただけはそうでないでしょ?」
「は、はい。」
「必ずまた来てください。わたくし待ってますから…。」
キルヒアイスは圧倒される思いでこの日は退出したのだが、二度三度と訪れるうちに自然と昔のように打ち解けた関係になっていった。彼らは別荘から近い湖水方面に遠出し、語らいあうようになった。つまりキルヒアイスは彼女に感化されていったのである。アンネローゼは白い日傘を差してキルヒアイスに言った。
「わたくしが子供を陛下と作らなかった理由は御存知かしら?」
「それは愛していらっしゃらなかったからでしょう。」
「それもあるわね。でも、一番の理由はあのルドルフ大帝からのお種を残すことを由としなかったからです。あの男は優生思想を振りまいて、差別意識で選民しましたが、そういうあの男の血統こそこそ根絶やしにするべきだったのです。」
キルヒアイスは相槌を打ちながら、まさに烈婦であるなと感嘆していた。そしてやはりラインハルトの姉君であると心の中で激しくうなずいていた。
「では、あなたはそのような思想のもとに、陛下と契りを結ぶことにしたのですか?」
「当たり前ですわ。私と枕をともにする回数が増えるごとに、陛下の子種を残す機会が減るのです。しかしこの事は絶対に秘密ですよ。昔からのなじみであるあなただから打ち明けたのです。決して誰にも言わないと約束して。」
キルヒアイスはため息をついた。烈婦であるが、やはりとても繊細なのだ。
「…寂しくはないのですか?最初に訪れた時、あなたは寂しいと言った…。」
「ええ、わたくしは寂しい…、だからあの女が許せないのです。弟も。わたくしが命がけでやっていることを踏みにじって。」
「あの女?」
「今は聞かなかったことにしてください。」
アンネローゼはそう言うと、白い傘を揺らしながらキルヒアイスの前を歩いて行った。
ラインハルトたちは戦いが一応の停戦状態に入ったことで安堵していたが、ブラウンシュバイク公はイゼルローンを奪還すべきであると言い、リッテンハイム公と激しく対立していた。リッテンハイム公は戦争が長引くのを由とせず、同盟に譲歩して縮小すべき時であると説いた。その裏で、彼らの幼帝の誘拐は画策された。
深夜賊は忍び込み、寝所を襲って幼帝を連れ出した。賊はフェザーンの構成員で組織されていた。彼らは同盟側に幼帝を売り渡し、交渉材料のひとつとした。名ばかりの臨時政府が同盟内に誕生し、その擁立は反ブラウンシュバイク派の貴族たちだった。要するに北朝と南朝のようなものである。同盟側でも困惑の動きを見せたが、それを収めたのはやはりトリューニヒトであった。彼は帝国側がこの臨時政府を皇室の正統なものと認めるなら、イゼルローンの通行権は譲歩してもよいと言い出した。ヤンたちは何をバカなと言い、帝国と交渉する必要はないと言った。彼らはイゼルローンに駐留を続け、半独立状態に近くなっていた。本星ハイネセンとの連携は切れつつあった。
このような分裂の危機にあって、ラインハルトはフェザーン回廊を押さえるべきであると主張し、そこからハイネセン制圧を進言した。ブラウンシュバイク公は迷ったが、フェザーン回廊からの進軍を可決させた。この進軍は遠路であったが、イゼルローンを通過しないので、敵勢力は少ないと思われた。だがフェザーンは中立を保っていたので、おそらく同盟から反抗されるであろう予感があった。
帝国の皇帝は空席になり、仮初めの皇帝代理として、一歳の養女が皇帝として擁立された。ベーネミュンデ夫人はまだ幼帝は敵国で存命中であると聞かされても、頑として聞き入れず、涙のうちに喪に服して大公と呼ばれる存在になった。彼女はそうして政治の表舞台から姿を消した。
こうして皇室に空席が目立つようになると、アンネローゼの周辺では動きが活発化してきた。彼女が皇位の座を狙っているとの噂が流れた。しかし彼女の人となりを知る人々は、それを一笑に伏した。あのたおやかな女はそんな女性ではないと。事実ラインハルトらが帰国するまではそうだったのである。
フェザーンの通過にはそれほどの労力はかからなかったが、ハイネセンの制圧はそうではなかった。ラインハルトたちはハイネセン成層圏の十二個の軍事衛星の存在に手こずった。それは全方位で射程圏内に入るものであった。結局彼らの遠征艦隊は臨時政府基地をたたいたのみで帰国することとなった。しかしこの時、どさくさに紛れてヤンの艦隊がこの十二個の衛星を、電子機器が反応しない特殊物質の氷山で爆破したのである。臨時査問会が招集されたのはこの時で、ヤンは軍事法廷に立たされたが、仲間の活躍で逃亡した。彼らはイゼルローンに籠城し、ハイネセンとの連絡を絶った。ハイネセンにおける帝国の臨時独立政府は空中分解し幼帝は行方不明となった。おそらく死亡したのだろうと言われた。
帝国で反貴族連合が蜂起したのはこの直後だった。彼らは同盟ハイネセン内に領土が広がると勘違いしていた。その目論見が崩れ去ったので、各惑星で貴族の叛乱蜂起が起きた。それを受けて今度こそブラウンシュバイク公は核を使うのではと言われた。ラインハルトたちはその先兵であるように噂された。
遠征を終えて帰国したラインハルトの憔悴しきった顔を見て、ヒルダは何も言えなくなった。無駄足であったとは言わない。臨時政府は消滅したのだ。しかし元からあったものではなかった。ただ元の状態に戻しただけだった。そのための遠征であった。
その日の深夜ラインハルトは自室でパソコン内の書類を整理していた。彼はあるファイルがひとつ増えていることに気づいた。またウィルス関係かと思って閉じようとしたら、勝手に開きある映像を写し始めた。自分でない自分がヒルダを襲っている。むろんアイコラであることは彼にはすぐにわかったが、場所と時間帯を判断するために彼は冷静に視聴を続けた。ファイルの最後には「戦争反対!公表されたくなければ戦争をやめろ!」の字幕が書かれていた。彼はゆっくりと立ち上がり、録画できる映像機器があるか自室を探した。
6.謀殺
その日出仕したヒルダはいつもより大きな絹のスカーフを首にカフスピンで留めていた。彼女は首に手をやり、何度か確かめるような仕草をした。指先が心無しか震えている。
「いつもと違いますね。それ、似合ってますよ。」
と、後ろを通ったキルヒアイスが彼女に声をかけた。そのまま彼は壁の向こうに行き席についた。
その日のヒルダの仕事の進捗度について、監査役のオーベルシュタインは見逃さなかった。彼は会議後、ヒルダを呼び出し訓戒した。
「君は紅一点なのだから、居づらい気持ちがあるのはわかる。しかし心ここにあらずでは仕事にならない。誰か気になる者が部内にいるのかね?」
「いえ、おりません。」
「ならいい。仕事に戻りたまえ。君は婚約中らしいからな。気をつけたまえよ。」
「はい。」
と、ヒルダは訴えるように言葉を前に押し出した。
「あの、書庫に。」
「書庫がどうかしたのかね。」
「…なんでもありません。」
ヒルダはオーベルシュタインの机の前から礼をして下がって行った。
この部内と部内に続く棟は、部外者はほとんど入れない。作戦指令室なので、ほぼ外部の者は普段はシャットアウトされている。覆面をしていた。それしかわからない。彼女は書庫の映像データを、こっそり管理者権限モードで閲覧してみたが、問題の時間のものは空白になっていた。計画的犯行。足元から床が崩れ落ちそうに感じる。しかし私は立って仕事をしなければならない。ヒルダは誰かに相談することを思ったが、かぶりを振った。チームの和を乱すことになる。それでなくても敗戦が続いているのだ。そんな事は言えない。
その時、オーベルシュタインがまたヒルダを呼んだ。
「書庫に行ってこの書類とこの書類をファイルに綴じてくれ。パソコンデータには入れられないものだ。」
「は、はい。」
ヒルダがあわてたように受け取ったファイルの束を抱き抱えると、いつの間にいたのかラインハルトが横に立っており、
「私が持って行こう。」
と言った。
「あ、いいです。」
「いいから。」
とラインハルトはファイルを取り上げると、廊下へのドアに消えた。
書庫に入ったラインハルトは、部屋の自動電灯の下でファイルを所定の位置に戻したあと、天井近くの棚に設置していた小さな電子機器を取り外して手で握りつぶした。
「二回か…。」
聞かれるだろうつぶやきだったが、聞かれてもいいと思った。
ブラウンシュバイク公とリッテンハイム公の内紛争いは、帝国内で拡大していた。リッテンハイム公派の青年貴族らは、ガイエスブルク要塞に立てこもり、その伴星のヴェスターラント周辺を占拠していた。彼らはここから首都星オーディンまで進撃し、皇帝の首を挿げ替えると言い出していた。むろんそれはゴールデンバウム王朝の者ではない。つまりリッテンハイム公がその後継者になるという事だったのだ。ブラウンシュバイク公は激怒し、ガイエスブルクへの進軍を開始した。そしてその先鋒として、ヴェスターラントに核ミサイルを撃ち込んだ。これは明らかに彼の誤りであるが、ラインハルトとオーベルシュタインはブラウンシュバイク公に思いとどまるように進言はしなかった。彼らは親書を作成していた。それは皇帝代理の皇女の名において記されていた。このことはリッテンハイム公にも伝わっており、彼はガイエスブルク要塞をその親書によって譲渡する旨を取りはかっていた。これらはブラウンシュバイク公の知りえることではなかった。つまり一種の内部告発であった。
キルヒアイスがラインハルトとヴェスターラントの核爆発について話し合ったのは、その直後である。
「ラインハルトさまはあの核攻撃を見過ごすはずがない、そのような方だと心得ております。民衆を犠牲にして、一時の利益のためになぜご自分をおとしめなさるのですか?」
キルヒアイスの言葉に、ラインハルトはしばらく答えなかった。やがて口を開いて言った。
「無辜の民を殺したことは、おまえの言う通りだ。彼らは私を呪い殺して然るべきだろう。事実そうなるだろう。だが私一人の力ではやつを失脚させることは不可能だった。」
「失脚、ですか?」
「そうだ。揚げ足を取ったとおまえは思うだろう。確かに俺はやつが墓穴を掘るのを見ていただけだった。それはその通りだ。別に俺は生きながらえようとは思っていない。軍に志願した時からそう決めていた。」
「それは理屈です。素直に謝るべきです。」
「おまえに謝って済むのなら、そうする。俺がおまえに一言も相談せず、オーベルシュタインと決めたことが気に食わないのだろう?」
「そんな事では…論点をすり替えないでください。」
ラインハルトはキルヒアイスの方を見ずに、少し笑った口元で言った。
「おまえは俺の、なんだ?」
キルヒアイスは言葉に詰まった。ラインハルトはそう言うと、ドアを開けて出て行ってしまった。
後に残されたキルヒアイスはその場に立ち尽くしていた。アンネローゼから聞かされた話を彼は反芻していた。戦争がどれほど民を傷つけるかということ、そして自分は皇帝の犠牲になったのに、ヒルダは逃げ延びて普通の生活を送れたことなど。そして―。
「あなたとなら、きっと皇帝として民を平和に治められます。私が力になりますから、弟を諫めてください。あの子には毒蛇のようなところがあるんです。」
キルヒアイスがアンネローゼとの寝やの間でのこの相談を、どうして受けたのかはわからない。ただ彼はラインハルトとの思想上の距離がどんどん開いていくのを止めたかったのかもしれない。また彼は、自分のラインハルトの補佐に徹する役回りに不満を抱いていたのかもしれない。確かにあったはずの友情に亀裂が生じたとはっきりわかったのは、後日キルヒアイスがパソコンを開いた時、問題の録画ファイルがすべて高原の花の環境ビデオにすり替わっているのを見た時だった。むろん彼はヒルダに対するセクハラを行う危険性を感じ、それはただちにやめることにした。部内ではラインハルトは以前と同じように事務的に接していた。ブラウンシュバイク公が陰謀により毒殺されたのはその頃である。
公が豪華な個人執務室で書類を書いている時、突然ドアが開いて、数人のサングラスの男たちがどやどやと入ってきた。リッテンハイム公もその中にいた。リッテンハイム公は言った。
「皇帝陛下が遺憾に思っておられます。責任を取っていただきたい。」
「なんだと。一歳の幼女が何を遺憾に思うのか。わかったぞ。貴様ら書類上でわしを更迭する気だな。」
「更迭ではない。排除です。」
リッテンハイム公は運び入れたワインキャピネットからひとつのワインを取り出し栓を抜いた。
「飲んでいただきます。」
「き、貴様ら何をするかぁっ!」
暴れるブラウンシュバイク公は数人がかりで押さえつけられて、毒ワインを瓶から直接飲まされた。公の体はすぐに動かなくなった。
「ガイエスブルク要塞に連絡しろ。蜂起は終了だ。」
リッテンハイム公はそう言うと、部屋をあとにした。
ラインハルトが皇帝代理として演台に立つように言われたのはその後である。リッテンハイム公は兵士たちの恣意掲揚のためと言った。
「こたびの内紛を収めるための演説をしてほしい。」
ということだった。キルヒアイスはその事に疑いは持たなかったが、なぜラインハルトがと思った。彼はその時卑屈であると思いつつ、なぜ君が選ばれたのかなと部内でおそるおそるラインハルトに尋ねた。
「それはやはり道化役が必要だからだろう。」
と、彼は言い、
「俺を殺したい連中には絶好の機会だな。狙っているのは同盟だけではないだろう。」
と言った。
キルヒアイスがどうしてそう思うんだ、と言うと、ラインハルトはすでに作戦司令を発案しているのは俺だということが世間に知れ渡っている。だからそういうことだ、とこともなげに答えた。
演説の日は滞りなく式典は進んだ。しかしキルヒアイスは入場の際に拳銃の所持を断られた。ひたひたと、何かが近づいている気がした。暗い宇宙空間の遠くに艦隊の光点が見え、それが次第に数を増していくのを見守っているような感覚である。何をバカなことを、彼は掲揚台前に参列者として立ちながら考えた。しかし彼一人が果てしない荒野に立たされているような気がした。それはラインハルトの話では彼の立場であったはずだ。
と、突然式典会場に数人のバズーカ砲を持った男たちが躍り出た。ラインハルトが演説をしている最中だった。
「ブラウンシュバイク公の仇だ!この裏切者!」
と、男たちは言い、バズーカ砲を発射した。砲撃は演台の天井部分の壁に命中し、猛煙があがった。キルヒアイスは腰の拳銃を取ろうとして、それがないことに気づいた。彼は彼の隣のバズーカの男をその時狙おうとしなかった。その様子はたぶん演台のラインハルトにも見えたはずだ。このただ一瞬のキルヒアイスの判断を、彼はその時いつもの冷静な蒼い目で目撃したのだった。
キルヒアイスはその後横の男に飛び掛かり、押さえつけようとした。その体の背中を、光線ナイフが貫いた。血潮が吹き飛び、キルヒアイスはすさまじい形相になった。なんという痛み。つまり、今自分は、屠殺場にいたのだ。やはりそうだった。キルヒアイスの胸に悲哀の波が押し寄せてきた。彼はやはり自分を許さなかった。遠くなる意識の中で、彼は自分の名を呼ぶラインハルトの声を聴いた。この痴れ者と思ったが、彼はようやく言葉を吐いた。彼に似合いの言葉だろうと思った。
「ラインハルトさま、…宇宙を手にお入れください…。」
ラインハルトはキルヒアイスの手を取っていたが、それが力なく落ちた時泣いていた。彼がこんな人前で、手放しで泣いたのはこの時限りだった。
7.激突
アントン・シャフトは先の貴族蜂起のリップシュタット戦役が終了後、執務室のパソコンで文書を作成していた。彼は科学技官であり、ワープ航法の権威者である。画面にざっと並んだ科学論文の中で、ある論文のタイトルに彼の目は注目した。それは巨大質量物体のワープについて書かれた論文で、理論上は可能であると結論づけていた。執筆者は無名の学生だった。
シャフトは論文の文面の前でしばらく考えて、これは使えるぞと思った。彼は全文コピーに取り、記憶媒体に保存した。その論文は巨大要塞の移動についても可能と書かれていたからだ。誇大表現ではあるが、あの廃棄処分のがらくたには使えそうだと彼は考えた。ガイエスブルグ要塞は度重なる貴族らの戦争により、老朽化が激しかった。リップシュタット戦役の終了時点ですでに廃棄は決まっていた。これをうまく利用しない手はないぞと彼は考えたのであった。論文中のたくさんの数式については、彼は理解はしていなかった。彼は次に会議があった時に進言しようと思った。
リッテンハイム公は式典の時の流血騒ぎについて、遺憾であると言ったが影ではこのように言っていた。いわく、ラインハルトが姉と密通している友人が皇室に謀議をたくらんでいるので処分願いたいと。そう頼まれたので彼はそれに乗った。軍の士気に利用できると踏んだのである。それについて、彼はラインハルトが甘ちゃんであると近侍にもらした。
「あのグリューネワルト夫人の弟だろう。いつまでも姉の影を追っているなど、碌な男ではない。しかし新兵たちには感動的な場面に映ったであろう。友の死を悼む気持ち、さぞかし伝わったであろうな。」
「はい。なんでもペンダントに遺髪を入れているそうです。」
「そういう言い伝えは聴いたことがあるが、なにやら男色くさい。私は感心せんな。」
「ごもっとな意見でございます。」
「まあ見栄えがいい男だから、お飾りとしてはいい者だろうよ。今後も皇帝代理として一応立てておくことにしよう。」
これらの風の噂は、ラインハルトの耳に直接入ることはなかったが、彼はそれを知っていた。彼は共同墓地に新しく建てられた、キルヒアイスの墓に白百合の花束を持って訪れた。キルヒアイスの両親が参りに来た形跡があった。しばらく彼は花束を添えずに立っていたが、やがて花束を両親の献花のそばにそっと置いた。風が吹く中で、彼は胸元のペンダントを開けて、中の赤い髪の毛を確かめ、またゆっくりと墓地の丘を降りて行った。
「イゼルローンの奪還作戦に卿の良い意見があると聞いたが。」
と、作戦指令室に招かれたシャフトは声をかけられた。声の主はオーベルシュタインだった。彼らは暗いオペレーションルームで、3Dの宇宙図の前で秘密の会合をしていた。シャフトは論文のページをタブレットでめくり、御覧のような数式で、理論上はガイエスブルク要塞をワープで移動させることは可能であります、と答えた。一同の間でため息がもれた。ロイエンタールはあんな質量のものを、と思わずつぶやいた。
ラインハルトは少し笑って、中の人間のワープの際の圧力計算はしてみたのか、とシャフトに言った。
「は、搭乗する人間の内部圧力については、この論文では…。」
「もういい。で、卿はそれをイゼルローン要塞の前に出現させたいというわけだ。そうだな。」
「その通りであります。同盟側はそれは予測することはできないでしょうから。」
オーベルシュタインは引き取って言った。
「どうなさいます。確かにこの近距離でガイエスブルグの主砲で攻撃すれば、イゼルローンのトゥールハンマーに対しては有効でありましょう。」
「そう、ある程度はな。しかし向こうの方が出力が大きい。二万の将兵がまた死亡するであろう。」
ラインハルトの淡々とした口調に、シャフトは内心平伏した。やはりこの案はだめみたいだと彼は思った。それは予感していたのだ。だがラインハルトはこう続けた。
「しかしやってみる価値はありそうだ。卿の言う通りワープできれば、実行してみよう。」
このラインハルトの言葉に、ロイエンタールは心底驚いた。むざむざ倒されるために、軍の大金をかけてワープ実行すると言うのか。これは正気の沙汰ではない。
「あんなやつだとは思わなかった。ヴェスターラントの一件以来、やつの態度が変わったように思う。あの核爆発では二百万人が死んだ。それを黙殺できる精神力がついたという感じかな。」
と、ロイエンタールは酒保のバーでミッターマイヤーに言った。ミッターマイヤーは杯を手で回しながら答えた。
「いや、あれは元からああだ。アムリッツァで艦隊一個分焼却処分したのが初戦の頃だったろう。なんとも思っちゃいないのさ。キルヒアイスの一件だって、やつにとっちゃ首飾りぐらいにしか思っていないんじゃないか。」
「おい、それは言いすぎだぞ。一番の腹心の友だったんだからな。俺だっておまえに死なれたら打撃だ。」
「態度が変わったというのは?」
「うまく言えないが、迷いがなくなっているみたいな感じだ。だから非常に危ない。今回の件も、たいした大艦巨砲主義だよ。地道に艦で攻めるつもりはないのかね。」
「それで以前に同盟にイゼルローンを盗られたからな。一気に王手をかけるつもりなんだろう。つきあわされる身はたまったもんじゃない。」
ミッターマイヤーはそう言って杯をあおった。
その頃、ヒルダはまたあの木製の人形の夢を見るようになった。長い間見ることがなかったのに、やはりあの恐ろしかった書庫での体験のせいだと彼女は思った。自分が鬱状態になっている。それは部内のメンバーのキルヒアイスが亡くなったことも関係しているのかもしれないと彼女は思った。彼女はためらった末に、上司のオーベルシュタインに訴えた。体調の不備が自分にはあります、少し静養させていただくことはできないでしょうか、とおそるおそる言うと、オーベルシュタインは次の作戦は非常に困難を要する秘密のものなので、君ははっきり言って足手まといになる。しっかり休みたまえと言った。
ヒルダは帰宅して、ベッドに横になった。妊娠検査薬は事後すぐに調べた。陰性だったので安堵したが、なぜこんな目に会うのか。あの職場に自分はいていいのだろうか。しかし辞任することはおそらくできないだろう。向こうが首を切る以外にやめる方法はないのだ。そう思った。そして、心の中で暗雲が沸き上がっていた。あの問題の人物は背格好がキルヒアイスに似ていた。彼はラインハルトをかばって死んだらしい。というような噂を聞いている。何か関係があるのではなかろうか。
と、その時枕元に置いていたスマホに着信音が入った。電子メールだった。開いてみるとラインハルトの姉を名乗る人物からの文面だった。
「あなたがわたくしの親友だった故キルヒアイス伯と同じ職場の方と聞いてメールをお出ししています。わたくしはラインハルト・フォン・ローエングラムの姉のアンネローゼでございます。弟からあなたの話を聞いております。キルヒアイス伯の生前のご様子を聞きたく、お手紙を書くことにしました。わたくしとラインハルト、キルヒアイスは幼少の頃遊び親しんだ幼馴染でございます。今わたくしは下記の山荘で静養中でございます。よろしければお訪ねください。積もるお話をぜひお聞かせ願えればと思います。 草々」
ヒルダは目を丸くしてしばらくメールを見ていたが、起き上がり、リュックサックに財布とスマホを詰めこんだ。たぶんいたずらメールではないだろう、彼の本物のお姉さんだろう。彼女はその高原地帯の山荘に行くことにした。ラインハルトに尋ねることは彼女は忘れていた。
アンネローゼの山荘は、首都オーディンから少し離れた山岳部の中腹にあった。ログハウス風のコテージで、ヒルダが歩いて行くと牧羊犬のような犬が飛び出してきて来客があると吠えた。ヒルダが犬に躊躇していると、中から使用人の男性が出てきて、どうぞこちらへと言った。
コテージの中には暖炉があり、季節は秋だったが薪火がくべられていた。その横のロッキングチェアにアンネローゼは座っていた。
「御挨拶が遅れてしまいごめんなさい。少し体調が悪くて立ち上がれないんですの。どうぞおかけになって。」
と、そのラインハルトと同じ金髪の女性は言った。ヒルダはおそるおそる長椅子に腰をおろした。ヒルダが座ると廊下の戸口から、少年が盆にコップを二つ乗せて運んできた。
「ありがとう、エミール。そこに置いてあげて。」
と、アンネローゼは言った。髪はやわらかく一つに横に束ね、ゆったりした紫のモスリンのドレスを着てひざ掛けを膝にかけていた。
「この子はエミールと言いますの。孤児院から引き取られてきたんです。私の身辺を世話してもらうようにしています。」
「そうでしたか。」
と、ヒルダは言った。
「あなたも孤児院にいたことがあると聞きました。」
「え、あの。」
「あらご存じなかったんですの?わたくしたち、あなたのことを時々話していたんですのよ。キルヒアイスさまはそれはもう褒めておられて。」
「はあ。」
「あんなことで亡くなってしまわれて、わたくし本当に悲しかったのです。それでこのエミールをそばに置くようになったのです。」
「ええ。」
「職場ではキルヒアイスさまはどうでしたか?あなたに親切だったのかしら?」
ヒルダは考えていたのと違う状況に今自分は置かれていると思った。親友というのはたぶん嘘だ。たぶん恋人、そんな関係…。
「私は同じ部署にいただけで、彼のことはそれほど詳しくは知りません。仕事上で話をしたことはあります。今回亡くなられて、お気の毒だったと思います。」
するとアンネローゼは薄く笑って
「詳しくはお知りにならないの?それはそうでしょうね。ごめんなさい、あんなぶしつけな手紙をお出しして。でもあなたは親切な方だから、ここまで来てくださったんですのね。」
と言った。そして、
「せっかくだから部署内にどんな方がいるかお話してくださらない?キルヒアイスさまがどんな職場にいたか興味があります。」
と言った。ヒルダは防御態勢にならないといけないと思い、言った。
「あの、部外者にはあまりそういう話は。」
「でも弟をかばって亡くなられたのでしょう?本当は詳しく知りたかったのに、教えてくださらないんですもの。せめてそれぐらいは…ね?」
ヒルダはアンネローゼに乞われるままに、部内のメンバーの名前をあげた。名前だけなら、顔と識別はできないはずだと彼女は考えた。アンネローゼはそうなの、とひとりうなずいて、
「ずいぶん少人数ですのね。女性はあなたおひとりなの?それはいろいろと大変でしたでしょう。」
と言った。
「え、ええ、まあ、そうです。」
「弟とはどういうご関係?」
「え、ラインハルトさまとですか。別に何も。」
「エミール、お客様がお帰りになるわ。お見送りして。」
ヒルダははっ、となりあわてて立ち上がった。アンネローゼは申し訳なさそうに言った。
「ごめんなさい、急がせてしまって。急に体調が悪くなりました。少し長くしゃべりすぎたようです。またいつかお話ししましょう。」
アンネローゼの言葉に、ヒルダは無言で頭を下げた。
帰途の途上で、ヒルダはぼんやりした頭で今あった状況を反芻した。おそらく彼女は自分の恋人が自分の弟をかばって死んだことが、許せなく思っているのだ。だから代理行為で、私に対して今処罰的言動をしたのだと。彼女は変な夢を見て以来、心理学についてもひとり学び続けていた。ヒルダは思った。
代償行為。あれもそうだろうか。死んだ友人の髪の毛を首にかけている行為。ヒルダは髪の毛→紐→ロープと考えて、あわてて首を振った。あの方が自殺を考えているわけがない。あんな強い精神力の持ち主が。ヒルダは満天の山の星空を見上げてそう思った。
アンネローゼが王宮内からその山荘に移っていたのも理由があった。先の謀議があるという政治的理由で、彼女は隠居していたのである。しかしそれらの歴史的事項は、ヒルダの頭にはなかったし、あの幼少時に見た光景の、皇帝に妾として仕えた少女がアンネローゼだとは、彼女は認識できなかったのである。従ってアンネローゼが恋多き女性であるらしいように見えたのも、そうした空閨の後室の女性ならよくあることという認識であった。だがこれはラインハルトにとっては、おそらくそうではなかったのである。
彼はもうおわかりの通り、ガイエスブルグ要塞に囮の艦隊をつけて差し向けて、一見その要塞で攻撃するように偽装した。それは「普通」にである。
「ケンプの艦隊をつける。もしそこで命を落とすのなら、ケンプもそこまでの男という とだ。」
と、短いヒルダとの執務室での会見で彼はそう言った。その態度はしごく普通のものであり、ヒルダも彼は落ち着いていると思った。オーベルシュタインの話では非常に困難な作戦であるという話だったが、それは杞憂だったのかと思った。彼女はオーディンに残り、艦隊は出撃した。
シャフトらが見守る中で、ガイエスブルグ要塞は無事ワーブ転移を果たした。しかし周辺の宇宙空間にはひずみが生じた状態だった。巨大質量のものが空間移動したのだから、それは当然の成り行きであった。イゼルローン要塞にいるヤンらは動揺した。要塞内は激しく振動し、さながら大地震のようであった。それも彼らが動転する要因であったろう。ヤンたちは必死であった。
「ガイエスブルグ要塞、主砲こちらに向けて発射してきます!」
「仕方がない、トゥールハンマーで応戦しろ!その後あの要塞の底部にある出力推進装置を狙え!照射角40!」
まず主砲同士の光線の激突があった。
ヤンは下調べして、要塞の図面をネットから秘密に入手していた。こんな事もあろうかということであった。その図面に問題の稼働推進装置はあった。そこを狙えば、要塞は回転しながら自爆するはずであった。
ケンプの艦隊がその間も間断なく集中砲火を浴びせかけていた。ヤンには余裕がなかったのであろう、彼の指示通り要塞下部に砲撃は届いた。それで要塞は自動安全操縦を離れ、空転を始めるはずであった。ラインハルトはその瞬間片手をあげて命じた。
「撃て(ファイエル)!」
要塞が回転すると同時に、背後の母艦から熱線の束がガイエスブルグ要塞に命中した。要塞は回転しながらイゼルローン要塞に向かって爆進をはじめた。
「なにっ?!」
ヤンはその瞬間驚愕した。イゼルローン要塞のトゥールハンマーにガイエスブログ要塞は高速回転しながら激突した。すさまじい音響をたてて、トゥールハンマーは完膚なきまでに破壊された。
「貴様、最初から要塞をつぶすつもりで…!」
こんなやつだったとは、とヤンはベレー帽を床にたたきつけて思った。おそらくアムリッツァと同じやつだ。こちらの反応を読んでの物理的攻撃だった。それにしても秒単位の攻撃角まで予測していたとは。
「あの要塞は…。」
と、横からキャゼルヌが言うのに、ヤンは答えた。
「おそらくもぬけの空だ。最初の主砲攻撃は囮で、母艦からの遠隔操作だろう。総員退艦せよ!爆発するぞ!」
ユリアンが心配そうに見上げるのに、ヤンは答えた。
「大丈夫だ。やつらには置き土産を置いていく。また来る日のために、今は退く。」
と、言った。
「イゼルローンを奪還したのはいいが、トゥールハンマーが使い物にならないのなら、話にならん。君はあのがらくたをどうするつもりかね?何の防衛ラインにもならんものを、占拠運営しても仕方がないのだがね。」
と、その後ラインハルトはオーディンで軍議に呼び出されていた。発言者はむろんリッテンハイム公である。しかしその席上で彼は、一冊のファイルを提出して言った。
「トゥールハンマーはまた再建すればよいのです。私がこのたび設計図面を書きました。」
「何、君がか。」
「少し図面をかじった事がありましたので。僭越ながら閲覧していただければと思います。」
リッテンハイム公は激怒した。
「き、貴様予算を何だと心得る。貴様は首だ。」
「申し遅れましたが、それはあなたの方こそです。ここにもう一冊ファイルがあります。先のエルウィン殿下誘拐事件に関する調査報告書です。私はこれを司法に提出する所存であります。」
8.幕間狂言
イゼルローン要塞については以上の顛末だったのであるが、リッテンハイム公の失墜を受けて、新たなる権威を巡った貴族争いはまた勃発していた。だが彼ら作戦司令部は留め置かれたままだった。また彼らのリーダーはラインハルトということになってしまっていた。彼は内政にまで口を出すにはまだ至らなかったが、それに近い位置づけに近づいていた。そうした時期に、ヒルダの元にあのキュンメルからの電子メールが舞い込んできた。一度どうしても会って話をしたいというのである。しかも執政官のラインハルトの一行で来てほしいという話であった。
ヒルダは長い間彼らと顔を合わせていなかった。風の噂で、キュンメルが絵画収集に目覚めているという話を聞いた。芸術家肌のメックリンガ―から自筆の絵画作品をもらい受けて、大事にしているという話だった。きっと孤独に暮らしている。申し訳ないと思う気持ちとともに、きっと恨んでいると思った。そして自分もできればあの館に戻った方がいいのかもしれないと思った。オーベルシュタインから前回の作戦の時、はっきり足手まといと言われた。その私が仮初めの婚約者のキュンメルのために彼らの予約時間を作る必要がある。おそらく断られるだろうと思った。そして、私は婚約した覚えはありません、という言葉を心の中で彼女は反芻していた。この状況を耐えなければならないのはなぜだろうと思った。不満が爆発しそうだ。しかし顔に出してはいけない、そう思いながら彼女は最初オーベルシュタインにこのような予定を入れてほしいのですが、と予定表を見せて言った。
「この人は君の婚約者かね。」
「そうです…。」
「我々と面会したい、それも足を運んでくれというのはなぜかね。」
「彼の意向だと思います。」
「ずいぶんと勝手な願いだとは思わんのかね君は。」
「…私もそう思います。」
「だったら予定をはずしたまえ。この件はなしだ。」
バカバカしいことであるが、一応言質は取らなければならない。キュンメルにばれるはずはないのだが、話は通しておく必要はあるのだ、そう思いながら席に戻りつつあったヒルダをラインハルトが呼び止めた。
「それはフロイラインの婚約者の人だな。非常に病弱だそうだな。職場仲間としてお見舞いに行ってもいいだろう。彼女の将来の夫となる人だ。」
「あの。」
「いや、全員で行く必要はない。ここにいる三人だけでいいだろう。」
「私も行くんですか。」
と、横からオーベルシュタインが言うと
「そうだな。たぶん来てもらった方がいいだろう。」
と、ラインハルトは答えた。
キュンメル邸にはランドカーで行った。なんとラインハルトが自ら運転していた。いつもは運転手の運転が多かったのだが、今日はどうも勝手が違ったようだ。オーベルシュタインが、あなたは最高司令ということになっておりますから、命の危険もあるのですがね、と言っても素知らぬ顔だった。
行ってみるとキュンメルは邸の中庭の東屋で休んでいるということだった。三人が中庭に出て見ると、ゴルフ練習場のような芝生が敷き詰められていた。
思わずヒルダが私のいない間に改装したのねと言ったら、東屋の長椅子に腰かけたキュンメルがヒルダに弱弱しい笑顔を見せて言った。
「僕が握っているこのスイッチがなんだかわかりますか?この芝生の下には鉄板の空洞があって、そこに高密度のゼッフル粒子が密閉されています。僕が起爆スイッチを押すと爆発します。」
オーベルシュタインが貴様、というのをラインハルトは片手で制した。
ヒルダは真っ青になっていた。とんでもない場にラインハルトたちを召喚してしまったと思った。彼女はおろおろ声で言った。
「なぜなの、キュンメル。あなたも死んでしまうわ。」
キュンメルはぜいぜい肩で息をつきながら答えた。風前の灯の命で、彼は語った。
「僕はもういいんだ。僕はもうどうせ死ぬ。それなら、ヒルダやそいつらと一緒に死んだ方がいい。だってそうでしょう?この男はゼッフル粒子でたくさんの将兵を焼き殺した。そんなやつは死ぬべきだし、ヒルダのそばに置いておきたくない…。」
オーベルシュタインが言った。
「貴様どこでその情報を手に入れた?作戦の詳細は一般市民には一切知らされていないはずだ。」
「どこだっていいでしょう。そう、敵国からですよ。帝国の専制政治は滅ぶべきです。同盟の民主主義政治が正しいのです。」
ラインハルトはそれを聞くと、胸元からペンダントを取り出してパチンと蓋を開けた。彼はじっとその中身を無言で見おろしていた。
「僕はいろいろな情報網からそれをつかんだ。それでローエングラム伯、あなたを罰することにしたのです。」
ラインハルトは無言で立っていた。何かの神示を待つ人のようだった。キュンメルは激高した。
「なんだ、僕の話を無視するのか!そんな物見るな!どうせヒルダの写真でも入っているんだろう!」
ラインハルトはそれを聞くと、ペンダントをキュンメルの方に向かって素早く投げた。
「確かめてみるといい。」
キュンメルが受け取るかためらった姿勢になった瞬間、ラインハルトは拳銃でキュンメルの手元を撃った。キュンメルがあっ、と起爆スイッチを取り落とした瞬間、オーベルシュタインがキュンメルに飛び掛かり押さえつけた。キュンメルは抵抗しようとしたが、すぐに動かなくなった。
「死んでますね。」
と、オーベルシュタインが体をのかせながら言うと、ヒルダは小さく叫び声をあげキュンメルに駆け寄った。
「どうしてなの、キュンメル。あなた、どうして…。」
ヒルダの目に涙が浮かんだ。それほど長い期間ではなかったが、彼女の献身的看病に、いつもキュンメルは弱弱しい笑みで答えていたのだ。今も彼は半分眠っているような顔で死んでいた。
ラインハルトはペンダントを拾いあげ胸元に戻すと、オーベルシュタインに言った。
「この男のパソコン歴を調べろ。思想的教唆から同盟側からのルートがわかるだろう。あと、この庭には遮断壁を作り、粒子を除去する手配をしろ。」
「は。」
「フロイライン。」
ヒルダは涙顔をあげて、ラインハルトの方を見た。
「あなたの婚約者には気の毒なことをした。彼の死期を早めたのは私だ。恨んでくれて構わない。」
と、ラインハルトは背を向け去りながらヒルダに言った。
リッテンハイム公は失脚した後、行方をくらましていたが、影で同盟側にいる帝国の亡命者であるメルカッツと連絡を取っていた。メルカッツは同盟内にあった臨時帝国政府の後始末を受けて、そういった連中と密議していた。しかし事態は思わしくなかった。それでリッテンハイム公は娘であるエルフリーデを差し向けることにした。いわゆるハニー・トラップである。この案はメルカッツは成功を否定的に言ったのだが、父親であるリッテンハイム公はそれで由とした。彼は何人も妾に子を産ませており、エルフリーデはそのような娘たちの一人だったのである。
最初エルフリーデはラインハルトのいる宿舎マンションの前でうろうろしていたが、セキュリティが厳しいので中に入ることができなかった。それで彼女はラインハルトの退社する時間帯を見計らって、待つことにした。
エルフリーデはその日わりと質のよいドレスを着ていた。ラインハルトがやって来たので、彼女は声をかけてみたものの、ラインハルトはほぼ無視して自動ドアを開けて中に入ってしまった。あわてて後をついて入ろうとしたところを、ラインハルトは彼女の顔を手でつかんで外に押し出した。エルフリーデは必死で、懐に隠していたナイフで刺そうとしたが、それも手刀で落とされてしまった。
「何すんのさ、童貞!」
と、エルフリーデが叫んだが、ラインハルトはすでにエレベーターの中の人であった。
ラインハルトのところはそういったことで無理だとわかった。というか、顔認証識別コードで、マンションへの入館は以後できなくなっていた。それで彼らが次に狙いを定めたのは、巷で漁色家であると言われていたロイエンタールであった。
ロイエンタールとミッターマイヤーはワルキューレ乗りの双璧と呼ばれた人物で、ミッターマイヤーは早くに結婚し、結構な愛妻家であったが子供がなかなか産まれなかった。それに対しロイエンタールはラインハルトらよりも八歳ほど年上だが独身のままで、彼は幼少時の母親の行動によるトラウマにより、女性に対し障壁があるようであった。つまり彼は左右両眼の色が異なるヘテロクロミアの眼の持ち主であったが、それは父親譲りのものではなく、母レオノラの遊蕩によるものであった。この母は父と違う眼を疎んじて、赤子の時針で突き刺そうとしたのだそうである。そうであるというのは、現場を目撃した小間使いの証言によるもので、むろん彼自身がそれを目撃したわけではない。しかしこの逸話は口さがない使用人たちの話から彼の耳に入り、幼少時深く心を傷つけられた。従って彼は成長時より女性遍歴を重ねるようになり、女性とはだいたいにおいてその遊蕩児で浪費家であった母親のようなものであるという認識であった。
今彼は作戦司令部の束の間の休暇で、キルヒアイスらも楽しんだ湖畔の別荘地帯に来ていた。アンネローゼが彼のテーブルの向いに座っていた。
最初電子メールで呼び出され、ラインハルトの姉であり、故キルヒアイスの幼馴染であるというヒルダも受け取ったメール内容を見て、彼が思ったのは面倒な女だということであった。彼女が元後宮の女だということはむろん彼は知っていたし、今のラインハルトの昇進に一役買ったらしいということも彼は理解していた。ラインハルトは彼の上司ということになりつつあったので、はじめはキルヒアイスの話でもして適当に相槌でも打っていようと思った。しかし実際に会ってみるとラインハルトとよく似た美貌の持ち主で、年齢よりも若く見えた。また話上手で、男を立てる感じの話し方をした。これに気をよくした彼は、ひょっとしてキルヒアイスの死が彼女に関係しているのではと思いつつ、アンネローゼとの逢瀬を重ねるようになっていった。
だがこれはアンネローゼの側はそうではなかったらしい。彼女は心が冷たい女に見えるだろうが、やはりキルヒアイスの死は痛手であった。同じ轍は踏みたくない思いがあり、ロイエンタールが自分と同年齢ぐらいなのもあり、彼が年下だったキルヒアイスほどうまく操縦できない男であることをやがて彼女は見抜いた。また同じ職場にいるヒルダのことを話に出してみても、彼はほとんど無反応であった。女慣れしている彼にとっては、ヒルダはただの事務員その一であった。焦りの中で、ただのアバンチュールとしてずるずると会い続けることで、たぶん妊娠するかもという危険性があった。皇帝に仕えている際には、彼女は後宮の妾として避妊薬を渡されていたし、器具も装着していた。彼女はその任を解かれたので、それらは自分で管理し用意しなければならなかった。そうした危険なゲームになりつつあったので、潮時をそろそろ言い渡そうと彼女は考えた。それで彼女は言った。
「私たち、そろそろ終わりにしましょう。」
「終わりと言うのは。」
「もう会わないということです。」
湖畔に一迅の風が吹き抜けた。
アンネローゼは白いつばひろの帽子を傾けて、そう言った。そういう時の彼女は、年若い女生徒のようであった。そのうなだれた様子は、貴婦人と言ってもよかったのだが、ロイエンタールには自分を刺そうとした母親と同じ種類の女に見えたのだろう。別れ話を切り出すのは彼の方が多かったせいもあった。最後に彼は残酷な事を言った。
「指輪がなければ、応じられませんか?」
「結婚できないという意味では…。」
「そういう意味ではないです。」
と言って、彼は席を立った。
今まで何度もあった別れの場面であった。湖畔の街から帰り、彼は首都の繁華街で酒に酔った。何軒かバーをはしごし、痛飲した。やはりあの女とは付き合うべきではなかった。だいたいラインハルトの姉という時点でやめておくべきだったのだ。
「これから俺の職場は地獄だな。ま、そのうち忘れるさ。」
と、彼は自分を笑った。職場でラインハルトを見るたびにあの女を思い出すだろうと思った。
足元がおぼつかない状態で、宿舎に帰ったのは深夜過ぎだった。玄関先に立っている女がいた。見知らぬ女であった。
「お兄さん、大丈夫?」
とその女が言うのを、ロイエンタールはドアを開けて無言で中に引きずり込んだ。女は何か言い、笑ったのだが、彼は事後女の腕に手錠をはめた。貴族の趣味道具のひとつを彼も持っていた。要するに監禁したのであった。
9.翻転
ロイエンタールがエルフリーデを監禁したのは、何のことはない、彼女が自分はリッテンハイム公の娘であると言ったからであって、しかもナイフ所持して刺そうとしたからである。下の下の手であったが、この娘を隠匿することにしたのは、一重に彼の性癖によるものであったし、それで将来的に不都合が起きるとはこの時点では予想していなかった。アンネローゼにふられた事も影響していた。彼女はロイエンタールのそういう気分を巧みに利用し、敵対関係を作りながら半同棲状態に持って行ったのである。おそらく頭のゆるいふりをしながら、彼女は湖畔でのいきさつも観察していたに違いない。つまり平たく言えばスパイであったわけなのだった。しかしこの事は長い期間作戦本部の面々は知ることはなかった。またロイエンタールは彼女を監禁することで、利益があると信じていた。つまり彼としては情報源のつもりだったのである。
イゼルローンは帝国側に再編成されたが、主砲が建設中であることは、同盟側にも筒抜けであった。同盟はこの機に数をそろえて一気に帝国をたたく事を軍部が言い出し、イゼルローンを追い出されたヤンもそれに従わざるを得なかった。トリューニヒトに従うのは彼の意に大いに反するところであったが、彼の仲間も帝国への反撃に同意し、艦隊は編成された。主星ハイネセンから延長の、バーラト星域、さらにその先のガンダルヴァ星域とバーミリオン星域が主戦場ということで案に制定された。彼らは第一陣の艦隊を差し向けた。まずは様子見であった。
彼らがその星域を主戦場に考えたのは、先のイゼルローン戦で使われたワープ航法に対する懸念からである。回廊内でのワープにより空間でのひずみ率が増大したと考えたので、その恐れが少ない宇宙空間を選んだのであった。帝国内にはまだ稼働中の要塞が何個か存在し、まさかそれらを同様にワープで使うとは思えないという意見もあったが、回廊内での戦闘は危険であるという意見で一致した。これにはヤンは不服であった。というのもそれらの星域は主星ハイネセンからの距離が近かったからである。彼は半独立的立場を取ったこともあるが、返り咲きすでに上級司令官に任じられていた。しかし軍部の決定に従うしかなかった。彼はユリアンに彼ら軍部は無能であるとこぼした。それでも敵の戦力を割くにはそれしかないでしょう、とユリアンは言い、イゼルローンにはまたいつか攻略できる時がありますとヤンに言った。
帝国側も同盟が動いたので艦隊を動かすこととなった。ラインハルトらはむろん今回はワープによる戦闘は考えていなかった。その点は彼らも承知していた。同盟側の艦隊の配置を見たラインハルトは、艦隊をスライドさせ順送りに前線に出す方法を言った。
「それには何の意味があるのですか?」
とミュラーが問うと、ラインハルトは少ない戦力で多いと見せかけるものだ、と言った。
「同盟側はおそらく持てる艦隊のすべてで包囲するであろう。戦力比から見てそうするであろう。そこが狙い目だ。」
「すると包囲された艦隊は死力を尽くすことになりますが。」
とオーベルシュタインが言うと、
「そこは私が出る。別部隊を編成する。ロイエンタールにヒルダを補佐官としてつけて行ってもらう。」
とラインハルトは言った。
「つまりいつかの復讐戦というわけですか。なぜロイエンタールに行かせるのですか。」
と勘が鋭いオーベルシュタインが問うと、彼が適任と思うからだ、とラインハルトは短く答えた。作戦会議は散会となった。
ヒルダはこの任務を聞いた時、先のキュンメル邸での一件を思い出していた。あのゼッフェル粒子が満杯の鉄のプールを果たしてキュンメル一人で建設したのだろうかと。誰か手助けした者がいるはずだ。ラインハルトらの話では同盟側からの教唆であるという話だった。確かにキュンメルはそのような事を言っていた。でも――あの時、彼はどうして胸元のペンダントを見ていたのだろう。キルヒアイス伯に助けられた自分の命に対する罪悪感。そう、無数の犠牲の上に我々作戦指令室は成り立っている。だから彼はその意味で見ていた。それはおそらく間違いではない。彼女はそう思った。
今回の作戦も、私の考えるところでは重包囲網が卿の艦隊には展開される。それでいいのだろうか。もしかして、あの鉄のプールも――と彼女は考えて首を振った。上に立つ卿が滅びの美学に魅せられているなど考えたくもない。私がしっかりしなければならない。しかしあの山荘からの帰り道に思ったことはやはり本当だったようだ。やはりあのキルヒアイス伯がそばにいないことは、卿の精神状態を非常に不安定にさせているのだろう、と彼女は考えた。
彼女はハイネセンに派遣されることまではまだ知らなかった。ロイエンタールに随伴せよ、とだけラインハルトからは伝えられていた。彼女にとって辛い局面がこれから待ち構えていた。それはつまり、ハイネセン制圧をロイエンタールの横で確認せよということなのであった。これは彼女のような穏やかな心の持ち主には耐えられることではなかった。しかしラインハルトはこの時それを彼女に強いたのである。
後にバーミリオン会戦と呼ばれるこの戦は、同盟側の数段並んだ艦隊列の前面に、ラインハルトらの旗艦が現れたところで口火が切って落とされた。彼が言ったとおり、前後の艦隊を入れ替えることで一見永久機関のような動きでラインハルトらの艦隊は進んだのだが、ヤンらはすぐにこれを見抜き、包囲陣を開始した。しかし戦力比に差があるとラインハルトが言ったとおり、包囲はそれほど厚いものではなく、ヒルダが心配したほどの重包囲ではなかった。同盟側は来るイゼルローン再攻略に備えて、予備艦隊を温存していた。つまりその場で持てる分だけ、とラインハルトが言った通りの展開になったのである。
ヤンはこの展開には拍子抜けしたのだが、包囲網を狭めるにつれ、中心の艦隊からワルキューレで爆雷を包囲の密集地帯の艦隊列に仕掛ける戦法を見て、やはりこいつはそれほどバカではないと思った。しかしヤンはこれが時間稼ぎであるということには気づかなかったのであった。
ロイエンタールらの艦隊は、主戦場からかなり離れた航路を取った。ハイネセン本星には迂回したので、ヤンらには気づかれることはなかった。しかし近づいてくる本星を見て、ヒルダの懸念は大きくなった。これはだまし討ちなのではないか、と彼女は思った。彼女が疑惑の眼で見ている前で、ロイエンタールは降下せよ、と部下に命じた。その時彼は外部回線を使ってメルカッツを呼び出した。それはエルフリーデから聞き出していた暗号によるものだった。ヒルダから見える艦橋のデスクパネルにだけ、その映像は映された。むろんロイエンタールはヒルダがそれを見るであろうことは知っていたし、彼女がどうするか見たかったのである。
ロイエンタールはアンネローゼからの話で、ヒルダの出自は聞いていたし、その恨み言についても聞かされていた。しかし彼はアンネローゼの頼みは聞き流した。おそらくそのような事情でキルヒアイスは死んだのだな、と彼にはうっすらと見当がついた。そして自分は関係ない立場を取りたいと思った。だが今回自分の任務にヒルダを立ち合わせたラインハルトの真意は、むろん自分がエルフリーデを匿っていたことも承知の上で、この俺に悪役をふらせたいということなのだと思った。この場でメルカッツになびくという方法もあるのだが、そのメリットがとても少ないこともラインハルトにはわかっているのだろう。なるほどただの秘書官では飽き足らないのか、と彼は思った。とんだ茶番だが、こんな事は制圧作業のついででしかない。早く済ませないとなと彼は思った。彼もまた軍人であった。
呼び出されたメルカッツはとまどっていた。
「なんだ貴様は。なぜこの回線を知っている。」
「南国の薔薇は手折りました。帝国軍人として申し上げます。今すぐトリューニヒトと話し合って降伏することを勧告します。我が軍はそちらの政府施設にいつでも照準を合わせられる。」
「なんだと貴様、ふざけるな!」
「広域放送でいたずらに民衆を扇動はしたくない。早くご決断することですな。」
「民衆を盾にする気か。卑怯千番…!」
「亡命者に言われたくないですな。では。」
回線を切ったロイエンタールが顔をあげると、ヒルダが震える手で拳銃の照準を合わせていた。ヒルダは押し殺した声で言った。
「おやめなさい。今すぐに。そんなことは。」
ロイエンタールは腰の拳銃に手をやり、ゆったりと構え向き合った。彼は言った。
「手が震えておいでだ。人を撃ったことはありますか。ないでしょう。あなたにはできませんよ。同盟の味方をする気ですか。」
ヒルダは身を震わせながら必死に言いつのった。
「こんなことは許されません。神様がきっと許しません…!」
「残念ながら今は戦争なのですよ。あなたが気にかけている男が命じたものなのでね。君はそれを認めないといけない。」
一声銃声がして、ヒルダはあっ、と腕を押さえて頽(くずお)れた。ロイエンタールが正確に撃ったのだった。ヒルダの拳銃は銃弾に当たり床に転がった。
うなだれたヒルダの両脇をすぐに衛兵らが腕で取り押さえた。営巣に連れていけ、とロイエンタールは冷たく命じた。まるで計画通りだなと彼は思った。連行されるヒルダの両眼に涙が光っているのを彼は見た。
これから彼女は牢屋で必死で考えるだろう。彼の真意、彼の良心について。ほとんど彼らは深く話し合ったことはないというのに。そういう関係もあるのだな、とロイエンタールは思った。文学少女的関係か、と彼は整理した。自分も十代の頃はそういう魂の牢獄を感じたこともあったが、もう忘れたと思った。そしてあの男は今は彼女の心を閉じ込めたが、すぐに彼女は身を翻し逃げ出すだろうと思った。今まで俺にもそのような女が多かったのだ、と。
帝国からの脅しを受けて、トリューニヒトはすぐに降伏のサインを出した。彼はイゼルローンが帝国側になった瞬間から、自国が不利であることを考えていた。想像力のある彼は、ワープ航法による本星への攻撃の可能性を考えていた。決して付和雷同ではなかったのだが、メルカッツや交戦中だったヤンはその折れ腰に激怒した。彼らはしかし、同盟が帝国の属国化しても留め置かれた。ロイエンタールの軍はそのままハイネセンに駐留し、ラインハルトからその領主の主命を受けた。
10.客死
首都星オーディンの山岳部はその日北風が吹いていた。季節の変わり目、温帯のこの地方にはよくある気象現象である。その小糠雨の中を、一人の少女、エルフリーデが急ぎ歩いていた。彼女は雨の中、アンネローゼの山荘前で犬に吠えられて立ち往生していた。どなた、と声がしてアンネローゼが中から現れた。エルフリーデは傘もささずに歩いてきたようだった。
「びしょ濡れなんだ。中に入れてくれないかな。あんたに用があって来た。」
と、コート姿のエルフリーデが言うと、アンネローゼはとまどった様子だったが、やがてどうぞと中に入れた。この山荘目掛けてやって来る人間は今はもうめったにいない。相手が年若い少女だったのでアンネローゼは中に通した。すでに彼女が後宮にいた時から数年がたっており、もう軍部の人間の足も途絶えて久しかった。またロイエンタールとの別れ話があって以来、彼女は人を避けていた。遠い噂で弟のラインハルトが宰相に任じられたという噂を聞いた。しかし弟からの連絡は途絶えていた。
「あんたに見せたいものがあってさ。これなんだけど。」
と、エルフリーデは暖炉の前でコートを脱ぐと、バックパックからビニール袋を取り出した。中に書類の束が入っているのが見えた。警察関係のような形式のものだった。エルフリーデは面白そうに言った。
「これ、なんだかわかる?私の親父の残した調査書類なんだよね。あんたの弟の犯罪歴が書いてある。それであいつは宰相どまりなんだよ。皇帝にはなれない。」
アンネローゼは思わず袋を取り、中身を取り出した。書類には見慣れた弟の顔写真が上部に貼ってあった。
「あんた皇帝の妾だったんでしょ。話はロイエンタールから聞いてるよ。あたしも妾の子なんだよね。あのリッテンハイム公のね。」
と、エルフリーデは言いながらポケットからタバコを取り出し火をつけた。
「それ言い値で買ってくんない?ちょっとお金に困ってんだ。そんなにふっかけないからさ。ま、手数料かな。」
「…わかったわ。いくら?」
「話がわかるじゃない。その写真の男、あんたの恋人だったんだって?弟さんまたなんで殺したんだろうねぇ。そいつ親父に握られてたから、弟さんも政界で苦労してんだね。」
アンネローゼは立ち上がり、箪笥からお金を取り出すと、エルフリーデに握らせて言った。
「誰にも言わないって約束して。」
「そいつはどうだか。私は気ままな渡り鳥なんでねぇ。ま、下手にばらすと私もやばいから、なるべくご期待に沿うようにするよ。それはそうと、ロイエンタールとはどうして別れたのお嬢さん。あいつはそいつらよりずっといい男だよ。」
エルフリーデはそう言うと、けらけらと笑いながら山荘を後にした。
アンネローゼはしばし茫然としていた。しかしあわてて書類をめくっていった。しばらく血相を変えて彼女は書類を眺めていたが、やがて彼女は顔をあげ、エミールを呼んだ。
「エミールあなたにお話があります。もう一度孤児院に戻りなさい。」
「え、どうしてですか。」
「いいからなんでも、戻るのよ。そして人があなたを呼ぶまで待機しているのです。いいこと?」
「…はい。」
ハイネセン制圧後独房に二週間入れられたヒルダは、反省文を何枚も書かされ、労働奉仕したのちに釈放された。これでもう私は解雇されたはずだと彼女は思ったのだが、廊下でオーベルシュタインが待ち構えていた。
「君は残念ながら一般人の生活には戻れない。そう、いろいろなことを知りすぎている立場だ。」
「…はい。」
「作戦に対して不満があったのは認めよう。しかしあの場合、降伏を勧告するのは最良の方法だった。君はどうしてそう思わなかったのかね?なぜなら敵味方双方痛み分けでそれ以上の犠牲を出さずに済むからだ。」
「…その通りだと思います。私の浅慮でありました。」
「わかればいい。君は今日づけでローエングラム公の専属秘書に抜擢だ。私は反対したのだがね。ああいったまねをされては困る。」
「…。」
「今後よく注意するように。」
オーベルシュタインはヒルダとともに歩きながらそう言うと、執務室に入ってしまった。ヒルダはその場であの作戦は本当にラインハルトが考えたのですか、と尋ねたかったが、それは聞けなかった。彼がそういう人間であったということは、私とは関係ないのだ、と思った。それは独房の中で何百回となく繰り返し考えたことだった。幻滅したからどうだというのだ。私の人生とは無関係なのだ。何も思い迷うことなどないのだ。ただの職場の人間なのだ。
翌日からヒルダはラインハルトの秘書官として働く毎日となった。予想した通りそれは多忙な毎日だった。彼は最高司令と宰相を兼任していた。ヒルダは粗相のないよう努めるのに精いっぱいで、余計なことは考えないようにした。帝国の領土が広がったことで、彼は一応善政を敷いている為政者となっていた。特に財政上で問題な行動もなかった。若いのによくやっているという民衆の評価だった。しかし彼は公共の場にはほとんど姿を見せなかった。従って大観衆の前で手を振るなどの示威行為もなかったのである。
今ヒルダはラインハルトとともに執務室横のテラスで昼食を摂っていた。各々食べていると時間のロスがあるので、そういうことになっていた。むろん毎日というわけではなかったが、週のうち何回かはそうした時間があった。それはヒルダにとっては気づまりながらうれしい時間ではあった。気づまりというのは今まで彼の立てた作戦がほとんど彼女にとっては空前絶後のものばかりで、良心に照らし合わせると頑じ得ないものばかりだったからである。うれしいというのは彼は美貌の持ち主だったし、その態度は紳士的だったからだ。そういう天が二物を与えているような人間は、やはりめったにお目にかかれないものだからだ。
今彼女はゴールデンバウム王朝の最後の姫宮についてラインハルトと話をしていた。
「あの方はあのままになさるおつもりですか?まだ幼い方でいらっしゃいますが、長じると貴族らに利用される恐れがあります。」
「それは先の幼帝事件のことで言っているのか。」
「そうです。ラインハルトさまは人がどうやって集まっていくと思われます?」
「どうやってとは?集団心理のことだろうか。」
ここでヒルダは言葉を強調するように言った。
「敵、ですわ。共通の敵が存在すると、人は結束し行動に移します。共闘認識が人の集団意識を高めるのです。そういう集団心理下ではどんな残酷なことでもやってのけます。」
「フロイラインの考え方は一理ある。しかし私はあの姫宮はあのままにしておく。ゴールデンバウム王朝を廃位するつもりはない。たとえその存在がわれわれ影の内府に敵として障害になろうともな。その時はその時でまた考える。」
「そうですね。廃位なされば、世間に冷酷な君主と思われますから。」
ラインハルトはここでヒルダの顔を見たが、また穏やかな口調で続けた。
「私は皇帝になる器の男ではないよ。フロイラインにはよくわかっていると思うが。では。」
ラインハルトはそう言うと席を立った。テーブルに残されたヒルダはしばらく無言で座っていた。話したかったことはこんな事ではなかった。しかしそうした会話が彼らの間では続いていた。
それからしばらくたって、ラインハルトはヒルダに、私の身の回りの世話をする人間を一人雇ったから、君は今後はそういう事は気兼ねなく任務遂行するようにと言った。ヒルダはその事を聞いて、少し打撃だった。彼の持ち物をそろえたり、会議の時の服装を整えたりすることは、実はひそかな愉しみであったのだ。それらはエミールというそばかすの少年が行うことになった。幼年学校の少年兵という話であった。ヒルダはエミールという名前に聞き覚えがあったが、それがどこでかははっきりと思い出せなかった。
同盟側は国としては存在しなくなっていたが、帝国への抵抗を続ける勢力は各惑星で補給を続けながら航行を続けていた。そのひとつがヤンたちの艦隊であった。不思議なことにラインハルトらは彼らを放逐し、殲滅しなかった。あるいはオーベルシュタインの言うところの犠牲を少なくするという目的であったのかもしれない。とにかく同盟への賛同者の難民を乗せて、彼らは宇宙空間を渡航していた。
艦橋に座るヤンは言った。
「そろそろイゼルローンに帰還してもいい頃だろう。」
ユリアンが尋ねた。
「あそこは今帝国領になっています。再占拠は難しいと思いますが。主砲のトゥールハンマーが最近再建造したという噂です。」
「だからさ。我々に出番が回ってきたというわけだ。」
ヤンはユリアンに紙片メモを渡した。
「この通りにやるんだ。彼らには不可能だ。」
ヤンの作戦を聞き、彼らは準備を急いだ。
イゼルローンにはルッツの艦隊が駐留しており、ラインハルトの命を受けて待機していた。ヤンの艦隊の航跡はむろん彼らにはわかっていた。まず艦隊同士の砲撃戦があった。
「危険です、ヤン提督。彼らはイゼルローンの主砲を発射してきます。」
ユリアンが言うのに、ヤンは首を横に振った。
「主砲は発射できない。彼らにはできないはずだ。白兵戦で内部を占拠せよ。」
ヤンが言う通り、帝国側は主砲を発射することはなかった。そしてルッツの艦隊は同盟側がイゼルローンに取り付き、内部から侵入し中の兵士を虐殺するのを見ているままだった。
ウドの大木だな、とヤンはひとりごちた。
シェーンコップらは要塞内で強化スーツで電檄斧を奮いながら、なんてこいつらは弱いんだ、と強襲した。たちまちあたりは血の海と化し、兵士らの挽きちぎられた死体で埋め尽くされた。彼らは主砲のコントロールルームを目指した。そのドア開閉装置の暗号キーもヤンの用意した暗号文で難なく開いた。ユリアンやヤンも後に続いていた。
コントロールルームには巨大な電子パネルが並んでいた。それらは皆稼働していなかった。暗黒の壁が沈黙を守っていた。ヤンは言った。
「この暗号文を入力しろ。こんなこともあろうかと、要塞から逃げる時に電子脳部分をハックしていたんだ。みな動作停止状態だ。」
「さすがですね、ヤン提督。」
「我々にしか動かせないんだ。この主砲で今からあの帝国の艦隊群を攻撃する。」
ヤンに渡された紙片にある、ロシアンティ―についてのある書籍の説明文の一行をユリアンは注意深くキー入力した。コンソールが反応し、壁のパネルは皆青白い蛍光色に変わった。
「やったぞ。さあ照準合わせだ。」
ヤンが主砲を稼働させ起爆のスイッチを押した瞬間だった。ルームはその瞬間すさまじい爆音を立てて破壊された。
「ヤン提督!」
ユリアンは叫んでいた。彼らはルームごと吹き飛ばされていた。主砲台は跡形もなく爆発し続けていた。
「…なんてことだ…。」
シェーンコップがつぶやいた時、彼方からドローンらしい物体の群れが現れた。
ヤンは爆発で床に倒れていたが、その上から天井に取り付いたドローンの一体が左脚あたりを素早く狙撃した。それは、あらかじめ予定されていたような動きだった。なぜならドローンは他の兵士たちには心臓部分を狙撃していったからだ。そして、同盟の兵士のほとんどが倒れた中で、ユリアンだけが生き残っていた。彼もドローンに狙撃されていたが、幸いなことにそれはつま先であった。
ユリアンは足を引きずりながら、ヤンの体の方に這いずって行った。
「ヤン提督…ヤン提督…!」
ヤンの左脚の狙撃部分には大腿動脈瘤があるところだった。大量に血が流れだしており、すでにヤンの意識はない状態であった。
ユリアンは両手を当てて血を止めようとしたが、やがてあきらめて顔の涙を拭いた。顔が血で汚れて真っ赤になった。
「こんなことで…、フレデリカさんになんて言えば…。」
その時破壊されたパネルの一部に白い文字が静かに浮かびあがった。ユリアンの眼には、それは無味乾燥なものだった。
―キミノ王国ダ―キミタチノ王国ダ――
ヤンはこの文字を見ることなく、床に髪を散らして息を引き取った。そばに彼の愛用のベレー帽がころがっていた。彼は数か月前にささやかな結婚式を、艦隊内で挙げていた。フレデリカ・グリーンヒルがそのお相手であり、彼らは仲むつまじく艦隊内の一角で暮らしていた。フレデリカが強襲部隊にいなかったのは幸いであった。ユリアンは膝を押しかがめて泣いた。
この時ドローンがヤンの左脚を撃った理由、それはキルヒアイスがあの日ヒルダにタックルをかけたのと同じ脚だと言えばおかしいだろうか。
イゼルローン要塞は、再建造計画に不備があったという理由で放逐された。ルッツの艦隊は本国に帰還し、ラインハルトは報告を受けた。残存勢力がまだ要塞内に残っています、と言われても、彼は掃討を命じなかった。再建計画は白紙に戻された。
その頃超高速亜空間飛行システムに画期的な開発が起き、フェザーン回廊を通過するルートでも輸送が早くなる運行改革があった。
イゼルローン要塞は砲台跡として残り、ただの関門所としてラインハルトの命により存続されることとなった。ユリアンとフレデリカは要塞内に反帝国同盟のサークルを存続させたが、それは小規模な自治領として残存した。
11.黒き森
ヒルダは夢を見ていた。
またあの木製の人形が立っていた。またこの夢だわ、と彼女は思った。人形は深い森の中に立っていた。湖面の上に彼女と人形はいた。すうっ、と足元を風が凪いでいた。私は宙に浮いているんだわ、とヒルダは思った。宇宙みたい。
と、人形が小首を傾げた。その頭に金色の王冠がかぶせられている。
ああ、あなただったの、と彼女は思った。
やっぱりそうだった、あなたでしたね。
そう思った時目が覚めた。枕元の目覚まし時計が五時を指していた。彼女は起き上がり、支度をはじめた。出勤にはまだ早いが、何かが頭でかちりとはまったような気がした。朝の光が窓から差し込んで、ヒルダの顔を白く照らし出した。彼もこの光を見るといいのにと彼女は思った。そうして階下に降りて行った。
その日ロイエンタールは久しぶりに首都星オーディンに帰還していた。ハイネセンに駐留していたうちに、街は以前よりもビルが立ち並び、近代的な様相を押し進めていた。
彼はこれから貴族らの内輪のパーティに出席するつもりだった。公的な催しものはラインハルトの治世になると、縮小されていた。以前のフリードリヒ4世の治世ではそのようなパーティがよく催されていた。ランドカーで移動して形ばかりの仮面をつけると、彼は夕暮れの会場内に入っていった。
中では紳士淑女の群れが笑いさんざめいていた。それは以前の頃と同じであった。そう、彼が何度もアバンチュールを楽しんだ頃のものと同じであった。と、彼は会場内にひときわ大輪の花のような美しさの女性を見つけた。
彼女は仮面をつけていたが、彼にはすぐにアンネローゼだとわかった。山荘に隠居していたはずだったが、これはどうした風の吹き回しだと思った。シャンデリヤに照り映える銀色のクリノリン姿で、宝飾品は彼女の薄い金色の髪のそこここにきらめいていた。優雅に扇で口元を仰ぎながら、彼女はすべるような足取りでロイエンタールの前に現れた。
「お久しぶりですわね。お元気でいらっしゃる?お別れしてから、わたくし涙に暮れておりましたの。またお会いできてうれしいですわ。」
と、彼女は低くささやいた。皇帝に気に入られた時からの、彼女の教育された気品あるふるまいであった。ロイエンタールは内心苦笑しながら、礼をして彼女の手を取った。
「グリューネワルト伯爵夫人には、わたくしがハイネセンの太守であることはお見通しなのですな。もったいないことであります。」
「あらそうでしたの。わたくし少しも存じ上げませんで。踊りましょう。」
二人は観衆の見ている中で、優雅なワルツを踊った。その後二人はシャンパンを片手にテラス席に出て涼んでいた。
「あなたにお会いできるなんて思いもよりませんでしたわ。すっかり風に酔ってしまって。」
「いや、なぜあの時私から逃げたのですか?」
「あらそれは…あの時は今とは違います。弟もまだ宰相の地位ではありませんでしたし。わたくしも落剝の身でしたから。」
「なるほど。今は違うというわけですか。」
「ええそう。わたくしにもまた後ろ盾ができましたので。あなたとも以前のようにおつきあいできたならと思うのですけど。」
「ハイネセンは遠いですよ。」
「かまいませんことよ。弟の作った今の世の中はつまらないんですもの。こうした会合も私人の集まりということになっているでしょう。陛下が生きていらした頃は違いました。」
と、ここでアンネローゼはロイエンタールの膝に手を伸ばして言った。
「時々オーディンに還るという約束をしていただけるのなら、わたくしはいいのですわ。」
「なるほどね。」
と、ロイエンタールはうなずくと、では河岸を替えましょうか、と言った。ええ、とアンネローゼは少し笑ってうなずき立ち上がった。
それから少したったある日。
その日ヒルダは会議に出席するラインハルトらを送り出し、執務室に帰ってきていた。時計は午後五時を回っていた。そろそろ会議場から彼らが帰ってくる頃だと思い、階下を窓から眺めた。執務室には大きなステンドガラスがはまっている。教会みたいね、と彼女は勝手に思っていた。むろん教会の装飾のようなものではない、直線的なデザインであったが、色ガラスから差し込む光は部屋を明るくしていた。
と、その時到着したランドカーに駆け寄る男が窓から見えた。ヒルダが見ている間に、男は何か火炎瓶のようなものを車に向かって投げつけた。ヒルダがあわてて階段を駆け下り、玄関先に走っていくと、男が燃えている車を指さして叫んでいた。
「ヴェスターラントの時のことを思い知れ!金髪の孺子(こぞう)!俺の家族はあの爆発で死んだ!」
騒ぎを聞いて警備兵が男に次々と飛び掛かり、たちまち上から押さえつけた。男はばたばたと足で暴れていたが、手錠をかけられ連行された。
燃えている車の横合いから、オーベルシュタインに肩車をされてラインハルトが出てきた。少しケガをしているようだが、命に別状はないらしいのを見て、ヒルダはほっとした。おそらく先に車から降りていたのだろう。しかし危ないところだった。
執務室に彼らは移り、ケガの手当をした。ヒルダの昔薬剤師として働いていた知識が役に立った。長椅子に横になったラインハルトの肩に包帯を巻き終えて、ヒルダはこれで大丈夫ですよ、と言った。
「念のため今日は帰宅の際警備兵をつけましょう。」
と、オーベルシュタインが言うのを、ラインハルトは止めた。
「大事ない。私は今日はここに残る。」
「しかしあれはテロ組織の一員だと思われますが。ここにいるとまた狙われるのでは。」
「移動する方が危ない。私は少し熱があるようだ。動きたくない。」
「熱ですか。」
「今まで黙っていたが、このところ夕方頃微熱が少しある。だが執務に差しさわりはないので言わないでいた。今回は少しこたえたようだ。」
「それはいけませんですな。」
と、オーベルシュタインは言い、ヒルダに向かって
「公に何かよくなる薬を処方しろ。君には少しその知識があるのだろう?下の階に薬剤の保管室がある。こんなこともあろうかと施設内に作っておいてよかった。」
「はい。」
と、ヒルダは答えたが、ラインハルトはさえぎった。
「時間がかかるのならいい。調合せねばならないのだろう。」
「なんとか早くやってみます。」
オーベルシュタインが横から言った。
「無理はいけません。ヒルダ嬢に任せることです。ケガもしておられますからな。」
「…わかった。まかせよう。」
ヒルダは下の階の医務室兼倉庫で薬剤を探し、調合した。薬は基礎的なものしかなかったが、解熱作用のあるものを選んで飲み薬を作った。やはり四五十分ほど時間はかかり、薬を手に戻ってきてみると、オーベルシュタインはいなくなっており、他の局員たちも退社していた。
「オーベルシュタインさまは?」
と、ヒルダが尋ねると、ラインハルトは
「飼い犬の餌やりに早く帰れと言って追い返した。あれは犬を飼っているんだ。老犬らしい。拾ったそうだ。」
と言って起き上がった。ヒルダが薬を飲ませると、少しむせながらラインハルトは薬を飲んだ。
「すぐによくなりますから…。」
とヒルダが言うと、君は母親みたいだな、とラインハルトは少し笑った。
「今日はここに泊まられるのですか。」
「ああ。下に警備員はいる。こうしていたらいいだろう。」
「でも。」
「さっきの男の言葉を君も聞いたろ。私は死んだ方がいい人間なんだ。特に君が心配することはない。」
「あんな人の言うことは間に受けるべきではありません。だいたい、卑怯です。いきなりあんな…。」
「卑怯者というのなら、私がそうだな。昔キルヒアイスにもヴェスターラントのことは同様に言われた。それを思い出すためにも、こうして首にかけている。すまない、君には関係のない話をしてしまった。」
「あの攻撃は卿が命じられたのではありません。確かそうではなかったのでは?」
「しかし私は見て見ぬふりをした。君なら止めただろう、この前君が営巣入りした時のように。君は勇気ある人間だ。」
「それは違います。卿はたくさんお考えになって、その中からその選択をされるのです。いつもそうです。私にはそれがわかります。私のはただの向こう見ずの勇気です。子供の勇気です。」
「しかしそれが正しい時もある。それは純粋な正義だ。彼は私よりも純粋な人間だったのだ。」
ヒルダはそこでため息をついて言った。
「もうやめましょう。そういう考え方は体によくないですわ。卿は今多くの人間に必要とされているのですから、今夜はゆっくり体を休めてください。私はこれで帰ります。」
ヒルダはそう言って、椅子にかけたコートを手に取った。その後ろでラインハルトは宙空を見つめ、一言つぶやいた。
「…帰らないでほしい。私には君が必要だ。」
ヒルダはその時、瞳から大粒の涙をこぼした。聞こえないふりをして帰ることもできた。そうすれば明日からまた同じ日々が続くはずだった。同じ安寧の日日が。でも彼が、おそらく藁をも掴む思いで口にしたのだ。そう思いたかった。それならば私は良い藁しべになろうと思った。彼がそういう人間であったと思い絶望したあの日々を、彼女は消したかった。
翌朝マリーンドルフ邸の庭掃除を朝早くからしていた使用人のハンスは、ヒルダお嬢様が疲れ切った顔で朝帰りしてきたのに出くわした。また営巣入りみたいなことだったのかとハンスは尋ねたが、ヒルダは首を横に振って
「同じようなことよ。」
とだけ答えた。しかし玄関先で彼女と会ったマリーンドルフ伯はすぐに養女の異変に気付いた。彼は言った。
「おまえ朝帰りしたのか。」
ヒルダはええ、お父様と答えた。
「おまえはマリーンドルフ家の長女ということになっとる。相手は誰だ。」
「何もなかったわ。」
「嘘をつけ。待ちなさい、ヒルダ、ヒルダ。」
ヒルダは階段をのぼり自室に入り中から鍵をかけた。養父からの追及は今は聴きたくなかった。ベッドに身を投げ出し、固く目をつむった。
彼との接吻は待ちわびていたものだったが、あの愛撫は病人のそれではなかったように思う。私はまただまされたのだろうか。あの時と同じ――あの時と。また職場で。なんて学習能力のない――彼女はそう思った。今日が公休日でよかった。そのため卿もあのようなふるまいに出たのだろう。今後ずるずると関係は続いていくのだろうか。私は拒否できる自信がない。馬鹿なことをしてしまった。愛というなら愛していると思う。でも向こうはそうでないとしたら?
休み明けの顔合わせの時、ラインハルトは彼女のことを見ないようにしているようだった。つまりやはりそうだったのか。と、彼女は思った。彼女も自分からその事をにおわせないようにふるまった。そのまま二人はそのようなことは一か月ほどなかった。転機はようやく彼女は思い立ち、まさか一回のことでと思いつつ妊娠検査薬を試してみた時だった。結果は陽性だった。ヒルダはこの検査薬の反応には気が動転した。今月の生理が来なかったので家で試してみたのだ。養父に相談したらどうなるだろうと思った。高齢な養父には連れ合いは先立たれて存在せず、親身になってくれそうもなかった。とにかく勇気を出してラインハルトにこの事を言わなければと思った。たぶん彼は堕ろせと言うに違いない。その時の掻把の痛みを想像して彼女は夜ベッドで泣いた。薬学を志したことがあるので、そういう医学的知識はあったのだった。
しかしその翌日の早朝、庭師のハンスは朝早くに邸宅前にランドカーが到着し、スーツ姿で赤い薔薇の花束を持った男性が颯爽と降り立つのを見てあっけにとられた。
「もう起きておられるだろうか?」
「え、あ、たぶん。」
「お邪魔させていただいてもよろしいだろうか。」
「お嬢様も旦那様も朝はわりと早いですだ。」
「それは助かる。」
ヒルダは最初寝間着姿で出てきて、階下にラインハルトが花束を持って立っているのに気づき、あわてて部屋に入り服を着替えた。養父が何か話しかけているのが下から聞こえた。お父様、私が話します、と大声で叫んで、彼女は階段を急ぎ降りて、ラインハルトを応接間に引き込んだ。養父も後について入ろうとするのを、彼女は押しとどめた。
「少し二人で話させてください。」
「しかしな、おまえ。」
「あとでちゃんとお話しますから。」
ドアを後ろ手で閉めて、彼女ははあとため息をついた。そして言った。
「どういうことですか?」
ラインハルトは下を向いて言った。
「どういう事ではない。私は責任を取らねばならない。君のおなかの子のことで。」
「なんで知ってるの?」
「君のことならなんでも知っていると言ったらきっと語弊があるのだろう。だが守る必要があると思った。それで取り急ぎ来た。まずこれを受け取ってほしい。」
ラインハルトが渡した花束は、ずっしりと重かった。その後彼は何冊かの通帳を手渡した。
「これは?」
「あなたへの約十年間ほどの送金だ。記録として残してある。その…若い頃の…。」
ヒルダは開けてみた。その細かな数字の羅列は、ある事を雄弁に物語っていた。雨の日も風の日も、入金のリストは続いていた。
ヒルダの眼からぽつりと涙が落ちた。
「あなた…だったんですか…では…あの時の…。私が…孤児院で…。」
ヒルダの眼にあとからあとから涙が湧いてあふれてきた。肩を震わせて彼女は言った。
「ど…して言ってくれなかっ…こんな…大事なこと…。」
「それは全額私の出した金ではなかったからだ。言えなかった。それと、もうひとつ君に渡しておかなければならない物がある。」
「え…。」
涙顔をあげたヒルダの目の前に、一枚のカードが差し出された。
「君のことを読んだ詩だ。おそらくそうだと思う。生前詩の朗読会で彼が作った。君を汚した男が。」
カードは古いもので、数行の詩文の下に、ジークフリード・キルヒアイスの流れる文字の署名がしてあった。
「私は彼を排除した。自分の欲のために。それでも君がいいというのなら、この手を取ると誓ってほしい。できなければ、おなかの子は処分してくれてかまわない。私は男だから、こんな言い方しかできないが…。」
「排除って…、つまりそれは…。」
殺したんですか、とヒルダは口の中だけで唱えた。声が出なかった。いいえ、彼は多くの犠牲の上に立っている人だ。それはわかっていたはずなのに。
その時応接間のドアが開いて、養父が入ってきた。廊下で立ち聞きしていたらしい。
「すまないが、今日はもうお引き取り願えんか。娘も疲れておる。わしらでこの問題についてはよく話し合うから。どうか今日のところは、なあ。」
と、マリーンドルフ伯は言った。ラインハルトは素直に立ち上がった。
「フロイライン、返事はなるべく早いうちにお願いする。では、失礼する。」
と、彼は言った。
『秋
失せやすい思ひ出に 夢路に行き来して
かのラインの乙女は 黄金の中に
炎の輪にとらわれし騎士は 引き止めたり
することの 何といふよろこび
思ひ出はすぐ傍にやって来て 夏よりも
よく見られたものだ…
かうしてすべては赫ける絵のやうだった
それにひきかえ 夏には 夢の乙女は影絵の趣になっていた
そうして樹々は 自分らの家で 仕事をしていた…
ジークフリード・キルヒアイス』
ヒルダは詩文に見覚えがあった。たぶんリルケの詩だ。書き換えて作られている。夏というのは日の光が黄金色だから、たぶんラインハルトのことなのだろう。詩の朗読会がいつ頃行われたのかはわからない。ヒルダには幼い頃に一緒に歩いたキルヒアイス少年の顔は思い出せなかった。かろうじて覚えているのは、言葉を交わしたことのある幼いラインハルトの顔だけだった。
そうして彼は知っていたのだ。私がキルヒアイスに襲われたという事を。あの頃のことは今ではもう遠くなってしまったが、たぶん私はラインハルトの事を目で追っていた。それを彼は目撃していたのだろう。
でも朗読会で配られたこのカードを、ラインハルトは破棄せず持っていたのだ。やはりそこにはまだ友情が残っていたのだろう。キルヒアイスにとっては冗談ではない事だろうが。だが言わなくてもいい事を言う彼の気持ちを考えると、ヒルダにはラインハルトが痛ましかった。
窓の外は夜の雨だった。
私は彼について行く。そう思った。返事は近いうちにしよう、ただその時結婚をうれしがる顔はしないでおこうと思った。彼の心を揺らさないようにしようと。彼は私を自分の裁定者に仕立てようとしている。そうなってはならない。私は彼のお姉さんではないのだから。友人を殺してしまった彼の事を、そっと見守らなければ。ヒルダはそう考えていた。
ラインハルトはマンションの自室で古い文書ファイルを画面上に出してじっと眺めていた。タイトルは「ヴェスターラントにおける核攻撃についての報告書 〇年〇月〇日作成 作成者 ヒルデガルド・フォン・マリーンドルフ 各審議会における答弁の記録とその解説」。画面をスクロールして彼はしばらく眺めていたが、やがて閉じて立ち上がった。窓の外の雨雲が黒く動いて、やがて本降りの雨になっていった。
ハイネセン本星に帰還していたロイエンタール公は、しばしばアンネローゼを伴い、公的な場に姿を現した。二人は婚約しているのではと噂された。あれはほとんど夫人であると言われ、夫人は妊娠しているという噂まで出ていた。その頃公は、自治領として存続しているイゼルローン要塞について、ラグナロクの戦いを仕掛けてもよいのではと、会議上で発言した。つまり最終掃討決戦を決行してもよいのでは言い出した。賊軍は滅ぼすべきであると言う声も議場では上がった。ラインハルトはこれに異議を唱え、会議は終了となった。あんな若造の鶴の一声で決まるのか、と貴族連の重鎮の者らは悔しがり、ラインハルトの姉と付き合いだしているロイエンタール公を推す向きが徐々に広がっていった。
その頃ロイエンタール公について、戦争中に同盟側と連絡を取っていたという文書が見つかり、その査問会が秘密裡に開かれた。ロイエンタールが性癖で匿っていたエルフリーデについての審議が行われたのである。ロイエンタールは自分は戦争中に、彼女から得た情報は利用したが、それだけの関係であり、身の潔白を主張した。それどころか自分のそうしたふるまいが、帝国側にとって大いに有利に働いたと主張した。ラインハルトもこの査問会には出席していたが、彼は傍聴人の如く終始無言でロイエンタールの言葉を聞いていた。結局ロイエンタールの主張が認められ、彼はエルフリーデと共謀したことは認められないという審議結果になった。当然の結果だとロイエンタールは憤慨しながら査問会をあとにした。すでにエルフリーデとの関係は終わっていたから、彼にとっては迷惑な昔話であった。
ロイエンタールがラインハルトから狩行の誘いの電子メールを受け取ったのはその直後である。いわく、あなたが私の姉と付き合いだしていることを耳にした、そのことであなたと話し合いたい。義弟としてあなたの教示を受けたいと書かれていた。何を他人行儀な、かつて同じ作戦指令室にいた仲ではないか、とロイエンタールは思ったが、おそらくエルフリーデのことで小言のひとつでも言うつもりだろうと思った。議場にいた彼の顔はロイエンタールにも確認できていた。今後どうも面倒な男になりそうだと彼は思い、念のため狩用以外に銃を予備に何丁か用意した。それはネットで取り寄せた。鴨狩りとはやつも風流なことを、と思った。しかしアンネローゼの気持ちを考えると、殺したりするのはまずいだろうなと思った。
要するに彼女は血を見るのが大嫌いなのであり、それが自分のせいであったりするのは我慢がならないたちらしいのだった。戦争を嫌っているのはそのせいであり、しかし皇位につきたいと思っている彼女をなだめるのはなかなか大変であった。あのキルヒアイスを殺したのはあの子らしいのです、と打ち明けられて、ロイエンタールが考えたのは、要するに政治の表舞台から彼を消滅させるということであった。すでに手はひとつ打ってあるとアンネローゼは言い、付き人のエミールの出す午後のミルクに毒を微量であるが混ぜてあるという話をした。もちろんエミールには知らせていませんけどね、あれには栄養剤と言ってあります、と彼女は言った。
こうした話を打ち明けられて、ロイエンタールもキルヒアイス同様、これは猛女であると思ったのであるが、ラインハルトの今の宰相の地位を踏み台にして、このアンネローゼとの子供で一気に皇位継承まで駆け上がれるのではないかという幻想は、なかなか魅力的に思えた。それで今回向こうからの狩行の誘いを聞いて、ここで半身不随にでもしておけばいいのではと考えた。実はこの前のテロ工作も、そのような事情から起きた現象だった。むろんそれらは遠方からの玉突き事故であったので、まったくロイエンタールの工作とはばれることはなかったのである。
狩行は首都オーディンからアンネローゼのいた山荘地帯からさらに山奥に入った山地で行われた。彼ら二人の他に随行の伴の者も少しいたが、途中で彼らと別れた。ランドカーを停めた地点からだいぶ離れた場所で、やはり開けた湖水があるあたりが鴨の猟場だった。ロイエンタールはワルキューレ操縦でもそうであるように、射撃の名手であったから、鴨をかなりの数しとめた。それに対してラインハルトのしとめた数は少なかった。というか、彼は熱心に撃とうとしていなかったかのようであった。ロイエンタールが撃つのを見てから銃を取り上げることが多かった。自然撃つ回数は少なくなった。ロイエンタールがおまえももっと撃たないとと言うのに、ラインハルトは鴨が落ち着くのを待っているんですよ、と答えた。静まった方が的に当たりやすいと彼が言うと、ロイエンタールはそういうものかね、それじゃ鴨が逃げちまうぞと答えた。ラインハルトは言った。
「思い出しますよ。幼年学校時代のことを。あそこで銃の撃ち方を習いました。」
「それは俺もそうだよ。だが俺はおまえよりずっと前だな。俺は旧式の銃も持たされたことがあった。最低だったぞあれは。」
「だから手並みがいいんですね。」
「まあな。伊達に長年やっていないってことさ。ところでおまえの姉上だが、俺がとってしまっていいのかな。」
「それはもちろん。私には過ぎた女性です。」
「そりゃどういう意味かな。おまえそっくりだと思うこともある。一時別れたこともあったんだが、向こうからまたやって来た。あれは風雅な女だよ。」
「…子供はできたんですか。」
「うん、まあ、まだ二か月ぐらいか。まだ安定期じゃないんで、家にいるように言っているんだ。そのうち正式に式を挙げる。元皇帝陛下の女性だからな。ちゃんとしてやらないといけない。」
「それはありがたいことです。礼を言わないといけない。」
「なんだ。俺がちゃらんぽらんみたいな言い方だな。」
「そう聞こえましたか。なら謝ります。」
「しかしおまえが弟分になるなんて、思ってもみなかったよ。最初にキルヒアイスと来た時にはな。あいつもいなくなったが。」
彼らは今猟場の湖岸から離れて、高台の崖の上に来ていた。昼食を摂り、話し込んでいたのだった。と、ラインハルトは歩いて崖の先のところに立って言った。
「キルヒアイスに言ったことがあります。こういう開けたところで、俺は宇宙を手に入れるんだと。」
「へえ。」
「私は今そんな気分ですよ。」
崖からは素晴らしく眺めがよかった。遠くに連山の青い山並みがそびえ、小鳥が遠くの方の森で谷渡りの声をたてていた。その美しい景色の中心に、背中を向けてラインハルトはじっと立っていた。ロイエンタールは猟銃をゆっくりと構えた。そのまま撃てば、彼の背中に当たるはずだった。
「?!発射しない?」
ロイエンタールは銃を見た。空砲か?バカな、一体どこですり替えたんだ、と思った瞬間、ロイエンタールはこちらを向いたラインハルトの拳銃で頭を撃たれていた。即死であった。
アンネローゼはロイエンタールからのスマホの伝言メールを見て、その搭乗する予定の航空便の到着を空港で待っていた。しかし空港で彼は乗降客の中にはいなかった。彼女は航空会社に問い合わせたあげく、搭乗リストにいるはずなのになぜ乗降客の中にいないのか、と必死に言いつのった。当局は行方不明者リストにロイエンタールの名前を入れ、それはやがて大々的に報道された。ハイネセンは領主を失い自治領に統合され、元イゼルローン要塞とともに帝国内の自治国として存続することとなった。その盟主はユリアン・ミンツであった。アンネローゼはその報を聞いて失意の絶頂になり、おなかの赤子を流産した。
12.星の海へ
帝国は仮初めの平和を保っているという噂だった。ユリアンらの率いる自治国は今のところ反抗の意思は見せなかった。しかし時間の問題であろうと言われた。ただ元の状態に戻っただけだという反政府市民らの指摘があった。しかし国の状態ははるかに以前よりも進歩していた。ビルや施設が整備され、建設ラッシュは進んでいた。イゼルローン要塞が廃棄処分になり、輸送の流通がスムーズになったせいもあった。その頃、ヒルダは赤子を無事出産した。
彼らの結婚はむろん内密に行われ、人心の知るところではなかった。式にはヒルダの養父とオーベルシュタインが参列しただけだった。アンネローゼには連絡が行ったのか不明であったが、もしあったとしても彼女は体調不良で来なかっただろう。型通りの指輪の交換を行い、互いの頬への接吻があった。薄いヴェールをかぶったヒルダは涙ぐんでいた。
彼女は式の前からすでにラインハルトと同棲生活を始めていたが、そのキッチンに置かれた水差しと錠剤を見て顔色を変えた。彼女は中身を確かめただちに試薬検査を行い、毒素であることを確認した。エミールに問い詰めても、少年は泣きじゃくるばかりで要領を得なかった。上にいる誰かに命令されてやったとだけしかわからなかった。彼女がラインハルトにその事を告げると、彼はこともなげに答えた。
「たぶん姉上だろう。私は狙われているんだ。君に言わなかったかな、彼女は私の友人の愛人だったんだよ。それを殺したからね。十分すぎる理由だよ。」
「知っててなぜ飲んだんですか。」
「そうだな。君も手伝ってくれるとうれしい。意識が戻らない例もあるそうだが。」
「麻酔、ですか。」
「君ならもっと他にいい方法がわかるだろう。それを期待している。」
ヒルダの出産した子供はアレクサンドルと名付けられた。しばらくはヒルダも赤子の世話で忙しかった。むろん公務はもうやめていた。オーベルシュタインもさすがにまだ働けとは言わなかったのであった。ただ彼女が抜けたことで、執務の遂行に支障が出る文句は言った。
ラインハルトが言った言葉が彼女には気がかりだった。その方法は彼女にはわかっていた。地球の東洋医学の隠された薬草学に、その種類の薬草はあった。手に入るところに保管されていることも知っていた。ただ彼女はふんぎりがつかなかった。本当にいいのだろうかと。それほど彼は今の地位が嫌なのだろうかと。
そんな折、彼女は夫のパソコンにひとつのファイルが目立つ場所に置いてあるのを見つけた。ヴェスターラントと書かれたファイルだった。彼女は開けてみた。自分が昔書いた文書のコピーがまず出てきた。これは何年前のものだろう、ずいぶん古いと思った。確かブラウンシュバイク公に命じられて作らされた文書だわ、と彼女は思った。でもこれがどういう?と思い次々に開けてみると、人物相関図が出てきた。そして、彼の日記のようなメモ書きも出てきた。
「〇月〇日 キルヒアイスからヴェスターラントの事で意見を言われる。」
という下に、「キルヒアイス⇔ブラウンシュバイク」と書かれた記号があった。
彼女は頭を押さえた。
待って、混乱してきた。彼は私のことを好きだから、私を思って私を襲ったのでは?違うということ?そう言いたいの?あれは、じゃああれはパワハラだったということ?彼の私に対しての愛は…。ラインハルトは今は私にそう考えろと言いたいの?でもこの文書は確かに私は作った。それは覚えているわ。あれは愛じゃなかったと言うの?だけどあのカードは…あのカードは…。
「勝手に僕のパソコンを見るのはいけないね。僕の奥さん。あのカードは僕が偽造したわけではないよ。正真正銘彼の筆跡さ。」
いつの間にかラインハルトがドアのところに立っていた。
「じゃあ、これはどういう…。」
「ひとつはブラウンシュバイク公に命じられた。ひとつはアンネローゼよりも君が好きだと悟った。ひとつは僕の物を横取りしたいと思った。そんなところかな。」
「…。」
「僕の葬儀はそろそろした方がいいんだけど。君は手伝ってくれるかな。」
「…そういうところは昔の口調ね…、生きて帰れないかも知れないわよ。」
「姉貴なら嫌だけど、君の手にかかるなら本望さ。」
「あなたがいないと、アレクサンドルはお姉さまの手に渡るわ、たぶん。」
「ああそうだな。ミッターマイヤー夫妻のところならいいのにな。あそこにはまだ子供がいない。」
「もう、そんな冗談…。」
いつになく明るいラインハルトであった。
それから数か月後。ラインハルト・フォン・ローエングラムの葬儀がしめやかに行われた。会は密葬に近く、関係者だけの葬儀であった。閉会時にアンネローゼは三歳のアレクサンドルの手を取って、わたくしと一緒に参りましょう、と言った。その手にはペンダントが握られていた。危篤の際にラインハルトから贈られた品であった。もう枕もあがらないラインハルトは姉を呼び寄せ、片身の品を手渡したのであった。その瞬間ペンダントは薄い銀色の光で透明に輝いた。そう横に立つヒルダにはそう見えた。
「では、お姉さま。私は行きます。」
と、教会で影になって、ヒルダはアンネローゼとアレクサンドルの二人に言った。
「ええ、この子の後ろ盾はわたくしが行います。やっとローエングラム朝ができるのですよ。」
にこやかなアンネローゼにヒルダは無言であった。最後に一言だけ彼女はアンネローゼに言った。
「お姉さま。わたくしはエッダのヒルダです。それをお忘れなきよう。では。」
アンネローゼはぽかんとしていた。彼女は古い伝承や文献とは無縁の女であった。ヒルダは黒衣のままランドカーの人となった。
それから数か月後。
ヴェスターラントの地区管理事務局に若い夫婦連れが訪れた。転居届を出すためであり、そのサングラスの男は書類にラインハルト・ミューゼルとヒルデガルト・ミューゼルと書き込んだ。
「あそこは立ち入り禁止地区の近くだがね。あんなところに住むのかね。」
と、地区管理人は言った。
彼らは農業と金融業を兼業しながら生活を続けているようだった。生活は貧しく苦しかったが、やがて女の子がひとり生まれた。その後、彼らの住居に訪ねてくる男性がいた。もう初老の男で、男の子をひとり連れていた。
「こんな年齢でこの俺にこんなことさせんなよ、ひやひやしたぞ。まさに幼帝誘拐事件だねぇ。」
と、男は言った。いつぞやの山高帽の男だった。女の子は叫んだ。
「パパ、アレクサンドルが来た。」
「パパを覚えているかしらね。アレクサンドルは。」
ヒルダが言う前に、アレクサンドルは泣き出して走って行って彼らに抱き着いた。
男は一晩泊まって次の日に帰って行った。
「あの人がね、空港で待っている時にパパが皇帝になりそこねた男だって言ったの。」
「うん。そうだな。」
「アレクサンドルなんて名僕嫌いだ。英雄みたいな名前。」
「パパの友達も英雄の名前がついていたんだ。それをパパは俗な名前だって言ったことがあった。それはよくなかったと思っている。」
「そうなの。」
「アレクサンドルはさ、守る者という意味なんだ。地球の古いギリシャ語でね。」
「僕妹ができてるなんて思ってもみなかった。ゼルダっていうの?」
「うん。仲良くするんだぞ。」
「うん。パパとママががんばった。」
「こいつ。」
寝る前のトークはそこで終わりになった。ヒルダが電灯を消しに来たのだ。ヒルダは言った。あの子たちここで暮らすことをどう思うかしら。ラインハルトは答えた。そうだな、今に僕がそうだったみたいに親父を怨むだろうよ。出て行くね。僕が嫌いになるよ。そうなったら君とまた二人きりだ。君がよければだけど。ヒルダは悲しげにほほ笑んだ。お友達と心の中で約束したんでしょう。ここで暮らすと。そうだな。あいつはわかってくれるさ。俺の勝手な思い込みだけど。
あなたもう寝ないの、とベッドの向こうから妻の声がした。ラインハルトは寝床でラジオの天気予報をイヤホンで聞いていた。南南西の風、風力3。次はカリギヤ地方です。気圧は952ミリバール。明日は晴れるでしょう。
ここで暮らすということは、常に風水害との隣り合わせだった。もっと別の天災もあるかもしれない。先のことはわからなかった。
少し彼はアンネローゼに渡した銀のペンダントのことを思い出していた。ヒルダが調合した毒は仕込んでおいた。しかし彼女はペンダントを開けて見るだろうか。それほどキルヒアイスのことを愛していただろうか。彼女は捨てるかもしれない。それでもよかった。友人の遺髪が手元にないのは寂しい限りだが、アンネローゼが友人の髪で命を落とすのは美しいと思った。もう若くはない彼女の最後の青春の輝きに思えた。しかし彼女はそれを裏切るだろう予感はあった。
そしてキルヒアイスは自分をあの世で許さないだろうと思った。あのヒルダの公文書の内容に激怒したブラウンシュバイク公がキルヒアイスに命令し、やらせた。しかしそれはもともと皇位簒奪を言い出したリッテンハイム公の陰謀によるものだった。アンネローゼもリッテンハイム公には反対していたから、キルヒアイスに同様に半ば命令していたのだろう。彼はピエロを演じていたのだ。覆面をかぶっていたとヒルダは言った。本当は愛していた。たぶんそうだった。それを自分は殺した。たぶん許してくれないだろう。いつかまた会えるだろうか彼には。
ラジオ放送はまだ続いていた。続いて大陸地方です。
シャフトに流したワープ航法の情報について、ラインハルトは慮っていた。あれは彼の発明だった。しかし彼は自分が発明したと言いたくなかった。自分がそう使用したように、しばらくは軍事利用されるだろうと思った。あの情報が平和利用されるまで自分は生きていないだろうと思った。従って彼は逃げたし、彼自身がそのワープ航法の犠牲になることも考えていた。身から出た錆だと彼は自身を笑った。その時は天啓だと思ったのだった。
しかし彼は思うのだ。あの暗い作戦司令室で、はじめにいたあの暗室の部屋で、緑色に光る計器類を読みながら宇宙の海図に線を引いていったあの作業。あの作業をもう自分はしなくてもいいのだ。願わくばあの作業も、何がしかの地上の幸福につながっていたと信じたい。
ラインハルトは瞳を閉じた。
「ほんとだ、音がしますね。」
年若い妻の声が、耳元に聞こえてくるような気がした。
―完―
引用文 リルケ「ランプの下で」 堀辰雄訳 青空文庫
あとがき
お久しぶりでございます。前回のアルドノアゼロ作品からだいぶ時間が経ってしまったかと思います。二年ぶりですかね。
今回は今放映中の銀河英雄伝説ノイエテーゼです。実は一期から放映は見ていたのですが、アニメは作画が美しいと思いましたが、最初それほど心惹かれなかったのですが、原作本をプライムリーディングで第一巻を読み、それから気になって図書館で続巻を借りて、ついにキンドルで全巻そろえてしまい、それからアニメ資料集を買いこみついに二次創作を書くことになってしまいました。いつもの改変もので、受け付けない方も多いかと思います。今回は原作とかなり違えてあるので、剽窃というのもおこがましいかもしれません。私なりの解釈としか言いようがないです。
特に登場人物の性格や行動原理がかなり原作とは違えてあります。一部どうしてそうなっているのかと疑問を持たれた方も多いかと思います。ただ自分としては、全体を自然な流れになるように考えたつもりです。いつもの思いつきで、最終場面はこうなると早くから決めて書きました。むろんこの終わり方に不満を持つ人は必ずいると思います。ただ原作を読んでいて、かなり後半の展開は私には不満だったので、こうした措置になってしまいました。ラインハルトが皇帝にならなかった点も、私の趣味でしていることです。自分としては、知っている知識を総動員して書いたつもりですが、いつものことで舌足らずな点や間違っている点は多々あると思います。どうか大目に見ていただけたらありがたいです。
今回書いている時は10CCのアイムノットインラブと中谷美紀さんのクロニックラブをよく聞いていました。またノイエテーゼのアニメの切り出し動画もよく見ていました。特にアイムノットインラブは訳詞の意味を逆にして聞いておりました。つまり自分の都合のいいように聞いていたわけですが、こうした事も何かの足しになったとしたら幸いです。
あとタイトル名ですが、有名な手塚先生のアニメ作品から拝借しました。BGMが確かムソグルスキーの展覧会の絵でした。キエフの大門はノイエっぽい曲だと思いました。また今回の小説が内容的に手塚さんの性を扱った作品と近い感じがしたので選びました。原作も出産などが出てくる大人っぽい内容でしたので、そういう風にしてみました。あとバルトークの木製の王子というバレエ音楽もよく聞いていました。小説中に出てくるヒルダの夢に出てくる木製の人形というのは、この作品から考えて出しています。かかし王子という名前でも知られているこの作品は、王子がかかしに自分の王冠や衣装を着せて、ヒロインに王様としてダンスを一緒に踊らせるという内容になっています。私の今回の小説のヒントになった作品です。
それではまたどこかで何かの作品でお会いできましたら。
2024年9月26日 おだまきまな拝
ある街角の物語


