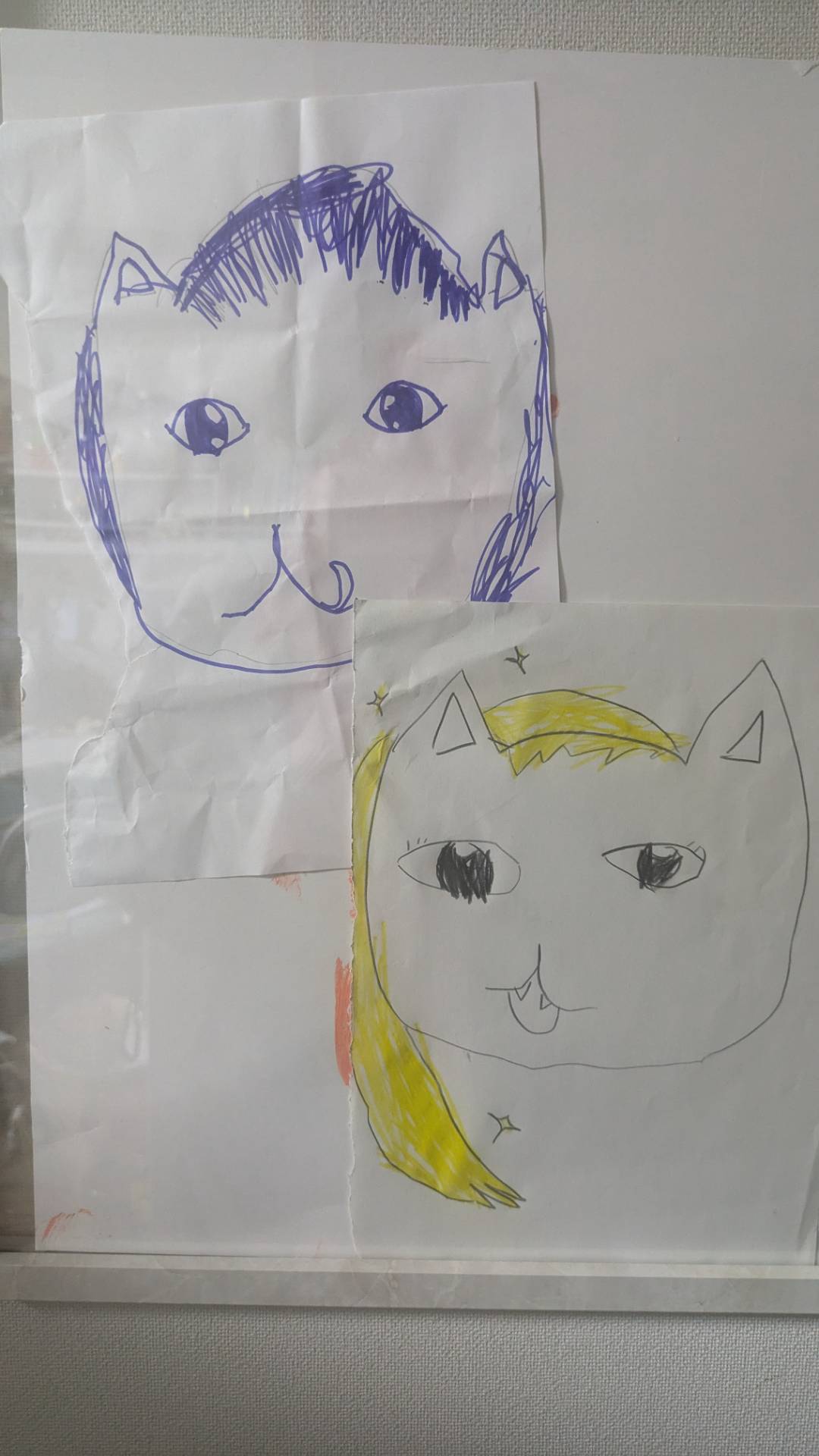
CAT File 3 :行方不明が多すぎる 報告書作成中…
現在鋭意作成中
アレコレ書き変えたり、辻褄を合わせたり、止まったり…
頑張るので、とりあえず一時公開。
000. CAT: Chasm Adjust Taskforce

C.A.T. とは Chasm Adjustment Taskforceの略であり、人間界における境界事象を中心に扱うネコビトの組織である。ネコビトはネコでありヒトでもあり、ネコビト自身が境界事例の典型である。ネコビトは猫らしくある程度テキトーで自由気ままなので、突き詰めるべきではない事柄を適当にうやむやにして、至極真面目な人間の世界にうまくなじませる役割を担っている。これは彼女らの物語である。
001. 三ツ池さんと深堀地区の喫茶「むじな」
CAT本部では、今日もネコビトたちが爪を研いだりネイルをしたり、遊びに来た情報屋と雑談をしたり、それぞれ思い思いに時間を過ごしている。
「すみません、三ツ池さん」
「にゃにー?」
「これから三ツ池さんがハリコミに行くの、深堀小学校の近くですよね?」
最近、中途半端にCATに戻ったちゃるママこと分地が言う。分地は事務兼映像係で捜査からはまだ身を引いている。
「深堀地区?うん、そうだよ。」
「あの、すねこすりのコータ君が、相談したいことがあるそうなんです。彼の小学校、深堀小学校なんですが、近いんでついでに寄るのって可能ですか?」
「いいよー帰りに寄るね。」
「あ、じゃあ、深堀地区の『秋のオトナの純喫茶』クーポン、あげます。」
「ええ?いいの?」
「『むじな』でも使えるそうですよ。私も喫茶店好きなんですが、純喫茶はちゃるが退屈しそうで試してなくて…」
「やったぁ、ありがとう。」
三ツ池は気軽に引き受け、帰りに深掘地区にある喫茶「むじな」の新作、「サツマイモと小豆と秋刀魚の三角関係」なるスイーツを試そうと心に決める。
002.フワモコ王国のマッチョ

疑似ロココ調の豪華な扉の向こうから、ためらいがちともとれるほどに穏やかなノックの音がする。不破望子はパソコンから目を上げ、老眼鏡を素早く外して豪華な机の引き出しにしまうと返答する。
「はーい、どうぞ。」
「不破さん、すみません。」
休館日明けの水曜日の午前十一時、有名テーマパーク『フワモコ王国』のCEO、不破望子は深刻そうな表情のCFOの訪問を受ける。「内々に」お話ししたいとのことだったので、不破は若干の緊張感をもって、住野CFOと、後ろについて入る警備局長の蔵市を迎え入れる。
「どうしたの?」
「それが…こちらの映像をまずは御覧いただきたいんです。」
蔵市が手にした分厚いタブレットに館内の防犯カメラの映像を映し出す。
「あらあら、これは…」
フワモコ王国の防犯カメラは高精細で、しかも死角をできるだけ作らないように多数設置されている。そのうちの一つのモニターに、背の高い、サングラスをかけた筋肉隆々の男性が写っている。彼は晩秋のうすら寒い日にも拘わらず、黒いタンクトップを着ている。
「ずいぶんと肉厚なマッチョさんねえ…こういう方もこのふんわりスィートな癒しを求めてくれるなんて、嬉しいじゃない。」
何かしら重大な事故でも起こったのではないかと危惧していた望子は、緊張がほぐれて少し高い声で笑う。しかし、住野と蔵市の顔は晴れない。
「いえ、それがですね…」
蔵市は画面を複数のカメラ画像に切り替える。1階エントランスに2人、2階フォトコーナーに3人、地階のアイスクリームコーナーに1人、「出窓のある青い壁のおうち」に1人。皆、筋肉の豊かな腕を袖のない服からぶら下げて、腕組みをしたりアイスを舐めたり、何やら無線でやり取りしたりしている。
「こういうお客様が、あと7人いらっしゃいます。」
「ええと…そうねえ、傭兵部隊の遠足かしら…」
「皆さま、年パスでご入場なさっています。」
「あ、あら、結構お高い年間パスポートで? 全員? 団体割引と間違えて買っちゃったって事? いいのよ、払い戻して正しいチケットご案内して差し上げて…」
「あ、いいえ、そうではないので…」
住野は言いにくそうに口ごもり、蔵市と視線を交わしてから言葉を継ぐ。
「ご報告が遅れまして申し訳ありません…実は、皆さま、先週から毎日いらっしゃっていまして…」
「毎日…?!」
「しかも開館から閉館まで…いかなるお客様でもこのフワモコ王国を満喫なさる権利があることは重々承知です。しかし、しかし…『フワモコ王国』はハニー・バニー、ふわふわのフワリンとモコモコのモコリンと、ゆるリンとキュンキュンと…と、とにかく、ノンビリきゅんきゅん、可愛い王国です。こう…筋骨たくましい方々が集団で毎日となりますと…」
CFO、チーフふんわりオフィサーの住野が、言葉を選びながら本音を述べる。
「ええと…いえ、決して…とにかく、ここをジムと間違えるお客様もいらっしゃるのでして…」
タブレットにうつし出された映像では、フワモコな仲間たちに囲まれて詰まらなさそうにしていた十代中盤と思しき少年が、彼の5人分は体重のありそうな男性にサインを頼んでいる。巨大な筋肉の塊の男性は肩を揺らして笑い、左右の胸筋をそれぞれに動かして見せると、少年の差し出した紙にサインをして渡す。
「うーん、可愛いワールドにもワビサビ界隈にもないエンタメね…」
望子は、クリスタルガラスの万年筆で高級なメモ用紙に「マッチョ」と書きつける。
「あ…」
住野が額を曇らせる横で、タブレットの映像に目を落としていた蔵市が小さく息を飲む。
「どうしたの?」
「あ、いえ、あのですね…」
蔵市はどういうわけか動揺している。その目はタブレットの映像の一つにくぎ付けになり、頬はみるみる紅潮していく。
「あら、蔵市さん、大丈夫…?」
「蔵市さん!鼻から血が!」
不破望子と住野が心配そうに小さく叫び、蔵市は驚いて不破が手で示した唇の上に手をやる。
「あ、な、なんでもないんです、ただ…え、血?」
鼻の下に当てた指先に生暖かいものを感じ、蔵市は慌てふためいて化粧室へ消える。
「大丈夫かしら…」
望子と住野はお互いに心配げに視線を交わし、望子は私用のタブレットで「鼻血・発作」と検索しだし、住野は先ほど蔵市が見ていたタブレットに視線を落とす。二人とも、仕事仲間思いの良い人達である。
003.グレイのスーツとグレイヘア

青木は休日をドラマNCISの鑑賞で過ごしたのち、情報屋の吉田と落ち合って深堀地区へ向かう。連続窃盗事件の容疑者宅を張り込むためだが、三ツ池の報告では洗濯物にタヌキの着ぐるみが干されていたという。交代前に、二人は喫茶店で情報交換ついでに一息入れる。
「えー遮無さん来ないんですか。」
「遮無ちゃんは来る予定ないですねぇ。雨所は後で来る予定ですよ。」
「雨所さんかぁ、あの人愛想ないんだよなぁ。」
「愛想ってなんですか?」
青木は吉田を時々日本語の勉強に使っている。
「えーと、フレンドリー? 愛想って、フレンドリーすかね。フレンドリーじゃないんですよね、あの人…。同じちょっと灰色っぽいシマなのに、冷たいんす。」
「雨所は雨所でプライベートな人なんです。Don't take it personal.」
「パーソナル? えーと…ところで、なんでタヌキのキグルミなんですかね、目立つのに。」
「うん、おかしいです。この辺の名物は蕎麦です、ウドンじゃない。」
「え、タヌキといえば蕎麦屋じゃないすか」
「ダルマじゃないんですか。」
「それはこの辺だけじゃないかなぁ…あ。てことはソイツ、この辺の事よく知らないのかな。お、この、アナゴのチーズケーキ、うまそうだな。」
深堀地区の喫茶「むじな」は、ネコビトやその他の境界ビトには有名な人気店だ。店主は人間のようだが、ネコビト向けのメニューも充実している。
「あ、あれ!」
「What?」
「あれ、あっちにいるの、沼田署長じゃないすか?」
「Wow, who is that handsome...?」
「ええ、あの人?はんさむ?そりゃ、オシャレだけどさ...ちょっと、頭が白くて丸くないっすか?タマゴみたい。」
カウンターから沼田署長へ笑顔を向ける小柄な男性をみながら吉田が言う。タマゴみたいな頭の男性は品の良いヒゲに蝶ネクタイ、そして高そうなエプロンをしている。
「No, that’s not the guy I’m taking about. ちがいます、あの人は owner of this cafe. Mr. スーシェ。」
「あ、そーですか。オーナーさん、須子ゑさんってんですね。じゃ、署長さんのほうは…ああ、ほんとだ、あれは…グレイのスーツの。へぇえ、眼光鋭いな、こわ。」
沼田署長と、ペアルックのようにそろいのライトグレーの三つ揃いを着た男性が、メニューを片手に熱心に話し込んでいる。カウンターからゆっくりと歩み寄った須子ゑ氏に、沼田が話しかける。
「あのスーツ男、署長のboy friendかな。」
「でも、どっかで見たようにゃ…誰だったにゃ…」
吉田は記憶を辿るが、それよりもタマシイ風豆腐の天ぷら、黒蜜がけが気になってきている。オーナーの須子ゑ氏が、沼田署長に紹介されたらしいスーツの男性と握手を交わす。
004.心臓君の失踪届

「うーむ、『むじな』のでの待ち合わせまでまだ少し時間が…だいぶあるにゃ…先に行って席取りするかなぁ」
「席取りなんて野暮にゃ真似をするのか?」
「ムジナは人気店ですからね…限定メニューだけ先に頼んじゃおうかなぁ…」
三ツ池が連続窃盗未遂事件の張り込みを終えたのは深夜の0時だ。交代の青木・雨所組と情報屋の吉田が、「優先度の高い」案件で交代に遅れたからだ。寝不足気味の三ツ池捜査官と、昼間は寝てすごして機嫌の良い繰津は、新築の解放感にあふれた深堀小学校にいる。深堀小学校は100年近い歴史を誇る伝統ある小学校だが、最近校舎が建て替えられておしゃれになっている。
「ふぁーあ、眠い…あ、ここ書いてね。あ、繰津さん、勝手に写真撮っちゃ…」
「いやいや、元の収まってた場所も撮っとかにゃいと」
お疲れ気味の三ツ池、楽しそうな繰津、元気な小学校1年生、すねこすり人コータ君が、涙にくれる人体隊解剖模型君を囲んでいる。人体解剖模型君は、自分の心臓パーツ君の捜索願を書いている。
「ここに書くんだよ、シ・ン・ゾ・ウ!」
コータ君が覚えたてのカタカナを空中に書き、得意そうに微笑む。
「うーん、にゃるほど。心臓ぱーつが行方不明か。でもよくにゃい?要るの?心臓。」
「要ります!」
「でもねえ…無くても死ぬ訳じゃなにゃいし」
繰津は人体解剖模型君の気持ちにはあまり寄り添えないようだが、興味津々で彼を観察はしている。
「死にそうなくらい心配です!」
人体模型君はそういうと、はらはらと涙を流す。人体模型君の右側の目玉君は取り出し可能なので、机に飛び降りてハンカチでそれをぬぐう。すねこすりビトのコータくんは、人体解剖模型の肩に手を置いて言う。
「繰津さん、もっとやさしく! シンちゃんは人体解剖模型君の大切な家族なんです!」
人体解剖模型君はこの小学校が建て替わるずっと前から深堀小学校に籍を置いていて、生徒たちに親しまれてきた。最近のお気に入りは、5年生の有志の生徒から送られた左右で柄の切り替わったお洒落なパンツだ。授業で手縫いしてくれたそうで、柄違いが沢山ある。
「見付かるといいね」
「うん、僕、シンちゃんがいないと…」
人体解剖模型君ががっくりと肩を下ろし、その拍子に左肩が外れて落ちる。と、左手は「いてぇ」と小さく抗議の声をあげる。
「あ、ごめん、ひだりん」
小声で謝りながら人体解剖模型君がひだりんを拾い上げるタイミングで突然、耳をつんざかんばかりの大きなピアノの音が響き渡る。
じゃじゃじゃじゃーん。
「にゃ、にゃんだあの聞き覚えのあるメロディは?!」
三ツ池はとっさに立ち上がり身構える。繰津は座ったまま耳を伏せて一応警戒をしているそぶりを見せるが、口角は嬉しそうに上がる。聞いたことのない男性の歌声と、続いてヒステリックな叫び声が広い廊下を満たす。
「うわぁぁぁ!!続き!!続きは!?」
その声はどうも、壁のない廊下の突き当たりの階段の向こうから響いてくるようだ。繰津は耳の位置を戻して嬉しそうにニヤニヤし、寝不足の三ツ池は思わず半猫姿になって毛を逆立て、人体解剖模型君は溜め息をついて階段の方を眺める。
「ああ、ベートーヴェンさん…大丈夫かな。」
「にゃにやつにゃ?」
「ベートーヴェンさんは学校の不思議仲間で…悩んでいるみたいなんだけど話してくれないんだ。」
学校の怪談の主人公たちにもそれぞれ、悩みがあるようだ。
「そっか・・・ここにちゃる捜査官がいてくれたら、必殺ほだし落としで証言がとれるんだけどねぇ・・・」
また先程のピアノの音が何音か続いたあとで叩きつけたような不協和音が響く。そして、遠くから、「うるさい!お前みたいな天才に何がわかるんだ!」と叫びが続き、その後しばらくしてから「わかったよ、わるかった。」と少しヴォリュームを下げた謝罪の言葉が聞こえてくる。あちらから半透明の白い鬘の快活そうな様子の青年がふらりと飛び出して、通りすがりに解剖模型君に手を振っていく。
「ああ、モーツァルト君、またヴェートーベン君を怒らせちゃったんだな…」
「モーツァルト君とヴェートーベン君は悪いの?」
「ううん、どっちかというと仲良しだよ。でも、いつもモーツァルト君がヴェートーベン君をからかってて、バッハ先生に叱られるの。」
「バッハ先生?」
「それはあだ名でね、人間なんだけど…」
廊下の疑似懐古な柱時計が0時の鐘を打ち、三ツ池はそれでもコータ君の学校ゴシップに笑顔で耳を傾ける。
繰津は所々で質問を差し挟み、最新の学校の怪談事情を書き留める。
005.蔵市さんとSNSの王子ヨリック

フワモコ王国警備局長・蔵市はトイレで鼻血をぬぐい、ついでに、動揺で飛び出しかけた猫耳をふんわりとカールさせた巻き毛の下の押し戻す。
蔵市にはここ1年、追い続けている『推し』がいる。SNSのニャンスタグラムでひそかな人気を集める北国の金髪腹筋王子・ヨリックだ。ヨリックは腰まで流れる豊かな黄金の髪、北国の晴れた空のように曇りのないブルーの瞳、真珠の前歯に白い板チョコの腹筋を持ち、その魅力をカメラの前で存分に、とはいえ十秒程度、発揮する。いつも短い動画だが、カメラに向けられるきりりとした表情と鋭い視線にドキリとして心を奪われる者は多い。しかし、ヨリックの魅力はそれだけではない。その剃刀の刃のように鋭い視線は一瞬にして、一塊のためらいもない善意にとって代わり、若干、と言うよりは期待よりはかなり高い「やっほう!また会えてうれしいよ!」という声で視聴者を歓迎する。それに続いてフワモコのセーターのような温かさで、「君は君のままでいいはずなんだよ?」「さあ、僕とパッピーになろうよ」とカメラ目線で語り掛ける。そのインスパイアリングな言葉が、訛りの強い北国の言葉で、誠実に語られる。第一印象とのギャップと優しい言葉に、心奪われた人々は、毎日をなんとなく上機嫌で生きることができる。蔵市はその一人だ。
蔵市は、トイレの鏡の前で鼻字を拭きながら、「まあ、ちょっと下顎と腹筋が似てるくらいだし、天使のような彼があの規格外マッチョ軍団に紛れているわけはないか。」と考え直し、再び仕事用の引き締まった表情を作る。
「で、でもヨリックもマッチョよね…それに北国の生き物はベルクマンの法則に従って、でかいわけで…でも、いやいや。」
蔵市はそう自分に言い聞かせ、花柄の壁紙の廊下を抜けて豪奢な装飾の重い扉を押し開けて不破CEOのオフィスへ戻る。蔵市は普段通りのバラの華やかな香りを期待して無意識に息を吸い込んだが、その鼻腔にスパイシーな制汗剤の臭いが流れ込み、むせる。そして、目の間には巨大な筋肉の山が数塊ほどあるのだが、むせかえった蔵市はその中のひときわ黒い山にぶつかり跳ね飛ばされる。
「ああ、ごめんよ、大丈夫かい?」
大きなスキンヘッドのマッチョは素早く床に膝をつき、蔵市の小ぶりな手を取って立たせてやる。みれば、先ほど十代の少年にサインを書いてあげていた、優しいマッチョだ。マッチョなのに可愛い笑顔で、蔵市を先ほどの少年を見守るのと同じように優しい目で見ている。
「おい、ビリー、どうした」
あちらの黒い巻き毛にサングラスのマッチョが、腕組みをしながらこちらの優しいスキンヘッドのマッチョに声をかける。こちらのマッチョは蔵市に笑顔で会釈をし、それからサングラスのマッチョに「こちらのレディにビリーの尻がぶつかっちゃってね」と返す。
「そいつぁ失礼したな…お嬢さん、ビリーの尻を許してやってくれ。シッポを不幸な事故で失ってな、後ろがよく見えてないんだ。で、このお嬢さんは…」
「ああ、そちらはうちの警備局長、蔵市です。」
「ごめんね、クライチさん。」
マッチョの山の向こうから、物怖じしない不破望子の声が響く。不破望子はマッチョの大群にも特に気圧されるタイプではない。しかし、フワモコ王国警備局長の蔵市は、自分の2倍は背丈があろうかと思われるマッチョに、あたたかく優しい笑顔で取り囲まれて、緊張で体が強張るのを感じる。
警備局長の自分が、いない間に、得体のしれない集団に不破CEOのオフィスを占拠されてしまった。そして、CEOは自分の勝てそうもない相手に囲まれている…だが…彼女は、先ほどのビリーの素早さと、同時にその動きの隙の多さを思い出す。シッポがない?と言うことはシッポのある何かしらの境界ビトね?でも、アタシならヤやれる、アタシなら…
「ど、どうしたの、蔵市さん?」
職業病の仮想戦闘を蔵市が脳内で繰り広げ始める前に、望子が声をかけて現世に連れ戻す。
「ふ、不破さん!この方たちは?!」
「それが…お義母さまに会いたいそうなの。ご用事がおありだそうで…」
「やっほう!こんにちは!それじゃ、僕から説明させてもらってもいいかい?」
突然に、フレンドリーすぎる笑顔がマッチョの山の向こうから現れ、いつもの訛りのある子で語り掛ける。ヨリックだ。蔵市は混乱する。自分は、SNSの夢を見ているのか?
「やぁ、レディ・クライチ!初めて会うね!握手する?」
蔵市は差し出された手に身構え、それから紅潮し、それから失神する。
「ああ、レディが倒れた!」
「鼻血だ!誰か止血できる奴いるか?」
「こんな小さな鼻じゃ無理だ!」
どうやらマッチョたちは手当てがあまり得意ではない様子なので、望子と住野が苦笑しながら蔵市をロココ調の長寝椅子に横たえる。
006. 佐備捜査官とハンナさんと花子さん

ネコビトは、基本的には本猫様態は猫サイズ、ヒト様態はヒトサイズ、ネコビト様態は個人差が大きいものの、大体は各々のヒト様態に準ずるサイズである。そして、ネコビトの中には鬼ヶ首カリンのように顔だけネコビトのままであったり、知多捜査官のように普通の人間よりも背が高く足が速いものもいる。CATの佐備捜査官は、一般的なネコビトよりも本猫、ネコビト、ヒト姿のサイズ差が大きい。佐備捜査官は、人間で言えば目尻に皺が入る年齢だが、ネコビト姿で行う潜入捜査ではいつも子供役を押し付けられてきた。佐備の一家はラスティスポッテッドキャット、世界一小さな猫の家系だ。
「私、ヒト姿だとそんな小さくないんですけどねぇ。三ツ池さんより背は高いと思いますよ、なのになんでいつも…」
ショートパンツのスーツを着た佐備捜査官は、可愛らしいネコビト姿でため息をつく。
「でも、人姿だと、佐備さんも三ツ池さんもでかいにゃ」
ちゃる捜査官は子供らしく思った通りの言葉を口にする。そして、CAT用携帯端末でちゃるママに仔猫2匹とアイスクリームと魚の絵文字を送信し、佐備捜査官と合流した旨の連絡を入れる。即座にちゃるママから、猫と爪の長いイイネマークの絵文字が返信される。
「子供から見たら大人はみんな大きいのかもしれませんね…でも、小学生かぁ…」
「サビさんは、ちゃると潜入捜査は嫌なの?」
ちゃる捜査官が、悲しそうに聞くので、佐備捜査官は慌ててフォローする。
「ち、違うんですよ!? ちゃるちゃんとペアは楽しいんですよ、ただ、ただね…同級生って設定はどうかなと…」
今回、佐備捜査官とちゃる捜査官が潜入するのは「全国花子さん会議」だ。「全国花子さん会議」では、全国の小中学校のトイレに住む花子さんが各地区から代表を選出し、人間や境界存在にまつわる問題や改善点について話し合う。今回は、インターニャショニャルスクールの花子さん、「ハンナ」さんの依頼でネコビト代表の小学生2人として佐備捜査官とちゃる捜査官が会場に潜入することになっている。今回の会場はちゃる捜査官の通う猫草台小学校だ。これは沼田署長が裏で苦労して調整した結果であるが、ちゃる捜査官はそのことを知らない。
「じゃあ、サビさんは4年生ってことにしようね」
ちゃる捜査官は自分よりずっと小さい子に言い聞かせるように優しく言い、にっこり微笑む。佐備捜査官は自分の猫姿の可愛さには絶対的な自信があったが、猫姿では確実にちゃる捜査官に負けるだろうと考える。そして、それが何故か佐備捜査官には妬ましさではなく安心感を与えてくれる。佐備捜査官は可愛い子供でいるのには心底飽きているので、その役割にふさわしい後輩が出来て嬉しい。
「あ、サビちゃん、ちゃるちゃん。お久しぶり!」
沼田署長の友人でインターニャショニャルスクール代表のハンナさんが待ち合わせ場所の駅前広場で手をふる。彼女は花柄のワンピースを着ていて、幽霊であるが故に重力の制約を受けないのか、そのワンピースがふわふわと広がって花のような印象だ。ハンナさんは沼田署長の元同級生で、沼田署長曰く「夭折した天才美少女」だが、沼田署長と同じ年数をこの現世では過ごしているので、それなり言動には大人の説得力がある。ハンナさんはハグついでに半透明の手で二人の頭をくしゃくしとゃ撫で、ニコニコと「よろしくね」と声をかける。ハンナさんをはじめ、幽霊が実態のある存在に触れるには相当なエネルギーを使うので、これは最大限の好意の表現だ。ちゃる捜査官は子供らしくニコニコと応えてスカスカする空中でハグし返す動作をし、佐備捜査官は最大限の努力をもってハンナさんの手を取って握手をする。佐備捜査官はハンナさんの幽体の手にわずかながら触れた感じを与えることができたらしく、「わぁ」の一言をもらえる。
「ハンナさん、今回はよろしくお願いいたします。」
「いたしみゃす」
「うん、よろしくね。あ、それからね、友達を紹介するね。」
ハンナさんは半透明の淡い茶色の髪をなびかせ、すいと横にずれる。後ろから、同じく半透明の15歳くらいの女の子が現れる。
「こちらは深堀小学校の花子さん。ちゃる捜査官、共通のオトモダチがいるって聞いてるよ」
「こんにちは!ねえ、コータ君知ってる?」
ふんわりしたなかに知的な印象の印象のハンナさんに比べて、深堀小学校の花子さんは背が高くクールな印象の女性だ。重くはない黒髪ボブと、切れ長の目を生かしたアイラインが現代的なので、随分垢ぬけて見える。
「ええ、知ってるわよ。コータ君って、すねこすりっこだよね、ちゃるちゃんの話聞いてるよ...一年生なのにCAT捜査官なんてすごいわね…と、サビ君、かな?あなたも小学生なのね?三年生くらい?」
花子さんは子供慣れした様子で優しく語りかけるが、佐備は着恥ずかしげに笑う。
「あ、いえ、私は中年です。童顔ですが…」
「あら、失礼…ごめんなさい、あんまりにも可愛いから…。」
戸惑う深堀花子さんに佐備は大人の笑顔で微笑みかけ、深堀花子さんは抱きつくネコビト姿のちゃる捜査官の頬を優しく撫でる。ちゃる捜査官はゴロゴロと喉を鳴らして応える。
「はぁ、かわいい。うちの学校にもネコビトさんに通って欲しいなぁ。コータ君だけじゃモコ足りない…」
そんな話をしながら、改札から駅前広場への階段を上ると、4人は閉店後のオープンカフェ、「バードランド」の前に落ち着く。地元有志の配慮で、今日だけは白い椅子とテーブルがそのまま出してある。そこへ、佐備が持ってきたバスケットからサンドイッチと牛乳と、炭酸水とガラスの器を取り出す。
「ちょっと休憩しながら、打ち合わせもしちゃいましょう」
「ええ。」
言いながら、佐備捜査官は花子さん達のために、ガラスの器に炭酸水を灌いて三角のマドラーを差し込み、スペクトラムに分けた光のジュースを造る。
「わあ、虹色ソーダ。」
「きれい!だけど…それはお化けの人の飲み物にゃ?」
「そうですよ、生きていると飲めないんです。でも、ちゃるさんにはこっち。」
佐備捜査官が差し出した牛乳とサンドイッチをちゃる捜査官は花子さん達のジュースを横目で見ながら受け取る。そして、サンドイッチを一口かじり、それが自分の好きなキュウリとハムのサンドイッチだと知って、瞳孔が大きく開く。
007. 穏やかでない空気とそれが収まる感じ

「では、会議が始まる前にすこし打ち合わせをしましょう。後で沼田と繰津が来る予定ではあるんですが、まずは概略から…」
佐備は一度言葉を切ると、キュウリのサンドイッチをかじっているちゃる捜査官へ視線を投げる。それを受けて、ちゃる捜査官がキュウリを飲み込んでから、言葉を継ぐ。
「はい。アメショ捜査官からざっくりと聴いているんだけど。…境界にヒビが入っちゃったのにゃ?」
ちゃる捜査官の目はいつになく真剣だ。ハンナさんが、いちど深堀花子さんの方を向いてお互いに頷いてから話し始める。
「ええ…まだはっきりとはしていないのだけど、境界亀裂かもしれない。うちと、深堀さんのところと。他の噂も聞かないことはないんだけど、確実なのはウチと深堀さんのところ。あとはどうにも、情報が出てこないの。」
ハンナさんが言葉を切ると、今度は深堀花子さんが続ける。
「保守的な花子さん達は、どんなに大きな亀裂でも自分たちで修復しないと恥だと思っている節もあって。でもそうすると無理をして、成仏したり転生しちゃう花子さんもいるの…」
花子さんは『学校の怪談』などで有名だが、実際のところは全国の小学校やそれに類する学校に住む幽霊や怪異現象を引き起こす存在のまとめ役、いわば影の校長のような存在である。一般的に、花子さんは近隣で夭折した女性で、「成仏」していない幽霊がなることが多い。この世に留まれるほど霊力の強い女性が務める「花子さん」は、子供と言う高エネルギーの存在が集まる、小学校という場を守っている。そしてそこで生じる数々の亀裂を人知れず修復し、時には子供達を亀裂から遠ざける為に脅したりもする。
「私たち花子さんって、ほら、青春半ばだったり、まだその手前で死んでたりする人が多いじゃない?だから霊力も強いんだけど、誘惑には弱いのよね…」
頬杖をついてそう語るハンナさんに、深堀花子さんもガラスのマドラーで虹を吸い上げながら頷く。
「誘惑とは?」
「異世界転生とかよ。」
異世界転生の概念よりは、境界亀裂の向こうのパラレルワールドや別の惑星の方に親しみのあるネコビトふたりは顔を見合わせる。佐備捜査官の記憶にあるキノコ人間の世界や、ちゃる捜査官がママから聞いた宇宙船に乗ったネコビトの世界へ、人間の女の子が行ったところでつまらないだろうというのが2人の感覚なのだ。
「よくわかんにゃいにゃ。」
「うーん、境界の向こうの世界に魅力を感じるということですか?」
「ええ。私はもう、死んだ年がそれなりだったから平気なんだけど…深堀さんなんかは、ちょっと気持ちがわかるのかな?素敵な人がいたら、いいなぁって、飛んでいっちゃう?」
「まあ、ね…まあ、でも、大抵は裂け目の向こうは蠢く目玉だらけのスライムとか、なにもない荒野とかだからね。危ないからすぐ閉じちゃう。」
「そして、危ないなと思ったらCATとRNAに頼るの。」
落ち着いた声でハンナさんが言うと、佐備捜査官の耳がピクリと動く。そして、「RNA?」と、驚いたように繰り返す。
「ええ。彼らが何をしているのかは私たち幽霊にも謎なのだけど…芸術が絡むと、動いてくれることがるの。」
「RNA...やはり、存在するんですね…それで、ハンナさんは接触なさったと?」
「ええ、ちょっと、失くしものと言うか...」ハンナさんがそれ以上触れてくれるなと言った雰囲気を醸したのを感じ取り、深堀花子さんが話題を少しだけ逸らす。
「佐備さんは、そのRNAには接触したことないんですか?」
「ええ...ネコビトには割と適当ながらもアートを扱う人々はいますし...RNAのような組織は、あまり表立って我々猫とは関わってくれないんですよね。そうか、ゆう...」
その時、佐備の言葉を遮ってハンナさんが嬉しそうにすぅと浮かび上がる。」
「ぬまたちゃん!こっちこっち!」
佐備捜査官とちゃる捜査官が振り返ると、沼田署長と、グレーのスーツの男性があちらから歩いてくる。沼田署長は笑顔で手を振り返し、沼田署長の隣の小柄で眼鏡をかけた男性は、不敵とも取れる微笑を浮かべる。
「沼田ちゃん!ひさしぶり、元気だった?こちらの方は?」
ハンナさんが笑顔で出迎え、ちゃる捜査官は人懐こく署長に飛びつく。
「このかた、署長のぼーいふれんど?」
それで、沼田署長は目をパチクリさせてちゃる捜査官の頭を撫でなら引きはがし、ハンナさんのエアハイタッチ複雑版を難なく共に舞ってから、ちゃる捜査官の差し出したCAT通信機の画面を確認する。
「しょちょうの彼氏はっけんって、メッセージ来てたのですにゃ。」
沼田署長は笑い出す。
「違うのよ、彼はRNAのランドンさん。今回、最近、ちょっと亀裂の発生件数が上がってるんじゃないかってことで相談に乗っていただいているというか…。」
「我々の方でも、少し気になることがいくつかありましてね。こうやってリエゾンを組ませていただくことにしました。」
「こんにちは!CATのちゃるです!よろしくお願いいたします!」
ちゃる捜査官が礼儀正しく頭を下げると、グレーのスーツの男性は優雅に腰をかがめて礼をし、「よろしく」とまた不敵な笑いで呟く。
「ランドンさんもネズミ人にゃ?マッチョじゃないないにゃ。」
ちゃる捜査官が無邪気に言うと、エージェント・ランドンはしばしの沈黙ののち、楽し気に笑う。
「おや、お若いのにもうマッチョコレーツに遭遇したことが?」
「うん、あるよ。大きくてマッチョで、頑張り屋さんな人たちみたいだよ。」
「はは、その通りですね、マッチョコレーツは...そういう人たちです。」
それでなにかしらの共通の共通認識を確認する二人を、ハンナさんと深堀花子さんは不思議そうに見ている。
「マッチョコレーツって…?」
それで、ちゃる捜査官は先日遭遇したストリートアーティストのビアンカ姫と、その取り巻きのエクスペリメンタル・ラッツの話を始める。ちょうど休暇中で活躍できなかった佐備捜査官も、興味津々でその話に耳を傾ける。
「へえ、そんなマッチョが…」
「そして、テンテイルズが…」
そして、深堀花子さんがぽつり、と言う。
「あたしね、叔母さんがさ、テンテイルズのいたバンドが好きでさ…」
そして、涙ぐむ。
「あたしね、それで、叔母にギター習ってさバンドやってたんだ。なのに…」
深堀花子さんがため息をつく。するとその周囲の空気が一気に冷え込み、彼女の周囲の闇が増す。深堀花子さんのアイラインが一層濃くなり、マスカラがまるで泣いてでもいたかのように目の周りを黒く染める。その髪に闇がわだかまってゆらゆらと揺れ始め、指先からは紫色の霊気が流れ出す。テーブルの上のグラスの炭酸水から色が消え、マドラーが黒く染まってカタカタと揺れる。ハンナさんが心配そうに後ずさり、沼田署長と佐備捜査官は、花子さんの鎮静化に効果がある金木犀の香りの香水に手を伸ばす。空気が湿り気圧が増して重くなる。
「へえ!ギターすごい!」
花子さんの周囲で深まる闇をものともせず、ちゃる捜査官が満面の笑みで言う。
「ねえ!『ぶっ壊しや』って曲、弾ける?」
「え、ええ…?あ、ひ、ひけるけど…」
「ほんとに?ひいてひいて!!」
「い、今ギターがないから…」
「ええーきーきーたーいー!!」
深堀花子さんの周囲の闇は薄れ、そのかわりにちゃるの期待に満ちた目から放たれる光で満ちる。数十秒ののち、エアギターが深堀花子さんによってかき鳴らされ、夜の空気がビリビリと震える。一同は幽霊はエアギターで音を発することができるのだという、新しい知識を獲得する。
「ゆせーいでぃすわずんいんよーぷらーん!」
エアギターから放たれる轟音とちゃる捜査官の明るい歌声で闇は振り払われ、楽しげな雰囲気の名で佐備捜査官とエージェント・ランドンとハンナさんが挨拶と名刺交換を済ませ、それから佐備捜査官が軽食をふるまう。
「キュウリのサンドイッチ、サーモンと玉ねぎの甘酢和え、あとは鶏ささみ、ミニトマトとモッツアレラのオリーブオイル掛けです。幽霊の方にはその気配のハーブ和えを…」
佐備が手早く洒落た紙皿を実体のある人々に配り、籠から取り出した密閉容器の蓋をはずしてテーブルに並べる。
「わあ、佐備さん、人間ぽいのね。」
ハンナさんが笑顔で彼の顔をのぞき込むと、佐備は小学生の大きさで紳士の笑顔を浮かべる。
「日常は人間で過ごしているもので…」
「あら、なんで?」
「我々の一族は人間の食べ物が好きなのです。それから、なんというか、人間の大きさの方が便利なので…」
佐備捜査官が言葉を濁すと、1曲引き終わって休憩しに来た深堀花子さんがスペクトラムジュースをマドラーで吸い上げながら聞く。
「佐備さんの人間姿…て、やっぱり、可愛いの?」
「どうでしょうねぇ、ランドンさんよりちょっと年上の感じじゃないかなと思いますよ、もう中年だし。」
「ほう、ネコビト姿ではずいぶんとおさな…いえ、お若いとお見受けしますが。」
エージェント・ランドンはどういうわけか気を悪くした様子で、ニヤリと笑いながら意地悪を言う。
「あははーそうなんですよね。僕、いつも潜入の時は子供役でして。」
佐備捜査官はあまりエージェント・ランドンのとげのある感じを気にしていない様子でチーズを勧める。
これは一般論だが、花子さん達は幽霊でいることに慣れてくると、若干精神状態によって見た目が変わる。そして、深堀花子さんもハンナさんもその例外ではない。
「人間姿も若いよって、ママは言ってたよ。」
一曲歌い終わってご機嫌なちゃる捜査官が言うと、二人の花子さん達は好奇心で目に星が入る。
「え、若いの?」
「ここからどう変わるの?見たいみたいー」
「そうですね、私からも一つお願いしたい…一緒に働くとなると、ヒト姿もいちど見ておきませんと…」
エージェント・ランドンまでもがリクエストするが、佐備捜査官は、でも子供用のスーツのサイズが、と口ごもる。
008.モーツァルト君と美女たちとピアノ

深堀花子さんが不在の深堀小学校では、お目付け役がいないのでなんとなく締まらない雰囲気だ。だが、ネコビト刑事が来ているなら、厄介事も起こらないだろう。そんな事を考えながら、モーツァルト君はふわふわと浮きながら廊下のゴッホの絵から水仙を失敬し、男子トイレで鬘のキマリ具合を確認する。それから、隣の女子トイレの扉を叩いて、つい期待してしまった返答がないのに笑い出す。そうだ、友人の花子さんは出張中だ。さっき、そのせいで学校に締まりが無いと考えたばかりなのに。花子さんは小学生たちとも仲が良いから、ベートーヴェン君の気になっている曲を教えてもらえないかと思ったのだが、何故出かけている人に聞こうと思ったのだろう。モーツァルト君は、ベートーヴェン君の理不尽な罵倒を思い出してため息をつく。
「君みたいな天才に何がわかるんだ!」
でもねえ、僕だって君だって、ただの印刷された肖像画だぜ…
それから、美術室手前の掃除用具入れの上に載せられた箱から、割と新しいスマホを取り出す。電源を入れると、何種類かの音楽アプリが入った画面が明るく輝く。数年前に友人になった卒業生がプレゼントしてくれたものだ。モーツァルト君は自分からはあまり人間と関わることはないのだが、その小学生はクラシックファンの変わった小学生だった。クラシック音楽は好きだが、楽器は弾けないので聞く一方だ、と言ってたのが、卒業して数年後にはサンプリングされた音楽をどうこう言っていた。モーツァルト君はすっかり影響されて、最近では音楽室にしまい込まれたレコードプレーヤーでDJプレイをしている。目下の悩み事はそれが新任の音楽の先生に見つかって捨てられてしまうのではないかと言ったあたりだが、モーツァルト君はあまり深刻には考えていない。自分はどうせプリント、スマホがあれば模造品のブーシェの絵の美女と踊れるし、これはこれで毎晩楽しいのだ。
「もーおそいー」
緑のドレスの美女が言うと、もうひとりがモーツァルト君に微笑みかけながら「どうせ花子ちゃんのとこでしょ」と言う。
「それがさ、聞きたいことあったんだけど、花子ちゃん、今日出張でさぁ。ねえ、君たち教えてよ」
「うふふ、何を?」
「1曲弾いてくれたらいいわよ」
「楽器ないから」
「それが、あるのよ。バッハ先生が描いてくれたのよー」
ブーシェの美女は、モーツァルトの背中を押して美術室の奥へ誘い、美術準備室の扉を開く。そこにはまだ油の乾かないピアノの絵と、同じような時代の服装をした粋な男性が何名かいる。
「へえ。実は僕、時代的にチェンバロしか弾いたことがなくてさ。やったあ、ひいてみたかったんだ。」
「あら、音楽室のは?」
「鍵かけられちゃうんだ」
「外せないの?」
「外せるの?」
「試してないの?」
「僕、いい子だから」
「またまたぁ〜」
美女たちと談笑しながらモーツァルト君が絵画の中へ入ろうとキャンバスのふちに足をかけると、美女が慌てて引き留める。
「待って、時々ここ、時空が閉じちゃうの。だから…」
美女が合図をすると、粋な男たちがピアノを押して絵の中から出てくる。
「やぁ!アマデウス、待ってたぜ!」
「俺達用の楽器もあるんだぜ!」
男たちは嬉しそうにピアノと管楽器を額縁から引っ張り出す。緑のドレスの美女が、壁の他の額縁からも「叫び」君や「ナルシス」君を引っ張り出しながら言う。
「さぁ、ここで今夜は即興曲パーティーよ!アマデウスちゃん、貴方、弾くのよ?」
「おや、ハードルを上げるなぁ」
そして、モーツァルト君は先日仕入れた演歌のアレンジをグランドピアノで弾き始める。しばらくするとそこに絵画から抜け出してきた男女とその間や人間ではないものたちも混ざって、思い思いに踊ったり談笑し始めたりする。美術室の棚の上では、すました表情の石膏像たちがうらやましそうに美女と青年たちを見下ろし、その下の棚には絵具を乾燥中の生徒たちの絵や粘土細工が並べてある。
009.廊下にて

「うう、北国の酒場的なメロディが『魔笛』の和音でアレンジされてる…」
寝不足の三ツ池は自分が一瞬幻聴をきいているのかと疑うが、隣の繰津がニヤニヤと笑っているので、そうではない事を確信する。繰津はこういう奇妙なものが大好きなのだ。
「おや、三ツ池ちゃん、モーツァルトきくにゃ?」
「聞かないけどこれだけ知ってるんだよね、鰹節屋で流れてて…」
「鰹節屋?」
「でも、あれは…おかしいなぁ、音楽室とは反対側から聞こえる…?」
三ツ池が猫耳をピンと立てていると、人体解剖模型君が偵察から走って戻ってきた外耳パーツ君と軽く話し合って返事をする。
「美術室の方ですね。モーツアルト君がよくパーティしてるみたいだけど…でも、いつもはもっと今っぽい音ですよ。」
コータ君があくびをしながら続ける。
「うん。もっとチャカチャカズンドコした音だよね。」
「そうそう、人数多いと体育館使ってね。いろんな絵の人達が来て…華やかで…」
人体模型君が笑顔で続け、一同は彼にわずかでも笑顔が戻ってほっとする。
「いいねぇ、楽しそうだにゃ。」
「うん、楽しいよ。人体解剖模型君なんか、こないだ青いドレスの女の子に…」
「わわ、やめてよぅ。」
それで、三ツ池と繰津は2人で盛り上がるコータ君と人体解剖模型君にいとまを告げ、美術室の方へ向かう。
「うう、演歌の魔改造、これって意外といけると思ってしまう…寝不足のせいかな…」
「ネコビトに寝不足は鬼門にゃ、頑張り過ぎはダメにゃ。とはいえ、これ…ニャルほど、さすが天才モーツァルト…ん?同じフレーズがリピート…?」
「ああ、サンプリングしたんだよ!気に入った?」
突然に背後から声をかけられて三ツ池とクルツは尻尾を毛羽立たせて飛び退る。
「にゃあ!」
「うわっ」
三ツ池が繰り出したキャット・クロウがモーツァルトくんのカツラの白い毛を何本か切り落とし、モーツァルトくんは後ろに倒れ込む。
「ああ、ごめんにゃ。」
「う、後ろにまわるにゃあ!シャッ」
お怒りモードの三ツ池だったが、廊下にひっくり返ったモーツアルト君を見ると大人しくなる。
「あ、いや、ごめんにゃ。」
「すまんにゃあ、三ツ池はご機嫌にゃなめで・・・ネコビトは寝ないと殺人的になるにゃ」
繰津がモーツァルトくんの手を取って引き起こし、モーツァルト君は「へえ、大変だねぇ」と笑いながら立ち上がる。それから、奇妙な顔をする。
「あれ?君、僕をさわれるんだね。」
「成人男性にしては軽かったにゃ、死人だからかにゃ?」
「いや、僕はただのコピーだから・・・体重も存在もペラいんじゃない?」
モーツアルト君が軽く笑ってうと、繰津は真面目な顔で首を振る。
「よにゃよにゃ陽気なぱーりーしてるモーツァルトなんて聞いたことないにゃ。謙遜も過ぎると毒ぞ。」
「そう?ありがとう。で、どうしたの?」
「実はしんぞ・・・」
「きゃぁぁぁぁ!!!」
美術室から叫び声が響き、青ざめたブーシェとルノワールと、その他名画で顔を見たような気がしないでもない男女が真夜中の小学校の廊下へなだれ込む。
「あれ?みんなどしたの?」
「化け物が、ばけものがあぁああ!!」
髪の毛が幾千匹ものヘビな割には美人な女性が叫び、モーツアルトが「レディ・ゴルゴン!大丈夫?!」と駆け寄る。
「ゴルゴン…別名メデューサ…ってパリピだったんだにゃ…」
「まあ、なんか向いてそうな気も…じゃにゃくて、髪の毛がヘビな人が言う化け物って何ですかね?」
「そりゃあアレだ…きっとデカくてウネウネしたやつ…」
「え、なんも武器持ってきてないすよ」
「わしはあるにゃ。」
「痴漢避けのペッパースプレーじゃないですか。ネコビトを襲う痴漢なんているんですか。」
「いや、ちょっと捕まえてみたくて。」
「あ、それ私もやりたい」
メデューサが楽しそうに会話に参加し始めるので、三ツ池は埒が明かないと判断して、廊下に備え付けの消火器を手に取る。
「繰津さん、協定違反はダメっすよ。さ、いこ。」
三ツ池と繰津は駆け出す。
010. ピアノとGみたいなやつ

美術室は音楽室とは反対の2階に位置し、美術準備室は美術室の奥にある小さな小部屋だ。美術室直前にある手洗い兼筆洗い場の壁と掃除用具入れに身を隠し、三ツ池と繰津は小声で会話する。
「ニャンも見えにゃいにゃ。」
「ヘビアタマちゃん、なんかみえる?」
何故か繰津に付いてきたメデューサに三ツ池が問いかけ、遊び慣れた雰囲気のメデューサは軽い口調で返す。
「えとね、なんか生徒たちが嫌ってるGって生き物みたいなのがざーっとね、で、ソレが集まって…ぎゃああ!」
メデューサちゃんは叫んでなにものかをスカートの裾から払い、次いでピンヒールで踏みつけようとするが、それは素早く飛び退って繰津の厚底ブーツの陰に隠れる。
「うわっ」
「あーあーもう、どいてどいて。」
三ツ池が呆れたようにいい、肩から下げていたポーチから取り出したプラスチック製の瓶をそれに被せる。
「ほれ。」
瓶に蓋をして3人がそれじっくりと観察する。
瓶の中にいるのは、まるで手袋のように派手な色彩の小さな、人間の手だ。表は紫で裏は明るい緑色。指にあたる部分は柔らかいようで、軟体動物のように不定形でぬるぬるとうごめいている。そして、移動した跡には粘質の液体が残り、わずかにプラスチックの表面を溶かしている。
「うへぇ、こっち睨んでる…」
極彩色の手の甲には、全く可愛くない人間の叫ぶ顔が鎮座しており、唇から垂れる涎を膨れた舌で体中に広げている。それが到底自然な生き物の動作には見えず、虫が好きな三ツ池やクリーチャー慣れした繰津にすら嫌悪感を抱かせる。
「うへぇ…なんか、元カレに似てる…」
メデューサも鼻の横にシワを寄せて心底嫌そうな顔をする。
「これが、たくさん?」
「うん。いた、絨毯くらい大量にいた。でかいフナムシみたいにざーって動いてた。」
「メデューサさん、退治、参加する?」
「うーん、いいや。だいじょぶ。」
「ほんじゃ、引き返した方がいい。これ、わしの名刺だから。ニャンかあったら連絡してにゃ。」
「ありがとうー」
メデューサは蛇の髪で、名刺を受け取り、繰津が差し出した猫の手を両手で握って嬉しそうに二回ほどジャンプする。そして、「気を付けてね!」と繰津と三ツ池をハグしてからモーツァルト君を残してきた方へ駆け出す。
「ピンヒールで走れる彼女もバケモノにゃ。」
繰津が笑顔で見送り三ツ池はフレーメン反応の顔で手にした小瓶を見ている。
「顔さえなければヒトデ型ナメクジみたいで可愛いのに…」
そう呟く三ツ池と、ペッパースプレーと線香用チャッカマンを構えた繰津の周囲を、ゾワリと蠢く黒いものが取り囲む。相変わらず、北国と酒場と魔笛の和音のフレーズが、エンドレスでリピートされている。そこに合わせて、おぞましい生き物が呻きのような声を上げる。
011. ニコニコ喧嘩と止まった時計

「ところで、ハンナさん、開会式は確か⋯」
「えーと、0時半からだからあと30分はあるわよ」
ハンナさんがバードランドの前に立つ街灯に備え付けられた時計を見ながらいうと、深堀花子さんが驚いたように言う。
「あ!ごめんなさい、あそこの時計、止まってるの!」
「にゃんで?」
「あ、ええと、そういえば前にカミナリ落ちてたてママが言ってたみゃ…でも…」
地元民のちゃる捜査官が言うと、一同はにわかに焦りだす。
「今何時?」
深堀花子さんが慌てて言う。沼田所長がふわふわのグレーの毛をかき分けて手首の高級時計で時間をみようと試みている。境界ビトの正装であるネコビト姿の署長の毛をかき分けて、ちゃる捜査官が時計を読み取る。
「0時18分だよ。ぬまたさん、用事あるの?」
「あ、挨拶があるの、私と深堀さん」
「あいさつ?」
「え、ええ。ねえ、ちゃる捜査官、あのオジサン2人、止められる?」
佐備捜査官とエージェント・ランドンの笑顔の対決は続いている。30代に見えるエージェント・ランドンは洒落た「老眼鏡」をかけて佐備捜査官の渡した品の良い名刺を検分している。佐備捜査官は、いつの間にか人間姿になっており、ショートパンツのスーツの丈はヒザ下から膝上になっている。佐備捜査官は、頑張っても20代にしか見えない。
「んー…ニコニコケンカは無理だにゃ。でも、どっちもにゃんで若く見えたくないにゃ?」
「うーん、オジサンっていうのはね…」
しかし、ちゃる捜査官の疑問に答える時間は沼田署長にはない。
「ごめんね、説明したいけど、もういかなきゃ」
「大丈夫よー行っていって」
沼田の焦りに気付いたハンナさんがちゃる捜査官の手を取って沼田を追い出す。だが、その隣にもう一人の挨拶要員の深堀花子さんはいない。深堀花子さんは凍りついている。紅潮しない筈のお化けの頰が真っ赤に染まり、体から漏れ出す霊気が薄い桜色に染まっている。
「ふ、深堀ちゃん…?」
ハンナが声をかけると、深堀花子さんは我に返ったように桜色のオーラを引っ込める。
「あ、あれ、あれが佐備捜査官…?」
佐備捜査官から視線を外さずに深堀花子さんが呟く。
「そうよ。オジサンだけど、人間姿だと18歳くらいにみえるわよね。でも本人にいっちゃ駄目よ、傷付くから⋯」
沼田署長は言いながら、まだ上の空の深堀花子さんを掴もうとして中空を引っ掻く。
「は、花子さん!?」
沼田署長の高級腕時計は長い毛の下で、0時20分を示す。ハンナさんが、ちゃる捜査官に何事かを囁く。ちゃる捜査官は頷いて甘えた子供の声を出す。
「ねーねーはにゃこさん、エアギターして〜」
ちゃる捜査官にリクエストされた深堀花子さんはお姉さんモードに立ち返ってエアギターを掻き鳴らし、桜色を頬の上にだけに残してキリリと表情引締め、沼田署長と会場へ急ぐ。
012. 「should you need us」
全国花子さん大会の今回の会場は、ちゃる捜査官の通う猫草台小学校だ。深堀小学校と同じ建築家が担当した木造りの校舎と体育館で、こちらの校舎には数点の疑似ステンドグラスもあしらわれている。深堀小学校にも当初は予定があったのだが、設置して早々に理由なく割れてしまう事態が2度ほど続き、予算の関係で導入が中止された。
「皆さま、おはようございます。」
司会の犬山小学校の花子さんが滑らかな声で開会を告げる。
「全国の花子さんならびにご関係の皆さま、境界内外のご来賓の皆さま、本日はお忙しい中、第75回全国花子さん定例会議にご参集いただき、まことにありがとうございます。また、会場をご提供いただきました猫草台小学校の校長先生⋯はいらっしゃらないので代理の生徒代表、佐備さん、ちゃるさん、ありがとうございます。あ、お席にいらっしゃらな…」
ひとしきりのお礼と犬山花子さんの自己紹介とが続き、ついで、人間的な枠の堅苦しさに飽きてきた幾人かの花子さんがふわふわと浮き出す。皆、姿は10歳から18歳くらいの若い女性で、亡くなった年齢は多岐にわたれども皆、子供と通じ合える部分があるくらいなので、心は若い。しかし、普段は子供達と接するために気を張って生きている。故に、花子さん達は周囲に子供がいないかえって若返る。もしくは、子供還りする。沼田署長が形ばかりの来賓挨拶を終える頃、花子さん達はさざめきのような囁きの会話とクスクス笑いで会場を満たしていた。
「えー誰でもトイレへの出現の可否についての小委員会は階段を上がって右の家庭科室、音姫と花子さんヴォイスの相性についての小委員会は1年3組の教室で…皆さん、すみません、後ろの方聞こえますか?」
犬山花子さんが、連絡事項を述べようにも会場が静まらないのを見て、深堀花子さんが代わりに登壇する。
「犬山さん、一度盛り上がってから落ち着いて貰おう。」「はい。お願いいたします、深堀さん。」
それで、深堀花子さんは、先程まで沼田署長が挨拶に使っていたマイクを演台からかっさらう。
「はーい!花子さんのみんなー!!」
深堀花子さんはマイクで観衆に声をかけ、エアギター掻き鳴らす。花子さんたちの注目が深堀花子さん集まる。
「いっくよー!全国花子さんソング!!」
会場からは歓声が上がり、目をきらめかせた花子さんたちが立ち上がる。深堀花子さんはエアギターを投げ、何故かそれが床に落ちる音がし、演台は後ろにさげられてドラムセットと第二のエアギターが登場する。深堀花子さんはマイクを手に手拍子でリズムをつけると、そこから歌いだす。
第一花子さんSONG
Knock knock knock
いつでもお付き合いできるわけじゃないのよ
そんなにお暇なわけではないの
時は短し遊べよ子供
なんでも一人でできるわけじゃないでしょ
あんまり抱え込んじゃだめ
時は短しask for your help kid
扉は3度叩いてね
in case that you need me
大抵はそこにいるわ
should you need us
should you need us
call me
call out my name
yeah I am Hanako-san
そこから、3曲ほど花子さんソングが続く。全国の花子さんたちは大いに楽しんでいる。花子さん達の気持ちがひとつになり、照明が控えめになり、バラード曲「たとえ忘れた事さえ忘れても」のイントロが始まったときだった。
突然、轟音がひびき、舞台の板床が激しい音を立てて割れ飛び散る。突如出現した奈落へと、演台とドラムセットが崩れ落ち、ドラマーの花子さんが悲鳴を上げて中空へ飛び退る。ドラムを呑み込んだ床の亀裂はバキバキと音を立てて床板だった板材が立ち並び、それから地下へと吸い込まれゆく。緞帳は激しくはためき、まるで真空へ手繰られるように亀裂へと引き寄せられていく。
「犬山さん!」
素早くドラマー花子さんを開けてバスケットコートの方へ逃がした深堀花子さんが、緞帳とともに亀裂へと吸い寄せられていく司会の犬山花子さんに気付いて取って返す。
奈落の底から、巨大な生き物の叫び声がし、真っ赤な炎が吹き出して板材を焦がす。
013. シュローディンガーの兄
「もう! なんで電話でないのかしら…」
フワモコ王国では不破望子がスワン型の固定電話を耳にイライラしている。義母の米子トラも、友人の沼田署長も、頼みの綱の鬼ヶ首カリンまでもが電話に出ない。マッチョたちの間からその様子をうかがいながら、住野と蔵市が小声で話し合う。
「え、不破さんの仰ってる鬼ヶ首カリンって、あの…?」
「ええ、ワビサビ桃源郷のカリリン師匠モデルよ…」
「実在するんですね…」
「あら、鬼ヶ首カリン、昔は割と有名だったのよ?まあ、蔵市さん若いから知らないか。」
「そうなんですねー…」
マッチョ達は思いの外礼儀正しく、室内のロココ風の調度品をこれ以上壊さないように細心の注意を払っている。少し前、蔵市が鼻血を吹いて倒れた時には、頭を打たぬように支える担当や、手から取り落としたタブレットをキャッチする担当、そして「北国の黄金」ヨリックを一応ガードする係の3人が急に動き、疑似ロココの花瓶が床で砕け散った。今は、巨大な陶器の置物のように硬直して動かないマッチョの手前に、長椅子に腰掛けて大人しくしている普通サイズだが腹筋は板チョコの男性がいる。腹筋の板チョコの上には、バラ柄の艶のいい布がかかっている。
「ヨリックさん、そのカバー、多分絹だから息苦しいんじゃない?もう、顔から取っても大丈夫だと思いますよ」
住野が、笑いながらそちらへ声を掛ける。彼は、クッションカバーを顔に被ったままで優雅に、しかしそこはかとなく可愛らしく長椅子に腰をかけている。
「そう?でも、僕の顔をレディがこわいんじゃあ取れないよ、いいんだよー」
ヨリックは自分の美しさには気づいているが、それ以上に自分が連れ歩いているマッチョの一団と同程度か、それ以上に怖そうに見えるとの歪んだ自己認識を持ってる。
「多分、蔵市はあなたが怖いわけじゃないと思いますが・・・」
「そうかなぁー? ホントに? ホントにこわくない?」
そんな会話を、バラの柄のクッションカバーを被ったヨリックと、住野がはじめる。蔵市はそれでも、今はヨリックがクッションカバーを取らないで欲しいと願う。その蔵市の願いが届いたのか、受話器を手にした望子が振り返ってクッションカバーをかぶったままのヨリックへ声をかける。
「ヨリックさん、ごめんなさい、お義母さまも沼田署長も、つかまらないわ。よかったら私の方で用件をお伺いしますけれど…」
ヨリックはバラ柄のつやつやしたクッションカバーのまま、隣に立つ黒髪で大柄なマッチョ男性に「うーん、ねえ、話してもいい?」と聞く。
黒髪のマッチョは「致し方ないでしょうね」と無表情で返す。それでヨリックは、不破望子の方に向き直り、彼女にだけ見えるようにクッションカバーを目の上まで引っ張り上げて話し出す。
「僕らね、北の方のサンタとご近所の、さる王国の王族なんだ。あ、あの、アメリカン・ローデンツ・キングダムの系譜ではないよ。もっとちいさいよ、すごく小さい国だよ。で、僕の妹ね、あそこのテンテイルズの絵を描いたコなんだけどね。アーティストネームはシュローディンガー。知ってる?」
不破望子はお気に入りのストリートアーティスト、シュローディンガーの兄と名乗る男性をしげしげと眺める。
「あ、ええ、シュローディンガーさんのお兄様…?」
望子が疑わしげなのも仕方がないのは、彼らが全く似ていないからだ。屈託のない笑顔も、バラのクッションカバー下から溢れる金髪も、それが流れ落ちる先の割れた腹筋も太い腕も、妹にはあまり似ていない。
「ええと、ビアンカさんでしたわよね。褐色の瞳のお綺麗な…」
すると、ヨリックはアクアマリンの青の瞳を煌めかせて嬉しそうに笑う。
「うん、そうなんだ! ははは、僕ら、あんま似てないでしょ? 僕ら、パパが違うの。でさ、僕の妹ね、行方不明なんだ。米子トラさんとか、貴女とか、ネコビトさんでしょ? 意外と怖くないよって妹が言ってたなーって思い出してさ。探してくれないかなと。」
「行方不明?ビアンカさんが…? 神出鬼没の芸術家なら、それが普通というわけでは…きっと、ないのですね?」
「うん。いつもはよく電話くれるんだよね。でも、ちょっと前から、通じなくて。僕にも、親衛隊のマッチョコレーツにもコンタクトがないなんて、変なんだ。」
「その、こちらの方々が、マッチョコレーツ…?」
「うん。ここにいるほとんどのマッチョボーイズは、マッチョコレーツ・エクスペリメンタル。妹の親衛隊なんだ。で、彼とビリーだけ、マッチョコレーツ・エクスプローシブ。僕の親衛隊だよ。」
黒髪の年かさの男性が頷き、ビリーは笑顔で片手を上げる。住野が小声で「ビリー超かわいい」と呟くのを蔵市は聞き流しながら、その下の顔を想像しまいとしながらバラ柄のクッションカバー話しかける。
「では、皆様全員…その国のどなたかの親衛隊なのですね?」
「ん?そーだよー」
「あ、はぁ、そうですか…」
クッションカバーのバラ柄がこちらへ向き直り、明るい声が聞こえてくると蔵市は軽いめまいを感じて曖昧に微笑んで会話を終えてしまう。そこへ、扉を叩く音がする。
「あ、あら、何かしら…」
モコが扉へ向かおうとする同時に、扉が開き、麻酔銃を構えたスーツの一団と、何やらフワフワした白い塊ががなだれ込む。今度は望子が青ざめる番だ。白い椅子がなぎ倒され、マッチョの一団が腰まで白いフワフワしたものに埋まるのを見て、望子がため息つく。
「ああ…」
014. 行方不明の親族
「モコさん、もこさん!」
「あ!はい!ここに!」
溢れ出した白い塊はフワフワとした見た目とは裏腹に、嬉しいときのウサギのように元気よく跳ね回る。その向こうから品の良い女性の声と咳が聞こえる。
「またワタボコリが…ケホケホごめんなさい、亀裂廊下を通ってきたら、ホコリが変化してダストバニーズが大量発生しちゃったみたい。亀裂が不安定になっているわね。」
つややかな白髪を肩で綺麗に切りそろえた和服の女性が、レースのあしらわれたハンカチで口元を押さえながら跳ね回る塊の向こうから現れる。不破望子の義母、米子トラだ。
「あらあら、模様替えなさったの? マスキュリンな彫刻がいっぱい…あらまあ、ダストバニーズまみれ…」
米子トラは、見慣れた疑似ロココ調の室内に居並ぶ軍人風の人々に張り付いたワタボコリのキャラクター、ダストバニーズを掴んでは今入ってきた扉の向こうに投げ返す。
「ホウキはこのお部屋にはなかったかしら? あら、彫刻かと思ったら生きてる…ごめんなさいね、ほほほ…」
トラは屈んだ姿勢のビリーの頭から、フワモコ王国の有名サブキャラクター、ダストバニーズを払いのけ、若干名残惜しそうなビリーに気付くと、「差し上げましょうか?」と微笑む。
「ありがとうございます! うちの娘たち、大好きなものですから!」
「まあ、娘さんたち? お二人いらしゃるのかしら?」
「はい、双子で。もうすぐ三人になります。」
「あら、素敵。子供ってかわいいわよねぇ…では…」
トラは着物の襟元から懐紙入れを取り出し、そこから薄紅色の紙を一枚引き出すと、小さくネズミ語でささやきかける。すると、薄紅色の懐紙は手のひらの上で素早く自らを折り畳み、小さな小箱を形作る。それから、まだビリーの肩に残っていた5、6匹のダストバニーズを捕まえてその中に閉じ込め、ビリーの大きな手のひらにちょこんと乗せる。
「ありがとうございます!」
ビリーは嬉しそうに礼を述べ、トラも微笑む。あちらでは、ちょっとかわいいと思っていたビリーが既婚者だと知り若干がっかりした様子の住野がホウキを取りに廊下へ出ていく。
「トラさん!もしかして、トラさんですか? ネコビトだと思ってた!」
住野と入れ替わりでトラに近づくのは、相変わらずクッションカバーをかぶったヨリック王子だ。
「ええと。そうよ。もしかして貴方…リーピチープ王国のヨリック王子?」
「はい! よく知ってますね!」
その声だけで、輝くような笑顔が想像できる蔵市はめまいをおぼえ、リーピチープ王国についての知識を総動員して気を落ち着ける。
リーピチープ王国は欧州の山の中にある小国で、代々の元首は女性が務めている。30年くらい前までは鍾乳洞やサファイアなどの鉱物が有名だったが、最近は地下施設で量子関係の実験を行っている経済新聞電子版で読んだ気がする。しかし、SNSで人気のヨリックがリーピチープ王国の王子だとは知らなかった。それとも、自分が笑顔と腹筋と前向きなメッセージに惑わされて見落としたのだろうか。彼は、リーピチープ王国のステルス集客装置なのだろうか? うん、それならそれで、いい。
蔵市のとまどいをよそに、小柄な米子トラは腹筋の上空に目を向け、持ち上げられたクッションカバーのから覗く青空のような瞳を見上げる。
「ええ…存じ上げておりますよ。夜叉孫がお世話になっているものだから…いえ、なっているのだと思うのだけど。それで、あの、セドリック、まだそちらにいます?」
「え?」
「いないのね・・・」
米子トラはがっかりした様子で肩を落とす。専用吸引機でダストバニーズを吸いながら扉口に近づく不破望子は、優しく声かける。
「お義母様、またセドリックさん行方不明なんですか?」
「そうなのよ、なんでも、仕事が落ち着いたから友人を尋ねるって…てっきり、また、ビアンカさんのところだとばかり…」
そして、トラがため息をついて中空に腰をかける動作をすると同時に、目にもとまぬ早業で黒いスーツの若者がトラの腰が落ち着く先に折り畳みの椅子を広げて受け止める。不破望子のオフィスは、白い家具と筋肉質な一団と白いふわふわしたキャラクターとスーツにサングラスの青年達で足の踏み場もない。
015. 須子ゑ氏と4人目の行方不明者

須子ゑ氏は、カウンターの中で1セットで30万するカップを丁寧に拭いている。表には「準備中」の札がかかっている。ずらりと並んだ高級品のカップを満足そうに眺めて「ボン。」と呟いてから、スーシェ氏は思い出したようにカウンター席で肩を落としている吉田に呼びかけた。
「吉田さん。」
「はい。」
「CATとはいい関係でいたいとお知らせしましたよね。」
「はい。」
「何故、ヘイスタック君の件をきちんと話さないのですか。このままでは泥棒扱いです。」
「すみません。いっちゃいけないのかなって。」
「ノン!それは違います、我々はCATやRNAと対立したくはないのです。もはやこの依頼はプライベートな案件とは言えません。ヘイスタック君は誘拐の手掛かりを探していたのです。ようやく、見つかったとの報告は受けていますが、見つかったのと救出は別問題ですからね。親御さんは依頼主に多大な圧力をかけています。このままでは…ですから、もしもCATやRNAが力を貸してくれるのであれば、その方がいいのです。」
「ああ、そうですか。では、次、遮無さんに会った時、いってみます。それでいいすかね。」
「ウイ。しかし、この依頼は・・・」
スーシェが独り言のように呟き、つややかな口ひげと明るい瞳の上に並んだ黒い眉をくもらせる。吉田がメニューに目を落とし、「タマシイの天ぷら黒蜜がけ」を頼む衝動に負けようとしたその時、アール・デコ調の洒落た扉に吊るされた鈴が鳴り、帽子を目深に被った男が入ってきた。まるで昔の映画のマフィアみたいだな、と吉田はなんとなくの印象で考える。彼は大きな紙袋を抱えている。男性はまっすぐカウンター席の方へやってくると、吉田に明るい声で挨拶する。
「やあ、吉田くん!」
それから、店内が無人なのを確認すると大きな帽子を外す。彼の顔には鼻がなく、代わりに大きな目が人間の目と鼻の領域にまたがってある。その握り拳ほどの大きさの目玉は、優しい茶色の虹彩で吉田を見下ろしている。吉田は、少し落ち着かない気分になるが、ヘイスタック氏が温和な妖怪だとは知っているので、恐ろしいという気持ちにはならない。
「へイスタック君!君は、張り込み中だったのではないのですか。」
「それが、美人な猫警察さんたちを巻いたかとおもったら、今度は人間の警察にも職務質問されちゃって。慌ててキグルミを着ようとしたら、破れちゃったんだ。で、これ、ミス・オレンジに直してもらえないかなって。」
「ミス・オレンジは縫い物はしません…事務的なお願いはしていますが…まあ、とはいえ、縫い物が得意な方をご存知かもしれませんね。」
「オレンジさんて、あの美猫の。」
「ええ。しかし、捜索人を誰も見張っていないとなると気になりますね。」
スーシェ氏は顎に手を当て、少しの間考え込む。誰もいないせいで少しの間、気が抜けのか、キラキラした聡明な目や口ひげの上の鼻が消え、その顔はきれいに剥いた卵のように何もなくなる。吉田は、何故ただのネコビトギャング団の下っ端の自分が、のっぺらぼうやCATと関わっているのかと奇妙に思う。別に悪いことはしていないが、なんだか恐ろしいような気もする。
と、喫茶店の入り口でチリンチリンと音がする。「準備中」の札に気が付かなかったようで、緊張した面持ちの人間の女性がドアから顔をのぞかせる。スーシェ氏はとたんに優しい笑顔を取り戻し、いらっしゃいませ、と言って女性たちを迎える。ヘイスタック氏は額から口元までを手のひら撫で、刑事物の役者のような目と鼻をどこからともなく出現させる。そして、何か言いたげな吉田の肩を叩く。吉田は、グレーと白の縦縞のシャツを着た、若い人間の男性姿をしてる。
「吉田くん、猫じゃない時はそういう顔なんだね!」
「ああ、はい。で、キグルミ…いるんですか?もうCATの人たちに知られてるし、人間姿じゃダメなんすか?」
「僕、人間に化けてるとモテちゃうんだよね。まあ、もう捜索人、たぶん見てなくても大丈夫だよ。彼女はここで仕事も持ってるし、また消えるなんてなんてことはないと思うよ。」
「探してたのって、女性だったんですか!それをタヌキのキグルミ着た男性が付け回すのは、人間の世界では問題になりそうですね、もうやめたほうがいいすよ。」
「そうなのかい?」
「ええ、やばいっす。でもあの…なんで、タヌキなんですか。」
そこへ注文を取って帰ってきたスーシェ氏が言葉を挟む。
「ノン、タヌキではなく、アライグマです。貴方のギャング団のムッシュ・ラスカルが、侵入が得意と聞きまして…秘密裏に行動したかった我々としては、彼にならうことにしていたのです。」
「スーシェさん、ラスカルは…自分ではそう思ってるだけで、実際のところはすぐに捕まるコソドロです。」
「ふむ。それは困りましたね…」
そう言ってスーシェ氏はにっこりと微笑む。ヘイスタック氏はあまり何もわかっていなさそうに、しかしやはりニコニコ笑う。吉田は、さてはこの妖怪達、何かあったらラスカルに面倒を押し付け消えるつもりだな、と考える。
016.「むじな」で0時に待ち合わせ

「こんばんは」
真夜中を少し過ぎた頃、須子ゑのカフェ「むじな」ではようやく「準備中」の札が「Entrée」にかけ代わった。捜査官の遮無、分地が談笑しながら扉を開き、チリンチリンと鈴が鳴る。遮無が店内を見回すと、ツヤツヤとした白い頬に上品な微笑を浮かべた須子ゑが迎える。
「いらっしゃいませ。」
「こんばんは、スーシェさん。あの、三ツ池ちゃんと繰津ちゃん、まだ来てません?」
「ええ、お待ち合わせでしたか?」
「そうなんです。『むじな』で午前0時にねって言ってたんですけど。」
「そうですか。しかし、本日は沼田さんと青木さん、あとは雨所さんにしかお目にかかっていませんねぇ…」
「そうですか…三ツ池、こちらの秋の新作メニュー、楽しみにしてたから、絶対来ると思うんだけどなぁ。」
「うん、来れると思ってなくて割引券あげたんだけど、すごく嬉しそうだったよ。ちょっと前の現場が押してるだけじゃないかな?」
「あれ、なにかあったけ?」
「実は深堀小学校に寄ってもらったと思うんだけど…遠かったかな?」
「深堀小学校ですか。実は、すごく近いんですよ。」
須子ゑが、品とタイミングよく情報を挟む。
「そうなんですか?」
「ええ。実は…近道に使える境界亀裂がありましてね。最初は危険かなともおもったんですが…同世界内なせいか、安定しているんです。時々あちらの境界ビトの先生も、それを通ってこちらに寄ってくださりますよ。」
「へぇ…境界亀裂…まぁ、昔からある場所ってありますよね。パワースポットになっている例もある。」
「そのようですねぇ。おや、いかがなさいました?」
興味深げに話す遮無とは対照的に、分地の猫耳は倒れ、首の毛が立っている。
「あ、ぶちは…」
遮無が気を使って何か言おうとするのを遮って、分地は抑えた声で言う。
「境界亀裂に、落ちたことがありましてね。安定ね…まあ、安定していそうでそうでない場所もありますからね…」
分地が無理やりに笑顔を作ると、顔の右側で、毛色の分かれ目に沿ってゾロリと歯の並んだ口が耳まで裂け、目玉も裂け目の上に新たにもう一つ出現する。須子ゑの微笑みが一瞬消える。が、須子ゑは須子ゑで妖怪なので、すぐに品のよい微笑にもどって「ウイ。」と頷く。そして、二人の様子を伺っている遮無と、毛の裂け目を仕舞った分地を、テーブルへ案内する。
席に着くと、あちらの席に座った女性が目に入る。スラリとした品の良いその女性は、ボリュームのある白っぽい金の巻き毛を胸元まで流し、透け感のある布を多用した緑色のワンピースを着ている。その肌も透けるように白く、ただ唇と頬は品の良いバラ色だ。ムッシュ須子ゑは軽く微笑みかけ、「お茶をまたお持ちしましょうか?」と声をかける。
「ええ…では、ミルクティーで…ああ、だが、わらわは煮干しは召さぬゆえ…入れぬようにしてたもれ…」
「ウィ。ミミジャも要りませんか?」
「ミミジャ…あ、え、それは、では、お願いできたら嬉しいかもしれんのぅ…」
「あ、こっちは『サツマイモと小豆と秋刀魚の三角関係』2つと、私は、カフェ・オ・レ、分地はブラックコーヒーでお願いします。」
「ウイ」
クールな遮無が遠慮なく注文をすると、須子ゑはそれを伝票に書きつけて微笑んで小さく会釈し、立ち去る。自分のバケモノ顔が一般客に目撃されなかった心配だった分地が隣のテーブルの女性に視線を目をやり、急に笑顔になって彼女に挨拶する。
「お隣の席、どなたか思えば…小川先生!」
ノンビリとカップに描かれていた薔薇を愛でていた隣の女性は、声をかけられると驚いたように顔を上げる。
「おや、そちは、たしか、ちゃる捜査官のご母堂…ちゃる殿は本日は…おられぬようじゃな…」
「ええ。今日はCATの仕事でして。」
「左様か、残念じゃ…そちらは、では、CATの方ぞな…?これはこれは…」
小川先生は遮無に、挨拶代わりに微笑む。微笑むと目元に走る細かい線からすると、どうやら大人と呼ぶにふさわしい趣きあるの女性だ。しかし、年齢不詳の、のんびりした可愛らしさのある雰囲気だ。
「ええ、こっちは遮無、凄腕の捜査官です。」
ちゃるママこと分地も嬉しそうに遮無を紹介し、遮無捜査官は軽く頭を下げ会釈する。遮無捜査官のほうは、怪訝そうに分地と「小川先生」を観察する。長い手足に白銀の巻き毛、小川先生は到底一般人には見えなかったが、分地は小川先生を、深堀小学校の美術の先生として紹介する。
「小川先生、プライベートは華やかなんですね。」
「プライベートは?」
遮無は、この妖精の女王のような女性からどうすれば華やかさがなくせるのかという疑問を、この巻き毛だけで彼女を音楽家「バッハ」になぞらえたセンスの小学生を考慮して、可能性を排除しきれないがゆえにオウム返しで問いかける。分地はそれを知ってか知らずか、補う情報を追加する。
「いつもは髪はくくるかお団子で、ジャージかツナギをお召しですもんね。」
「うふふ、これはわらわの実家から持ってきたものなのじゃ…こちらではお茶をするときに何を着ていいわからぬゆえ。絵を描く時はツナギという衣装を着るのじゃが。わらわ、ほんとうはコレより、ツナギの方が好きでの…」
「ツナギ格好いいですもんね。」
「うむ。それにジャージとやらはも、動きやすいしのぅ…」
それで小川先生と分地は楽しげに会話をかわし、ちゃる捜査官が今夜は「花子さん会議」に出ていることや、深堀花子さんやすねこすりっ子のコータくんの話題に移る。それを遮無は事情が分からないながらも、色々と推測して補う。
「最近は、ヴェートーベン殿が何か悩んでいるようでの。いつも、同じ曲を途中までひいてはやめてしまうのじゃ。」
「ヴェートーベン?」
「彼とモーツアルト殿は七不思議の一つじゃ。他にワーグナー殿やサティ殿もいらっしゃるが、なかなか起きては来られぬの。」
「ああ…小学校の先生がこんな夜中にと思ったけど…やっとわかりました。先生も、境界ビトでいらっしゃるんですか?」
遮無は思った事を口にしたまでだったが、どこかのんびりした感じのある小川先生の周囲の空気が、少し張り詰める。分地は驚いた様子で小川先生を見つめる。小川先生は、そして、遮無捜査官を嫌いだと決めたらしい。須子ゑが運んできたミルクティーを一気に飲みほすと、遮無を完全に無視して席を立ち、分地に挨拶をする。
「では、ぶちどの、またお目にかからんときまで暫し、いとまを…」
「あ、夜も遅いので、送りますよ。」
「いや、それには及ばぬ、大丈夫じゃ。道があるのでの…」
「道?」
「うふふふ…」
そう笑うと、小川先生は鈴のついたドアではなく、店の奥の方へ歩き出す。通りすがりに須子ゑに何やら大きな金貨を渡し、恭しく礼をされる。そして、壁に掛けられた大きな額縁の前に立つ。その大きな額縁には、古風な木造りの扉が描かれている。現実と見まごうばかりに写実的に描かれた扉には、ガーゴイルの顔が輪を咥えた形のドアノックが描いてある。ガーゴイルは、小川先生が近づくのを見ると、真鍮の小さな腕で口から輪を取り外し、何事か捲し立てる。
「…絵のガーゴイルがしゃべってる…なんだこれ、新しいタイプのディスプレイか…?」
遮無が目を丸くして分地に問いかけ、分地はフレーメン反応の顔をしてあんぐりと口を開け、ガーゴイルを見ている。小川先生は優しい声でガーゴイルに何事か語り掛け、ガーゴイルは頷いて口に輪をはめる。とん、とん、と小川先生が優しくそれを鳴らし、扉が開く。あちら側には、オートロックの鍵穴を備えた、少しお高いマンションの入り口が見える。
「では…」
小川先生が会釈をしながらその向こうに足を延ばしたとき、あちら側でマンション入り口のオートロックの扉が開き、背の高いトレンチコートの男が姿を現す。彼はぎょっとした様子で立ち止まる。その拍子に左右一体型のサングラスが外れ、それが床に落ちてコツンと音を立てる。すると、急に扉とマンションの入り口が勢いよく遠ざかる。マンションのオートロックの鍵穴台が急に小さくなり、木造りの扉とマンションの床の間が黒く沼のように溶ける。
「あ⋯」
小川先生がバランスを崩し、扉の反対側に顔を出しなおしたガーゴイルが、小さい悲鳴を上げる。その様子を見て、これが異常事態だと判断した遮無が、ネコビトモードで素早く飛び出す。境界から身を乗り出して、半ば闇に呑まれかけた小川先生の白い足首を捕まえる。その遮無のピンヒールブーツを、分地が猫爪を突き立てて掴む。小川先生と遮無は引きずられるよう落下するが、分地が描かれた扉に片足をかけ、滑り落ちるのを防ぐ。遮無が境界亀裂へぶら下がる小川先生の足首を掴み、分地が遮無のブーツを掴み、そのままジリジリと、綱引きのように後ろに下がる。
「ノン!」
呆気に取られていた須子ゑも我に返り叫んで駆け寄る。遮無のもう片方のブーツを掴もうとするが、そのヒールの鋭さに怯む。分地はそれには構いかけずに、遮無の高そうなブーツを気にする。
「遮無ちゃんごめん!ブーツ穴あいたかも。」
「いいの、古いし。ありがとう、そのまま引っ張り上げて…わぁ、なんだ?!」
突然、分地の腕時計型端末から耳をつんざくサイレンがなり響く。ぶちはそれをちらと確認すると、片脚で描かれた扉を蹴って、素早く一気に遮無と先生を引き上げる。サイレンは相変わらずの大音量で分地の腕時計型特殊通信機から響いている。分地はその音を止めて内容を確認すると、一息に境界亀裂へ飛び込んでいく。後には、放り出された遮無捜査官と小川先生が、水揚げされた地引き網のように転がっている。
017. 境界亀裂と異世界
その亀裂は大きかった。猫草台小学校の体育館の舞台は見るも無残に破壊され、まるでそこに真空の宇宙空間が広がるかのように暗く、どうもそれ独自の引力があるように、周囲の物を引き付けて暗闇に吸い込んでゆく。その向こうから、空間を引き裂く叫び声がする。巨大な弦楽器を無理矢理に弾いているような音だ。
「うう、引っ張られる…」
犬山花子さんを裂けた板材の間から救い出した深堀花子さんだったが、今度は自分が暗闇に引き寄せられている。深堀花子さんは意識を手のひらに集中させ、板材を掴む。幽体でも、死ぬ気で集中すれば物質を掴める…けれど、こんな頑張る必要があるのかしら?私、この世界に未練なんかあったかしら…?このまま、手を離して、どこへ行くのかしら、天国?あるいは、異世界…でも、荒野だったらやだな…
そんな思考が生じ、深堀花子さんの幽体が板材を掴む力が弱くなる。手のひらが透ける…
「はにゃこさん!」
ちゃる捜査官が、飛び出した板材の間を縫ってかけてくる。
「だ、ダメよ、危ない!!」
深堀花子さんが叫ぶのを無視して、ちゃる捜査官が深堀花子さんの手首を掴む。深堀花子さんはその握力に驚く。ちゃる捜査官は一生懸命の子供の可愛さと、CAT捜査官としての大人びた顔の両方の表情で必死に深堀花子さんの手首をつかんでいる。子供の握力としては若干痛いくらいの強さだ。幽体であるはずの腕に、短く整えられた爪が食い込んで痛い。
「ありがとうちゃるちゃん!」
深堀花子さんが集中力を取り戻し、もう片方の手でちゃる捜査官の腕をつかむ。しかし、そこでちゃる捜査官の子供ネコビトの爪が図らずも板材から抜け、二人は境界の奈落へと吸いこまれそうになる。
「ああっ!!」
「にゃあああ!!」
「ちゃる!!」
追いついた佐備捜査官が、ちゃる捜査官の足首をすんでのところで掴む。佐備捜査官の毛は吸い込まれる空気による風で乱れ、そのせいで余計に若く見える。
「サビにゃん、ありがとにゃ!!」
ちゃる捜査官が嬉しそうに振り返って言う。しかし、佐備捜査官もまた、板材にしがみついた片手でちゃる捜査官を引き戻すのに苦労している。足を板材にかけ、なんとか両手を自由にする。
「あっちに何かみえるみゃ。」
ちゃる捜査官は佐備捜査官の苦労も知らず、明るい声でいう。しかし、花子さんが若干安定して浮力を取り戻すと、ちゃる捜査官は深堀花子さんを引き寄せて佐備捜査官にその手首をひょいと渡してしまう。
「あ、ちょっ、ちょっと待ってね、人間に…」
佐備捜査官は子供ネコビト姿よりも成人人間姿の方が筋力があると判断し、人姿に姿を変える。
「あ…」
その姿を目にした、深堀花子さんが息を呑む。乱れた髪の下のサビ捜査官は、17,8歳の若者のように見える。それが花子さんの、失われた記憶を蘇らせ、花子さんのオーラを桜色に染め上げて佐備捜査官に吸い寄せられる。それに気付かず、サビ捜査官は一気にちゃる捜査官を引き戻し、板材の間に避難させ、深堀花子さんの差し出した手を掴む。深堀花子さんの桜色のオーラがサビ捜査官の手のひらから伝わって全身を包む。佐備捜査官は驚いてしばし動きを止める。その瞬間、ちゃる捜査官が避難させられていた板材の間から飛び出して叫ぶ。
「見えた!ドラゴンにゃあ!!かわいい!!」
そして、振り返りもせず、境界亀裂へと続く暗闇へ飛び込んでいく。
「あああああ!!」
佐備捜査官が慌ててその尻尾を掴もうとするが、その手は届かない。ちゃる捜査官は、板材の上をひょいひょいと越え行く。ところが、境界の暗闇は、ちゃる捜査官が通り過ぎたあとには金色の壁に変わる。事態を理解できないまま、佐備捜査官は必死にちゃる捜査官を呼ぶ。
「ちゃる捜査官!!」
「ちゃるちゃん!!まって!!」
深堀花子さんも既に桜色のオーラをかなぐり捨てて我に返っている。そして、先程までは暗い奈落であった空間へ、金色の眩しさに目を細めながら飛び込み、ちゃる捜査官の後を追う。体育館の舞台が崩れ落ちた下を少し下ると、その先は別の空間が続き、到底ここが体育館やその裏の校庭だとは思えない。黄金の壁と道が、異空間へと二人を導き、サビ捜査官と深堀花子さんは必死にちゃる捜査官の消えた先へ進む。彼方のラベンダー色の空から、巨大な弦楽器のような何かしらの鳴き声が鳴り響く。
「ちゃるちゃん…」
深堀花子さんは心配でたまらないように呟き、佐備捜査官は青ざめている。そして、呟く。
「殺される…」
二人が後にしてきた空間、つまり小学校の体育館の方から、凄まじい轟音と叫び声が響く。
「まずい、にげろ!」
叫ぶと佐備捜査官は深堀花子さんの手首を掴み、ラベンダーの空の下、黄金の道を走り出す。「さ、サビくん!?」
深堀花子さんは思い出した。これは、サビくんだ。高校1年生のとき、クラスメイトだったサビくんだ!!ネコビトだったの!?それに、こんなにオジサンなのにオジサンじゃないんてズルい!そして…わたし、サビくんに手を引かれて走っている!!ずっと、いや、ずっと、は記憶がないから多分違うけど、きっと、いつか夢見たシェチュエーションなんじゃない!?
クールな筈の深堀花子さんだったが、サビ捜査官手を引かれて走った跡には、異世界らしくピンクの可愛い花が咲き乱れる。しかし、ちょっと待て…
「さぁぁびぃぃぃいいい!!」
物凄い地響きのような唸り声がサビ捜査官を呼んでいる。目の前には突然、巨大な黄や橙色の色の樹木が立ち並ぶ森が出現する。通常、CATの捜査官はこういった場所にはむやみに飛び込まないものだが、さらに地響きの唸り声が自分を名を呼ぶのを聞き、サビ捜査官はネコビトに戻って毛を逆立てて飛び込んだ。そして、青い下草の中を暫く走ってから、ようやくに止まって肩で荒い息をつく。
「さ、サビ…捜査官?ど、どうしたの、私たち、何から逃げてるの!?」
「ちゃ、ちゃるちゃんを…」
「ちゃるちゃんを?ね、あの声は何!?」
佐備を呼ぶ地獄の呼び声が、異世界の空気を震わせる。
「ちゃ、ちゃるママです…」
「え、あ、ああ…おかあさんね…え、バケモノなの?」
「も、元捜査官なんですが…ちゃるちゃんに関する時だけは…」
「さぁぁぁびぃぃいいい……」
「ひぅぃぃ…!!」
佐備捜査官と深堀花子さんは、叫びながら再び駆け出す。
018. ちゃるにゃんと竜
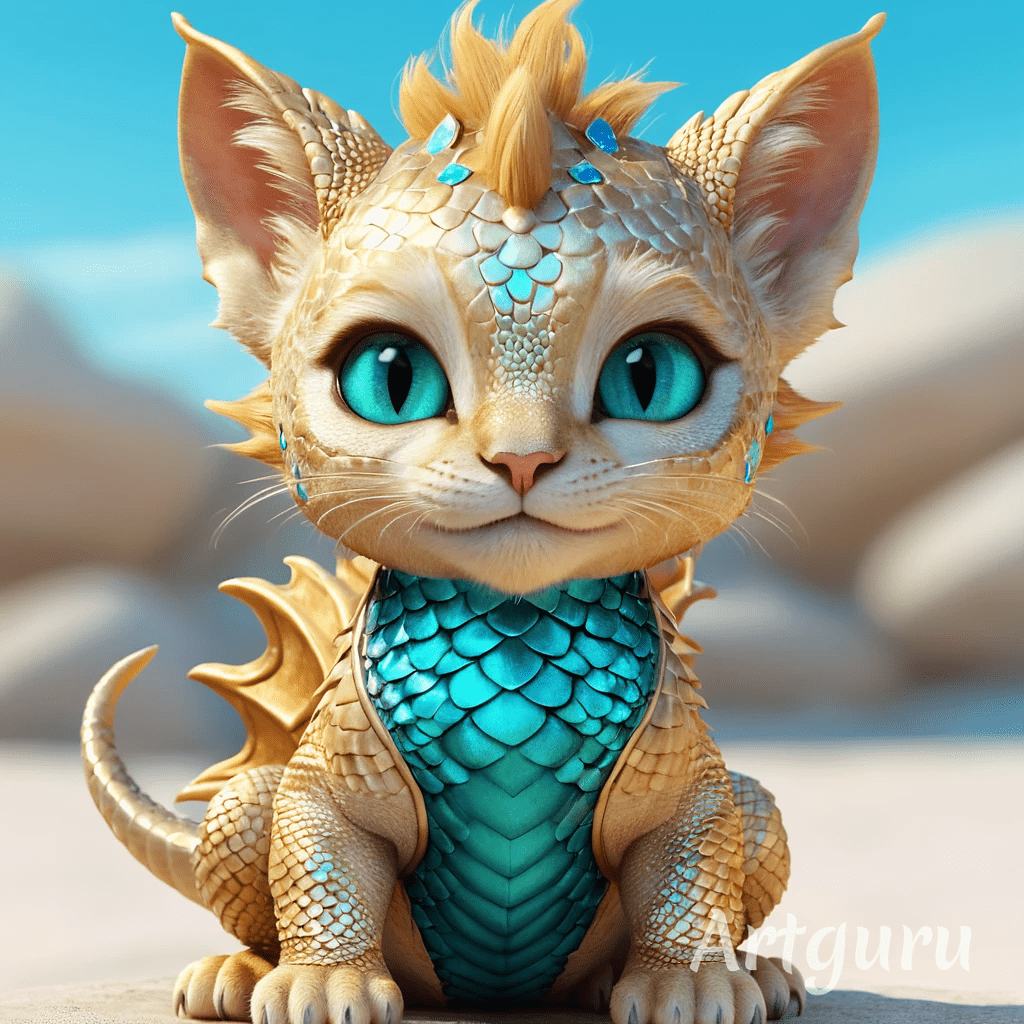
分地捜査官が「むじな」から境界亀裂へ飛び込んだのと同じころ、ちゃる捜査官はご機嫌で異世界を探検していた。先ほど見かけた大きなドラゴンは見失ってしまったが、自分の世界とは少し違ったこの世界も面白い。見たことのない大きさのトンボ、小さな人間を背に載せたオレンジ色の蛾、木々の肌は黄色く、派手で臭い花があちこちに咲いている。頭上にはスカイブルーから濃い藍色まで、様々な青の、様々な形の葉っぱが生い茂り、所々で透けるオレンジときれいな対照だ。つまり、このジャングルは、はでにゃのである、とちゃる捜査官は考える。あの蛾はあの濃い黄色の木にとまったら見つけにくいだろう。陰がオレンジっぽく見えるから。ちゃる捜査官はそれから、足元の奇妙にふかふかとした白っぽい地衣類をしげしげと見詰める。と、黄色と青の茂みの向こうで、小さな鳩笛を無理やりに吹くような音がすることに気がつく。ギュルル、とでも表現したくなるその音を追って茂みをかき分けると、金とターコイズブルーの、ネコ人の子供ような後ろ姿を見つける。ただし、その背中には金色の何かが背負われている。ちゃる捜査官は、少し緊張しながら声をかける。
「にゃにゃ?」
ちゃる捜査官は戸惑った。人間語で話しかけたつもりが、猫語しか出てこない。そして、ターコイズブルーの髪のネコビトはゆっくりと振り返る。大きな猫の目、微笑んでいるような猫の口に大きな牙が飛び出している。そして、頭に比べて目は大きく、体は小さく、肌は鱗に覆われている。ちゃる捜査官はそれを素早く見て取り、わずか7歳ながらも豊富な生き物の知識を活かして、この鱗は周囲に紛れるためには有効な色彩だと結論づける。
(周囲に擬態しているのだにゃ。と、いうことは食べられやすい立場なのかにゃ?)
ちゃる捜査官は相手を怖がらせないように笑顔を作るが、その金とターコイズブルーの猫は威嚇のシャぁっという声を立ててちゃる捜査官に飛び掛かる。
「にゃあっ!」
ちゃる捜査官はとっさに自己流の攻撃回避術、「くるんとしてぎゅう」を駆使して相手の攻撃を受け流してからくるりと後ろに回り込んでその生き物を抱きしめる。すると、人間やネコビトで言えば3,4歳くらいのサイズの金色の生き物は、今度はきれいな笛のような音を響かせて逆にちゃる捜査官の腕にぎゅうとしがみつく。ちゃる捜査官がその大きなくすんだブルーの目をのぞき込むと、今度はゴロゴロと猫と同じ音を出す。
(かわいいのにゃ。鱗がサラサラだにゃ。)
「にゃにゃ。」
ちゃる捜査官は笑顔で話しかけるが、相変わらず猫語しか出てこない。抱っこしたターコイズブルーの髪の生き物には背中に小さな羽があり、短い首から下はすべてが滑らかなイエローゴールドの鱗で覆われている。手に相当する部分は猫よりは、図鑑で見たティラノサウルスに似ている。きれいな草餅色の、とはいえ鋭い爪が生えている。
(ドラゴンの赤ちゃんかにゃあ?)
先ほど、体育館の舞台で見かけたのは、金色の大きなドラゴンだった。時々、ちゃる捜査官の世界に彷徨い出ては捕獲されて保護区やもとにいた世界へと縁さんが送っていくタイプとは少し様子が違った。なんというか、猫的なのだ。無論、ちゃる捜査官はわくわくしている。そうだ、写真を撮ってちゃるママとCATのみんなに見せてあげよう。思いついてちゃる捜査官は、新調してもらったCAT捜査官専用通信機を腰から下げた「ジャスト・イン・ケース・ポケット」から取り出す。そして、気が付く。自分の腕も、猫毛ではなく、金色の鱗で覆われている。好奇心に駆られて振り返ると、あまりお気に入りではなかったシャツの背中が破れて大きな傘のような金色の翼が生えている。手のひらの肉球はそのままだが、猫爪も大きくなって草餅色になっている。ちゃる捜査官はそれが楽しくて、とりあえずドラゴンの赤ちゃんと自撮りをする。そして、とりあえず「いつも心配性なママにゃん」に送ろうとする。が、何度「送信」タップしても、写真は送信されない。
「にゃにゃみーなー」
おかしいなを発音できないまま、しばらくターコイズブルーの髪色のネコドラゴンを抱っこしつつ通信機を操作してみるが、電波がないのだと結論づける。
(そういえば、電波塔がにゃいのだから当然にゃ)
それで少し不安になる。ちゃる捜査官は、自分のサバイバル技術は生まれ持っての強運も味方して自信があったのだが、問題は周囲の大人たちだ。
(ママがサビさんと署長にキレるにゃ…サビさんがブッコロされるにゃ…)
「こみゃみゃみゃー」
ちゃる捜査官がため息をつくと同時に、背中から生暖かい強風が吹く。生暖かいのに、ジャスミンの香りがする。驚いて小さなドラゴンを庇いながら振り返ると、巨大な猫のの目がワンセットと、巨大なネコドラゴンのヒゲと口がすぐ後ろにある。
(親ドラゴンにゃ!)
先程見かけた親ドラゴンだ。親ドラゴンは、巨大な暗緑色舌でべろりとちゃる捜査官を舐める。ちゃる捜査官は、ママに佐備捜査官がブッコロされるかもしれない心配は忘れて目を輝かせる。巨大な金色猫ドラゴンは少し面長で、若干馬っぽい顔をしている。
019. 美術室の不穏なきらきら星

パーティーがお開きになった美術室では、床に絵具の艶の残る楽器や女性のハイヒールなどが散乱している。机やいすは隅に追いやられ、中央には大きなグランドピアノが鎮座している。これを片付けるのも自分たちの仕事になるのだろうか。いやいや、「怪物」をさっさと退治して、あとは学校の真夜中の住人たちにやってもらおう。三ツ池が美術室の壁掛け時計を確認する。そういえば、「むじな」での待ち合わせは午前0時だった。今はそれを30分ほど過ぎている。その壁掛け時計の上を、可愛くない手のひらウミウシが割と素早く横切っていく。先程瓶に捉えた個体は紫と緑だったが、それこそウミウシの如くに、蠢きまわるそれぞれが異なる色彩をしている。そして、口のあるもの、嘴のあるもの、顔のないものとそれぞれのようだ。三ツ池と繰津は相変わらず、美術室で「怪物」に取り囲まれている。
「どうする?」
「火炎放射するにゃ」
若干ワクワクした声で繰津は答えるが、足元でフナムシのように集団で高速移動するヒトデ風の生物をそれで撃退できるとは三ツ池には思えない。それに加え、メデューサが退散してから暫く時間は経つが、このヒトデ達は右から左へ、壁から床へと移動するばかりで、一向に攻撃をしかけてこない。エンドレスにリピートする北の酒場モーツァルトアレンジが流れるなか、美術室の隅に寄せられた長い机や椅子の下にいた、比較的大きな個体まで姿を現す。だが、うねうね、ねちょねちょと素早くあちらへこちらへ移動するだけだ。
「…繰津さん、こいつら…」
「にゃんか、マスゲームしてるみたいに見えるニャ。ほれ、ヒレひっくり返して…」
「ヒレ…なんですかね…指じゃないですか?アタシには、盆踊りっぽく見えるけど。」
「うん、まあ、踊ってるにゃ。」
「指だね」
棚の上に置かれた埃をかぶった石膏像が言うと、ネコビト二人は一瞬無言でハイジャンプして壁を蹴る。その拍子に壁にかけられた複製画が落ち、まだ抜け出していなかった額縁住民から抗議の声が上がる。
「ああ、ごめん!」
三ツ池が急いでそれを拾い上げ、また身構える。その三ツ池の動きに驚いたのか、今や叫ぶ手のウミウシはあちらに積み重ねられた机や椅子の下へ退避し、そこで固まって波打っている。
「追い詰めたにゃ」
「ち、違うと思います」
「しかし、あそこじゃ着火できんにゃ…消火器も要る。」
「スプリンクラーがあるんじゃないですかね。」
繰津と三ツ池が小声で言い合うのが聞こえたのか、先程の石膏像が貴族然とした鼻にかけた声で言う。
「おいおい、物騒なことはやめておくれ」
「なんだ、着火だと?モリエール、着火と言ったのか?」
「そうなんだ、ネロ君。いくら君が放火魔だからって…」
「ネロじゃない!カラカラだって何度…」
カラカラ帝が不機嫌な声で応答するのに繰津が短く小さい笑いを発し、三ツ池は、小さな声で説明を求める。
「ネロってなんですか」
「ローマ帝国の暴君にゃ。ローマを放火したとかしにゃいとか噂があるにゃ」
薄暗い棚の上からはまだ会話が聞こえてくる。
「だいたい旧校舎の頃はアンタとは違う棚だったのに…」
「まぁまぁ、今時デッサンなんかしないんですから。断舎離されなかっただけありがたいと…」
「断舎離?皇帝を断舎離するとは…」
「まあ、落ち着いてくださいシーザーさん」
「違う!」
棚の上で石膏像が掛け合いを始めたあたりで繰津は笑いだす。それから、突然、「北の酒場」が、大音量の「カルミニャ・ブラーニャ」に切り替わる。
「なんだね、あれは?」
「知らん!」
棚の上では相変わらずの石膏像だが、繰津はもはやスプレー缶をかまえるのもやめて大きな肩掛けかばんを漁っている。三ツ池はそれを無視して右へ左へ移動する掌状の素早いウミウシ的な生き物に異変が起きたことに気が付く。ウミウシは仲間割れを始めたようでだ。くちばしで白とピンクの掌が隣の赤黒い手のひらをつつくと、赤黒い手のひらは真ん中の穴から黄色い触手を吐き出して応戦し、その向こうでは青と黄緑の掌が紫の掌を引きちぎって喰い始めている。
「にゃんだ?にゃにが起きた?」
「あー…わしの着信音のせいかもしれん。」
「にゃんでそんな大音量なんですか!」
「時々カバンの中で行方不明になるにゃ。」
「何が入っているんですか?」
「知るといろいろと失うものがあるぞよ…」
三ツ池がふと、自分が寝不足だったことや先ほど危うくモーツァルト君を引き裂きかけたことなどを思い出して手を止めたとき、抱えた額縁がかすかに振動していることに気づく。驚いてのぞき込むと、髪の長い女の子が、分厚い窓ガラスの向こうにいるような具合で境界を叩いている。三ツ池が驚いて彼女を見つめると、彼女は何事かを向こう側で叫んでいる。
「こ、これは…ブルードレスの女の子…!」
額縁の中から、髪の長い女の子が手を振って呼びかける。だが、まるで彼女は分厚い窓ガラスの向こうにいるようで、声は一向に通らない。
「火…けちゃダメ!…なの!」
「にゃ?聞こえないにゃ」
女の子は額縁を窓ガラスように叩く。
「あれ、出られないのかにゃ?」
三ツ池が言うの同じタイミングで、女の子は額縁から消える。
「にゃんだ、どうした三ツ池ちゃん?」
繰津が三ツ池が抱えた額縁を覗き込むと、女の子が書き殴ったメモを額縁のガラスに押し付ける。
「あの音楽止めて!!」
020.青い少女と赤い靴下

「え、何をとめて?」
「にゃんだ?」
額縁に話しかけながら後ずさる三ツ池に、繰津がちらりと視線をやる。そして、三ツ池が何をしているかはわからないものの、後退し始めていることに気づき、厚底ブーツを踏み鳴らして退路を確保する。相変わらずの大音響でカルミニャ・ブラーニャが流れているかと思ったら、突然にそれが止まる。
「ああ、まだ見つからないにゃいのに。」
「いったん出ましょう。」
「スミャホがみつからないと出られないにゃ」
「違います、部屋から出ましょう!」
後ろ手で繰津が美術室のドアを開け、三ツ池がそのドアを素早くすり抜ける。廊下へ退散した二人の前に、困り顔のモーツァルト君と、笑顔のメデューサちゃんがいる。メデューサちゃんは嬉しそうに繰津に駆け寄る。
「繰津さんの携帯番号、つながったー! 本物の番号くれたんだね、ありがとう!」
「あ、ああ、さっそくかけてくれたのにゃ…」
「でもさぁ、くるりん、アプリ使わないの?」
「そ、それはプライベートにゃ…」
メデューサが繰津を「くるりん」と呼び始めたあたりから、三ツ池は二人の押し問答を放っておいて額縁を壁に立てかける。
「モーツアルト君、教えてにゃ。このブルードレスの女の子、最初から絵から出てこられない仕様?」
「ブルードレス? ああ、イレーヌちゃん? いや、そんな…普段はよく出て来て、ワルツなんかを踊ってくれるよ?」
ガラスの向こうの青いドレスの少女は、掌に載せた何かと会話をしている風であったが、三ツ池とモーツアルト君がのぞき込んでいるのに気づいて手を振る。三ツ池がCAT手帳を開き、そこに「出られない?」と書いて彼女に見せると、彼女は隣にたたずんでいた大理石の天使像と何か言葉を交わしてから、頷く。
「しょうがニャイな…」
「あ!」
モーツァルト君が小さな声で驚きを表出する。
「どうしました?」
「そこ、イレーヌちゃん手のひら…」
「ああ、あ、あれ?」
「やっぱりそうだよね?」
「うん。そう思うにゃ。」
モーツァルト君と三ツ池は、顔を見合わせて頷く。
「にゃんだ、どーした?」
プライベートな連絡先を誰ともシェアしたくない繰津が、その間に割って入る。さらに、繰津の秘密主義を面倒くさい認定して、深追いしないことにしたメデューサが、3人の背後から蛇を割り込ませて様子を伺う。それから、3人の間に割り込みながら明るい声で言う。
「シンちゃん!そこでなにやってんの?」
青いドレスの女の子の手のひらでは、赤い靴下に半ばくるまれて、行方不明の心臓の「シンちゃん」が控えめに体育座りしている。
021.そんなに近くに立たないで

「こ、ここまで来れば...」
肩で荒い息をしながら佐備捜査官が呟く。深掘花子さんと佐備捜査官は、異世界の見慣れない色のジャングルの奥深くに逃げこんでいた。
「そりゃ、声はしないけど。」
深掘り花子さんは、黄色とオレンジの木肌の木の陰に腰を下ろしながら、ネコビト姿の佐備捜査官に視線をむける。
「分地さんてひと、そんなにこわいの?」
「元捜査官ですからね。」
「でも、沼田さんも佐備さんも現役捜査官だけど、怖くないじゃない。」
サビ捜査官がかつての同級生だったことを思い出した深掘花子さんは、敬語を自然に破棄している。しかし、サビ君とお喋りした記憶はあまりない。そして、サビ君が自分を覚えていてくれている自信も、あまりない。少し寂しい気持ちで、かわいい猫ビト姿のサビ捜査官を見つめる。ネコビト姿佐備捜査官は、宙をしばし見つめてから笑顔で返す。過去に一度だけ、ブチギレ分地さんを見たことのある佐備捜査官は、その異形の様相を花子さんに伝えない方が各方面で平和だろうと判断して、こういう。
「どうでしょうねぇ。分地さんはママさんですからねぇ。」
「ああ…ママは…まあ、コワイわね。」
深掘花子さんは深掘花子さんで、小学校で目撃した様々な怒れるママさん達をたちを思い出し、コワいという佐備の言葉には一理あるのだろうと推測する。そして、一般的にママネコビトは皆ああいう恐ろしい声を出すものなのだろうという間違った解釈で落ち着く。
「でも、分地さんも、心配しすぎなんです。」
「まあ、ママさんだからね。」
「しかし、ちゃる捜査官は立派な捜査官です。おそらく、CAT歴代の捜査官の中でも群を抜いて優秀な。」
「そうなの? あのかわいいおチビちゃんが? めっちゃ可愛いのに?」
深堀花子さんはちゃる捜査官の可愛らしさを思い出してニコニコし、それから、再度佐備捜査官に目を走らせて、こちらも可愛い、と思いながら聞く。
「ええ。貴女も見たでしょう?ちゃる捜査官は一瞬で亀裂を塞いでしまいました。ちゃるさんは底知れないですよ、他にも必殺ホダシオトシやピンポイント・リクエスト、枚挙にいとまがありません。自然に自分の身を守る、というか、なぜか勝手に守られている。何か強力な磁場がある。だから、分地さんがあんなに心配する必要はないんです。」
猫ビト姿に戻った佐備捜査官は、愚痴を言いながらも膝下までの丈の短いズボンからはみ出した猫足についた、レモンイエローのクッツキムシを摘まんでは外して投げている。そのクッツキムシが落ちた先で、茂みの真っ青な葉を何かが揺らし、二人は動きを止める。が、何が飛び出して来るでもなく数分が経ち、二人は警戒を解いてため息をつく。
「すみません、お手数なんですが、」
サビ捜査官が急接近する。
「他にヒッツキムシが付いているところはないか、お手数なんですが見ていただけないでしょうか?」
そうして両腕を広げてを見せるので、花子さんは真っ赤になって震えて咳をする。
「ちょ、ちょっと!そそそんなに近くにたたないで…」
「ああ、すみません」
サビ捜査官は微笑んで一歩離れる。立ち居振舞いは立派な大人の紳士だ。ずるい。佐備捜査官は猫ビト姿だと、とても幼くてかわいい。せいぜい小学生でも真ん中くらいの学年といったところだ。小さなちゃる捜査官のお兄ちゃんと言ってもなっとくするくらいの大きさだ。いくら高校生の頃に佐備君が好きだったとはいえ、猫人だったことは知らなかった。これじゃないの。この姿に恋したとあれば、私は変態だわ。
「い、いっこ、ここ。首のうしろ、ヒッツキムシ。」
花子さんがレモンイエローのヒッツキムシをためらいがちに引き剥がすと、佐備捜査官は振り返ってにっこり笑う。それで、花子さんの枝にまた花が増える。
「ありがとうございます。しかし、すごいですね。花子さんにはお花を咲かせる能力があるのですね。」
「あ、い、いや、えーと」
「私は生徒さんの能力を花開かせるところから来ているとばかり…」
「あああ、え、えと、違うの、違うのよこここっちの世界に来てからだし」
「そうですか、でも、素敵ですね」
それに追加された微笑みで、また枝に鼻が増え、今度は周囲の地面からも小さなピンク色の花をつけた、これは緑葉の小さな植物も芽吹く。そのピンク色の花々から、優しい香りが漂う。すると、先程、二人を沈黙させた青い茂みが、再びガサガサと音を立てる。
「な、なに…?」
再び二人は動きを止める。すると、その青い繁みと薄紫の下草の間から、何かが顔を覗かせる。クルクル、ゴロゴロと喉を鳴らし、ゆっくりとそれは姿を現す。大きな猫の目、金色の鱗、真っ青な巻き毛のたてがみ。背中に小さなコウモリの翼。それが先程、花子さんパワーで地面からも芽を吹いた小さなピンク色の花をパクリ食べる。そして、二人にむかって可愛らしい猫の声で「にゃっ」と鳴く。
「かかか、かわいい…!!」
花子さんは、佐備捜査官以外にクラクラさせてくれる可愛らしさ助けを求めるように、その金色の小さい猫ドラゴン手をのべる。佐備は警戒したように上着のポケットに潜ませたテーザー銃に手を伸ばすが、猫ドラゴンはゴロゴロと喉を鳴らしながら花子さん近づく。そして膝に飛び乗ろうとする。しかし花子さんは幽体なので、猫ドラゴンはスカッと足がかりを失ってコケる形になる。そして、花子さんの膝と二重写しような絵の中で、コケた先に咲いている花をまたパクリと食べる。花子さんがその場からそっと立ち上がると、寂しそうに彼女を見上げて、サイレント・ミャウを繰り出す。
「ああ、かわいい…ごめんね、私、触れないの。」
言いながらも、屈んで意識を集中させ、幽体の掌で辛うじてその青いたてがみを撫でる。たてがみは風になでられるような具合に波打つが、花子さんにできるのはその程度だ。幽霊が物質に触るのはそのくらいむずかしい。
「猫ドラゴン…きっと、こちらの世界の方なのですね。」
花子さんが抱き上げられないので、佐備捜査官が子猫ドラゴンを抱き上げる。
「ちゃる捜査官が、ドラゴンを見たと言っていましたね。この方でしょうか…」
「ちょっと小さくない?」
「そうですね、遠くから見つけるにちょっと、小さいですね。」
「そういえば…ねぇ、ここ、どこかわかる?」
「実はですね、わかりません。」
「え、なんでよ!?」
「すみません、CAT通信機の電波が届いていないようでして…」
「はぁぁ!?…あ」
深掘花子さんは若干キレ気味に怒鳴った自分に驚く。見れば、大きな目の仔猫ドラゴン抱いた大きな目幼いネコビトの男の子が、半ば口を開けて自分を見つめている。
「ああああ! ご、ごめんなさい!」
「花子さん…」
「ごめんなさい、私、時々…」
「昔、髪型違いました?」
「え?」
「歌も、もっと激しいの歌ってませんでした?」
「え、あ、ええ…?」
深掘花子さんには、実はあまり生前の自分の記憶がない。ないと思いたい…
022.「むじな」の亀裂前
ちゃるママこと分地元捜査官が亀裂に飛び込んだ後、遮無捜査官はとりあえず隙間を5センチほど残して壁に描かれた扉を閉める。そして、亀裂から引っ張り上げた小川先生を近くの椅子に誘導して座らせる。それから、一度、先程隙間を残して閉めた扉のもとに戻ってそこから中を覗き、そして、今度はため息をついて完全に閉める。ため息にかすかにシャーという音が混ざる。
「さて…」
遮無捜査官は、焦りすぎて顔が消えたスーシェさんに向き直る。通りすがりに床に落ちたスーシェの口髭を拾いながら、遮無は瞳孔の細くなった目を、スーシェのつるりとした卵のような顔に向ける。
「私のサングラス、落としちゃいましたよ…」
遮無捜査官はネコビトモードなので、高めに結わえた髪が首筋まで届くあたりまで、品の良いベージュの毛が逆立っている。遮無捜査官は、沈着冷静に、お怒りだ。
「たしかに、深堀地区は妖怪特区です。しかし、これは申請外の人工亀裂ですね…」
「は、はぁ…」
「そして、彼女は…クイーン・ティタニア10世ですね。」
「ち、ちがいま…」
「…では、あの絵は彼女が描いたのではないと?ハダカデバネズミ王国の女王には描かれた世界とこの世界を繋ぐ能力があると伺っていますが。」
遮無が鋭い猫爪が出た指で壁に描かれた扉を示すと、扉に描かれたドアノッカーは小さな悲鳴を上げる。追い詰められたスーシェは、茹でたての卵のような顔に汗をかいて、ますます茹でたての卵っぽくなる。そのスーシェの様子を見たティタニアは、震える声で訴える
「…ま、まだ…わらわは、即位するとは…しないとも…」
それでバッハ先生は俯いてしまう。その華やかだった巻き毛はすっかり伸び切り、毛先はどういうわけか、びっしょりと赤く濡れている。遮無は、それを見てティタニアを責めることはしないことしたようだ。かわりに、相変わらず冷静にスーシェに向かう。
「それにスーシェさん。」
「は、はい。」
「我々CATをなめて頂いては困ります。ハダカデバネズミ王国の次期女王が深堀小学校で先生をなさっているという事は我々も掴んでおりました。まあ、とは言え、どなたがか、まではまだ掴んではいませんでしたが…しかし、問題は、そこではないでしょう?」
「…ウィ。しかし、我々は…」
「ええ。ここで彼女のガードを解いて、彼女が女王を継がない理由を聞き出そうとなさっていたんですね。」
「ウイ」
「それは理解いたしますし、感謝もいたします。しかし、ここ深堀地区は元々が小さな境界亀裂の多発地域です。不安定な状態で絶妙なバランスの上で安定しているのです。ダメでしょう、新しい亀裂作らせちゃ。しかも、実用目的でなんて。そのくらい、妖怪である貴方がたが一番よくわかっているでしょう。それとも、たくさんあるから一つくらい増えても構わないと?」
遮無捜査官の声低く抑えられ、そのお叱りは氷のように冷たい。スーシェはおびえて若干足元も薄くなる。
「は、はぁ」
「白坊主化して逃げないでくださいね。」
それから、遮無は亀裂の瘴気に当てられて髪からカールが落ち、真っ青な顔色の小川先生の方をちらりと見る。どういうわけか毛先が真っ赤に染まった彼女は、ただ黙って涙を流している。遮無は流石に彼女には同情し、ほぼ表面化していなかった怒りをおさめる。
「さ、スーシェさん、『小川先生』、切符切らせていただきます。ちゃんと罰金払ってくださいね。」
そして遮無は、溜息をついて洒落た薄いバッグから切符帳を取り出し、素早く必要事項を書き込んで切り取る
「はい。入金期限は2週間。短いから、気を付けて。」
「え、そ、ソレだけ?」
「まあ、四ツ谷と違って今回は誰も死んでないし」
「あ、いや、四ツ谷でも死んでないですよ。」
「でも、噂になって落語にもされちゃったじゃないですか。」
「あ、あれは…」
「とにかく、亀裂生成禁止違反切符。今回は小さいから2人で1枚。割り勘してくださいね。」
「は、はい。」
「あと、私のサングラス代は別途請求しますから」
そう言うと、お怒り遮無さんは壁の扉に、派手な黄色の「立入禁止」テープを貼る。遮無が手持ちのシール5枚を全部貼り終わった頃、CATの高性能スマホが鳴る。遮無はそれを、ヒヨコ鳴き声に設定している。遮無はそれ確認しながら、先程座っていた席に着く。
「さあ。仕切り直して、さっき注文したの、持ってきてください。」
遮無はお茶をしてから、沼田署長が発した緊急動員に応じるつもりのようだ。
023.繰津捜査官の逡巡と三ツ池の絶望
三ツ池、繰津、モーツァルト君、メデューサちゃんは、美術室前の廊下に集まって額縁を囲んでいる。額縁の中には、明るい背景に青い服の女の子、その手の上に心臓君、後ろに寒そうにしている大理石の天使がいる。繰津はその額縁の、本来であればキャンバスに絵の具が乗っている部分を、猫爪でコツコツと叩く。
「普段は、みんな額縁から出てくるんだ。」
モーツァルト君が神妙な面持ちで言う。
「そーそー、ここに壁がなくなるの、空気みたいになるんだ。」
「これ、昔からそうなのかにゃ?」
「いや…これ、みんな、小川先生が少し手を入れてるんだ。古い複製画の汚れを落としたり、色を足したり、ニスを塗ったり。あと、スマホを見ながら、一から描くこともあるよ。」
「小川? 音楽室のマタイ受難曲の人?」
「ううん、作曲家のバッハさんじゃないんだ。作曲家としての彼の絵はあるけど、この学校では寝てて、起きてこないよ。」
「え?」
「小川先生は、バッハさんみたいに髪のカールした、女性の美術の先生だよ。ちょっと天然だけど、たぶん天才。」
「天然…にゃるほど、おとぼけなのか?」
「え、天然パーマじゃないの?」
「それもあるかも。でも、おっとりさんだよ。」
「ふくざつだにゃ…じゃあ、さっき音楽室で怒鳴ってたのは?」
「ああ、あれはベートーヴェン君。彼は時々勝手に悩んでる。あと、音楽の教科担当の趣味でジョン・レノン君とかも飾ってあるけど、彼はたまにしか起きてこない。ポール君はまだご存命。」
「いや、あれは実は偽のポールで実物は死んでいるにゃ…」
繰津が声をひそめ、モーツアルト君とメデューサちゃんが楽しそうに耳を寄せるが、三ツ池は眉をひそめて額縁の検分に戻る。廊下に数枚、名画が飾ってあるが、中はもぬけの殻だ。三ツ池はそれに腕を突っ込み、中の事物に手は届かないものの、メデューサちゃんが言っていた通り、境界が「空気みたい」になっているのを確認する。その額縁を通り抜ける瞬間、ネコビトの腕の毛が逆立つ。何度か出し入れして、その額縁の延長線上を通る場所で、磁気で砂鉄が柱になるような具合で、そこだけが引っ張られたように毛が立つ。
「繰津さん、これ、境界亀裂というにはあまりにスムーズと言うか…境界を消したみたいな…」
「そしてにゃ、こっち、境界亀裂だか消去だか、なんにせよ、それが閉じた跡っぽいにゃ…」
三ツ池が他の額縁を調べている間に、モーツアルト君とメデューサちゃんをすっかりポール死亡論者にした繰津は、満足げに閉じたブルードレスの女の子のいる額縁をしらべるのに戻っている。
「閉じた亀裂…窓みたいに開けらんないもんですかね…」
三ツ池が呟くと、繰津がニヤリと笑って宣言する。
「できる!」
「え? じゃあ、開けましょうよ。」
「うーん、でも、これやると分地ちゃんがブチ切れそうな気がするんだにゃ…」
「人命名救助です。気にしないでください」
寝不足モードに戻りつつある三ツ池は、若干語気を強めて言う。繰津は、それに若干気圧されて、額縁の中をのぞき込む。これは人命救助なのか…? 繰津捜査官は額縁の中の心臓君と女の子を見て暫し考える。
「早くしてください。むじなでの集合時間、すぎてますよ」
どこか殺気だった三ツ池の声と、期待に満ちたメデューサ、分厚いガラスの向こう側で困った表情の少女と、心臓君。繰津は腹を決めて、先程のカバンを漁り始め、今度は割とすんなりと小さい袋を取り出す。そして、その小さい袋から、割と大きな折りたたみナイフを引っ張り出す。
「いいか、分地ちゃんに言うにゃよ…」
繰津はしばし、ぶつぶつと小声で呪文めいたものを唱える。そして、急に「ええい、ままよ!」と叫び、ぐっさりとそのナイフを額縁壁に突き立てる。ナイフは、額縁の壁にゼリーのように突き刺さる。
「うぬ、分厚いにゃ…」
繰津はそのナイフをぐっと手前に引き、一度右ずらしてから抜く。そしてもう一度突き立て、さらにこちらへ引く。切り取られた壁が、ゼリーか寒天のように、ズルリと床に落ちて跳ねる。それを飛び退ってよけたメデューサちゃんが驚きの声を上げる。
「わお。なにこれ、分厚い!」
「境界の壁にゃ。ここはすぐに閉じるにゃ、さ、早く!」
繰津は叫ぶと、再び呪文めいたものを、今度は声高に唱え始める。三ツ池は寒天の開いた隙間から、青い服の少女が差し出した心臓のシンちゃんを受け取る。その間にも寒天の壁の隙間は狭まり、シンちゃんが巻き込まれそうになる。三ツ池が思い切り腕を引きぬくと、ズルリ、とシンちゃんは引っ張り出され、透明な粘液塗れのまま、メデューサちゃんの手のひらへ引き渡される。
「おかえりー」
メデューサちゃんは優しくシンちゃんを受け止め、モーツァルト君が差し出した絹のハンカチで彼を拭く。
三ツ池は、続いて青いドレス女の子を引っ張り出そうと腕を突っ込む。だが、境界寒天の壁はますます狭まり、三ツ池は顔まで半ば隙間に突っ込んで女の子に手を伸ばす。もう少しで手が届く、その時だった。ズルリ、と三ツ池が、腕から胴、足までもがその寒天に引きずり込まれる。シンちゃんに気を取られていた繰津、メデューサ、モーツァルトは、それに気が付くのが一瞬遅れる。三ツ池が苦しそうに寒天の中でもがく。寒天ガラスの向こう側では、少女と天使が悲鳴を上げて、慌てて三ツ池をその分厚い層から引っ張り出す。ズルリ、と、先程、あちら側でシンちゃんが引き摺り出された具合で今度は三ツ池が壁のこちら側で引き摺り出される。ベチャッっと音を立てて、三ツ池は真夜中の美術館の床に落ちた。
「ああっ…閉じちゃった…」
少女が残念そうに呟き、三ツ池は青ざめて振り返る。まるで、水族館の魚のように、分厚いガラスの向こうから、心配そうなメデューサ、モーツァルト、それに髪を掻きむしって叫んでいるらしい繰津が見える。
「うう、芋と小豆となんかの三角関係が…」
三ツ池は、今夜ずっと楽しみにしてきた「むじな」のスイーツに、ついにたどり着けないかもしれない、と、絶望する。
024.美しきハダカデバネズミ王国の姫
ティタニア姫の髪は境界の瘴気の茶色い水滴が染み付いてカールはすっかり延びた上に、毛先はべっとりと赤い何かで濡れている。彼女は青ざめたまま空を見つめ、涙を流す。その大きな瞳は長い睫毛に取り囲まれ、潤んだ瞳は室内優しい灯り、うつろながらも美しくと光っている。
「…大丈夫ですか。」
「…見ては…ならぬものを見た…」
「…何を、ご覧になったのですか…」
「わらわが…王国を継がなかった時に来たる陰惨な深淵じゃ…わらわは、わらわは初めて、理解した…」
スーシェがようやくに、人好きのする小洒落た顔を取り戻し、彼女のぐっしょりと茶色く濡れた肩に、高級そうなニットの膝掛けを惜しむこともなく掛けてやる。
「そうですか…貴女も、マウス・オブ・マッドネスを覗かれたのですね…」
ティタニア姫は震える唇を一文字に結び、テーブルの上に置かれた遮無の手を握って尋ねるようにその目を見詰める。遮無は、それを謎めいた微笑みで包み、それから、優しく言う。
「境界は時により場所により、違う場所へ繋がります。私が見たものと、貴女が見たものはきっと違う。今回が、たまたま、恐ろしいものだったのでしょう。」
「そうか…いや、そうじゃの。」
ティタニア姫は遮無捜査官の手をまだ握りしめたまま、視線を運ばれてきたカフェ・オ・レ、ミルクティーのミミジャ沿え、そして二人分の「サツマイモと小豆と秋刀魚の三角関係」に、落とす。
「わらわは今まで、気軽に…本当に気軽にいくつもの境界亀裂を作り、塞ぎ、あるいは繋ぎ変えてきた。かような、恐ろしい場所へ繋がることもあるという、繰り返し語られてきた忠告に耳を傾けず…」
それから、ゆっくりと遮無の手を離し、わずかに震えが残る手で豪華なティーカップ引き寄せ、スティック状のミミジャでそれをかき混ぜてからソーサーの上にそっと置く。白地に大輪のバラの花が描かれた華やかなそのカップとソーサーは、ティタニア姫によく似合っている。
「わらわは、即位する決心ができた。もはや、稚技に等しき無用の境界遊びは、せぬ…」
「そうですか…さ、お茶が冷めちゃいますよ。」
遮無は、静かに言うと、微笑みながら自ら自分のカフェ・オ・レに口をつける。遮無のカップは、深い青に白のラインが印象的な、モダンなカップだ。遮無はスーシェ見立ての良さに感嘆する。
「スーシェさんお店は素晴らしいですね。お忍びの姫が足繁く通われるのも納得だ。しかし、そもそも、何故、王国を捨ててこの国の深堀り地区へ?」
遮無が軽い口調で聞くと、だが、ティタニアはとたんに言い淀む。
「う、うむ。それはじゃな、ええ、あの…パンダルマンががの、その、好きでな…で、絵本の作者がな、友人の…ええと…」
スーシェが、そこに足りない情報を補いように、ゆっくりと、語りだす。
「我々がティタニア殿下を探し始めた時、その、我々もハダカデバネズミ王国の重要性を認識していなかったのです。彼らは、霊魂としてこの世界にようやくたどり着き、元の世界での身体組成に一番近い…老いない、病まない、母系の社会を築く生物に同化しました。美と善に満ちた世界が滅ぼされ、代わりに彼らが得たのは、地下に住まう小さき毛なきものたちたちの世界…しかし、そのハダカデバネズミの姿は、王国の人々が元の世界での姿とはあまり違っていたのです。そこで彼女らは…そもそも、外部の血を入れるのは女王がその伴侶を娶るときだけですので…世界で一番、彼女らの元の世界の姿に違い男性を…つまり、こちらの人間の言葉で言えば、「美しい」男性を代々、夫としてきたのです。」
「ああ、それで姫は、こんなに…ええと、お美しいのですね。なるほど。正直、我々もごく最近まで…ハダカデバネズミ王国の方がこんなに…名称と異なるお姿だとは知りませんでした。だから、我々もここまで特定に時間がかかった。エージェント・ランドンの情報がなかったら、吉田くんを締め上げる事も辞さないつもりでしたが…」
「ええ。ですから、ハダカデバネズミ王国の当主は、美しいのです。ええ。なのですが…ですが…、姫が恋してしまったのが…あの…まあ、道ならぬ恋なのです。」
「道ならぬ?相手も女性とか?」
「いえ、それならかえって都合がいいのです。お子を成すのに、材料だけちょこっと、適当に美しい男性を捕まえてお金と地位を与えるだけでいいのですね…」
「ああ、そうか。では、相手が既婚者?」
「それはそれで問題ですね。しかし、今回ケースではないのです。」
「では、どういう…?」
突然、激しい鈴の音が鳴り響く。そして、「やあ!ごめんね!」と明るい男性の声が響き、それから、シルエットだけは二枚目俳優のようなヘイスタック氏がカフェに転がり込む。
「ごめんごめん!まさか、鉢合わせるなんて思ってなくって!亀裂、すごかったね、君たち、落ちなかったかい?無事?よかった!ごめんね、ティタニアさん!」
突然に嵐のようにやってきたヘイスタック氏は、明るい声でティタニアに謝りながらその隣の椅子に腰を掛ける。ティタニアは弾かれたように席を立つ。
「貴様は…!」
「ああ、こんにちは、初めまして、でしたっけ?いっつも監視してたから初めての気がしないなぁ。」
あっけらかんとトレンチコートを着たサイクロプスが言うと、ティタニア姫はさらに気血を挙げる。
「貴様か、最近何やらとおるわと思っておったら…我が居城で何を…!」
「やだなぁ、スーシェさんまだ話してないの?あ、アナタ…CATの人だね?」
ヘイスタック氏が笑顔で差し出した手を、遮無は人差し指と親指でつまんで握手とし、これ以上場を緊迫させないように沈黙を6秒置く。そして、身構えたティタニア姫にミルクティーを手のひらで示して座らせ、そばに立っていたスーシェに視線を送る。その視線は、彼にとってはあらゆる脅し文句を含んでいる。
「で、その、道ならぬ恋のお相手とは…?」
再度、遮無のCATの特殊通信機鳶の声で鳴く。遮無は、それをチラと覗き込んで、溜息をつく。
「うーむ、署長、招集を掛けたのに…青木と雨所しか現場にいないな…分地の居場所が消えましたね。困ったな、手が足りない。」
「猫の手も借りたい?吉田くんは?」
イケメンサイクロプスが明るく言うと、あちらでガチャンと音がする。
「吉田くん!スパ⋯じゃなかった、ここでお茶しようよ!」
ヘイスタックが明るい声で呼ぶと、あちらの柱の陰からゆっくりと吉田が顔を出す。その耳は完全に倒れ、背の毛は逆だっている。
「いや、えっと…CATさんとか、コワイんで…」
「大丈夫だよ、君、遮無さんのファンじゃないか!」
「ああ、いそがしいのに。」
遮無は、呟くと手錠を3つつなぎ、スーシェ、ティタニア、ヘイスタック、吉田くんをひとまとめにする。
「死にたくなかったら、ここで待っててください。」
遮無は4人写真を撮るとグループニャットに送信する。
025.境界狭間の渡り廊下
「にゃあああ、境界亀裂に落ちてしまった…」
三ツ池は、以前に見掛けたブチギレ分地さんを思い出す。目玉が大小5つくらいあって、顔から肩まで裂けた境界からカニの手みたいなのが出ていた。カニの手は、3本くらい生えていた。それを自由自在に動かして、目に見えない何かと戦っていた…私もあれになるのか…?
「いやだぁぁぁっ!」
三ツ池は寒天まみれの三色の髪色の頭を抱えて叫ぶ。
「私だってイヤよ、出られないのは。」
冷静な女の子の声に驚いて顔を上げる。ブルードレスの女の子と、真っ白い天使の像が覗き込んでいる。三ツ池はパニックが収まるまで、ふたりの顔をみている。ふたりは三ツ池が落ち着くまで、関係ない話を始める。
「わたしの赤い靴下、行ってしまいました…」
「バイオリンに続いて、ついてないわねぇ…可哀そうに。また外に出られるようになったら、コタツ靴下持ってきてあげるからね。靴下なら大丈夫、絶対手に入れられるから。」
「ありがとう、イレーヌさん。でもコタツ靴下ってどこで手に入れるんですか?」
「モーツァルトさんのスマホで、通販で買うの。」
「そうなんですね...しかし、支払いは?」
「いろんな先生のクレジットカード番号を適当に使うのよ。」
「ダメじゃないですか?」
「まあ、私、絵だから。バレないわよ。」
「そ、ソレはダメにゃ!はんざ…って、にゃんだ、ここは?」
職業意識が戻ったところで、三ツ池は肩から生えたカニのハサミの事は忘れ、周囲を見渡す。時々見かける境界亀裂のように真っ暗でも、真空でもない。いたって平和な、いうなれば、美術館か、大邸宅の渡り廊下のようだ。
「ここは、こういう世界よ。ずーっと、続いてる、細長いところ。間の通路かな。」
そういうと、イレーヌちゃんは右、左と指で示す。イレーヌちゃんの後ろにはすこし離れて壁があり、それが、右にも左にも、見渡す限り延々と続いている。暗いわけでもなく、かといって明るすぎるわけでもない。壁の色は所々異なり、見渡す限りの壁には、そこここに額縁が下がっている。その間に暖炉や彫刻、飾り棚に家具、ヒトをダメにするソファまでもが配してある。いたって心地よい空間だ。三ツ池は、自分が通り抜けてきた寒天のような境界を振り返る。寒天は今やゼリーのように透き通り、あちら側で繰津が何かを叫んでいるのが見える。
「ここ、ふだん、お嬢ちゃんがすんでいるところなの?」
「いいえ。私のお家はあっち。」
イレーヌちゃんは、どこかのお金持ちの居間のような室内が描かれた、壁に掛けられた絵を示す。
「あっちには、出たり入ったりできるんだけど。天使ちゃんは、自分のところには戻れないみたい。」
「ふーむ。絵によって差があるのかにゃ?」
「あ、いえ、天使ちゃんは彫刻なの。絵じゃないのよ。」
「うーん、じゃ、ここは絵の中の世界と学校のあいだってわけじゃにゃいのか…」
「たぶんね。この空間は、わりと昔からあるのよ。」
「え?昔から?」
「ええ。私、自分の絵が飾ってあるところならどこでもいけるの。ううん、どこでもじゃないみたいだけど、行けたの。今はいけないけど…前は、他の絵の友達と遊んだりできたし、貸し出された先の美術館の中も散歩できたのよ。なのに、最近は…あの学校にしか、行けないのよね。でも、それもふさがっちゃった。」
三ツ池は背中がぞわりと寒くなるような気がした。この空間に、閉じ込められる!それだけは避けたい、ここにはネコビト向けの甘味処もドライブに最適な田舎道も温泉もない!
「てことは、ここが最後の出入り口だったてこと?」
「うーん、最近は、学校が楽しかったから、チェックしてなかったの。でも、他に出口は見つけられてない。全部はチェックしてないわ、だってここ、ものすごく広いのよ。」
「うぬぅ…そうだ、天使ちゃん!天使ちゃんの…天使ちゃんはどこから来たのにゃ?」
「ああ、わたしですか? 大きな博物館です。ちょっと探し物をしていて、迷子になりまして…帰り道がわかりません。」
「迷子? じゃあ、閉じ込められたわけではないのかにゃ?」
「ここは広いから。」
「ふむぅ…ヒントにならずにゃ…」
三ツ池は腕を組んで考え込む。ふと見ると、額縁の向こうでは、半本猫姿の繰津が牙を剥いて斧を振り上げている。
「…にゃんかコワイから、別の出口、さがそっか。」
二つの世界を隔てる間の寒天に繰津の斧が跳ね飛ばされるのをみて、三ツ池は作り笑いで少女と天使に提案する。二人は分厚い寒天の向こうに見える繰津の、必死さゆえにだいぶ本猫に近くなってしまった姿が可愛く見え、吹き出してはいけないと必死だったので、それに笑顔で同意する。三ツ池は、CAT手帳に「出口、他にないか探します」と書いて寒天に貼り付ける。繰津は本猫顔で、同じように手帳に「13号室へ行け」と書いてみせる。
「…13号室? ニャンだそれ?」
三ツ池はそう書いて見せようかとも思ったが、繰津が、すかさず呪文と地図らしきものを書き殴ったメモを続けて寒天に貼るので、それをCATスマホで写真に撮る。
「コレ何?」
「地図と呪文のようですが…私は天使なので、禍々しいものはちょっと…」
「まあ、いいにゃ。行ってみようか。」
三ツ池は一応、壁に掛かった絵に13号室っぽいものはないか、絵を覗きながら歩き出す。その廊下は長く、品が良く、時が止まったように静かだ。
026.ウインクと掌底
不破望子は困っていた。行方不明探しはフワモコ王国ではなくCATに依頼すべきだと思うけれど、まずは、と何故か不破のオフィスに持ち込まれた依頼が2件。その内の1件は新しいエリア「ワビサビの郷」のメインデザイナーの行方捜しだ。しかし、頼みの綱の沼田にも、どういわけかその部下たちにも、連絡がつかない。望子は、黒服スーツの一団に警護された義母トラと、クッションカバーを被った肉体美の若者が、楽しそうに談笑しているのを、スワン型の受話器を握りながら眺めている。この電話機はエナメルでコーティングされた白鳥の置物の中に機械部分が収められた年代物で、首を外して受話器として使う優美なものだ。その優美な置物の隣で机の上をダストバニーズが跳ね回り、あちらには彫像のように並ぶマッチョ達。彼らは室内の物を壊さないように、じっとしていて動かない。そして、とりあえず通常の業務に戻った住野と、住野に箒を渡されてダストバニーズを集めて回る蔵市。優雅なフワモコ王国CEOのオフィスは、今やカオスだ。
しかし、望子は困りながらも、頭のどこかで新しい企画、「ムクツケーキーズのプロテインスイーツビレッジ」のアイディアが次々と浮かんでくるので若干わくわくしている。ダメよ、フワモコ王国にマッチョなんて…可愛くない。いいえ、あの、ビリーと呼ばれた色の黒いスキンヘッドの彼はかわいいかもしれない。左右の胸の筋肉を別々に動かして、ダストバニーズをはねさせてあげている。ダストバニーズはハニー・バニーの設定ではあくまでもサブキャラだが、あの男性と組み合わせて売り出したらいけるのでは。その隣の、クッションカバーを被った金髪の男性は、神話の神のように美しいのに、話すとちょっと残念なくらい軽くて人懐こくて、キャラクター化しやすい。どうやら蔵市さんも彼が気に入っているようだし⋯他に、ビリーの上司のような黒髪の巻き毛の男性、あれは無口キャラで美神と組み合わせたらいいかも。ああ、彼らならムクツケーキーズ戦記、実写映画でいけるのでは? 演技はできるかしら…モコは、脳内で調子よく企画のアイディアを練るときにいつもするように、壁に掛けられたテンテイルズの肖像を眺める。脳内で、肖像のテンテイルズに話しかける。
「どうかしら…館内でカワイイに馴染めないけど、ご家族に付き合ってついてきている子を見たの。マッチョな方に話しかけてた…そういう世界も、提供できたら、素敵かしら…?」
「ふむ、君はいつもクリエイティブだ。しかし、ハニー・バニーやマカロン・キトゥンズが築き上げたブランドイメージがゆらいでしまわないかい?」
「そうね、そうだわね…ワビサビの郷をオープンしたばかりだし…温泉施設の追加の話だってあるし…」
「そうなのかい?」
「ええ。猫町なら昭和初期の…あ、あら?」
脳内の会話は、そこまではあくまでも不破望子と、不破望子の想像するテンテイルズの会話だった。ところが、今、彼は、ウインクをした。シュローディンガー・ビアンカが描いた、白黒の、渋いテンテイルズが、ウインクをしたのだ。そして、一歩横へずれた。そして、絵の中に、フードを被った何者かが現れた。背の高いテンテイルズよりもだいぶ小さく、ルーズなシルエットのフードとパンツの向こうにうかがい知れる体格は華奢だ。それが、こちらへ向かって歩き、額縁に足をかけ、飛び降りる。
「すみません、どうも…不破さん、緊急で沼田さんに連絡とりたいんですが…」
フードを後ろへ降ろし、彼女はそう言う。絵を描いた、ビアンカ本人だ。不破望子は驚いて立ち尽くし、周囲のエクスペリメンタル・ラッツからは歓声が上がる。歓声とともに、何かが壊れる音がして、小さな謝罪の声も聞こえるが、ビアンカは笑顔で手を振ると、不破望子へ歩み寄って真剣な眼差しで言う。
「セドリックが…行方不明です。まずいです。ワビサビのキャラ原画、まだ揃ってないですよね?」
「え、あ、ああ…」
「大丈夫ですか?」
ビアンカは、当惑する不破望子の顔に素早く手を伸ばし、その鼻の下を撫でる。そして、その指先に付いた鼻血を見せる。不破望子は、先程のウインクの破壊力と、蔵市が、何故、ヨリック氏にクッションカバーを被せたままにしているのかを悟る。そして、そのクッションカバーが目の前に現れて、ビアンカをかっさらって抱きしめる。
「ビアンカ!!」
「やめろ…っ!! あれ? お兄ちゃん!? ごめん!!」
ビアンカが自分を抱き上げたのが兄だと気付いた時には時すでに遅しで、クッションカバーは掌底を食らった兄の鼻血でみるみる染まっていく。
「あははは、ひどいなぁ、でも無事でうれしいよ!!」
気付けば黒髪巻き毛の大男が、そのカバーを丁寧に外して、目にも留まらぬ早業でヨリックの鼻に脱脂綿を詰めている。その脱脂綿は、蔵市が差し出している。
「えっと…お兄ちゃん! セドリックを探して!!」
「もちろん! でも、僕ら、ずっと君達を探してたんだ。見つかるかなぁ。ねぇ、トラさん…」
珍しく顔を曇らせて、ヨリックは鼻ポンを詰めた、それでも美しい顔を、不安げな米子トラに向ける。米子トラの隣に、いつの間にか、小柄なハンサムな男性が立っている。女性陣も筋肉陣も知らない人物だったが、男性はエージェント・ランドン、RNAのエージェントだ。
027.水色ゆるいウルフカット
深堀花子さんは過去の記憶を掘り出したいのか封じたいのかよく分からなくなって沈黙していた。生前、この、佐備捜査官と多分、同級生だった。佐備捜査官は高校生だった。花子さんは、女子高生だった。それを佐備捜査官に思い出して貰いたい。だが、佐備捜査官は、死んでいないのに私の事を私だとわかってくれない。なぜ…?
「あ、いや、申し訳ない。そんな、若い女性に過去のことなんて」
「べ、別にいいけど」
それで、また沈黙が続く。先程抱き上げた仔猫ドラゴンを抱き直しながら、佐備捜査官は花子さんと少し離れたところに腰を降ろす。
「…いやあ、このドラゴンさん、ちょっと、昔クラスにいた方を思い出しましてね。もしかしたら、その、ちょっと独特な音楽がお好きな方だったので…お知り合いじゃなかったかなと。」
「ふぅん。どんな人?」
「ちょうどこんな風に、ソフトなウルフヘアでして…色は、この子よりも薄い、明るい水色に染めていて…」
佐備は膝の上の可愛らしい仔猫ドラゴンの青いタテガミを撫でながら言う。
「え?」
深堀花子さんは幽体なのに自分の顔から血の気が引いて行くのを感じる。全身もすぅと冷え、手足が透けるのを感じる。
「格好よかったですよ、こう、眉毛も無くて…」
花子さんは思い出した。あの頃、テンテイルズから入った音楽の世界で、なぜか更にその数十年昔の歌手、トミー・ブラックスターに惚れ込み、その格好を真似していたのだ。青いウルフヘアに眉無し、時々革ジャン。いや、革ジャンは自分の祖母のものだが…
「あああ、し、知らない!」
「そうですか…」
佐備捜査官は残念そうに微笑み、あぐらの上で寝息を立てだした仔猫ドラゴンたてがみを撫で始める。あのピンクの花、食べていいものだったのかしら。花子さんはそれ以上あれこれ思い出さないように関係ないことを考える。
「そ、そういえば、これからどうするの?電波ないんでしょ?」
「そうですね…遭難した時は動いてはいけないとは言いますが…」
それから、暫く沈黙が流れる。遠くからは、何か聞いたことのあるようなクラシックの音楽が流れてくる。いや、クラシックではないかもしれない。しかし、オーケストラの演奏のような気がする。
「クラシックか…でも、ちょっと、コントラバスの音が大きいと言うか…」
「どこから響いてくるんでしょうねぇ。」
「えっと…」
その時だった。
「ふぁんふぇあーーーん」
「にゃにゃにゃーん」
優しい金管楽器のような旋律が頭上から聞こえ、今来た方へと通り過ぎていく。二人が見上げると、黄色い枝と青い葉の梢の上を、金色に光る鳥のようなものが通り過ぎた。そして、その後、激しい風と重低音の旋律が同じように通り過ぎ、枝々を揺さぶって青い葉を散らせる。そして、その後にまた少し高い音と控えめな枝々のざわめきが続き、消えた。
「ね、聞こえた?」
「ちゃる捜査官声でしたね、あ!」
佐備捜査官が抱いた仔猫ドラゴンが、彼の腕を振り払って飛び出しす。そして、音が進んでいった方向へと飛んでいく。
「追いましょ!」
それで、二人は仔猫ドラゴンとちゃる捜査官の声が進んでいった方向へ再び駆け出す。
028.バイオリンの取り換え子

「ふむー13号室にゃあ…」
三ツ池はつぶやきながら、ぶらぶらと果てしなく長い廊下を進む。途中、時々、ブルードレスのイレーヌちゃんは友達を見つけては短い立ち話をし、その間に三ツ池は携帯を見返したり天使と話たりする。天使は、革張りの高そうな何かしらのケースを手にしている。
「天使ちゃん、それは? 大理石づくりじゃないんだね。」
「ああ、これは…バイオリンケースです。昔、博物館に遊びに来てくれた子がくれたんです。赤い靴下と、これ。」
「赤い靴下…シンちゃんがくるまってたやつにゃ。」
「ええ。彼は、イレーヌちゃんに誰かの命乞いをしにきたようですね。」
「誰かの?」
「『君の瞳は殺人光線、僕の心臓は粉々さ』って、流行ってませんでした?」
「うーん、ちょっと前に…流行ったかにゃ…? でも、流行歌にゃ。」
「ええ。イレーヌさんによると昔の歌の翻訳カバーなんだそうですが…それをシンちゃんさんの家族が上の空で歌っていたとかいないとか…恐ろしくなっていらしたそうです。」
「ニャルほど。」
「それで、このケースをお家にと提供したのですが…ないのです。」
「ない?」
「私の大理石のバイオリンが…」
「おやまぁ。」
また行方不明、ならぬ遺失物の書類が増えそうだと三ツ池が耳を倒しかけたところへ、天使は続ける。
「代わりに、本物のバイオリンが入っているんです。これはきっと、誰かの大切なものだと思うので。それで持ち歩いてるんです。」
そう言って天使は古そうなヴァイオリンケースを抱きかかえる。三ツ池には明らかに大理石の質感の天使の袖や手のひらが、絹や人間の肌の柔らかさで動くのを奇妙な感覚で見守る。
「ホラ、開いた。」
天使がヴァイオリンのケースを開いてみせると、そこに木製の見事なヴァイオリンが当然のように鎮座している。
「こちらにはきちんと弦が張ってあって、弓には馬の毛が使ってあります。私のバイオリンは大理石でできてるんですが…」
「大理石のヴァイオリン…でも、あにゃた弾けそうだね。」
「そりゃあもちろん。天使ですから。」
そこから天使は「もしもご興味があればなのですが」と前置きしてから、大理石と形而上の音楽についてできるかぎりわかりやすく語ってくれる。天使によれば天使は大理石のヴァイオリンで、「この地上で奏でられた最も適切で美しい演奏」を瞬間瞬間で再現することができるので、天使の演奏は「決してオリジナルではないけれども最上ではある」ものだそうだ。それを三ツ池捜査官は、自分にはキーワードをメモすることしかできなさそうだと判断して、「撮っていい?」と許可をとり、天使が嬉しそうに語り直すのを動画におさめる。三ツ池捜査官は寝不足と血糖値低下により判断力が落ちているので、その動画を「k2ab好きそう」とコメントを付けてグループニャットに送信する。しかし、それは電波が回復するまでは送信待ちの状態になる。
「にゃー電波が…」
三ツ池がため息混じりに呟くと、あちらの絵の中の牛乳を貰ってきたイレーヌちゃんが慰める。
「まぁ、仕方ないじゃない。牛乳いる?」
「いただきますにゃ…じゃないいただきます。」
三ツ池は疲れると猫語に戻りがちである。とりあえず、おいしそうな牛乳を一気飲みすると、向こうから笑顔でその様子をうかがっている黄色い服の女性に気がつく。それで目礼すると、女性はニッコリ笑って手を振る。
「パンもくれたわよ、いる?」
「いる!!」
イレーヌちゃんが差し出した美味しそうな焼きたてパンをかじりながら、三ツ池は黄色い服の女性に何度も頭を下げ、女性は可笑しそうに笑う。彼女の声は額縁の縁からこちらへは響いてこないが、三ツ池の感謝は伝わったようだ。
029.境界亀裂からコンニチワ
遮無捜査官が、信号で止まるたび、チラチラとタブレットにうつる4人の様子を確認しながら猫草台小学校へ車を飛ばしている頃、体育館では沼田署長と、なにかしらの臭い液体に塗れた分地が、可愛らしい仔猫ドラゴン2匹と、巨大な親ドラゴンの顔を前に、真面目な顔で立っていた。
「にゃにゃっにゃっ!」
仔猫ドラゴンは怒った様子で分地に翡翠色の猫爪を振りかざしている。
「いやね、ごめんね、ちょっと怒りすぎたかなとは思うよ…」
「にゃっ!しゃっ!」
「だって、ちゃるの安全は任せてくださいって言うから…」
「しゃーっ!!」
「ごめん、ごめんってば…」
分地元捜査官は、お怒りちゃる猫ドラゴンに平身低頭だが、そのすぐ隣の沼田署長は巨大な金色ドラゴンで緊張しながら、お怒りちゃるドラゴンに癒やされもし、色々と混乱するので早く部下たちが到着しないかと願っている。遮無はきっと冷静に戦闘態勢に入るだろうし、繰津は大喜びでドラゴン捕獲計画を立て、雨所は物静かに沼田の指示を待ち、三ツ池は…三ツ池はどうするだろう。とはいえ、仔猫ドラゴン化したちゃる捜査官も、ヘドロまみれな上に、顔のサイドにある3つ目の目玉をしまい忘れた分地も、境界から飛び出した金の巨大なドラゴンの顔にはお構い無しだ。
沼田は、その大きな金色のドラゴンのエメラルドグリーンの目が、心なしか悲しそうに見えるのに気がついた。ちゃる捜査官よりも小さな、ターコイズグリーンのタテガミの仔猫ドラゴンが、その黄金のヒゲにじゃれつく。大きなドラゴンは、馬にも似た鼻を鳴らし、ちゃるによって固められた境界亀裂の向こうにある喉で低い優しい音を響かせる。その生暖かい鼻息に前髪のカールを吹き飛ばされながらも、沼田署長は、彼女はお母さんなのね、と考える。先程聞こえた轟音は、このドラゴンの発した声なのではないだろうか。彼女が、この空間を突き破って、境界亀裂を生じさせ、体育館の舞台を破壊したのではなかろうか?
「どうすればお話が聞けるのかしら…」
沼田署長は、金色ドラゴンの前に歩を進め、緊張で笑顔が強張らないように大きく息を吐く。
「にゃ…にゃ、なーお?」
沼田署長は控えめな笑顔と猫語で語りかけるが、巨大な金のドラゴンには通じないようだ。僅かに広げた、ズラリと真っ白い歯が並ぶ赤い口から、遠くで鳴らされたパイプオルガンのような低音が響き、風圧で沼田署長は僅かに圧される。だが、その低音は不愉快ではない。
(ジェットバスみたいね⋯痩せそう⋯じゃなくて、通訳、通訳さんが必要ね。猫語が通じないのなら、ドラゴン語かしら?あ、それなら…)
しかし、分地に激しくお怒りだったちゃる捜査官が、沼田に気付いて駆け寄る。
「にゃにゃにゃ、にゃー」
「そうよねぇ…顔が猫でも声は…楽器みたいよね。」
「にゃにゃ。」
「そうか…猫語も通じないの…じゃあ、ちゃる捜査官はどうやってここへ…?」
「にゃにゃ!」
ちゃる捜査官が示す先では笑顔のハンナさんと若干疲れた様子の深堀バンドのドラマーと、幽霊猫とDJのユニット「ネコネス」、有志の男性幽霊達によるマリアッチが暇を持て余したように談笑している。皆、大会閉会式を盛り上げるために、沼田署長がハンナさんの力をかりて集めたメンバーだ。その内に控えめに歌う幽霊猫にハンナさんがエアヴァイオリンをあわせはじめ、二人の優しい音色が控えめに体育館の隅から流れる。傍らでサンプリングマシンを操作する長髪の青年が二人の演奏にリズムを乗せはじめる。
「にゃみゃにゃ」
「え、あ、ハンナさんとネコネスさんと、幽霊猫カラさん?」
「にゃにゃにゃん!にゃにゃなーなーにゃにゃなー」
「ええ?ドラゴン語?ヴァイオリンなのに?」
「みゃみゃー」
ちゃる捜査官はどうしても猫語から離れられず苛ついた様子だが、ちゃるママはちゃる捜査官のお怒りの方向が逸れてホッとした様子で整理する。
「ハンナさん、あの、ドラゴン語は…?」
「うふふ、ハンナちゃんは人間語と猫語とドラゴン語もできるのよ。一時期、ドラゴン保護区近くに住んでたそうなの。」
ハンナさんのかわりに沼田署長が嬉しそうに答えるが、ハンナさんは苦笑しながら訂正する。
「ドラゴン語は、わかるけど…幽霊じゃ、というか人間には発音不可能なの。実体のあるヴァイオリンがあればひけるんだけど…」
「にゃーにゃっにゃ?」
「ええ。ヴァイオリンだけは、幽霊になっても実物を持てるの。体の一部みたいなものだからかな。でも、今は持ってないの。」
ハンナさんはドラゴン化したちゃる捜査官に説明する。
「ああ、そうだったわね…だからRNAに依頼をしたのだったものね…」
沼田署長が、表情を曇らせ、チラとドラゴンの方を伺う。ドラゴンは、ちゃる捜査官ドラゴンが気になるようで、時折、低い優しい音で鳴いて呼びかける。ちゃるママがそれを睨みつける。巨大なドラゴンがそれを歯牙にもかけない様子でちらと見る。ハンナさんはその様子を観察しながら、抑えた声で解説する。
「ええと…大きなドラゴンは、ちゃるちゃんが自分の子供だと思ってるたい。あと…」
突然、ドラゴンがわずかに首を伸ばす。長髪の青年が警戒した様子で、幽霊猫を抱きかかえて後ろへ下がる。
「あと、1匹子供がいるみたいね…ちゃるちゃんカウントされちゃってるから、あっちの小さいドラゴンとあわせて、正確には3匹…?」
「え、ええ…!? まさか…。」
沼田署長の脳内では、仔ドラゴン化した佐備捜査官の姿が浮かぶ。しかし、佐備捜査官の姿は見えない。
「ああ、佐備君…」
「それに深堀花子さんもいないんだよね…だって、戻ってきてないもの…」
ハンナさんが、言うと、沼田、分地、ちゃる、は巨大ドラゴンと仔ドラゴンの向こうの琥珀色の境界に透けて見える、遥かなる景色に言葉を失って立ち尽くす。
030.エージェント・ランドンとユニコーンの尻尾
「これこれ、シドニー・ランドン。ご挨拶が先でしょうに。」
米子トラが厳しいながらもほほ笑みを隠しきれない声でエージェント・ランドンに声を掛けると、ランドンは不敵な笑みを崩さぬまま優雅にお辞儀をする。それから、居並ぶ巨大なマッチョ達を一人一人品定めするように眺め、美マッチョとその妹、次いで不破望子に目を留め、真っ直ぐに望子に歩み寄る。
「お邪魔しています、マドモアゼル・フワ。噂に違わずお美しい…あ、いや、これは失礼。前時代的でしたね。いつも祖母がお世話になっております。」
「あ、え、ええ…御義母様にはよくしていただいておりま…祖母…え? あ、もう驚かない…ええと、ごきげんよう、ランドンさん。ご血縁の方なのですね…」
不破望子は、同じく米子トラの孫だか夜叉孫だったかの、失踪したまま元夫とも、何代下だか把握しきれない孫のセドリックとも、エージェント・ランドンが全く似ていない事に奇妙な衝撃を受ける。誰に似ているか…あえて言えば、300歳の美しいおばあさんであるところの、義母米子トラに似ている。だが、それは今の状況とはあまり関わり合いはない。
「ええと…」
「我々、RNAの方で、現在2件の行方不明案件を抱えておりまして。その内の1件がこちらのデザイナー、セドリック氏なのです。それから、ユニコーンの尾の毛を使ったヴァイオリンの弓。」
「はぁ。ユニコーンの尾…あの、ユニコーンはうちにはキャラだけで、本物はおりませんが…」
「ええ。承知しております。」
「では、何故…あ、いや、御義母様を訪ねておいでで…」
すると、今まで大人しく兄の髪を編んでいたビアンカが声を上げる。
「見た!見たわよ、ユニコーンとヴァイオリン!」
「…おや、リーピチープ王国のお姫様…」
若干警戒した様子のランドンに代わって、リーピチープ王国の王子様が「マジで?」と妹に問いかける。
「お兄ちゃん、ソレじゃバカっぽいわ。もっと王子様らしくもう一回。」
「さようか?」
「よろしい。」
ビアンカが兄に殿様的な話し方を仕込むのをエージェント・ランドンは眼鏡を調整し直すことで時間を潰して待ち、ビアンカが向き直ると指をパチンと鳴らす。ビアンカと周囲のマッチョは身構えるが、エージェント・ランドンはすまして微笑む。
「失礼、これでストリーミングをスタートさせましたので…どうぞ。」
「え、ストリーミング…?」
「ええ。一応、RNA内でも情報を共有しておきたいもので。」
「うーん、RNAか…でも、やっぱり顔出しはまずいなぁ。お兄ちゃん、それかして。」
ビアンカは兄から薔薇柄のクッションカバーを奪うと、頭に被って話し始める。
031. 四季の人々

三ツ池とイレーヌちゃんと天使は長い廊下を進む。右も左も変わり映えしない同じ、立派な額縁に素敵な棚に、時々混ざる寝椅子にアートという名の空き缶に、退屈そうな貴族たちの肖像だ。中には丸い額縁の中のヒトのお母さんと子供や、ぷっくり丸々としたモナ・リザ、ハート型の額縁に入った太やかなネズミの絵もあれば、青い上着を着たウサギビトの少年の絵まである。
「あれは…ウサビトかにゃ…しかし、さっきのパン美味しかったにゃ…あの葡萄もおいしそうだにゃ…」
三ツ池は「13号室」を目で探りつつも、あてもなく進む。壁にかかる静物画にはどれも美味しそうな果物やパン、チーズや海老的な何かが描かれているが、時々そこに混ざってお亡くなりになったウサギなどもある。先ほど青い上着のウサビトの少年の肖像を見ているので、三ツ池には若干ショッキングだ。そこから気まずい思いで目を逸らすと黄色いブドウが目に入る。それで、「ああ、これなら…」と手を伸ばす。ブドウを一粒つまんだところで、ぱしりと手をたたかれて飛び退る。
「これ!人の髪をなんだと思ってるんだ!」
見れば、憤慨した様子の、男性とも果物の塊とも見える人物がぷりぷりとキノコでできたほおを膨らませている。
「にゃ…あ、もうしわない!」
三ツ池が素直に謝ると、怒った食べ物でできた人物はぷいと後ろを向いてしまう。
「ほほほ、彼は美味しそうですものねぇ。猫ちゃん、お腹が減ってるの?」
朗らかな声が隣の額縁から聞こえ、やはり美味しそうな果物でできた女性が微笑む。
「よく笑えるのう、あんたも耳を齧られたじゃろうが。」
と、女性とは反対側の額縁から老人の同情とも皮肉とも取れる声が聞こえ、三ツ池はその額縁から話しかけたのがほとんど切り株と枝のような老人だという事を見て取ってぎょっとする。
「あら、あたくし、別に腹ペコねずみちゃんに髪飾りを差し上げるのは構わないのよ。猫ちゃんもいる?」
そう言って額縁の中の婦人がは髪飾りの赤いさくらんぼを引きちぎり、三ツ池に手渡す。
「あ、ありがとうにゃ…」
「あら、イレーヌちゃん!」
「こんにちは、『夏』さん。ねえ、十三号室って知らない?」
「13号室…現代芸術っぽい題ねぇ、あたくし存じ上げないわ。『春』ちゃん、どう?」
「ええと…知らないな、ごめんね、イレーヌちゃん。」
『春』と呼びかけられた女性は花びらで構成された顔で申し訳なさそうに微笑む。彼女が話すとふんわりと花の香りが広がり、そこからは『春』ちゃんとイレーヌちゃんの会話となる。
「あのね、イレーヌちゃん!次の『化け猫カリリン忍法帖』、ワビサビ桃源郷が舞台なんだって!」
「ええ!深堀池じゃないの?」
「ほんとよ!関係者だって人が教えてくれたんだ」
「ええーいいな、それでそれで?」
三ツ池は、よもや名画の世界でも『パンダルマン』が人気だとは、という驚きと、名画同士もガールズトークするんだな、という驚きの両方に気を取られて、もらったさくらんぼを口に放り込みながら目を泳がす。先ほどの気の毒なウサギに視線をやらないように…と、見上げると、ハートの形の額縁が揺れている。三ツ池がその額縁を見上げる間にも、名画同士の会話は楽しそうに続く。
「え、なにちょっと関係者ってだれ?」
テンションの上がってイレーヌちゃんが熱心に言うと、花で構成された若い女性は嬉しそうに声をひそめる。
「ちょっと前までこの辺を散歩に来てた丸っこいネズミさんなんだけど…かわいいの。」
「丸っこい?かりん様はスリムマッチョな美女アネゴなのに?」
「うん、作者のお孫さんなんだって。でも、最近来ないんだよね…私、ここ出ると崩れちゃうから探しに行けないし。心配なんだ。」
「へぇ、どうしたんだろうねぇ…」
その会話を聞きながら、三ツ池はハート型の額縁をみている。青い空に雲の背景、ぷっくりとした天使のような服を着せられた、ネズミビトの、あれは…
「セドリック…?!」
セドリックは、三ツ池に向かって必死で手を降っている。何かを叫んでいるようだが、それは聞こえて来ない。
「んにゃぁ…ハートか…」
げっそりと言うと、三ツ池は少し高いところにあるそのハート型の額縁に手を振り返す。セドリックくんは嬉しそうに手を振り替えし、目を輝かせている。しかし、彼の絵は高いところに飾られており、三ツ池もイレーヌちゃんも天使も、見上げるばかりだ。
「うーん…どうするかにゃぁ」
「お友達?」
「知り合い」
「そうなの…?」
「にゃあ、アンタ天使だし、飛べないの?」
「無理ですよ、大理石だし」
「役に立たないにゃあ…」
「あら、肩車って手があるわよ?」
イレーヌちゃんがニコニコと笑いながら提案する。
「え、ええ…?」
大理石の天使は大理石の目を見開いて半歩下がる。
032. 雨所とRNAのエージェント達
雨所は割とマイペースで、どちらかと言うと乙女で大人しいネコビトだ。少なくとも自分ではそう思っている。遮無先輩のクールビューティーには憧れるが、自分には再現可能だとは思えない。三ツ池や繰津のように己が道を行けるタイプではないし、好きなオシャレかわいい服を、あわよくばちゃる捜査官や佐備捜査官に着せたいと目論むだけの夢見がちな、やはり地味で大人しい乙女なのだ。そんな事を考えながら、雨所は最近話題の『むじな』の前にラベンダー色のスクーターを停める。
カフェ『むじな』は噂で聞く程度の頃は興味があったが、興味があるうちには訪ねる時間がなかった。しかし、あまり話題になると、話題になっているという事実自体が、自分の好きな感じかどうかに疑いを持たせる。しかし、この店構えは気に入った。土壁風の外壁。オシャレだ。営業時間なのに「Entrée」の札が「準備中」に架け替えられている。『むじな』のドアの前で、雨所捜査官は遮無からのメッセージを確認する。
『余罪ないか探ってみてね』
それで、ツイードのピッタリした上着を着た雨所はドアのガラスから中を覗いてみる。店の入り口には品のいい衝立が立っており、中の様子は直接伺えない。それで、雨所は身をかがめて窓のしたへ移動する。昔の映画の女優のようにコケティッシュなベリーショートから飛び出した猫耳だけを、僅かに開いた窓の前に持ってくる。男女4人の声が聞こえてくる。
「…遮無さん、戻ってきませんね」
「あの奈落へ飛び込んだ猫女、死んだかのぅ…哀れじゃ…」
「あ、大丈夫、あの人、割と無敵っすよ、肩から蟹みたいな爪生えるし」
「蟹、とな」
「でも、あの人と遮無さんだと、俺的には遮無さんの方がコワイす。」
「なぜじゃ」
「カニよりは美人の方がコワイっていうか…」
「あれは…そうか、ヌシらの間では美しいのじゃな」
「え、違うんすか?」
「我々の国では彼女は平均的じゃ。均整の取れた容姿がハダカデバネズミ王国では当然というか…それゆえに、こう、もちっとな、美には不完全性が欲しいところじゃ…」
「ふ、ふかんぜんせい…!?」
吉田が言葉を失っているところへ、サイクロプスのヘイスタックが明るい声で割り込む。
「へぇ、でも僕には二人とも素敵にみえるなぁ、あ、もちろん貴女も。」
「おや、ヘイスタック君、ネコビトやネズミビトは苦手だと仰っていませんでしたか」
「うん、でもレディなら皆さん素敵だからねぇ」
「ノン…」
スーシェが呆れたように溜息をつくと、ヘイスタックは明るく笑う。
『アホな世間話してます、姫の確保だけでいいですか』
『吉田くんと店主は解放OK、姫とトレンチコートは確保。』
『はーい、じゃあ、繰津さん来ないけどいいかな』
『来てないの? 一人だと危ないから、もうちょっと待ってみて。』
「もう、危なくないのにぃ。」
雨所が不満げに溜息をついたとき、『むじな』の手前の狭い道路に、巨大なリムジンが停車する。雨所は素早く『むじな』看板の後ろに隠れる。黒光りする長い高級車の窓もすべて黒いスクリーンが張ってあり、中はうかがいしれない。
しばらくすると、手前の扉が開き、大きな体格のいい男性が降りてくる。浅黒いつやつやした肌その頭頂まで続き、ヘンリーネックの長袖シャツは真っ白で清潔感に溢れている。彼のすぐ後ろから色白の一回り小さい、ハンサムな坊主の男性が降り立つ。雨所捜査官が看板からのぞくと、二人の向こうに、車の中からこちらを指さす美しいおばあさんが見える。それをうけて二人はこちらに手をあげて合図をしながら近付いてくる。
「ハァイ。俺は可憐、こっちは寒。RNAだ。君はCATのミズ雨所だね?」
「あ、はあ。YES。」
「ランドンから話を聞いているよ、その、中はどんな様子だい?」
「遮無が4人を縛って放置してます。」
「亀裂は?」
「消えたみたいです。」
「亀裂が? 誰か落ちたのか?」
「落ちたというか…時々飛び込んじゃう人がウチにはいるんで…」
「ウワォ。クレイジーだね。」
「ですよね」
その会話を続けながらも、エージェント可憐、エージェント寒は突入の構えを取り、雨所もテーザー銃を構える。
無言で頷き合い、静かにドアを開き、素早くついたての向こうへ1回り込むと、「CATだ、手を挙げろ!」とピシャリと言う。吉田くんの手錠を外そうと四苦八苦していたアライグマが手を挙げる。
「吉田くん…と、ラスカルね。」
「アライグマ…?!」
驚いたように寒が言うと、雨所は困ったように笑い、アライグマに向けたテーザー銃を下げる。
「いいの、吉田クンもラスカルも、情報屋なの。返してあげてもいいかな?」
「まぁ…俺たちは彼に用はないし。あ、でも、そっちの彼。」
「ああ、そうよね。ラスカル君、ジャンプして。」
ラスカル君はアライグマビトではなくアライグマなので、アライグマのまま不安そうに立ち尽くして頭を振る。それで、吉田君が、その毛皮から、パールのイヤリングと琥珀のカンザシ、そして幾つかのアクリルスタンドを取り出して、それを取り返そうとするラスカルの君の手を振り払って雨所に渡す。
「あ! 妾のアクスタ…」
「すんません、コイツ、手癖悪くて。でも、コレを取ったのはコイツじゃなくて…」
吉田君が申し開きをする前に、RNAの二人がトレンチコートのヘイスタックを引っ立てる。ヘイスタックは相変わらず笑顔だが、スーシェ氏は青ざめてそれを見つめている。可憐が、そのトレンチコートを裏返すと、宝飾品とアクリルスタンドがバラバラと床に落ちる。
「ヘイスタック君、君は…」
「イヤだなぁ、僕は何もやましいことなど…」
「レディの部屋からモノを盗むとは、なんと恥知らずな…」
スーシェ氏は怒りに青ざめ、顔も半ば消えて眉間のシワばかりが目立つ。寒がヘイスタックから吉田の尻尾に繋がれた手錠を外し、後ろ手に手錠をかける。
「ヘイスタック、別名アブソルート・ビギナー。
お前さん、美術品専門の泥棒じゃなかったのか。」
可憐が不思議そうに床に落ちたアクリルスタンドを拾い集めながら言う。アクリルスタンドには、パンダルマンやカリリン師匠などの他、油絵の男性の絵や青い服を着た少女の絵もある。
「なんだいこのキャラクターは? パンダ? はは、寒、ちょっとにてる」
「俺はパンダよりはグリズリーだよ」
二人とも巨大なネズミビトなのに、と雨所は思いいながら、その1枚を可憐から受け取る。まるぽちゃの可愛い男性がキューピッドの服を着せられて恥ずかしそうにしている。
「…なんか、この人、見たことあるな…あ!」
次の瞬間、絵の背景から、猫の手が飛び出し、アクリルスタンド内の男性をあちらに引き倒してしまった。それに伴って、絵はあちらへ倒れるような具合で、かき消えてしまった。そして、雨所の手元には、透明でハート型のアクリルスタンドだけがのこった。
「えええええ…ナニコレ…?」
雨所が消え入るような声を出すと、始めてヘイスタックの顔から笑顔が消えて、とても残念そうな表情をする。
「あーあ、消えちゃったの? せっかく御礼がもらえると思ったのにぃ。」
「何を言ってるんだ、まったく。行くぞ。」
可憐と寒がヘイスタックを引っ張っていこうとするその方向に、気づけば、先ほどの綺麗なおばあさんと、ハンサムで小柄な、眼鏡をかけた男性が立っている。
「絵が消えた、と…?」
眼鏡の男性が雨所にツカツカと歩み寄り、その手からハート型のアクリルスタンドを優しく引き抜く。雨所は、その男性があまりにも自分の好みだったので、指紋を確保しようとアクリルスタンドを奪い返す。男性は呆れたように振り返り、振り返った先の美しいおばあさんが今度は雨所に歩み寄り、微笑みかけて、アクリルスタンドを引き抜く。
「ふふふ、ごめんなさいね。これね、夜叉孫の行き先の手がかりなの。」
「え、ええ…? でもきえちゃいましたよ、なんなんです、この絵…?」
「檻です。ねえ、そうでしょ? ティタニアさん。」
美しいおばあさんは、手錠から自由になったスーシェ氏が素早くさし出した、この店で一番上等な椅子に腰掛ける。ティタニアは、そのハート型のアクリルスタンドを、悲しげな目で見上げる。その髪は濡れたように赤く染まっている。
033.暗い森とサビイロネコ
「…うう、ちゃるちゃん…あっという間に消えたわね」
「すっかり迷ってしまいましたね…」
ちゃる捜査官の声を追って追いかけたものの追い付けず、深堀花子さんと佐備捜査官はジャングル奥底で迷っていた。日が暮れたのか、森は暗い。深堀花子さんは、自分の身体をうっすらと光らせながら、真っ暗い森をゆっくり進む。ゆっくりと進むのは、別に足元があやしいとか、暗すぎるというわけではない。ただ、仔ネコビトサイズの佐備が、赤ちゃんネコビトサイズの仔猫ドラゴンを抱いて歩くのに疲れてきた様子だからだ。考えてみれば、最後に軽食を摂った後、彼はずっと何も食べずに走ったり、子供サイズの身体で赤ちゃんを抱っこして歩き回ったりしているようなもので、疲れないわけはない。それとも、ネコビトは疲れにくいものなのだろうか?
「…ちょっと、休もっか。暗いし。」
「そうですね。」
そう言ってこちらを見て微笑む佐備捜査官の瞳は、暗い周囲の環境に合わせて瞳孔が真ん丸になっている。それがまた可愛いので深堀花子さんの足元にまたゾロリと何かが生える。
「ああ、灯り。ありがとうございます。」
見れば、それは光る小さいキノコで、佐備はそれを深堀花子さん意図して生やしたものと誤解したらしい。
「え、ええ。」
深堀花子さんは動揺を見せないようにほほ笑み、空中で腰掛ける。佐備捜査官がすっかり寝込んでしまった仔猫ドラゴンを柔らかそうな苔の上に下ろし、CATの特殊通信機でその写真を撮る。
「ちいさいドラゴンさん、可愛らしいですねぇ、親御さん、どこにいらっしゃるんでしょう…」
「ちゃる捜査官の後に飛んでいった巨大なドラゴン…金色だったわよね。あれがママさんかな。」
「あるいは、パパさんか…おばあさまってこともあるかもしれませんね。」
「それか、全く別種で、もしかしたら、これで成体だったりして。」
「え? あ、ははは。」
深堀花子さんは、その佐備の笑いに、初めて気まずそうな気配を感じ取って一瞬考えを巡らせる。幼い様相の成体…そして花子さんは気づいた。
「あ、ご、ごめんなさい!」
「あ、いや、確かにと思いまして…我々の一族もかつてはジャングルで暮らしていたんですよ。サビイロネコといいまして…」
「あ、ああ! だから佐備さんなのね! 私、サビ猫って女の子しかいないって聞いてたから名前は関係ないかと思ってた!」
深堀花子さんは佐備捜査官が自分の話を始めてくれたのがうれしくて仕方がない。
「ええ、そうなんです。サビイロネコもこういったジャングルに住むものでして、そうするとあまり大きくないほうが生存に有利なのかもしれません。ジャングルといえば、我々は元いた世界でも森のような場所を好んだと聞いています。」
「元いた…?」
「ああ、これは一部のネコビトの話なのですが…」
花子さんが、人間に預かり知るところのないネコビトの謎を垣間見ることができるかと身を乗り出す。その時、突然、佐備捜査官のCATの特殊通信機が光る。
『そのカバーやめませんか』
見れば、画面に、バラの柄の枕カバーようなものを被った女性と思しき人物が映っている。
『イヤよ、配信でしょ? 顔がうつるとまずいの』
『しかし、これでは見る側からすれば拿捕された人質…』
『イヤよ、取ったら話さないんだから』
そんな会話が続くのを、深堀花子さんと佐備捜査官は見守る。
「この女の子…なんで布被りたいの?」
「わかりません。これがどの世界の通信かも…」
「うーん、これ、私達の世界よ。」
「え?」
「背景にマッチョな人いるでしょ? その横に、ハニーバニーいない?」
「ああ、いますね…」
『見たの。ユニコーンよ。暗い森で、光るタテガミを揺らして、綺麗な女の子が仔猫とドラゴンと並んでる絵よ』
薔薇の花の絵を被った女性が、そうして言葉をきる。それから、誰かの背中が画面の前を覆い、少しして、「マカロン・キトゥン」のお面を被った先程の女性が姿を現す。
『ありがとう、でも、なんでまたお兄様にカバーかけるの?』
『すみません…鼻血が止まったご様子だったので…』
『あ、今度は貴女が出てる、鼻血』
ほの明るい画面から交わされるとりとめのない会話を、深堀花子さんと佐備捜査官はため息混じりに見守る。
「ユニコーンって言った?」
「我々みたいでしたね」
「ああ、ドラゴンとか猫とか、ユニコーン以外はそうね」
「いえ、ユニコーンは…」
その時、深堀花子さんは、何十年ぶりかに、柔らかい風が頬を撫でるのを感じた。その風は、何十年ぶりかに嗅ぐ、綿菓子の香りがする。佐備捜査官は、緊張した面持ちでこちらを見ている。深堀花子さんは、ゆっくりと、振り返る。
CAT File 3 :行方不明が多すぎる 報告書作成中…
ちゃること我が娘と相談しながら進めました。
◯本物のヴァイオリニストさんに出演許可を頂いたので、ドキドキしながら書いてます。
◯深掘花子さんは6期鬼太郎の猫娘イメージです。
◯佐備さんは元々は好きだった刑事ドラマの本城さんのイメージだったのですが、全然違う方向へ行ってしまいました。
◯小泉八雲のムジナと、水木しげるののっぺらぼうが、ポワロだったら素敵だなと。ポワロはスーシェ以外認めません。曰くリアルちゃる。
◯ドラゴンはキングギなんとかですが、首が3本設定は使いにくいのでやめました。仔猫ドラゴンは日光東照宮の狛犬の色です。
◯ヨリックにはSNS上に実在のモデルがいます。北欧の奇跡です。
◯ビリーはテリーです。ビリーの上司はシルベ…なんとか・スタなんとかです。エクスペなんとかって映画の人たちみたいな感じです。


