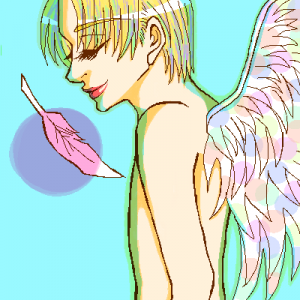Hesthquez
体が痺れる。指に力が入らない。
舌は重くもつれ、思うように言葉が紡げない。
這いつくばる地面になんとか爪を立て体を起こそうとするも、ただ無意味に終わる。
あんなにも自由に動かせたこの体は自分のものだというのに、何ひとつとして言うことを聞いてはくれない。
吐き出したワインは、まるで血の如く美しく磨かれた床を汚す。
「まったくもってよい眺めだなあ、我が弟よ」
見上げた先、恍惚の表情を浮かべる兄君は、弾んだ声色で私を見下ろす。
「いつも上品に澄ました苦労というものを知らないようなお前が、まるで潰れた蛙の如く地面に貼りつく姿を見られるなど、こんなに愉快なことはない。……失礼、蛙のようと言ったか? これではまるで、女神ヘケトを侮辱しているようだな」
そう悪びれず言う兄君を見上げる視界は、少しずつ霞んできたのか、世界が白く覆われてゆく。
「何が起こっているかわからないか? 単純なことだ。お前の飲んだその杯に毒を盛った」
なぜ、問おうとする唇から洩れたのは、声にならない音。
それでも兄君は理解したらしく、深まる恍惚とそれに比例して顕になる喜びを含んだ声で話し続ける。
「“なぜ”? “なぜか”だって? ああ、弟よ、それこそ私が一番知りたいことなのだよ。“なぜ”父の跡を継ぎ、次の王となるのがこの私ではなくお前なのだ? “なぜ”ふらふらと町から町へ彷徨い遊び、下賤な民たちとくだらぬ仲良しごっこをする、王家の矜持も小間使いを虐げる力すらない、非力で愚かなお前が王位を継ぐのだ? 王の長子である、生まれた瞬間から次の王になるべく決まっていたはずの、お前より遥かに賢く、生まれついて人の上に立つ才がある、この、私ではなく!!」
まるで芝居がかったかのような喜びの声は、一転してどんどんと憎しみと怒りを含んだものへと変化する。
「可笑しな話だろう? 元来ならば長子が王位を継ぐのが慣わしだというのに。父君は何を考えお前を王にしようと言うのだろうな、可愛い王子、我が弟よ。代わりに私に贈られたのは、お前を補佐するようにというありがたいお言葉と、お前が受け継ぐはずだった小さき領土と、粗末でくだらぬ神殿だ。贈られるものが逆だとは思わないか? 我らが王はまだお若いはずだが、まさかもう耄碌しているわけではなかろうな?」
猫撫で声でそう言う兄君に、体が震える。
兄君が私を疎ましく思っているのは、子供の時分からなんとなく気づいてはいた。
それでも、彼の言う通り私よりも先に生まれ、民草のために豊かで平和な王国を存続させるべく、王になるための教育を受けてきた兄君のことを尊敬していた。
だからこそ、父君が私に王位を継がせると仰ったとき、真っ先に王になるべく器ではないと断ったのは私自身だ。
私の身には、本来私に与えられたもので充分幸せなのだと。
何よりも、血を分けた兄弟なのだ。
たとえ彼が私をどう思っていようと、愛情を覚えるのは当然だ。当然のはずなのだ。
だというのに、私自身無意識に蓋をしていた感情が、まるで首をもたげる蛇のように静かに、そして確実に黒い煙となり立ち上り、私の全身を舐めつくす。
そこには、目の前の狂気的な姿の兄君への恐怖と、やはり私は彼に愛されていなかったのだという、絶望のみがあった。
「まあ、もうどちらでもよいことだ。年老いた役立たずの王も、その妻も、もう用無しなのだから」
ひゅう、粗末な壁にぶつかり消えてゆく風のような呼吸が、喉から音を鳴らす。
王とは、そして妻とはつまり、私達の両親ではないか。
彼らは無事なのか? ふたりはまさか、血のようなワインや毒のビールに塗れ倒れ伏しているのか? 今のこの私のように?
思わず見えぬ瞳で兄君を仰ぎ見やれば、彼の声はぞっとするほど優しい音を奏でる。
「安心するがいい、可愛い弟よ。お前達の墓は、王家らしく立派で美しい物を建ててやる。勿論、来世へ迷いなくゆけるようにと、肉体を損なうこともせぬ。この世で一番の腕を持つミイラ職人に、お前達の体を預けるつもりだ。棺も副葬品も何もかもが、豪華絢爛な素晴らしいものになるぞ」
そう言いながら、私のそばへとひざまずいたであろう兄君の気配を感じる。
同時に、喉の先に、硬く冷たい尖った物が触れ、麻痺しているはずの体からどっと冷や汗が吹き出す。
「ただし、念のため首は掻き切らせてもらう。万が一毒が効かなかったことも考えてな。まあ、お前のその姿を見るに、心配には及ばないようだが」
もはや、我が命もここで終わりか……そう思うと同時、誰かがこちらへ走ってくる足音と、王子、と呼ぶ声がする。
どうか、こちらへ来ないでくれ。私を見つけないでくれ。ここはとても危険なのだ。
「王子、ご無事ですか? 陛下と皇后様が……」
願いは虚しく私の中で木霊するのみで、神々へ届くことはなかった。
心配と恐れを含んだ声の主は、私達を見つけた証拠に、驚きに息を呑み、言葉を失くし立ちすくんでいるであろう気配がする。
ああ、なぜここに来たのが、私のこの無様な姿を見つけるのが、火の中に自ら飛び込む愚かな山羊のごとく危険に晒されるのが、よりによってそなたなのだ。
「ああ、お前は確か……トートの神殿へ支える巫女か。お前のような者がその様子でここへ来たということは、王と王妃は混乱の元となることに成功したようだな」
そう蔑み、吐き捨てるように彼女へ声をかける兄君は、身を起こしじりじりと彼女の方へ近づく。
目に見えなくとも、動く気配で、空気の流れで、響く音で、狩りをする獣が獲物を変えたのがわかる。
確実に仕留め、放っておいてもそのうちに肉を喰らえるであろう私ではなく、小さく、哀れで無力な彼女の方へと。
「混乱の元……? つまり、お二方が倒れられたのを、あなたはご存知なのですか? それに……それに、彼は? どうしてこんな……」
そう戸惑いながら返す彼女の声が、私へと近づいてくる。
這いつくばる私の体を、私よりも小さい手が抱き起こす。
どんどんと体が冷えてゆく私とは反対に、温かい体温が私に触れる。
ああ、彼女は生きているのだな。そして、そして私は……——
「“どうして”かだって? それはお前が知っているのではないか? 偉大なる知恵の神トートを通して、お前なら容易く予見できたのでは? その為にあの神殿に仕えているのだろう? 健気なことだ、その卑しい身分にありながら恋い慕っている王子を探しに来るとは。私がお前のその汚らわしい思いに気づかぬとでも思ったか? 腐っても王族である我が弟を見つめている、お前の吐き気を催すような視線に? 私を嫌悪し、疑い深く注視していたのも知っているぞ。できるだけ私から弟や王達を守ろうと、悪あがきしていたのもな。だからこそ、真っ先に王子を探しに来たのだろう? もっとも、お前ごときが王子や王達のためにできることなどなさそうだが」
蔑む口調を隠そうともせずに、兄君はそう吐き捨てる。
「……なんと愚かな。こんな事をしても、あなたが偉大な王になれるわけなどないのに。寧ろ、これより未来、あなたは美しく平穏な国を支えた王とその妻と子を殺めた、恥ずべき血族として歴史に残るでしょう。神々の裁きは平等なのですから」
いつもは間延びしたようにゆったりと話す声を震わせながら、彼女がそう応える。
声がか細く聞こえるのは、恐怖心の現れなのか、否、私の意識が薄らいできたからか。
震えているのは、声だけでない。触れたぬくもりから、彼女のすべてが恐怖に包まれているのを感じる。
可哀想に、なぜここへ来たのだろう。
この身を支えるその細い腕を解いて、今すぐここから立ち去ってしまえばいいのに。
こんな、温度の消えゆく、ただ死にゆくだけの私などを捨て置いて。
「“愚か”だと? “恥ずべき血族”? この私がか? いいや、哀れで愚かな女よ、その逆だ。私は誰も成さなかったことを成す。例えそれが、血を分けた者を葬ることになったとしても、それは偉業のための小さき犠牲だったにすぎぬのだ。お前の言う神々の裁きなど、そんなくだらぬものは関係ない。愚かで臆病な者共が自身を高めようともせず、何も成し遂げることができない言い訳をするために作り出した戯言にすぎぬ。お前もいつかわかるだろう。もっとも、それはお前が生きている間に起こることではないのだが」
上からどす黒く、冷たく響く声が降ってきた刹那、咽せ返るほどの鉄の香りが漂う。
同時に、私の体を支える細腕が力を失くす。
それでも、この身を案じ床に叩きつけられぬようにと気遣う彼女の体が、私の横へと倒れこむ気配がする。
「だが、今宵ばかりはトート神に感謝せねばな。これこそ“神の思し召し”だ。弟を葬るよい筋書ができたぞ。身分の違いで結ばれることはないと悲観した恋人達は、その若さと愚かさゆえ、ついに共に来世へ旅立つことを決める。それを発見した王と妻は、我が子を失った悲しみのあまりこの世を去る。かくして、悲劇を抱えてそれでも国のために王位を継がねばならぬ私は、国民の同情を集めるだろう。案ずることはない、群衆など、“太陽神ラーの息子”である王の言うことはどんなことでも信じるものだ。だからこそ、我ら王族の名声と安寧は永遠なのだ」
薄らいでゆく意識が、夢から覚めたようにはっきりするのがわかる。
こんな感情を抱くのは生まれて初めてだ。まるで炎のように怒りが体を駆け巡る。
その炎が原動力となり、私の持てる力の最後まで振り絞る。
横に伏した彼女へと伸びた手は、全身を巡る熱さとは反対に頼りなく、震えながら彷徨う。
その手を、自分のものよりも小さな手が導き、頬であろう丸みのある場所へと触れた。
重なりあった掌を伝う、彼女の荒く苦しむ息遣いを感じる。
彼女の苦悶しているであろう顔すら見えないのは、幸か不幸か。
彼女の瞳に映る私は、どんな表情をしているのだろう。
この何も映さなくなった目から熱きものが流れている気がするのだが、これは私の涙か、はたして血なのか、もはやわからない。
流れゆく何かを拭い去るように、彼女の細い指が頬に触れた。
「また会える」
いつも私に微笑みかけてくれたときと同じ声で、しかし微かにしか聞こえない音でそう言ったのが、不思議とはっきりと耳に届いた。
そうしたのちに、頬にあった指先が力を失くし、落ちてゆく。
命の灯火、アンクの炎が彼女の中から消えてゆくのが、見えぬ目で見えた。
せめて、この瞳にその姿が映るうちに、その手を握りたかった。
この掌が温かいうちにその頬に触れ、愛を囁き、そこを赤く染めさせたかった。
毒を含まぬ唇で、そのふっくらと色づいた唇に口づけをしたかった。
その細く小さな体を抱きしめ、優しくぬくもりある柔らかな心を独り占めしたかった。
せめて、そなたを好きだと、誰よりも愛しているとこの声に乗せ伝えたかった。
そうだ、私は、そなたの恋人になりたかったのだ。
「……——」
想い人の名を呼んだはずのこの声は、音になることなく消えてゆく。
彼女のこの姿を見つけた家族らの悲しみは、どれほどのものだろう。
私のために傷つき倒れ、息絶えるなど、あってはならぬことだったのに。
王をこんな愚かな形で失くしたこの国はどうなるのだろう。
優しい人々ばかりのこの美しい国だ、きっと皆が不安に苛まれてしまう。
どうか私達の強くも慈悲深い神々と大地と星々が、皆を守り導いてくれると信じたい。
ついぞ、父君と母君の顔を見ることもなく、感謝を伝えることすらできなかった。
お二人は、共に旅立てたのだろうか。どうかせめて、酷く悲しい最期の最中でも、おひとりで孤独になることなく逝けたのなら。
あんなにもお互いを支え合い、慈しみあっていたお二人なのだから。
私の守りたかった何もかもが消え去り、そうして私の世界が終わる。
十二月ももう終わりにかかるという時期だというのに二十度近くもある午後、小さな町の小さな通りで、僕は少し汗ばんだ体を休めるためにナビゲーションアプリを確認していた。
つい先月、スフィンクス街道の修復が終了した記念に催されたカルナック神殿の式典での賑わいが嘘だったかのように、ここは穏やかでゆったりした時間が流れている。
古代の様式をこの現代に蘇らせるという名目の元、古代風の煌びやかな衣装を纏った人達がド派手な打ち上げ花火を背景に夜の町をパレードするというあのお祭り騒ぎは、考古学に詳しい人間達からすると、太陽神であるアメン・ラーを信仰していたはずの古代の人々がはたして夜の闇の中で祭りを開催したのかという嘲笑混じりの雑談として一蹴されたりしたのだが、それはそれとして、もしかしたら月神トートが喜んだんじゃないかなんて僕は呑気に思っているのだけれど、彼はあらゆる学問や知識の神としての一面もあるから、やっぱりあんな騒がしいお祭は苦手なのかな、とも思う。
そんなことを考えながら体から少し汗がひいたのを感じながら、同時に僕は、子供の頃からたまに見る夢の断片の数々と、そこに類似した世界が広がるある歴史にまつわる“物語”を頭の中で反芻しながら再び歩きはじめた。
目的の場所まで、あともう少しだ。
古王国第四王朝以降のどこかに実在したとされている通称“残虐王”は、王座に就いた最初こそ両陛下と弟である第二王子を悲劇的な形で失くした“悲劇の王”として民衆から同情を集め支持されていたが、そのうちに酷くなってゆく圧政と、例えどんな身分の者でも自分の気に入らない者は秘密裏に処刑してゆく無慈悲で冷酷な性質がどんどん表面化していき、傲慢さと大胆さと残忍さを隠さなくなったと同時に民衆からの信頼と愛情も失っていったという。
更には同時期ナイル川の氾濫で甚大な被害を受けた国と民衆を救済するどころか、自らと数人の“お気に入り”達以外を見捨てる形の政を行い、とうとう民衆の不満と怒りが爆発した。
そしてその時を待っていたかのように、あろう事か奴隷とし蔑み嘲笑っていた小人症の男が、王が自らの家族と罪なき女性を権力と富と名声を得るために亡き者にしたことを暴いたのち無惨にも処刑されたことで、民衆も家来達も彼を王座から引きずり下ろすことに決めた。
王家と同等の力を持っていたはずの神官達も例外ではなかったようで、常日頃から神官達が神々に支えているのを心よく思っていなかった無神論者の王に虐げられ軽んじられていた彼らはろくに裁判をすることなく王を有罪とし、輪廻転生信仰を持つゆえにミイラという歴史に残る文化を作った古き良き時代の人々はしかし、“残虐王”を葬る際は、その輝かしき文化を放棄したらしい。
王の遺体は“来世で蘇り、同じことを繰り返すことのないように”とミイラが作られることなく火に焚べられ、遺灰をナイル川に撒かれたとも、どこかへ埋められたとも、風に流されたともいう。
どの説が本当なのかわからないが、あるいはすべてがもしかしたら真実なのかもしれない。
王と王妃、そして第二王子らしき人物のミイラと埋葬の際の副葬品は発見されているのに、肝心な第一王子のものは何ひとつとして見つからないのも、そもそもが存在そのもののほとんどすべてが不自然に歴史から消されているような形で見つかったのも、これで説明がつく。
あのラムセス三世を暗殺したとされるペンタウアー王子でさえ公平な裁判で裁かれ埋葬されたというから、これは当時としてはかなり異例な上、王国建国以来、もっとも王家にとって侮蔑的で不名誉だったことだろう。
もっとも、ペンタウアー王子は王族でありながら、不浄であるとされる山羊の皮で遺体を包まれるという罰を与えられたのだが。
対する第二王子は“残虐王”とは反対の性質だったらしく、優しく穏やかで聡明かつ好奇心旺盛で、その好奇心の対象は特に国に住む人々へ向けられたという。
幼い頃から国中を走り回り、民衆がどのような働きをしどのように生活しているのかを自らの目で見て周り、青年の頃ともなると忙しく働く者達を手伝い、身分の低く貧困などに苦しむ者を支援し、神々への信仰も厚く街の人々と分け隔てなく神殿で祈りを捧げるなどしていたらしく、民衆から愛情を持って迎えられていた。
同じ年頃の者達の輪の中に自分の身分を隠し紛れ共に遊び周り、王子と気づかないまま友情を結んだ者達が、迎えにきた家臣に真相を知らされ驚いたこともあったという。
国とそこに住まう民達を愛し、愛されていた彼は元から賢明だったこともあり、王族としての距離感を損なうことはなかったらしいのだがそこはやはり年頃の青年で、乙女達が目隠しをした相手と代わる代わる踊り回り、歌が止まったときに目の前にいる相手を当てる遊びをしている際、王子が恋していた乙女が目隠しをし相手を当てる寸前で、その相手とすり替わり目隠しをとった乙女をたいそう驚かせたという逸話も残っている。
その乙女というのが実のところ、第二王子が亡くなった際に王子と抱き合うように倒れ、背中から心臓のあたりを一突きされて息絶えていた女性であり、その記録というのもすべて、虐げられていたところを王子に救われ、王子自らに読み書きを教わりながら小間使いとして雇われていた、あの“残虐王”の悪事をすべて暴いた件の小人症の男が残したものによる彼らの“歴史の一部”である。
この“歴史の一部”が発見されたのはごく最近のことで、それも先述したごくごく断片的なものではあるものの、僕達のような歴史を辿り“物語”という人々の人生を紐解くような人間にとって大発見であったのは間違いない。
事実、“残虐王”はそれまでずっと“悲劇の王”として歴史に名を刻んできたけれど、実際には子供の頃からその残酷さは表れていたようで、自分が少しでも気に入らないことがあれば癇癪を起こし、どんな身分の者であっても王家以外の者を見下し蔑み、傷つけることも厭わなかったという。
実際、着替えの際に自分の肌に爪を立てたとして侍女を血が出るほど平手打ちしたりしたらしいのだが、それもただその侍女が“なんとなく”気に入らなかっただけで、肌を傷つけられたという事実はなかったようだ。
そしてその残酷さと無慈悲さを危惧し、およそ国をまとめ人の上に立つべき者ではないと判断した王と王妃はとうとう、本来ならば第一子である彼に譲るべき椅子を、人格者であり民衆からの信頼も厚かった第二王子へ渡すことを決意した。
当然、第一王子は怒り狂い、王と王妃が王位を継ぐ者を王室内にて内密に発表した日から数日後の満月の夜に王室にある祈りの間にて、神官達と笑談がてら神々について語り合う王と王妃へ日頃の感謝だと毒入りの果物を口にさせたのち弟の自室へ行き、祝いの酒だと毒入りのワインを飲ませ、あの事件を引き起こしたのだ。
だが、第二王子はといえば、本来継ぐべきだった領地と恋する女性がいつも通っていた領地内にある小さな神殿を貰い受けるだけで幸せなのであり、自分は兄を支え助ける役に就くと王になるのを辞退したというのだから、まさに悲劇だ。
この物語を紐解いて僕が一番心震えたのは“悲劇の王”が“残虐王”だったという事実ではなく、むしろ彼らの生きていた時代の彼らの物語そのもので、それというのも“子供の頃に見ていた夢”というのがこの歴史的物語の世界そのままだったからだ。
夢の中の僕はとても位の高い人物で、愛情深い両親と、心配しながらも見守ってくれる家臣達と、そして怒りやすく少し冷たいところのある兄に囲まれていた。
書物を読み耽り、勉学に励むのもそれはそれで楽しかったのだが、何よりも好きだったのは家臣達の目を盗んでこっそりと出かけ、同じ年頃である平民の友人達に会いに行くことだった。
その合間には、馴染みの大人達が漁をするのを手伝ったり、市場で新鮮な果実を齧りながらたわいもない話で盛り上がったり、時には恋人と共に過ごす友人を仲間と一緒にからかったりなんてしていた。
暖かい陽が降り注ぎ、ぬるく穏やかな風が吹いていた太陽の国とそこに住む人々が、とても愛おしかった。
たまに小人症の男と話す夢を見ることもあって、そんな時はいつも決まって、小人症の男が僕にありがたいお説教をしてくれていた。
彼の身分からしたらどう考えても失礼極まりない態度なのだが、夢の中の僕は兄貴風を吹かせ一から十まで僕の面倒を見ようとする彼のことがとても好きだったので、怒ることなくそれを受け入れ許していた。
特に彼の好んだ説教は色恋についてで、ありとあらゆる手段を使っては僕の恋愛を成就させようとするのだが、僕自身は奥手だったせいかなかなか上手く実行できなくていつも彼をやきもきさせていた。
それでもそんな時間すら夢の中の僕は楽しくて、同時に兄が彼のことを蔑み忌み嫌うことをとても悲しく思っていた。
僕が一番楽しみだったのがある女性の夢で、彼女こそ夢の中の僕が恋をしていた相手だった。
彼女は同じ年頃の女の子達に比べても小柄な方で、顔も特別美人というわけでもない平坦で気の抜けたような顔立ちで、鼻にかかったような声で少し舌がもつれるような話し方をする子だったけれど、夢の中の僕はそんなところも含めて彼女のことをとても美しいと思っていた。
何よりもその性格がとても好ましくて、同年代の女の子達と共に賑やかに過ごす一方で、どこか周りと少し距離を置いて一歩ひいた態度でいながら困っている人にはそっとその手を差し伸べるところや、読んだ書物の内容を興奮気味に話す僕の横で何をするでもなくそっとそばに寄り添い、話に耳を傾けてくれる姿がとても好きだった。
仲間達とともに神殿へ行き、祈りを捧げたり神々について話し合うときにひっそりと彼女を見るのが楽しみで、特に彼女が信仰していたトート神の神殿へ一緒に行く時間は何よりも尊くて、彼女がある神官からその信心深さゆえに巫女として見染められたのを知った時は、深く感銘を受けたものだった。
そんな夢の数々の内容と、明らかになった“残虐王”とそれを取り巻く人々の物語が自分でも驚くほど類似していて、子供の頃から古代の物語に魅了され続け結果今の生活を送っている僕は、なぜ僕が今この道に進んだのか、まさに愛と運命の女神ハトホルの導きでこの世に生まれ、隠された歴史を明らかにするため導かれたのではないかなんて思っているのだが、そんな眉唾ものの非科学的な話は仲間達に笑われてしまうだけなのである。
ただ一人、真剣に僕の夢の話を聞いてくれたのが僕をこの道へと誘ってくれた恩師で上司でもある教授で、ありがたいことに妙に感じ入った表情で僕の話を信じてくれたのだった。
そんな教授はといえば、そもそもがこんな壮大な物語を紐解くきっかけになった女性の元へ、教授本人の代わりに資料を提供してくれたお礼と、それに伴ってよければ自分達が研究している現場を見学に来てはどうかというお誘いをしてくれという言付けと共に、雑用がてら僕をこの町へ派遣したのであった。
「若い女性なのだから、私より君の方が適任だろう」なんて冗談混じりに言ってはいたがその実、現場を離れてしまうのが寂しくて嫌なのと、人付き合いするより研究に没頭しているのが好きなのを誤魔化す口実だったんだろうけれど、僕はといえば良い息抜きになるなと考えているのでお互いの利害が一致しているのだ。
そんな風な中で、彼が「これは君にしか頼めないことなんだ」と神妙な顔で言った教授の言葉をふと思い出していた。
「きっと、行けばその意味がわかる」とも言った彼の雰囲気は少しいつもと違うもので、妙に印象に残っている。
亡くなった祖父から小さな古書店を受け継いだというその女性は、店の中を遺品整理がてら片付けている際に店の奥のそのまた奥の、奥の奥もよいところにひっそりと置かれていたある書物を見つけた。
見慣れない絵のような文字が書かれた複数枚のそれは、どうも知っている紙の質感でないこととどうにも文字がヒエログリフのように見えるということで、とても貴重な歴史的資料なのではないかと教授に連絡してきたのが始まりで、その勘はまさに大当たりでその資料の正体は“悲劇の王”の人生の真実を綴ったパピルスだったのである。
そんな重大かつ貴重なものだというのに、代々家系に受け継がれているものなのか、はたまたいつかの時代のどこかの誰かが古書店へ売った代物なのかは、彼女自身も知らないらしい。
ヒエログリフは読めないけれど価値そのものを見抜いた聡明なその女性は、歴史を紐解き後世の人々へ学びを与えられるならば喜んでと、持っていたパピルスをすべて譲ってくれた。
読めない自分よりも、読める人達のところにあるのが書物としての存在意義がある、と言葉を添えて。
ナビゲーションアプリが目的地へ着いたことを知らせるので、僕はメモに書いてある古書店の名前と目の前にある建物の扉に書いてある店名を見比べ、ここがそうだと確認した。
dhwty——ジェフウティと綴られたその店の名は、古代の言葉で月と知恵の神の名だ。
一般的には“トート”という名前で知られているのは実はギリシャの人達が呼んでいた月の神の呼び名だったりするのだが、現代の言葉で発音するのは難しいから僕もついついトートと呼んでしまう。
もっとも、店の名の由来が神の名なのか古代に実在した王の名からとったものなのかわからないけれど、本を売るのを生業としているならやっぱり知恵の神の名からとられたのだろう。
扉を開けると、軽快な鐘の音が響く。
中はこじんまりとした店内で、調度品は魔法使いの男の子が主人公の映画に出てきそうな物ばかりだ。
「すぐそちらへ行きますから!」
店の奥から、女性の声が聞こえる。
その瞬間、体が燃えるように熱くなるのを感じた。
細胞ひとつひとつが震えるような感覚が、全身を巡ってゆく。
その震えはまるで、僕の中のもうひとりの僕が、ようやく求めていたものに出逢えたと叫んでいるようだ。
「先程電話したアダムです。どうか気になさらず、ゆっくりいらしてください」
だって、今この感覚ですぐに来られても困るんだ。心の中でひとり言い訳をして、僕はなんとか自分を落ち着かせようと、店内の本棚に積まれたたくさんの本の表紙に目まぐるしく視線を送った。
さっき電話をしたときはなんともなかったのに、この感覚はなんなんだろう。
そう思う一方で、僕のもうひとつの感覚が「答えを知っている」とばかりに胸の鼓動を強く叩いている。
「お待たせしました。ごめんなさい、奥の方で本の整理をしていたんです」
忙しく足音が近づいてきてそう彼女が話すのを、僕は目の前にある本のタイトルを読みながら聞いていた。
博物館の展示物が、古代エジプトのファラオであったミイラが持つ不思議な石版の力で夜毎動き出すという内容のファンタジー映画シリーズのノベライズで、子供の頃に何度も何度も映画を観たものだ。
アメリカで生まれ育った僕は映画に出てくる実在する博物館に毎日通って、展示物を眺めながら夜になると目の前の展示物が動き出しているのを空想してはワクワクしていたのだが、本物の博物館にはそもそも不思議な石版を持つミイラが収まった棺なんてものはなくって、博物館の閉館時間がきて家に帰るまでの道のりが無性に寂しかったのを覚えている。
こんな本もあるんだな——そう思いながら伸ばした指先は、先程以上に興奮に震えて思うように力が入らない。
鼻にかかったような声で、少し舌がもつれているような話し方。“今は”イギリス風の訛りがあるんだな。
大きく息を吸い込み振り返ると、目に飛び込んできたその姿にまた体と心が震える。
小柄な見た目、少し平たい顔。
大きな茶色い潤みがちな懐かしい瞳は、今は丸い眼鏡の奥にある。
短く切り揃えられた髪から覗くイヤリングが、輝きながら揺れている。淡い色に染めた短く整えられたネイルがとても可愛くて素敵だ。
言葉にできない感情が次々と溢れ、僕ともうひとりの僕が交ざり合い溶けるように、とうとう涙がこぼれ落ちた。
「——……ヘススケス」
“あの時”とうとう呼べなかった名を、震える声で音にすると、少し困ったようにこちらを見ながら佇んでいた彼女が僕の頬に手を伸ばして、涙を拭う。
これじゃあまるで、“あの時”と同じじゃないか。
“僕”はいつも彼女の前にいると、かっこ悪い姿を見せてばかりだ。
「また会えた」
そう呟いてはにかんだ彼女を、僕はたまらずに強く抱きしめた。
僕の胸の中で、彼女も涙を流しているのを感じる。
鼻先に、彼女の髪の香りが広がる。
この腕の中にいる彼女は、とても温かい——ああ、僕達は生きているのだと、ただただそう思った。
Hesthquez