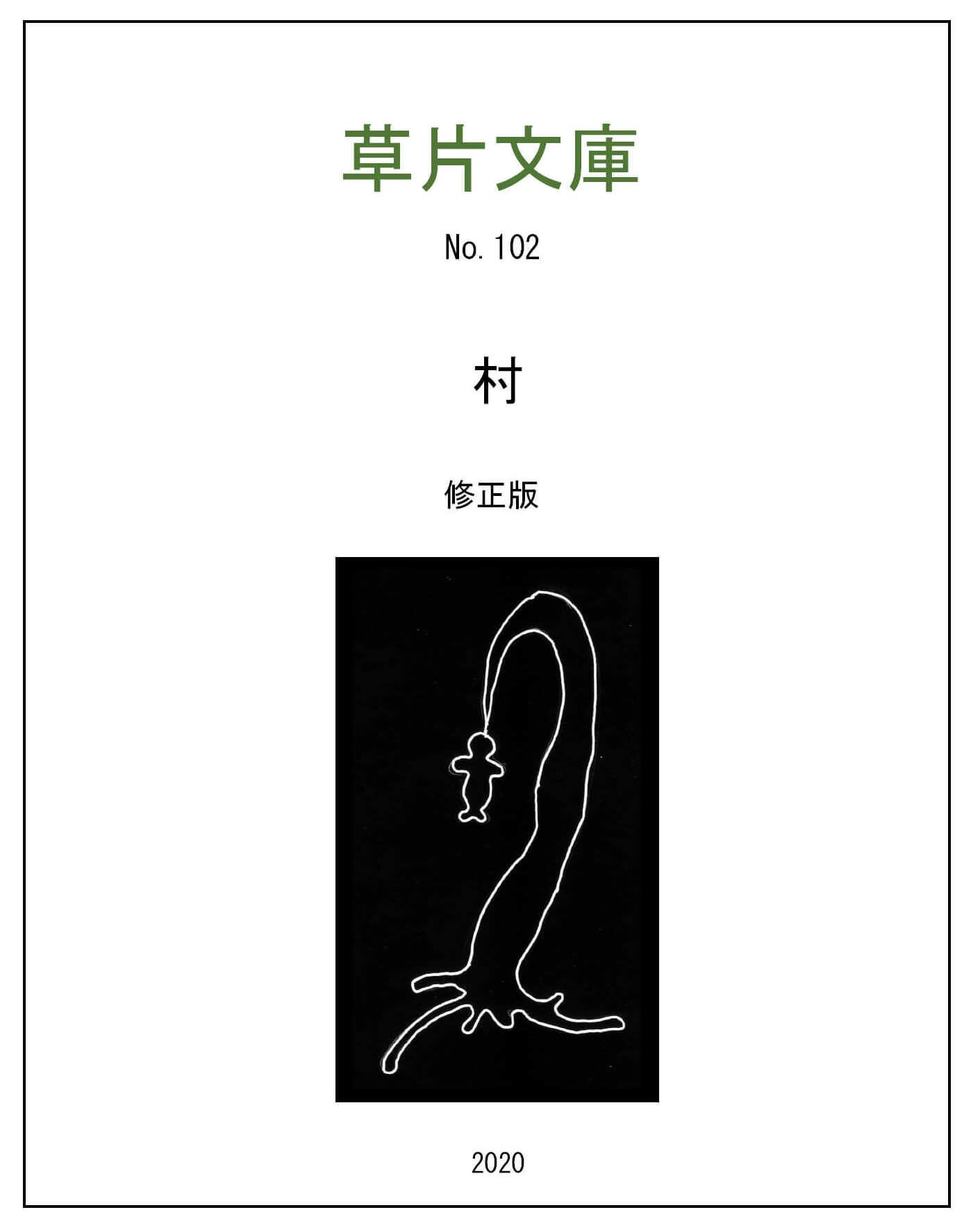
村-透明人間譚
透明人間の話3 縦書きでお読みください。
日本に村はいくつあるのだろう。インターネットで見ると183とある。東京にも村はあるが特に島に多い。大昔は村ばかり、と言うより、村という名前のない部落がたくさん存在したわけである。どんどん一緒になって強い村の名前が町になり、市になって今がある。
学生の頃は小さな集落を訪ね、昔からの風習や伝承を調べるのが趣味の一つであり、そういった場所に、自然にわき出る野天湯でもあれば、何ごとにもまして嬉しいことだった。しかし社会にでてからは、そういった趣味の旅行はここ二十年する事ができない。仕事で地方に行くとき、ついでに湯に入る程度である。大学では柔道部にいたが、練習もあまりせず、よく旅をしたものである。今は退職したらそんなことをして暮らしたいと思う年になった。
私は警視庁に勤める刑事である。東京で起こる犯罪の多くは地方に調査に行かなければならない。犯罪を指令している本部が名古屋や大阪、九州ということはざらにあるし、東南アジアに本拠地があることだってある。そのような場合、担当したグループの誰かがその場所へ調べに行く。さらに犯行をした人間は東京から離れたところに逃げ、隠れるものである。そう言った具合で、犯人を追いかけて地方に行くことは多い。
今回も犯人を追ってこの村に来ている。東京から新幹線なら四十分、そこからバスで一時間というところである。駐在所があるだけの小さな村で人口は五百人ほどだ。隣の町に吸収されるのも時間の問題だろう。
一昨日、都内のマンションで強盗傷害事件が発生した。単独犯のようで、防犯カメラから犯人は割れている。一度、同様の事件を起こした男だ。ちょっと凶暴のところがあるので気をつける必要がある。生まれ故郷がこの村の近くの町だ。
私はその町の宿屋に泊まって犯人を捜している。今日はこの村の駐在にことを告げ、協力を頼みに来た。町からバスで三十分ほどのところである。巡査は山室さんと言った。
「このあたりは、親戚でかたまってるから、外から誰かくればすぐわかります、もし隠れているとすると、人のいない神社か、消防団の小屋とかいったところでしょう。住人には報せときます。私が見回りもしますので、おそらく隠れるのは大変でしょう」
「そうでしょうね、この村の奥に道が続いているようですが、どこにいくのでしょう」
「山を越す道で、山菜採りや茸採り、猟師がイノシシ狩りに利用するくらいで、あまり人は通りませんね、その先には温泉のでるところがあって、その大昔には、かなり大きな部落がありました。今はリゾート会社が作り直した家が数十軒ありますが、もう空き家で壊れていますけどね」
「そこに潜むこともありますね」
「そうですね、だけど、この村を通って、食べ物を持って行かないと何もない所ですから、どうでしょう」
「車で行けるんでしょう」
「大きくない車ならいけますけど、途中までですね、川があって、小さな橋が架かってます。小さい車でもその手前までです、そこから歩かなきゃならない。隠れるにはよくないところです」
「明日にでも行ってみたいと思います」
「刑事さんバイクに乗れますか」
「ええ」
「それなら、明日バイクを用意しときます」
「今日はこの村の中を見て回ります」
「何なら、私も一緒にいきますよ」
「だけど、ここを空けるわけにはいかないでしょう」
「いや、うちのが、いま雑貨屋のばあさんのとこに行ってますけど、すぐ帰りますから、何かあれば連絡くれます、近くだから一緒に雑貨屋に行きましょう、自転車はありますからどうぞ」
巡査は裏からもう一台自転車を持ってきた。
「そこのばあさんは、この村のことも、奥の部落のこともよく知っているので面白い話が聞けるかもしれませんよ」
二人で雑貨屋に向かうと、ころっとした色の白い女性が買い物かごを持って歩いてきた。
巡査が自転車を止めて、「富ばあさんいるかい」と聞いた。
「いるよお」
女性がにこにこして答えてから、巡査は「刑事さん、うちのです」と紹介した。
「警視庁の葉山警部さんだ、村案内するから留守頼む」
「あれ、警部さん、よろしくお願いします、後でお茶でも」
「あ、ありがとうございます」
彼女は丸い顔を思いっきりの笑顔にしてお辞儀をしてもどって行った。
雑貨商「富田商店」は何でも売っていた。土埃のこびりついたガラス戸は開けたままで、中には商品が雑多に積まれている。
三毛猫が顔をだした。山室巡査は「みい」と呼びかけて、猫を抱き上げた。よほどの猫好きだ。
猫を下に降ろしながら「富ばあちゃんいる」と中に声をかけた。返事がない。
「今うちのが来てたからいるはずですよ、庭に回りましょう」
巡査はいったん表にでて、家の脇の垣根に沿って庭に入った。そこで驚いた。どこかの立派なお寺の庭園だ。埃だらけの商店の裏に立派な屋敷があった。
「昔の庄屋さんだけ」
びっくりしている私に巡査が説明をした。
「富さん」
おばあさんが大きな箱にいっぱいはいっている苺をパックにわけている。
「今年はぎょうさんだなあ、静岡の次男さんが毎年送ってくるんですよ」
「おりゃ、山ちゃんいつきたの」
「いま」
「今まで、ヨッチャンいたんだよ、二パックやったでな」
ヨッチャンとは巡査の奥さんだろう。腰が曲がっているがしゃきしゃき口を動かしているばあさんが腰を伸ばした。私を見つけたようだ。
「あれ、テレビの刑事さんだねえか、もしかすると鶴こうに万歳の番組みかね」
誰かと間違えているようだ。
「警視庁の葉山警部だよ」
しわしわの小さな顔がなんだといっている。
「ほんまもんかい、テレビのロケかと思ったわい」
「なあばあちゃん、東京で悪いことしたやつが、こっちに逃げてるかもしれないんだと」
「へえ、こうぇえな」
「それで、ほらあっちの誰もいなくなっちまった部落に明日いくんだが、村のこと刑部さんに話してくんねえか」
「ええよ、苺くいながらにしよう、あがってくれや」
ばあさんはパックに入れた苺を持って庭から母屋の縁側にあがった。
巡査もあがったので私もあがった。巡査は勝手を知っているようで、座敷のテーブルの周りに、隅に積んであった座布団をおくと、どうぞとすすめてくれた。富ばあさんはすぐに洗った苺を持ってきて「食えや」と自分も座って苺に手を伸ばした。
「今年の出来はいいよ、どうぞ」
私も一つ口に入れると、これはしこたま美味かった。
「刑事さん、犯人はなにしたんかね」
「強盗傷害なんですよ、こんな男です」
犯人の写真を見せた。
「ポスターはないんかね、お店に張っとくが」
「まだポスターは作ってないんで、写真はありますからおいていきます」
「そうけ、だけどこの村にゃ隠れるところは山ん中で、こういゆう奴はそんなとこいかんな、どこか女のとこでもいるんじゃないのけ」
探偵小説が好きなのじゃないだろうか。的を得ている。
「ええ、おっしゃるとおりでこの辺にはこもらないだろうと思うんですが、こいつの昔の女が、隣の市の出身だったから、このあたりにも声をかけておこうと思いましてね」
「アベック逃亡かね、女の車かね」
ずいぶんテレビのドラマに毒されている。
「わかりませんけど、一パーセントはあるでしょうね、八百万盗みましたからね、それに女の実家はモーターバイクの販売店でね」
「だがんね、この辺は女としけこむとこはないね」
「富さん、あっちの部落はどうだろ、空屋がたくさんあるからね」
「盗人(とうじん)村かい、そうだな、あそこにゃあ、いい露天風呂があるな」
「だけど誰もいないんでしょう」
「そうですけど、オートバイやサイクリングツアーの連中や、ハイカーが行くことはありますよ、昔は共同温泉小屋だったところが、屋根しかなくなってますが、湯がでていて入れますよ」
山室巡査もそう言った。
「だけど、金持ってたら、そんなとこいかんでしょうがね」
ばあさんはいぶかしげだ。
「だいたい、あそこは化けもん部落だけんな」
盗人や化けもんやろくな呼ばれかたされていないとこだ。
「どうして盗人部落と言われてるんですか」
「こりゃあ、あたしのじいさんから聞いたんだけどな、昔あそこの奴らは夏に暑くても、男も女ももんぺはいて、足袋はいて、深い編み笠かぶっとんだとよ、だけど話しゃまともで、庄屋んとこに珍しいもん持ってきたり、悪さはしねかったんだそうだよ」
「それで、なぜ盗人部落なんですかね」
もう一度聞くと、富ばあさんは、次のような話をした。
その昔、この村はいい水が流れていて、いい米がたくさん取れた豊かなところだった。畑にはいろいろな野菜が実り、村はきちんと年貢を納め、町の代官様もほめておったそうだ。皆よく働き、人がよくて、住みやすいところだった。そう言うこともあって、よその地から移り住む者も多かった。移ってきた者の中にとても変わった夫婦がいた。暑くても身体に衣をまとい、深い傘をいつもかぶっていた。村人に対してはとても礼儀正しく親切に接していて、庄屋さんが貸した田畑をよく面倒を見ていた。どうしてそんななりをしているのかと、村人がたずねると、ちょっとでも日に当たると火膨れができて死んでしまうからだと言った。ところが夜も同じ格好をしている、日がでてないのにおかしいと思った村人が聞くと、月明かりどころか星明かりでさえ、おかしくなると言うことだった。
ちょっとはへんだと思ったのだが、ともかくよく働いて、取れた物を届けにくるし、庄屋はそれ以上のことを聞かなかった。
二年程たって、その夫婦が山奥の方で暮らしたいが駄目だろうかと聞いてきた。その理由も、山奥の方が涼しいし、自分たちの体にいいからと言うことだった。庄屋は奥のほうは自分の領分でもなし、それは自由にするがいいと言ったそうだ。ただ田を作るようないい場所はないぞと言ったが、畠をつくって、静かに暮らしますと言うことだった。それで、だめだったら、戻ってきなさいと夫婦を送りだしたそうだ。
一年ほどたったときに、夫婦二人で挨拶に来たそうだ。自分たちで、林の中に掘っ建て小屋だが家も建て、川っぷちには掘ったら湯がたまるところがあって、住みやすいと言っていた。それに、親戚筋の人たちもいずれ来て住むということだった。夫婦は秋だったので、大きなマイタケなどたくさんの茸を持ってきてくれたそうだ。そのあたりではよく採れるということだった。
それからはしばらく、音沙汰がなかったのだが、村のもんが、鳥打ちにそっちの方にいったということだった。そしたら驚いたことに、山奥を切り開いた立派な畠ができておったという。それに、どこでどうやって手に入れたのかわからんが、ともかく、削った木で造られた家が二軒建っていて、遠くから見ただけだが、着物に身を包んだ二人がせっせと、畠の野菜の手入れをしておったそうだ。
鳥打ちはその夫婦とは直接話をしたことがなかったので、挨拶せんで帰ってきたということだった。庄屋は親戚も来て、よくやってるんだと、安心したということだ。
それから五年も経った年だったか、飢饉がおそった。日照りが続き、米は不作、畠の物もとれなくなった。それでも米の蓄えが庄屋の倉にはあった。庄屋は村人に少しずつでも米を配ってやろうと倉を開けた。米の量は帳簿にきちんと記されてあったので、村人にどのくらいわけることができるか前もってわかっていた。ところが倉にあるはずの米が半分になっていた。俵の数が半分なのである。こりゃどうしたことかと、いくら考えてもわからないことだった。
ともかく、村人には配らなければならぬ。半分になったが、それでも庄屋は皆に米を配った。もともと山菜や茸は豊富なところだったので、その年は何とか持ちこたえた。それにしても、米俵が半分になっていたのには首をひねった。盗賊が入った跡はなかったし、倉の鍵は庄屋さんの部屋の手箱に入れて置かれている。使ったときは必ずその中に鍵をもどす。一日としてしまい忘れたことはない。
そんなとき、村の鳥打ちが、また山奥に鳥をとりにいって、昔村にいた夫婦の家のそばを通った。その様子を庄屋さんに話したところとても驚いた。なにせ十軒ほどの家が建っており、人が住んでいるというのだ。いったいどこから人が行ったのか不思議だった。その部落にはこの村を通らなければ行けない。この数年、よそから部落に行く人を見かけたことはなかった。しかし、真夜中に通ったとすればありえることでもある。親戚筋のみんなが日の光に弱いので、夜中に行ったに違いないと庄屋は考えたという。
「それでなあ、庄屋さん、なにが入っているかわからんけど、倉までありましたが」
と鳥打が言ったのだが、庄屋は奇妙な話だと思いながらも「あの夫婦の一族が移り住んだんだろうや、うまく暮らしているようでよいことだ」と言ったのだが、鳥打ちはあの倉は米倉に違いないと思ったそうだ。
鳥打ちはまたその部落に行ってみた。家々に人がいる気配がない。そこで、銃を背中に担ぐと、そうっと倉に近づいた。倉には鍵がかかっておらず、中に入ってみた。やはり米俵が積んであった。こりゃどうしたことかと俵を見ると、明らかに村の庄屋さんの米俵だ。大変だと倉をでようとするとすごい力で撥ね飛ばされた。外に転がりでた鳥打ちは背中の鉄砲を掴まれたが、胸のところの結び目をほどいて、鉄砲をはずすと一目散に駆け出した。無我夢中で逃げ、ふっと振り返ると、遠くに鉄砲が宙に浮かんでいて火を噴いた。玉は鉄砲打ちの耳もとをかすめると飛んでいった。
ともかくなんとか村にたどり着くと、ことの次第を庄屋に話した。
「あそこの奴らはみな盗賊だあ」
鳥打ちはそう言って、なんとかしなければと庄屋に意見したのだが、人のいい庄屋は、確かに倉から米がなくなっているが、鍵のある部屋に入ってきた人間はいない、本当にとったのかどうかわからんといって相手にしなかった。
しかし鳥打ちが言いふらしたので、山奥の部落は盗人部落といわれるようになった。
その後、そのようなことはおこらなかった。
ただこんなことがあった。村のある夫婦が庄屋さんから山奥の部落の方に行くと茸がたくさん採れると聞かされたものだから、朝早く二人して籠を背負ってその部落の近くの山に行った。確かに滑子や椎茸、それに舞茸なんぞもたくさん取れた。
二人はよく聞かされていた山間の部落をちょっと見てこようということで、茸の籠を背負っていってみた。赤子の泣き声がしたので、その家に声をかけたが誰もいないようだった。のぞいてみたが、小さな布団が敷いてあって、確かに赤子用だが姿は見えなかった。
次の家も、次の家も、人はだれもいなかった。部落の下を流れる沢にいってみると、屋根のかかった石に囲まれた露天湯があった。こりゃあいいと、夫婦して浸かったのだが、誰もいないのに、湯が大きく揺れるし、所々でぴちゃぴちゃと湯が跳ねる。人が入っているような感じを受けた。ともかく湯は気持ちがよく、疲れがいやされた夫婦は茸のかごを背負って村に帰ったということだった。庄屋さんにはそういったことを話したそうだ。
その後、戦が勃発し、村の隣の町で大きな戦いがあった。庄屋はいち早く、村人を山奥に避難させ、負けた方の落人が村人に危害を加えないように取り計らった。負けた軍の兵士たちに食べ物をたっぷり渡して、山奥の部落のことを教えたのである。落人たちは言われるとおりに、盗人部落のほうに逃げて言った。庄屋はその部落がどうなるか気になったが、ともかく村人を護ろうと思ったのだ。
難を逃れた村人は家に戻ったが、山奥の部落の人たちは落人たちに殺され、家をとられてしまったのではないかと庄屋は心配した。様子をみてくるように、村の若い衆にたのんだのだ。ところが戻ってきた若い衆は、口々に部落には誰一人おらず、たくさんの兵士の遺骸が、部落の入口の道の脇にうち捨てられていたと言った。庄屋は部落の人はどこかに逃げたに違いないと考えたが、なぜ落人たちが死んでいたのかはわからなかった。
それから、何年も過ぎ、庄屋も代が変わり、村人も部落の話をしなくなったという。たまに鳥を撃ちに山奥の部落に行く村人がいたが、部落の家はきれいに手入れされており、畠に野菜も見事に大きくなっていたが、誰もいないようだと言った。そうっと家にはいってみたところ、いきなり、家から引きずり出され、しこたま殴られたが、相手はおらず、気味が悪くなって逃げてきたということだった。
新しい庄屋は、おやじから昔もそんなことがあったことを聞かされていたので、村人に山奥の部落には近づかないように言い聞かせ、それ以来、誰も行かなかったと言うことだった。ただ、一年に一度、倉の中の米俵が半分ほどが消えることがあり、それも父親に言われて聞いていたので、庄屋は神の意志だと思ってあきらめていたという。ただ多くの村人はあの盗人部落の仕業だと思っていたそうである。
そのような話だった。
富ばあさんはその話をした最後に、「その村長というのが、うちのひいひいじいさんくらいだな、それでな、今話したのはわしが爺さんから聞いたことだけどな、倉の中にな、古い書き付けがいくつかあった、そこに、若い村の男が山奥の部落まで行ったことが書いてあってな、そいつは村でもいわく付きの悪で、若い女子に悪さをする奴だ、部落に行った目的も部落の女子を拐かそうっていう魂胆だったというんじゃ、それで、野天風呂の近くで待っていたら、深い傘をかぶったおなごが入りに来たんで、見ておったそうだ。それがな、おなごが傘をとったら、頭がなくてな、着ている物をとったら、見えなくなったいうんじゃ、もっと近づいてみたらな、いきなり殴られて、その後はまったくわからなくなったそうだよ、部落の入り口のあたりに放り出されていたんだが、幸い生きておって、ようやく村に帰り着いたという話だった。どう思いなさるかな、刑事さん」
「うーん、なんともわからんですな」
「あたしゃ、あの部落にゃ透明人間が住んでおったんだと思う、盗人部落ちゅうのは、透人部落言うことだと思ってるんじゃ」
ずいぶん現代的なばあさんである。山室巡査が「富おばあさん、そんな人間おらんよ」と言っている。
ばあさんは歯の抜けた口を開けて笑った。
「うちの亭主も、透明人間だと言っておったよ」
「その庄屋さんのひいひいお孫さんですね」
「まあ、そうだが、養子だけどな」
「豊おばあさんが庄屋さんの直系ですよ」と巡査が補足した。
「その部落にその当時の家は残っていないのでしょう」
「いいやな、今はどこかの東京の開発会社の土地でな、湯もまあまあ出るし、壊れそうな古い部落を取り壊して、同じような形のコテージをつくって貸しだそうとしたんよ、だから、古い形の家は建っておるよ、だが、そこに泊まった連中から、気味悪いところだと噂が立って、来る人がいなくなってもう二十年ほどさ、手入れもしていないから、またもとのように半分壊れたような家が残っとる、二つばかり大昔の家を改修して博物館のようにしておったが、もう崩れておるじゃろ」
「それで、バイクのツーリングの連中が利用するわけですね」
「だけど、そういう連中もなんだか気味悪いところだと言っとったよ、アベックでオートバイに乗ってきた若いのが、露天風呂に入っていたら、誰もいないのに女の方が乳触られたなんて言いよって」
「まだ、透明人間が住んでいるとでも」
「そんなこんはないでしょうがの」
うまいイチゴを食べながらそんな話をした。
次の日、用意してくれたバイクに乗って、山室巡査と盗人部落に行った。
山道を行き、いったん下ると谷にでて、そこにかかっている細い橋を通り抜けた。
そこで山室巡査がバイクを止めたので私も降りた。
巡査が橋の際を指さして、「昔はこの倍以上の広いしっかりした橋があったんですよ」と言った。「リゾート開発で作ったんですが、人が来なくなってしばらくしたら台風で壊れちまって、これは仮の橋なんですよ、それがね、台風はそんなに大きくなかったんでね、誰かが壊したんじゃないかっていう噂が立ちましてね」
「どうして壊す必要があるんです」
「いや、あの部落にはまだ誰か住んでいて、そいつが部落に人が来ないように壊したったってことです」
「そんな様子があるんですか」
「富ばあさんが言ったことですよ」
「透明人間とはまた奇抜な考えですね」
巡査はそれには答えないでまたバイクにまたがった。
我々はそこからもう二つの山の中腹の細い道を通って盗人部落の入口に着いた。木々の間に確かに十軒ほどの壊れかけた家が集まっていた。別荘としてはなかなかいいところだ。昔は住むところとして安定したところだったのだろう。
巡査が「あれを」と道の脇の草むらを指さした。見るとまっぱだかの男と女が重なるように上向きで倒れている。バイクからあわてて降りた。
男も女も頭から血を流している。
男は追っていた犯人だ。女は男の昔の女だった。どちらもまだ脈はある。なぐられてそんなに経っていない。ハンカチで傷を押さえた。血はかなりでてくる。
「山室さん、はやく町の警察に連絡して、救急車を橋のところまでよこすように言ってください、男と女が頭部打撲で多量の血を流している、脈はある」
巡査はもう連絡を入れていた。
刑事さん、救急ヘリを呼びました」
男と女を橋のところまでどのように運ぶか考えていた私はほっとした。巡査は俺よりずっと要領がいい。
「私は部落の家に何かないか見てきます」
巡査はさっさとバイクでいってしまった。取り残された私は二人をよく観察した。男は抵抗をした跡がない。急に襲われたようだ。堅いもので頭をたたかれている。露天風呂にはいっているときにやられたのだろうか。金を奪うなら、露天風呂に入っているうちにそうっと金だけ持って行けばいい。殴らなければならない理由があった。何かを知ったからか。女のほうはちょっと違った。頭の殴られた傷だけではなく、あらだに擦り傷のようなものがある。
山室巡査がもどってきた。
「シーツがあったので、持ってきました」と渡してくれた。女にかけた。女は犯されているようだ。いや、情交の時になぐられたのか。とすれば、片方は抵抗したはずだが、その様子がない。この二人は複数の者に襲われたのだろう。
と、ヘリコプターの音が聞こえてきた。ずいぶん早い。
「このあたりには降りられないと思いますので、我々の頭上でホバリングです。隊員がロープで降りてきます。抱えて中に入れます」
作業はそんなにかからなかった。
あっという間にヘリは二人を町の病院につれていった。おそらく命は大丈夫だろう。
「警部さんパトカーを交番まで回してもらいましたから、それで病院に行ってください」
「いや、手回しがいいですね、助かります」
村に戻ると、交番にはもうパトカーが着ていて、山室さんの奥さんとパトカーの警官が話していた。
その警官が「葉山警部、病院にお送りします」と後ろの扉を開けた。
「よろしくお願いします、山室さん、助かりました、事件のことがわかったら、お話にきます」
挨拶をしてパトカーに乗った。
車を出すと、運転している刑事と思しき警察官が、町の警察署の田坂です、ヨッチャンと同期でした」
と言った。えっと思った。
「ヨッチャンというのは山室巡査の奥さんですよね」
「ええ、刑事だったのにやめて、山室さんの嫁さんになっちまったんです、もったいないけど、山室さんもすごい人だから」
「なんです」
「山岳救助隊のリーダーしていて、ヘリの免許まで持っているんですよ、だけど警察官に応募して警察官になったから、年は我々より上だけど、巡査やってるわけです」
なるほど、納得した。要領がいいわけである。
警察署に着いたら、刑事課の部長が、犯人とその女は入院させた旨知らせてくれた。命は取り留めたようだが、男が話のできるようになるには半月以上かかるということだった。頭の傷が少し深いようだ。
病院先に行ってみると、二人ともICUにはいっていて、とても話せるような状態ではない。山村巡査に連絡を取り、明日二人の服や持ち物がどうなったか、盗人部落に調べに行くと伝えた。
女の兄からの情報だと、オートバイが二台持ち出されているということだった。彼らはオートバイで逃げる途中にあの部落によったようである。
山村巡査とまた盗人部落に行った。数年はリゾートとしてつかわれていただけあって、部落内の道はひび割れがひどいが、一応舗装されていた。会社が補修を行っていないとみえ、家々の窓のガラスは割られ、壁の木などは反っていて隙間があいている。当時は木製の作りで見栄えはよかったのだろう。
一軒、一軒見て回ったが、彼らの着ていたと思われるような服は見つからなかった。押入にはぼろぼろになった布団などが押し込まれていて衛生上よくない。
一軒の家の前で巡査が言った。
「この家からシーツをみつけたんです、あ、ここにバイクの跡がありますね」
入り口のところに二種類のバイクのタイヤの後があった。それだけではなく、家々の周りの道にもバイクの跡がたくさんあった。乗り回したのに違いない。
「あいつらもここに泊まったんじゃないですか」
中に入って、押入を開けた。ここは使えそうな布団がはいっている。台所は洗っていない食器がほうってあった。
「水はでないんでしょう」
「リゾートの宿泊施設の時は、井戸水を電動ポンプでくみ出して、それぞれの家に配水していたようですけど、今はだめですね」
「彼らの着ていたような物は見つからんね」
「金もバイクも、着ている物もあの二人を殴った犯人がとっていったということですね、二台ともないから犯人は二人組だ」
「むこうに、古い建物が博物館になっています、後はそれだけです」
巡査が案内したのは、林の奥の藁葺きの家であった。説明書きがあったようで、入り口に壊れた看板がある。
「おそらく百五十年ほど経っている建物で、リゾート会社も、貴重だからと、メンテナンスしてこのあたりの歴史資料館にしようとしたようですよ、ほら、倉もあるでしょう」
隣に板葺きの建物があった。蔵というより物置と言ったほうが良さそうだ。
「建物の中に入れますか」
「もう、ほったらかしですから入れますが、板の間は抜けるかもしれないので気をつけないと」
母屋に入ってみると、意外とさっぱりときれいだった。これなら人が住めそうだ。
「誰か直しているんじゃないかな、ほっとくとこんなにきれいではないでしょう」
「そうですね、誰か来ているのかもしれませんね」
そのとき、ふっと、人がいるような気配がしたが、誰がいるわけではなかった。
「倉も見てみましょう」
入り口からのぞくと、中は土間になっており昔は俵でも積んであったのだろうが、蜘蛛の巣だけである。
「流れの方の野天湯にいってみましょう」
巡査についていくと、沢に壊れかけた屋根のかかった露天風呂があった。まだ湯気が立っている。気持ちが良さそうだ。入りたくなる。
「いい湯なんですよ」
巡査はその周りを調べている。
「なにもないですね」
「あの二人が話せるようになれば、様子が分かるでしょう、いろいろお世話になりました、私は明日東京に帰ります、二人はいずれ、東京の警察病院に回されます、何かわかったら、連絡しますよ」
「はい、宿に戻られる前に、これからうちでお昼でもどうですか」
「あ、それはありがたく」
と言うことで、駐在所に併設されている山室巡査の家で、奥さんの打った蕎麦を食べた。地元の野菜や茸の天ぷらがうまい。ビールがほしいところだ。
奥さんが黙ってビールを持ってきた。
「町の警察にいわないでくださいね」と笑いながら注いでくれた。亭主にも注いだ。のんびりとしていい。東京ではこうはいかない。
「もと刑事さんだったそうですね」
そう聞くと、「あらいやだ、誰も捕まえたことがなくてやめました」
「俺を捕まえた」
山室巡査がぼそっといった。まじめな顔で冗談を言う。
「山室さんは山岳救助隊のリーダーだったそうですね」
「はい」
「たいしたことないの、救い出したの私一人、警察から救ってくれたわ」
奥さんがケラケラケラと笑った。
東京で警部をやっている俺は独り者、村の駐在さんになれば、こんなにいい奥さんがくるのか、どこかの島にでも異動を申し出ようか、などと半分本気で考えた。
東京の仕事に戻り、殺人事件の担当に回され、犯人探しの指揮をとっていた。しばらくすると八百万強盗の犯人と女の状態がよくなり話が聞けると連絡がきた。
今やっている殺人事件の犯人はすでにわかっており、部下に任せとけば問題ない。私は警察病院の病室で話を聞くことにした。
強盗に入ったときの様子は部下がすでに聞き出しており、検察庁に書類は提出してある。歩けるようになれば、逮捕状をとることになる。女の方が傷が軽かったようだが、やはり性的暴行を加えられており、あまり話をしたくないようである。女性の方は犯人逃亡幇助で逮捕状を出す。別の病棟におり、部下の女性の刑事にまかせた。
「どんな奴に怪我させられたんだ」
「わかんねえ、周りにゃ誰もいなかった、いきなり石かなんかで、頭殴られて、それっきりわかんねえ」
「何で服着てなかったんだ」
「着てたよ、ポロシャツと、Gパン、盗まれたんだよ、下着もみんな、金も、バイクもな」
「女が殴られたのは見たのか」
「いや、見てねえ、いきなり俺はぶっ倒れた、ただ、あいつのぎゃあと言う声が聞こえたような気がした」
「それじゃ順を追って話してもらおうか、東京で強盗やった後は新幹線と在来線を乗り継いで、さらにバスで、町にきたんだな」
「ああ、その日のうちにな、女に連絡しといておちあった、町で二日ほど公園なんかで寝ていたが、女があの部落のことを知っていて、誰もいないからしばらくそこにいようといって、バイクを持ってきてくれた。なかなかよかったよ」
「食べ物はどうしたんだ」
「一週間分はもってたよ、そのあとは、もっと遠くにいくつもりだったんだ、八百万じゃ、たいしてもたねえけどな」
「食料は家の中においておいたのか」
あの家を調べた時食べ物は何もなかった。
「ああ」
「あそこでバイク乗り回したんだろう」
「ああ、誰もいねえから、好きなように乗った」
「おまえを殴った犯人は食料ももっていってしまったようだな、あそこで人を見たか」
「いや、俺たちがいたときには誰も来ねえ、あの露天風呂よかったな」
「殴った奴は急に現れたのか」
「だからよ、家を出てバイクに乗ろうとしたら、なぐられてよ、わかんねえ、ただな、あそこに泊っていたらな、夜、なんだかぞわぞわして、見られているような気がしてなんなかったな、やっているとき、あいつも見られているみたいなんて言っててな、誰もいねえし、電気はつかないから真っ暗だしな」
「昼間はなにしてたんだ」
「ごろごろしてたよ、スマホでテレビ見てたり、音楽聴いたり、たまに水んとこいってよ、遊んで、あの風呂に入って、こんなにのんびりしたことねえな。そうだ」
彼は思いだしたように言った。
「便所はよ、使えねえじゃん、それで、林のなかでやったんだ、あいつが、林にいったときに、風もないのに、かさかさ人が歩く音がしたり、草が動いていたりして気味悪かったと言ってたな、あいつの様子はどうなんだ」
「傷はお前より軽いようだが、大分疲れているようだ」
「会えるんかな」
まじめなところもありそうなやつだ。
「刑務所からでたらな、まじめにやれば早くでられる、相手に怪我をさせたから、ちょっと長いよ」
「そのつもりはなかったん」
「後は詳しく、法廷では正直に話せよ」
彼は以外と素直にうなずいた。
そこに、女のところに行っていた部下の刑事がちょっと来てくれと言いに来た。
廊下にでると「検査の結果では、性的な暴行はあったようですけど、射精はしていないようです、それより、彼女、大分混乱して、おかしなことを言っています」
「どんなことを言っていたの、あっちで話してくれるかな」
女性の刑事を待合室に連れて行った。
「女性ははじめから殴られたのではないようです」
「どういうこと」
「家から出ると、いきなり腕を捕まれて、家の中に引きずり込まれたそうです」
「犯人を見たの」
「誰も見ていないって言うんです、床の上で着ている物を全部とられ、のしかかられたそうです、一人じゃなくて、二人だと言っています」
「それじゃ、犯人見ているんでしょう」
「透明だと言っているんです」
「ことが終わって、暴れて外に飛び出たら、彼が頭を血塗れにして、倒れていたと思ったら、石が浮いて自分の頭を殴ったそうです」
「ずいぶん錯乱しているね、医者はなんと言ってるの」
「警部の言ったとおり、錯乱だそうです、まだ退院させることはできないということです」
「わかった、すると、彼は逮捕できるが、彼女は無理か、裁判は当分開けないね」
「だと思います」
それをきいて私は署にもどった。ちょうど、おっていた殺人犯の逮捕をしたことの知らせが来たところであった。
私はすべてが終わった後、警視正に休暇を申し出た。警視正は二つの事件を相次いで解決に導いたし、いいだろうと、三日の休みをくれた。今まで、土日すらあまり休んだことがない。
私はもう一度、あの村に行きたかった。
あの村の富ばあさんの話してくれたことが頭にこびりついていたのだ。
村に行き、山室巡査にあった。ことの次第を話したところ、彼は私を見て、「怖いことになりますね」と言った。彼は村の駐在さんにしておくにはもったいない。
「実は葉山警部に連絡しようか迷っていたのです、あれからしばらくした夜中、村の中をバイク二台がすごい勢いで走って町の方にいったのを見た人がいるんです。しかも二台のオートバイに人が乗っていなかったというのです。そいつは酒を飲んでいたので、そのためとも思ったのです。そのバイクは町のバイク屋の店の前に置いてありました。女の実家です。しかも、犯人達の着ていたものもきちんと畳んでおいてあったということです。どういうことでしょうね」
「性被害は大丈夫」
「そちらはありません」
「豊ばあさんの話では透明人間は本来、働き者で、まじめだということですね」
「盗人村の再来ですか、静かに生きていた連中が、凶暴になってきたのでしょうか」
「そんなに悪さをする連中じゃないんじゃないか、もしそうだったとしたら、もっと被害が増えている、あの二人が透明人間の若い奴の生活をかき乱したんだろう」
「そうですね、普通の人間でも若い奴はいろいろなことをする」
「オートバイで町にでたのは透明人間の若者だろう、きっと、年寄りの透明人間にお説教されて返して来いと言われたのかも知れないね」
「それで、葉山警部、わざわざ私のところにそれを言いにきたのですか」
「いや、あの部落にある、野天湯に入ってみたいと思ってね」
「透明人間を感じたいのですね」
私はうなずいた。
「オートバイ二台用意します」
「いや、一台どこかで借りられますか、私一人で入ってきます、勤務中に湯に入っていていてはしかられますよ」
私がそう言うと山室巡査は笑った。
「私のバイクお使いください」
「私は休暇をもらってきました。いつか奥さんと一緒に入りに行くといいですよ」
今度は赤くなった。
「帰りによりますから、どこかで飲みましょう」
私はオートバイを古い家の前に止めた。降りて玄関までいって、「おさわがせしました」と言った。さらに「湯に入らせていただきます」とも言った。
その後、道の脇にとめて、沢におり、野天湯に入った。盗人村の野天湯は気持ちがよかった。川の流れを見ながら、ゆっくりと湯を楽しむのは何十年ぶりか。
十人ほども入ることのできる広い湯である。大昔は男も女も汗を流した後に一緒に入ったに違いない。
目をつぶって浸かっていると、ぴちゃっと音がした。目を開けると、湯が大きく揺れている。
湯の揺れが自分に近づいた。湯の動きが体に感じる。湯の中に透明な女の下半身が輪郭として見えた。人肌が自分に触れた。手を伸ばすと人間の肌を感じた。さらに手をはわすと柔らかな膨らみを感じた。いきなり彼の上に見えない女のからだがのってきた。あとは目を瞑ったまま果てた。目を開けると、滴を垂らした透明な女の人形(ひとがた)が湯からあがるところだった。石の上の濡れたれた足跡がゆっくりと、上流のほうにいき、やがて、林の中に消えた。あの犯人たちを殴った若者の母親だろうか。お詫びだったのだろうか。昔旅人にそういったもてなしもあったと聞く。
しばらく湯の中で目を瞑っていた。
もう心配ないだろう。
ゆっくりと湯からでた。
駐在所にもどり、
「もう大丈夫ですよ、なにもおきないでしょう」と山室巡査に言った。
「とられたお金はどうなったのでしょうね」
「きっと、戻ってくるでしょう」
彼はうなずいて、
「家内が、腕を振るいたいと言ってます、うちでどうです」と笑顔になった。
「このあいだも御馳走になったし、申し訳ないから、外にでましょうよ」
「もう作ってしまっています」
結局その夕は、刑事だった奥さんの手料理でしこたま飲んでしまった。しかも、そこに泊まってしまったのである。
すがすがしい秋の空のような透き通った休暇だった。
東京に戻りしばらくして山室巡査から電話があった。村民の一人が札の入った袋を拾って届けに来たということだった。中は七百五十万だったそうである。やっぱり戻った。日本にもあんなにいいところがあるのだ。
川を見ながらの露天風呂を思い出した。湯の中の透明な女のやわらかい肌が。
村-透明人間譚


